
| 餐 歩 実 施 状 況 (H20年=2008年) | |||||||||||
| № | 歩行起点(最寄駅) | 歩行終点(最寄駅) | 距離(km) | 実績 | 餐歩日 (餐歩記) |
歩行出発地点への 往路便&参加人数 |
当日最高 標高点m |
||||
| 区間 | 通算 | 所要時間 | スタート | ゴール | |||||||
| 1 | 日本橋 | 明大前駅入口 | 13.8 | 13.8 | 3:53 | 10:15 | 14:08 | 2008.01.11金 | 単独歩行 | ・ | |
| 2 | 明大前駅入口 | 分倍河原駅入口 | 17.5 | 31.2 | 5:20 | 9:13 | 14:33 | 2008.01.14月 | 単独歩行 | ・ | |
| 3 | 分倍河原駅入口 | 大和田橋南詰 | 13.2 | 44.4 | 3:44 | 9:21 | 13:05 | 2008.01.25金 | 単独歩行 | ・ | |
| 大和田橋南詰 | 高尾駅前 | 6.8 | 51.2 | 1:44 | 9:40 | 11:24 | 2008.01.30水 | 単独歩行 | ・ | ||
| 4 | 高尾駅前 | 藤野駅前 | 16.9 | 68.2 | ・6:01 | 9:36 | 15:37 | 2008.02.01金 | 単独歩行 | 小仏峠548m | |
| 5 | 藤野駅前 | 鳥沢駅入口 | 19.4 | 87.5 | ・5:49 | 9:46 | 15:35 | 2008.02.08金 | 高尾発9:25大月行・参加2名 | 恋塚560m | |
| 6 | 鳥沢駅入口 | 笹子駅前 | 19.0 | 106.6 | ・5:35 | 9:45 | 15:20 | 2008.02.22金 | 高尾発9:02大月行・参加3名 | 笹子駅603m | |
| 7 | 笹子駅前 | 上行寺(勝沼) | 15.8 | 122.3 | ・5:30 | 9:23 | 14:53 | 2008.03.30日 | 高尾発8:20甲府行・参加3名 | 笹子峠1096m | |
| 8 | 上行寺(勝沼) | NTT西交差点(甲府) | 16.2 | 138.5 | ・5:00 | 10:00 | 15:00 | 2008.04.06日 | 高尾発8:20甲府行・参加3名 | 上行寺432m | |
| 9 | NTT西交差点(甲府) | 本町交差点(韮崎) | 13.5 | 152.0 | ・4:45 | 10:23 | ・15:08 | 2008.04.12土 | 高尾発8:01甲府行・参加2名 | 本町交差点360m | |
| 10 | 本町交差点(韮崎) | 台ヶ原<梅屋旅館・泊> | 18.1 | 170.2 | ・4:49 | 10:50 | 15:49 | 2008.04.25金 | 高尾発8:46小淵沢行・参加3名 | 台ヶ原宿618m | |
| 台ヶ原<梅屋旅館> | 神戸八幡交差点(すずらんの里駅入口) | 19.3 | 189.5 | 5:10 | 7:48 | 12:58 | 2008.04.26土 | 前泊・参加3名 | 原の茶屋965m | ||
| 11 | 神戸八幡交差点(すずらんの里駅入口) | 中山道合流地点 (下諏訪) |
21.3 | 210.8 | 7:02 | ・9:25 | 16:27 | 2008.05.26月 | 高尾6:42→9:20すずらんの里 ・参加3名 |
御射山一里塚917m | |

 ~行程概要と餐歩状況
~行程概要と餐歩状況 「関ヶ原の戦い」に勝利した徳川家康は、日本橋を起点に五街道(東海道・中山道・甲州街道・奥州街道・日光街道)を整備したが、この甲州街道(甲州道中)を幕府の生命線として考えていたと思われる。
一朝事ある時、江戸城半蔵門を出れば即甲州道中であり、内藤新宿には百人組鉄砲隊、八王子宿には千人同心を配して、一路甲府城へと待避できるし、甲府に至れば富士川の舟運で駿府への連絡も可能、かつ、下諏訪宿に至れば中山道にも接続していた。
この甲州街道(甲州道中)は、江戸城南側を廻って半蔵門から内藤新宿・高井戸宿・府中・横山(八王子)を通って甲府経由で信州の下諏訪で中山道と出会うまでの約53里(約211km)を、内藤新宿からの33宿(小さな宿場を入れると45宿)で結んでいた。もっとも、これには諸説ないしは時代の変遷により変化があり、当初(1604年)は甲府まで36里・36宿、5年後には下諏訪までの56里42宿に延長され中山道に繋がったが、のち、道筋が変わったりして、今日では52里説もあるようだ。
また、戦国時代には甲斐武田氏の軍勢が駆けめぐる軍用道路だったが、徳川家康が江戸と軍事要衝である幕府直轄の甲斐・甲府城を結ぶ官道として制定して以後は、「茶壺道中」、「三度飛脚」、そして富士や身延参拝・甲斐善光寺・信濃の善光寺に詣でる多くの旅人の行き交う道となった。
ただ、この道を参勤交代で利用したのは、信濃の高島・高遠・飯田の3藩のみで、交通量や宿設備も他の4街道に比べれば劣っており、常備人馬は25人・25頭ほど、布田(調布)5宿は合わせて一つの宿とされていた。従って、当初は各宿場とも振るわず、数宿連合で月割り制で問屋業務を勤めていたという。
しかし、享保九年(1724)に甲斐が再び幕府直轄地となってからは代官所が設置され、甲府城に勤める甲府勤番や幕府役人の通行が多くなった。
そんな訳で、「お茶壷道中」がこの甲州道中唯一の大通行であった。幕府に献上される「宇治茶」が中山道を通って、下諏訪宿から甲州道中を経て江戸へと入ったが、このお茶壷道中は一日当たり人足約六百人・馬五十疋と疲弊していた各宿場にとっては負担の大きいものだった。この道中は将軍通行と同じ権威をもっていて、道中で出会っ
た大名は乗物のまま道端に寄って控え、家臣は下乗、供の者は冠り ものを取って、土下座で行列の通過を待った由である。
庶民は、♪「茶壷に追われて戸をピシャン 抜けたらドンドコショ・・・」と家に隠れたそうである。
このお茶壷道中は慶長十八年(1613)から慶応二年(1866)まで230年間も続いたというから大変なものだ。
なお、慶長年間には「甲州海道」とも呼ばれていたようだが、享保元年、幕府は「甲州道中」と改称し、明治に至って甲州街道となったようだが、庶民は通称「甲州街道」と呼ぶことが多かったらしい。
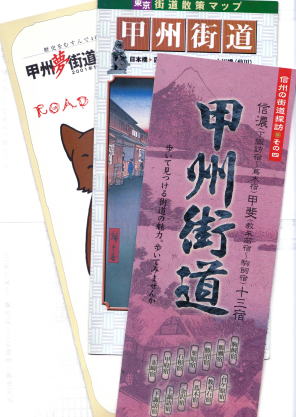
| 宿場 | 距離 | |
| 始 | (日本橋) | (km) |
| 1 | 内藤新宿 | 7.9 |
| 2 | 下高井戸 | 7.8 |
| 3 | 上高井戸 | 1.4 |
| 4 | 国領 | 6.0 |
| 5 | 下布田 | 0.3 |
| 6 | 上布田 | 0.2 |
| 7 | 下石原 | 0.9 |
| 8 | 上石原 | 0.8 |
| 9 | 府中 | 5.0 |
| 10 | 日野 | 7.8 |
| 11 | 横山 | 6.9 |
| 12 | 駒木野 | 6.8 |
| 13 | 小仏 | 2.9 |
| 14 | 小原 | 6.3 |
| 15 | 与瀬 | 2.1 |
| 16 | 吉野 | 3.7 |
| 17 | 関野 | 2.8 |
| 18 | 上野原 | 3.7 |
| 19 | 鶴川 | 1.9 |
| 20 | 野田尻 | 4.3 |
| 21 | 犬目 | 3.3 |
| 22 | 下鳥沢 | 4.6 |
| 23 | 上鳥沢 | 0.6 |
| 24 | 猿橋 | 2.9 |
| 25 | 駒橋 | 2.4 |
| 26 | 大月 | 1.8 |
| 27 | 下花咲 | 1.5 |
| 28 | 上花咲 | 0.6 |
| 29 | 下初狩 | 1.4 |
| 30 | 中初狩 | 2.6 |
| 31 | 白野 | 4.1 |
| 32 | 阿弥蛇海道 | 1.9 |
| 33 | 黒野田 | 1.3 |
| 34 | 駒飼 | 8.4 |
| 35 | 鶴瀬 | 1.9 |
| 36 | 勝沼 | 4.2 |
| 37 | 栗原 | 3.4 |
| 38 | 石和 | 6.1 |
| 39 | 甲府 | 6.0 |
| 40 | 韮崎 | 14.0 |
| 41 | 台ヶ原 | 15.6 |
| 42 | 教来石 | 5.4 |
| 43 | 蔦木 | 4.6 |
| 44 | 金沢 | 12.2 |
| 45 | 上諏訪 | 13.2 |
| 終 | (下諏訪) | 5.1 |