���͂ǂȂ��ł��Q���ł��܂��B
�Q����S�O�O�~�i��������܂ށj�@����O�T�O�O�~
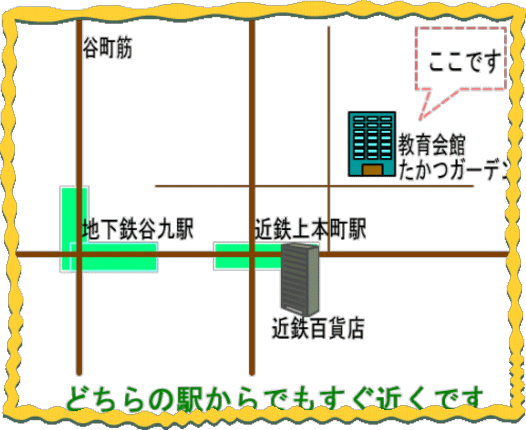 �Q�O�Q�T�N11�����
�Q�O�Q�T�N11��������@�@���@�@11��9���i���j �@13�����J��A14���J��
��@�@��@�@���{������ �RF���̊�
��@�@�� �@�@�ԒˍN�Y�i����j�u�W���[�i���X�g�E���Y�A���̕� �@�@�@�@�@�@�@�̋O��
�@�@�@�[��{�c����k���i�x�g�i���j�f���̔z�M�ցv
�@���W���[�i���X�g�ƂȂ�_�@�͋��s���ŐV���w�̏���G�������Ɏt���������Ƃ��B1938�N���������ǂɓ��ǁB�펞���ő�{�c���\�̕�������B1944�N11���̃��C�e��Ŗ���͏����Ɉꉭ�̑̓����肪�K�v�A����I����E��s�@���ƕ���B�I���A����͋������s�{�̑�16�t�c�̓��C�e�ŋʍӁA���̉p���n�ɂ͕�肪�ї��A���d�ȑi���ł������ƏՌ������B���̏o���_�ő�{�c������Ă����W���[�i���X�g���Ƃ����n�_����̔��f�����Ă䂭�B1960�N���{�d�g�j���[�X�Ђ�ݗ��A�x�g�i���푈�������B�z�M�j���[�X�͐��E���Ŕ���^�����N�����x�g�i���a�����ꏕ�ƂȂ����B����́u�x�g�i���푈�Ƃ����傫�ȕ���ŏ����Ȗ�����^����ꂽ���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A ���j�̋L�^�W�́A�͂�����ł��邱�Ƃ́A���肪�����Ǝv���v�Ƒ������Ă���B
�@���̃y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���ȑO�́̕u�������v�ɂ���܂��B�u�������v��������������
�Q�O�Q�T�N����
10������ �@�������u����i�{�����E�_�ˑ�w��w�@�����w�����ȍu�t�j �u�w�ɉE�̑䓪�x�Ƃ͉����H�|�t�����X�ƃx���M�[������Ɂ|�v
�䓪���郈�[���b�p�́u�ɉE�v
�@���܃��[���b�p�S�̂̐����́A�ێ�^�}�����������Ă���A���S�͂��ቺ���Ă���B ����ŁA���{�ł́u�ɉE�v�Ƃ��Ēm���鐭�}�i�t�����X�́u�����A���v�Ȃǁj���c��� �����̐��͂��߂Ă���B���[���b�p�Łu�ɉE�v���}�����͂��߂Ă��鍑�́A1 �ʂ��n ���K���[�ŋc��̂T�S�����߁A2 �ʂ��|�[�����h�i�R�S���j�A3 �ʂ��t�����X�Ŗ�20 �� ���߂Ă���B4 �ʂ��C�^���A�ŁA�����[�j�̉��Ő����ɂ��Ă���B
�@ �t�����X�́u�����A���v�́A�t�����X�����c��577 �����A120 �c�Ȃ��ߑ傫�Ȑ��͂�
�Ȃ��Ă���B�}�N�����哝�̂��}��̗^�}�u���a���̂��߂̘A���v�́A�����̐��}�ō\��
����Ă���B�}�N�����͒����E�h�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă������A�N�����v�Ȃǂō����̕s�l�C��
�������B�ق��ɁA�̓}�⍶���}�i���Ƃ̃t�����X���Y�}�j�A�u�����A���v���E���́u��
�����}�v�Ȃǂ�����B �t�����X�̉E���̌n���́A�h���t���X�������_�@�ɁA�u�A�N�V�����t�����Z�[�Y�v����
���A�A���W�F���A�푈�ɎQ�����āA����ɉ��S�����Ƃ������Ă���W�����E�}���[�E��
�y�����u�퓬����������v�������A�P�X�U�X�N�ɂ͋ɉE�c�́u�V�����v�����������B����
�́A�i�`�X�̗p��Ƃ����B�����̑g�D�́A���}�Ƃ��������A���ڍs���̂��߂̉^����
�ł���B�u��������v���T�R�N�O�Ɍ������ꂽ�w�i�ɂ́A�A���W�F���A�푈����A�����l
�������A�A���u�l�ɕ������Ƃ����ӎ��������A�t�����X�œ����Ă���A���u�l�J���҂��
�����A�{��������Ă������ƂȂǂ�����B�ނ�́u���C�X������`�v���f���A�u��������v
���g�債�Ă����B�Q�O�O�Q�N�̑哝�̑I���ŁA���I���[ �Ƀ��y����₪�c�������A�V���N���ڐ�̖��哝�̂ɂ�
�����B���̂Ƃ��A�Љ�}���V���N�����������B���̌�A ���B�c��I���ŁA�u��������v�͖��i�A���}�ɂȂ����B
���B�c��́A���퐶���̂��Ƃ͋c�_�����A���[���b�p�� ���̖��Ȃǂ��c��ō����̊S�������B
�u�E�������v����u�ɉE�v
�@�u��������v�́A�P�S�N�O�Ɂu�����A���v�ɉ������A���̃}���[�k�E���y���ɓ}��
�サ���B����Ȍ�A�H���ύX���s���A�}�����C������A�ɒ[�Ȕr�O��`���������B����
�H���̃\�t�g���́A�u�E�������v�ƌĂ�Ă���B�u�E�������v�̉ߒ��́A�ǂ̂悤�ɂ���
�߂�ꂽ�̂��B���Ƃ��ƁA���̃��y�����u��������v�����}����������c���`���d�����A
�Љ��������咣�A�u�ɉE���v��������Ă����B�ŋ߂́A�d�t���E�ȂǁA�������_��
����Ď咣��ς���u�|�s�����X�g���v���A���ʓI�����͕��Ă���B���̎咣�́A
�u�t�����X���Ăт��ǂ��Ă���v�u��������v�u���M���������v�u�������グ��v�u��
�������v�u�s�@�ږ��̗}���A�팸�v�u�n�Y�n���v�u��Õی����P�v�ȂǁA�u�ɉE�v�̃C���[
�W�Ƃ͂������A��荞�܂��l�������B�ږ��ɂ��Ă͌o�ς̂��߂Ɏ����ȂǍ�
�������x�����D��̎咣�Ŏx�����g�債�Ă���B���̒��ŁA�u�C�X������`�̈�|�v��
���́A�]������p������Ă���B���̌��ʁA�哝�̑I���ɂ͕K���o�ꂵ�A�����������P
�d���̐���͎�����Ă���B�}�X���f�C�A���A���܂́u�����A���v���u�ɉE�v��
�͌Ă�ł��炸�A�P�Ȃ�u�ێ�h�v�Ƃ��Ă���B
�x���M�[�́u�ɉE�v
�@�x���M�[�́A�k�����I�����_�ꌗ�A�암���t�����X�ꌗ�ŁA�A�M���{�ȊO�Ƀ��������{
��t���[���f�������{�ȂǂT�̒n�搭�{������A�U�̐��{����Ȃ鍑�Ƃł���B���
�����^�}�A�����{�ŁA�u�ЂƂv�̐������Ȃ��B�I���͊��S����\���ŁA�������}����
������B�A�M���{�̊t���́A�I�����_�n�ƃt�����X�n�������ɂȂ�悤���@�Œ�߂�
�����B
�@ �x���M�[�̋ɉE���}�u�t���[���X�E�x�����t�v�̓I�����_�ꌗ�̐��}�ŁA�u�x���M�[��
��̓Ɨ��v�u���ږ��v�u���C�X�����v�̎咣����������B���B�c��ł͑�P�}�ł��邪�A��
�N��}�ł���B�x���M�[�ɂ́A�u�h�u���v�Ƃ����u�ɉE�v�r���̍��ӂ�����B�u�ɉE�v���}
�������瑽�����Ƃ��Ă��A�����ɏA�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�t�����X�ꌗ�̐��}�u����̉Ɓv�́A�Q�O�Q�P�N�Ȍ㔭�������V�����u�ɉE�v���}�ŁA �܂��c�Ȃ͂Ȃ��B�L���X�g���I�ȉ��l�ς������A���S�ɂ́A�I�̃C���X�g������A�ΘJ�� �c�����C���[�W���Ă���Ƃ���邪�A�ڍׂ͕s���ł���B���d�t�����A�E�ނ͖]��ł��� ���B�܂��A�t�����X�́u�����A���v�ƘA�g���Ă���B���Ȃ݂ɁA�t�����X�͐����������O �ꂵ�Ă���A���}���ɃL���X�g���I���͎̂g�p�ł��Ȃ��B�P�X�W�T�`�Q�O�P�V�N�A�x���M �[�ɂ��u��������v�Ƃ������}������A���ږ��A������`�������������A������@���ᔽ �i�l�퍷�ʁj�Ȃǂ̖����N�����A���ł����B
�܂Ƃ�
�@�t�����X�́u�����A���v�́A���ƃt�����X���u�����邪�A�x���M�[�́u�t���[���X�E�x �����t�v�́A�n��Ɨ��u���Ƃ����Ⴂ������B�x���҂́A��N�A���N�w�A�u���[�J���[�A �j���������A����w�͎x�������Ȃ��B�_���n��̎x���������A���G���[�g�A�����f�C�A�� �����ł���B���{�ł́A�����̐��}���u�ɉE�v�ƂƂ炦�Ă��邪�A���݂̃��[���b�p�� �́A�}�X���f�C�A���u�ɉE�v�Ƃ͂Ƃ炦���A�P�Ɂu�ێ�h�v�ƂƂ炦�Ă���̂��������B �ږ��A��̂��Ƃ����ł͌��݂̃��[���b�p�̏]���u�ɉE�v�Ƃ��ꂽ���}�𗝉��ł��Ȃ��B �����̐��}�����A�}�N������T���R�W�Ȃǂ̐����Ƃ̕����r�O�I�Ȃ��Ƃ�����B�T�� �R�W�́A�u���x�ȋZ�\�������Ă��Ȃ��ږ��͏o�Ă䂯�v�Ǝ咣���Ă����B�ނ���A���݂� ���[���b�p�̌o�ώЉ�ւ̕s���A�A�C�f���e�B�e�B�[�s���A�G���[�g�s���A�O���[�o���Y ���s���Ȃǂ��A�����̏]���́u�ɉE�v�ƌĂꂽ���}�䓪�̔w�i�ɂ���B
9������ �@���ы`�F����i�{�����j�@�@�u�s���̍l�Êw���č\�z����I�I�[��J����ƈɓ������̐��E�Ɋw�ԁv
��J����[�s��ƍl�Êw�ւ̓�
�@��J���邳��́A��g�{���@�Ȃǂł����ꂽ�l�Êw�҂ŁA���N�{��̉���Ƃ��ė��Ȃlj�̊����ɂ��v�����ꂽ���A��N�S���Ȃ�ꂽ�B�҂̏��т���́A�����ّ�w�ŁA1976�`81�N�������ŗ����Ă�����J����l�Êw���w�B�u�搶�ƌĂԂɂ͈�a��������v�Ƃ����悤�Ȑe�����t��W���������B
�@���т���́A1979�N�ɍl�Êw�̐��E�Ƃ��đ��{���ςɏA�E���āA���@�ȂǕ������s���Ɋւ���Ă����B�J���ƈ�Օۑ��^���̊Ԃł͂��܂������̕������s���́A�o�u�����Œ��_���ނ����A���݂͗l�X�Ȗ�������A�Ȃ���p�ɗ��Ă���Ƃ����B
�@��J����́A�������s���̑�ꐢ��Ƃ��āA�������s���ƍl�Êw�����҂Ƃ��Ă̓������ł����B9�Ŕs����ނ����A���U�����ɂȂ��Ă����̂��߂ɓV�c�É��̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ������N�́A�s��ɂ�鉿�l�ς̓]���ɏՌ������B�l�Êw�����҂Ƃ��Ă̊�J����̊w��̍���ɔs�펞�́A��x�Ɛ�O�̂悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ��Ȃ��Ƃ����v��������B
�J���A��Քj��Ɣ��@����
�@���{�e�n�ŊJ�����i�݁A��Քj��Ɣw�����킹�ɔ��@�������s���Ă������B���Ɍ��̃��P���}��Ղ��j��邱�ƂɂȂ����B�u���h�[�U�[���Q�`�R�u�̏����������Ɛ{�b�킪��т����Ă����B�c���@���Õ��@���A�؊������������B��J����́A�s���S�������ߓ��`�Y���ƂƂ��ɔ��@�����B���_�������H���݂̍ۂ̔��@�ł́A���쐳�D���A���J�@�����炪�؊������Õ��@�A�Õ��̉��ɖ퐶����̔Ȃ̒��ɖ؊��������Ă���̂������B���_�̍H���ł́A���s�̊w������������Ĕ��@�̋Z�����B���H���c�̔�p�œ������t�����̂ŁA���@�œ������t���ƊF���ǂ낢���B���эs�Y�̖剺���������ւ��A����̔��@�ɂȂ����Ă������B��g�{�����͎R�������Y�̎w���̉��A����̒����F���Ɨ�������щ��C�O�Y���̎w���Ŋ�J�����@�����ɎQ�����邱�ƂɂȂ����B���l�����@�ŋ{�a�̉�����T�`�U���I�̑��̈�Ղ���������A��J���哱�Ŕ��@���ꂽ�B�u��J�̔��@�̌�͉����c���v�ƌ����u���@�̌����Ȑl�v �Ƃ����]�����B
���эs�Y�Ƌߓ��`�Y�̉e��
�@��J����̊w��I��Ղɉe�����y�ڂ��Ă���̂����эs�Y�Ƌߓ��`�Y�ł���B�l�Êw
�́A��J�������ّ�w�ɓ��w�������̓}�C�i�[�Ȋw�₾�����B���ł́A����Ɨ��������ɍu�����������B1974�N���A�l�Êw�̐�C������������w�́A����A���A���u�ЁA�֊w���炢�Ō�͔��������B�����ł́A�������肾�������эs�Y���n���Ђ́w���{�l�Êw�T���x���e�L�X�g�ɁA�u�l�Êw�T���v���u�`���Ă����B��J����͎l�N�ԂŎO������̍u�`�����B�l�Êw�ւ̊w���̃j�[�Y���ӂ��Ă��������1969�N���ŁA�֓��ł͑�w�̌������ɒ������ۓ�������A�������w�������������I�Ɏg�p���Ė��ƂȂ����B�u��������́v�Ȃǂ̊w���^�����N�������B1985�N�ɂ͘a�c���Ⴊ�����Ō��������J�݂����B
�@�ߓ��`�Y�͉��R�ōl�Êw���������ÁA�s���Q���^�̍l�Êw���߂����w�������̍l�Êw�x���s���Ă������A20������w�l�Êw�����x�ɖ��̕ύX���ꂽ�B��J����́A�w�������̍l�Êw�x�̎������ق����Ƌߓ��ɐ\�����ꂽ�B��J����̃X�^���X�́A�s�����Q������l�Êw�����ł���A���̂��Ƃ́A�ӔN�ɕ{�����Z�̎����l�Êw���Ɓi�{���a�����Z�j�Ɍږ�Ƃ��ĎQ�����A�Ί��y��������Z���Ɏw�����Ă������Ƃɂ�������Ă���B��J����́A���_�������ݎ��̔��@�ŏ��эs�Y������e���A�ߓ��`�Y����͕�����_���I�ɂ߂čl����X�^�C���̉e���Ȃǂ��A��J���g�͎�����ςݏグ�čl���鎩���̃X�^�C������肠�����B
�_�ˎ���
�@���Ɍ��_�ˎs�����u���œ�������������A�_�ˎs�Ɋw�|���Ƃ��ďA�E���邱�ƂɂȂ����B1969�N�ɂ͐_�ˎs�����̌ܐF�ˌÕ��������Õ��̕������s�����B1981�N�ɂ́A�_�ˎs�������قɋ߂�悤�ɂȂ�A�w�|�ے��ƂȂ����B�u�����ق̔Ԑl�I�ȑ��݂ɂȂ����v�悤���Ƃ̊��z���c���Ă���A���̍�����s���̎d�����S�̐����ɋ�ɂ�������悤�ɂȂ����Ƃ����B���̍��A�_�ˎs���̋I�v�ɂ͑S���̃q���t�~�����ւ̏W�����܂Ƃ߂Ă���B�@�@
�ɓ������i�������j�[��R������čl����l�Êw��
�@�ɓ������́A���É��ŏ��X�ƕs���Y�Ƃ��o�c���Ȃ���l�Êw�����������ݖ�̌����҂ł���B���C���Z�̍��A���Ԑ���́w���{�����̌`���x��ǂ݁A�l�Êw�҂��u�����B���É��͍s���̏o�����x���A�ً}���@���ݖ�̐l�ɂ�点�Ă����B�ݖ�̐l�͂܂Ƃ܂�ɂ����Ƃ�����肪����Ƃ���ꂽ�B�ɓ��͈��m�w�|��w�ɓ��w���邪�A���̐搶�����Ȃ������̂ŁA���É���w�ŊJ����Ă������É��l�Êw�k�b��ɎQ�����čݖ�̌����҂ƌ𗬂����B���т���͖��É��ɂ�������ɓ��̌o�c���鏑�X�ׂ̗̋i���X�ł��������������ɂȂ����B�ɓ��́A���̌��R��w�ɕғ��A�������e�[�}�ɑ��_���������B�ނ͖�R������čl���╨���̎悵�A�����̍l�Êw��g�ݗ��Ă��B���É��l�Êw��̔��N�l�ƂȂ茩������
�i�퐶����j�̔��@�����Ȃǂ��s�����B�l�Êw����74���Ɍf�ڂ����u�����̑�^�Õ��v�́A�Õ��̕��z�Œn��Љ���l���錤���ł���B1972�N�̈ɓ��̌����ƌ��݂̍l�Êw��
�����͕ς��Ȃ��B1972�N�́w�l�Êw�G���x�Ɍf�ڂ����s��5���I�̊Z�ˌÕ��ɂ��Ă̘_���̎������؍��̌����҂Ɍ��Ă��������A�����i���A�Ñ㒩�N�̉���i����j�̑����t���{�̂̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��킩�����B
��J����ƈɓ������̍l�Êw�̋��ʓ_
�@��l�̓���������l�Êw�҂ɂ͑����̋��ʓ_������B�ނ�́A�s���ɐV�����l�Êw�̐�������B���w���̍�����l�Êw�ɊS�������A��w�Ő��x�I�ɍl�Êw�̋�����Ă��Ȃ��B����́A1950�`60�N��ɍl�Êw���w�҂ɋ��ʂ̂��肩�����B
�@��l�͒n��̎������W�ɂ��n��I�l�Êw�������s�����B��J�́A���d���E���ےÂ��������A�u�퐶����̓��d���v�i�w�_�ˎs�j�x�j�������A�q���t�~�����ւ̑S���I�����W�����s�����B�ɓ��́A�u�����̑�^�Õ��v���܂Ƃ߁A�Õ����z�ɂ��n��Љ�̗��j��`�����B
�@����A��l�̈Ⴂ�́A��J���E�ƓI�����҂ƂȂ�A�ɓ��͍ݖ�̌����҂ł��������ƂŁA��J�͕������s���̑�ꐢ��Ƃ��Ă̋�Y���o�����A�Ɩ��Ɉ�������A�ϋɓI�Ȍ�����1980�N��܂łł������B�ɓ��́A�l�Êw�ɐ�]�ł��Ȃ����Ƃւ́u�˂��݁v�����������A���U�����̍l�Êw�҂ł������B
���܈����p���ׂ����Ɓ[�s���̍l�Êw�̍č\�z��
�@���݁A�����������s���͋Ȃ���p�ɗ��Ă���B1970�N��ɍ\�z���ꂽ�u�L�^�ۑ��̐��v�͐��x�A�w�⌤���Ƃ��Ă����E�ɂ��Ă���B1970�N��ɊJ���ɂ���Քj�����݁A�������ی�@�����肳�ꂽ�B���@��p�͌����ҕ��S�ƂȂ����B�����������Z���^�[�́A���ނ���A�����̐E���͌������Ƃ��Ė������狋�^����B���c�@�l�̂��̂́A���Ƃ�������ƁA�������܂܂��B�E���̐g�����قȂ�B���݂́A����ɔ��@���������Ԉϑ��ɂȂ��Ă��Ă���B���т���̎���͐E���Ɉ�Ղ����ӎ������������B���݂͑�w�̌������ő̌n�I�ɋ������A���@�����K��3�T�Ԃ����s���邪�A�w���͌���ɗ�������Ȃ��B�╨�̌��������S�ƂȂ�A����łȂ��s���w�����D���Ȏ҂��ӂ��Ă���B�����s�������[�e�C�������Ă���B����ŁA�l�Ï���i������A�ό������̑ΏۂƂȂ�A������ꂢ�ɂ��邱�ƂȂǂɗ͂�������Ă���B����Ŗ{���ɕ�����������̂��B�s���͍l�Ï��̏���҂ɂȂ��Ă��Ȃ����B1950�`60�N��̎s���A���Z���A���������͒n��̒����ɎQ�����A�s���̍l�Êw�҂��吨�����B�s���̔��@�����W���[�ƂȂ��ď�Ɛ肳��Ă���B�ݖ�̌����҂͂��܂ǂ��ɍs�����̂��B���܂����s���̍l�Êw���č\�z����Ƃ��ł͂Ȃ����낤���B
8������ �@�R���N������@�@�R�����e�C�^�[�E�ԒˍN�Y����i����j�u���s�̊w���W�c�a�J�j�|���ꑤ�E�l���n������̍l�@�v
�u�ڏZ�ҁv���܂߂��n��j���K�v
�@�R������́A�w������͓��������̐�O�E�풆�ɂ�����h��̐���e��̖��O�����ɂ��Č������Ă����B���̉ߒ��ŁA���j��e�����̎j�ɂ́A�a�J�҂�ڏZ�ҁA��������̒��p�H�Ȃǂ̌��O��������ė����l�X�̌����E�L�^���������Ă��邱�ƂɋC�������B���̂悤�Ȑl�X���܂߂��u�n��̗��j�v�A�u���{�̗��j�v���K�v�ƍl�����B
�@�w���a�J�ɂ��ẮA�c�ꂩ��푈���Ɏq�ǂ��������������ɂ����Ă����ƕ����Ă������A�Ȃ��������̌������Ȃ��̂��Ǝv�����B���s�͊w���a�J�ɂ��Ă̒����E������������ł����B����ŁA�a�J�w�������ꂽ���̒����E�����͏��Ȃ������B�����ŁA�������ւ̊w���W�c�a�J�j���͂��߁A��w�@�ł́A�l���n���ւ̊w���W�c�a�J�j�ɂ��āA��Ɉ��Q���Ɠ������ɂ��Č��������B
�w���a�J�̂͂��܂�ƍ�_�n��̑a�J��
�@1944�N�̃T�C�p�����̐킢�A6���̖k��B�����Ȃǂ̐틵�������āA��s�s�̍����w�Z�����Ȃɒʂ��w���̑a�J�𑣐i���邽�ߊw���a�J�Ɋւ���2�@�Ă�1944�N6��30�����肳�ꂽ�B�u�w���a�J���i�v�j�v�Ɓu��s�w���W�c�a�J���{�v�j�v�ł���B ��P�K���̏œs�s�h����~���ɍs���A����̐�͂ƂȂ�q�ǂ������i�u��2�����v�j���Q�����邽�߂Ɋw���a�J���s���邱�ƂɂȂ����B
�@���s�A�_�ˎs�A���s�̊w���a�J���s��ꂽ�B�w���a�J�̌����́A���̑a�J�ʼn��̂ɗ���Ȃ��ƒ�̊w���͏W�c�a�J�ɎQ�������B�Ώۊw�N�́A�����w�Z�����Ȃ�3�N���ȏ�6�N���܂łł������B�w���a�J�̐\�����ݏ́A�W�c��96119���A���̂�116950���A�c����149603���ŁA�v362672���ł������B
�c�������q�ǂ�����
�@�W�c�a�J�ɎQ���ł��Ȃ������q�ǂ������������B�a�J�O�̒����ł́A149603���������B���̗��R�͗l�X�ł��邪�A�@3�N�`�U�N�܂ł̉��̂ɗ���Ȃ��w���E�A�a�C��Ⴊ���A���̑��̖���������q�ǂ��͐g�̌����ŏ��O���ꂽ�E�B�w����l�����茎10�~��ی�҂����S�������A�n���ƒ�Ƒ��q�ƒ�͎x��������������A�C�a�J�����ɕK
�v�ȕ��i���K�v�ł������A�D�W�c�a�J����]�����̂��ɉ��̑a�J��c���ɕύX�����ҁA�Ȃǂł���B�i�c�������Ƒa�J�g�Ƃ̊Ԃɂ́A���ꂫ�̂��������Ƃ��L�^����Ă���B�����̐ԒˍN�Y����Љ�̎����s�����ہw�l�̐푈�x�t�ɂ��ƁA�ʏo�����w�Z�̎c���g�ɁA�W�c�a�J�����w����������̎莆���͂����ہA�u�����͐Â܂肩�������B������A�܂���ʓ͂����B�w�搶�ǂ܂�Ƃ���!�x������������B�w���������H�Ƃ�����A���S�Ȓn���֓������z�Ɏ莆�Ȃo���ւ�x�c�������͑a�J�����Ɍ������G�ӂ������A��P���Ɏ���ł������B�j
�l���n���̎����
�@���s�̑a�J��́A���ɂ������ߋE�n���Ƌߐڌ��ƂȂ����B7��25���܂łɁA���A���s�A����A�ޗǁA�a�̎R�A�ΐ�A����A����A�����A���Q�A���������܂����B7��22���Ɂu�a�J�����ܐ�l�����֎����������v�Ɠ����V���ŕ��ꂽ�B���ŁA�����i���Q�j��7��25���A�u�a�J�w�������֎O��l���R�֊w�k�o�w�v�Ƃ���B�����̑a�J�n�͍���Ɠ�����2���ł��������A�n���I�ɗ��ꂽ���Q���̂��ɑI�肳�ꂽ�B��㑤�́A�n���I�ɂȂ�ׂ���_�ɋ߂��Ƃ������]���Ă����B�ŏI�I�Ȋ����́A���Q���͍��ԋ�A���쌧�͍`��E�������A�������͑吳��E�������ƂȂ����B�����A���ԋ�͐ΐ쌧��\��A�������͑��{���獁��Ɠ����ɕύX���ꂽ�B���������܂�܂ŁA�����ƐՂ��J��Ԃ��ꂽ�B�ύX��������������A����Ԑ��̏������\���ł��Ȃ����Ƃ��������B
����Ԑ�
�@�����̎s�����́A��������r�I�L�x�ʼnq���E��Ñ̐��A��������Ȃǂ���������Ă���Ƃ��납�犄�蓖�Ă�ꂽ�B��㑤�́A�{�s�̖�l�E�{�x�x���E�s�c��c���Ȃǂ��A������̌��́A�n�����������E�s�������E���w�E����t��E����{�w�l����Ȃǂ����͑Ή������B�������ł́A�a�J�w��������邽�߂ɍ��R�l���L���@�����邱�Ƃ��������B����������7��1���̎��_�ŁA�a�J�ҏZ��ނ̓��肪����ŏZ��c�c�@�̉�����v�]���Ă���B�܂��A�a�J�҂���������ΕĔ��̔z���𑝂₷�悤�ɍ��ɗv�����Ă���B��������ւ̗v�]�Ƃ��āA�u�����h�q�̑�a��v�̐��_�Łv�������}������A�K�v�ȕ����A�ݔ��Ȃlj������Ăق����A�����E�w�Z�E�_�Ɖ�E�w�l��E���N�c���̑��������S���̋��͂Ŏx���Ăق����Ƃ����v�]���Ȃ��ꂽ�B�������A�W�c�a�J��Ɏ��ޕs������e�n�̏h�ɂł͐ݔ��̕s�������o�A���ƂȂ����B�������̒�����ł́A�쉶���������w�Z�̎q�ǂ�����16�l���ݔ��s�ǂ������̉Ύ��ŖS���Ȃ����������������B�����̕��S�͎�����̍s���������ׂ��Ƃ���𒊏ۓI�Ȑ��_�_��p���Ēn��Љ�E�Z���ɓ]�ł��ꂽ�B��㑤�Ǝ��������������9��11���܂łɊ����悪�m�肵���B���Q���̍ŏI�I�Ȏ���l����2925�l�Ɍ��܂����B1944�N9�����_�œ��\�n��1097�l�i����980�l�j�A����\�n��1828�l�i����1562�l�j�ł������B�l���������������R�́A�W�c�a�J����]��������
�ł����̑a�J�ɕύX���\���������Ƃɂ��B
�w���a�J�J�n�Ǝ����
�@1944�N8��28���A���{���̊w�����a�J�n�֏o�������B�l���n���ւ̏W�c�a�J��9��13������͂��܂�A�Վ���ԂƗՎ��D�ւł̈ړ����s��ꂽ�B�e�n�̑a�J�n�ł͎�������}���A�a�J�w��������ɑ��ċB�R�Ƃ����ԓx�ʼn�����A�Ƃ����\�}������ꂽ�B
�@�a�J�w�����Z���Ɉ�������ė�Ԃʼnw�ɓ�������ƁA�n���̋����E�s���㗝�E�����w�Z�Z���E�w�l��E�w���Ȃǂ����Č}�����i���Q�j�B�a�J�w�������́A�o�����镺������̂悤�ɑ����Ă����B���������ȁu�o�����镺������v��V���Ђ͉��o���ĕ����B
�@����ŁA�a�J�w�����₹�ׂ��Ă��Đ��C�̖����p�ɁA�}����l����͂��ߑ��������Ƃ������Ƃ��������B�a�J�w���̓��L�ɂ́A���������}�����������Ƃ�A���̓��̖�Ɂu�����ւ����������Ă��������܂����B���������������������܂����B�v�Ƃ������z���������B���̊w���ɏ��߂Č\�K�̏��������n���ꂽ�Ƃ��A���܂���������̐搶�ɏo���Ȃ����ƌ���ꂽ���A�o�����̂͏��q�w���̈ꕔ�ŁA���Ƃ̎q�ǂ��͑S���g���A�j�b�L��m�O�A�щ��ł��͂��H�ׂ��҂������B���т̔z���͏��Ȃ��A�w���������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ������B����Ԑ��\�z�̉ߒ��Ő펞���{�̑��͐�Ԑ����_�Ԍ�����B
�����Ƒa�J��
�@�a�J�w���̓������́A�Z���͔M��Ɋ��}���A�H�����ӂ�܂����B����ŁA�a�J�҂ɑ��镗������͋����A�a�J�҂̕����̔�������Ȃǂ��ᔻ�̓I�ƂȂ������Ƃ��������B
���Q�V���͎А��Łu�n���ւ䂯�Ε����͖L�x���B������������Ƃ����E�E�E�������ׂ��s�ׂ��A�E�E�E�n���l�͑����Ɍx�����Ȃ���Ȃ�ʁB�v�ƌ����ɒ��ӊ��N�����B�������A�w���ɑ��Ă͂����܂Ŋ��e�ɁA����̍������琬������j�ł̂��݁A���N�j���̑a�J�҂𑄋ʂɂ����Ă����B�V���Ђ́A����ł���w���a�J�ւ̗������Z���̒��łЂ낰�邽�߂ɕ𗘗p���A�w���a�J�ł́u����v�Ƃ���������g���Č�����������Ă����B
�a�J�����̏[�n��Ƒa�J�����̕��G�ȊW
�@�a�J�w���̐H�Ǝ���́A�z�������Ȃ�����������̂ł͂Ȃ������B�a�J�O�����̏d�������������݂�ꂽ�B���M�������w�Z�̌���������ƁA�ꕔ�̓��������A�Ĕт����сA�������͖�����S�Ŗ��X�`�ƒЕ����t���B���⋛�Ƃ����������^���p�N���̗����͎��X�����H��ɏo�Ȃ������B�������A�H�Ǝ���͒n��⎞���ɂ��قȂ�A��T�ɐH�����s�������Ƃ͌����Ȃ��B�n���̊w�����a�J�w���������ɐH�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�������A��r�I�H�ƂɌb�܂�Ă����ƒ������A�������Ă��Ђ������v�������Ă����킯�ł��Ȃ��B�a�J�w���͂Ђ����������A�Ƃ�����ۂ���s�������ʁA�����̑a�J�̃C���[�W�������Ă��邱�Ƃ��l������B�n���Z������̎x�����������B�u�Ȃ��݂̉Ƃɍs���ƁA���̓s�x���݂₰��������ċA�����v�A�u�w�l����⏗�w���ɂ����������A������c���̊�t�A�H�Ƃ̊v�Ȃǂ̋��͂��݂�ꂽ�B����ŁA�䂫�������u����v�E���� �����E�s�e�E�͂ȑԓx�ȂǕ��G�ȊW������A��肪�������邱�Ƃ��������B
�̐U��Ԃ�
�@�w���a�J�̖ړI�́A�s�s�h��̉~�����Ǝ���̐�͂Ƃ��Ă̎q�ǂ������̐�������邱�Ƃł������B�������A�W�c�a�J�ɎQ���ł��Ȃ������w�������������B�V���Ђ͊w���a�J�̑��i�E���m�ɍv���������A�u����v�����܂����p�����B������́A���E�a�J���E�n��Љ�E�Z���ɗv�]���]���o�������A�n��ƏZ���̕��S�Ƃ��Ȃ����B����Ԑ��\�z�ߒ��ɐ펞���{�̑��͐�̐����_�Ԍ�����B����̌��������́A�j���̓����𗝉����A�Œ�ϔO�ɂƂ��ꂸ�j���ᔻ���J��Ԃ����Ƃ��d�v�ł���B
���ԒˍN�Y����R�����g
�@ �@������1935�N���܂�ŁA�����w�Z�̑n�����ɓ��w�����B�R����`������A�s���A���ȏ��̃X�~�h����������A�u�����`����v�������A���̌�A�܂����������Ƃ������A�u���܂��ꂽ�v�̌J��Ԃ��Ƃ�����ۂ�����B�����ŁA�V���𗘗p���悤�Ƃ������A�l���ł͐}���قɂȂ��̂ŁA�V���Ђɒ��ڍs������A1��500�~�ƌ���ꂽ�̂ł�߂��B�R������̒����́A���k
�Ȍ������Ǝv���B�����w�Z2�N�̎��A��P�����邩�玨�Ɏ�����ĉB���A�̓n�^�L�ł������ď����A�Ȃǂƌ���ꂽ���A�����Ƃ����ɗ����Ȃ������B�o�g�́A�ؒÐ�s�ő���P�������ɒ��߂Ă����B�_�ˋ�P���o�������B�h�ɓ�������A�y��������ė����Ă��ċ��|���������B�I�풼�O�A���H��H�ׂɋA��ƌx���x��A�@�e�|�˂����B���s�E�ޗNJԂ̌R�p��Ԃ��_��ꂽ�B�w�Z�ł́A�u���������Q��܂����v�ƌ����ĐE�����ɓ���Ȃ��ƁA�搶����蒼�����������B�����̎���͑a�J��F�߂Ȃ������B6��30���ɓ�����t���ސw��A�a�J���F�߂�ꂽ�B
���Ό����q����R�����g
�@ �@���̊w���a�J�͐V�C�s�j�j���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B���s�̋���ǂ̎j���ŁA1944�N9���A1945�N4����P�O�Ƌ�P��̂��́A1945�N7���A1945�N7���`8���̂܂Ƃ߁A���L�^����Ă���B1945�N�̊w�Z���Ƃ̏��a���v������A�쉶�������w�Z��16�������S�����L�^���c����Ă���B�������V�}�������M�d�Ȏj���Ƃ��Ďc�����B��2���W�c�a�J�ɂ��ċD�Ԃ̎����\������B1945�N�A�l���ւ̑a�J�͋@���̐ݒu�ŊC��n�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B
�����^�E��
�R������@����͎̕l���ɂ��ڂ����B�h��@�����ō����͎��O�ɓs�s����ދ��ł��Ȃ��Ȃ����B�a�J�����҂��u�������z�v�Ƃ����������������B
�Ԓ˂���@�a�J�����͉ƂɋA��܂Ő푈���I���Ȃ������B
���삳��@�����������Ȃ��A�V���L���ɂ���炴��Ȃ��B�n��łǂ��~�߂�ꂽ �̂��A���������Ȃ��A������肪�d�v�ŁA�R������̌����͋M�d���B�`��̑a�J�������V�ێR�łȂ��A���R�̉F��`���獂���ɂނ��������R�͑䕗�ł����H
�Ό�����@�䕗�ŏo�������ƂȂ�A���[�g���ύX�ɂȂ����B
�哇����@�����s�̏o�g�B���n��̎���Ȃǂ����Ă��邪�A�a�J�̎��̂����ꂼ��قȂ��Ă���̂������Ǝv���B
�ɉꂳ��@�쉶�������w�Z�ɋΖ��B�^�����i�������邬������j�ɏW�c�a�J���Ă����쉶���������w�Z�̐��k16�l���ЂŖS���Ȃ����B16���𓉂�1946�N�ɒn���Z���炪�\�Z�n���������������B���݁A�쉶�������w�Z�ł͏\�Z�n���̃��j�������g�A��ݓW���Ȃǂ��q�ǂ���������莆�ŋ���[�`���[�u�ɂ�����Ȃǂ��Ȃ���A�a�J�̖�������Ɏ�����Ă���B���N�͔��\���N�Ő^�����ƃY�[���łȂ��Ƃ肭�݂��s���Ă���B�����c����13�l���w�Z�֗��ď،����Ă��ꂽ�B�펞�̗��j���ǂ��Ȃ��ł䂭�̂��A�n��Ɗw�Z�ōl�������B���Ǝ����ł��Ȃ������q�ǂ����������Ǝ����������Ƃ�����]���o�Ă���B
���Y����@���鍑���w�Z�̑a�J�������������X�ő��Ǝ����������Ƃ�����]������A�݂�Ȃŋ��͂��đ��Ǝ����������Ƃ�����B
��т���@���s����a��s�n��ɂ��a�J���������Ă����B�a��s�ŋ�P�����Ȃǂ��܂߂Đ푈���ӂ肩���鋳���n��Ɗw�Z�����̋��͂Ŏ��g��ł���B
��������@�i�w���a�J���j�n���w�Z�ɂ���Ă��������Ԃ�����B�a�J�̈�ۂ́A�u�H�ׂ��Ȃ��v�u�����߂�ꂽ�v�̃X�e���I�^�C�v�����y���Ă��邪�A�R�����āA�������������ׂ�K�v�̂��邱�Ƃ��킩�����B�a�J���Ƃ�����ŁA�n��ɍٗʌ����������̂��H�w���a�J���܂߂Ăǂ�ȑ��͐�̐��������̂��H
�R������@���̎���͂ނ��������B���Ǔ������킩��Ȃ������B�u�푈���́v�Ƃ́A�n��Љ�S�̂��u����Ă����Ȃ̂��H
�с@�W�c�a�J�ƏW�c���Ƃ����ꍇ�����邪�A�Ӗ��̈Ⴂ�͉����H1944�N6���ɖk��B�ɔ��������������A��B�̑a�J�͂�����n�܂����̂��A�������̂��H
�Ό�����@�W�c����n�܂����Ǝv����B�����ł͔��ƌ���Ȃ��B���ʂ̌������ɏW�c���̌��t������B���K�I�ȈӖ�������B
�R������@��B�̑a�J�ɂ��Ă͂킩��Ȃ��B
7������ �@�����b�q���� �@�u�~�����}�[�̌���ɂ��ā|���̍��̎x��������ʂ��āv
�~�����}�[�A�M���a��
�@��s�͌��݃l�[�r�h�[�i�ߋ��Ƀ����S���A�����O�[���j�ŁA����̓~�����}�[��i�r���}��j�ł���B�����̖�70���̓r���}���ŁA���̑��P�R�T�̏��������i�V�����A�J�����A�J�`���A�p�I���Ȃǁj������B�@���͂X�O���������k�A���ɃL���X�g���A�C�X�������ȂǁB���y�ʐς�68��Km2�œ��{��1.8�{����A�l���͖�5500���l�ł���B �@��v�ȎY�Ƃ́A�_�ƁA�V�R�K�X�i����A�W�A��3�ʁj�A�����ƁA���r�[�E�T�t�@�C�A�E�Ő��Ȃǂ̕�A�����؍ނȂǂ̓V�R�������L�x�ł���B
�R���ƍِ����̐����Ɩ��剻�^���ABRCJ�|���̍��x���J�n
�@�r���}��1948�N�ɉp�̐A���n����Ɨ��A1962�N�ɍ��R���N�[�f�^�[���s���A�l�E�C�����R�ɂ��ƍِ������n�܂����B1982�N���Ж@�̉������s���A1823�N�ȑO�Ƀr���}�i�~�����}�[�j�ɐ��܂�Ă��Ȃ��l�́A�r���}�i�~�����}�[�j���Ђ����ĂȂ��Ȃ����B�i1824�`1826�N�̑�ꎟ�p�Ɂi�C�M���X�E�r���}�j�푈�̈ȑO�Ƀr���}�ɏZ��ł��Ȃ������l�͔�y�����������ŁA1948�N�̍��Ж@�ł̓C���h�l�Ȃǂ��������A�A�������Ƃ���O��o�߂���ƍ����ɏ��i�����j���q���M���̐l�X�Ȃǂ́A�����Ƃ��ĔF�߂�ꂸ�A�Љ�S�̂łЂǂ����ʂ��Ă���B
�@1988�N�R�������ɔ�����w���𒆐S�Ƃ���s���̖��剻�^�����S�y�ɍL�������B�s���̔�\�͂̉^�������R�����͂Œe���A����l�̎����҂��o���B���E�ɂ��̃j���[�X���`����ꂽ�B���̍��A�������r���}����~�����}�[�ɕς���ꂽ�B���̔N�̔N������88����ƌĂꍑ����R�̃V���{���ƂȂ��Ă���B1989�N�A�E���T���X�[�`�[���R�������ɂ���ւ����B1991�N�X�[�`�[���m�[�x�����a�܂���܁B
�@��������́ABRCJ�i��ʎВc�@�l���{�r���}�~���Z���^�[�j�̑�\�����ł���B1988�N�̌R�������ɔ�����s���̒e�����A�����r���}�E�����O�[���ɑ؍ݒ��ɖڌ������������w�Z�̉p��̐搶���������n�A�����J�l�̃J���T�L�E�P���A���B�T�J�v�Ȃ͔�Q�҂����@����a�@�ւ̕���������J�n�A���ꂪ���ƂɂȂ�ABRCJ�����܂ꂽ�B�Ȍ�A�^�C�����̓�L�����v�ł̋��犈���ȂǁA�r���}�i�~�����}�[�j�̐l�X�ւ̕��S���ʂɂ킽��x���𑱂��Ă���B
��������́A�Ζ���̊w�Z��BRCJ�̐搶���������A�r�f�I�ɓ��{��^�C�g���������肵�ċ��́A�J���T�L�����A����ɑ�\�������p�����B
NLD�̑��I������
�@1990�N���I����NLD�i��������A���j�������������A�R�͌��͈ڏ������ہA�s���̒e�������߂��B2007�N�m���Ǝs���̔����{�f�����s��ꂽ���A�R���������e������Q���ŁA���{�l�W���[�i���X�g���䌒�i����ޒ��ɎˎE���ꂽ�B2008�N�A�T�C�N�����E�i���M�X���P������ɐV���@�̍������[���s��ꂽ�B2011�N�X�[�`�[����̓�ւ�������A2012�N�̕⌇�I���ŃX�[�`�[�����NLD���҂����I�����B2025�N�̑��I���ŁANLD���������ANLD�������a�������B�e����`���[�����哝�́A�X�[�`�[�����ƌږ�ɏA�����B2018�N��NLD�̃E����~���哝�̂��A�C���A2020�N�̑��I����NLD���Ăш��������B���ێЉ�́A�~�����}�[�������ڊǂ����ƔF���A�o�ϔ��W�ւ̓����J���ꂽ�B
�R�̃N�[�f�^�[�Ɩ\�͎x�z�ɋ����Ȃ������̒�R
�@2021�N2��1���A�~�����}�[�R�ɂ��N�[�f�^�[���N����ANLD�̊���400�l���S�����ꂽ�B���R�ɂ��\�͎x�z���s���Ă��邪�A����ɋ����Ȃ������̒�R�������Ă���A�R�c�f���͑����Ă���B1988�N�̃N�[�f�^�[�̎��̃f���͒��������Ȃ��������A2021�N�Ȍ�͍R�c�f���͑����Ă���A�u�X�v�����O���{�����[�V�����v�ƌĂ�Ă���B�������̎d�������Ȃ�CDM�i�s���s���]�^���j���s���Ă��邪�A�R�͂���ɑ��Ď��e�C���Ēe�����s���Ă���B769�l�����S���A4000�l�]�肪�S�����ꂽ�B����ɋA��ƌx�@������̂ŁA���������n��⍑���̊O�֓����Ă���B���{�ɂ�CDM�̒��w�Z�̐搶�����Ă���A��\�������Ă���BPDF�i�l���h�q���j�́ANUG�i�������ꐭ�{�j���F�߂��R���ł���B1988�N�����͓����邾���ł��������A2021�N�Ȍ�͎��������̖�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�F�߂Ă���B�������A����͎��O�̕���ł���A���ʂ̌R���Ŏg�p����悤�ȋ��͂ȉΊ�Ȃǂł͂Ȃ��B�~�����}�[�̐l�X�́A���݂̏��u����v�Ƃ͍l���Ȃ��B���R�̍U�����玩�������̐g����邽�߂ɂ�ނ���������������ē����Ă���ƍl���Ă���B���������̌R�������ɐ���Ă���B�n���ł́A���������������A���R�͋ōU�����Ă���B5�`6���Ɋw�Z��_�����U�����s���20���l�̎q�ǂ��������S���Ȃ����B3��28���}�O�j�`���[�h7.7�̒����^�n�k���N����A�����6.9�K�͂̒n�k���N����3800�l�ȏオ�S���Ȃ������A���R�͋𑱂���500�l�ȏオ�S���Ȃ����B
���q���M�����
�@���q���M���ɑ���~�����}�[�Љ�̍��ʈӎ��͍��[�����̂�����B�X�[�`�[����̃��q���M�����ɑ���i�͂����肵�Ȃ��j�p���ɑ��āA�C�O����͎��]�����Ƃ��������o���B����������Ă���ۂɂ��X�[�`�[����ɑ���^��������l�ɏo������B���q���M �����ʂ́A���R����ʍ����������ɂ������Ƃɂ�荑���x�z�����₷�����邽�߂ɈӐ}�I�ɍ��ʂ����ނ������ʂ��B2016�N��NLD�������ł������ɁA�ߑ㉻�ւ̊��҂��������B2017�N�A�x�@�P���������N����A���R�����q���M�����U���A70���l�����O�֒E�o�����B���ۓI�ɃW�F�m�T�C�h�Ƃ����ᔻ���N���������A�X�[�`�[����̓W�F�m�T�C�h��ے肵���B�X�[�`�[����ɂƂ��āA���q���M�����ɂ��Ắi����ȉۑ�ł�����������I�Ɉӌ��������邽�߂́j�Ώ����鎞�Ԃ�����Ȃ������Ǝv����B2021�N�Ȍ�A�R�ɒe�����ꂽ�����̒��ŁA�������Ƃ����q���M���ɑ��čs��ꂽ���ƂɋC�Â����l�X����A�u���q���M���ɑ��Ă���܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������e��������B���q���M���ɑ��鋭�����ʈӎ��͍���ω�����ł��낤�Ǝv����B2012�N�A���q���M���̓�L�����v�ɍs�������A�^�C�̃L�����v�Ɋr�ׂĐl�������A�����������Ƃ��Ă��Ȃ��ĕ��������̂ɂ��������Ă����B�Ђǂ���炵�����Ă���A��l�ɃC���^�r���[�����悤�Ƃ��Ă��q�ǂ����������͂ނ̂ŁA�o���O���f�V���̃z�e���ɌĂ��A�ނ�̓z�e���̎����ɓ���Ă��炦�Ȃ������BBRCJ�̂悤�ȏ������g�D�ɂ͎x���������ނ��������Ǝv��ꂽ�B
���R���x���鐨�͂Ƃ�
�@���|�I�����̍��������R�̖\�͎x�z�ɒ�R��NLD���x�����Ă��钆�ŁA���R���x���Ă���̂́A���R�n��̉�ЁA�O�����͂ł��郍�V�A�ƒ����ł���B���V�A�́A�q��@�ȂǕ���A�o���g�債�ė��v�Ă���B���m�̌P�����s���Ă���B�����́A�~�����}�[���o�ăC���h�m�ɐi�o���郋�[�g���m�ۂł���̂ŁA���̒n����������Ă������Ƃ͏d�v�ł���B�������{���i�o���Ă���A���{�l���U�����܂ꂽ�^�C�����t�߂ɂ���L���ȍ��\���_�͒������{���J���A���v�Ă���B�����ЂƂ��R���x����o�ϓI��Ղɓ��{��ODA������B�~�����}�[�ɐi�o������{��Ƃ�����������B�L�����́ABRCJ���܂ނm�f�n�Ȃǂ̍R�c�v���ɂ���Ĉ����g���邱�Ƃ����肵�����A�܂����{��ODA�ɂ�鉇���͑����Ă���A���̎����͌R�ɗ����悤�ɂȂ��Ă���B�N�[�f�^�[�̂��ƁA�����}�̖������Y�͌M�͂�������Ă���B����̓��{���c�́A���P�C�R�[�Ɍ��݂����Z��n���R���������Ƃɑ��āA�܂������R�c�����Ă��Ȃ��B
BRCJ�̑��̍��̎x��
�@�x�������Ƃ��āA�u�ً}�l���x���v�Ƃ��ĕĂ���Ȃǂ̐H���E�����x���A�{�v���W�F�N�g�Ȃǂ̎����x���A�u����x���v�Ƃ��Ċw�Z�Z�Ɍ��݂�w�p�i�Ȃǂ̎x�����J�E���^�[�p�[�g�c�̂Ƌ��͂��čs���Ă���B���N�A�^�C�����̓�L�����v�Ɏx���ҁA�c�̂��ē�
�[�c�A�̂h���i�����j���l�s�����B���u�Ђ̃T�[�N�����c�A�[�ɎQ�����A�ږ��w�Z�œ��{������������\��B�x�������Ƃ��āA�u�\�[���[�����^���v�i���z�����d�ŏƖ����Ƃ����܂肽���݉\�ȃR���p�N�g�ȃ����v�j�⎕�u���V�����Q����B�T�C�N�����E���M�ɂ��ЊQ�x�����s���Ă��邪�A�R�ɕ������킽��Ǝs��Ŕ����Ă����肷��̂œn���Ȃ��B��ٓ��Ŏx�����������Ă���̂Ŏ^�������J���p���̂��Ă���B
�@�n�k��T�C�N����������A�l���x������ЊQ�x�����s���Ă���B�R�������͓����Ȃ��B
����K�⊈�����s���Ă���B8���Ɋ烁�\�b�h�Ɍ������B�܂��x���c�̂ɏꏊ����
�Ă��炤�B�����������Ă���Ă���Y�����̖͌^��A�^�C������L���ȍ��\�̊�n�̃r���Q�������肷��B�����͒������{�ō���Ă���̂ŁA�^�C���̃J�t�F�́A�u�`���C�i�r���[�v�ƌĂ�Ă���B���\�b�h�́A���\�̂��Ƃ�����̂œ��{�l�̓������x������Ă���B���ꍼ�\���^����̂Łu�~�����}�[�x���v�Ƃ������Ƃ������ł��Ȃ��B�~�����}
�����݂͌��ɏ��������Ă���B���K�v�Ƃ����x�����A�̔�Q�ɑ�����̂��B�h���K�v�ŁA�J���[�B��J�����B�Ŕ�Q���傫���B���z���ނ��l�オ�肵�āA���ς��肪���Ă�����l�オ�肷��B�펞���̓��{�̂悤�ȁA�����Ȗh��肪�ł��Ȃ����������Ă���B���[���ł̂��Ƃ�̒��ŁA�u�������̊w�Z�����S�łȂ��Ȃ�܂������A����ł��w�Z���J���܂��v�Ƃ��������A���̌�A�u�߂��̊w�Z����������A���炭�����܂��v�Ƃ����A���������B
���^�E��
�����삳��@���q�����M�̏@���́H�i�����j�C�X�������ł��B���{���{�̌R���ւ̎x���́H�i�����j�{�����ɁB
���咬����@���q�������R�̋���Ɋւ���Ă���B�͐�ӑr���ɂȂ���B�����͑����Ă���̂��H�i�����j�J���[�B�ɂ͍U�����g�債�Ă���B�����j���[�X�͕����Ȃ��B�~�����}�[�ԏ\���͌R�̎x�z���ɂ���B�ԏ\����ʂ�������͌R�ɍs���i�~�����}�[�����Ŏ��Ƃ�W�J���Ă���C�I���Ȃǂ͌R�ɋ`������n���j�B
���x�z����@���w�c�A�[�̓}�C�N���o�X�ň��H���s����ς��B���j�Z�t�⍑���Ȃ���t�c�Ȃǂ̍��ۑg�D�Ƃ̊W�́H�i�����j������L�����v�ł͍��ۑg�D�Ƃ̊W�͂Ȃ��B�a�@���݂́u�W�����O���N���j�b�N�v�ƌĂ��a�@��������B�����ǂ̊댯��������̂ŁA��Ï]���҂̋��Z�{�݂͕ʓ��Ɍ��݂���B�w�Z�E���@�Ȃǂ̌��݂́A�ޗ���𑗂�A�n���̃R�~���j�e�C�����B�����́A�|�A�؍ށA���[�J���̗t���W�߂č��B�����ƌR���{�͗F�D�W���B �@�����ґS���̈ӌ����f�ڂł��Ȃ��������Ƃ����l�ђv���܂��B �i���ӁE�с@�k��j
��BRCJ�i��ʎВc�@�l���{�r���}�~���Z���^�[�j�͎x��������������肢���Ă��܂��B
���N����@�l���6��~�i�N�j�@�@�l�E�c�̈��1���~�i�N�j
��������T�@���[���ł̊����A�^�C�E�r���}�����K��ւ̎Q��
�����N���A�����ȃv���[���g��܂�
���������@�@�EQR�R�[�h�̐\�����݃t�H�[��
����t���������́@�u�䂤�����s�v00930�|0�|146926 ���`�͂a�q�b�|�i�@���s��������͓X�������[���n�`�X��408
�u�肻�ȋ�s�v�����x�X�A�ԍ�6553928�i���j ���`�͓��{�r���}�~���Z���^�[
6������ �@�� ��������u���{�Ӌ���̗��j�|�����ւ̊��]�F�_���̂Ȃ������鎞�v

�͂��߂�
�@���悻�T�O�N�قNj��s�{���ӊw�Z�œ����Ă��܂����B�ӊw�Z�̂��Ƃ��_���̂��Ƃ���ؒm�炸�ɔ�э��݁A���̊Ԃɂ��_����D���l�ԂɂȂ��Ă��܂����B�P�T�N�O�A���̎v�����u�Ԃ�Ȃ킽���v�Ƃ����G�b�Z�C�Ɏd���Ă��̂ł����A����ɋȂ����Ȃ�ė\�z�����܂���ł����B
�����^���Ƃ���
�@�܂��A��㖯�O�j������̎�|�ɍ��킹�āA�����ȉ^���Ƃ̏Љ�����܂��B���s�ӈ��@�𑲋Ƃ��吳���̔��R�^���ɎQ�������Ӑl�E���쌓���Y�B���s���ӊw�Z�ŃG�X�y�����g���w�ѕߔ����ꂽ���ށi�ɓ��O�Y�j�Ɣނ��x�����Ӑ������B����E�ɓ��Ƃ��Ȃ���A�v�����^���A���y�����Ŋ��Z���ԂȂ��珑�L�����Ƃ߁A���������^����J�������ɂ�����������㎋�̍�ȉƁE��c���`�Ȃǂ��������܂��B
�Ⴊ���̓���
�@���o�Ⴊ���̂���l�́A�����ɂ��Ⴊ���ƕ������̊O�E�̗l�q���݂͂ɂ����ł��B�������A���ۓI�T�O�𗝉����邱�Ƃɒ����Ă���ƌ����܂��B����́A���o�Ⴊ���̂���l�Ƃ͑ΏƓI�ŁA���o�Ⴊ���̂���l�́A��̓I���ۂɂ͗���͂������ł����A���ۓI�T�O�͋��ȌX���ɂ���悤�ł��B
�Ӑl�̗��j
�@�Ӑl�̗��j���T�ς���ƁA���i�@�t�͕��ƕ���̑S�Ă��o���A�����i�����t���邱�Ƃɂ���ĐE�Ƃ܂����B�]�ˎ���̐j���t���o���Ƒ̂̎d�g�݂Ɋւ���L���Ǝ�̋Z�ŐE�Ƃ܂����B�ՁE�O�����̎t���������͖Ӑl�B���Z�Ƃɂ��g���A�]�˖��{���F�̍������ɂ���Čo�ϗ͂�~���܂����B�r���ł͂Ȃ��A�Љ�̒��ň��̈ʒu���߂Ă��܂����B����ɑ��A���[���b�p�ł͖Ӑl�͕n���ɒǂ�����܂������A�A���E��͕��L�������B���{�ł͖Ӑl�͂�����x�L�������A�E��͌����܂��B
���R�a�ꂪ�I�ڑł̂ł͂Ȃ��I�ǂ����āA���̌�̐j���t�̊���������炵�܂����B���E���̖ӊw�Z�͂P�V�O�O�N��̃p���ł����A���ɐ��R�a��͂P�U�O�O�N����I���̊w�Z��n�݂��܂����B
�_���ɓ��镶���̗��j
�@�����̔����͋I���O�U�O�O�O�N���炢�B�b�����������`�������q�G���O���t�������f��
�ɍ��ނ��Ƃ͋��ʁB�p�s���X���玆�̔����͑傫�Ȃ��Ƃł����A�Ӑl�ɂƂ��Ă͕��ʂ̕����͉��̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�]�ˊ��̊��������́A���L���n���R��p���ď�
���܂����B�����ւ̊��]�̏ؖ��ł��B���[���b�p�ł́A�A���t�@�x�b�g�̓ʎ����l���o��
��܂������A�搔�������̂ŃA���t�@�x�b�g�̉搔���ȗ��������[���^�C�v���C�M���X�ŊJ������܂����B���ł��ꕔ�Ɏg�p����Ă��܂��B�̂��A�t�����X�ŃV�������E�o���r�G���P�Q�_�ɂ��_�����R���p�̈Í��Ƃ��ĊJ���������̂�Ӑl�p�ɓ]�p�B��������C�E�u���C�����N���P�T�̎��A�����̂U�_�ɉ��ǁB�֎~����܂������A�֗��Ȃ̂ʼnB��Ďg�p����܂����B�����Ĕނ̎���A�S���E�֍L����܂����B�y�����������������̂��ŏ��̓��@�ł����B�_�����ł��ĂQ�O�O�N�ł����A�W�O�O�O�N�̒��������̗��j�ł́u�V�l�v�ł��B
�@�P�W�V�W�N�A���s�ӈ��@���É͑��l�Y���n�݂��܂����B���������P�T�O�N�ɂȂ�܂��B�P�W�W�Q�N�̓����̋��甎���ق̗v���Ɂu�_���v�Ƃ����\�L������܂����A�����̐ΐ�q�������{�ŏ��߂ē_����n�݂��܂����B�É͑��l�Y�͓_���Ɉ˂炸�u�Ӑ��w�������V�@�v�Ƃ����Ĕw���Ə����m�[�g�ւ��ɂ�����@��p���܂������A����͏����镶���A�h��镶���Ƃ�����_������܂����B���̒i�K�ł͖ɍ��ޕ����B����ɘX�Օ����ŕ������������K�B�����ēS�M�ŗ͂����ď����i���E�t�ɂȂ邪���Ղ�ǂݎ��j�B���E�Ώ̕������l���o���B���̈���A�ΐ�q���������ӈ��w�Z�̋����E���k�Ƌ��ɉ�c���S��J���ē_�����m�����܂����B�S��ڂ̉�c�̓��ł���P�W�X�O�N�P�P���P�������{�̓_���n�݂̓��ƂȂ��Ă��܂��B����ȗ��A���k�̕��K�A�莆�A�앶�A�Ǐ��A���k��̓��[�A�L�^�E�ۑ��A��������\�ƂȂ�܂����B�n����L���\�ɂȂ����͉̂���I�Ȃ��ƁB�_�����[�͓��{�����E�ōŏ��ł��B�U�_�S�Ă�ł��o���������́u�߁v�ł���͈̂Ӑ}�I�Ɂu�ځv�ɂ����悤�ł��B
��������
�@�Ō�ɂ��`�����������Ƃ́A�ӓ����̓��X���ۖ���A�_���u���b�N�̏�ɕ���u���A�����b�����铙�̉ۑ肪���邱�Ƃ�m���Ă����Ă������������Ƃ������Ƃł��B
���^����
�i��j���̕s���R�ȕ��ւ̃T�|�[�g�V�X�e���̂h�s���⑽���ꉻ���i��ł��邪�A�ڂ̕s���R�ȕ��ւ̃T�|�[�g�V�X�e���̂h�s�����̌���͂ǂ����H
�i���j�����҂��{�����e�B�A�̕����X�}�z��ʂ��ĉ��u����T�|�[�g����V�X�e�������J������Ă���B
�i��j�Ǐ��o���A�t���[�@�̂��Ƃ`�h�ɂ��d�q���Гǂݏグ�\�t�g�̊J���ȂǁA�_�����ꂪ�i�ތX���ɂ��邪�c
�i���j�h�s���̗���͎~�߂�ꂸ�܂�������厖�Ȃ��Ƃ����A�_���̓X�g�b�v������߂����莩���̃y�[�X�œǂނ��Ƃ��ł���B�܂������̕����Ƃ��Ďv�l�ƌ��т�������
�\�����`�����̂Ƃ��āA�����_���͂�͂�K�v�B �i��j���i�@�t�̒���?�ۂ��_�i�����ꂽ��A�]�˖��{�����Z��喼���݂Ɉ�������A�ߑ�Ȃ�Ƃ��������E�ߐ��ɂ����ĖӐl�ɑ���ی쐧�x���������̂͂Ȃ����H
�i���j���̕s���R�Ȑl�ƈ���āA�ꌩ���ċC�Â��₷���B�l�N�e�����Ӑl�ł��������Ƃ�A�]�ˎ���A�e�˂��ړ����ď����闧��ɂ��������ƂȂǂ��L���ɓ��������\�������邩���m��Ȃ��B
�i��j�G���V�F���R���ӈ��w�Z�̋����{���Ɋւ���Ă������H �i���j�⋴���v�i���{���C�g�n�E�X�̑n�n�ҁj�Ⓓ���Ď��Y�i���s���C�g�n�E�X�j�Ɗ��̖ӊw�Z�ŃG�X�y�����g������L����^���Ɍg����Ă������A�����{���ɒ��ڊւ���Ă������͂͂�����Ƃ͕�����Ȃ��B����̉ۑ�ł���B
�����ʂ̓s����A�ꕔ�������グ���Ȃ��������Ƃ����l�т��܂��B
5������ �@���w��u�S�㒹�Õ��Q������v�ē� �������j����i�^�c�ψ��j
��R��
�@�O�����u�w�O�ɏW���A�w�r���R�K�ɂ��� �݂��ɂ�L�ꂩ�琢�E��Y��S�㒹�Õ��Q
�̒��S���Ȃ���R(����)�Õ�(�`�m���V �c�ˌÕ�)����Ղ����i�ʐ^�P�j�B�Ƃ͂���
�M�U�̃s���~�b�h��`�̎n�c��˂ƕ���� ���E�R�啭��ɐ������鋐��Õ��̑S�e
�͌����^�̃t�H�������܂ߌ��n���Ȃ��B�� �s�ł͗אڂ������������C�����グ��
100m ��猩���낷�v��𗧂ĂĂ������c�ƒ��O�ɋC���Ɍ��������K�X���R���Ƃ����g���u���������B���̌�A�ϑ����Ă���
�C�M���X�̉�Ђ̔p�ƥ���ޔ���ȂǂŌv�悪�ڍ����Ă������A�t�����X�̉�Ђɍ�
�ϑ����������ɊԂɍ��킷�ׂ�10 �����{�ɂ͉c�Ƃ��J�n����悤�ł���B
�@��R�Õ��̕��u����486m �Ƃ���Ă������A�ŋ߁A�{�����͎����̐��ʉ��̕������܂�
525m �Ƃ������Ƃ������B�A�����̌Õ��Ɋւ��Ă͈ˑR�Ɛ��ʏ�̒����ŕ\�����Ă����
�Ń_�u���X�^���_�[�h�ł���B�����͌���u�O�d�v��������(��^�Õ��̎��͂ɒz���ꂽ
�����傤 �����Õ�)�ł��������R�Õ�����R�Õ�������(��2 ��)���璣��o���O��(��3
��)������ ������Ęp�Ȃ��邱�ƂɈ�a�������邱�Ƃ���z�������́u��d�v�������Ƃ��������咣
����Ă����B���A�ŋ߂̔��@�����̐��ʂ� ��͒z����������O�d�������Ƃ���������
�L�͂ł���B�����]�ˊ��ɂ͎O�d�ڂ͖��� ���Ă��Ė������ɒn���̑����O�d�ڂ̌@��
��\���o���B���̍ۂɖ����ł̓y�n�� �@��̘J����d���Ă�����������������
�Δ_�Ɨp���Ƃ��ė��p����Ƃ��������t�� �ł������B�ޗǂł̑O��œy�n���L��
�ɂȂ�ł��낤�Ƃ����ژ_��(���ۂ����� ����)���������̂ł͂Ȃ����A����Ȗ��O
��痂������_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���G�s�\�[ �h�ł���B�z�������͏��֓�����5
���I���Ɛ���B����͐m���V�c(�I�I�T�U�L�m�~�R �g�A�m���͓ޗǎ���̖����B�V�c�̏̍���7
���I�ɐ������剤�ƌĂԂׂ�)�̑��q�Ō�� �v���������V�c�̗˕�Ƌ{���������肵�Ă���ΒÃ��u�Õ������֓�����5
�� �I�����Ɛ��肳��Ă��邱�ƂƖ��� ����B1872 �N�ɑ䕗�ɂ��y����(��
���̍䌧�m���ŏ��Ăɂ�铐�@���� ����)�ɂ��O����2 �i�ڎΖʂ̒G ���Ξ���Ί��ƕ����i���I�o���A
�䌧�̖�l�ɂ��G�}�ł̕��� �o����Ă���B
���̑��̌Õ�
�@�ەێR�Õ�����R�Õ��� ���˂ł���B���⍑�w��j�ե���E ��Y�ł���Ȃ��甿���L�`�Õ�(�O ����~���̑O�������Z���Õ�)�̑O�����͂��Ď����c�t�����ݒu����핽�����B�V �c�˥�˕�Q�l�n�͋{�����NJ��Ŕj��Ƃ�邪�A����ȊO�͊��S�ɔj�ꂽ���̂� �����S�㒹�Õ��Q�ɂ͖�100 �������������44 ��݂̂ł���B�A�W�A�����m�푈��A �n�傪�Ǔy�p�̓y���Ƒ�n�J���̂��߂ɔ��p�������Ƃ��傽��v���ł���B��̒J(�� ��)�͋{�������甆�˕����Ɏw�肳��Ă��邪�Õ����ǂ����^�킵���B���ݒu�ɂ�蕝 ���L�����Ă����R���ɕ����ԓ���̌`�������@�ŌÕ��̊m�͂Ȃ��B���H���̍ہA �O�炪�藣���ꂽ�\���������̂ł͂Ȃ����B
�@ ��̒J(�Õ�)�߂��ɂ͐m���V�c�̍c�@�֔V�Q�̖��t�̔肪�ݒu����Ă���B�̎��͕̂Q
�̓V�c�ւ̈�r�Ȉ���\���������}���e�B�b�N�ȓ��e�����A�ܘ_�A��R�Õ����m���V�c��
�ł���Ƃ����O��ł����ɗ��n����B�����v�R�Õ��̕��u�͋{�����w�蔆�˂�����n�A��
���͍�s�Ǘ��B�O����~���������������H���̍ہA�O������7m �t���������������`�ɑ�
�삵���B�z�������̎p�ɂ��߂Â���̂��]�܂����ۑ������̂�������Ǝv���B
�ΒˌÕ�(�~��)��1955 �N�̓y���̎�ɂ� ��j��̍ہA���Í��Z�n�̐X�_��ږ�
(����)�ƕ�����������╨���̏W�B3 �` 3.5 ���̎�������ƌ`���ւ��o�y�B���ČÕ���
�������ʒu�ɌÕ����C���[�W�����z�R������ ����Ă���B���`���������{���̌Õ��Ƃ͈�
�Ȃ��Ă��邪�����̐Ղ͗�ߍ��ݕ\�� ���Ă���B�O���V���E�V�Õ�(�~��)�̕��u��
�������܂\�y�ƁA���̉��̓y����Ō@�� �o���A�����V�n�t���܂ɐςݏd�˂�H�@�ő��������B���y�̋��x�����߂�Ñ�l�̍��x�ȋZ�p�ƒm�b���M����B�ΒÃ��u�Õ��̔���
�̎���(�R)�Õ��́A�펞���R�����˖C�w�n�ɗ� �p���ׂ������ɒ��a5m ���̒G�����@��B1947
�N�A�G�����瑽���̓S�Ђ��������ꂽ�ɂ��S�� ��1952 �N�A�y���̎�̂��ߊ��S�ɔj�ꂽ�B
���݂͌Õ��̂������ꏊ�Ɂu�Õ��^�W�]��v�� �ݒu���Ă���B�K�ˌÕ��͑O����~���Ō��݂�
�{����x���w�Z�̕~�n���ɂ���A�w�Z���݂� �ۂ��O�����͔j��A��~���͎c��������핽��
�ꌻ��̍�����2.5 ���B�Õ��}�b�v��K�C�h�u �b�N�ɍڂ�Ȃ��̂͊w�Z�̕~�n���ɂ���̂Ŏ��m���邱�ƂŎx�Ⴊ����Ƃ̔��z���炾��
�����B
�s���^���Ŏ�����C�^�X�P�Õ�
�@�C�^�X�P�Õ��͉���I�ȑO����~���ł���B1955 �N�ɒn�傪�J���Ǝ҂ɔ� �p�B�Ǝ҂͓y���̎�̂��߃R���N���[�g���̋������݂�����ۑ��^�����u���B�Ⴋ�l�Êw
�ҥ�w����n���̏����w�Z�̋�����k��Z���炪�Õ��������g�D���A����������r���z
�z��w�K�凌����������W�J�B��t�����ڕW�z �ɒB���Ȃ����A�O�}�{�����K���ۑ���i����|
���S�����ɕ����s���Ǝ҂���̔����グ �����f�B�����݂��ĕۑ����ꌻ�݂Ɏ���B
�R���N���[�g���̋��͔j��̊�@�ɂ��������� ���L���ɍ��ނ��ߊ����ĕ������Ȃ�����c����
�����B
�@ ��_�R�Õ��͕��u��203m �̑O����~���B�� ����2 �d�ŕ���30 �` 50m�B���_�V�c�̏����n
�Ƃ��ė˕�Q�l�n�Ɏw��B���n�̐����ɂ��Ă̌Õ����ʐ}������������ꕔ�傫���L�����Ă���l�q���m�F�ł����B���O�ɂƂ��Ď�
���͗��ߒr�ł���A���Ɍq����_�Ɨp���̊m�ۂ��������`�ł��邱�Ƃ��ǂݎ�ꂽ�B
4������ �@�������P����i�͓������܂��Đ���c�������j�u�d�v����������w�ԁv
�@�����ȕ⏕���ƂőS���̏d�v�������̒����ɍs���Ă����B�����S�������̂�13�������A�����͂��̒�����5���ɂ��Ď��̗��ꂩ��b���������B
�����̐E�l����̋Z�̑��ʂ��A��H����̎v������Ƃ������A���ł͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ȋZ���A���ɑ�?�i���������j�Z�p�Ƃ����āA�|����Ï��A���Ȃǂ��k���Ȏd���ɂ�ďC������Z�p������B����͍��قƂ�njp���l�����Ȃ��Ȃ��ςȂ��ƂɂȂ��Ă���B�������������Ă�������B����͑f���炵���A�����̘A���ł������B�������͂Ȃ��c���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̎���̐�����z�����Ȃ���A�l���Ă������������Ǝv���B�Ȃ��u�`���ؑ��v�̒�`�͐F�X���邪�A�킪���ł́A�Â����猚�Ă�ꂽ���g�\���ɂ��ؑ����z�Ƃ��đ����Ă���
�B
�P�D�d�v������ ����ƏZ��i���쌧���K�s�j
�H�����̏���ƏZ��ɍs�����̂�2010�N12��24���B���̎��͂ƂĂ������đ�ς��������]�ˎ���͂����Ɗ��������̂ł͂Ȃ����B���K�͒��哹�̉��̓��̕���_�ŎO�͂̓�̉��ƈ��܌o�R�̖k�̉��������Ō������ɔɉh�����Ƃ����B����ƌ����͓V��2�N�i1831�j���� 1�K���ĂŃX�^�[�g�������A���̎����͗������邱�Ƃ����s�肾���āA�����̋q�����邱�Ƃ����z���A5�N��ɕ�������ɏ悹��2�K�ɑ��z�������B���������H������ł̓V�[�g�ŕ����A�������������W���b�L�A�b�v���ďグ�Ă����B
�@ ���̍H����2009�N����2013�N�ɂ����čs��ꂽ�B�O�͂��Ȃ�ÂтĂ������A������̏���Ƃ̌`�͑S���ς��Ă��Ȃ��B�]�ˊ��̒��哹�́A�h�ꂪ69�����邪�A���K�͍]�˂���
30�ԖځB���H����́u������v�ɓ���B���Ȃ݂Ɂu�ȑ��v��������Ă����̂́u�ȓ���v�B�����͍ȐA�������œ����̕��͋C�͂��̂܂c���Ă���B
�@ �g�p����Ă�����킪�A�N���ށA�}�c�ށA�P���L�ށA�g�K�ނŁA�q�m�L�̍ޗ���1�{���Ȃ��A�q�m�L���Ȃ��Ȃ���ɓ���ɂ����ꏊ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�܂��A���̏����̓C�`���E�̖Ŏ}�����̂܂ܑS�����Ă���B�����̑�H���s�[���Ƃ��Ă��̖́A���������g���������炢����Ȃ����Ƃ������Ƃł�����Ǝv���B�u���̊ԁv�����ł͂Ȃ��~���Ƃ��A�Ђƕ������G�������Ă����Ă���A�����������Ƃ�����A��?�Z�p���ꐶ�����c���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍl�����̐���ɓ`�����邱�Ƃ��ł�����Ȃ����ȂƂ����ӂ��Ɏv���Ă���B
�Q�D�d�v������ �n�ӉƏZ��i�V������D�S�쑺�j
�z����\���鍋�_�ŁA����7�N(1667)�ɍŏ����Ă�ꂽ�Ƃ������Ƃł���B�V�����̖k���A�R�`���ɔ��ɋ߂��Ƃ���ɂ���B����Ȓn��ŁA
�ƁA���D�≮�A���Z�Ƃ��c�݁A�_�ƌo�c�ł�50�����������Ă����B���~�̓y�n��3��A���������ׂ�550����A��������͂ނ悤�ɓy��������
�B1788�N�Ɉ�x�Ď���1817�N�ɍČ����ꂽ�B
�@ 2009�N���畽���̑�C���� 2014�N�Ɋ������� 8���~�̍H��ł������B�����͊��ł͂Ȃ��g�`�����Ŕ̏�ɐ��悹�Ă���B�{���o���q�����NHK�e���r�h���}�u���v�̃��P�Ŏg��ꂽ�B�~�n�����~���L��ʼn��~�͓��i��������j����ŁA�����ʐς�1,207�u���蕽�ʐ}�������ĕ����Ȃ��Ɩ��q�ɂȂ��Ă��܂��B1�K��2�K�ƍ��킹�ĕ����̐���40�A����ŕ֏���7�����A������4�����A�����g�p�l��75�������B����������ƐV���Ȃ̂Ɍ��z���ɂ��B�܂������̉��ɎV�����̂������ׂ��������Ă��āA���̏�ɔ��悹�������ɂȂ��Ă���B�V���̐�͎��C���܂�ŏd���B������낷���ɔ�̐̏�܂łƂ邾���ʼn��̐�͒u���Ă���B���̐�1��5��ʂ��g�p����Ă���B���ꂾ�������傫���̐��W�߂邾���ł���ς��B���̂悤�ȉ����͑��̒n���ɂ͂��܂�Ȃ��B�܂����ꂾ���傫�ȉ������Ǘ����₷���悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��邱�Ƃɋ������B�Ƃ��x����y��̑O�̍\���ނ�����قǑ傫������K�v������̂��Ƃ������Ƃ������ł����B��̐�̏d�������邩�牺���������肵�Ȃ��ƃ_���ŏ����ɂ��̂������傫�ȗ����g���Ă���B����Œ��̌p���肪����̑���Ɠ������̂��g���Ă����Ƃ������Ƃ͂ƂĂ��ʔ����B
�R�D�d�v������ �N��ƏZ��i�������m���S���o�_���j
�@ ������2011�N�ɍs�����B���ی��N(1644)�A�o�_���ɐ^���y�̒��ɍ��S�������������B�����şN��Ƃ͐m���S�Ɉڂ�Z��J���āu������v�������肵�āA�V�������S���c�ނ悤�ɂȂ����B��i5�N(1755)�ɓS�t��������]�˂��q�����ꂽ�B
�@ �N��ƏZ��͌��� 9���̌������d�v�������ɓo�^����Ă���B�ꉮ�͊������ł͂Ȃ�?�i������j�����Ŋ���肸���Ƃ����͂����邪�d�v�������Ƃ��Ă��������Ă���B
�@�o�������������͏��]�̏����˂̓a�l��������ɂȂ������Ɏg�����B���̎��͌䐬����J���ēa�l�͌䐬�ʂ����`�ɏ�����܂ܓ����Ă���B�a�l�����܂������~�̉�������͂�?�����ł��̉��ɐ�����������B�������̘L���͓a�l�ƉƗ���2�i�ɕ�����Ă���B�O��ɒr������A���̏�ɑꂪ����ď����s�������u��Q�v�Ɩ��t�������������琅���������l�H�̑�ƂȂ��Ă���B�������ւ̗U���͒������̂��炦�Ő����͖����ƈ���ĊJ���I�ȕ��͋C�Œ���������蒭�߂Ȃ��炽���ȂށB
�@ �N��ƏZ��̗v�̒����̑���������́A���ɑ傫�ȍޗ����g���Ă���B�傫�ȍޗ����g��Ȃ��ƁA���ꂾ���L���Ƃ����d�����Ƃ��ł��Ȃ��B���̎��g�̑����̉��H�́A�͂�����ɑg��ŏ�v�ȃt���[��������ĉƑS�̂��ł߂Ă���B�L���䏊�̐^�ɂ���d��͎ϐ������鏊�ƐH�ׂ鏊��ǂłȂ��đ傫�ȗ���n�����悤�ȏ�Ԃŋ�C���X���[�X�ɏo����ł���悤�ɍ���Ă���B�u������v���S�̍�Ǝ{�݂̘F�͂ƂĂ������ɂȂ�A�ؑ��ł��邽�߉Ύ������X�N�����B�{�݂�����̂ɂ������p10�̂���������4�ŁA�����Ȃ��y�Ԃ�6�������Ă���B���ɂ��̂������d�|��������A�S�y�����ɑ厖�ȗv�f�ł����āA���x�̍����S�����邽�߂ɗl�X�ȋ�J���Ă���Ă����Ƃ������Ƃ��킩��B
�S�D�d�v������ ���X�؉ƏZ��i�������B��S�B�j
�@������2011�N�ɍs�����B�B�̓���̓��C�݂̊��n��ō��X�؉Ƃ͏������߂Ă�
���B�����̌����̒��ł��ő�K�͂ŁA���ނɂ��̂������傫�ȍޗ����g���Ă���B
�@�B��̓����͌��ւ� �R���邱�Ƃł���B���̌��ւ̈�ԏd�v�ȏ�����́A�_�����o���肷��B�B�͕������@���ꌬ���Ȃ��B�p���ʎ߂̎��̒m�������������ĕ�����ׂ��Ă������B2�ڂɑ��̎傾�����l�������p���̂��鎞�̎��̊Ԃ̂悤�Ȍ��ւ�����R�ڂɈ�ʂ̏Z�����o���肷��Ƃ���̌��ւ�����A����͌��i�Ɏ���Ă����B
�@�����̓X�M���g���Ă��邪�A����͓����Ƀq�m�L����{���Ȃ�����ŁA�ϗp�N���͗�邪�g�킴��Ȃ��B�傫�ȑ单���͐S�ނ����ꂢ�ɃV���A���ɂ���Ă����B�x�c�тœ�����Q������A���̎��͑单�������ւ����������d���̂ŏ����ÂW���b�L�A�b�v�����ςȍH���������B�����ł́A��̍H���������ɒ��̐^���{�[�����O�̋@�B�ł���ʂ��āA�����悤�ȕ��ނ���������ł������B
�@�����ł̏d�������ޗ��̓}�c�ŁA�������������ς�����A�������ƌĂ�Ă���B�}�c�͖{�y�̖Ƃ͈Ⴂ�A�����}�t���S�R�Ȃ����ނƂ��Ă͔��ɗD�G�Ő߂����Ȃ����ꂢ�Ȃ��̂�����B���Q�ɂ������N���}�c���吳����܂ł͂������������A����50�{���炢�����Ȃ����̂͂����Ă��炦�Ȃ��Ƃ������Ƃ炵���B
�T�D�����ƏZ��i�������������s�������s�j
�@�����哇�ł͖{�y�Ƃ܂��Ⴄ�����̉Ƒ�������Ă���B�Ί_�ŕ���������オ�点�Ȃ��悤�ɂ��ĉ�����Ⴍ�����z���������ĕ����ǂ��炩�痈�Ă������悤�ɂ��Ă���B���݂͉��������قɓW������Ă��邪�A�q�L��������ƌ����傫�����̂���炸�|��Ă��ȒP�Ɏ����グ�邱�Ƃ��ł���B�䕗����̉����ł͌������y�����ĕ��œ����Ă��l�͂ʼn^�Ԃ��Ƃ��ł���B�\�̌����ƃh�[�O���ɂQ������ĊԂ̓n��L���ɂ͕ǂ��������Ȃ��B����������ƃJ�S�̂悤�ȑ���ʼn��������Ɍy���ޗ����ׂ��B�ׂ��|��n������Ɋ����ڂ��ē�ł������芇���Ă���B�\�̕ꉮ���y�ǂ͎g���Ă��Ȃ��B�y�ǂ��g���Ƃ̓V���A�����オ���Ă���̂Œ������܂Ȃ��悤�Ɏg��Ȃ��B���ƒ��̊Ԃɔ�ʂ��Ă��邾���Ŕł���Ώ���ł��ȒP�Ɏ��ւ��Ă������Ƃ��ł���B����ς蒷�N�̒m�b�ōޗ������X���Ȃ��䕗�����Ă�����邱�Ƃ��Ȃ��B���̕�炵���́A�������������Ǝv���B
�i���^�����ɂ��Ă͏ȗ������Ă��������܂��j
1������ �@���`�O����i�����j����ҋ��c����ǒ��j�u�n��ɍ��������j�w�K�|���^����w�ԓ��{�̗��j�v
�u�n��v�u�����v���ނɂ��ƂÂ�����
�@���݂̊w�Z����͑�ςł���B�h�b�s���p�A�w�K�w���v�̂̎��{���v�A�ώG�Ȋϓ_�ʕ]���ȂǑ��Z���ɂ߂�B���̒��ŁA��䂳��́u�Ȃ�ł��Ȃ��H�v�Ƃ������k�̋^���厖�ɂ�����ƁA���k�ɖ₢��������Ƃ��ɂ��Ă����B�u�����ߋ��̘b�v��g�߂ɂ��邽�߁A�u�n��Ɋւ����v�A�u�����v���ނ���A�v���[�`���邱�ƂɂƂ肭�B�u�n����w�K����Ƃ������Ƃ́A��E���w�N�����̎d�������łȂ��č��w�N�A����ɒ��w���Z���ꂼ��̒i�K�ŁA���ꂼ��ɉ������w�K��W�J���ׂ����̂��ƍl����B������A�Y�Ɗw�K�����j�w�K���₦���n�悩��o�����A�q�ǂ��������n��ׂ邱�Ƃ����Ƃ�
���āA���ꂼ��̊w�K�̓W�J���l����v�i�암�g�k���������ψ����j���Ƃ���{�ɂ��Ă���B��z���Z�Β��ɂ́A�^�Ӗ쏻�q�́u�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���v�Δ�▭�����́u�Ƃ��̂��ނ炢�@�͂炫��̂͂��v�Δ�A�䌧���Ղ̖{�莛�ʉ@�Ȃǂ����w���Ė��������̗��j���A���S�㒹���Z�ł́A�y�������w���čs��̕z�������Ɠޗǎ���̐����ƕ������A�l����������ƂɂƂ肭�B
���^����l������{�j�̎���
�@�����s�����j�����قł�������ǂN���k�ƐA���u�ȌJ��v�̌������{�A�ƒ�Ȃ̐搶�̋��͂Łu���Â���v�ɂ����킵���B�]�ˎ���́u�_�Ƃ̔��B�A���i�앨�͔̍|�v���Ƃł́A���^��������Ĕ��肵�Ă����ɐH��ꂽ��A�Ă̐��܂��A�䕗�Ń��^���|�ꂽ�肷��̌����炨�S������̋�J�������킩��B�����̎Y�Ɗv���̎��Ƃł́A�u�J��ȁv�̑@�ۂ��玅������̌������A�u�r���������v�Ƃ������Ƃ�������A�u���Ԃ̎��Ƃ���@�B���g���đ�ʐ��Y�v����̂��Y�Ɗv�����Ƌ����Ă���B
�Ǎ�̗��j
�@���ȏ��ł́u�G�g�̒��N�o���ŁA�e�喼�����^�̎�������A��A���������v�Ə����Ă��邪�A�i���c��i�ꋴ�喼�_�����j�́w�V�E�ؖȈȑO�̂��ƒ�������ؖȂցx�i�����V���j�ł́A�㊿�ɓ�C����ؖȂ��`���A14���I������15���I���ɖ��̍^����̍��A�ؖȍ͔|�Ɩȕz���Y�����W�����B����Ɍ�����ؖȂ��`�����A�����Ŗ{�i�I�ɍ͔|����A���i13�i1406�j�N�Ɂu���{�����v�i�������{���R�j�Ɂu�ؖȁv���i�������F���v�ɑ���ԗ�j����A1408�N�̑���Ǝg�҂ɂ́u�ȕz�v���A1451�N�̓��ÉƎg�҂ɂ́u�ȕz��O��l�C�v������Ă���B���̂���̖ؖȂ͔����i�Ŏ��v�����������i�������B���{�ł́A���߂̐łƂ��Đ����i�����Ă��F�ېőΏۂƂȂ鐬�N�j�q�j�̗f�i�悤�j�͖��z�A���i���傤�j�́u�ȁv�͎\�̖��������u�^�ȁv�ł������B���Y�ؖȂɂ��Ă͕���11�i1479�j�N�j���ɁA�ߌ��[�Ƃ����m���Ɂu�ؖȈ�[�v���y
�Y�ɑ���ꂽ�L�^�������i�i���j�B���ł͓V��9�i1540�j�N�w�����a���L�x�ł͐ےÐ����S���ԂŐ��Y���ꂽ�u���Ȗؖȁv�����s�Ŏ������Ă���B�]�ˎ���̖Ǎ쒆�S�n�A�O�͖ؖȁA�ɐ��ؖȁA�ےÖؖȂ͐퍑����ɑf�n������֓��A���C�A�l���A��B�ȂǓ��k�ȊO�ōL���Ǎ삪�s���Ă����B�ؖȂ̎g�p���@�ɂ��Ă͕��߁A���A��A�w����n��A�Γ�ȂnjR���i�����������B�{�����w�_�ƑS���x�i���\10�N�j�ɂ͖ؖȐ��Y�n�ɂ��āu�͓��E�a��E�ےÁE�d���E����v�Ȃǂ��L�^����Ă���B�ؖȐ��Y�͐퍑
�`�]�ˊ��ɔ����I�ɔ��W�����B�ؖȂ͒����i���j�Ɋr�וۉ����┧�G�肪�悭�A�͔|�E�a�сE�D�z�̐��Y�H���ŕ��Ƃ��������₷�����i���Y�E���ʖʂŔ��W��������ɂ�����Ă�������ł������B
���Ƃ̎��H��
�@�V���̑䏊 ��₪�u�V���̑䏊�v�Ƃ����Ӗ����G�}��ʐ^�ő����~�Ⓦ���q�H�Ȃǂ̊C���ʂőS�����Ȃ�����̖ؖȂ⓺���]�˂ɑ���ꂽ���ƂȂǂŊm�F������B
�A��a��̕t���ւ�
�@��ł͏��w�Z�����a��̕t���ւ����K���B�G�}�œ����̍^���̑����A��Q���m�F���A���@�r���q�����S���̕t���ւ��Q��^�����Љ�B���i�h�Ɣ��Δh�̈ӌ�������B�t���ւ���A�V����a��Ŗȍ삪������ƂȂ����B���^�Ƃ������i�앨�͌����ɂȂ�A�ݕ��o�ς��_���ɐZ�����Ă��������Ƃ𗝉�������B�엿�Ɉ�ʂɂ���̂ŋ��@�̊g��ɂ��Ȃ������B�t���ւ��ŁA���r�V�c��O��V�c�ȂǐV���ȐV�c�J�����s��ꂽ���Ƃɂӂ��B
�B�Y�Ƃ̔��B�ƎЉ�̕ω�
�@�e�n�ɏ��i�앨�̓��Y�i������Y�Ɣ��B�Ɖݕ��o�ϔ��W�������ނ��Ƃ������u�����̗��v�i�������j���������فj���Q�l�Ɋm�F�B�u�͓��ؖȁv�̖��ŖؖȐ��i�����y�����B�Ȃ�g�ԂȂǎ������ނ�������B�ݕ��o�ϐZ���Ŗ{�S���̊K�w�������l��������B�F�c��Ñ��i���E���Îs�j�̐D���i�V��14�N�j�̎����ʼnƑ��ȊO�̐l���ٗp�����K�͂ȐD���̑��݁A�����̕S���ł��@�D�肾���Ő������Ă�����l�����邱�Ƃ�m��B���������}��ł́u�}�j���t�@�N�`ՃA�i�H�ꐧ��H�Ɓj�v�̑��݂��m�F�B
�C�S���Ꝅ�Ƃ������킵
�@�o�ϔ��W�̈���ňꝄ��ł����킵���N���錴����T��B���Ύs�x�̞��莛�ɂ���u�y�䒉���q�̌�����v�����āA1783�N�̐猴�������l����B���N�͑䕗�A���J�ŖȂ��s�삾�����B�ꋴ�̂̕S���͋�[�̔N�v���ƂƉ��[�肢���o�����B���ۂ��ꂽ�̂ŕS�������͈Ꝅ���N�������|���̐�㍲������P�����B���s���̑{���ƌ����̌�A���|���̔p�~�A�N�v�̌����ו������F�߂�ꂽ�B�������{�͊����Ԃ��d���A�_���̎��R�ȖȔ̔����֎~����A�≮���Ԃ����������������Ă����B�S���́u���i�v�Ƃ����������������������Ď��������̗v�����������Ă����B
�D���{�̎Y�Ɗv��
�@���a�т��Ƃ肠����B���Ђ͌��݂̑��s�����Z���h�[���̋ߏ��ɂ������B�a��h�� �Ȃǂ��ݗ��Ɋւ�����B���{���͓���28���~�ŁA�ї��A�r�c�A�I�{��Ȃǂ̋��喼���q�������o�������B�C�M���X����ŐV�̃~���[���a�ы@��A���A�ő�K�͂̍H��ƂȂ����B�����͒����Ȃ�A���A�J���҂͋ߗה_������W�߂��B���̌�A�O�d�A�V���A����A�����Ȃǂő�K�͍H�ꂪ�ł��Ă������B���a�ѐ����̌����Ƃ��āA�~���[���a�ы@�A�����Ȃ�C���h�q�H�A�q�œ������C���h�ȁi�����Ȍ����j�A���㐧�A�����ԘJ���A�Ⴂ���H����i������j�A�����O�a�ы@�ɃC�M���X����������ւ������ƁA�Ȃǂ��l����B�@
�E�Љ���̔���
������Ⓑ���ԘJ���̖��ɑ��ĘJ���҂��������������B�n�吧�̂��ƂŔ_�Ƃ̎q�����H��̗ȏ����œ�����������Ȃ��������Ƃ𗝉�������B�V���a�т̃X�g���C�L�̏Љ�B�����푈��ɘJ�����c���ӂ������ƁA�����x�@�@���J���^���������������Ƃ𗝉�������B�����z�Ŏ����ł͏Z���^�����N�����Ă������Y����߂Ȃ��������R�Ƃ��āA
��������̌����ł��邱�ƂƐ����ƕ���ŗA�o�i�̒��S�ł��������Ƃ�������B
�F���i�C�Ƒ��̕ω�
�@��ꎟ���E����A���{�͋�O�̍D�i�C�ƂȂ�Y�ƍ\�����ω��A�Ɛ莑�{���m�������B�s�s���A��O�����̕��y�A���i�C�Ɓu�����v�̔������l����B���D�ƂƐ��S�Ƃ̐����A�A�o���E�����ƂȂ�݉ؖa���ł����a�Ⓦ�m�a�сi���a�тƎO�d�a�т������j����C�ɐi�o�A�����i�o����ɂȂ���B�H�Ɛ��Y�z���_�Ɛ��Y����܂��_�ƍ�����H�ƍ��ɂȂ�d���w�H�Ɣ��W�Œj�q�J���҂����������ƁB1925�N�ɂ͑��s�̐l���͓������āu����v�ɕω������B�䓰�����݂���A��k�Ə铌���ω��A�H�ꂪ�ӂ��Ă������B���ш�O�́u��}���@�v��������n�J���A��ˉ̌��A�S�ݓX�ݗ��Ȃǂ̎����ōl��������B
�G���E���Q�Ɠ��{ �@���E���Q�̓��{�ւ̉e���𗝉�������B�����̌o�ώx�z�A�l�����t�̋����ցA���a���Q�Ől�X�̕�炵���������A���쑈�c�ƘJ�����c�̑����ɂ��ď��a���c�Ȃǂ��ɍl��������B�Ȏ����Y���A�Ɠ��H�Ƃ���H�ꐧ��H�ƁA�@�B����H�ƂɊg�債������E�����ԘJ���A�J���^���̍��܂�Ȃǂ��l���Ă䂭�B
�@���^
����������@�u���Ïo�g�ŁA���Ƃ��D���Ńg���^�D�@2�䂪�������B�����ł͌Â��D�@�ŁA�������Ȃǖڂׂ̍������Ԃ�����n��Y�Ƃ��ł��Ă���B�͓��ؖȂ�����̂ɂȂ������Ȃ��g�����̂��H�v�����u�@�ۂ��������A�~���[���a�ы@�ɂ���Ȃ������B�v�u��B�͕��Ƃ��i��ł����̂ň����ȉԂ������Ă��o�c���������B�v
���с@�u���K�〈�w���ƂŁA1���Ԃ̘g�ł͂ނ��������Ǝv�����A�Q�R�}�Ȃǂ̎��Ԋ��͂��Ă���̂��H�������u�P���Ԃł���Ă���B�v����������u���w�Z�ł͂P���ԂŖȌJ����w�����Ă���B�����̎����قœ����݂��o���Ă���B�v
���������u���c�̉��ŖȂ�����Ė��{���F�߂��̂��H�v�������u�w������d��@�x�ŔF�߂��A���̂Ԃ�͔N�v�̑ΏۂƂȂ����B�v�u���a�т́A�Ȃ���ォ��͂��܂����̂��H�v�������u�H��p�n�Ƃ��č��L�n����邱�Ƃ��ł������߁v�u�C���h�Ȃƒ����Ȃ� �������́H�v�������u�C���h�Ȃ̕����A�@�ۂ����������v�u�a�ыƂ͂Q��㐧�Ȃ̂ɐ����͂������̂͂Ȃ����H�v�������u�����͏��H�̎��ƕ����������A�a�т͋@�B���傫���ғ������邽�߂Ɍ�㐧�ɂ����v
�@�i�����ׂĂ̎����ӌ����Љ�ł��Ȃ��������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B
�Q�O�Q�S�N����
12������ �@���c�@�i����i�{�����E���ΘJ�ҋ��狦���u�ÉƁi�ӂ邢���j���O�̐l�Ɛ��U����w�ԁv
�ÉƎ��O���L
�@�{�����̖ؒ×͏����i100�j���u��O�̊v���I����I�o�ŕ��ۑ���v�i���c����j�̃j���[�X��2020�N����2024�N�܂ŘA�ڂ����u�ÉƎ��O���L���v�������t����P�s�{�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B���Ɍ��ł̑��n���̎Љ�E�J���^���Ɋ����̒e���ɂ��������g������čv�����A����ŌÏ��X�u���_���v�X��Ƃ��č����O�̏��ЁE���������W�A���y���������ɍݖ�̗��j�����ƂƂ��Ĉٍʂ�������������ÉƎ��O�̍s�����ڍׂɋL�^�������L167����蒠�̎��������Ƃɂ��Ă���B�ÉƂ̐l���ƍs���ɖ�����ꂽ�������O���i�w���蒬�j�x�ҏW���j��{��T�ꎁ�i�_�ˑ�w�����j���u�ÉƎ��O���L������v��20�N�ԑ������B�����͂��̌㍑��}���ٌ����������ɗa����ꂽ���A�����������ʂ������L��蒠�����Ȃǂ����J�����B�ؒ×͏����́A�����̎��������ƂɃj���[�X�ɘA�ڂ����L�����܂Ƃ߁A2024�N���A�w�Ï��X�u���_���v�ÉƎ��O���L���|���Ɍ����Y�K���^���̗��j�I�𖾁x�Ƃ��ĕ����t���o�ł����B
�Ï��X�u���_���v�X��ƂȂ�
�@�ÉƎ��O�́A1890�N���Ɍ������S�������i���E�����s�j�ɐ��܂ꂽ�B�_�ˈꒆ���A���o�C�g�̉ߘJ�ɂ��a�C�Œ��ތ�A������̏��L���o�Đ_�˂ŌÖ{���u���_���v���J�Ƃ����B�Ï��X�Ƃ̎n�܂�͑S���e�n�ւ̌Ï������t���ƍs���̗��ł������B���N�E�����E��p�ȂNJO�n�ɂ��s�����B�O�n�̗��́A�Ï������̔����t�������ł͂Ȃ��A���������Ƃ����Ă��������炢�̃t�B�[���h���[�N�ƂȂ����B��p�̐Ί��{�l���`���������}���w��p�Ί�}���x�Ƃ��ďo�ł������̂͑�w�̌����҂�������ڂ����тčw����]���������B�ÉƂ͕���@�g�����C�܂ł̕��L��������ǔj����Ǐ��Ƃł����������łȂ��n�ɑ������Č����������B�ނ̊����̌��_���A���̍s���̌��ɂ���B
�@ �Љ�^���|�����i��^�����疳�Y�K���^����
�@�ÉƂ��Љ�^���Ɋւ��悤�ɂȂ��������́A�����i��^���̈�Ƃ��ċN���������������N��A�吳��y���ւ̎Q���ł������B���̍��̌ÉƂ̎v�z�́A�������@�̐��i��̗���ł������B���̌�A1923�N�ɕ��ʑI�����x��v�����镺�Ɍ��N�}�ɓ��}�A����ɐ_�˃T�����[�}�����j�I���̈ψ����A����������_�ˎx�������ɏ]�������B
���̍��A�ÉƂ͂���܂ł̎v�z����]���A���Y�K���^���̗���ɗ����Ă���B�T�����[�}�����j�I���́A�T�x���x�m���A���ّސE�蓖����Ȃǂ�v���Ƃ��Čf�����B����������͖��Y���}��������������s���j�̂��f���Ă����B1926�N�A�J���_���}���_���J���}�̉��U��ɍČ������ꂽ�B�ÉƂ͌����Ɠ����ɓ��}�����B�ÉƂ����̂悤�ȑg�D�I�ȎЉ�^���ɓ����Ă��������R�Ƃ��āw�ÉƎj���ژ^�x�Ɂu�l�͖{�\�I�Ƃ����Ă��悢���푈�������ł������B�E�E�E�͋����푈���Ή^���́A�Љ�^��������^���̈�Ƃ��ēW�J���Ȃ���Ό��ʂ̏オ��Ȃ����Ƃ��Ⴂ�l�����ɂ���ċ�����ꂽ�B�v�Ə����Ă���B
�@���̂悤�Ȏ����A�ÉƂ͐X�˒C�j��R��@�ρA��R��v�Ȃǂ̊����Ƃ╶���l�A�m���l�Ƃ̌𗬂����Ă���B�^�Ӗ쏻�q�Ƃ͏��Ȃ����킵�A���q�͌ÉƂ��u�����̌Ö{���ł͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B1927�N9���̕��ʑI�����x���{��͂��߂Ă̕��Ɍ��c��c���I���ɘJ���_���}���痧��₵�����ɔs�����B���̌�A�R�E�P�T�����͂��܂����ꂽ���A1929�N�J�_�}�Č��̊������ɂS�E�P�U�����őߕ߂��ꂽ�B���㏐�̓Ɩ[�ɍS�����ꂽ�ۂ̓��L���c����Ă���B
�@�u�����撲�����鍠���Ǝv���Ă���̂ɁA�������Ƃ��Ƃ����̍������Ȃ��߂��������B�l�͂�������炸�_���X�Ɖ̗w�ƁA�lj�`���̈���𑗂����B�����͑f���炵���w�l�̈��i���j���ł����������B����E��ɂ����Ȃ��قnj|�p�I�ȋ������������B�������R��̂��Ƃ�z���A�Ƃ���䂭���u�̂��Ƃ��l����ƃZ���`�����^���ȋC�����ɂȂ��Ď��X�܂��܂���A���ɂ͚j������������Ƃ��������B�v
�@���̌�V�J���_���}�_�ˎx���������A1931�N�ɓ��{�J���g�����]�c����n���]�c��������A���c���ƂȂ�A1935�N�ɂ͗F����y�������ɎQ���A���k���ƂȂ�A�ÉƂ͈Ȍ�A�吳�E���a�ɂ����Čx�@�E�R���̒e���ɋ������g������A���ɂ͐��_�I�ɑ傫�ȔY�݂�����Ȃ���A���Ɍ��𒆐S�Ƃ��鑐�n���̎Љ�E�J���^���̒��S�l���Ƃ��Ċ����B
�w�d�����y�����x
�@�펞���̎����ɂ��Ă͍���̒��������̉ۑ�ł���B�ÉƂ͖{�y��P�̌������Ȃ邱�Ƃ�\�����c��Ȏ����������ɑa�J�����Ă����B�����̎����́w���_���Ƒ��E�}���ژ^�x�ɋL�^����Ă���B���A�ÉƂ�1946�N�ɓ��{���Y�}�ɓ��}���A�͐��S�������i���E�����s�j�ɋA�����ċ��y�����ɂƂ肭�ށB���̍��A�����ێ��@�ᔽ�ŌY�ɕ����Ă����ԏ��[����������ɋA���A�ÉƂƌÑ�j�����ɋ������Ď��g�ނ��ƂɂȂ����B�ÉƂ̌Ñ�j�����Œ��ڂ����Ɛт́A�������œ��{�ŌÂ̌Ö@�ؐΕ��i1300�N�O�j���������Ƃł���B�ÉƂɂ��āA�����̊w�ҁA�o�ŊW�҂��A�u�����̌Ö{���ł͂Ȃ��v�ƌ����Ă� ���B���̊w�҂��ނɏ��ЂɊւ��鎿������Ă����Ƃ����B
�@�ؒÂ���́A�ÉƎ��̋ƐтƂ��đ�1�ɉ������y������̑n���Ƌ@�֎��w�d�����y�����x�̊��s�A��2�ɐ�O���Y�^�������W���̎��Ƃ̐i�s�A��3�ɁA�����̌������A�J�f�~�[�Ɉˑ����邾���łȂ��A���_���̏��X�����ƌ������A�G�b�Z�C�ɂ��܂Ƃ߂����ƁA�Ö{���l���̐^���̋L�^�ł���A�Ƃ��Ă���B�ÉƂ́A���܂�ς�����牽�ɂȂ肽�����ƕ�����A�u�܂��Ö{���ɂȂ肽���v�ƌ������Ƃ����B�ނ͏I���A�Ǐ��̏d�v����������B
�@�ÉƂ��w�d�����y�����x��10���ɏ������_���u����j�̌����Ƌ��y�j�̊W�i��j�v�́A�ނ̋}����N�O�̂��̂ŁA��e�Ƃ��]���ׂ��_���ł���B�i�ȉ��Ɉꕔ�Љ�j
�@�u���j�͏����̊w�҂�D���Ƃ̓Ɛ�ɔC���Ă����ׂ��w��ł͂Ȃ��A���ׂĂ̐l�����g�ɂ��āA�ߋ��Ɍ�X�c��̔Ƃ����߂��̂��߈�ʂ̐l�������ɔߎS�ȋ����Ɋׂ���������m���āA���݂̎������Ƃނ��т��čl���邱�Ƃ͍ł��d�v�Ȃ��Ƃł���A�܂�����ɏd�v�Ȃ��Ƃ͉ߋ��̗��j�I�m����o�������āA���݂̗��j�̗����I�m�ɔᔻ����͂�{���A����̕������߂����Ȃ����߂ɖ��O�̗͂����W����Ƃ������Ƃ��ő�̖ڕW�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�i�ȉ����j�v
���^
�R������@�������̌Ö@�ؐΕ��̔����͗L���ŁA�b�z�w�@�̃N���u�ł����������B
���삳��@�o�P�P�S�̑勴���[�͕��o�o�g�A���e�͗���̍����}�Ƃ��Ēm��ꂽ�B���[�͐�O�͋��Y�}���ŁA���͎����}�̕{��c���������B���̓V�����\���̎�i�����@�}�j�B
�c������@�_�ˎs�}���قɁA�{��T�ꎁ�����������w�ÉƎ��O���L�����x���������B���L�̏ڍׂ��L�ڂ���Ă���B�o�P�Q�V�̑吳���[�f�[�̎ʐ^�̉���͂܂������A�E���̊X����`�̎ʐ^�B�ÉƂ̌����p���̓����́A���H�ƌ��т��Ă��邱�Ƃ��B
�i���S���̔������f�ڂł��Ȃ��������Ƃ����l�т��܂��B�j
11������ �@�����@������u��ɂ��R�����������|�����A����������v

�͂��߂�
�u�����R�����v�́A���݂̍�s���������E�x�@�w�Z�E�������w�Z�E�ߋE�����ċz��Z���^�[�E�J�Еa�@�E���{�����h�ɁE�����c�n�Ƃ��̎��ӏZ��n�ɂ�����B
1932�i���a7�j�N�A����s�k�撷�\�����ɐ^�c�R����R���A���ړ��B����n�d�����ړ]�E���R�a�@���V�݁A�u�R�����v�ƂȂ���
�R�����ɂȂ�O�͔_�Ɨp���r����i��{�r�Ɩє��r�j����A�߂��Ɂg��c�h�i�㓙�Ă���c�j�̏������߂��ɂ���قǗǂ��_�n�������Ǝv����B
1928�i���a3�j�N�ɘb�����������A�_���͎������ƖҔ��B3�N������ŌR���ɉ������A1931�N�ɍH�����n�܂����B
���̓A�����J�i���R�̕a�@�ƂȂ�A�n���̋����肢�ŕԊ҂��ꂽ�B �����}�́A20���l�̑̌��҂�n���̐l�̕������ƍ���}���كA�W���Ȃnj���������쐬�A�����̔z�u����Ԃ�T�邱�ƂƂ���B
�@�����A���E�����L�����v�̕���
�����������ق̃A�W�A���j�����i�A�W���j�̗��R���n�d���ړ]�W�����̐v�}�Ƒ̌��҂̕�������1948�i���a23�j�N�ČR�̍q��ʐ^�̏�ɕ`�����������B�����L�����v�͋ߋE�����ǁu�����ݕt�_�v�t�}�Ƒ̌��҂̕����������a23�N�ČR�̍q��ʐ^�̏�ɕ`�����������B
�A������ƋR����������n�d��
������́A�ŏ��͌����������ɂ��������A���R�a�@���o�����̂ŁA�������c�n�Ǝ��ӏZ��n�ɔ_������y�n����グ��`�ŗ������������B�I�풼�O�́u����������҂̈ɁB���w���������i8��15���ߑO�����j�v�B �R�����́A1870(�����R�j�N������ɑ�1�R�����Ƃ��ĕҐ��B1896(����29�j�N�R����l�A���Ɖ��̂��A���݂̐^�c�R�����j�Ɉړ]�B1932�i���a�V�j�N�R���A���������]�����i���������E�x�@�w�Z�j�Ɉړ]�B1941�N�A�{����l�A���Ɖ��̂��A�g���b�N�Ɛ�Ԃ��g�p�B1945�N4���A�{����l��[�������U���A�{�y�h�q���ɓ]���B�{�y�h�q���͂W�������W�h�����ꂽ�B1945�N4���A���ŌP�������Ґ�����A�Ւn�́A���ő��i�ŃK�X�������j�ƂȂ�B
�@�I����1945�N8��20������A�ŃK�X����̃h������10���{���͓�����ɉ^��A���{�����P�r�̒��ցA���{���ݕӂɁA�c�肪���тɖ��߂�ꂽ�B�p���H�ŋ����Ƃ��Ă�����l�P�������S�B�r�ŗV��ł����q�ǂ������@�i�������@���͓�����s���c�̗��R�c�N�w�Z�̂��ƂɈڂ����������a�@�Ɂj
�n�d���́A1876(�����X�j�N�A������n�d��l�����Ƃ��ĕҐ��B1934�i���a�X�j�N�R���������Ɉړ]�A1935�N12���A���͎����ԕ����ƂȂ����B
�B�̌��҂��������n�d���̂悤���B
��̕��ɂ�4�̕���������A�ꕺ���ɖ�20�����Q�Ă����B�����̂R�ӂɈ�l��60�p�̂��ӂƂ�̃}�b�g�������Ă����B�}�b�g�̏�ɖѕz��~���A�����ꖇ�̖ѕz��Ɋ��������ɐQ��B���̗l�q����܁i�����j�ƌ����Ă����B���т��E�Q���E�Q�Ԃ���ł��Ȃ��B
���͏�肱����̂͊ȒP�����A�オ�����ւ�I���镺�����E��(�E��j�����B�Lj��̘A�ѐӔC��Njy���ꂽ�B�ۈꒋ�邵�đ{�����ɘA����ċA�����A�q�����̉��̉c�q(�R�̗��u��)�Ɉ�T�Ԋċւ��ꂽ�B�ߕ��̕R�͂��ׂď�����A���������ɐ������āA����������Ď�����Ă����B3�x�̐H���͔тƂ������݂̂ʼnq�����o�R���ēn���ꂽ�B�������͔ǑS�̂��ސT�𖽂����A�����Ƃ����u�A�ѐӔC�v����������ꂽ�B1�T�Ԃ����Ĕނ��Ǔ��A���āA���炭1�l����Â��Ă��Ă����B�ς���ꂸ�֏��Ŏ��E���������������ƕ������ꂽ�B�i�ݏ㐴������̘b�j
�C���R�a�@�������@�ɂ���
1934(���a9)�N3��22���A�n�d���ƈꏏ�ɉq���a�@���V�݂���A���̌�1937�N�A���R�a�@�������@���ł����B1941�N�A����302�~���ǂ��Ґ�����A���R�a�@�������@�Ƀs���N�̏��W�ߏ�������ԑ��E�a�̎R�E�ޗǁE���ɔǂ̊Ō�w���z�u���ꂽ�B
1945�N6���A���R�a�@�́A�������@��������𗘗p���Ċg����6���ؕa����60���A���e����5��l���z���A���O�����P���R�a�@�A���������Q���R�a�@�Ƃ���B1945�N�A�ꕔ���ޗnj��������֑a�J�A��J��(�{���Ƒ�1�a��)���쉮(��2�a��)�E��쉮(��3�a���j�i�w����s�j�x�㊪���j���������B
�Ō�w�ł������c��������̏،��ɂ��ƁA�Ζ��͂Q����12���Ɍ��B37���܂ł���37���͌��j�E�`���a���B�a���ɂ́A�����Ƀx�b�h�����ъe���ɋl��������Ō�w�̉�����������B�a���ƕa���̊Ԃ͂��ƍL�����������B��̕a����60�l���炢�B36�ԓ��̓T�u���N�ƌĂꐸ�_��a��ł����l���������āA�Ō�w�ł͂Ȃ����������L��
�S�����߂��炳��Ă��āA���҂��\���Ɠd�C�S�e�����Ė��炳�ꂽ�������B�[�ɉp�쎺������S���Ȃ����l��A��Ă������B�u���R�a�@�͋S�̋����E���̓��Ԃƌ���ꂽ�B
���R�a�@�����a�@�ł̎��҂̐��̌����ȕ͌������Ă��炸�A�߂��̂����́u�����L�^�v�ł́A���a17�N166���A18�N255���A19�N529���A20�N628���A�v1,578���Ƃ���A�ō���20�N2���̑��V22��126�l�ƂȂ��Ă���B
1945�N10���A�A�����J�i���R�����L�����v�ɂȂ������A�a�@�͉͓�����s�̋����R�c�N�w�Z�ՂɈڂ�12�������ȂɈڊǁA�u�������a�@�v�ƂȂ����B
10������ �@�ߍ]����コ��u��B�@�ۘJ���҂̂��������̐擪�ɗ����ē��������鏗�q�H���̔����v
�s������a�J����
�@�ߍ]����͑��s�`��s���Ő��܂ꂽ�B���e�͈����̐��܂�ŁA�n��Y�Ƃ̐̉��H�Z�p���o���č`��ŐH�Ƃ��ē������B���w�Z6�N�̍��A��P������ė��e�̐��܂ꂽ�����ɑa�J�i���̑a�J�j�����B�c�ɂɐe�ʂ̖����l�͏W�c�a�J�œ��������]�s�ɍs�����ꂽ�B�����A�a�J�͂܂����x�O�ɗ\�s���K�I�ɐ����s���A���̌�{�i�I�ɑa�J�����B�i���Q���҂̐X������A�`��̐l�͘a��s�ɗ��Ă���
�Ƃ̕��������B�j�ߍ]����o���̖��O�͌N����̉̎��ɗR������B�ߍ]����͔����őo�q�̖��͐��B���O�̂��Ƃœ��̐��k����͂₳��Ă����߂�ꂽ�B�����͂ǂ����Ȃ��������A���������ċA���ė����̂ŁA�u���̂𗘗p���Đl�������߂�Ƃ͉����Ƃ��I�v�Ƃ�肩�������B�����̐��i�͂��Ă�ŁA���͕��w�����������B���w�Z�̍��A�S�C�̉p��̐搶���A�u�ׁ[�x���̕w�l�_�v�ɂ��ċ����Ă���āA���̎����̎v�z���w�B
���m�@�ۂɏA�E�A�V�x���A�}���҂����}���銈����
�@1948�N�V�����w�Z�𑲋Ƃ��āA���̐����A�D���Ȃǂ�����]�ƈ�����l�̑��Ƃ̓��m�@�ہi�L�����O���s�j�ɏA�E�����B�d���͑@�ۂ�D��O���������Ă����B��h�Ɂi1500���قǁj�̎�����ƂȂ菗�H���Ԃ̗v���Ȃǂ��܂Ƃ߂ĉ�Б��ɓ`���邱�ƂȂǂ����Ă����B�����A�V�x���A�}���҂��A�����Č̋��ɋA���Ԃ��e�n���ړ����Ă����B�����̌������̍L�����O���s�̎���w�ɗ�Ԃ���Ԃ��邱�Ƃ����̒m�l���畷���Ă킩�����B�A���ė������m���A�̂��̂�����b�������肷�邱�Ƃł͂��܂����Ə��H�����ɌĂт����āA�ߌ�9�����ɏo�����čs�����B����w�̏o�}���̕]���͕��߉w�܂œ`����Ă����B��Ԏ��Ԃ����̊��}��ł��������A�A�����m�����ɂ͊�ꂽ�B�ߗׂ̐E��̒j���J���҂����H�����̈��S�x������ďo�Ă��ꂽ�B���̍s���͊�h�ɓƎ��̍s���ł��������A��Б��́A�悯���Ȃ��Ƃ����Ďd���ɍ����x����ƍ���Ƃ��āA���S�I�ȏ��H��ސE�ɒǂ����B�ߍ]��������̌�A�����J���G�X�œ��@�������Ƃ�����A���ق���Ė������镟�R�ɍs�����R�D���ɏA�E�����B�J���g���Â��肪���o��
�đ��o�����ɔz�u�]��������ꂽ�B����Ȃ���l�̎����J���ɏ]�������B�����A�������ɍs���ƍ�{�a�т̘J���g�����f���Ȃǂ̊��������Ă���̂�ڂ̓�����Ɍ��āA����ȐE��i���R�̖a�щ�Ђ̏o�����j�ɂ͋����Ȃ��Ǝv�����B
�ێO�~�z�ɏA�E�|12���ԘJ���ƃZ�N�n���̑̌�
�@���a�@�ɒm�l���������ɍs�������A���̖a�щ�Ђœ����Ă����l���E���ɂ����B���̐l�́A���a�L�˂ɋ߂Ă�����1950�N�̃��b�h�p�[�W�ʼn��ق���Ă����B�ޏ������B�̖a�щ�Ђɐl�肪����Ȃ��ƕ����A�ێO�D�z�ɏA�E�����B�����ŁA��B�̘J���������@���ɂЂǂ����m�炳�ꂽ�B���̎���ł��������A��B�ł�10���ԁ`12���ԘJ�����܂���ʂ��Ă����B���m�@�ۂ╟�R�D���ł�8���ԘJ��������Ă����B
�@�H�����܂��������B�����舫���̂́A�j���̉����t�i�D�@�̒���������Z�p�ҁj�̃Z�N�n���s�ׂ������B�ߍ]����́A�K�⋹��G���Ă���ނ�̎���s�V�b�ƒ@���Č��ނł������A�ق��̏��H����݂͂�Ȕ�Q���Ă��䖝���Ă���ꍇ�����������B�����ԘJ���A�Z�N�n���A�H���Ȃǂ̑ҋ��̂Ђǂ��Ȃǐ�B�̖a�щ�Ђ͂Ђǂ���Ԃ������B
�J���g���̌�����
�@1961�N�ێO�D�z�ŘJ���g�������������B�J���g�������鎞�ɑ��k�����l�́A�т̂������ł������B�ޏ��͐�O�A�[�l�������[�^�[�Y�̃^�C�s�X�g�����Ă������A�g�������ȂǂŎ����ێ��@�ᔽ�őߕ߂��ꂽ�o�����������B���́A��s�̕�e�^���̒��S�I�Ȋ����Ƃ������B�����K�₵�ĘJ���g���Â���̂`�a�b�������Ă�������B�܂������̖a�щ�Ђ̑g�����̋N���܂ƂȂ����̂���{�a�јJ���g���̌����������B�@1959�N�c�K���ɂ�����2000�l�̏]�ƈ���i�����{�a�тŘJ�g���������ꂽ�B��{�a�јJ�g�́A�u2���12���ԘJ���A�����x�ɖ����v�Ȃǂ̈��������u��B�J��@�v��Ŕj���āA��B�̖a�щ�Ђ̘J���҂��܂��A�����̖a�щ�Ђ̘J�g�Â���ւ̎x�����s�����B�����D�z�̑��c�ł́A�J�g�������Ɏ��C��тт��E����20�������o�b�g����K�Ȃǂ���������R�̏��q�g�����≞���̑g�����ɖ\�s��������Ƃ����������N�������B5�����d�����Ƃ������ԂƂȂ������A�������ɑg�����������J�����B
�@�g���������ЂƂ̌��ȂǂŁA�n��ň�ԋ��͂Ȏx������������̂����E���g���������B�N�^���A�T�[�N�������A�w�K��Ȃǂ�����ɍs��ꂽ�B��{�a�т̒��ɘJ���w�Z���ł��āA�s��̐搶�Ȃǂ������ɗ��Ă��ꂽ�B
�g���������A�����͑g�����ƂȂ����B��Ђɂ́A�@�H���̉��P�A���������P�B8���ԘJ�����m���C�d�C����@�̍w���D�L���x�ɁA�����x�ɇE���̑��A��v�������B���̌�A���̉�Ђł��������őg���������s��ꂽ�B
�@�����́A�ߍ]����̑��ɒҒm�b�q����i����{�a�сj�A�o���I�q����i�������D�z�j�̂���l���g�����������Ȃǂ̑̌������A���{�F�Y����i�����ߌ���j�̉�j���i���S������܂����B
���^
�X������@���s�̍x�O�a�J��2��3���ŁA�`��̎q�ǂ��͘a��s�A1945�N6���ɓ�r�c���w�Z�ɗ��Ă���Ƃ�������������B�X�c�a�т͂��͂܂����ď��H���������Ƃ����b������B�Z�N�n���͐�B���Ђǂ������̂��H�@ �����@�ӂƂ�̒��܂œ����Ă���Ƃ������Ƃ��������B���₪�点�͈̔́B �҂���@��{�a�тɂ������A�[���Z�������͖��ɂ������A���]�ɑ��k�ɍs���ăX�g���C�L�������B�J���������A��Ђ���B���Ƃ����w���������B�\�͒c�̉��������A�g���������Ȃ����邱�Ƃ��������B �с@�����g����Ԃ̕��m�Ƃ͂ǂ�Ȍ𗬂��������̂��H �����@�قƂ�nj𗬂��鎞�Ԃ͖��������B���̐l�Řb������͂��Ă����炵���B
9������ �@�Ό����q����i����j�u�w�l�x�ƒn��̕���A�ܑ�F���̖��w�����v�q���L�x����v
�ܑ�F���̖��v�q�Ɠ��L
�@�v�q�ܑ͌�F���̎l���Ƃ���1883�i����16�j�N�ɐ��܂ꂽ�B�ܑ�͎F���ˏo�g�ʼn��B���w��A�������{�̊����ƂȂ�A��㑢�����i�̂��̑����ǁj���㊔��������Ȃǂ��J�݁A���𒆐S�ɓ��{���{��`�̊�b�ƂȂ�e�펖�Ƃ��N�������B�ܑ�̍ȖL�q�ɂ͎q�������A�l�j�̎q�������͊F��e���������B�v�q�̎���͏��ŁA�ƒ���ł͓���I�ȑ��݂ł������B
�@ �v�q�͐q�포�w�Z�𑲋ƌ��Z�Ŏs����㍂�����w�Z�ɓ��w�A�Z�N�Ԃ̑����Ȏ������߂������B1901�N�A����v���Y���̐��������Y�ɉł����B�����Ƃ͍����E���֏��A�y�n�o�c�Ȃǂ��c�݁A�F���̎��Ƃɂ����͂���D��̗L�͂ȏ��Ƃł������B�����Y�́A���݂������Ă��鐙���q�ɂƂȂ��Ђ�n�Ƃ����B
�@�v�q�̓��L�́A�����̈���q�����L���Ă������A��J���_��k�Ђɂ��Ƃ�����A�����ƂɂȂ������A���L���������ꏊ�L�҂�����s�ɘA��������A���s�j�Ҏ[���Œ������邱�ƂɂȂ����B���L��1911�N����1945�N�܂ŏ����p���ꂽ�B
�����Ƃ̐���
�@�F���͋v�q����̎��ɖS���Ȃ����B�v�q�̌������ɗp�ӂ��ꂽ���Q�̕i�������Ă��ܑ�Ƃ����ɗT���ł���Ƃ͂������A�����Ƃ��炩�Ȃ���������Ă����Ǝv����B�v�q�ƌƂ̊W�͌����Ȃ��̂������B���̂��Ƃ��A�̂��ɋv�q�̒����̉Əo�̌����ƂȂ����B�ԓ��̉�ژ^�ɂ��A�ܑォ�����ꂽ�z�R��Ђ̕s�U���A��㓖��̎��E�̌������Ƃ���邪�m���Ȃ��Ƃ͂킩��Ȃ��B�����Y�Ƃ̊ԂɂR�l�̎q�������܂�A�݂Ȗ��O�ɐ��̎�����ꂽ�B
�@1910�N6�����������Y�����s��c���ɓ��I�A1911�N11���ɂ͓d�C�S�������ɏA�C�����B��Ɏs�d���ʂ�A���̊g���̂��߂Ɂu����v������̂ŁA1911�N�X������]�V�q���ɓ]�������B���L���n�܂�̂́A1911�N9��29���A���z���I��������납��ł���B�Q�ԍ��Ŏŋ��������������ƁA�������͓̂n�ӛ��R�̗��j���ŁA�����\���������ł͂��܂�Ƃ������e�B1912�N1��7���͎�������Ƃ���`��H�ׂ��Ƃ����L�q�B���̓���O��A�l�M�������̏�ɓ����グ�I�ɂ��Ă����̂��A������̏`�ɓ���ĐH�ׂ�ƕa�C�����Ȃ��Ƃ������K���������B�v�q�̐����Ƃł̖����͋`��^�l�̂��Ƃ�
�ߗފǗ��Ȃǂ̉Ǝ��A�����A�ڑҁA�Ɠ��g�p�l�Ȃǂ̊Ǘ�����ł������B14�l�����g�p�l�i�펞4�`5���������j�ւ̋����́A�ߋG�������猎�����ɕς�����B
�ĐՐ����
�@1912�N1��16���A�u�{���ߑO�ꎞ���A��g�V�n�l�Ԓ��V�y�ق��o�v�Ƃ���A���ږx�ɂ����ĉЂ��g��A���ږx�k���̎s�d�~�݂���Ό�A�쑤�~�݈ĂɕύX����u�ĐՐ��v�ƌĂꂽ�B�����Ȃ��s�̎s�d�H���Ă�F�߂Ȃ������B���̌��ŁA�A���s���Ɠd�S�������������Y�A�Q�����R�����Ȃǂ����C���邱�ƂɂȂ����B 1912�N4��5���A�F���̖��F�����������E�̒��S�l�����c�`�O�Y�̑��V�����Ɏq���A��ōs�������l�o�������i��20���l�j�A�悭����Ȃ������Ƃ����B
�@1912�N8��20���A�u�{���s�����v�Ƃ���A���V�������8000�l���W�߂����s�����J����A�ĐՐ��i���Ë����j�̑S�����ƐA���s���đI�����c���ꂽ�B
�Əo�����Ɠ��L�������Ɖ]������
�@�v�q�̓��L�́A�ŏ��̂���́A�����ւ̎w������̂̏o������ȂǁA67�����قǂ́u���Y�^�v�I�ȓ��e���������A�����قǂɒ����Ȃ�A1912�N12��31���ɂ�599�����ƂȂ�B
�@1912�N2��19���`5��22���Ɏ��Ƃܑ̌�Ƃɒ����ɂ킽��Əo��������������L�̓��e���ς���Ă���B�Əo�̌����́A�ƂƂ̊W�̖�肪�傫���B�ƃ^�l�̋@�����u�V��v�Ə����A�Əo�O�ɂ́A���̂悤�ȕ\���͂Ȃ������B�Əo���Ă���́A�Ȃ��߂ɗ���l��A���k����l�̂��ƂȂǂ�������Ă���B
�@�v�q���g�̂��Ƃ�\������̂ɁA�u�����v�Ə����A�u���v�Ƃ����\���͎g���Ă��Ȃ��B�Ό�����́A�u�����v�́u���v���O�ɏo���Ӗ�������̂ł͂Ǝw�E����B
���^
�i��j�펞���̓��L�͂���̂��H
�i���j�펞���̕��͂���̂ŁA�������Ă݂����B �@�G��`���̂��D���ŁA�_���X������Ă����B���a�̎����͈�ԑ�ς������B
�i��j�G�͒N�ɏK���Ă����̂��H
�i���j�s���B
�i�ӌ��j�����̏����Ōb�܂ꂽ�ƒ�̐l�͓��L�������l�����������B���̕�����L�������Ă����B
�i��j�����Ƃ����������������ƂƁi�F���Ƃ̊W�Łj�F���˂Ƃ̊W�͂Ȃ��̂��H
�i���j�����͍����͎l���������ɓ������B
8������ �@���i�������j���コ��i�����{���w�Z�Љ�ȋ����j�u�q���|���Ɠ��U�|���w������w�o���ܓ���̃`���R���[�g�x�v
�Ȃ����̖{���������̂�
�@�����u�q���|���Ɠ��U�v�ɂ��ď������ƍl�����̂ɂ́A3�̗��R���������B
�@��1�́A�~�c�a�q����푈�̌��̏،��������ƁB�~�c����͋�����؍����i���E�{���t���u���Z�j���̍H��i��㗤�R���a���x���j�Ŋo���܂̓��������U�������̃`���R���[�g�̕��Ƃɏ]�������B�����������q�𑗂�o���Ă������Z�ł���Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ă������Ƃɋ������ׂ��B
�@��2�́A�S�c�������̏��������Ƃɂ����f��w�i���̃[���x�ȂǁA���U�����̏����ȋC�������������ē��U���������X�����L�����Ă��邱�Ƃւ̊�@���������B���U�͔����ł�����̂ł͂Ȃ��B���{�͐�n�Ŏc�s�s�ׂ��s���A�����ł����炩�Ȃ悤�ɓ��{�������R�Ɏ��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A���{�R���m�͎g���̂Ă������B�@�@
��R�́A���{�̐N���푈�𐳓�������u���s�j�ϔᔻ�v�A�u���j�C����`�v�̒������o�Ă������Ƃւ̊�@���������B1990�N��ɑ����̎Љ�Ȏ��Ƃ��Q�ς������Ƃ��������B���w����ΏۂɁu�����푈�͐����v���e�[�}�ɂ��āA���k�̐푈���O���[�v�i�ŏ��͑����h�j�Ǝ^���O���[�v��O�ɋ����ɂ��f�C�x�[�g���s��ꂽ�B�u�����̔_���̐����͑�ς������v�u���B�����ږ�������Ă����v�Ȃǂ̈ӌ����o�����ƁA�푈�^���h���ӂ��Ă䂫�A�����h���������Δh�������ɂȂ��Ă������B�u�푈����ނ����Ȃ��v�_�ɂ���Ď^���h���ӂ��Ă������̂ł���B���ꂪ���������ɂȂ��āA��I�Ȕ���ӎ��ł͕s�\���ŁA���{�̐푈�̃��A���Ȏ����ƁA�Ȃ�����Ȑ푈�������̂��̈��ʊW�i���j�F���j��`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����B
�q���|���Ƃ�
�@�u�q���|���v�͑���{����̏��i���ŁA1941�N�ɔ�������A�u���C��|�v�u��͑����v�Ȃǂ̌��\����`���ꂽ�����܂ł���B�P�V���������A�w������q�l�Ȃǂ́u����v�́A�t�Ɉӎ��������낤�Ƃ����铭��������B���Ђ͒������k���̕�V�i���E�c�z�j�ɂ��x�X���������B�����m�푈���n�܂�ƁA�q���|���͂قƂ�njR�ɔ[�����ꂽ�B���A�R�����o���A���̈��������i���o���L�����Ŏ҂��ł��B�펞���͌R���u�q���|���v���Ǘ����A��ʎs���̊Ԃɒ��Ŋ��҂͂قƂ�ǂȂ������B 1951�N�A�o������@�ň�ʎg�p�͋֎~���ꂽ���A�q���|���͌��݂ł��d�x�̂��a �Ȃǂɏ�������Ă���B�܂����q���ł͊o���܂Ɩ��ێ�����Ă���B�푈�ɂ͌������Ȃ����炾�낤�B
�q���|���Ɠ��U
�@�q���|���͎�ɍq�ɗ^�����Ă����B�R���H��̖�ԋΖ��҂ɂ̓q���|���̏��܂��^�����A�ΘJ�����̏��w���ɂ��^����ꂽ�B1945�N5���̉�����U�ł́A���e���ʍU�����ɏ��������B����j���A�R��̊����G����q���|���𒍎˂��ꂽ�B�����A����@�͂��łɎc�菭�Ȃ��A���U�ɂ����K�@�̔��e�@���O�����K�@�i�ԂƂ�ځj���g�p���ꂽ�B�B������͒��˂����ꂽ�̌����A�u���܂Ŏ��łӂ���Ă����g�̂����錩�闧�������Ă���B���̓��ɃV���L�[�b�Ɛ����Ȃǂǂ��ւ��A�_�o�͍V�Ԃ�g�����瓬�u���N���Ă���̂�������v�ƌ���Ă���B
�@�R��̊����G����́A�����A���˂̒��g���q���|���Ƃ͒m��Ȃ������B�R��w�Z�ł��������Ă��Ȃ������B��Ԃɉ���ɏo��������U���ւ̒��˂͎��̌R��ɂ܂�����A�㊯�͍s��������Ȃ������Ƃ����B���A��������͌��̏㊯����u����̓q���|���������v�ƕ������B
�����Ƃ��X���ȍ��A���U
�@���U�ɂ́A�q����U�i���e��ς[����A�l�Ԕ��e�u���ԁv�j�A�������U�i�l�ԋ����u��V�v�A�l�ԋ@���u�����v�j�A������U�i�x�j���̃��[�^�[�{�[�g�u�k�m�v�j�Ȃǂ��������B�C�R�̓��U�ӔC�҂ł���吼�뎡���́A���U���u�����̊O���v�ƌĂсA�{���̍��ł͂Ȃ����Ƃ��\���F�����Ă������A��x�n�߂��푈������~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��u���̃��[�v�v�ɂ͂܂肱��ł����B
�@ 1944�N10���A�֍s�j�����́u�_�����U���i�~�����j�v���čq���͂���������Ƃ����\�z�O�̐�ʂ������߂��B�����V�c�́A�u���̂悤�ɂ܂ł��˂Ȃ�Ȃ��������B�������A�悭������B�v�ƌ������Ɠ`�����Ă���B���������̌�́A�A�����J�R�̗D�ꂽ���[�_�[�ƈÍ���ǂɂ���āA���U���͐��ʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B���{�R�w�����͓��U�������̐�ӂ��ە������i�ƍl���A�V�c�̂˂��炢�𗘗p���ē��U�𐳓��������B�u�~�����v�𗦂����֍s�j���g�́u�ڂ��͓V�c����{���̂��߂ł͂Ȃ��A�ň��̍Ȃ̂��߂ɍs���v�ƐS���f�I���Ă����B���������́u���U�̎u�����v�Ƃ߂��āA�F�[�����䂩����R�Ƃ��Ă������A��������āu�u��v�̎���������B���{������⏑�ɂ͖{���������Ȃ������B���U���u��ɂ��s��ꂽ�Ƃ�����`�́A���ԂƂ͂����͂Ȃ�Ă���B
�~�c�a�q����̑̌�
�@�~�c����ٌ͕�m�̉ƒ�̎O���Ƃ���1930�N�ɐ��܂�A���w�Z5�N���̎��ɑ����m�� �����͂��܂����B�������O�����ɐi�w�������A�푈�������뜜�������e�̔��f�ō��ɑa�J���A������؍����ɓ]�Z�����B1944�N�ɂ͓��Z�ɌR���H�ꂪ�u����A�v���n�u�{�ݓ��Ŋo���ܓ���̃`���R���[�g�������Ƃ����w���ɂ���čs���Ă����B�~�c����́A���Ƃ���w�����`���R���[�g�𓐂ނ̂ŊĎ������ڂ���������w�����ꂽ�B�㋉������X�p�C���Ǝv��ꂽ�~�c����͂������ɉ���ɌĂяo����A�`���R���[�g��H�ׂ�����ꂽ�B�H�ׂ�Ƒ̂��J�b�ƔM���Ȃ�A���ʂ̃`���R���[�g�ƈႤ���Ƃ������킩�����B�ƂɋA���Ă��̘b������ƁA���e�́u�q���|���ł������Ă���̂��ȁv�ƌ������B�`���R���[�g�͖_��ŋe�̌�䂪���Ă���
���N�l�ւ̃����`��ڌ�����
�@���Ғʂ�̃X�p�C�̖�ڂ����Ȃ������~�c����́A���Ύs�̎R�ԕ��̐����i�Ȃ肠���j�ɂ���閧�R���H��^�`�\�i�u���Βn���q�Ɂv�̈Í����j�ł̋ΘJ��d�𖽂���ꂽ�B���H��͐퓬�@�u�i�Ђ���j�v�i���q��@�j�̃G���W��������ړI�Ƃ��Ă������A�ˊэH���Ō��ݒ��������B��2800�l�̒��N�l�J���҂Ƃ��̉Ƒ�700�l�������B�n���̏��w�Z�ɂ͒��N�l���������47���������Ă���Ƃ����������B
�@�^�`�\�͂₪�ĕČR�̋�P�̕W�I�ƂȂ�A�U�����������Ȃ��Ă������A�C���C�����̂点���R�l�i���m���j�����N�l�J���҂ɑ��郊���`���n�߂��B�\�͂̓G�X�J���[�g���A�֎q��������܂ʼn��邱�Ƃ��������B���Z�͂������Ă��邾���ł������B�~�c����́A�^��Ɏv���āu�Ȃ�ŁH�v�Ə��Z�ɉ��x���q�˂��B��l�̏��Z���u�����Ē��N�l������v�Ɠ������Ƃ����B�s���́A�^�`�\�ŏ��ޏċp����`�����B���ꂪ�؋��B�ł̂��߂Ƃ͒m��Ȃ������B
�@�~�c����́A�i�P�j�o���ܓ���`���R���[�g�̐�����Ƃ̈ꕔ�ɏ]���������ƁA�i�Q�j���{�l���m���ɂ�钩�N�l�ւ̃����`��ڌ��������ƁA�i�R�j�؋��B�ł̏��ޏċp�ɏ]���������ƂȂǁA�d�v�ȏ،����s�����B����́A���{�R���m��ꂽ���Ȃ��푈�̎�����`������̂ł���A���{�l������̋M�d�ȏ،��ł���B
�R����`����Ɛ푈�ӔC
�@���U���\�ɂ����͓̂��{�̌R����`����ł������B��؍����ł��u����w���v�i��ؐ����E���s���q�����j�����̋ΘJ��d��A�^����Łu�d�ʉ^�����Z�v�u�~�}�Ō싣�Z�v�Ȃǂ��s��ꂽ�B�c���p�̓h��G�ł́A�A�����J�����܂��Ղ��ɂ���q�ǂ��̎p���`����Ă����B
�@ �w�k����������䒉������͊C�R�̐l�ԋ����u��V�v�Ɛl�ԋ@���u�����v�Ƃ���2�̓��U�P���ɏ]�������B��̒��F����́u�k�m�v�ɂ����U���ɎQ�������B��l�͓V�c����N���푈�ɔᔻ�I�ł��������A������U�Ɏu�肵���B�u�펀�v��������Ȃ����̂Ƃ��čl���Ă���A�ǂ݂̂����ʂȂ�X�������̂��ƍl�����̂ł���B�Z��͐��̓��U���B���̕�����ᔻ���A���{�R�̖\�͓I���ق̎��Ԃ����A���ɏ،������B
�@���{�̐푈�ӔC���̂́A�V�c�A�푈�w���ҁi�R�l�A�����ƁA���E�W�҂��܂ށj�A�����A���f�C�A�A��ʖ��O�Ȃǂ���������B�����͌R����`����𐄐i��������̐ӔC�҂ł���B���A�����g���f�����u�����q���Ăѐ��ɑ���Ȃ��v�Ƃ����X���[�K���́A��㋳��̏d�v�ȖڕW�ƂȂ������A���̌��t�ɂ́A���̌��������̕��i���ʂ��Ă���B���Q�̎����A���҂ɑ��鎋�_�̂Ȃ��������S�̍l�����ł���A���E������Ǝv���B
�@���O�̐푈�ӔC�ɂ��āA1946�N�ɉf��ēɒO����́u�푈�ӔC�҂̖��v�������A�s���u�R����V���ɂ��܂��ꂽ�v�Ƃ��������̍����̑ԓx��ᔻ���āA�u�ᔻ�͂Ǝv�l�͂������Ă��������v�̐ӔC�ɂ��Č��y�����B
�@���N�͗��j�C����`�I�Ȓ��w�Z���j���ȏ����A3��������ɍ��i���A�e�n�ō̑��ɔ�����^�����N�����Ă���B��x�Ɛ푈���N�����Ȃ����߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ́A�i�P�j���O�����������Ȃ邱�ƁA�i�Q�j�푈�̌��������ɂ���l�Ɏv����y���邱�ƁA�i�R�j�������z�������O�̘A�т�z�����Ƃ��K�v�ł���B
���^
���R�肳�@�~�c����̂��o����̍��X���Ύq����͐�㏉�߂Ăٌ̕�m�ŁA�Љ�}�̎Q�c�@�c���i���I����1971�`77�N�j�ƂȂ������ł��ˁB ���������@��ł̓P�V�͔|������Ă��āA�����̃^�o�R�ɂ��A�w���������Ă����̂ł͂Ƃ������Ƃ������A�ǂ����H�i������F�����̃^�o�R�ɂ��A�w���������Ă������Ƃ͕��������Ƃ��Ȃ��B�j ���с��@����̓��c�@�k����̘b�ŁA�W�H���̎��ƂŌR���a���ɂ����`���R���[�g��H�ׂ��Ƃ̂���
6������ �@���@�K�v����i����j�u���̐���ǂ��ā|�C��A�픘�A�R���ٔ��̎j���T���|�v
���̐푈�̌���`���邱��
�@������͕{�����Z��ސE�サ�炭���āA���e�i�̐l�j�̐푈�̌��n�߂��B���O�ɂ͏ڂ����b���Ȃ��������A�{�l���n��Ő푈�̌���b���Ă��āA���̃������c���Ă����B�h�C�c�̑哝�̃��C�c�[�b�J�[�̌��t�u�S�ɍ��ށv�Ƃ���悤�ɐ푈�̌��҂̋ꂵ�݁A�푈�̎�����`���邱�Ƃ����厖�Ȃ��ƂƎv���A�������̐푈�̌����������`���A���̐l��������āA����ɑ̌����A�`����A�����N�����Ă䂭���Ƃ����҂���C�������������B���ꂪ�A�W�A�̐l�X�̊Ԃɂ��L����A�푈�̔ߎS�����킩�������Ă�������ǂ��Ȃ邾�낤���Ƃ��l�����B
�@�T1��A�����ƒn�������̉Ȗڂō��Z���ɋ����Ă��邪�A���e�̑̌������グ�Ă���B���k�͐Â��ɕ����Ă���Ă���B��҂ɓ`���Ă䂭��ŁA����̏�͑厖���B
�R���ؖ��ƕ��Е�̒�������
�@ �@���̍u�������Ɂu��ƍٔ��v�Ə����ꂽ���̂��������B�u��ƂɂȂ����̂��H�v�Ƃ����^�₪�킢���B�����ŁA�܂������̊�{�ƂȂ�R���ؖ��A���Е�Ȃǂ��璲�n�߂��B
�@���挧���{�ЂȂ̂Ō��ɖ₢���킹�ď��ނ������B1945�N�ɒ�������A�L���̑D���ʐM����[���ɏ����A��4��������̂��ɑ�5�����Ɉڂ����B8��6���ɍL���s���Ŕ픚�A9��18���܂Ŗ��a�@�ɓ��@��A20���ɏ����ƂȂ��Ă���B�i���a21�N6���ɏ����㖞���ƂȂ��Ă��邪�A���̈Ӗ��͕s���B�j
�@���Е�ɂ́A1944�N���������d�M�u�K�����̒ʐM���ƂȂ��Ă���B�c����͒ʐM�����ƈ��S�Ǝv�������w�Z�ɓ��w�������炵���B���̌�A��㏤�D�̒ʐM�m�Ƃ��Ē��p�z�����ꂽ�B�����J���Ȃ̃E�G�u�T�C�g������Β��p�D���̖��듙�̎���������Ƃ킩��A�l�b�g�Ŗ₢���킹�āA3�����قǂŃR�s�[�𑗂��Ă�������B�D���J�[�h�ɂ��ƁA��3���ʐM�����m�ŁA6��19���Ɏu�A�g���ۂɏ�D���Ă���B6��15���ɍL���̉F�i���o�q�A�v�T���Ŋ֓��R���悹�đ�p���Y�ŗA���D16�ǂ̑D�c�������A�t�B���s���Ɍ��������B���͖�i�����D�����B18�˂������B
�Đ����͂Ɍ��������
�@���D�ɂ�4285�l����D���Ă������A�r���A�A�����J�̐����͂Ɍ������ꂽ�B�ߑO���ɍŏ��ɒ��߂�ꂽ���A�����̔�e�����A���v�����Ȃǂ��ׂċL�^���������B
�@�ߌ�3�����A6���Ԃقǂ̕Y���̌�~�o���ꂽ�B���������ɂ��܂��Ĕg�Ԃ�Y���Ă���Ƃ��Ɍ���Ɏ��̂������������Ă��Ă����Ƃ����B�~�����ꂽ�D���܂���������āA�����̕��m����d����ɂ����S���Ȃ����B1944�N7��19���ɂ悤�₭�}�j���ɂ����B�t�B���s���ɂ́A���v�D�ɏ���Ă����D���╺�m�������ς������B�����̌����m�̏������{����������o�ł���Ă���B1944�N�̃t�B���s���ɂ͕ČR�������Ă��Ă����B7��18���ɓ�����t�������E�����B1944�N10��23�`26���A���C�e���C�킪�s�����{�͑�s�����B�t�B���s���S�y�ŃQ�����ɂ�锽�U���͂��܂�A�A���R�ߗ�4���l���{�y�ɑ����A���{�e�n�̕ߗ����e���Ɏ��e���ꂽ�B���́A�t�B���s������悤�₭3�x�ڂɒE�o���ċA���ł����B
�L���Ō����ɔ픚����
�@���͋A����A4���ɒ�������D���ʐM����[����5�����ɔz�����ꂽ���A8��6����8��15�����A�L���̕��ɂʼn������Ă����Ƃ����픚�����̂ł���B�����̓�����p�x�ɂ��A�����͓|�Ȃ��������A�|�ꂽ�����������ĉ�����ԂɂȂ����B��n���班�����ꂽ�����w�Z�̖��a�@�ɑ��������B���A���������̌�����3���������ǂ̕⏞�����߂�ٔ����N�����ď��i���Ă���B
���l�ٔ��̏ؐl�ƂȂ�
�@�@ �@���A���Ƃ̂��钹�挧�q�g�s�ɋA�����B���Ƃ͌R�����̏����ŗT���ȉƂ������B��˃t�@���ŁA�G���u��ˁv�̃R���N�V����������A���{���ꂽ���̂��ۑ�����Ă���B����1947�N�ɏ��w�Z�̐搶�����Ă�����ƌ�������1950�N�Ɏ������a�������B
�@�Ƃ��낪�����̏����̍Œ���GHQ����ˑR�Ăяo�������B���lBC����ƍٔ��ւ̏o��𖽂���ꂽ�̂��B���̍u���������������́A��ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����H�Ƃ����^�f��������B�����������ق̋L�^�ׂ�ƁA���̖��O���������B�퍐���ٌ̕�̂��߂̏ؐl�ł������B
�@�����́A�t�B���s������̋A���D�u���Ίہv�i��㏤�D�j��1944�N12��13���Ƀ}�j�����o�q��A14����15���ɕČR�@�ɂ�锚�������B�D�ɂ�1619���̘A���R�ߗ��Ə�g��100���A�}�j������̕w���q700���A����D��1000���A�x����30���A���̑��ɑ�p�l�R��26������D���Ă����B���g�Y�͏�g���ł͂Ȃ��A����D���Ƃ��Ă̕֏�҂ł������B
�@�U���ɂ��ߗ��̎����A�D����E�o�����ߗ�����{�R���m���e���������ƂȂǂ�����A�ʂ̑D�ɏ�芷���Ė�i�ɒ������Ƃ��ɂ͕ߗ��̐����҂͖�600���ƂȂ��Ă����B
�@�ٔ��ł́A�ߗ����Ǘ���������ƑD����9�����퍐�ƂȂ�A2�����i��Y�ƂȂ����B���́A1947�N3��10������5��9���܂ŁA�ؐl�Ƃ��Ă����炭��������l�ٔ��i�����l�n�فA2000�N�ɉ��z�j�ɏo�삳����ꂽ�Ǝv����B�ٔ��j���ɂ͕��̏،����e���݂���Ȃ������̂ŁA���㑼�̎���������\��ł���B
���^
���R����@��l�̂Ō��푈�̌��͑厖�Ǝv���B�����̒����Ȃǂ́A�ǂ̂悤�ɂ��āA�ǂꂭ�炢���Ԃ����������̂��H�����@2016�N�ȍ~�A�����̎d�������������Ă���A�i�̒��ŏЉ���j�������ق⎩���̖����Ȃǂ̂ق��A�l�b�g�����Ȃǂł������������B
���삳��@���������w�������������u�K���ƒ��M�ȍu�K���i�̂���NTT�ɂȂ���j�Ƃ̊W�́H
�Җ{����@����P6�̎Q�l�������̋�{�^���Y�w�펞�A���D�c�j�x��T���Ă��邪������Ȃ��B
�咬����@�R���͑��{�̂��͍̂����ɏ�����Ă������A�{���ɂ��قȂ�B���́u�푈�ɗ^����ȁv�ƌ����Ă����B
��������@���͒�������ɔh�����ꂽ�B�Z�̘b�ł́A�������ɍs�����Ƃ����B����90�̎��ɐ푈�̌��̘b�����B���R�a�@���������ɍU�߂��đS�ł����B���͒�@�ɍs���Ă��Ė����������B���̂��Ƃ͋@���ɂ���A�R���炷���A������Ɩ�����ꂽ�Ƃ����B
�R�肳��@�{���ŋ߂Ă������A�����ۂ̐l�̘b�����B����3�`4�N�ňٓ����邪�A���̐l��35�N�قǂ����B�����g������ǂɂ������A�R�����Ԃ̘b�ŁA�N����L���Ɏ�邽�߂ɌR���̍��̂�����҂����邱�Ƃ����B���N�����ۂŋ߁A�����ɂ��킵���������̐l�́A�R�����̂����j�邱�Ƃ����ӂł������B�펞���C�쓇�ɂ����l�ƌ��n���w�ɍs�������A���̒��ւ͓���Ă��炦�Ȃ������B
�@
���J����@�����̍����ɏ����ꂽ���O��41���Ȃ̂́A42�����Ɖ��N����������Ȃ̂��H�@
�@
�Җ{����@�����ɏ����̖��O�������B�j���������Ȃ������̂��H �@��肳��@���͘a�̎R���V�{�s�o�g��17�Ŏu�蕺�ƂȂ����B���w�Z���ŏ��w�Z�̑�p�����ƂȂ������A�������������ČR�l�ɂȂ����B�����ŁA�\�A���Q�킵�čU�߂Ă����Ƃ��ɒ��ƌ����߂œ��{�R���R�킵���ۂɁA�u�Ђт��v�Ƃ������̂̕����Ő�����Ƃ����b�����Ă����B1945�N9���ɋA�������B �@
�x�z����@���_����B29������̈ԗ�Ղɍs�����B�푈�̌���m�邱�Ƃ��厖�Ǝv���B�A�E�V���r�b�c�������e���ɂ��s�������A�g���E�}�ɂȂ�قǂ̑̌��������B
�@���^�A�ӌ������͊����ɍs��ꂽ�B���ׂĂ̎Q���҂̈ӌ����f�ڂł��Ȃ��������Ƃ�����т��܂��B
5������ �@���w��u���E��Y�E�Îs�Õ��Q������v �ē��@�������j�i�^�c�ψ��j

�T���S���ɐ��V�̉��A�Îs�Õ��Q���������B���䎛�s�E�H�g��s�ɂ܂�����H�g��u�ː�[���̍��{(����)��n�𒆐S�Ƃ����S�q�l���͈̔͂ɂP�R�O��ȏ�̌Õ����m�F����A��������̂͂S�T��Ƃ���Ă���B
�@�ߓS�y�t�m���w�ɏW�����A�w�O�ɂ���ē��𗘗p���ČÕ���Õ��Q�ɂ��ĊȒP�Ȑ����������B
�@ ���̌�܂��s��R�Õ��i�`��(����)��(���傤)�V�c�ˌÕ��j�ɍs�����B���u���Q�R�Om�̑O����~���œ�d�̍��ƒ炪���������Ƃ��m�F����Ă���B�]�ˎ���ɂ͖Ȃ͔̍|���s���u�ȎR�v�ƌĂ�Ă����B�n�`��A���ɐ������܂�ɂ������l�͎��R�ɏo���肵�Ă����B�z�������͌ܐ��I��������㔼�Ɛ���B
�@ �����Ă��̌Õ��́u���ˁv�i��Õ����ӂɒz�����Õ��ő�Õ��̔푒�҂̉Ɛb���A���邢�͔푒�҂̌��͂������함�[���Ă��鏬�Õ��j�̈�ł��铂(����)�C�R(�Ƃ��)�Õ��ɍs�����B���u���T�Xm�̔����L�`�Õ��Ō�~���̓씼���͕{���ƋߓS���ɂ��j��A�O�����͖��Ԃ̒���o�Č��݂͍X�n�ɂȂ��Ă���B���䎛�s�������������E���J�̗\�肾�������B�z�������͌ܐ��I�㔼�Ɛ���B
�@���ɓ�ˌÕ��i���j�Ձj�̖@�ʂ̊K�i����܂œo�����B��ӂU�Rm�����Vm�̕����������̗���Ŏl�p�����`�͂悭������Ȃ������B�ԋ߂ɒ��ÎR�Õ����]�ߒz�����������Ɏl���I�����Ɛ��肳���̂ŁA���̔��˂Ƃ��Ă悢�ł��낤�B
�@�Õ����~��ď��������ƒ��ÎR�Õ��i�`��(�Ȃ���)�P(�Ђ߂�)��(�݂���)�ˌÕ��j�ɓ������B���u���Q�X�Om��������{�̌Õ��̑傫�������L���O�ő�X�ʂɂȂ�B�O����~���ō��{��n�̍ō��n�_�ɗ��n���Ă���B���@�����͂��ꂽ���A�����܂ŋ{�����Ǐ��̈�O�݂̂ł���B�S�㒹�E�Îs�Õ��Q���ŌẤ��剤�˂ƌ����邪�A�푒�҂Ƃ���Ă��钇�P����艞�_�V�c�i���P���̕v�j�̕����������S���Ă���̂ŁA�{�����́u����(�����傤)�v�͍������Ȃ��B�i���X��A�V�c�̌ď̂�p���Ă��邪�A�V�c�̗p��͂V���I�㔼�ȍ~�Ɍ����̂ŁA���̎��_�ł͖{���u�剤�v�Ƃ����ׂ��ł���B�j
�@���ÎR�Õ��̑��ʂɉ����ĕ������̋��傳���������Ă��邤���ɁA�������Î��R(���ނ���)�Õ��ɒ������B���u���P�T�Om�̑O����~���ł��邪�A���̌Õ��̓����͕����܂œo�邱�Ƃ��ł��钆�^�Õ����Ƃ������Ƃł���B�{���A�������L�̕������ł���Õ��͒��ɓ���ē��R�ł���A�܂��Ă␢�E��Y�͒N�������R�ɏo����ł���ׂ��ł���B�Ƃ��낪�A���̌Õ��͔��ɒ������P�[�X�ł���A�ό��|�C���g�Ƃ��ėL���Ȃ͎̂��͎c�O�Ȏ��Ԃ��B
�@ ���͕������̍����ւ̊J���������Ɛi�߂Ă����ׂ��ł���B����܂œo�蕭�u�̋K�͂�`�������ł������Ƃɉ����A�����炵���悭�_�c�R�Õ��A���ׂ̃n���J�X����R�E�����R�������A�ꕞ�̑u�����𖡂�����B�z�������͎l���I�㔼�Ɛ���B
�@�@�ԖʎR(�����߂���)�Õ��͓��قȌÕ��ł���B�����㎩���ԓ��̍��ˉ��ɗ��n���Ă���A���H���݂̍ہA���r���P�{�Ƃ��Õ��̐^��̂݃R���N���[�g���A�[�`��ɕ⋭���A���������u�ɉ����ăJ�[�u�����Ă���B��ӂQ�Qm�A�����Q.�Vm�̏�������������1956�N�ɍ��j�ՂɎw�肳��Ă����������ŁA���̌�̍H���Ŕj�ꂸ�ɕۑ����ꂽ�B�������ۑ�����̂Ȃ�A���߂Đ������x�͌f�����Ăق������w�lj����Ȃ��B���O�̒m�����Ȃ���A����ƕ����炸�ɍH���̐��y�������Ƃ����v��Ȃ��ł��낤�B�~�����ցi�ܐ��I���ߍ��j���o�y���Ă���A��肪�אڂ���咹�ˌÕ�����o�y�����~�����ւƓ��l�ł��邱�Ƃ���A�咹�ˌÕ��̔��˂ƍl������B
�@�咹�ˌÕ��͕��u���P�P�Om�Œz�������͎l���I���Ɛ��肳��A�~�����ցE�`�ۏ��ւ̂ق�������2���o�y����ȂǍ��j�Ղɂ��w�肳��Ă��鉿�l����Õ������A��~���̕��u�������~�j����`�łR�J���̑傫�ȌE�݂�����B����͑���E��펞�ɗ��R�̑吳��s��i��������`�j����P����鎖�Ԃɔ����A�ߗׂɐ퓬�@�������\�ȕ��̍L�����H�i���݂͕{���j��~�݂��A���̐퓬�@���B���Ă����u����(����)��(����)�v�̐Ղł���B�܂���~���̕������ɂ͂S�J���́u�e���v�Ǝv���邭�ڂ݂�����ꂽ�B
�@ ���͗_�c(����)(��_)�R�Õ��ł���B���u���S�Q�Tm�őS����Q�ʂ̋K�́i�e�ς͑�P�ʁj�B�O���������ɓy���ꂪ������i�������×����A���u�̉��Ɋ��f�w�B�V���N�Ԃɒn�k�ŕ����j�B�Q���{�ȏ�̉~�����ցA�e��`�ۏ��֓����o�y���A�z�������͌ܐ��I�O���Ɛ���B�O���������~���܂ŕ����A���̋��傳�����������B
�@ �����ė_�c�����{��K�ꂽ�B�{�i��苫���̈ē������̂��ɂɓ���Ē����A�_�c�R�Õ��̔��ˊێR�Õ����甭�@���ꂽ����̂Q��̋��������Ƌ���i���̕��l�̓�����͂S���I�����琷��ɂȂ������N�Ƃ̌𗬂ɂ���Đi������Z�p���ړ����ꂽ�Ƃ����w�i
���j���l�X�ȋM�d�Ȏ����������Ē������B
�@�Îs�Õ��Q��2019�N�ɕS�㒹�Õ��Q�Ƌ��ɐ��E��Y�ɔF�肳�ꂽ�B���̂��Ǝ��̂͐l�X�̊S��[�߂�_�@�Ƃ��Ă������Ƃ����m��Ȃ����A���R�ɗ�������Ȃ��Õ����w�ǂ�
���錻���P����Ȃ��̂ł���A���̔F��ɈӋ`���������̂��^��ł���B�܂��Ă�V�c�ˋy�т���ɏ�����Õ��͋{�����Ǘ��̉��A�����҂ł��痧�������Ē������邱�Ƃ��w�ǂł��Ȃ���Ԃł���B�{�����̓V�c�ˎ��肪����Ă��邱�Ƃ��������Ƃ��Ă��A�����҂���ɂ͈�ʐl�ɂ��J�����āA���j�̐^���ɂ�蔗�邱�Ƃ������ɂƂ��Ă̗��v�ł���A�����̐i�W�Ђ��Ă͕���
�̔��W�ɂ���^����̂ł͂Ȃ����낤���B
4������ �@�u���C�A���E�A���h���[�E�r�N�g���A����i�I�b�N�X�t�H�[�h�����������j�u�@���Ɛ푈�v

�ǐS�I�������ۂւ̓�
�@�u���C�A������͕č��l�u���X�J�B�̃I�}�n�s�̏o�g�ł���B�A�����J�̐^�A�g�E�����R�V�����L����n�悾�B�x�g�i���푈�ȑO�͒��������������B���O�ɓ�����]����ꂽ���A�����͓G���E�����Ƃ��A�E����邱�Ƃ����₾�����B�}�^�C�`�������ɂ��u�G�������A���Q����҂̂��߂ɋF��v�Ƃ��邱�Ƃ��璥�����ۂ������B���̂��߂ɁA2�N�Ԃ͉������̂��߂ɐs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��w���Ǝ��A�鋳�t�ɂȂ�Γ��{�ɍs���č��ېe�P�ɖ𗧂Ă�ƍl��1961�N�ɃL���X�g���鋳�t�Ƃ��ė����A�R�w�@��w��3�N�ԉp����������B�鋳�t�Ȃ̂ŃL���X�g���̕z�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
��ؑ�قƑT�Ƃ̏o��Ǝ��]
�@���̂��߂ɂ܂��A���{�l�͂ǂ̂悤�ȐM�������Ă���̂���m��K�v���������B���Ċ���������ؑ�ق́w�T�Ɠ��{�����x�ɁA�u�����͎��߂̏@���ŁA��x�Ƃ��Đ푈�ɉ��S�������Ƃ͂Ȃ��v�Ə����Ă������B�L���X�g���́A�����ł͂Ȃ������B�����͖{���ɕ��a�I�ȏ@���Ȃ̂��H�Ɣ��M���^�ŁA�x�݂𗘗p���Ă͉i�����ō݉ƂƂ��ĎQ�T�����B���̌�o�Ƃ��āA�����@�̑m�ƂȂ����B�ԉ���w�̎s�씒���i�w�m�E�ՍϏ@�j�́w�T�Ɛ푈�ӔC�x��ǂ݁A�����͕��a�ɓO����@���ł͂Ȃ������ƒm�����B��؎��g���A1904�N�́w�����̐푈�ρx�ɂ����āA�u�K�v�ȂƂ��͂��ł������ׂ��̂��̂Ă悤�B���҂̏�ɕ��@�̊����v�Ə����Ă����B�X�Ɂu�m���͈ꗱ�̕Ă����Y�ł��ʂ��A�����̐��_�͘B���ɂ͖𗧂Ă�v�Ƃ����i��Ӎ��g�����Ȃ����j��̌��t�Ɏ��]�����B�����@�A��y�^�@�ȂǑ��̏@�h�����������œ��{�l�̐�ӂ����߂悤�Ƃ��Ă����B
�R�ɂ��T�̗��p
�@���{�ܘY�����͍݉Ƃ̑T�C�s�҂ŁA�����̑T�́u�R�l�T�v�ł���A�N�b��̂̐��_�ŁA�u���v���Ȃ����u���v�ɂ��邱�Ƃ��咣�����B����Ƃ���T���̂��̂��c�R�̐^�̐��_�ƂȂ�Ƃ����B�R�͑T�𗘗p���A�T�̕��������ǂ��Ƃ����͂����̂ł���B�L���X�g�����̂Ăđ����@�̑m���ƂȂ��Ă���A���̂悤�Ȕ����ɏo��V���b
�N�������B�܂��T�����Ƃ��������a�ɓO�������E�I�@���͂Ȃ������B���_�_�ɂȂ낤���Ƃ��Y���A�@���̋����ł͂Ȃ������ɍ����I�Ȃ��̂�����̂ł͂Ȃ����Ə@���̌������͂��߂��B
�A�j�~�Y���Ə@���̋N���|�@�����Ȃ��l�Ԃ͕K�v�Ƃ��Ă������H
�@�q���g�͓��{�̐_���ɂ������B�_���̍����̓A�j�~�Y���i���{�����ł͂Ȃ��j����͎��R���q�ł͂Ȃ��A������Ώۂɐ���̑��݂�F�߂�l�����ł���B�����I���E�̗��ɐ��_�E������A���낢��Ȑ_�X������B�A�}�e���X�͑��z�̐_�A�X�T�m�I�͉J�̐_�E�E�E�B���s�̕�����ׁA���[�}�̔_�k�_�T�[�g����k�X�A�G�W�v�g�̑��z�_���[�Ȃǐ��E���ɕ��ՓI�ɑ��݂���B�@���͂�����A�Ȃ����܂�Ă����̂��H
�@�z���T�s�G���X�ƌĂ�錻���l�ނ̗��j�͖�30���N�O�ɂ����̂ڂ�B���݂���@����1���N���炢�̗��j�����Ȃ��B����ȑO�̃A�j�~�Y���̗��j��ʂ��Đl�ނ̐��_�j��m�邱�Ƃ��ł���B
�@�l�ނ̑c��͕����œ����A����s�������������B�l�ނ́A�����c�邽�߂ɂ����A���R�E�����������ɗL���Ȃ悤�ɗ��p���邽�߂ɐ_��������B�����ɏ@�������܂ꂽ�B�J���~�点�邽�߂ɉJ�̐_������A�_�ɐ��ʂ����������B���ʂ��Ȃ��Ɨ��ݎ����ł��Ȃ��B
�@�����̎������Ă����l�ނ́A�����ǂ������Η�����Ƒ���i�G�j��ނ��邩�E�����A���������������c�邽�ߎ����̐_�X�����Đ�����B���ꂪ�@���Ɛ푈�̎n�܂�ł͂Ȃ����B�A�����J�ł͐푈������ۂɁA�ufor God and Country�v�ƌ������B�\���R�́u�_�̎v�������v�Ƌ���Ő�����B����͐_�̂��߂̐푈�ł͂Ȃ��A�_�𗘗p���Đ키�B���`�͎��������̕��ɂ��葊��ɂ͖����B����́A������E����B���ꂪ�ŏ��̒鍑��`�푈�������B���������̗��v�̂��߂ɏ@���A�_�𗘗p���Đ�����B�i���{�ł͐푈�Łj�G���u�S�{�ĉp�v�Ǝv�����ނ��Ƃɂ���Đl���E�����Ƃ��ł����B�@���́A���́u���`���v�̈ӎ�������B �@�A�j�~�Y���̓����́A�����̂��߂̏@���ŁA�l�̂��߂̏@���ł͂Ȃ��B�X�T�m�I���J���~�点��͕̂����S�̂̂��߂ł������B�������V�������Ȃ��Ɛ_����Ȃ��̂Łi�肢���Ă���Ȃ��j�A�V�����l�F�V���[�}�����o�ꂵ���B��\�I�ȃV���[�}�����ږ�Ăł������B�����ł���ږ�ẮA�_�̂�������m��A�����̍s�������肵���B�܂育�ƂƐ����͈�̂ł������B
�@�_�Ђ̏j���̒�ɂ̓A�j�~�Y���̐��E�A�_�b�̐��E������B�A�����J�l�����A�A�����J���Z���̐_�b�̐��E��m��ׂ��ł���B�_�b�̐��E�͋��`�łȂ��B�_���ɂ����`���Ȃ��A�P���q����P���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�J�[���E���X�p�[�X�ƁuAxial Period�v
�@�h�C�c�̓N�w�҃J�[���E���X�p�[�X��1930�N��ɁA�u�@���ɂ������ϊv�̎���
Axial Period�v�Ƃ����l�������������BBC800�`200�N�̂���A���E���Ő��ғI�Ȑl�X�̊ԂɁA�����I�Ȉӎ��ϊv�����܂ꂽ�B�����ōE�q��V�q�Ȃǁi���q�S�Ɓj���A�C���h�Ńu�b�_�A�}�n���B�[���i�W���C�i���j���A�����ŃG���~���Ȃǂ��A�M���V���ł̓z�����X�Ȃǂ��o�ꂵ���B�����̈ӎ��ϊv�̓����́A�@�@���͕����̂��߂ł͂Ȃ��A�l�̂��߂ł�����B�A���R�E�̐ۗ��̒T���B�B�����͕����̂��߂ł͂Ȃ��A���ՓI�ȋK���ł���B
�����̎���́A���݂͕������ł̃^�u�[���������A���̎��ォ�瓐�݂͑S�Ă̐l���瓐��ł͂����Ȃ����ƂɂȂ����B
�@���ƃe���E�푈
�@���_�Ƃ��āA��X�̍��Ƃ���@�ɒ��ʂ���ƕ����̎���ɂ��ǂ�Ƃ������Ƃ��B�j����̓o��́A�S�l�ނ��E�����Ƃ̂ł��鎞��ɓ������Ƃ������Ƃł���B�i�`�X�̋�R�i�ߊ��Ńq�g���[���߂������Q�[�����O�́A�u�s���͓��R�̂��ƂȂ���푈��]��ł͂��Ȃ����A�푈�Ɋ������ނ̂͊ȒP���B�w�U������Ă���B�댯���B�x�ƌ����A�����͏]���B�v�ƌ�����B
�@�@���͐푈�������炳�Ȃ����A�@���͈א��҂ɂ�藘�p���ꂽ�B1932�N�A�O�䍇���������̒c�@�����ƑO������㏀�V�����E���ꂽ�����c�����́A�e���ɕ������ւ�������������A��d�҈�������@��ŕٌ삵���ՍϏ@�m���̎R�{����́A�u���ƍ��̂ɊQ���ׂ����̂���Ƃ��͂��Ƃ��P�l�ƌĂ��҂��E�����߂Ȃ��ƕ��͉]�Ӂv�i�u���C�A���E���B�N�g���A�w�T�Ɛ푈�x�j�Ə،������B
���^�E�ӌ�����
�@���i���j�A�t���J��300���N�O�̒n�w���烋�[�V�[�i���l�E�A�E�X�g�����s�e�N�X�j�̉����o�����A30���N�O�̐l�ނƂ̂������́H�u�~�g�R���h���ADNA�v��������`�q�݂̂�`���邱�ƂƁA�V���[�}���������ł��邱�ƂƂ̊W�́H�܂��A�A�_���ƃC�u�͂ǂ��炪��ɂł����̂��H���i���J�j���h���t�E�I�b�g�[�́u�k�~�m�[�[�v�T�O���@���̍����ƕ��������Ƃ����邪�A�uAxial
Period�v�Ƃ̊W�́H���i�сj�����̎���ł�����V�q���Ƃ́A�_�k�����ȑO�̎�̏W����̐l�ނ��w���Ă���̂��H�����ł���Ȃ�A���{�̓ꕶ����͎�̏W�̐�������Ƃ��āA�ꕔ���n�I�_�k�����������A���{�l�Êw�̗L�͂Ȑ��Ƃ��āA�푈���قڂȂ������Ƃ���Ă���B���V�́A�퐶����̂��̂��l���E����̂ɏ\���傫���̂ɑ��āA�ꕶ�̂��̂͏��������^�ȉ��̓����̎�Ɍ����B�펀�҂̈⍜�̔�������銄�������Ȃ����Ƃ��T�Ƃ��Ă�������B���̂��Ƃɂ��Ăǂ��l����̂��H���i�����j���n�̎���ŁA������E�����Ƃ��푈�̑S�Ăł͂Ȃ��B����ɂӂ�邱�Ƃ��A�Փ˂̂����B�����c�邱��
���ő�̖ڕW�B�����ɂƂ��Ă̎ז��҂̑��݂�����B�A�����J���Z���̌��t�ɁA�����̖��O��l�Ԃƕ\�����A���̕����͐l�Ԃł͂Ȃ��ƕ\������B���i���R�j����̐��E�ŋN�����Ă�����ɂ��āA����̕������ɂ��ĕ��������B���i�����j�����Η��̂悤�Ɏ��������̎Љ�̗���ɗ��̂��A�l�ޑS�̗̂���A����̐l�Ԑ��i�d����j�̗���ɗ��̂��A����Ă���B���ۘA���̑n�����͕��ՓI�����̗��z���������B���{���A�����J�̍��Ǝ�`�Ƌٖ��ɂȂ�̂��A�A�W�A�̐��E�Ƌٖ��ɂȂ�̂��i�d�v�ȑI�����j�B���{�͓��I�푈�Ȍ�A�����J�Ɩ�������āA���{�͒��N���A�A�����J�̓t�B���s����D�����B������u���_���l�v�ƂȂ��Ē鍑��`���m�ŐA���n�̕���肠�������āA�ǂꂾ���㏞�����̂��B���I�푈�Ȍ�A�����J�Ɩ�������āA���{�͒��N���A�A�����J�̓t�B���s����D�����B���{�͂ǂ̂悤�ɐ����c��̂��B���l�Ɠ�������̂��A�A�W�A�̗���ɗ��̂��B���A�̈��S�ۏᗝ�����C������̋��ی����Ȃ����Čܑ卑�̎x�z���Ȃ������Ƃ��K�v���B���ՓI�ӎ��̏�ŁA���A�̉��v���K�v�B����̍��A�R������邱�Ƃ��K�v���B���{�͊j����֎~���ɎQ�����ׂ��ŁA�A�����J�R���ݓ��ČR��n�Ɋj�����u���Ȃ��悤�ɂ��ׂ����B���i���j�@����M���Ă���B���c�̎w���҂͐푈�ӔC��F�߂悤�Ƃ��Ȃ��B�ǂ��Ɋ�]�������Ă����Ă��������̂��H�Q�[�����O�̘b�͏d�v���B�������{���U�߂�ꂽ��ǂ�����H�ƕ����l�����邪�A����������Đ������肤���Ƃ͂܂��������B���i�����j�@���ɂ͌��Ɖe�̕���������B�e��F�߁A�����̏@���ɂƂ��āA����������m��A��������Ă������������B���i��j�z���T�s�G���X�͋�������\�͂��l�������Ƃ������A����ƃA�j�~�Y���̔����Ƃ̊W�́H���ꐫ�����𒌂ɂ��Ă���A�푈���J��Ԃ��N�����Ȃ������B���a�ł��邽�߂ɁA�����̈ӎu�d���邱�Ƃ��厖�ł���B����̔ږ�āA�o�ł�ƌ��������B���i���Y�j��O�A���h�w�l���1000���l�̏������g�D����A���̔��˂̒n�����ł��������Ƃ������B
�i���ʂ̓s���ŁA�����҂̈ӌ��S�Ă��f�ڂł��Ȃ��������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B�j
3������ �@���R�ĕv����i����j �u�����w�u�p��v�̍s���x�Ɓw�e��̐��x�����s���āv
�u�p��v�Ƃ�
�@���R����́A����܂ł̌����������e�A��㖯�O�j�����Ȃǂɏ������߂����ƂȂǂ�2���̖{�A�w�u�p��v�̍s���x�A�w�e��̐��x�ɂ܂Ƃ߂ďo�ł����B�o�Ō�A���R�����悤�ȃ^�C�g���Łw�p��̍s���|���̍s�����x�Ƃ����{���A������^���o�ł��ꂽ�B���e�͎����Ƃ͈Ⴄ���_�Ő펀�҂̌����ƒlj������Ă���B�����_�Ђ́A���q�����Ȃ��̂ō����I�ɂ͂��т����B���q������g�D�I�ɎQ�q��������A�V�c�̎ʐ^�������āA�̔������肵�Ă���B���̖{�̒��҂́A����Ȑ_�Ђ̑ԓx��ᔻ���� ���āA�펀�҂̈ԗ��^�S����l���Ă���B�������ǂ��l����̂��͑傫�Ȗ�肾�B�u�p��v�Ƃ͖����ɓ��c�����g�p�������t�Łu�������썰�v���Ӗ����A�펀�҂��]���錾�t�œ��I�푈�����肩��g�p���ꂽ�B���R����́A�͂����Ă����Ȃ̂����Ԃɂ������čl���Ă݂����ƌ��B
�^�c�R���R��n
�@�^�c�R���R��n�i�����s�V������ʑ��{���j�ɂ͖�6000�̕��Ɩ�8000�̈⍜��[�߂�[����������B�呺�v���Y�͑�ォ����{���R������\�z�������Ă������A1871�N�̔p�˒u���ɂ�蒆���W�����̂��Ƃœ����ɒ����R���ł����B�^�c�R�͒����R�̕�n�����n����n�ƂȂ����B
�@���ׂĂ��펀�҂Ƃ͌���Ȃ��B�a���҂⎖�̎��҂���������Ă���B�m���̕��̍����͉��m���̂��̂��킸���ɍ����B���m�̕��͓����K�i�����A���Z�͎���ŕʊi�̕�肪�����B��l�X�̌o���ׂ��B�����ɍۂ��Ē�R���A�\��ĉc�q�ɓ����ꂽ���ɕa�������l�A���E�����l�ȂǕ�������������ĕs�{�ӂȎ��𐋂����l����������B�����̐l�������܂Ƃ߂Ė������ꂽ�̂ŁA�݂�Ȃ܂Ƃ߂āu�p��v�Ƃ������Ƃ͎��Ԃɂ���Ȃ��B���̂��Ƃ��w�p��̍s���x�Ŗ��炩�ɂ��悤�Ƃ����B
�u�����v�̑���
�@�V���̌P�����Ԃ̍����u�����v�ƌĂсA�����P�O�N���܂ő��݂����B�U����ԁA�K�������^���Ȃ��A���������ŋ���ɓ������B�������m�̏o�g�̑啔�����_���ł���A�������ɌC���x������邪�A�͂�����Ă��Ȃ��̂ō������B�������m���Ȃ̂Ŋ���Ȃ������B���b�p�Ŏ��Ԃ��m�炳��邱�ƁA�ꎅ���ꂸ�s�����邱�ƂȂǁA����Ȃ������ɃX�g���X�����܂�K���ł��Ȃ���҂����������B���ʁA�a�C�ƂȂ�҂�����
�o�ċL�^�Ɏc���Ă���B�u�����v�ƕ��ɂ���l�͑��ȊO�̐l���قƂ�ǂł������B
���̐l�͎��炷���������ꂽ���A�n���̐l�͉Ƒ�����̂��������ɗ���܂łɁA�Α����ꖄ������Ă����̂ŁA�u�����v�̕悪�����������B�`���a��P�����i���j���̎��̂Ȃǁj�Ɏ��ʕs���̎����������B
�@����ŁA���ɂ���ꂽ�P�U�X��̕悪����B��c���i���E��s�k��c�j�̕�ŁA���̐펀�҂̂U�`�V���̐펀�҂𗤌R��n�Ɠ����K�i�ł������B����͖{���̉p����J����̌����������Ă���B�^�c�R�ɂ͂Q�̈قȂ�X���̕悪�������Ă���B
���쓃�Ƃ�
�@���쓃�͓��{�R���w�i�ƂȂ��Ă���ꂽ�⍜��[�߂鋐��ȃ��j�������g�ł���B���n�Ɛ�n�ɂQ��ނ���ꂽ�B���{�R���x�z�̈���g�債���O�n�ŖS���Ȃ������m�̈⍜���[�߂�ꂽ�̂���n�̒��쓃�ł���B�T�����̋���Ȓ��쓃�̒��ōő�̂��̂��n���s���̂P�O�O�����̓��ł���B���̑��͂R�O�`�T�O���قǂł���B�s�펞�ɁA�قƂ�Ǒł��ꂽ�B�C���h�l�V�A��t�B���s���ɂ��v�悳��Ă����B���쓃�Ƃ͈�̉��ł������̂��H��������́A���{�̑哌�����h���\�z�̐S�����������Ă���Ƃ����B�����ւ̐N���̋^���ᔻ���������̂ɑ��ẮA�u�����ɖ���p��Ɋ�������ł���̂��v�Ƃ����������Ŕᔻ�E�����B��O�̏C�w���s�ɎQ�������w���̊��z�ɂ́A�u���쓃�����Ċ����v�Ȃǂ�����������B
�@�P�X�R�S�N�̃K�_���J�i���̐킢�Ȍ�A�펀�҂������o���Ă���⍜���҂��Ă��Ȃ��Ȃ�A�u�⍜�͖����Ă��p��͊҂�v�Ƃ������R�Ȃ̋K�肪�ł��A���쓃�̎��Ԃ��ω������B�펀�҂̍Ȃ����́A���g�̖������������A�����_�ЂɁi�펀�҂̍��������҂�Ƃ����j�S�̂��炬�����߂闬��ƂȂ��Ă������B�s��ԍہA�R�͒��쓃�̈⍜�ɂ��āA���n�œK�X�������ׂ��Ƃ����w�����o�����B���B�ł̓\�A�R���C���̑Ώۂɂ����B�����l�͈⍜���ӂ݂��Ĕj���B�A�W�A�����m�푈�ŖS���Ȃ����펀�҂̔����̈⍜�����ǂ��Ă��Ȃ��B
����̉ۑ�
�@�\�A�R���i�����Ă����Ƃ��A���ƌ��ɂ���2�`3000�l�̓��{�R������1945�N8��22���܂œO��R�킵���B�ق��̖��B�ɂ������{�R�����{�l���������ق����炩���ē������̂Ƃ͑傫�ȈႢ�������B���̊ԂɁA�����̓��{�l�������͒E�o���邱�Ƃ��ł����B���̒��ɂ́A���k�������ɂ��������юi�A�~�����v�A���������Ȃǂ̌�ɏd�v�Ȍ����҂ƂȂ�l�X�������B���R����́A�����̂��ߒ��ƌ��܂ōs�������A�����S�������̎n�܂钣�k�܂ōs���Ȃ������B�\�A�R���Ȃ��~�߂�ꂽ�̂��A�N���o�H�̓��Ⓑ��̋��E�ɉ��}�̏�Q���̍H���������͂��ŁA���̍H���ɒ����l����S���l�����A�I����Ɍ������̂��߂ɎE�Q�����̂ł͂Ȃ����H���{�R�̓O��R��Ƌ������̒E�o�����k�Ƃ��ē`�����钆�ŁA���̂悤�Ȏ������������̂ł͂Ȃ����Ƃ����^
��������A���R����͂��̂��Ƃ̒������ł��Ȃ��������Ƃ�S�c��Ƃ��Ă���B
���^�E����
�@���⍜����ʂɂ��ǂ������Ɋe�n�ɒ��쓃������\�z���������B���֑�ł͍Z���̒��쓃�̈⍜���⑰�ɕԂ������A���̍��Ղ��c���Ȃ��悤�ɂ����B�����L�n�̒�����ɑ��Ăf�g�p�͂ǂ̂悤�ɑΉ������̂��H�f�g�p�͈⍜���J���Ă���ꍇ�͏@���I�Ӗ���F�߂��B�e�n��ɂ��Ή����قȂ����B���M���R�̒��쓃�͂ǂ����H�M���R�͈�s�꒬���̂��̂Ƃ��Ă̈ʒu�Â������ꂽ�B�⍜���������B���⍜���Ԃ���Ȃ����Ƃ����������ꂽ�w�i�ɂ́A���{�l�̎����ρA�썰�̊ϔO���������̂ł͂Ȃ����B���펀�҂̈�̂�O��I�ɖ{���ɕԊ҂����A�����J�̎Љ�ɂ͐l�Ԃ̑����A�l���d���閯���`�̊��o������A���{�̎Љ�ɂ͐l���A�����`�̊��o���ォ�������Ƃ��⍜���Ԃ���Ȃ����̔w�i�ɂ���Ǝv���B�@ �i�����ʂ̓s���ł��ׂĂ̔������f�ڂł��Ȃ��������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B�j
2������ �@�����@�M����i����j �@�u���d�H�Ɛ�B�H��ւ̋Ɩ����Ɏn�܂������w�̎��Ɓ|�c�����ꂳ��i���c���Y�j�̏،�����v
��҂ɓ`����펞���̋L��
�@���{���S�����͑��̍œ�[�̒��ł���B���p�ɖʂ��ċ���ȑO����~����������j�n��ł���B�펞�������ɂ́A���d�H�Ɛ�B�H��i���E�V���{�H�@�j������A�C�h�͂Ȃǂ̕��킪�����Ă����B�H��ɂ͋����A�s�ȂǂŔ�������A��Ă���ꂽ���N�l�J���҂ƋΘJ�����œ�������钆�w�������������B1945�N�̔s��ԍہA�R���H��̂��邱�̒n��ɂ͘A���R�̋�����Ɍ������Ȃ��Ă����B
�@��������́A�����Łu�n���m�v�Ƃ����m���o�c���Ă��邪�A�u�l�C�`���[�g���C���v�Ƃ������w����ΏۂƂ�����O�t�B�[
���h���[�N�̊w�K���s���Ă���B�����w�Z�Ɛ[���n�敟���ψ���̋��ÂŁA���a���n�w�K���s�����B�w�K�e�[�}�́A�@�ΘJ�����ɂ���l�̎��A�A�R���H��ł͂��܂������w�̎��ƁA�B��8��15���̂R�ł������B
�P�C�ΘJ�����ɂ���l�̎�
�@�[���n��̋������w�����A1944�N7��15��������d�H�Ɛ�B�H��ɋΘJ�������ꂽ�B���ɂ́A�w�͗D�G�œ�����ւ̊C�R���w�Z�◤�R���w�Z�Ɋw�Z���\���đ̌����w����悤�Ȋw���������B�ݘa�c���w�Z���Łu�������v�ƌĂꂽ�w���́A���̂悤�ȗD�G�Ȋw���̈�l���������e�ł��̂悤�ȉΉԂ̎U��댯�ŏd�J���̍�Ƃɏ]�����邤���ɉߘJ�ŔM���ǂƂȂ莀�S����Ƃ������Ƃ��N�������B
�@������l�A�����ݘa�c���w�Z���Łu���J�v�Ƃ����w���͎t�͊w�Z�ɓ��w�����܂��Ă����ɂ�������炸�A6���ɉ������ꂽ�ΘJ�����ɏ]��������ꂽ�B�ނ́A�H����̓d�����ނ��o���ɂȂ�����������Ă��Ċ��d���S���Ȃ����B�����ݘa�c���w�Z�̎R��������C�i�̂��Ɋݘa�c���Z�Z���ƂȂ�j�́A��l�̎����}�����������邱�Ƃ����ہA���ȐӔC�̎��Ƃ��ꌩ�������o�Ȃ������B���A���_�̋@������������R���Z���͔F�߂Ȃ������B�������A��������̖�����1999�N�Ɋݘa�c���Z�ɓ��w�������A�S�C�����R�ĕv�搶�������i�{���̗��ɏo�ȁj�B������̎����Ɋւ��郌�|�[�g���������R�搶�̂��ƂŊݘa�c���Z100�N�j�ɓ�l�̎����������߂��A�����L�^�ƂȂ����B����ɕ{���ς������đ�����ɂ��鋳�瓃�ɓ�l�͍������ꂽ�B
�Q�C�R���H��ł͂��܂������w�̎���
�@�����A���d�H�Ɛ�B�H��ɂ͑����̒��N�l�J���҂Ɗݘa�c���w�Z����ΘJ������
�ꂽ�����ݘa�c���w�Z���������Ă����i�����N�l�̐��m�Ȑ��͂킩��Ȃ��B���S����O�Z�Z�Z���܂ŏ�������B�����A�s�A�����ł̒��p�Ȃǂ��܂��܂Ȍo�H�ŘJ���ɏ]��������ꂽ���̂ƍl������j�B���c���Y�̔o�D�c�����ꂳ��́A���e�����H�꒷�ŁA���g�͊ݘa�c���w�Z���Ƃ��ċΘJ�����œ����Ă����B
�@1945�N6��������A��������悤�ɂȂ蕺�퐶�Y�̕��i�����Ȃ��Ȃ��Ă��āA�H��̉ғ����Ԃ�����q�}�����Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă�������A������Ƃ����R�O���炢�̒��N�l�J���҂������ē��Ă����l�����A���w�������Ɂu�N�����A�{���͒��w�ŕ����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ɂ���ȏ��ł��������Ȃ��ˁB�i�w���l���Ă���낤�B�l�����w�������Ă������v�Ɛ��������Ă����B�ނ́A����������̑��Ɛ��������B���H�꒷�̕����^���A�Ђ����ɂT���قǂ̃O���[�v�ɂ����Ƃ��n�܂����B�����͐��}���ŊO����͌����Ȃ��B���̐^�Ɏ��������ċ�����͊F�Ɋw���������B�x�z����Ă��钩�N�l���x�z�҂ł�����{�l�̃G���[�g�\���R�̎�҂ɐ펞���̍H����Ŗ����ɍ������w��������Ƃ����������蓾�Ȃ����Ƃ��N�������̂��B
�@���̘b�́A�������c������ɒ��ڎ莆�������A�c������11���̕�ⳂɒB�M�̕Ԏ����͂����B���̎莆�Ƃ̂��ɒ����������܂œc�������K�˂ĕ��������������e�����Ƃɂ��Ă���B
�@���������Е��������������Ƃ��������B�����A�H����Œ��N�l���m�̃P���J���~�߂��ɖق��Č��Ă����̂ŁA�c�����u�Ȃ��~�߂Ȃ��́v�Ɛq�˂��Ƃ��A�����u�ނ�͂��̂悤�ɂ��ĕ����Ă���v�Ɠ������Ƃ����̂��B���̂Ƃ��A�c������͋�������u�������l���v�Ǝv�����Ƃ����B��������͓c������ɁA������̌��t�̐^�ӂƂȂ��������w���ɐ��w���������̂��ɂ��Đq�˂��������B�c������͓����������̋i���X�u�c���v�ŁA�o�D�̐��ʂ���傫�Ȑ��Ō���Ă��ꂽ�B
�@�c������́A������́A���ʂ���Ă��铯���̐l�Ԃ����ʂ��鑤�̓��{�l�Ɂu�ނ�͕����Ă���v�ƌ��������t�ɂ́A�ނ�ւ̎v����肪���߂��Ă���Ƃ����B
�u���𒆓r�Ŏ~�߂�����s�������Ƃ���܂ōs���āA�������肵�ē��{�ł̐������A�����������z������@��̂Ŋw���������v�Ƃ����ӂ��ɋ�����͍l�����̂ł͂Ȃ����Ɠc������͂̂��ɐ������Ă���B�܂��A�c�����u�Ȃ������~�߂Ȃ��v�ƕ������w�i�ɂ́A�c������̕�e�������A�u���N�l�������߂Ă͂����Ȃ��v�Ƃ悭�����Ă������Ƃ�����B�c������̌Z�����T���[���X�ŃN���[�j���O�X���o�c���Ă��āA�c��������p�����������Ǝv���A�a�J�̌�w�w�Z�����w���ɍs�����Ƃ������Ƃ��������B��e�́A���̂Ƃ��㋞���邱�Ƃɔ������Ƃ����B����́A�]��فi���쌧�j������ׂ��Ă���̂Œ��N�l�Ƃ܂������邱�Ƃ����ꂽ���߂Ƃ����B
����́A�֓���k�Ў��ɒ��N�l���s�E���ꂽ�����ɑ���������̎Ⴂ�Ƃ��̑̌��ɂ��ƂÂ��Ă���B�����āA������ɁA�u�����~�߂�v�Ƃ߂����{�l���w���ɐl�ԓI�ȐS��F�߂�������́A���̎q�ǂ������ɐ��w�������Ă�낤�Ƃ����C�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B
�R�C��8��15��
�@1945�N7��25������đ�38�@�������Ɖp��37�@�������͍̊ڋ@���������U���A28�����S���Ȃ����i���ʐ^�j�B28���͐[������ɍU������A�Q�l���S���Ȃ�A��l�͒��N�l�Ő���ŖS���Ȃ����B���͂�B29���}��������{�̐퓬�@�͖����A���s���Ƃ������đ��v�Ǝv���Ă������ސ삪���ƂȂ����B
�@ �@�c������́A�����Ƌ@�e�|�˂̒� ��K���œ����āA�Б�ɂ��ǂ�� �ƁA��ő��q�̊�����Ċ��삵�Ă����ƑΖʂ����B
�@8��15���̓V�c�̃|�c�_���錾����̃��W�I�����̌�A�C�R�̓��U���u�C�����v�̒��т��H��ɂ���Ă��āA�����̃J�M��n���Ɠ��{�����Ĕ������B���H�꒷�̕��́A�u�厖�Ȗ��ʂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v�ƌ����ăJ�M��n���Ȃ������B��ŕ����ƁA���̒��т͖ѕz��ʋl�܂ł������o���ē����o���Ă����Ƃ����B
���^
���Җ{�@�v����
�@�u���s�ݏZ�����A�ē��C�T�I�Ƃ����l�ɁA�H��Ő��w�̎��Ƃ����ƕ��������Ƃ�����B�v
�@�u���s�̒���n��ɖa�эH�ꂪ���������A�펞���͒��N�l�̏h�ɂ������B���ސ�̍H��ɓ쑽�ސ���i���݂̓�C�d�S���ސ���j�Œʂ��Ă����B���ސ�̕ߗ����e���̒ʖ�i�������V�C�`���A���w���Ĕg�����葢�D�ɓ���ʖ�ƂȂ����j���A���BC����ƍٔ��ŗL�߂ƂȂ菈�Y���ꂽ�B�v�@
�����R�ĕv����
�@�u�ē�����͒m���Ă�B���e�͗��R�����ŁA�R���X�ւ̐ӔC�҂������B�i�ΘJ�������ꂽ���w����2���j���d�������b����ɕ����Ă����B�ݘa�c���w�ł͋ΘJ�������� ���̂ƔF�߂Ȃ������B����͌R�ɂƂ��ĕs���_�ł��莩�ȐӔC�Ƃ��ꂽ�B�������͔[�������A�R���Z���i�ݘa�c���Z����j�ɍR�c�����B�����āA�ݘa�c���Z100�N�j�̒��ɏ�����邱�ƂɂȂ�A�����̋L�^�ƂȂ������߁A�ΘJ�������̎��̂ƔF�߂��A��l�͌����Ȃ��猩�������o���B���J����͕�q�ƒ�ŁA��e���S���Ȃ����̂Ő\�����ł����A���瓃�ɍ��������B�ΘJ�����̕⏞���͂����Ԃ�̂��ɁA���R�������Ƃ��ďo��悤�ɂȂ����B�����Ȍo�R�Ŏ葱�����������A���̂Ƃ������_�Ђɍ��J���邩�ǂ����Ƃ����A���P�[�g������B���J���⏞���̏����ł͂Ȃ��B�v
�����R�@�w����
�@�u�ސE��A�i��w�@�ɒʂ��āj���a�w�̌��������Ă���B���N�l�̋����A�s�ɂ��čL���̎O�H�d�H�ł�3000���������A�s����ē�������Ă������Ƃ����B���Y���v�ہ@�h����́u�ΎR�D�n�v���㉉�����Ƃ��A�����̉�Ёi�鍑�@�ہj�ɁA����̃Z�b�g�Ɏg�p���閃�̊��s���g���b�N1�䕪�p�ӂ��Ăق����Ƃ̗v�����������B���c����10���~�A����o�ăt�����X����A���A���Y�ɒ������Ƃ�����B���̂Ƃ��̌����i2005�N�j�ɓc������i����75�j���o�����Ă����B�V�i���I��ǂ�A�鍑�����i�����̎Ж��j�͔_����ɂ߂��Ă����Ə�����Ă����B�v
���R���p������
�@�u�������w�̎��ƂŊw�����������Ƃ̈Ӗ��͏d�v�B�w�����w�̊�{�ō������w�����̓y��ƂȂ邩�炾�B���݂́A���w����̒��Ŋw��Ǝ��ɋ�����@����Ȃ��Ȃ������A�w�����p���Đ��w�𗝉����邱�Ƃ��ł���B���Z���w�ɂ����ފ�b�Ƃ��Ȃ����B�v �i�����ʂ̓s���ł��ׂĂ̔����҂̈ӌ����f�ڂł����A���l�ѐ\���グ�܂��B�j
1������ �@�G�C�~�|�E�c�W���g����i���ۃW���[�i���X�g�E�č��o�g�E���n4���j �u�V���@���ɂ݂鍑�Ǝ�`�|�����w���B�V�����u�������v�̋L���|�V������731�����x����v
���{�̖��O�̗��j��T�����铹��
�@�G�C�~�[����́A�A�����J�E���V���g���B�i���C�݁j�o�g�̓��n�S���Ńt���[�����X�̃W���[�i���X�g�ł���B���[���b�p�A�I�Z�A�j�A�A���{�ɍݏZ���Ȃ��猻��j�̗l�X�ȉۑ���A���\���Ă���B�\�c���͖������N�ɃA�����J�Ɉږ������S���\���i���N�g�Ƃ����j�̓��̈�l�ł������B���̂��߁A�A�����J�ɂ��Ȃ�����{�l�̃����^���e�C��Y��Ă͂����Ȃ��Ƃ������т����ƒ닳����Ă����B���{���Y��Ȃ����߂ɁA�Ƒ��Ƃ̉�b�͓��{��B�����Ȃ��A���͂�i���C�X�j��H�ׂ����Ă��炦�Ȃ��قǂ��т��������B����́A���Ă��g���E�}�ƂȂ�قǂ̂��Ƃ������Ƃ����B
�@���{�̖��O�̐��ɒm���Ȃ��������j��m�肽���Ƃ̎v���œ��{�ɗ��w�����B��w�Łu�����̋�v�������e�[�}�Ƃ���N���X���������B���ꂪ���n�l�̂킽�����̐S�ɋ������B��t�����̐V�{�O���[�v�̈�l�A���Ε��l�Y�̎����̋傪�Ր��ɂӂꂽ�B�₪�Ĕނ̑��ɂ����铖�����{�����Z���@�̉��@������Əo��A���������J�n����܂łɂȂ����B
�V�����Ƃ̏o�
�@�A�����J�Ɉږ��������{�l�͏@������X�̐����̉��i�悷���j�Ƃ���l�X�����������B��y�^�@�̐M�҂����|�I�ɑ����������A�܂��ɂ͓V������M����l�����������B�M�҂̗F�l�̉Ƃɍs���ƁA�u���N���A�����A�����v�̃X���[�K�������ɏ����ē\���Ă������B�u���E���݂ȌZ��v����ې[�����t�ŁA�����͋��c���R�~�L�̋����ł������B�G�C�~�[����̉Ƃ̓J�g���b�N�ł��������A���R�~�L�̌��t�͐S�ɋ����A�G�C�~�[���g�A�F�l�ɑ��āu���E���݂ȌZ��v�ƌ����قǂł������B
�@�V�����̕������āA�u���Ȃ��͂����̐l�i�M�ҁj�ł����H�v�ƕ�����A�u���قǒ��R�~�L�̗����҂͂��Ȃ��v�ƌ�������قǂ������B
���B�u�V�����v��m��
�@�������Ă���A���鎞�̒�������ċ��R�V���a�@�ɓ��@���邱�ƂɂȂ����B�����ŁA���B�́u�V�����v��m�邱�ƂɂȂ����B���B�i�������k���j�ɁA�u�����y�y�v�Ə̂��ꂽ���[�g�s�A�����݂��邽�߂ɒ��쌧�̓V�����N��𒆐S�Ƃ��閞�֊J��c�����荞�܂ꂽ�B�������A����͍��ƂƂ̂��鋤���v���W�F�N�g�����������u����v�ł���A�l�X�͖L���ȍ���������̂ƐM���Ė��B�ɓn�����̂��B��ʂ̊J��c�Ƃ̈Ⴂ�Ƃ�
�āA�u�z���̂��߂Ɂv�Ƙb����Ă����ƋL�����Ă���̂ł����B
�V�R�P����
�@1934�N11���A�n���r���x�O�̊J��n�u�V�����E�������i�ӂ邳�Ɓj�v��200���]��̊J�����������B�J��c�{���̖ړI�ł������_�Ƃł͕s�삪�����A�H�Ɠ�N�����Ă������A�j�������j�i�̋��������炦��Ƃ����̂ŊF�����悵�čs��������d�����������B���ꂪ�A�n���r������24�L���قǗ��ꂽ�u���[�i�w�C�z�|�j�v�ɂ���731�����̌����ꂾ�����B��]�҂������ꃖ���Ԋu�Ō�ւŒj����������ꊮ���܂ő������B731�����i�h�u�������j�ł́A�u�}���^�v�ƌĂꂽ�ߗ��⒆���l�������ې�Ȃǂ̂��߂Ɂi�y�X�g�ۂɊ�����������A���̉�U������A������������悤�ȁj�c�s�Ȑl�̎��������Ă������A�V�����̐l�����͐^����m�邱�ƂȂ��A�ŏ��ɔނ�����e���錚�������݂��Ă����B3�K���āA7������8�����̌��������J���ɏ]�������B�u�}���^�v�̐l�X�́A�n���r���e�n�A���{�̎��ق̒n���Ȃǂɕ����߂��Ă������A���Ԃ�7������8�����Ɉڑ�����Ă����B�����̏C����S�����l�́i�ǂ̂����Ԃ���j�u���e���ꂽ�l�����łȂ���Ă������ƁA�����ꏊ�����邮�����Ă������ƁA�w�K�`�����A�K�`�����x�Ƃ��������������Ă����v�Ȃǂ����������B�i�V�����́j���[�_�[�̐l�����́u�G�ɑł������߂̌��������Ă���B���l��Ƒ��Ɍ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ����Ă����B�����͍����̂ŁA�V�����̐l�͋����āA���̎d���ɉ��債�Ă����B�������A���e����t���y�Y�������A���Ă��邱�Ƃ��������肵�ĉƑ��̒��ɂ͎���ɋ^�O���g�����Ă������B�틵������ɕs���ɂȂ��Ă��鎞���A�V�����̍�Ƃ��I���ɋ߂Â��Ă����B���̍��A�R�͓V�����Ɏu�蕺����悤�ɂȂ����B���W�Ƃ����������ŐN�����m�Ƃ��ĂV�R�P�������œ����悤�ɂȂ����B��20���قǂ����債�����A���̂����̂Q�l���،����Ă��ꂽ�B�܂��A�\�ɏo�邱�Ƃ��S�O�����W�҂̐�����ق��Ă��ꂽ���ƂŁA731�����ƓV�������ނ��т����Ƃ��킩���Ă����B
�V���������ł͂Ȃ����
�@����̖{�i�w���B�V�����w�������x�̋L���@�V�����Ǝ��O�ꕔ���x�j�̏o�łɂ�����
�āA���t�̈��ۗǕv�搶�A�F���g�搶����́A�u������Ă��鎑��������A�v�����菑���Ȃ����v�ƌ���ꂽ�B���B�V�����̌��݂ɂ́A���쌧�̐N��s�͂��J��c�͑������Ɏ��������B���쌧�͖��B�ɍő��̊J��c�𑗂��Ă���B�{�̏o�Ō�A���쌧�̖��֊J��L�O�قōu�������B�Q���҂͓V�����W�҂������������A�b�����тɁA
�u��������Ȃ��v�Ǝ�����ɐU��l�������B��������Ă��Ȃ��Ɗ��������A�����͐푈�͓�x�Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��邽�߂ɖ{���������B
�j�������x���O�ٔ��ŁA�q�g���[�̕��S�Q�[�����O���u�푈���N�����Ƃ��́A�����ɐ�ӂ����߂邽�߂ɋ��|��A���t���邱�Ɓv���K�v�ƌ�����悤�ɁA�V�R�P�����{�݂̌����͂́A�u�\�A�⒆���̍U��������{����邽�߂ɕK�v�Ȏ{�݁v�Ƃ������|����
��Ӎ��g�̈ӎ����R���V�����̐l�X�ɐA���t�������ʂ��B�����́A���ƂɌ}�����邩�A�R�����̑I�������Ȃ������B����͓V���������̖��ł͂Ȃ��B���Ƃ́A�����ȐM�҂̐S�𗘗p���Đ푈��731�����̂悤�Ȑl��l�Ƃ��v��Ȃ��c�s�s�ׂ�i�߂��̂��B
�@�V�����̖��́A�V�����M�҂̐l�X����������[�g�s�A���푈�ŕ��ꋎ�������Ƃ����Ȃ̂ł͂Ȃ��B��Q�҂Ƃ������Ƃ����łȂ��u���Q�̗��j�v�Ƃ��Ă��F������K�v������B�@�������Q�̈�[��S�����̂ł���A�@���̂�����Ƃ��čl���˂Ȃ�Ȃ���肾�B�ǂꂾ���̓��{�l�������l���E�߂����Ƃ��A���������悤�ȓ��{�l�ł����Ăق����Ȃ��B
���^����
�i����P�E�j���j731�����̂��镽�[�ƓV�����̋����́u�אځv�Ƃ͌����Ȃ��قǗ���Ă���̂ł͂Ȃ����H�������낪��������Ă��邪�A����ɏ،��҂̖��O���ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ����H�R���狋����������Ă���������ł͂Ȃ��̂��H
�i�����j�u�אځv�̈Ӗ��́A80���N�O�̒������k���͉����Ȃ��r��ŁA���[�͓����A�V�������牓���ɂ������Ɍ�����悤�ȓy�n�B���A�{�݂��j����ӂɏ��w�Z���ł�����l�X���Z�ނ悤�ɂȂ�V�����̒n��܂Ől�̋��Z�n�悪�g�����čr�삪�Ȃ��Ȃ��Ă����B�i��30�L���قǂ̋������j�u�אځv�Ə������̂́A�����̓y�n�̂�����Ƃ��ĕ\�������B�����̊W�҂����͂��̂悤�ɂ����Ε\�����Ă������Ƃ�
���x���������ɐq�˂Ă������A�u����͂���ł����ł��v�ƌ���ꂽ�B�i���̓���ʂ蔲���������錳�J��c�������̎v���Ɋ��Y�����j
�i�����j����͊֓��R�h�u�������̃Z�N�V�����̂V�R�P���������݂̂��L�ڂ���A�،�����������l���͑����ł͂Ȃ��̂Ŗ���ɋL�ڂ���Ă��Ȃ��B�R���ł��Ȃ������B�ߏ�ŏ��W���ꂽ���m�ő����łȂ��l�́A�Ⴆ�ΐH���̌W�Ȃǂ�����B���N���Ƃ�����̂́A�Έ�l�Y�i�����j���A�D�G�ȏ��N���n���e����O���āA���a�P�U�N�Ɉ�����̏��N����Ґ������B�ނ�͐Έ䂩���w�ł����P�`�S�N�̋�������B����������͈�����̕������Ȃ��B������`�l�����́A�i�����Łj�����n���r���ɑ����A�W���P�T���O���A�Έ䂩��A������������ׂ�Ȃƌ���ꂽ�B������́u���ׂ̈ɂ�����B�܂������͂Ȃ��Ƃ����m�M�v�����l�������������A���̌�̃����o�[�� �́i�m�M���j�Ԃ�Ă���l�������B�V�����{����W�̊w�҂ɖ]�݂������Ƃ́A���B�ł���Ă������Ƃ��A��������Ƃ����p���Łu���̎���͂܂������Ă����v�ƌ����Ăق����B�����ɑ��s���ǂ��ڂ���Ȃ��łق����B�i�ŃK�X�ŎE���ꂽ�j�q�ǂ�������Ă��郍�V�A�l�����̓����A�����Ɏ����ɂ܂Ƃ����ė���Ȃ��B
�i�،��P�E�����j1949�N���܂�ł��B���������`�吳�̍��ɒ����ɓn��A���e�Ɩ��B�Ő������Ă����B�ꂪ���O�]�t�߂ł͐ԗ��Ȃǂ����s���Ă���̂ŁA�����ɂ����玀�ʂ���ƁA�V���ɑ���Ԃ��ꂽ�B�n���r�����߂Ń`�t�X�Ȃǂ̊����ǂ����s���Ă����̂́A�u���������v�Ƃ��������Ă������A�V�R�P�����ƊW������̂��Ƃ����^�O���������B�n���r���̊X����^�����Ȑ�̌����Ԃōs�����L��������B
�i����Q�E�j���j�V�����{���́A�G�C�~�[����̖{��ɑ��A���������\���Ă���̂��H
�i�����j���҂������A�R�����g���͂�����Ă��Ȃ��B�l�b�g�ł͂��낢�댾���Ă��邪�A�ᔻ�͓������Ă��Ȃ��B�{���͓��X�ƁA�����̌������o���Ăق����B�����܂�����������ΔF�߂�B
�i�،��Q�E�����j1946�N���܂�ł��B���i1922�N���j��731�����̑����i�ꕺ���j�ł͂Ȃ��������Ǝv���B���܂�풆�̂��Ƃ�b���Ȃ��������A�u�y�X�g�ۂ̂����l�Y�~���������̂ŁA���ɂ���R�₵���v�Ƃ����b�������Ƃ�����B�����w�Z�Ő펞���̘b��e�ɕ����ė����Ƃ����h�����������Ƃ��A�֓��R�̖h�u�������i731�����̂��Ɓj�ɂ����Ƙb�����B���[��2�`3�N���āA�����A�����Ă���B�q�����̘r�͂������Ă����B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���ɂ͐�F��Ȃ������B�S���Ȃ������ɕꂪ��i�����ׂĔR�₵���B�������������Ƒ����ɂ��Ă�����Ă����悩�����Ǝv���Ă���B���ׂ������A��������ɍڂ��Ă����炱�킢�Ƃ��v���B
�i�،��R�E�j���j1993�N�ɕ��[�ɍs�����B�i�{�ݐՕ��߂ɂł����j���w�Z�������B�����A�w�Z�̋��Ɏ����ق��������B���ݍ�Ƃł��Ȃ蒷���ԓ����̂ŁA�g���b�N�������Łi��Ə]���҂��j�^�̂ł͂Ȃ����H
�i�����j�i�g���b�N�̌��́j�����w�E�ł��B�،��ł́A�V�������炠��n�_�Ŕn�Ԃ���g���b�N�ɑւ�����Ƃ����B���鏗���̏،��ł́A�����o�҂��i���[�̌��ݍ�Ƃ̂��Ɓj�ɍs���Ƃ��A�r���܂Ŕn�ԂŁA���������̓g���b�N�ōs���A���̐�̂��Ƃ�
����ׂ��Ă͂����Ȃ��ƌ���ꂽ�ƁA������Ƃ����B
�i�،��S�E����R�E�j���j�c�ꂪ�V�����̏��������Ă����B��p�ɕz���ɍs�������Ƃ�����B�J�o�����������Ă����l�����B�Łu�ّ��v�̓��ڂ����Ă����Ƃ����B�u�[�z�ƌ��e�v�Ƃ����e���r�h���}�̎�l���̃��f���Ƃ����Ă����B��p�Ƒ嗤�̊Ԃ�
�l�̌𗬂ɂ��ĕ��������B
�i����S�E�j���j�b���Ă��āA�i�������ʂ̐l���c�s�ȍs�ׂɊւ�������Ƃ́j�n���i�E�A�[�����g�̌����u���Ȉ��v�i�}�f�Ȉ��j�Ƃ������Ƃ��������B�悭�l���Ȃ��ƁA�i��X���j�������܂�Ă��܂��Ǝv���B�ق�݂����͒�R���Ă��Ȃ��̂��H�V�����ƂV�R�P�����Ƃ̍ŏ��̂Ȃ���͂ǂ��ɂ������̂��H
�i�����j�ق�݂����́A���Ɍ}�����Ȃ������_�͂��邪�A���ڍ��ɑ���d���͂��Ă��Ȃ��B�n�������̃��x���ł͗Ⴆ���s�s�Ȃǂł����낢�날�����B�u�G�z�o�̏ؐl�v�i���݂̂̓��j�͖��͂��邪�A���Ƃɑ��Ă͓��X�ƍR���Ĉ�l�����m�𑗂邱�Ƃ��Ȃ������B�V�R�P�����Ƃ̐ڐG�ɂ��ẮA�w�V�����\�N�j�x�i�����Łj�ɁA�֓��R�ɓV��������y�n1000���������肢�����������ƁA�i���Ɏ����Ɏg���l�Y�~�̎��炪�V�����̏��w�Z�Ɉϑ����ꂽ�B�s�w���B�V�����u�������v�̋L�^�x�j�B�܂��A�V�������u�V���S���v�����A����͕��[�ɒ����͂��Ȃ�������731�����Ƃ̗������������B
�Ō�Ɂ|�P���̍ۂɂ���������
�@�\�A�̎Q���A���[����̓P����731�����̏؋��B�ł��͂���ꂽ�B�V�������珵�W���ꂽ�l���̏،��ł́A
�{�݂�j�邽�߂ɔ��e�������āu�}���^�v�̐l�����̎��e����Ă����������ɓ������B���͔ނ�̉����⌌�őw���Ȃ��Ă����B���̒n���̂悤�Ȍ��i�����Ȃ��甚�j��Ƃ��s�����Ƃ����B
�i*���ʂ̓s����A���ׂĂ̎Q���҂̂�����₲�ӌ����f�ڂł��Ȃ��������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B�j