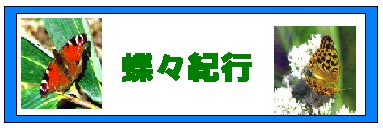




わざわざと言いたくなるようなじめじめした梅雨を選んで発生すのがミドリシジミの仲間だ。ゼフィルス(風の精)とも呼ばれ、オオミドリシジミ、アカシジミ、ウラナミアカシジミ、ミズイロオナガシジミなどが雑木林を好んで棲みかとし、ブナ科のクヌギやコナラを食樹とする。
ナミテントウ Harmoniaaxyridis Pallas:いわゆるテントウムシのことであり、遺伝子の表現型が翅の紋様に現れるため色彩と紋様が変化に富む。新座市 左よりApr 26 1996、May 25 1996、May 23 1996、Oct 21 1995、Jun 22 1996
ムラサキケマンで吸蜜するツマキチョウ(雄):雄の前翅先端が橙色なのでツマキチョウと呼ばれる。さいたま市秋ヶ瀬公園 Apr 26 1997
ナズナで吸蜜するツマキチョウ(雌)Anthocharis scolymus:毛呂山町May 3 1996
by Toshio HIRAI
11月に入るとウラギンシジミは越冬に入る。雑木林も冬支度をはじめ、落葉が林床を覆う。エノキの落葉を探ってみると、越冬に入ったゴマダラチョウの4齢幼虫が観察される。
成虫越冬態のキタテハに比べると、決まった越冬態をもたないヒメアカタテハは耐寒性が弱く、余りに厳しい冬は乗り切ることができない。オオイヌノフグリが水色の可憐な花を咲かせる1月下旬、早春の暖かな日差しに誘われて日光浴を楽しむヒメアカタテハに出会うと、何とはなしにほっとする(了)。
アカタテハVanessa indica:ヒメアカタテハに似るが属も生態も異なる。東京都高尾山 Sep 20 1997
秋桜(コスモス)は日本の自生種と思っている人もいるようだが、メキシコ原産の外来種である。キク科の一年草で、草原、公園から庭先まで至るところで見かけるようになった。さすがに外来種は逞しく、武蔵野の平野では10月末頃まで開花している。



クヌギの樹液を舐めるオオムラサキ(雌)Sasakia charondaとカブトムシ(雌)Allomyrina dichotoma:東松山森林公園 Aug 15 1995

梅雨が明けると途端に暑い夏となる。待ってましたと虫たちが雑木林に群れる。クヌギやコナラの樹液は数多の昆虫のレストランだ。客たちは必ずしもマナーがよいわけではない。蝶とて例外ではなく、結構気が荒い。キタテハは翅を目いっぱい広げてカナブンを威嚇する。ルリタテハの雄はテリトリーを作って他の雄を寄せつけない。

ミドリシジミ属の雌の前翅表面にある紋様も、多くの種で変異が表現型として現れている。橙色紋を持つA型、青色紋のB型、橙色と青色の2色紋を持つAB型、そして無紋のO型の4種があり、種類や発生場所で出現の比率が異なる。
後編に続く

そんななかで、ミドリシジミ(Neozephyrus japonicus)だけはカバノキ科のハンノキを食樹とする。ハンノキは湿性を好み、湿地や湧水地に自生し、防風林として田圃の畦にも植えられていた。しかし特に戦後、宅地開発などで湿地が干拓されハンノキ林は年を追って減少した。勢いミドリシジミの生息も孤立するようになり、1996年『さいたまレッドデータブック 動物編』に稀少種として掲載された。


アカシジミ Japonica lutea新座市 Jun 21 2003
オオミドリシジミ Favonius orientalis嵐山町 Jun 4 2004

春というよりは初夏を代表するウスバシロチョウもこの辺りで観ることができる。幼虫の食餌植物であるケシ科のムラサキケマンが生育するウメ林やクリ林を好んでゆったりと飛翔し、林縁のハルジョオンやタンポポで吸蜜する。シロチョウと名がついているが別名をウスバアゲハといい、アゲハチョウの仲間である。『春の女神』とも言われているギフチョウと近縁で、共にウスバシロチョウ亜科に属する。透きとおった翅が特徴で、日本では、北海道に生息するウスバキチョウやヒメウスバシロチョウと同じ仲間だ。初夏、林床の枯木や枯草に産みつけられた卵はその年幼虫体を形成するが、そのまま越冬し翌年の春を待って孵化する。ウメ林やクリ林を好むのは、真夏の高温から卵を守るためでもあると考えられている。
ウスバシロチョウが観られなくなると、武蔵野は間もなく雨季を迎える。

「武蔵野蝶暦」を読まれる前に:
一部を除いて筆者が1990年代に観察した記録である。残念ながら、現在(2019)では、絶滅したか、あるいは個体数が激減した地域も散見される。この20〜30年の間に、地球温暖化や開発による自然破壊等により、蝶の世界でも在来種の激減や亜熱帯・暖帯に生息する蝶の北上、さらには外来種の侵襲等により、武蔵野の蝶の生息状況は急激に変化しているようである。
越冬に入ったウラギンシジミ(左)とゴマダラチョウの4齢幼虫:さいたま市秋ヶ瀬公園 共にNov 25 1995
ウラギンシジミCuretis acuta:(左)ベンチに止まって翅を広げる雄。翅表の斑紋は鮮やかな赤。東松山森林公園 Oct 9 1995、(右)翅を広げて日光浴をしている雌。翅表の斑紋は薄い空色。さいたま市秋ヶ瀬公園 Oct 21 1995
林縁に繁茂するクズのマント群落を飛び交うウラギンシジミも、10月に入ると個体数が増加する。東松山の森林公園で雄のウラギンシジミを追いかけたことがある。占有行動をとっていたためか飛翔がすばやく、どうしても身近に観察することができなかった。諦めてベンチで弁当を広げたら、何時の間にか馴れ馴れしく寄ってきた。鶏の唐揚やソーセージの匂いに引かれたようだ。食事が終わっても暫くベンチから離れなかった。ウラギンシジミは訪花吸蜜の習性が殆どなく、カキ、イチジクなどの腐果、小動物の死体や鳥の糞、アブラムシやカイガラムシの分泌物を摂取する。
雌は雄ほど敏捷ではなく、葉上で休んでいる様子を容易に観察することができる。

ミツバチ、モンキチョウ、イチモンジセセリなどに混ざってヒメアカタテハが吸蜜に訪れる。特に橙色のキバナコスモスを好み、秋の深まりと共に個体数が増す。雌雄の交尾器の形態からアカタテハとは区別されている。アカタテハは成虫越冬態だが、ヒメアカタテハは決まった越冬態をもたず、条件がよければ何度でも羽化する。武蔵野では成虫ないし若齢幼虫で越冬するようだ。

キバナコスモスにはいろいろな蝶が吸蜜に訪れる (新座市):(左)モンシロチョウPieris rapae Sep 21 2000、(右)モンキチョウColias erate Sep 25 2000。
ヤブガラシで吸蜜するアオスジアゲハGraphium sarpedon:さいたま市秋ヶ瀬公園 Aug 18 1997
Camphor
ルリタテハ(雄)Kaniska canace:雄は占有行動をとるため単独行動が多い。新座市 Aug. 16 1996

林縁の叢で翅を広げて日光浴を楽しむミドリシジミ(雌 AB型):さいたま市秋ヶ瀬公園 Jun 21 1998
ところで、昆虫にも地域による個体差あり、日本中至るところでみられるベニシジミにしても、東京と大阪では異なった遺伝子を受け継いでいる。さらに、同じ地域でも結構変異が激しい。一見判りにくいが、このような変異が表現型として翅の紋様などに現れると、成る程と納得できる。日本ではナミテントウがその代表だろう。黄色地に細かい黒斑点があるもの、黒地に大きな赤い紋様があるものなど実に様々だ。
ハンノキの葉上でひと休みするミドリシジミ Neozephyrus Japonicus:通常は翅を立てて止まる習性がある。さいたま市秋ヶ瀬公園 Jun 22 1996

荒川中流域に広がる秋ヶ瀬公園には、今では稀少になったハンノキの群生地が残っている。
梅雨のなか休みにハンノキ林を訪れると、木漏れ日の中を忙しく飛び交うミドリシジミを観ることができる。雄は夕方テリトリーを作って活発に飛びまわる習性がある。ミドリシジミという名の由来は、多くの種で雄の翅表面が緑の金属光沢に輝いているからだが、そのような種の雄は気が荒く、雄同士で激しく追いかけあう。
雄も雌も時折ハンノキの葉でひと休みするが、翅を立てて止まることが多く、翅表面を写真に撮ることはかなり困難だ。ところが日光欲を楽しんでいる午前10時半過ぎにハンノキの林縁で待っていると、時折叢に降りてきて日向ぼっこをするものがいる。大概翅を開いてじっとしているので、ゆっくり観察することができる。
ミズイロオナガシジミ Antigius attilia さいたま市秋ヶ瀬公園 Jun 1 2002
ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata嵐山町 Jun 4 2004


カントウタンポポで吸蜜するウスバシロチョウParnassium glacialis:毛呂山町 May 3 1996


しかし、戦後の急激な宅地開発と近代農業の普及によって首都圏から次第に雑木林や田圃が失われ、今では奥武蔵や秩父にまで足を運ばないとなかなか自然豊かな里山にであえなくなった。
鎌北湖から東武越生線の東毛呂駅に抜ける里山は、今でも長閑な田園風景を楽しませてくれる。ゴールデンウイーク、林縁の田畑や畦には菜の花、ゲンゲ、タンポポ、ノゲシ、ハルジョオン、ナズナ、シロツメクサ、ミドリハコベ、カタバミなどの山野草が咲き競い、蜜を求めてハチやアブ、ハナムグリの仲間が群れている。
そんななかに『春の妖精』を観ることができる。林縁の日当たりのよい小道を小刻みに飛翔しながら時折タンポポやナズナで吸蜜しているのは、ツマキチョウだ。この日は運良く雌をシャッターに撮らえることができたが、なかなかこんなチャンスは巡ってこない。特に雄は忙しく、後追いしていてはまずシャッターチャンスは訪れない。ツマキチョウをよく観察していると、いくつかの花の間を何度となく巡りながら吸蜜しているのに気付く。そこで予め吸蜜しそうな花の前で待っていれば、かなりの確率で撮らえることができる。
イチモンジチョウLimenitis camilla:サカハチチョウ(夏型)と紋様が似ているが、生態も属も異なる。東松山森林公園 Jul 27 1998
リュックサックに止まったサカハチチョウ(夏型):逆八の字が鮮やか。汗の臭いに誘われたのだろう。武蔵横手 Jun 17 1995
セイヨウタンポポで吸蜜するサカハチチョウ(春型)Araschnia burejana:馴れなれしく簡単に手に止まる。武蔵横手 May 3 1996.


春、西武秩父線武蔵横手駅で下車、渓流沿いに谷間の道を五常の滝に向かって散策していくと、オレンジ色に映える小型のタテハチョウにあえる。クサイチゴ、ミズキ、ガマズミ、タンポポなど白や黄色の花を好んで忙しく吸蜜するかと思えば、雄は文鳥のように、手に止まって美しい翅を広げる馴れなれしさをみせることもある。何ということはない。汗に含まれるミネラルが目当てなのだ。斑紋が逆さ八の字なのでサカハチチョウと呼ばれるが、あまりそうは見えない。しかし6月から7月にかけて再びここを訪れると、成る程と頷ける。イチモンジチョウの仲間と見間違えるような鮮やかな逆八の字が浮き上がっている。年2回発生し、春型と夏型で大きく翅の模様が異なる日本では珍しいタイプの蝶だ。幼生期や成体の形態からヒオドシチョウ亜科、アカマダラ属に数えられる。年1回、春に束の間発生する昆虫は『春の妖精spring ephemeral』と呼ばれる。春型のサカハチチョウは、この仲間に入れたいほど可憐な蝶だ。
キバナコスモスで吸蜜するヒメアカタテハCynthia cardui:新座市 Sep 21 2000
『蓼食う虫も好きずき』というが、そんなクスノキを食樹にしている蝶がいる。アオスジアゲハである。昨今多くの蝶で個体数や生息地の減少が深刻となっているなか、都会型の蝶として数を増やしている。クスノキの毒を克服したことが今になって幸いしたようだ。動作が機敏で森や竹林の高いところをすばやく飛翔する習性がある。雨上がりの水溜りで吸水しているときなどでないと、なかなか観察が難しい。子供の頃、捕虫の困難な虫ベストテンに入っていた。
クヌギでひと休みするゴマダラチョウHestina japonica:さいたま市秋ヶ瀬公園 Sep 2 1995
一時、アメリカハナミズキが公園の植樹として持て囃されたことがあった。米国ではドッグウッドと呼ばれ、樹皮がイヌの虫下しになるそうだ。そういえば、あまり虫が集らない。桜と交換に米国から贈られたという話題性や花が綺麗なことと合わせて人気が高まったようだが、落葉樹のため落葉掃きが面倒でいつしか人気が落ちた・・・ようだ。
変わって好評を得たのがクスノキだ。毛虫の害が少なく、常緑広葉樹のためまとまった落葉掃きもいらない。クスノキの葉には樟脳の原料となる揮発性テルペンのカンファーが含まれ、虫の食害から身を護っている。ある種のアレロパシー(他感作用)である。カンファーをヒトに投与すると嘔気、嘔吐、眩暈、精神錯乱、痙攣などを引き起こし、重篤になると昏睡から呼吸困難に陥り死に至ることもある。
農家の屋敷林や鎮守の森に、恰も歴史を語るかのように生えている大きくて立派なクスノキ。今ではあちらこちらの公園で当たり前に観ることができる。
静かな光景にであうこともある。8月も半ばの昼近く、東松山の森林公園を散策していたときのことだ。林道から5メートル程池に向かった斜面林のクヌギに、雌のオオムラサキと、同じく雌のカブトムシが向かいあって樹液を舐めていた。仲良くひっそりと休んでいるふうであった。共に産卵という大役を終えた夏の森の王者が余命を穏やかに過ごしているのかも、などと想像していると、蝉の啼声が急に静かに聞こえるから不思議だ。
オオムラサキと生態がよく似た仲間にゴマダラチョウがいる。翅の紋様はオオムラサキがカラーならゴマダラチョウはモノクロといったところか。幼虫は共にエノキを食餌植物とする。エノキはハンノキ程ではないが湿った土壌を好み、斜面林の裾などによく自生する。幼虫はエノキの落葉に潜って越冬するので、落葉掃きがあると生きていけない。生活史の違いといえばオオムラサキは年1回夏に発生するが、ゴマダラチョウは年2回から3回羽化する。もう一つ、棲み分けとまではいえないが、オオムラサキが低地の山里を好むのに対し、ゴマダラチョウは平地の雑木林にも生息する。
クヌギの樹液に集まったキタテハPolygona c-aureumとカナブンTorynorrhina japonica Hope:キタテハは翅を広げてカナブンを威嚇している。新座市 Aug 3 1998

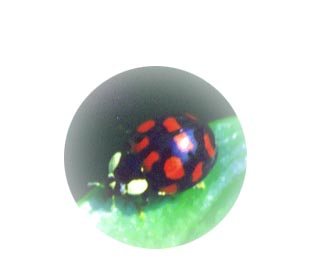
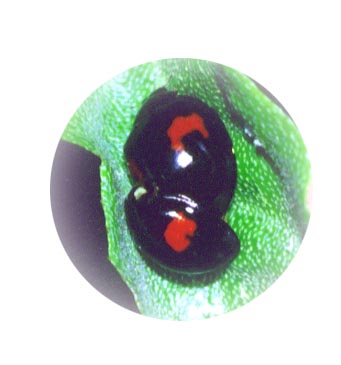
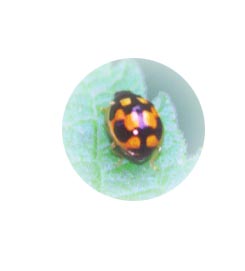

武蔵野蝶暦 前編
そんなアオスジアゲハが身近に感じられるのも、ヤブガラシが開花する暑い夏である。ヤブガラシはブドウ科の多年草で生長がはやく、他の植物を覆い尽くして枯らすこともある。別名ビンボウカズラと呼ばれる所以だ。昨今雑木林の管理が行き届かなくなったせいか、林縁の樹木にからまって繁茂している光景によくであう。ナミアゲハ、トックリバチ、ジガバチ、マメコガネ、コアオハナムグリなど多くの昆虫が吸蜜に訪れるが、アオスジアゲハもヤブガラシが大好物だ。個体数が増えたためか、はたまたヤブガラシが勢力を拡大しているせいか、吸蜜しているアオスジアゲハをよく見かけるようになった。そういえば何となく樟脳臭いような・・・。