 | 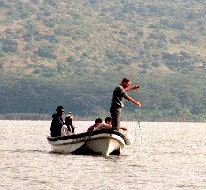 |  |
| Dr. Phil Hickley, Principal Investigater. | Volunteers were setting traps for catching fish. | The moment when a fish eagle capturing a fish. |
このプロジェクトは、アースウォッチとしては12年目、研究自体は16年目と歴史があり、基本的にはナイバシャ湖の水位変動が周囲の自然環境に与える影響を調査するというものですが、各研究者がいろんなことを行なっています。そしてボランティアは4組に分かれ、4日間ずつ3つの研究のお手伝いをしました。
研究者と研究の内容を紹介をしましょう。 まず、主任研究者のフィル、この人は魚が主な調査対象。朝食前に湖へでて漁用の網をセット。約2時間後に網を回収し、別の網をセット。これの繰り返し。そして、網にかかった魚とザリガニを外すのですが、これがとても根気がいる。とにかくザリガニがたくさん網にかかる。1回で約50〜60匹ぐらい。魚はティラピアとブラックバス。網は、メッシュサイズがいろいろ変えてあって、どのメッシュにどの魚がかかったか仕分けを行う。そして体重,体長を測り、ブラックバスは胃袋を調べる。胃袋から小さいザリガニが13匹もでてきたこともありました。ザリガニの子は水生植物の根を食べて成長し、それらはブラックバスに食べられる。ブラックバスは湖のほとりにすんでいるフィッシュイーグルの餌食になる。このイーグルはこの地域のトッププレデターの一つで、周囲の環境変化にとても敏感な生物だそうで、これも研究対象になっていて、イーグルの生息数調査も行います。
 | 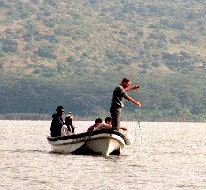 |  |
| Dr. Phil Hickley, Principal Investigater. | Volunteers were setting traps for catching fish. | The moment when a fish eagle capturing a fish. |
クリス。この人は湖の水生植物及びザリガニが研究対象。調査活動の大半の時間をボート上で過ごしました。湖のいろんな場所で水生植物を採取したり写真を撮ったり。これらの場所はきちんときめられており、毎年同じ場所で行われる。車のナビゲーションシステムのようなもので、衛星をつかって場所を特定。そしてここでもザリガニ。針金でつくったかごを6〜7個準備し、餌をセット。そして順番に湖中に投げ入れ、きっちり10分後に引き上げて何匹捕獲したかカウントし、性別も識別する。1度に約40匹のザリガニがとれたりする。ボートで草の生い茂ったところに突撃してかごをセットするような場所もあり、気分はインディ・ジョーンズ。しかし、とにかくザリガニが多く、私はフィル,クリスのチームを続けてやったため、毎日毎日ザリガニばっかり。一体アフリカまできてなにをしにかたのかと思った事もありました。ザリガニの繁殖力はおそろしいもので、10数年前に放され、いまではそこら中にいます。ちなみにとったザリガニは台所へ行き調理されて私たちの胃袋へ。実際とてもおいしいかった。
 |  |  |
| Mr. Chris Adams (Right), One of investigaters | Floating plants at Lake Naivasha | Traps for catching crayfish |
 |
| Hell's Gate National Park |
最後にジョー、この人は湖に発生するハエが調査対象です。私はこの人のチームには加わらなかったので内容はよく知りません。実験棟にこもっていたことが多かったです。
日程は、初日は移動、2日目はオリエンテーションとしてナイバシャ湖畔をハイキング。ここでいきなりキリンに遭遇してびっくり。NPでもなんでもないところ。最初ということもあり、このキリンが一番印象に残っています。まるでスローモーションでも見ているように走って行った。3日目から実作業に入り、4日働いて1日休みというローテーション。
 |
| The hill where we hiked. We happened to see a giraff. Elsamere is beyond the lake. |
ナイバシャでの生活は忘れがたいものです。毎日3時すぎにはティータイムがあってケーキが食べ放題。毎日の食事もうまいし、日本よりはるかにいい生活です。庭には白黒の毛皮をもった美しいコロバスモンキーの群れが遊びにきます。夜になるとカバが庭の草を食べにきます。地元の人はカバをとても恐れていて、実際、毎年何人もの人が亡くなるそうです。カバは、水にはいれば安全と思っているとのこと。だからカバが陸に上がっているときに、カバと岸の間に人が立つと、カバは帰りを邪魔されるものと思いパニックになって襲ってくるそうです。
このプロジェクトに参加して、ケニアの自然と人との関わりの一端をみれたような気がします。この研究自体、長いスパンで行われているもので、そこの2週間というのは、ほんの一瞬のことだと思うます。しかし、そういう環境に身をおいて実際に自然環境が影響をうけている現場をみるというのは、環境保護というものを考えるとき、この体験はすごく有意義なものになると思います。ケニアの人々は、経済的には貧しいかもしれませんが、精神的にはすごく豊かであり、エネルギーに満ち溢れて生きているような気がします。そんなケニアが、ケニア人が大好きになり、また、他のアフリカ諸国もみてみたいと思っています。