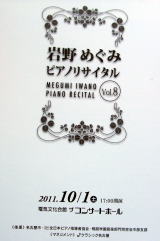平成23年10月21日(金)展覧会
今日は、生徒達が来る前に、展覧会へ。
母が書いた「少年老い易く学成り難し」の書道と、父の写真が賞に選ばれたので、見に行きました。

私がピアノを毎日練習するみたいに、母が展覧会に出すための書をいつも書いているのを見て、書道もピアノと同じように体力勝負だから、年をとると大変だわー!とハーハー言って練習していました。
何回書いても気に入らないのは私のピアノ演奏と同じ。書けば書くほど、難しくて結局始めに書いたのが一番良い仕上がりになる、と母は言います。
何回も書いているうちに、疲れてきて魂がこもらなくなってくるのは、ピアノ演奏とまるで同じ。
しかし、母が、来年出品するときはもっと良い賞をとりたいと思うから、私の生徒達もコンクールで、何かの賞に入ると、来年はもっと上にいきたいと欲がわいてくる気持ちがよくわかるものよ。そういう欲は年をとっても同じねー(笑い)と。
↑
賞に入った母の作品。「少年老い易く学成り難し」長い掛け軸で書を書くのは呼吸をとって一気に書いていくので、ピアノ演奏みたいに息が切れるんですよ。
父の写真はライオンの写真が賞に入り、もう1点は、ドビュッシーの交響詩「海」をイメージした作品。

書にしても、写真にしてもその作品が出来上がる前の作った人の思いをあれこれ思い巡らすのが私は大好きです。
どんな作品でも、生きているなあ、魂がこもっているなあと思える作品に出会うと、胸がドキドキしてきます。
今日は生命の鼓動が感じられる作品に多く巡り合えました。なかなか時間がとれませんが、ピアノ演奏に必要不可欠なことなので、なるべく見に行こうと思っています。
平成23年10月19日(水)折り返し地点の誕生日
今日は、私の40回目の誕生日。
人生80年とすると、その半分を、生きることが出来た事に感謝すると共に、折り返し地点に来たなあと30代のときとは、違う感慨深いものがありました。
シューベルトは31歳、モーツアルトは36歳、メンデルスゾーンは38歳、ショパンは39歳他、昔の人は音楽家に限らず、寿命が短いと思いますが、40年もこの世を生きてこれて、嬉しいです。

年を重ねると何が一番よいかといえば、物事に対しての許容範囲がより広がることかなと感じます。
10代、20代の若い頃は、何に対しても、結果が、黒か白かはっきり決まらないと、イライラすることが多いと思いますが、いろんな体験を重ねるうちに、どれも正しい結果なんてないのだ、ということがわかってきます。
そして、未解決のまま、曖昧に、尻切れトンボのまま終わってしまう事は、よくある事なのだと感じられるようになってきます。
結論は、別にはっきり決めなくてもいい、というアバウトな感じ方に変化していきますね。
だから、物事に対しても、自分に対しても、他人に対しても、より寛大に、どんどん許せるようになっていき、より柔軟に、考え方の幅が広く、何事も豊かに受け入れられるようになってきます。だから、年を重ねることは、私にとって、とても嬉しいことです。
今日も、生徒の皆さんから、心のこもった、カードやお手紙、プレゼントを頂きました。有難うございます。素晴らしい生徒達に囲まれて、本当に幸せです。
40代も、少しずつ、少しずつ、生徒達と共に歩んでいけたらいいなと思っています。

平成23年10月16日(日)繰り返しは生きること、それはとても幸せな証拠
先日、生徒から、とても興味深い質問を受けました。
長いこと同じ曲を弾いていると、飽きてしまうのだけど、どうすればよいか、といった内容でした。
そういう風に思う生徒さんは沢山いると思うので、それについて書いてみようと思います。
まず、どうして、飽きるのかといえば、「いつも、同じ練習をしているからじゃないかしら?」と彼女に言いました。
ただ、ボーっと頭を使わず、ダラダラ弾いていても意味がありません。
まず、目標を定めて、弾けていないところを、徹底的に弾けるようにする、とか、暗譜出来ていない場合は、最初から、最後まで、一回も間違えずに弾けるようになるまで、繰り返す、とか、自分に目標を持つといいよ、と答えました。
そう、繰り返す、ということが、ピアノの上達の一番のポイントです。
いえ、ピアノだけではありません。英語の単語一つとっても、その日に覚えたと思っても、明日は忘れるから、又繰り返す。繰り返すという事が、学習すること、ひいては、生きることなんだよ、とも話しました。
生きる、ということは、そんなに、毎日毎日が刺激的で、キラキラ輝いていて飽きる事は何もなく・・・・なんていうことは、まずありません。
それは、おとぎばなしの世界。現実は、どんな人でも、大体毎日同じ事の繰り返しで成り立っています。
食事の用意をするのも、ああ、面倒くさいと思っても、毎日やらなければならない事ですし、会社に行く人達でも、毎日やらなければならない事、学生は学校へ行って勉強する事が仕事だから、ある意味で、それは、人間として生まれてきた以上、やらなければならない義務なのです。
それを、どういかに面白くしていくか、は、本人の気持ち次第。
そこで、いかに、クリエイテイブな考え方が出来るかどうかだと私は思います。
繰り返す時は、いやいやながら、繰り返しても、上達しません。
そこに、「愛情」がこもっていなければ、上手くなっていかないものです。
ちょっと、強めに弾いてみよう、とか、弱めに弾いてみよう、ルンルンした気持ちで弾いてみよう、とか、憂鬱な気持ち・・・・とか、色々想像しながら、研究していけば、恐らく、飽きるという事はないと思います。
しかし、同じことを繰り返せるという事は、それだけで、大変に幸せな証拠なのです。
津波にあったり、大地震にあったりしたら、ピアノも流れてしまうし、第一ピアノの練習どころではなくなってしまうのです。
同じことを繰り返せる毎日に心から、私は感謝しています。
感謝の気持ちがいつもあれば、きっと、何をしても飽きるという事はないと思います。
平成23年10月14日(金)先生の影響力
リサイタルが終わって瞬く間に2週間が過ぎました。沢山の感想を子ども達からもらってどれも本当に嬉しく読ませてもらいました。
私はどんな偉い批評家が書いた批評より、子ども達の感想が好きです。
子供はとても素直だから、取り繕うことなく、思ったままをまっすぐ書いてくれるからです。
だから、私にとって一番、手厳しい批評家でもあります。
「先生の音はピンク色の優しい音がしました。それでいて、華やか。不思議な音がする・・・・」「心を込めるという意味がわからなかったけれど、先生の演奏を聴いてわかった」どんなに小さな子供でも、私の心が子ども達の心に届いたのだなあと思うと、どんな偉い批評家から頂く言葉より嬉しい気持ちになります。
子供は親の背中を見て育つ、とよく言われますが、本当によくわかります。
私の過去を振り返っても、3人の先生方から、大きな影響を受けて育ちました。
まず始めは、6歳から、15歳までお習いしたピアノの先生は言うまでもなく、今の私のピアノ演奏を全て作って下さった、素晴らしい先生です。
この時期で、ピアノのテクニックに必要なことが全て形成されていくので、一生涯の間で、この時期にどんな先生についたかで、ほぼ、その人の音楽人生が決まるといってよいでしょう。
この時期は、第一、人生の中で、一番意欲に溢れた年齢でもあるために、私はもうこれ以上は頑張れないと思うくらい必死で、練習していました。
しかし、ピアノに熱中したあまり、人間としての感情がなくなってしまったのです。
ライバルも多く、音楽をしているというよりは、何かいつも、闘っているようなそんな感じでした。
音楽高校に入り、大学4年生までの7年間、就いた先生は、それまでの先生と全く違い、放任主義でした。
それまで、手取り足取りでして下さったのとは違い、私は右往左往してしまい、本当に困ったのもこの時期。
しかし、放任されたおかげで、音楽を自分の力でつくれるようになりました。
先生から教えて頂くのを待っているだけでは、駄目だ、何とかしないと・・・・と思い、自分の力で這い上がったのです。
この時期がなければ、今生徒達を教える事は出来なかったはずです。
しかし、この時期についた先生からは、私の事をすごく愛して下さって、中学3年までの私の乾いた、ささくれだった心をとかし、私の心を暖かく開かせてくれました。
私にこんな感情があったんだと自分でもびっくりするほどダイナミックに変化していきました。先生の家で1日の半分以上を過ごし、毎日入り浸って先生のコンチェルトの伴奏をしたり、先生の家がまるで自分の家みたいに過ごした、高校、大学時代。
「ピアノ演奏は競争なんかじゃない、真心なんだ」と言う言葉をいつも私に言われ、疲れきって冷え切っていた私の心を暖かく慰めてもらっていたのもこの時期。
言葉遣いや、電話の仕方、手紙の書き方、マナーまで、男の先生だったのですが、教えて頂きました。
上京して淋しい事も手伝って、心から甘える事が出来た、そんな先生だったかも・・・・・。
そして、3人目はウイーン留学中4年間ついた先生。この時期はもう既に私は日本の大学を卒業していますし、ある程度自分の実力も、わかっていて、冷静な気持ちで、向かい合えた先生です。
ピアノに関しては、それまでに、7年間放任されて育ったため、自分の力で音楽をつくる、研究する、が身についていたので、全く困る事はありませんでした。
それよりも、夏になると、先生がウイーンの森にハイキングに連れて行って下さったり、先生のご自宅のガーデンパーティで一緒にゲームを楽しんだりと、ピアノ以外に大事な事が一杯あるんだと気付いたのがこの時期。
競争社会の日本を離れて、初めてゆっくり、のんびりマイペースに音楽に向き合えました。
この先生は、本当に生徒に誠実に向き合って下さる先生で、私が今、生徒達に接するときの礎となっています。
恩を受けた人に返すのでなく、必要としている人に返すのがよい、と一般的によくいわれます。
生徒達が私を必要としている時期は、これまで受けた恩を生徒達に返してあげるのが一番良いと思っています。
子ども達は私のピアノ演奏だけでなく、私の全て、生き方から、まるごと見ています。
そして、影響されていきます。だから、ものすごく緊張します。
子ども達が素晴らしい大人になってくれたら、日本は益々住みやすく、素晴らしい世の中になっていくと思うから・・・・。
私達が一生懸命育てないと、結局は自分達の身に降りかかってきます。
だから、私達大人が子供たちに差し出せるものはいつでも、最高のものを与えてあげないと、という気持ちで、私自身は1人1人の子ども達に教えています。
生徒達は私の背中を見ている・・・そう思い、毎日身が引き締まる思いで生徒達と接しています。
平成23年10月6日(木)伏せ、一つ覚えるのにもこんな苦労が・・・・・
昨日、大学へ行ったら、大学の同僚の先生方も私のリサイタルの感想を下さいました。
いつも聴きにいらして下さる大先輩の先生方から、前回から又4年たち、年を重ねて味わい深い演奏になっていますね、というお言葉や、大人の方は私の演奏だけでなく、プログラムに載せた私の言葉を喜んで下さる方が多く、大変嬉しく思いました。
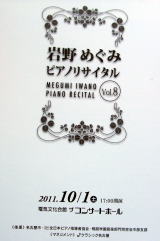
ありきたりのプログラムのご挨拶は面白くないので、今回は、かなり、こだわりを持って作ったプログラムだったからです。
普段私が考えている事を日記を書くような感覚で書きました。
「普段私が思っていること、言いたい事をそのまま代弁してくれた感じ」とおっしゃって下さる方や、「余っていたら、プログラムを下さい」とおっしゃって下さった方もいらしたので、早速差し上げました。
生徒達もレッスンノートなどに一生懸命感想を書いて来てくれてとても嬉しく思っています。
皆さんからの感想は私にとって一番の励みになります。
生徒達も勿論そうでしょうから、私は1人1人の生徒に対し、自分の思いを必ず言葉にするようにしています。
あるいは、レッスンノートにコメントを書く、とか。自分が思っていること、感じた事は、胸に収めているだけでは相手に伝わらないので、必ず、言葉にすることを私は常に心がけています。
それも、勿論、相手が聞いて前向きになれるような、嬉しい言葉を・・・・・・。
それによって、確実に生徒達は伸びますし、やる気を持って励むようになるからです。
昨日は高校のレッスンもあり、受験生達の演奏を久しぶりに聴くことが出来ました。
センター試験の願書をもう出して、全体が受験モードになってきたようで、顔つきが変わり、何より演奏がガラッと変わってきました。
見違えるように素晴らしい演奏になってきて、私は、心配しなくても、人間って本当に年とともに成長していくんだなあと、感激して帰ってきました。
成長、という面で思い出したのですが、この前、テレビで、アメリカのある方達が教育のプログラムの一つとして、犬を飼って育てていくというドキュメンタリーがあって、すごく共感しました。
そこの犬が待て、とか、伏せ、とか、色々訓練させられているのですが、その中の1匹がどうしても、伏せ、が覚えられないのです。
何回えさで導いても、伏せの意味が理解できないようなのです。
しかし、その犬を育てている方は、「何でいつまでも、覚えられないのか!」とか、「早く覚えろ!」とか、怒ったりせず、それどころか、一日の訓練の後に、「大変だっただろう?大丈夫だからな、今日は出来なかったけれど、明日はきっと出来るから、明日又頑張ろうな」とその犬を抱きしめてやるのです。
それが何日間も続き、もうだめかな、と思った時にあるとき、伏せがパッと出来るようになったのです!その方は感激して、えさを沢山与えて、「良く頑張った、えらかった、えらかった、今まで、本当に辛かったろう?」とねぎらって、身体中なでて、その犬を誉めてやるのです。
私もそれを見た時他人事ながら、やったあ!と痛く感動しました。こういう体験を通して、犬だけでなく、その方の心もその犬によって、暖められ、固く閉ざされていた心も開くようになるので、犬にとっても、その方にとっても教えられるわけですね。
これを見ていて私が毎日している生徒達のレッスンと全く重なるなあと感じました。
ある事柄がなかなか理解できない時は、愛情を持って、必ず根気強く待っていれば、相手が理解する時が来るという事を信じてあげる事こそが私の役目だと常に思っています。
犬も愛情を持って真剣に向き合ってくれる相手に対しては必ず忠実になれるのです。
人間なら、なおさらのこと。
愛情があれば、必ず、人間は大きく成長出来るのです。
私がここまで、こられたのも、言うまでもなく、皆さんからの愛情をたっぷり頂いているからこそ。
その中でも、生徒達からもらうパワーは、私にとって、一番の大きな力。
1人1人の生徒達は私の大きな宝物であり、人生の中で最も素晴らしい財産です。
平成23年10月4日(火)次の練習が始まり・・・・・。
リサイタルを終えて、2日間たち、その間に、皆さんから感想のメールやお手紙を沢山頂きました。
どれも、全部心暖まるお言葉を頂いて、心から感謝しています。皆さん、本当に有難うございました。
皆様の暖かい励ましの言葉に、疲れも吹っ飛ぶ思いがします。
しかし、今後もゆっくりとは休めず、11月に早速、コンサートが2回ほど遠隔地であり、、課題曲を全曲演奏するので、リサイタルの翌日から、その練習にとりかかっています。



ピアノの先生が対象となるでしょうから、生徒さん達にレッスンする時、どういう点に気をつけると、コンクールに入るかなど具体的にお話もとりまぜてコンサートを行うつもりです。
段々寒くなってきましたので、皆さんお身体に気をつけてくださいね。
平成23年10月2日(日)皆さん、有難うございました。
昨日、やっと、私のリサイタルが無事に終わりました。いらして頂いた、皆様には感謝の気持ちで一杯です。
又、綺麗なお花や心のこもったカード、プレゼント本当に有難うございました。
そこで、せっかく持って来てくださった方達の中には、お名前がなかったりする方もいらっしゃいます。
すると、私の口から御礼が申し上げられず、心苦しいです。
もしそういう方がいらっしゃったら教えて下さいね。
さて、リサイタル前の心境も書きましたので、今度は、リサイタル後の心境を書きます。
まず、終わった後はとても興奮するので、徹夜状態で、眠れません!可愛い生徒達の顔が1人1人鮮明に浮かんでくるからです。
リサイタルは、トラック1台分を引っ張る力がかかります。
本番の演奏同様、直前にもリハーサルで同じことをしますので、もう私の身体は2,3日間は使い物にならないように大変なことになっています。
自分の演奏に関しては、色々と反省点は数限りなくありますが、これも毎度のこと。
しかし、涙を流して聴いて下さったという生徒さん達からの暖かいお言葉を聴くと、本当に嬉しいです。
私の良い面、悪い面含めて全てまるごと愛して下さって皆さん、本当に有難うございます。
これからも、1人1人の生徒達を愛し、ピアノを愛し続けて、自分のペースで、前向きに明るく音楽に向き合っていきたいです。