


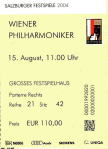
[8月15日] 音楽祭とホーエンザルツブルグ城塞、レオポルツクロン城へ
このページの後半は マーラー特集 です。
BGMとして流れているのは、マーラーの第5番、第4楽章です。これは、HomePage とっても小さなコンサート会場 より許可を得ております。著作権を侵害しないようにお願いします。なお、マーラー特集では、第1楽章、第5楽章が共に楽しめるようにリンクをはらせて頂きました。BGMを止めるときは停止ボタンをクリックして下さい。
| いよいよザルツブルグ音楽祭 マーラーの交響曲第5番を聴ける日がやってきた。ちょっと緊張気味?演奏会は午前11時開演である。それまで、時間があるので、文字が読めない人にも鉄細工の看板を掲げ、何のお店か分かるようにした Getreidegasse (ゲトライデガッセ)に行き、その足で Mozart Geburtshaus (モーツアルトの生家)に寄った。道を歩いている人の中に、演奏会に行くのか、正装をしている人がいた。早めに Grosses Festspielhaus (祝祭劇場)に着くとそこはちょっと別世界の空気が流れている。ほとんどの聴衆が着飾っている。でも、ワイシャツ姿の若者もいました。因みに、我々はジャケットを着て行きました。 | |||
| ゲトライデガッセ | モーツアルトの生家 | 別世界の空気が流れる祝祭劇場前 | 演奏会のチケット |
 |
 |
 |
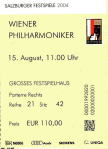 |
演奏の感想はちょっと言葉では言い表せません。感激の一言!あの印象的なトランペットで始まる第1楽章、ソナタ形式の第2楽章、スケルツオの第3楽章、「ベニスに死す」で有名なアダージェットの第4楽章、そして、終楽章。参りました。
前日の雨もきれい上がり、爽やかな天気。興奮を抑えてホテルに戻り着替えてから、レストランが集まるシュテルンブロイでバイキング形式の昼食をとりました。
その後、中世の要塞であった Festung Hohensalzburg (ホーエンザルツブルグ城塞)に行き、城の出口から市内と反対側に出てブラブラ歩きながら、レオポルツクロン城に向いました。写真でも分かりますように、この城は湖畔に面したすてきなところでした。はっきり言って穴場です。住民が釣りをしたり、ジョギングをしたり、サイクリングをしたり、家族連れで遊んでいる方もいました。そう、今日は日曜日だったのです。
 |
ホーエンザルツブルグ城塞の写真集 左:城塞に続くケーブルカー 左下:城塞 下:城塞より市内の眺め 右:城塞裏手、レオポルツクロン城への道から 右下:城塞裏手、レオポルツクロン城への道から |
 |
 |
 |
 |
| 城塞から歩き始めて1時間、一時迷子に近い状態になったが、地元住民の住宅環境?を観察しながら何とかレオポルツクロン城のある湖畔に着いた。相変わらず、地図を片手に自力でたどり着いたのである。写真左の湖畔に面する城の奥にホーヘンザルツブルグ城塞が見えますでしょうか?この湖畔でタンポポのような物が風に流され飛んでいました(写真中央)。不思議な光景でした。 | ||
 |
 |
 |
| Stadtbus で市内に戻り、市内のはずれにあるアウグスティーナ・ブロイという地元の人が多くいるビアガーデンで、ザルツブルグ最後の晩の食事を贅沢?にとりました。入り口近くのカンウターで代金を支払うと、陶製のビアジョッキが渡されます。それを手に自分でジョッキを洗い、ビールを注いでもらう完全セルフサービスのお店です。我々のテーブル近くでは、一日の仕事を終えた観光馬車の御者さんたちが、気勢を上げていました。木の下のテーブルは心地よく、最後の晩でもあり、私たちも大ジョッキを2杯空けてしまいました。ザルツブルグの食べ物で、ただひとつ心残りは、ザルツブルグノッケールというケーキが食べられなかったことです。 | ||
| マーラー特集 | BGMを止めるときはこのページの最初にあるスウィッチの停止ボタンをクリックして下さい。 このページの最初へ戻る |
|
というほど大げさなものではありません。この旅行に先立ち、そして終わってからも、マーラーのことについて色々興味を持って調べています。参考にさせて頂いた書籍類は以下のものです。内容を十分理解していないかもしれませんが、渡辺裕氏の本について感想をまとめました。また、このページの最初に書きましたように、HomePage とっても小さなコンサート会場 よりリンクをはらせて頂き、私の大好きな5番の第1楽章、第5楽章が MIDI で聴けるようにさせて頂きました。「とっても小さなコンサート会場」のサイトの趣旨、データ取り扱い事項等を遵守してください。
『文化史の中のマーラー』を読んで
この本は以下の構成で作られています。この章立てをみても分かるように、マーラーを作曲家個人としてだけで捉えていないことが分かります。私は筆者のこの姿勢にまず共感を覚えました。
第1部 同時代者の中のマーラー
第1章 花形指揮者の憂鬱 ――― 19世紀の歌劇場の状況の中で
第2章 芸術による社会革命の夢 ――― マーラーと学生運動
第3章 意識下の世界の探索 ――― マーラーとフロイト
第4章 総合芸術の館 ――― マーラーと分離派
第5章 指揮者マーラーの挑戦 ――― マーラーのベートーヴュン受容
第6章 文学世界と音楽世界の統合 ――― ピアノ版《大地の歌》に託されたもの
第7章 『ベニスに死す』とマーラー ――― マーラー、マン、ヴィスコンティ
第8章 都市の音の知覚 ――― マーラーのサウンドスケープ
第9章 都市近代化の中で ――― マーラーの生活圏を歩く
第10章 新しい音の世界へ ――― マーラーとチェンバロ
第2部 現代人の中のマーラー
第11章 マーラーとポストモダニズム ――― 芸術とキッチュのはざま
第12章 音楽の「論理」の解体 ――― 音楽の空間性
第13章 ワルター神話を越えて ――― 《第4》演奏史の分析
その第2章で筆者は次のようにのべています。
| マーラーの生きた世紀末の時代、中でもウィーンの世紀末は、今とりわけ注目を浴びているテーマの一つである。おそらくそれは、われわれが今現に生きている現代という時代とこの時代との間にある種の相似を直観的に感じとっているからであろう。共通した「時代の空気」と言ってもいいかもしれない。「時代の空気」などという言葉は、曖昧で実体がないと言っていやがる人もいるが、どんな時代にもたしかに固有の「空気」があるということを認めないわけにはいかないだろう。そしてそういう「空気」は、文学であれ、音楽であれ、絵画であれ、いやそれどころか衣食住から政治経済にいたるまで、文化のあらゆる領域に共通に浸み込んでいるのである。 こうした「空気」は決して一朝一夕にできるものではない。その源流をたどってゆくと、その種子がかなり前の時期に見出せることが少なくない。おそらく、感受性の強い若い頃の体験が人格形成に影響を及ぼし、そうした共通の体験をもつ世代の人々が後になって世の中を支えてゆく存在となるからなのだろう。ちょうど、今の日本で「大学紛争世代」の味わった社会改革の挫折感が、人々の間に政治に関するある種の無力感の「空気」を作り出しているように、そしてそういう空気が芸術や文化全体に色濃く影を落としているように、この時代の「空気」は、そこにいたる社会変動の過程と分かち難く結び付いている。 そのような観点からみてみるとき、ウィーンの世紀末の「空気」もまた、新しい色合いを帯びて見えてくる。そして、一八九七年に宮廷歌劇場指揮者という、ウィーンの音楽界を担う地位についたマーラーもまた、学生時代からウィーンの空気を吸って育ったという限りにおいて、この時代のウィーンを取り巻いていた社会状況によって生み出され、そういう「空気」を体現した存在のひとりなのである。(P22-) |
では、どんな時代であったか。筆者は続ける。
| マーラーの生きた時代のオーストリアの社会体制が確立されたのは、一九世紀半ばすぎのことである。今日のオーストリアのみならず、ハンガリー、チェコスロヴァキアも含む広大な領土を有していたオーストリア帝国にはさまざまな民族が暮らしており、ヨーロッパ全域に高まりつつあるナショナリズムの気運の中、帝国はついに絶対主義的支配原理を放棄し、民族自立を大幅に認めるなど、「自由化」路線を打ち出したのであった。その象徴とも言うべき「十月勅書」が皇帝フランツ・ヨーゼフ一世によって発布されたのは、ちょうどマーラーの生まれた一八六〇年のことであった。これがオーストリアの「近代化」の出発となった。「自由派」と呼ばれるドイツ人たちが主導権を握り、ユダヤ人解放など、さまざまな政策を実施していった。ウィーンの城壁は取り払われ、その跡にリングシュトラーセと呼ばれる環状道路が作られた。そしてその道路を中心として、市庁舎や博物館をはじめ、さまざまな公共建築が新たに建てられ、ウィーンの街は面目を一新した。(P24-) | |
| 音楽ばかりではない。造形芸術の分野では、マーラーの同時代人である画家のグスタフ・クリムトがやはり若い頃、リングシュトラーセとともに作られた美術史博物館と、新ブルク劇場とに天井画を描いている。また建築家のオットー・ワーグナーも若い頃にはリングシュトラーセを彩る華麗なアパートメントを数多く手がけている。やがて世紀末の「反逆児」となるマーラーもクリムトも、そしてワーグナーもこうして「リングシュトラーセ体制」 の空気を吸って育ったのである。(P25) |
そして、
| しかし世紀末になる頃にはこの体制はさまざまな形で矛盾を露呈することになる。「自由派」支配は決してハブスブルタ家の支配を駆逐したわけではなかったから、結局のところ、一部富裕なブルジョアが旧支配体制に接近していってそこに加わったというだけの話であった。ブルジョア内部の階層格差は広がる一方で、そういう実情に対する人々の不満は高まりはじめていた。さらにまた、さまざまな民族を抱えるこの国では民族運動という火種もそう簡単になくなりはしなかった。あちらを立てればこちらが立たずというわけで、各民族の自治が認められると、今度はゲルマン民族主義者たちが運動をはじめることになる。そういったことが積み重なった結果、世紀末には、左翼から反ユダヤ主義までさまざまな政治運動が顔をそろえることになる。これらは形こそさまざまであるが、いずれも「自由派」という旧陣営に対する新陣営の宣戦布告とみなすことができるだろう。(中略)文化に関しても同じであった。世紀末のウィーンで起こってきた芸術運動の多くは、リングシュトラーセ体制の中で育まれてきた旧弊な芸術の改革を目指す新陣営の挑戦であった。最も象徴的なのが、造形芸術家たちによって作られた「分離派」であるが、この分野に限らず、文学においても音楽においても、世紀末には旧陣営の「腐った文化」を相手にした文化戦争が大規模に展開されることになるのである。(P25- 中略 ) | |
| ここで問題にしたいのは、マーラーが学生時代を過ごした一八七〇年代にこうした世紀末の「空気」がすでに準備されていたということである。むしろこう言った方がいいかもしれない。この時代のある体験を共有した人々が後の世紀末文化を作り上げたのだと。 その「ある体験」とは、この時代に盛り上がった汎ゲルマン主義的な学生運動のことである。もちろん、世紀末ウィーンの文化の担い手たちがすべてこうした学生運動の活動家であったというわけではない。しかしながら一九六〇年代末の大学紛争が、必ずしも活動家でなかった人々の価値観にも大きな影響をもたらしたというのとまったく同じ意味で、こうした運動が当時の学生たちに及ぼした影響は大きかった。そしてまた、狭い意味の「活動家」の中にも、後のウィーンの文化の中で重要な役割を果たすことになる人々が相当数まじっていた。次章で詳しく述べるが、マーラーはそのような学生団体の一つである「ペルナーシュトルファー・サークル」の一員であった。(P26-P27) |
そして、
| 彼らの思想上のバックボーンとなったのは、ショーベンハウアー、ニーチェ、それにリヒヤルト・ワーグナーの思想であった。彼らの思想にはもちろん、それぞれに違いがあるが、それを論じるのがここでの目的ではないからここでは省略することにして、それらの共通点を探ってみると、人間の理性の背後に広がる無意識の領域に着目し、人間にとってむしろそちらのほうが本質的であることを強調しているということが挙げられる。言ってみれば彼らは、合理的に説明可能であるものこそが本質的であると考えてきた近代の啓蒙主義思想(代表的な存在が近代科学である)に対して、こうした一見明噺な「光」の部分は仮象にすぎず、世界の本質は合理的精神によっては捉えられない「闇」の部分にあるとする考え方をとる一連の思想家の系譜に属する人々なのである。 こうした思想は、自由派の政治に飽き足らない若者たちの心を捉えた。彼らは自由派の標模している「民主化」の根底にある人間の理性に対する安易な信仰の中にまやかしが存在していることを見抜いていた。彼らは自分たちの日常をおおっている表面的なまやかしの世界の背後にあるはずのものを求めようとした。そしてこうした思想をバックボーンにした新しい共同体をゲルマン民族の力によってこのオーストリアに確立することを夢見たのである。そこで重要な意味をもってきたのが、芸術、中でも音楽であった。これらの思想家は共通して、理性の捉え得ないものに触れるための唯一の手段が芸術、中でも音楽であることを主張していたからである。(P28-P29) |
|
| クリムトもマーラーも、そしておそらくはフロイトも共通に関心を抱いた、理性には捉えられない無意識の暗闇での悦楽と苦悩、世紀末ウィーンの「空気」がここには凝縮されている。彼らは皆、そういう関心を共有する「空気」の中を生きたのである。今このウィーンの世紀末が注目されているということは、そこに現代のわれわれをひきつけてやまない何かがあるということなのだろう。しかし、この素晴しい世紀末文化を育んだ同じ土壌は一歩誤ればマーラーを苦しめることになる「反ユダヤ主義」をも生み出す「危険思想」に支えられて成り立っていたということもわれわれは忘れてはならない。マーラーにせよ、クリムトにせよ、フロイトにせよ、その意味では「危険思想」の持ち主であった。(中略) それにマーラーの作品や演奏がウィーンの人々に引き起こした反感、それらは皆、こうした「危険思想」に対する「健全な人々」 の反応であったといってもよい。その意味で、マーラーの音楽が今受け入れられているとするなら、それは時代そのものが病んでいることの証しなのかもしれない。(P38-P39) |
いささか長い孫引きになってしまったが、スケールの大きい筆者の捉えかたにただ感心し、ますます、マーラーに興味が湧いてくるのである。第2章だけでこれだけの内容を持っているのであるから、この本は私にとってすばらしいし、難解であると言わざるを得ない。また、この文章を読んでいると、今我々の時代とマーラーの時代が重なり、我々はその歴史の中で生きており、我々が抱えている状況がまさに動いており、歴史の中で事象を捉えていかなければならないと感じるのです。
「空気」と言う言葉も、社会事象を考察するにつけ感じるものがあります。少し、細かいことですが、実は、あのザルツブルグ音楽祭を始めとして、最近、演奏会の「空気」に対して気になり始めていることがあります。それについて、次の「聴衆の誕生」が非常に参考になりました。
『聴衆の誕生』を読んで
私が演奏会の「空気」に対して気になり始めていることとは。
| 「演奏会」という言葉を耳にしたとき、われわれはどのような情景を思い浮かべるであろうか?雑踏を通り抜けてホールにはいると、そこには防音装置で仕切られた静寂な空間が広がっている。やがてステージに演奏家が登場すると、客席は水を打ったように静かになり、ピンと張りつめた空気の中で演奏が始まると、聴衆たちは真っ暗な客席の中で精神を集中してひたすら音楽に耳を傾ける・・・(中略) 「演奏会」という言葉を耳にしたとき、われわれはどのような情景を思い浮かべるであろうか?雑踏を通り抜けてホールにはいると、そこには防音装置で仕切られた静寂な空間が広がっている。やがてステージに演奏家が登場すると、客席は水を打ったように静かになり、ピンと張りつめた空気の中で演奏が始まると、聴衆たちは真っ暗な客席の中で精神を集中してひたすら音楽に耳を傾ける・・・(P4) |
|
| そんなことはあたりまえではないか、と言われるかもしれない。「クラシック」は芸術であって娯楽ではない。アイドル歌手の下手糞な歌であっても人気さえ出ればいい、というような世界ではないのだ! 演奏会ではわれわれは真に芸術的価値のある作品を鑑賞するという精神的な体験をするのだ。そこでわれわれが精神的な充実感を味わうことができるというのも、それだけの不朽の価値をもつ「名曲」を残した作曲家あってのことなのだ。そういう「巨匠」が尊敬されるのは至極当然のことではないか! そしてまた、そこで過去の曲が多く取り上げられるということもあたりまえのことにすぎない。真に価値あるものは時代を超えて不滅なのだ! 芸術にとっての敵は流行を追い求める軽桃浮薄な輩どもである。価値ある芸術を真剣に味わうこともなく、カッコイイ演奏家を追い求めるような輩は演奏会の場から締め出されてしかるべきである! 等々……。(P6) |
この本は、このような演奏会が当たり前で、普遍的と思っていた私にとって衝撃的な言葉から始まる。
| 演奏会とそこでの聴衆の聴取態度のありかた、そしてそれを支えている芸術観が十九世紀のヨーロッパでかなり特殊な条件のもとに成立したものであって、決して普遍的なものではない。(P6) |
そして、第4章 新しい聴取へ向けて 1節 軽やかな聴衆の誕生 1 マーラーの流行において、マーラーの第5番 第4楽章のアダージュットについて次のように話を進める。
| 弦楽とハープだけで静かに流れてきた楽章が、中間部にはいると情熱的な盛り上がりをみせ、第五八小節で頂点に達するが、そこから曲は寄せた波が返すように再び静まってゆく。そして第七二小節での主部の回帰とともに再び静寂の世界が訪れ、果てしない無限の宇宙に消えてゆくかのように楽章を閉じる、というのが、この楽章の伝統的なイメージだったと言ってもよいだろう。そして過去のさまざまな指揮者たちもまた、この楽章をそのように造形してきた。ところが最近になってそれとは非常に違ったスタイルの演奏が出現した。エリアフ・インパルのものがそれである。インパルの演奏を聴くと、静かに始まりだんだんと高揚し、また静寂に戻ってゆくという伝統的な流れがいたるところで破られ、奇妙な音がそのまま噴き出してくるような印象を受ける。 たとえば中間部におかれた頂点のところ(第五七小節と五八小節の間)では、バーンスタインもカラヤンも、はたまたショルティもシノーポリも大きく息を吸い込むかのように短い休止をおき、続く二小節にあらゆる思い入れを込めて若干テンポを落としてうたいあげるのが常であった。そしてそのことが、伝統的な意味での頂点形成を確固不動のものとしてきた。ところが、インパルはここを、休止もおかず、ほとんどテンポを落としもせずに、さらりと流してしまう。しかも、思い入れたっぷりに奏でられるはずの第一ヴァイオリンの旋律は、何やら耳慣れぬ強弱のつけ方とアーティキュレーションのために、妙に切れ切れな感じで聞こえてくる。このやり方はどうも音楽の自然な流れに逆らっているような印象を与える。 ところが、マーラーの楽譜を見ると、この部分には休止もリタルダンドもなく、しかもこともあろうに、「よどみなく」という指示までつけられているのだ! しかもこのあたりでインパルのつけている不自然とも思われるような強弱やアーティキュレーションも、マーラーがうるさいほど事細かにつけている強弱記号、スラー、句読記号などをいちいち馬鹿正直に守った結果なのである。(P203) |
|
| 頂点形成と主部の回帰という、楽章の構造上のキー・ポイントとなる二つのところで、マーラーがこのようなことをやっているということは重要である。ここでマーラーの与えている指示はほとんど「ぶち壊し」と言っても過言ではないほどのものである。頂点のところが淀みなくさっと流れて行ってしまうのは「肩透かし」もいいところだし、主部の回帰のグリッサンドに至っては、あまりの異様な効果に思わず耳をそばだててしまい、今自分が主部の回帰という重要なポイントにさしかかっているということをすっかり忘れてしまうほどなのである。こうなってくると、伝統的な交響曲と同じような意味で「構造的」に聴くことは、この楽章にとって本質的なことなのだろうかという疑念がわいてくる。 もしろマーラーの主眼は、個々の部分をいかに造形し、それによってそれぞれの部分でいかに強烈なイメージを提供するかという点にあったのであり、全体構成などはどうでもよかったのではあるまいかとすら思ってしまうのである。そしてここだけでなく、マーラーの音楽には「作品の全体」への配慮を忘れて個々の部分の造形の魅力に思わず惹きつけられてしまうような箇所が頻出していることは事実である。(中略) マーラーが細部の造形に異常にこだわったことは、彼の作曲過程や指揮活動に関する研究からも明らかになるが、マーラー自身がどのように考えていたのかはここでの本題ではない。重要なのは、最近になってマーラーの音楽のそのような側面が注目され、インパルのような演奏が出現してきたという事実である。(中略)(P205) |
|
| このような要素を潜在的にもっていたマーラーの音楽が今まさに流行しているということ、そしてとりわけインパルのような演奏が今まさに出現してきたということ、そういう中で今までとは違ったタイプの聴衆が出現してきたということ、マーラーをめぐるこれらの現象の中に現代の音楽状況が象徴的に現われていると言ってもいいだろう。このような現象は音楽の「精神性」を否定するものであり、「通俗音楽への頽落」であるという批判もあるだろう。しかし繰り返し述べているように、「精神性」の神話や「高級音楽」の思想そのものがきわめて十九世紀的な、ある意味では異常な現象であることを考えれば、それとは違う可能性をもった音楽やその聴取のありようが出現してくることは別段不思議なことではない。 そして何よりも重要なことは、このような変化を通じて、十九世紀の「精神性」神話が切り捨ててしまった聴取のありようの中に残されていた可能性が今、新しい音楽の世界を開きつつあるということである。そしてその新しい世界は決して音楽固有のものではなく、現代社会のありようと関わりながらわれわれの文化全体を蔽いはじめているように私には思えるのである。しかし結論を急いではならない。その問題を考えるためには、われわれはさらに現代のいくつかの音楽現象を取り上げてみなければならない。(P209) |
この渡辺裕氏の本は、私にとって音楽を聞くことの意味を考えさせてくれるとても有意義なものであり、世界は固定的でなく、いつも変化しているのだと言うことをあらためて教えてくれた。