
最近の若者は本を読まなくなっているそうだ。確かにもう10年以上も前に、新入社員にどんな本を読んできたか訊いたことがある。「漱石」も「藤村」も「ドストエフスキー」や「トルストイ」も、教科書以外で読んだことのある人がいなかった。そんな世の中になったのだろう。
断って置くが、私は決して読書家ではない。休みにはごろごろしてテレビを眺めている方だ。しかし、「一生の内には必ず読まなければいけない本というのがある」ということを信じてもいる。信じてはいるが、もちろんその「読まなければいけない本」を全て読んだのか?と問われると人生も半ばを過ぎて、頭を掻くしかないのだが。
ましてやこの頃。若い人たちが時間をつぶすための環境には事欠かない。ケータイ、やインターネットブラウザとしてのパソコン(なんとワープロとしても使える!!)、DVD、ビデオ、クルマ・・・。なんでも揃っている。本なんかちゃんちゃらおかしいのかも知れない。
一方、本を読まなくなったはずの日本なのに、あいかわらずベストセラーというのがあるのが不思議だ。最近では「チーズはどこへ行った」という本がミリオンセラーになっているようだし、そのパロディ本、「バターはどこへとけた」でさえ15万部以上という売れ行きだそうだ。数年前の「買ってはいけない」にぞくぞくとあらわれた類似本を思い出す。コバンザメ商法と言ってわるければ、「柳の下の二匹目のドジョウ」商法とでもいおうか。
これはどうしたことだろうか?売れる本は売れる、売れない本は売れない。そのように本の売れ行きがはっきりしてきたのだろうか。
個々人が限られた時間のなかで、本のために割く時間が少なくなっているとすれば、すでに定評のある本を読むのが効率的によいと言えなくもない。いろいろ乱読をして、結局面白い本に巡り会えないよりも、一応の評価が固まった本を読む方が面倒がないに決まっている。同じ本を読んだ人との話題もできるし、というわけだ。
なんとも情けない状況だと思われるのだが、その状況に拍車をかけているのが最近の「コンビニ本屋」である。
皆さんは本屋のチェーン店である「T屋」というのをご存じだろうか?「本屋」と書いたが、書籍を売ると同時にビデオやDVD、CDなどを貸し出したり売ったりしている郊外型の本屋だ。最近の書店らしく中は明るく、本屋というよりは、はやりのレコード店(なんてないか・・・)、音楽ソフト店といった感じの店だ。子供連れなどで賑わっていて結構な話だが、一度行ってみて奇妙な感じにとらわれた。本はたしかにたくさん並んでいるのだが、探そうとすると、ないのだ。なにが?って、本が、だ。
本はいっぱいあふれているがいわゆる「ベストセラー」か、それに準じる本ばかり。だれでも読みそうな本、つまり売れそうな本しか置いていないのだ。
これは困った。本当に良い本、大事なためになる本、自分が精神的に成長するための糧となる本、ベストセラーではないけれど昔から多くの人に読み継がれてきた本、大きな書店なのにいわば人類の財産とでも言うべきそのような本の棚がない。
あるのはマンガ、雑誌(「くだらない」と冠を付けたいが、止めとく)有名軽量作家の本、いわゆるベストセラーに名を連ねる本ばかり。要は回転率の高い(と思われる)本ばかりなのだ。
日本は資本主義の国である。「売れる本を置くのはあたりまえ、何が悪い」という声も聞こえそうだ。そりゃそうだ。売れない本を置くより、売れる本を置いた方が本屋は儲かるし、喜ぶ人も多い。もっともだ、と思う人も多いだろう。しかしちょっと待って欲しい。 ご存じの人も多かろうが、書籍や雑誌は再販指定商品だ。全国どこで買おうと定価は一緒。駅のコンビニだろうが郊外型の大型書店だろうが、はたまた街の本屋さんであろうが、どこで買っても本の定価は同じだ。なぜそれが可能か。
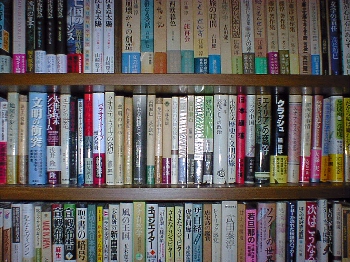 それは不思議な日本の書籍流通機構がそれを支えているのだ。
出版社は一冊の本の定価を決めるに当たり、広告などの経費や原価を計算しながら過去の類似書籍の売れ行きや、類似本の値段などをにらみながら、書籍の定価を決める。そして、本の流通を担う取次店にその定価の60%から70%程度(出版社によって異なる)で卸す。その中から取次店は在庫費用や運送費をひねり出し、書店は販売のための店舗の維持費用や人件費などの経費を出す、ということだ。
それは不思議な日本の書籍流通機構がそれを支えているのだ。
出版社は一冊の本の定価を決めるに当たり、広告などの経費や原価を計算しながら過去の類似書籍の売れ行きや、類似本の値段などをにらみながら、書籍の定価を決める。そして、本の流通を担う取次店にその定価の60%から70%程度(出版社によって異なる)で卸す。その中から取次店は在庫費用や運送費をひねり出し、書店は販売のための店舗の維持費用や人件費などの経費を出す、ということだ。書店に並ぶ本であれば当然売れる本もあろうが、売れない本も残る。いつまでも売れない本を限られた書棚に残すわけにも行かないので、書店はそれを返本することができる。つまり本は一時期販売のための在庫は持つものの、売れなければ返品できる不思議な商品なのだ。
つまり理屈上では、書店はリスクなしで商品を仕入れることができる。だからこそ売るのは難しいが、一部の人にとってはきわめて重要な本、または日本の文化にとって大切な書籍などを書店は安心して書棚に並べることができるのはずなのだ。売れる本は書店の経営にとって大事、しかし売れにくい本であってもそれを必要とする人たちのために棚を提供する、それが書店の責務であるはずだ。
その日本の文化を支えるべき「書店」がどんどん減っている。先に「T屋」と書いたが、このような傾向はT屋ばかりではない。駐車場付きの郊外書店がほとんどこの「コンビニ」的本屋だし、最近は街の大手書店さえ「岩波新書」の棚を探すのに苦労するほどだ。
このような状況は、しかし一方的に書店が悪いわけではない。大手出版社の出版物ばかりを優先する取次店、「売る」ということだけを目的に書籍の企画をする出版社、軽薄に流れる読者などもその一因には違いない。
だが、書店が我が国に置ける自らの文化的な地位を自覚しないでどうする。昔の書店には言いしれぬ雰囲気があった。本屋の棚の背文字に踊るタイトルや作家の名前がまぶしかった時代があったのだ。それを「いつの日かきっと読もう」と心に刻んだ青年も多かったに違いない。そんな雰囲気の書店はどこへ行ったのか?
本屋は金儲けに走らず、自らの役割を思い出せ!まともな本を並べろ!このままでは日本がだめになるぞ!
ついでにひとこと・・。
最近はやり出した「マンガ喫茶」というのがある。入ったことはないが、コーヒー一杯で好きな漫画が読み放題ということだろう。これもマンガ好きにとっては嬉しいしかけだろうが、本屋にとってはたまったものではない。このためマンガ本の売り上げが半減するようなところもあるようだ。マンガなどほっとけば良いと思うが、苦し紛れかこのマンガ喫茶にマンガを卸している書店があるそうだ。もちろんちゃんと販売すれば問題はない。そうではなくて、一時期マンガ喫茶に有料でマンガを卸し、読者がつかなくなったところで回収し、売れなかったことにして取り次店に戻すという犯罪を犯している書店もあるときく。つまり丸儲けである。これはもちろん書店とマンガ喫茶が結託しているのだ。
また、このごろ古本屋のチェーン展開が盛んだ。新しい本は定価の一割でひきとり、定価の半額で売る。売れ残った本は100円の棚に回す。これで必ず売れるそうだが、この古書店の近所の新刊書店では万引きが横行する。
「リサイクル」といえば聞こえは良いが、これで確実に新刊書の売れ行きが落ちている。新刊書の売れ行きがおちれば、出版社はますます売れる本しか出さなくなり、作者は疲弊して創作意欲にも響くだろう。出版を巡る「闇」は深い。
2001年12月