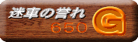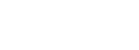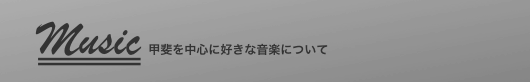
過去のものはこちらから Kai Story Kai Lives Kai Albums Others(一部Liveレポなど)
スウィート テンプル・ムーン・ライブ in 薬師寺大講堂 2012.8.12
しかしこの夏も暑い。
毎年のようだが八月初旬の暑さは熱さと書くに相応しい暑さだった。台風すらも避けて通る程の日本列島である。このまま8/12を迎えたらどうなる事やら、メンバーもそれなりの年齢なら観客もまたそれなりの年齢なのだ。そんな事を想いながら仕事をこなす日々。
果たして前週末の日曜は曇り、そこから暑いながらも耐えられる程度の暑さに落ち着いてきた。直前に帰省。高原地域(笑)は早朝肌寒い程。偶然にも流星を見る。翌日にはとんぼ返りで大阪に戻る。しっかり呑んでライヴに備える。
昼過ぎに起き出し、電車を乗り継ぐ。
…十分暑い。
乗り付けない近鉄電車。のこたらと西ノ京へ。会場である薬師寺はすぐ傍。境内に入る。
濃い朱塗りが奈良仏教らしい。金堂と大講堂の間の客席。横に広い。
が。
わしの席からはスピーカーと照明でおそらく佐藤さん、前野さんが完全にブラインド。ドラムセット(右)もまたブラインド。こっちはたぶん松藤さんだろうなあありゃりゃだがまあ音が聴こえればいい。などとしばし知人と歓談。当日券の新婚マッチョもいる。風が吹けば暑さもさほどではない。このまま吹いてくれればちょうどいいのだが。
開演時間になっても始まる筈は無いがとりあえず客席で待つ。
アフリカンサウンドなSE。
クラップが…….(^^;;
まあそれはともかく。
映像で観た花園を彷彿とさせる。音が消えた。
破れたハートを売り物に
連想から裏を掻く事も無くいつものイントロ。
甲斐さんの唄い方はいつになく優しく感じる。
丁寧に唄っている。
セカンドヴォーカルも優しく前に出る。
挑みかかる雰囲気はない。
翼あるもの
...花園リベンジっすか?(笑)
ツインドラムにパーカッション。
二曲目から既に全開である。
照明は至ってシンプル。
しかし歴史的建造物を遮らず、怯みもしない。
全てがワンセット、といっては不敬だろうか。
フェアリー
いつもならカラフルに染める照明だが、この日は控えめ。
ツインギターの絡みはやはり良い。
野外は久しぶりの筈だが、野外が当たり前のように似合う。
きんぽうげ
もう演りますかこれを(^^;
花園では演奏できなかったという曰く付きの曲である。
マイクアクションとご本尊のコラボレーションを観れないのは残念な席である。
わしの足回りの砂利が抉れて行く。
裏切りの街角
まあほんまよぉ聴こえるアコギじゃこと。
判りきって来たとは言え、やはりあのリズム感は凄まじい。
演奏も甲斐さんの声も、味わって欲しい、そんなMC通りに染み込んでくる。
シーズン
BIG GIGの映像がフラッシュバックする。
凪いでいた筈の風が吹く。
1ROの髪を揺らす。
強一さんのドラムも心なしか優しい。
ビューティフル・エネルギー
海シリーズその2。
この辺続けるのは絶対気に入ってる。
サビもリードで唄う松藤さん。
ん〜〜〜こんなんあったかなあ......
ギターも声も、通る。
決して太い声ではないのに。
やはり変態天才である。
悲しき愛奴
海シリーズその3。
出だしで引っかかる1RO。
そこにジャストで合わせるマック清水(爆
こういうのを笑いで済ませる余裕。
まあ癒し系の本家本元元祖である如来様の前ではこれぐらいがいいのだ。
甲斐さんはステージで平泳ぎ。
ナイト・ウェイブ
海シリーズその4。
これは悔しい。おそらく佐藤さんはスライドだったと思うのだが
完全なブラインドで見えず。
指差す仕草の松藤さんがキュート。
甲斐さんの声はやはり優しい。
BLUE LETTER
海シリーズはそれでも続くその5。
これは...いかん。
強一さんのドラムが効き過ぎ。なんじゃありゃ。
目から汗が吹き出す。
恋のバカンス
こうなりゃとことん海シリーズその6。
亡くなったもんなあ。
オマージュの意味合いも在るのだろうか。
安奈2012
一瞬飛ばされそうになったが(笑)
照明で勘違いしたのだろうか。
暗転すれば観客としてもこの次の曲を連想した筈だ。
アレンジされた安奈。
A.G.辺りのアレンジが基なのだろう。
サビのあの唄い方はわしはオリジナルより好きだったりする。
嵐の季節
暗転から一転、客席が明るくなる。
今「も」嵐の季節だったりするのだが、
それはそれとして結構楽しんでいたりもする。
狭い通路を行き来するカメラマンがちょっと邪魔だったのか、
隣の客がカメラをどつくシーンも(笑)
しかしこの空間になんとこの曲が合う事か。
氷のくちびる
松藤さんが声を挙げてカウントする。
やはり花園は意識されているのだろう。
花園で座布団を投げずに持ち帰り今も保管している知人は遅い初婚を迎える。
某マッチョは馬鹿なので三回目である。
ふっと思い出しつつ。
狂おしい想いは消える事も無く、己のカルマに身を委ねる。
照明は白が基調だが、間奏の二色は健在。
日光が甲斐さんで月光が1ROか。
ポップコーンをほおばって
とりあえずクラップはアレなのでもうやめようてば(^^;;;
サビ前後で変わったら気色悪いて。
それはさておき。
やはりストロボ。
1ROのアクションもいつも通り。
いつもより照明のセットは狭いのに窮屈に感じない。
後ろに鎮座ますご本尊、そして講堂の威圧も無い。
計算され尽くされたステージング。
漂泊者
サイドからカラフルな照明。
いつもの狂乱的な雰囲気はなく、むしろ、ドグマに付随する狂気を感じさせる。
この場でこの曲を演りきる胆力。
......怒られてないよなあ?(笑)
HERO
安奈からは一転、オーソドックスなHEROである。
ワンナイトなイベントにはこれ以上ふさわしいエンディングが在るだろうか。
ベタな選曲かもしれないが、大手を振ってベタに走る胆力も、
今の甲斐バンドは持ち合わせているのだ。
~Encore~
ダイナマイトが150屯
ご本尊の前でマイクアクションその2。
日本の仏教は大乗仏教の亜種であり、大乗仏教を広めた玄奘三蔵を奉る薬師寺は
その総本山的な位置づけになるのだろう。
大乗仏教だから許されるライヴであり、アクションであり、バンドでもあるのだろう。
ダイナマイトをぶっ放しても許される雰囲気が不思議であり当然でもあり。
Love minus Zero
照明が講堂の軒を照らす。
それがセットそのものであるかのように。
カラフルな軒先が霞む。
街路〜100万$ナイト
短いブレイクを挟み。
このシチュエーションと選曲であれば、オーラスはこれしかないだろう。
定番中の定番、必然中の必然。
甲斐よしひろは穏やかに噛み締めるように唄う。
カルマの暴発を避けるかのように。
講堂の中からは如来の光。
こちらに直接届きはしないが、対面の金堂を照らす。
伽藍をライヴ会場に仕立て上げる。
関西での野外ライヴと言えば花園を連想せざるを得ないが、直前のSEがアフリカンサウンドであった事、オープニングが「破れたハートを売り物に」であった事、「氷のくちびる」の松藤さんが声を出してカウントした事、バンド側も花園を意識したライヴであった事には間違いない。
近鉄沿線も関係しているのかもしれないが。
しかし同じ野外は野外でも、花園はラグビー場、開放空間であるのに対し、寺社仏閣、しかも名刹中の名刹、薬師寺は対極ともいえる閉鎖的な空間である。野外であるとはいえ境内という閉鎖的な場所なのである。
開放空間でのライヴは衝動を生み、暴動寸前に至った。
ではその逆で同じ事をすればどうなるのか、30年を経てどう変わったのか、そんなものを確認してみたかったのか。1300年の歴史の重みで衝動を抑え込もうとしたのか。もちろん客席もあの映像とはかけ離れた年齢層に達している。どちらも観たという幸運な客もいるにはいるだろうが、それでも30年の時が流れている。衝動的な行動を良しとできる年齢層ではないだろう。
一部に傍若無人なものがいた事も事実であるが。
とりあえず曲中の私語やめれ。
まあそういうのは場所に限らず一定数いるのは致し方も無いのでしょうがないのかもしれない。
暴動を恐れ、また仏閣だから甲斐よしひろは抑え気味に唄ったのだろうか。抑え気味と言う表現で語弊があれば、優しめな雰囲気で。それだけではなく、強一さんのドラム、岡沢さんのベースも抑え気味だったように思う。ろくでなしではビートを打ち抜いて来たが、開放空間のせいもあってか、今回打ち抜かれるようなビートは感じなかった。お寺の中で、穏やか且つ慇懃なライヴを演じたかったのか。
そんな訳が無い。
わしは冷血が演奏されなかった事が不思議にも感じた。わしの中では、甲斐よしひろの曲の中で、これほど明確にカルマを唄ったものは無いという認識である。ベタ過ぎるから外したのかとも思えるのだが。そんな冷血に顕著なように、カルマ=業を唄い上げて来た甲斐よしひろ、甲斐バンドが業を如何に扱うかという哲学に基づく仏教の場で、それら全て隠匿して衝動をも抑えてハイおしまい、そんな事を宣う訳が無い。
それはライヴが成立しえたと言う事実ただ一つで反証できる。
歴史的寺院とバンドが一体化した、一体化という表現が不敬であれば、少なくとも相乗的効果をお互いに持ち得たライヴ、わしにはそう見えた。音響、照明などスタッフも含めた甲斐バンドがあの場所に最大限の敬意を持った上で演奏し、大講堂の建物だけでなく、伽藍やご本尊も甲斐バンドの表現を後押ししているかのような感覚を受けた。仏様の前だからと畏まって穏やかに、それだけであんなライヴが成立する筈がない。
大きく話は逸れるようだが、以下薬師寺の公式サイトの文章を読んで欲しい。
http://www.nara-yakushiji.com/guide/hosso.html
この宗の特徴は阿頼耶識[あらやしき]、末那識[まなしき]という深層意識を心の奥にあるということを認めているところにあります。その阿頼耶識 を根本識[こんぽんじき]とし、一切法は阿頼耶識に蔵する種子[しゅうじ]より転変せらる(唯識所変[ゆいしきしょへん])としています。つまり私達の認 めている世界は総て自分が作り出したものであるということで、十人の人間がいれば十の世界がある(人人唯識[にんにんゆいしき])ということです。みんな 共通の世界に住んでいると思っていますし、同じものを見ていると思っています。しかしそれは別々のものである。例えば、『手を打てば はいと答える 鳥逃げる 鯉は集まる 猿沢の池』 という歌があります。旅行客が猿沢の池(奈良にある池)の旅館で手を打ったなら、旅館の人はお客が呼んでいると思い、鳥は鉄砲で撃たれたと思い、池の鯉は 餌がもらえると思って集まってくる、ひとつの音でもこのように受け取り方が違ってくる。一人一人別々の世界があるということです。
それを主張するのですから複雑難解です。しかしそれをいとも巧みに論理の筋道を立てて、最も学的秩序を保った説明がなされているところに、この宗の教理の特徴があります。
この宗の特徴は阿頼耶識[あらやしき]、末那識[まなしき]という深層意識を心の奥にあるということを認めているところにあります。
甲斐よしひろは曲だけでなく、その言動に於いてもこれと全く同じ事を述べ続けてきた。
「自分が何者か理解するために演る」そんな言動すらあった。
教義と信念(?)の一致。
それがあるからこそ薬師寺でのライヴが決まったのか、そんな想像さえしてしまう。教義を明確に認識、意識していたかどうかは知らない。しかし少なくとも、暗黙の内に、それこそ阿頼耶識の中で認識していたのは間違いない。これは確信を持った結果論だが、そんな一致が無ければステージは講堂の荘厳さに押しつぶされていた筈だ。従ってこのライヴに臨み、甲斐よしひろの中、阿頼耶識、末那識、纏めて言い換えれば、甲斐よしひろの衝動には、何らかの確固としたものがあった筈なのである。
ではその衝動とは、直接衝動的な表現を避け、穏やかに表現するという甲斐よしひろの衝動とは。
いつもの思い込み決めつけに入ろう。
まず薬師如来とは、快癒を導く仏である。薬師寺の成り立ち自体、天武天皇が持統天皇(鸕野讃良皇女)の快癒を祈念し発願されたものである。所謂癒しこそがその存在目的なのである。
先に断るが癒しのために優しく唄った、そんな短絡的な結論を導くつもりは無い。
さて、MCでも震災の事について触れた。やはり震災被害に対する想いがこのライヴの根本にあるのもまた事実だろう。被災者の癒しを発願したライヴ、それもまた一面なのだろう。
繰り返すが癒しのために優しく唄(以下略。
この日のライヴでは海の唄が6曲続いた。震災と海と言えばどうしてもあの津波を思い起こさずにはいられない。しかし海には破壊の一面だけでなく、癒しの一面ももちろんある。というよりむしろそれが表の顔なのである。甲斐の曲の中で、Blue Letterなどはその癒しが前面に出た曲の最たるものである。
しつこいが癒しのた(以下略。
昨年秋、石巻で甲斐バンドはライヴを行った。わしはラジオ音源を手に入れ、聴く事ができた。
これもまた全編穏やかな唄い方、且つアコースティックセッションであり、中でもビューティフル・エネルギーは素晴らしかった。この演奏で癒されない筈が無い程の素晴らしさである。そしてこの日のビューティフル・エネルギーもまた素晴らしかった。
これで最後にするが癒(以下略。
敢えて言ってしまうが、癒しがどうとか、そんなものは甲斐よしひろの口先にしか過ぎない。
表層上の事に過ぎないのだ。結論はまだ奥底にある筈だ。
ここで。
次の甲斐バンドはどうなるか、前回の拙筆の結びである。
甲斐バンドでグルーヴを突き詰め、ソロアクトになり、グルーヴに変節を加え、ドライヴ感を強調した。その先はどうなのか。それがわしの興味であった。しかしその次を述べる前に、グルーヴからドライヴへの変節に留意しておかなければならない事がある。
というかまさに今気づいた事なのだが。
グルーヴは、ステージ側から一方的に放たれるものであり、観客はそれに取り巻かれる事はあっても、自ずから発する事のできるものではない。ノる事はできても、客が表現できるものではないのだ。いわば、客からすれば受動するだけの一方通行なのだ。
対してドライヴ感はどうか。グルーヴ感同様、客が表現できるものではない。しかし決定的に違うのは、客の感情、衝動、心構え何でも良いが、メンタルな部分の能動性への働きかけである。
ろくでなしでは足に纏わる曲が多く歌われた。この事で前向きな、自分で歩き、走る、能動的な行動への誘いがあったのだ、それは前回でも述べた。
受動から能動へ。
これが甲斐バンド/甲斐よしひろの変節であったのだとしたら。このライヴは更にその延長にある筈だ。
と、すると。
いつに無いあの唄い方も、そこに行き着くと考えられないか。
観客の能動を誘うため、そうは考えられないか。
リズム/グルーヴを強調し、強く唄う事で客に音を当て、取り巻き、飲み込むのではなく、
リズム/グルーヴを抑え、穏やかに唄う事で客の衝動を引きつけ、引き出し、引き寄せる。
そういう事ではないのか。
こう考えてみると全てが合致する。
最も衝動的(これは悪い意味でも)であった花園を彷彿とさせる構成、
深層意識を認める教義を持つ寺院の総本山でのライヴ、
リズム/グルーヴを抑えた演奏、
そして穏やかな甲斐よしひろの唄、
これら全て観客の能動的衝動を引き出すためであったのだ。
だからわしの目から涙汗が噴き出したのだ。
衝動を引きずり出されたのだ。
否、導き出されたのだ。
これがこのイベントに限定されたものなのか、今後の傾倒となって行くのか、それは次のライヴを待つ以外に解答は得られない。
来年には甲斐バンドでのツアーが予定されている。
次の甲斐バンドは、甲斐よしひろは、どう来るのか。
早く来い来いお正月、である。