養老猛司氏が某大学で講演を行った際の内容がテレビで紹介されていた。最近の若者の働く気のなさについての
コメントだった。自主性を重んじ、やりたことを見つけさせるという最近の教育方針に異議を唱えていた。養老氏は解剖
学者として数々の遺体の解剖を行ってきたが、「私は好きで遺体解剖をしてきたわけではない、やらなければならない
からしてきたのだ。仕事はやりたいからやるのではなく、やるべきだからやるのである」・・・そのような主張であった。
コメントだった。自主性を重んじ、やりたことを見つけさせるという最近の教育方針に異議を唱えていた。養老氏は解剖
学者として数々の遺体の解剖を行ってきたが、「私は好きで遺体解剖をしてきたわけではない、やらなければならない
からしてきたのだ。仕事はやりたいからやるのではなく、やるべきだからやるのである」・・・そのような主張であった。
5月28日付読売新聞でフリーター・ニートの調査結果が報じられた。その調査結果に対して若者代表を自称する衆
議院議員杉村太蔵氏が下記のコメントをしており、興味深い。
議院議員杉村太蔵氏が下記のコメントをしており、興味深い。
ニート、フリーターになる理由として、「やりたい仕事が見つからないから」との割合が多いのも気になった。自分を
含めた若い世代は、学校や親から「やりたいことをやれ」と言われて育ったため、「やるべきこと」の重要性を軽視しが
ちだ。納税の義務など働く意義を社会全体で次世代に教える環境整備も欠かせない。
含めた若い世代は、学校や親から「やりたいことをやれ」と言われて育ったため、「やるべきこと」の重要性を軽視しが
ちだ。納税の義務など働く意義を社会全体で次世代に教える環境整備も欠かせない。
大学においても近年、学生のやる気のなさが話題になることが多い。私自身も、社会に対する不満やそれに憤慨す
る気持ちが学生には希薄になっているように感じる。講義中に「あなたが身近に感じた消費者問題」をあげさせても、な
いという学生が多いのである。だれも消費者であり、毎日が消費の連続である。今日食べたランチがまずかった・・・そ
れだって消費者問題だと言うときょとんとする学生もいる。
る気持ちが学生には希薄になっているように感じる。講義中に「あなたが身近に感じた消費者問題」をあげさせても、な
いという学生が多いのである。だれも消費者であり、毎日が消費の連続である。今日食べたランチがまずかった・・・そ
れだって消費者問題だと言うときょとんとする学生もいる。
こうした状況はある意味、豊かさのあらわれかもしれない。労働者にならなくても、消費者としての自覚がなくても、
生きるのに困らないのである。読売新聞の同記事で山田昌弘氏が以下のように述べている。
生きるのに困らないのである。読売新聞の同記事で山田昌弘氏が以下のように述べている。
彼らの生活を親が支えている。経済的に豊かになった国ならではの光景だ。このため、若者たちは一見、「働かなく
ても生きられる」ように見えるが、いずれ親が亡くなれば、生活が破綻する人が増えるだろう。
ても生きられる」ように見えるが、いずれ親が亡くなれば、生活が破綻する人が増えるだろう。
受験偏重の教育の中で、知識を詰め込むだけの学び方に慣れきっている学生が多い。「知識」は「意識」があっては
じめて身に付くのであり、「意識」をどう芽生えさせるかが今の教育に必要なことだと思う。学ぶ意味、それを社会に生
かす意味をどう意識させるか・・・試行錯誤が続く。
じめて身に付くのであり、「意識」をどう芽生えさせるかが今の教育に必要なことだと思う。学ぶ意味、それを社会に生
かす意味をどう意識させるか・・・試行錯誤が続く。
細川幸一
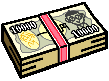
|
|

