




大東亜戦争論
「日本の元気」のホームに戻る
     |
日本海軍戦略の誤り
海軍の戦略といったが、後述のように日本海軍にそもそも戦略はなかった。
1.真珠湾攻撃
①真珠湾の無力化
真珠湾は太平洋の中間に位置し、アジア侵攻の重要な基地であることは、アメリカが、ハワイ王朝を卑劣な陰謀によって奪ったことでもわかる。真珠湾攻撃は、日露開戦が旅順攻撃から始まったのと同じ発想はなかったか。戦略的にはハワイを占領する必要はない。日本遠征の基地としてのハワイは最も重要である。パナマ運河を通過した米海軍の艦船は、西海岸で補給した後、ハワイにたどりついて直接出撃ないし、オーストラリアまで回航されて出撃するケースが多い。
珊瑚海海戦で90日の修理を要すると見られた、大きな被害を受けたヨークタウンは真珠湾のドックで応急修理を受けて、わずか3日でミッドウェー海戦に出撃した(*)。丸スペシャルの写真によればドックの周辺にはガントリークレーンなどの大規模修理設備がある。
燃料の補給だけではなく、艦船の修理能力も重要である。もしハワイの施設がなければ、単に西海岸から出撃した艦船が、西太平洋で戦闘を行うことができるための燃料が不足するだけではない。戦闘で傷ついた艦船は、はるか彼方のアメリカ西海岸までたどりつかなければならない。米本土と西太平洋を中継するハワイの価値は絶大である。燃料はタンカーで運搬すれば、何とか急場は凌げないこともない。
ちなみに停泊していた8隻の戦艦のうち5隻を撃沈する大戦果を挙げたと言われるが、実際には使えなくなったのは標的艦ユタは論外として、戦艦アリゾナとオクラホマの二隻に止まる。それどころか残りの戦艦は全て艦橋などの上部構造物を一新した。すなわち主砲と機関こそ同じだが対空対水上の両用砲の搭載、火器管制システムの一新、レーダーの搭載などによって近代化して生まれ変わった。スリガオ海峡海戦で戦艦山城以下の西村艦隊を迎撃した、オルデンドルフ艦隊の戦艦6隻のうち5隻が真珠湾で沈没あるいは損傷した戦艦であったことは有名である。これらの戦艦は真珠湾の修理設備により浮揚回収、応急修理され、米本土に回航、本格修理あるいは改装されたのである。
修理施設ばかりではない、繋留、揚陸などの施設がある。これらの施設がなければ西海岸やパナマ運河を経由した米艦隊は、西太平洋の日本占領地攻撃に出撃できない。石油貯蔵施設を破壊しなかったことを最も重大な過失にいいつのる識者が多いが、最も重要なのは港湾施設と修理施設である。いかに航続距離の長い米海軍艦隊でも、パナマ運河あるいは太平洋岸の基地から、直接ガダルカナル島攻略部隊を発進させるということは極めて困難である。すると利用できるのはオーストラリア付近の軍港に限定されるが米国からハワイを経由しないでオーストラリアに行くのも困難である。多数のタンカーを随伴してヨタヨタと太平洋を航行するのは難事だからである。
ハワイの無力化が継続できれば、米軍の反攻は永久にできないに等しい。残りの手段は太西洋を越えてスエズ運河を経由して太平洋に遠征するしかない。それこそバルチック艦隊の日本遠征の再来である。
ハワイが使えない米軍の大遠征に比べれば、南方と日本の占領地と日本本土の連絡の方がましである。戦力は距離の2乗に反比例するという。ハワイは日本侵攻のために作戦する艦船にとって必ず通らなければならない、一点である。必ずここを通るとなれば迎撃は容易である。日露戦争の日本海軍は、どこを経由してウラジオストックにバルチック艦隊が行くかに悩まされた。これに比べ米海軍はハワイを経由するしかないのである。
日本海海戦は艦隊決戦が目的ではなく、ウラジオストックにたどりついて、日本本土と大陸との兵員や物資の輸送や日本国内の海上輸送を阻止するために派遣されたバルチック艦隊と、ウラジオ到着を阻止せんとした連合艦隊との遭遇戦である。海戦の目的はあくまでもロシア艦隊のウラジオ到着阻止であって、艦隊決戦のためではない。
その後の日本海軍はこの本来の目的を忘れて、なぜか米海軍はただ日本を一路侵攻してきて、これを迎撃して艦隊決戦が起こるものと想定した。何の目的でどのようにして、米艦隊が太平洋で行動するかという想定を全く欠いていたのである。それを考えずとも米艦船は対日戦争のためにはハワイを絶対使用しなければならないことを考えれば、何らかの方法でのハワイの無力化を考えたであろう。
修理施設や接岸繋留などの施設は破壊されればハワイ島内では、応急修理すらできない。資材を本土から運んだ上に工事を行わなければならない。輸送と工事を妨害するのは困難ではない。被害を受けた米海軍の艦船がハワイで応急修理、ないしハワイ経由で西海岸まで帰投して修理しているところをみると、オーストラリアやニュージーランドの施設は使えなかったのであろう。
能力はあったとしても部品供給などの問題があったのかもしれない。近いにもかかわらず、オーストラリアないしニュージーランドに帰投したという記録が見当たらないのはそれなりの理由があったのであろう。だからハワイは米本土への中継基地として重要であったのであって、地理的にもオーストラリアへの中継基地ではあり得ない。いずれにしてもハワイという中継基地がなければ、米軍は南方を占領した日本軍に対して反攻をしかけることは極めて困難である。
山本五十六は石油タンクや修理施設攻撃について、南雲はやらないだろうとうそぶいたと言われるが、これほど馬鹿なせりふはあるまい。もし艦艇や飛行場以外に石油タンクなどの施設攻撃を山本自身が必要だと考えていたら、攻撃計画に含めきちんと指示していたはずだからである。このせりふが山本シンパのでっち上げであるか、単に山本の認識の薄さを示しているだけである。つまり贔屓の引き倒しである。:
繰り返すが、大東亜戦争の米軍の対日反攻を阻止する最も有効な手段は、真珠湾の無力化である。前述のように、米軍が太平洋の戦域に進出するためには船の航続力等の関係から、必ずハワイを経由しなければならない。真珠湾を無力化するのには、必ずしも真珠湾にいる太平洋艦隊の撃滅は必要ではなく、港湾施設、海軍工廠と石油施設の破壊がひとつの方法である。これらの施設が使えなくなれば、はるか米本土からやってきた米艦船はそこから動けなくなる。損傷した艦艇の修理もできないから、米海軍は西太平洋にたどり着くことはできない。これらの施設の再建を妨害しに向かった日本艦隊を阻止しようと米艦隊が進出して来たら迎撃すればいいのである。:
戦艦の最大有効射程を20kmとすれば、湾外から施設の破壊は可能たがが、真珠湾攻撃直後の時点では日米の戦艦はともに徹甲弾しか搭載していなかっただろうから、艦砲射撃は極めて効率が悪いし、要塞砲の反撃もある。残る方法は空襲か陸軍部隊による攻撃である。大東亜戦争では空母による空襲先方が常態したから、空襲による攻撃を優先する、と言うのは後知恵である。施設の破壊は陸軍の仕事であろう。陸軍は破壊だけ行えば占領せずに帰還すればよい。米国同様ハワイへの補給は日本にとっても困難になるから、占領せずに破壊して戻り、適時に回復を妨害しに行けばいい。大東亜戦争中、ハワイへの米軍の補給を阻止しなかったのは大きな誤りである。何せ米艦船はハワイまでは自由に行くことができ、ハワイを自由に使えたのである。
日本海軍は伝統的に艦隊決戦の前に航空機、潜水艦や駆逐艦による漸減激撃戦を行うこととしていた。主力艦群の戦力を削いだところで、戦艦同士の艦隊決戦で雌雄を決すると言う作戦の研究にだけ徹してきた。この場合日本海軍の空母の役割には2つが想定されていた。戦艦などの砲撃戦の弾着観測機の保護へのための制空権の確保と、漸減激撃戦への参加である。
零戦の航続距離が異常に長いのは、前者の目的のために、滞空時間を確保するためであって、結果的に長くなったのである。航続距離が長く脆弱な陸攻の援護は当初の開発目的ではない。出典は忘れたが、この指摘は兵頭二十八氏によるものであると記憶している。事実、十二試艦戦の当初の要求書には、耐空時間しか示されていない。開戦時の戦艦の戦力に関しては、日本では大和型二隻が、米海軍も開戦時にはノースカロライナ級、サウスダコタ級、アイオワ級の新型戦艦のいずれもが就役していないから、戦艦同士の年式では日米ほぼ対等である。真珠湾にはわざと旧式戦艦だけおいて、故意に攻撃を受けさせた、という説があるが、存在しないしない新戦艦など配備しようがない。
空母が制空権確保に徹し、航空攻撃を行わなかった場合、日本陸海軍のハワイ攻撃時には、作戦を阻止しようと在泊中の戦艦群が出撃する。日本海軍の血のにじむような訓練を積んだ上の作戦で、最初の大海戦に勝てなかったら何をかいわんやである。まして日本側には体制を万全に整えた先制攻撃という利点がある。勝機は充分にある。
施設の破壊に成功したら、その後は、真珠湾の施設の復旧を恒常的に阻止しなければならないが、ハワイの太平洋艦隊をつぶした日本にとっては困難な話ではない。打ち漏らしたという空母軍にしても、当面は日本側が優位にある。石油にしても、本土から運搬する必要がある。パナマ運河経由でサンフランシスコあたりからハワイにやってくる、米艦隊による真珠湾の復旧の準備や補給を阻止することである。
大東亜戦争の初期においてすら、米海軍の空母などによって、日本軍はゲリラ的攻撃に悩まされたが、真珠湾を自由に使わせたが故のことであった。ガダルカナルへの日本軍への潜水艦等による阻止攻撃も同様である。なお、ハワイ攻撃時に米空母を攻撃することを予定に組み込まなかったことを批判する向きが多いが、これは典型的な後知恵である。何せ事前の図上演習では米戦艦群に相当な被害を与えても日本空母のかなりが、沈没大破すると言う予想であった。つまり空母は捨て駒だったから、米空母の撃滅も重視していなかったのは当然である。
「海軍の失敗」では日本陸軍が強襲揚陸艦や本格的な水陸両用戦部隊を持つなど、実戦に即した柔軟な対応を評価し、海軍が本来任務である船団護衛を戦前には全く想定していなかったことを批判している。ちなみに陸軍の「神洲丸」は上陸用舟艇と兵員を搭載し、揚陸作戦を行うための世界初の、強襲揚陸艦、というべきもので、戦訓を正しく反映したもので、戦訓を無視し続けた海軍とは異なる。戦後は海軍善玉論が幅をきかせているが、海軍は、対米戦備を想定していながら、艦隊決戦に至るまでいかなる展開となり、そのためにどのような準備が必要かを戦前に考えていた形跡が無い。
開戦後フィリピン辺りを占領すれば、単に艦隊決戦と言う具体性を持たない戦闘が、何故か小笠原沖等で発生する、という抽象的な想定していなかった。繰り返すが、バルチック艦隊は艦隊決戦をしに来たのではない。太平洋艦隊の増援にウラジオ港に行って、日本海の制海権を握って、通商破壊日本を疲弊させるとともに、大陸の日本陸軍への補給を途絶孤立させ陸戦で勝利を得るためであった。日本の陸海軍もバルチック艦隊に同じ危惧を持ったのである。艦隊はあくまでも陸戦の補助者である。
戦争はスポーツではない。スポーツは正面から戦ってルールにのっとり勝敗を決すること自体が目的であるが戦争はスポーツではない。しかし日本海軍は海戦をスポーツのように、用意ドンで今から海戦が始まります、といって勝敗を決するものであると、日本海海戦の勝利後考え始めたのである。何故日本海海戦が生起したか忘れたのである。同時に艦隊決戦に必要な予算の獲得だけに邁進してきた。何度でも言うが海軍には戦略はなかった。
②被害率
真珠湾攻撃における米軍の迎撃能力は驚異的であった、といえば意外であろうか。私には日本機がわずか29機の損害であれだけの大戦果を挙げたという評価は不可解である。真珠湾攻撃の日本機は延べ約三百五十機であった。被害率は8%を超える。第二次大戦で空襲した爆撃機や戦闘機の被害率は平均すると米軍では、対独、対日戦で3~5%というのが相場である。ドイツ軍でもこの程度の迎撃能力である。
すると真珠湾攻撃の際の米軍の反撃はその2~3倍という極めて優秀な値である。まして対空戦闘の準備がされていた、戦時中の日独と完全に奇襲された米軍の差を考慮すればなおさらである。米軍の迎撃体制が「平時」の休日であったのにもかかわらずいかに優秀だったかわかる。また特殊潜航艇は全艇が撃沈破ないし捕獲されている。米軍艦は特殊潜航艇の潜望鏡を発見すると即時無警告で発砲撃沈している。空襲の1時間前である。これは索敵の優秀さを示すとともに、米海軍艦艇が何らかの戦闘体制に入っていたことを示している。
③艦砲の用途
航空攻撃に確信が無かったのならなぜ航空攻撃と艦砲による攻撃の複合をなぜ考えなかったのだろうという疑問が残る。これは突飛な考えではない。日本海軍は艦隊決戦の前哨戦として航空機や潜水艦で攻撃して敵艦隊の勢力を削ぎ、主力艦隊の勢力を米艦隊と対等にした上で、決戦に臨むというのが日本海軍の伝統的構想だったからである。まず航空攻撃である程度米艦隊の戦力を落とした上で、戦闘機のエアカバーの下で真珠湾湾口に近づき米艦隊と海軍基地に艦砲射撃を加える。当然要塞砲の殲滅も行う。
湾口からフォード島まで約5km、海軍基地まで8km程度である。戦艦の有効射程を持ってすれば、真珠湾内に入って袋の鼠になることなく湾外から充分射撃できる距離である。ここから強力な艦砲で艦艇のみならず各種施設の徹底破壊ができる。ただし前述のように、この時点での戦艦には徹甲弾しか搭載していなかったから、艦艇はともかく、陸上の目標は選定しなければ効果は薄くなる。当時まだ議論の分かれるところであった航空機の対艦攻撃能力からも海軍の伝統的戦法からも逸脱しない。陸上攻撃任務を終えた6隻の空母からすれば、戦闘機でエアカバーしつつ米空母出現に備えて索敵と攻撃の待機をすることは充分可能である。
*丸スペシャル No.97 ミッドウェー海戦 1985.3<BR>
④日本海軍の索敵
ミッドウェー海戦に敗戦して索敵が不足していたと批判される。確かにそうかもしれない。しかし索敵と言えばもっと大きな視点を忘れている。大戦後半、マリアナ沖海戦において、日本艦隊は潜水艦に襲われて大鳳、翔鶴の2空母を撃沈されている。大和は沖縄出撃では呉出港以来潜水艦に追尾されて行動は終始知られていたし、信濃は横須賀から呉に回航する途中、偵察行動の米潜に発見され撃沈された。
これに対して日本海軍は米艦隊の行動をほとんど知らずに、あらゆる上陸作戦をし放題に許している。上陸作戦を水際で阻止するのが、ベストであるが、それには上陸支援艦隊を日本艦隊が早期に迎撃しなければならない。現に、珊瑚海海戦などは、日本の攻略部隊を海上で早期に迎撃し、上陸作戦の芽をつむことに成功している。これに対して日本軍は全くと言っていいほど成功していない。
米軍は何をしていたか。潜水艦で日本本土などの要地を潜水艦で索敵していたのである。日本艦隊の根拠地は呉、トラック島などに限定されている。しかし米軍とて根拠地はハワイ、ミッドウェー、ポートモレスビーなど限定されている。つまりこれらの根拠地を潜水艦を使って監視していればよかったのである。日本の潜水艦は米本土西岸を砲撃する位であったから、航続距離に不足のないものは、かなりあった。
だいいち、潜水艦に太平洋を往復させて、艦載水偵でわずかな爆弾を投下させるほど日本海軍は暇だったのである。何という壮大な無駄をして、肝心の索敵や補給の阻止を怠っていたのだ。レーダーがなくても日本海軍独自の潜水艦に搭載された水上機を使えば索敵範囲は広がるし、潜水艦の秘匿にもなる。レーダーなどという最新技術がなくても、既存の装備を有効活用すればよいのである。ただし、後述するが、日本海軍だけが多用した潜水艦の水上機は、訓練時はともかく、戦闘時には一度発艦したら、帰投できない可能性が高く、一度きりの索敵行で、練度が高いパイロットを失う危険性も高いことは一言しておく。
バルチック艦隊回航の際日本はイギリスを始め諸外国の協力や信濃丸などの船舶を派遣して、バルチック艦隊の動静を知るのに必死になっていた。その結果迎撃作戦を成功させたのである。連合艦隊司令部の最大の関心は対馬沖か太平洋迂回航路を使用するか、いつ到着するかであった。それならば昭和の日本海軍も日本攻撃の米艦隊を迎撃して、艦隊決戦を挑む構想であったから、米艦隊がいつどこにいて、日本にくるか開戦以後の行動を偵察する手段を考えていなければならなかった。
繰り返すが、結果から言えば、日本海軍は米軍の幾多の上陸作戦を洋上で迎撃する事は一度もなかった。成功どころか、試みる事すらしなかった。ガダルカナル上陸、フィリピン攻略などの大艦隊の動静を全く掴んでいなかったのである。これでは艦隊決戦など起きようもない。上陸部隊は輸送船団などの非戦闘艦艇を多数同行しているから、海戦の足手まといになり、日本側の方が有利なはずである。私はこのような視点での海軍批評がない事をいぶかしく思う。それどころか、多くの識者は常道である水際阻止に固執したことだけを批判する。水際阻止は本来の戦法であるが、海軍はそれを可能にする作戦をとらなかったのである。
海軍は真珠湾攻撃などを行わずに、戦艦による艦隊決戦を行えば勝てた、と言う旧海軍の軍人の記事を見たが、米艦隊が泊地を出撃する動静には何の意も用いずに、いきなり日本近海で出会うところから記述が始まるのにはあきれた。日本海軍は上陸に迫る米艦隊を迎撃できた事はないのだから、このような事態が起こる前に米陸海軍のフィリピン逆上陸や日本本土上陸は始まってしまうはずである。艦隊決戦が発生するはずはないのである。考えて見れば、大東亜戦争の海戦の多くは、攻撃をしかける日本艦隊を米艦隊が阻止するために起きたことが多い。つまり日本の構想を実現したのは米海軍であった。
例えば珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦は、日本軍の上陸部隊と支援艦隊を上陸開始以前に、洋上で日本の攻略部隊を攻撃、上陸の企画そのものを阻止している。レイテ沖海戦では上陸終了後、栗田艦隊はレイテ湾に到着したがその間、米艦上機に散々叩かれたあげく、空の輸送船を攻撃しても仕方ないと、引き返してしまう始末である。
最も早く米攻略部隊を日本艦隊が迎撃した、マリアナ沖海戦でも、米艦隊の上陸支援の艦砲射撃を激しく受けてしまい、迎撃の「あ号作戦」が発動されたのは、米軍上陸開始直後となった。このため、サイパン島の日本軍の水際阻止戦術は失敗したのである。米海軍は暗号解読、通信傍受、航空偵察、潜水艦偵察等の色々な手段による索敵によって日常の艦隊の行動の把握に努力して、日本艦隊の攻撃を阻止する事に成功している。先の艦隊決戦を主張した元軍人にしても、索敵とは、既に対峙している戦場での艦隊陣形把握や砲戦の弾着観測などの戦術的な索敵であって、敵艦隊の日常の動静の把握と言う、戦略的な索敵に戦力を充分振り向けていないのは不可解である。
海軍に比べ悪く言われる陸軍であるが、日本海海戦以来、支那事変において航空作戦しか経験のない海軍に比べ、上陸作戦などの実戦の経験を積んだ陸軍は、強襲揚陸艦といえるものや大発などの上陸作戦用艦艇を世界に先駆けて開発するなど、過去に囚われない斬新な発想をしているものが多い。ダイハツなどの上陸作戦用機材が開戦当初の作戦に大きく寄与し、米英も密かに学んだ事は案外知られていない。まこと陸軍に比べ海軍中枢は悪い意味で官僚化して、発想が硬直化していると言わざるを得ない。
⑤真珠湾攻撃異見
現在の日本では、自虐的な者たちを除外しても、真珠湾攻撃を愚行だとする意見ばかりであるが、理由は論者によって異なるから、同一意見だとは言いにくい。それでも、騙し打ちとなってアメリカ国民を戦争に駆り立てた、とか、戦艦が沈んだところで引き揚げられることは分かっており、空母を取り逃がしたばかりではなく、石油タンクや工廠を破壊しなかったから容易に反撃された、などというものが大勢であろう。
さらに、対米戦は避けることができたはすだとする主張もある。そのいくつかのうちの例外的な極論は、アメリカを攻撃せずに、独ソ戦が始まった当時、松岡洋右が主張したのと同じくソ連を攻撃せよ、というものである。だが、昭和十六年から米国はソ連に対しても、レンドリースによって、大量の武器を与えていた。つまり中立ではなく、実質的にソ連側に立っていたのである。ソ連を攻撃するということは、日本が米国の敵となることを意味するから、対米戦を避ける方法とはなり得ない。また日ソ中立条約を破ることになる。現在の日本は、ソ連の条約破りを批判することができる立場にあるが、これをソ連、ロシアが無視して正当性を主張できるのは、勝者の側にあるからである。ナィーブな日本人は、たとえ勝者となっても、中立条約破りを正当化するほど外交巧者ではなかろう。
ハワイはフィリピンとは異なり、本土に準ずるからハワイを攻撃せず、植民地のフィリピンを攻撃すれば米国の矛先は鈍る、という説もある。これとて、メキシコ領に勝手に作ったアラモ砦に立てこもった米国人を全滅させた、ということを米墨戦争の口実とした米国にとっては、植民地か否か、ということも問題外である。米国領を避けて蘭印すなわちインドネシアの油田地帯だけを攻撃すればよかったという説もある。
尊敬する憲政史家の倉山満氏は「石油が欲しいなら、オランダ領インドネシアにだけ進駐すればいい話です。・・・当時のアメリカは石油会社の利益を守るために戦争を起こせるような国ではありません。」(嘘だらけの日露近現代史P209)と書く。しかし、支那事変に対して中立国のはずの米国が、援蒋ルートを遮断する目的でペタン政権と合意の上の仏印進駐にさえ、通商条約破棄や経済封鎖といった、事実上の宣戦布告行為をしている。経済封鎖を打破する目的の蘭印占領に反応せぬはずもない。
一部の人たちがいう、ハルノートは宣戦布告でも何でもないから無視すればよかった、というのは論外である。既に米国は石油の禁輸など、宣戦布告に等しい挑発行為を、いくつも繰り返していたからである。蘭印を占領すれば、米国はフィリピンから対日通商破壊をするから、結局日本はフィリピンを占領せざるを得ないのである。
これらの説は全てルーズベルト大統領が、参戦しない、という公約に拘束されて日本が直接米国を攻撃しない限り、対日戦争は始められなかった、という言説が事実である、という前提に立っている。ところがどうだろう。これはルーズベルト政権は対独戦と直接関係なく、対日戦を欲していた、ということを忘れている。「『幻』の日本爆撃計画」という米国人の著書によれば、ルーズベルト大統領は、300機の大編隊で日本本土を爆撃する計画を立案させ、実行に着手しつつあった、ことがわかる。
もちろん機体には中華民国の国籍標識をつけ、搭乗員たるアメリカ人は義勇軍として参加する、というものである。いくら義勇軍だと言い張っても、国際社会はもちろん米国民自身が本気にするはずはない、田舎芝居以下の見え透いた嘘である。結局爆撃機を英国に回すため機材が不足して爆撃自体は実行されなかったのだが、「計画は実行を開始していた」というのは、有名なフライングタイガースという日本軍と闘った「義勇軍」戦闘機部隊はは、爆撃計画の一部の爆撃機護衛飛行隊として派遣されたのであったからである。
既に、米国は前述のレンドリース法や大西洋への駆逐艦派遣とUボート攻撃などの実質的参戦行為を行っている。問題は爆撃計画もこれらの実質的な参戦行為も、国民に秘匿されていたどころか、マスコミに公表されていたのである。もちろんレンドリース法は議会を通過しているから、過半数以上の支持者が賛成していたのである。これらの事から、米国民は参戦反対であったという、世論調査の結果はうのみにしできない。
これらに対して、チャールズ・リンドバーグ(初の無着陸大西洋横断飛行の成功者)などの少数の例外を除いて、米国民や識者の間から公約違反だという、大統領非難の激しい議論が起こったということも聞かない。ルーズベルトや取り巻きの共産主義者が、支那の共産化のために陰謀を巡らせて、支那事変や対日戦争を陰謀したという説は尤もであるが、ここまで公然とやられれば、陰謀にはならない。結局米国民は建前はともかく、対独、対日戦争を心底では望んでいた、としか私には考えられない。だからハワイ以外でも、日本の東アジア諸地域への侵攻があれば、「リメンバー・パールハーバー」という合言葉がなくても米国世論は戦争への興奮で沸き立ったのに違いないのである。
この傍証として、例えば福富健一氏の「重光葵」に「・・・当時のアメリカ世論は日本人への怨嗟で満ちていた・・・」(P103)というように、1924年に成立した排日移民法が語られている。当時の日本人移民は、年間二百数十人に過ぎなかったから、米国民の怨嗟というのは、支那人のように蝗のごとく大量にやってくる民族移動に対する恐怖ではなく、劣等であるはずの有色人種である日本人が、ロシアを破り、米国国内にすら脅威を与えている、という恐怖心である。白人と対等な能力を持つ唯一の有色人種の日本人が、米国内でこれ以上増殖することに危機感を抱いたのである。
昭和天皇が排日移民法が、日米戦争の淵源であると語っておられるのは、同法に日本人が反発したことが原因である、というのではなく、その時点で、排日のための対日戦争の可能性を米国民が漠然と脳裏に描いていたことが原因である、と考えておられた、ということではなかろうか。日米交渉が困難になった時点でも、日本政府も国民も対米戦争の可能性を低く考えていた、あるいは望まなかった、という事実からも、排日移民法への反発が日本側からの対米戦につながっていると考えるのは無理がある。
米国が対日戦を望んでいたのは分かっていたはずである、というのは結果論のようであるが、そうではない。事実前掲の「『幻』の日本爆撃計画」によれば「アメリカの意図を理解するのに、日本は手の込んだスパイ組織の助けなど必要としなかった。1941年の秋には、日本爆撃計画はアメリカの活字メディアで広く報じられていたからだ。(P239)」というのである。日本人は外交官でなくても、欧米の新聞をチェックしていた知識人や政治家もいたから、その程度の公開情報は入手可能であった。公表されたマスコミ情報だけで、これらの事実は分かるからである。例えば駐米大使館が米国マスメディアの分析さえしていれば分かるからである。
多くの識者が論じているので一言だけしておくが、山本五十六司令長官が、真珠湾で太平洋艦隊を壊滅させれば、米国は戦意喪失して早期講和に持ち込めると、もし本気で信じていたとすれば、あまりにも戦史や国民性を知らなかったと言わざるを得ない。それ以前の米国の対外戦争は例外なく、事の大小、陰謀の有無を問わず、敵が最初の一発を売ったことを口実に始められてているからである。山本自身が戦艦の撃沈で満足して、徹底した破壊を行わずに艦艇の損失を最小限にして(艦隊保全)帰還することを許していることから、その後も簡単に戦争は終わらないと漠然と考えていたのであろうとしか、思われない。
脱線が長くなったが、対米戦が避けられなかったとすれば、いかに開戦すべきであったか、ということを論じる前提を述べたのである。第一に真珠湾攻撃だけが戦争に向かって米国民を団結させた原因ではない、とすれば真珠湾攻撃の可否や時期、方法等は軍事的にだけ考えればよいのである。
米国の対日戦の要石となるのは、真珠湾である。対日戦への補給や出撃は、ほとんど全て真珠湾を経由している。艦艇もすべて真珠湾を経由して移動しているからである。つまりハワイからこれらの機能を喪失させればよいのである。そのための一つの方法が、艦上機による工廠、港湾施設、石油タンクなどの施設の徹底した破壊である。艦上機による艦艇の攻撃はせいぜいそのおまけである。戦艦攻撃に全力を注いだのは、海軍首脳は山本長官を含め、戦艦を中心とした大艦巨砲主義で、戦艦さえ殲滅すれば、将来起こるべき艦隊決戦に勝てると信じていたからである。
余談になるが、い号作戦で空母の艦上機まで陸上に上げて、米艦船を撃滅しようとした山本長官は、やはり艦隊決戦思想の域を超えていないと思われる。艦上機搭乗員があたら消耗して、艦船攻撃をさせたのは、航空機を単なる消耗品として扱い、消耗により敵艦が少しでも減殺できればよいと考えた証左に思われる。きたる艦隊決戦に勝つためには、決して空母を主力艦たる戦艦のための、暫減作戦の道具としか考えていなかったのである。むしろ、ミッドウェー敗戦により、信濃を空母に切り替えた、山本以外の軍政の連中のほうがある程度切り替えが出来ていたのである。
ただし、それが海軍として正式に戦艦を中心とした、艦隊決戦思想の転換として決定された形跡はない。ただ、ミッドウェー海戦の敗北の後、大和型4隻と超大和型2隻を中心とした、㊄計画は中止になった。しかし、これは建艦計画の変更であって、これに伴う艦隊決戦思想の変更と言うものは、明記されていった形跡がない。いわばなし崩しに、空母中心の戦闘法に転換していったのである。
閑話休題。ハワイの空襲部隊への援護に随伴した戦艦は霧島と比叡だけだったが、せめて米太平洋艦隊と同数の長門以下の戦艦を出撃させ、随伴した巡洋艦による施設への艦砲射撃と、真珠湾から艦船を、戦艦等により攻撃するのもひとつの方法である。
実際に、ハワイに出撃しなかった8隻の戦艦のうち、金剛と榛名だけが南方作戦に支援として出撃していたが、長門以下の6隻は柱島に停泊し、「トラ、トラ、トラ」の一報を受信すると、山本に命じられて豊後水道を通過し、小笠原付近までのこのこ行って何もせずに帰ってきた。「私論連合艦隊の生涯」を書いた元海兵の豊田譲氏ですら、ある下士官の口を借りて「勲章をもらうための行動」と揶揄している。余った戦艦はあったのである。勲章を分け与えるための無駄な出撃、と言う発想こそ、山本が武人ではなく、典型的な官僚であることを示している。
山本五十六の連合艦隊司令長官はミスキャストである、と断言する説があるが、まさに、その通りである。それにしても前述のように、山本が米国の戦史について不勉強であった、ということは、官僚としての資質も疑わせる。山本が対米戦に反対した、というのが事実であったとすれば、対米戦を根拠に予算をぶんどり続けた海軍とはいかなる存在であったのか。
山本自身は対米戦に反対した、ということで好印象を持たれているが、その一方で、ロンドン軍縮条約に随員として参加した際、強硬に対米七割を主張するばかりではなく、予算の不足を説明する大蔵省職員に、暴力的恫喝を加えている。対米七割とは対米戦の主張だから、明らかな矛盾である。海軍にとって対米戦とは、予算獲得の方便であって、まさに悪しき官僚的発想に他ならない。
大東亜戦争における海軍の攻撃法は、航空機だけ、あるいは艦艇だけのいずれかだけの攻撃によるものがほとんどで、これらをミックスした複合的な攻撃が滅多にないのを不可解に思うのである。攻撃レンジと破壊力で、双方は補完の関係にあるからである。第三次ソロモン海戦では日本側は艦艇しか出撃していないが、米側は航空機が活動できる、昼間になると、航空攻撃による掃討戦を行っている。
ハワイ攻撃を行うとすれば、時期であるが、実際に行ったように開戦劈頭でなければ、攻撃は困難となるから開戦時である。後は定期的に米本土からの補給や施設の修復の妨害が必要である。そうすれば、人員や機材、燃料などの補給が亡くなるから、米潜水艦による日本軍の補給阻止の跳梁も格段に少なくなる。こうすれば、早期の対日反攻は極めて困難となる。その後であるが実際にも日本軍が悩んだように、第二段目の作戦が最も悩ましい。そのヒントはドイツとの連携によるイギリスの屈服ではなく、東アジアの植民地の独立であると考える。
小生の言う、真珠湾攻撃の主目的は、施設の破壊による無力化である。当然、在伯の太平洋艦隊は出撃してくるであろうから、それに対する迎撃は必要となる。そこで行われるかも知れない海戦は、結果であり目的ではない。ミッドウェー攻略が、山本自身は真珠湾攻撃で打ち漏らした空母の撃滅であり、軍令部も将兵も敵空母は出てこないだろうから、簡単に上陸できるだろうとふんでいたとしたら、意識の隔絶も甚だしい。例え容易に攻略できても補給が続かない、と軍令部はふんでいた、というのだから、何が何だか訳が分からない。山本も軍令部も緒戦の勝利に奢っていたのである。特に山本は奢りに加え、B-25による本土奇襲に狼狽していたのである。
⑥真珠湾対策の遠謀
なぜ、米国はハワイ王朝を倒して併合したか。ハワイ併合は複雑な経緯を経て、1900年に併合された。日本はこの動きを牽制するために、邦人保護を名目に東郷平八郎率いる浪速他の小艦隊をハワイに派遣したが、結局流れを止めることはできなかった。日本が明らかな牽制的行動に出たのは、ハワイがアメリカのアジア進出の中継基地となることを恐れたからである。これはまっとうな判断である。
日露戦争の前に、既にしてアメリカはこのような行動に出ていたのである。日露戦争が終結して、比較的日露の中が平穏になると同時に、ロシア海軍の脅威が皆無になると、日本海軍は官僚的発想から、予算獲得のためにアメリカを仮想敵国とした。ロシア艦隊が全滅したとなれば、仮想敵海軍は、太平洋を挟んで向き合っている米海軍しかいなかったからである。だが実際に、米国は上述のように太平洋を越えてくることを予定していたのであるし、日露戦争後、急速に対日感情が悪化し、米海軍も日英海軍を想定して戦備していたと考えられるから、対米戦備の充実は結果的に正解であろう。
ところが理解しにくいのは、対米戦備といっても、日本海海戦の結果だけからフィリピン沖あるいは、小笠原沖といった近海で一回限りの艦隊決戦で雌雄を決する、という想定をしたことである。日露戦争の海戦は一回限りではなかったことはすっかり忘れられているように思われる。
イ400型潜水艦は大西洋からパナマ運河を経由して廻航される艦艇を阻止しようというのであるから、廻航や補給の阻止という発想は存在したのである。しかし、同艦や搭載機の設計時期から見て、大東亜戦争勃発よりよほど前に構想されたのではあるまい。考えてみれば、回航の中継地点としては、ハワイの方が遙かに近く、他に代替手段がなきに等しいという点でも、パナマ運河と同様に重要である。
唯一、少ない攻撃力で機能を喪失させることができる、という点でパナマ運河の方が選択されたのであろう。また構想された時期が遅かったのも、潜水艦や搭載機の技術の発達に合わせた、というべきであろう。いずれにしても、今日残っている証言等では、ハワイの中継地点としての機能阻止、という構想はないようである。
しかし、ハワイ併合が行われた時点で、対日戦の際にハワイが太平洋艦隊の母港となることは予測されたはずである。また東海岸から、西海岸を経由しての回航基地となることも予測できたのである。まして時代が古ければ、艦艇の航続距離も短いから、なおさらハワイはパナマ運河より重要である。それなのに、日本海軍はどちらの想定もしなかった。単にハワイに太平洋艦隊が常駐すると、その戦力だけに注目してあせったのである。
従って軍艦と海軍機のスペックも、ハワイを攻撃対象とする想定をしていなかった。日本海軍の主力艦の航続力は、米海軍のそれより、よほど短かった。陸攻には、大きい航続距離が求められたが、あくまでも艦隊が島嶼に近づいたら、発進して攻撃する、という想定だった。陸上基地は移動できないから、大きな航続距離は必須なのである。ところが、日米交渉が難航すると、連合艦隊司令長官となっていた山本五十六は、突如として空母による真珠湾在泊の太平洋艦隊の撃滅を構想した。空母の実力が未知数である上に、艦艇等のスペックが真珠湾攻撃を想定していないから、軍令部がこぞって反対したのは当然であって、連合艦隊司令部内でも反対者の方が多かったと推定される。
真珠湾攻撃を強行したから、山本は一般的に航空戦力重視だと思われている。だが、彼の経歴と、その後の作戦を見る限り、陸上機、特に陸攻の艦艇攻撃力を重視したのであって、空母機動部隊を重視したのではなかったと考えられる。真珠湾攻撃直後で空母に余裕が無かったこともあるが、マレー沖海戦では英艦隊攻撃に陸攻を使用して自信を深めた。その後本格的に陸上基地からの対艦船攻撃を継続した、い号作戦でも空母搭載の零戦を陸上に上げて、陸攻の援護に当たらせている。艦爆も陸上に上げている。消耗戦で、高い技量のあるベテランの艦上機の搭乗員を多数消耗していった。
緒戦で押されていた米軍は、エンタープライズなどの空母の機動性を生かして、ゲリラ的に使用して、日本軍を悩ませた。反対に山本には空母が自在に移動できる航空基地である、という特性を効果的に使うという「空母機動部隊」の考えはなかったとしか思われない。結果から判断すれば、山本も航空機を主力艦の漸減作戦に使用する、という日本海軍一般の発想しかなかったと思われる。ハワイ攻撃も空母や艦上機を消耗しても、主力艦を撃滅すればよい、と言う発想だった。ハワイ攻撃のシミュレーション結果は、空母にかなりの損害が出る、という結果なのに強行したのである。山本長官の考える航空攻撃の主力ははあくまでも陸攻だった。
閑話休題。小生は、日本海軍が仮想敵国を米国に設定しながら、真珠湾にいずれ来るだろう、太平洋艦隊の撃滅と回航基地としての機能停止の手段を、永年何も検討していなかったことに疑問を呈しているのだ。このテーマは、必ずしも真珠湾を直接攻撃することが手段となるとは限らない。方法によって、そうである場合も、そうでない場合もある。
日露戦争の開戦は旅順艦隊攻撃から始まった。ひとつの例としてこれに倣うなら、日米開戦の海戦は米太平洋艦隊攻撃から始まるだろう。それに合わせて航続力などの艦艇のスペックが決まる。回航基地としての機能停止が必要だとすれば、真珠湾への攻撃は一度では済まないかもしれないし、手段は真珠湾の直接攻撃手段ばかりではなかろう。
結局小生の疑問は、早い時期から想定された、真珠湾の太平洋艦隊の根拠地化、と米本土からの回航基地化がありながら、何の検討もせず、いざ開戦となった途端に、一年程度の短期間で、真珠湾の太平洋艦隊を湾内で、艦上機で撃滅する、という案が突然浮上実行されたということである。付け焼刃で、艦艇のスペック不適合による真珠湾攻撃の困難さを克服して、とにかく攻撃を成功させることにしか連合艦隊の努力を集中するしかない。敵基地攻撃と言うのは、何らかの目的達成のための方法である。ところが突如として連合艦隊にとっては真珠湾の太平洋艦隊を攻撃すること自体が目的化したのである。
真珠湾攻撃を永年研究してきたのなら、対米戦における、メリット、デメリット、南方攻略との関係などなど研究できるのに、これらは一切顧慮されることがなかった。
⑦真珠湾攻撃は無理な作戦だった
空母による真珠湾攻撃は、元々無理なことが分かっていた作戦であった。前述のように事前の兵棋演習で、相手に損害を与えることができても、空母部隊にも甚大な損害が出るとの予想であった。まともに考えれば、これが正しいのである。米政府自身は、日本の真珠湾攻撃計画を知っていたにしても、知らなかったとしても、日本にどこかで先制攻撃をさせる、という方針であったのは厳然たる事実である。
真珠湾と特定されていなかったとしても、12月1日以降、日本軍がどこかに奇襲をかけてくるとの予想はあったのである。それが真珠湾なのかフィリピンなのかは不明でもよい。デフコンをあげて、全軍に相応の準備をさせておけばよいのである。現に特殊潜航艇は航空攻撃前に、ほとんどが米艦艇の先制攻撃によって撃沈されている。例えば巷間言われるように、真珠湾攻撃計画を知っていた、ということが事実であったとしても、米軍は日本の航空技術をなめきっていて、真珠湾の浅海で航空機による雷撃が可能であるとは夢にも思っていなかったから、真剣に航空攻撃への対処を考えていなかったであろう。
米空母の攻撃法は雷撃よりも急降下爆撃を重視していたが、これは撃沈しなくてもよいから、相手にダメージを与えて戦闘能力を奪えれば良い、というものである。戦艦や空母などの大型艦を艦爆の爆撃だけで撃沈は出来ない、と考えていたのは正しい。
いわゆるデフコンは、真珠湾攻撃時点では、既に平時ではなかった。米軍が体制を整えた時の防空能力は、第一波攻撃より第二波攻撃の方の被害が格段に多かったことでも知れる。米軍は、日本軍の戦闘能力をなめていたし、政府は第一撃を日本に打たせるという方針であった。日本軍の先制攻撃による被害は少ないにこしたことはないし、開戦の理由としてはとにかく日本による先制攻撃あればよかった。
米西戦争の引き金となったメイン号爆沈は、スペインによる攻撃かどうか判然としないのに、とにかく米艦が沈没したのだから、スペインが関係している、と言うことになって「リメンバー・メイン」という標語に国民が沸き立った。真珠湾でもフィリピンでも、日本軍が攻撃してきて、少しでも被害を受ければいいのであって、撃退しても構わなかったのに違いない。攻撃されても、大した被害は受けないと考えたのである。
また米国世論が沸き立って、厭戦から一気に参戦に傾いた要因は真珠湾攻撃前に、宣戦布告前に日本軍が攻撃したということであり、駐米日本大使館による宣戦の通告の遅れの罪は大きい、というのであるが、これには異説がある。誰の説か記憶にないのは残念であるが、海軍は最初に述べたように、宣戦布告後に米軍に体制を整えられて攻撃すると、失敗するという判定が出ていたから、外務省に頼み込んで(?)故意に通告を遅らせて、完全な奇襲となるようにした、というのである。もし、著書を見つけたら正確な記述も含めて報告することとしたい。
これは状況証拠だけで、確証はないようである。通説では、宣戦布告なりの重大な電文が来るだろうと予測されたのに、のんびり送別会をしていたなどの怠慢によって文書の手渡しが遅れたのは、信じられない失態である。そして、当時ハワイにいて大失策を犯した外交官たちが、揃いも揃って戦後大出世したのも信じられない、という。
そこで、文書の手渡しの遅れが故意だとすると、これらのことは不思議でも何でもなくなる。確かに当時の責任感ある外交官が、送別会ごときで致命的ミスをすると考える方がおかしい。そもそも、のんびり送別会などしている時ではない。送別会にかこつけて文書作成を遅らせたとも考えられるのである。海軍と外務省本省が組んでいたのなら、現地外交官の失策を責められない。それどころか、失策を責めれば彼等は秘密を漏らすだろう、というわけである。
米政府がそのことに気づいていたかどうかは関係ない。気付いていたとしても、都合が良いから放置しただろう。米政府は、日本の侵略政策を言い募るために、故意に陸軍悪玉、海軍善玉説を流し、海軍の元幹部もそれに便乗した。山本五十六や米内光政らが、真珠湾攻撃成功のために、外務省との取引に賛成しただろうと考えても不思議ではないし、知らなかったすれば不可解である。
さらに問題なのは海軍全体が、真珠湾攻撃の僥倖を実力と勘違いしてしまったことである。そしてポートモレスビー攻略やミッドウェー攻略は簡単、と自信を持ったことである。ミッドウェー海戦前、第一航空艦隊の幹部が、米空母など鎧袖一触などと豪語したのは知られている。しかし最前線のパイロットは、既に真珠湾攻撃や珊瑚海海戦以来の体験で、米軍の防空能力の高さを身を以て知っていたのである。
開戦当初は日本海軍にはまだ僥倖があった。マレー沖海戦で、英軍が空母の都合で英艦隊に随伴できず、航空支援をできなかったことである。もし、数機の戦闘機が艦隊防空にあたっていたら、陸攻は次々と撃墜されて、撃沈どころなかったであろう。それにしても、英艦隊の対空防御能力の無さは、同時期の米海軍に比べ、呆れるばかりである。
さらに当然であるが、宣戦布告前に英植民地の方が先に攻撃されたのに、英国は騙し打ちなどと言わず、淡々と対日戦を開始した。例え奇襲攻撃であろうとなかろうと、米国政府は先に発砲したことを持って、米国民を扇動したに違いない、という傍証である。
⑧東條総理は真珠湾攻撃を承認していない
「日米戦争を起こしたのは誰か」と言う本は、フーバー元大統領の回顧録を中心に、ルーズベルトの失政により、ソ連に漁夫の利を得させ、東欧の支配など一連の戦後の悲劇を引き起こしたことなど、多くの有意義な内容がある。しかし、1点だけ看過できない間違いがあるので、それだけを指摘しておく。
「真珠湾攻撃は、戦術的には大成功であったが、戦略的には取り返しのつかぬ超大失敗であった。これを立案実行した山本五十六と、これを承認した東条英機の愚は、末永く日本国民の反省の糧とならねばならない。(P170)」(藤井厳喜著)とあるのだ。
真珠湾攻撃の評価はさておく。図上演習ではそれなりの戦果は挙るものの、攻撃部隊が全滅に等しい被害を受ける結果となって、軍令部内で猛反対が起きたのを、山本五十六が強引に実行したことは良く知られている。しかし、東條は、真珠湾攻撃を実行することすら事前に知らなかった、という説を読んだことがあった。
そこで「東條英機宣誓供述書」で確認することにしたが、書架に見つからない。かなり以前に読んで、各項ごとに自分なりのメモを作っていたが、それも見つからない。そこで平成18年出版の「東條英機歴史の証言」(渡部昇一著)掲載の宣誓供述書でチェックすることにした。ページ番号は本書による。
「昭和16年12月1日の御前会議で開戦の決定をし、開戦までの重要事項は海戦実施の準備とこれに関する国務の遂行の二つである。ただし「前者は大本営陸海軍統帥部の責任において行われるものであって、」政府は統帥事項には関与できない。「唯統帥の必要上軍事行政の面において措置せることが必要なものがあり」これには陸軍大臣として在任期間における行政上の責任があるが、海軍に関しては陸軍大臣あるいは総理大臣としても関与できない。日本特有の統帥権独立の制度があり「・・・作戦用兵の計画実施、換言すれば統帥部のことについては行政府は関与出来ず、従って責任も負いませぬ。」という。
このことは戦前の日本の統帥制度を知る者には常識であり、総理大臣である東條にはそもそも真珠湾攻撃という海軍の作戦を承認する権限がないのである。だから本項のタイトルは「東條総理は真珠湾攻撃を承認できない」と書くのが正確であろう。
これで間違いの指摘としては十分であろうが、東條はいつ真珠湾攻撃計画を知ったのだろうか。これは供述書の記載では不分明であり、「開戦の決意を為すことを必要とした・・・之がため開かれたのが十二月一日の御前会議であります。」とあるだけである。
前掲書の渡部氏によれば東條は陸軍大臣在任中、大本営の会議に列したことは一回もなく、それではまずいというので、昭和19年になってようやく陸相と参謀総長を兼ねた、という。11月27日の連絡会議でハルノートに対する態度を決め、12月4日の連絡会議で外相から通告文の提示があり、「・・・取扱いに付いては概ね以下のような合意に達したと記憶します。」とあり、合意の内容が記載されている。
その後に「真珠湾攻撃其の他の攻撃計画及び作戦行動わけても攻撃開始時間は大本営に於ては極秘として一切之を開示しません。・・・私は陸軍大臣として参謀総長より極秘に之を知らされて居りましたが、他の閣僚は知らないのであります。」と書かれている。東條は参謀総長から、非公式ルートで聞かされたのに過ぎない。従って東條が真珠湾攻撃計画を知ったのは、11月27日~12月4日の間位であろう。既に艦隊は真珠湾に近づいていた。時期から推するに、真珠湾攻撃計画決定はおろか、出撃時点でも何も知らなかったのであろう。
権限からも時間的にも、東條が山本の「立案実行を承認した」ということはあり得ない。気になるのは藤井氏が「東條」ではなく「東条」と書いていることである。東條本人が気にする人物かどうかは別として、旧字でないは変であろう。侮蔑的なにおいがするのである。実は小生も恥ずかしながら昔は「東条」と書いていた。しかし、旧字体が正しいことに気付いてからは「東條」と書いている。小生は藤井厳喜氏は東京裁判史観に捉われない、まともな史観を持っていると考えている。その氏にして、東條に対する、このような偏見を無検証で書いている。書きなぐっているのに近い。東條氏に対する誤解が益々広がる所以である。
渡部氏は日本外交史の書を多く著している、岡崎冬彦氏が「戦争の勝負を別とすれば、東條さんは日露戦争の首相桂太郎より偉いだろうという主旨のことを言って」おられたのは卓見である、と書いている。現代人で東條をここまで評価するのを寡聞にして知らない。小生は日本の昭和史上の人物で、東條英機を昭和天皇の次に尊敬しているから、嬉しい評価である。
⑨真珠湾の無力化
真珠湾を無力化することが、対米戦にとっていかに重要かは、既に述べた。これらは主として真珠湾の施設を破壊して、米本土から西太平洋戦域に対する、中継機能を喪失させる、というものである。これは山本連合艦隊司令長官の真珠湾攻撃が、あくまでも主力艦の撃沈による将来の、艦隊決戦を有利に使用、というものであったこととは、全く異なる。亀井宏氏は(1) 「・・・山本大将みずからが、空母および航空機を海上戦闘の補助兵力-もっといえば、消耗品であるという考えにとらわれていたからこそ、思い切ってそのすべてを使用することができたのである。先見の明があったといわれる山本長官ですらそうであったのだから・・・」と言っているが、その通りであろう。
だが真珠湾を無力化するには、必ずしも直接攻撃する必要はない。ジェームズ・B・ウッド氏が(2)好例を示している。米軍による日本の艦船撃沈の戦果は、航空機によるものより、潜水艦の戦果の報が大きかったこと、日本海軍は有力な潜水艦を保有していたのにもかかわらず、戦力に見合った戦果をあげなかった、という有名な戦訓が下敷きになっている。
要点は下記の通り。
イ.日本の潜水艦の損失の大部分は、万全に護衛された米空母や潜水艦の周辺海域、充分な防御体制の艦隊停泊区域に対する攻撃によるものである。
ロ.日本軍と同様に、アメリカ軍も兵士や、弾丸、燃料の全てを、海上ルートで太平洋戦線に補給しなければならなかった。
ハ.海洋ルートは、サンフランシスコを出発するか、東部からはパナマ運河経由でなければならなかった。目的地は、真珠湾、オーストラリア、南太平洋の島嶼に限られていた。従って「米軍の兵站ルートは、予測可能な海洋ルートに限定されていた。「米軍戦力はガダルカナル島に海兵隊一個師団の一部を維持するのに苦労をしていた(P154)」というのである。すなわち米軍ですら兵站には苦労していたのである。
ニ.それゆえ、「真珠湾攻撃の直後、日本海軍は、すべての大洋航行型と艦隊型潜水艦をハワイ海域と米国本土西海岸沿岸に集中させるべきであった。・・・潜水艦は、西方へ急ぎ派遣される米軍増援艦隊の進行を効果的に邪魔することができたであろうし・・・一九四二年の初め頃には、日本軍潜水艦は、真珠湾攻撃で被った損傷を本格的に修理するため、本国へ帰国途上の米軍艦を攻撃するのに理想的な場所にいたはずであった。」
ホ.真珠湾での潜水艦作戦の失敗の後、日本の潜水艦部隊は、ハワイの潜水艦による攻撃の困難さを指摘し、「潜水艦は、商戦を攻撃するための兵器」であると報告したが取り上げられなかった。戦争の終わり頃日本海軍はそのことにようやく目を向けたが、その時は既に潜水艦の多くを損失した上に、米軍の対潜戦能力は飛躍的に改善されていて、時既に遅かった。
ウッド氏の指摘は小生が言いたいことを全て言っている。氏は日本の潜水艦が、いくつかの長所がある半面、大型故に潜航に入るのが遅いとか、魚雷の射撃計算機が低精度であるとか、レーダーを持たないなどの欠点はあるものの、大戦前半ならば、効果的に商船攻撃が出来、多くの潜水艦を消耗しても、戦局を変えることができたから犠牲に値する、と指摘している。
日本の戦史は、ガダルカナル争奪戦以降、日本軍が米軍の妨害による補給に苦労したことばかり書いて、大戦末期になってようやく海上護衛部隊が編成されたのは遅きに失した、と批判する。しかし客観的には米軍の報が兵站距離が余程長く困難であり、補給の妨害は日本海軍にとっては容易であった。
氏によれば米軍は一九四二年時点で日本潜水艦が補給の商船攻撃に出ることを恐れていた、というのだ。自分が困ることは、相手にとっても困ることでもある。日本軍は南方への補給妨害に散々苦労したにもかかわらず、米軍にも同じ苦労を強いることができるのに気付かなかった。早い時期にハワイ等への補給阻止に出ていれば、米軍の反抗は困難になるのみならず、潜水艦による日本軍の補給阻止も困難となるから、戦局は画期的に日本軍に有利になったであろう。
ちなみに、伊58潜に撃沈された、インディアナポリスは、原爆を運搬するために、サンフランシスコ近くから出発し、真珠湾を経由して、目的地のテニアン島に到着した。真珠湾は西太平洋の戦域に到達するには、欠くべからざる軍港なのである。
(1) 「歴史群像」太平洋戦史シリーズNo.4「ミッドウェー海戦」
(2)「太平洋戦争」は無謀な戦争だったか・ジェームズ・B・ウッド・茂木弘道訳
2.海戦
2.1 ミッドウェー海戦
①無駄なダッジハーバー攻撃
ミッドウェー攻略の陽動作戦として、ダッジハーバー攻撃と、アッツ、キスカ島攻略を行ったのは何重の意味で無駄どころか浪費であった。珊瑚海海戦でミッドウェー作戦に瑞鶴、翔鶴が参加できないため戦力が不足しているところに、陽動作戦に小型空母とはいえ二隻を割いたのであった。
しかも陽動作戦にひっかかったことを、レイテ沖海戦のように牽制に成功した場合に連絡する手配もしておらず、単に時間差攻撃を行うという形式的なものであった。牽制なら牽制の対象になるものがあるはずであるが、そもそもそれがない。ミッドウェーには115機の有力な基地航空機が待機していたが、これらは陽動作戦の対象になるはずもない。
ミッドウェー作戦は、あわよくば米空母部隊を呼び寄せて撃滅する腹であったとされる。とすればアッツ、キスカ攻略に空母牽制の意図があるはずがない。ミッドウェー攻略に役立たない練度の低い改装空母を体よく障害の少ない作戦に回したとしか考えられない。戦力が余っていると考えたとしか思われない分別のない作戦である。
しかもミッドウェー攻略に失敗すると敗戦を糊塗するために、アッツ、キスカを占領し続けてアッツ島玉砕という犠牲を払い、キスカ撤収作戦にさらなる戦力をつぎ込んだ。作戦が失敗して戦力が大幅に低下したのだから、更なる無駄は省かなければならないというのにである。
②ミッドウェー海戦の体制の不合理
ミッドウェー海戦に対する現在までの評論には、考えてみれば妙なものがある。南雲艦隊は、空母発艦のヘルダイバー艦爆の攻撃の何時間も前に、B-26爆撃機の他に、陸上から発進したTBF艦上雷撃機の攻撃を受けている。情報がないなら、これは空母からの攻撃の可能性が大であると解すべきである。いくらミッドウェー島付近には空母はいないと寝ぼけていた南雲艦隊も慌てなければ変である。この時点で、空母索敵に力を入れもせず、艦船攻撃兵装に切り替えていないのだから、空母に備えよと言う連合艦隊の命令などあったのだろうかと疑われる。
ミッドウェーの敗因は、兵装転換によるものではないと明瞭に立証した、左近允氏でさえ、艦上機の半数は連合艦隊司令部の指示に違反していた(ミッドウェー海戦P146)と指摘しているが本当だろうか。氏は兵装転換自体を命令違反とするのだが、元々半数を空母に備えよ、という命令があったのなら、各空母の艦上機の半数を艦船攻撃兵装にしておくということは後述のように不合理で、常に半数の空母を艦船攻撃の兵装にしておく、ということが、運用上も敵襲時の対応にも最も合理的だからである。
つまり南雲艦隊は、出撃時点から全空母の艦上機を陸上攻撃の兵装にしてあり、空母出現の際に全空母に艦船攻撃の兵装転換を命令したのである。もし連合艦隊司令部が、常に半数の艦上機を空母出撃に備えよと命令したのであれば、出撃前にその編成の確認をしていないと言うことは考えられないのである。確認していなければ、無能か作戦をなめきっていた、ということで軍事的には信じられない行為である。
具体的にはこうである。一隻の空母の半数の戦闘機、爆撃機、攻撃機の半数を艦船攻撃兵装で待機させたとする。戦闘機は艦船攻撃でも陸上攻撃でも同じであるが、残りはそうではない。だから半数の艦船攻撃部隊を、飛行甲板におき陸上攻撃部隊を格納庫に置けば、陸上攻撃はできない。逆にすれば、艦船攻撃はできない。後者の場合は、艦船攻撃に邪魔になる陸上攻撃部隊を発艦させてしまって、格納庫から艦船攻撃隊を上げていて発艦させていたら、五分や十分では攻撃態勢はできない。どう考えても、各空母毎に、半数を艦船攻撃兵装で待機させたら、即座に艦船攻撃に切り換える、ということは不可能である。
③ミッドウェー半数待機の疑問
ミッドウェー海戦では山本司令長官の命令で、搭載機の半数を敵空母出現に備えて待機させた、ということであった。ウィキペディアによれば、真珠湾攻撃の時点での搭載機合計は、補用機を含め、255機である。一方是本信義氏によれば(1)、ミッドウェー攻撃隊は108機で、対機動部隊待機も山本大将の厳命により108機とある。また是本氏による日本側航空機330機には、戦艦などの艦載機も含むのであろう。
255機との差は39機となるが、これは補用機、艦隊防空機などであろうか。ウィキペディアによるミッドウェー島第一次攻撃隊の編成は各艦の出撃機数は赤城27(9,0,18)、加賀27(9,0,18)、飛龍27(9,18,0)、蒼龍27(9,18,0)、となっている。カッコ内は、各々零戦、九七艦攻、九九艦爆である。これは是本氏の合計と一致する。すなわち赤城と加賀は搭載の艦爆の全機、飛龍と蒼龍は搭載の艦攻の全機が出撃したことになる。
また、赤城の項には、待機の九七艦攻は全機が魚雷を搭載しており、第一次攻撃隊出撃後飛行甲板上に上げられ、機動部隊攻撃待機をしていたとされている。加賀も同様であったろうし、飛龍と蒼龍の九九艦爆は全機が対艦用爆弾を装備して、飛行甲板上に上げられたのであろう。
真珠湾攻撃の際には第一次攻撃隊は第一波と第二波に分け、半数づつ攻撃隊を発進させている。これは飛行甲板に全機を揃えて発艦させられないための処置である。第一波が発艦し始めて、飛行甲板にスペースが出来始めると格納庫に待機していた第二波の機が上げられ、第一波全機発艦後しばらくすると、第二波全機が飛行甲板上に整列できて一斉に出撃したのだろう。
ミッドウェー攻撃では、これに準じて、真珠湾攻撃の第一波と類似の編成で、地上攻撃の第一次攻撃隊を出撃させた。そして、是本氏によれば、第二次攻撃の要あり、という無電(〇五三〇)により待機機の兵装を対艦用から陸用に転換したが、利根四号機からの敵機動部隊発見の報(〇六三〇)により、混乱したが、結局第一次攻撃隊収容後、待機機を再度対艦用兵装に転換して一番機発進の直前に急降下爆撃を受けた(一〇三〇)と言うのである。
ウィキペディアの言う、第一次攻撃隊が発艦したらすぐに待機していた機動部隊攻撃隊を飛行甲板に整列させた、というのは運用上煩雑となる。こうすると、待機機が飛行甲板上にいる限り、帰還した第一次攻撃隊は着艦できない。第一次攻撃隊は往復約二時間しかかかっていないから、飛行甲板に待機機を上げてから、二時間以内に、待機機を全機発艦させるか、全機格納庫に戻さなければならない。
一機平均発艦には一分は要するから、全機発艦には20分以上かかるし、格納庫から飛行甲板への出し入れは、それ以上かかるだろう。森村誠一氏によれば(2)、格納庫から飛行甲板からに引き上げて発艦体制を完了するのに40分はかかるという。話はそれるが、森村氏の著書には他にも貴重なことが書かれている。(P453)兵装転換は平常の訓練時でも、魚雷から八十番で一時間半、艦船用徹甲弾だと二時間半かかかり、逆は一時間半から二時間だという。しかも、兵装転換は格納庫で行われているという。格納庫からの上下は、エレベータの速度で最短時間は推定できるが、兵装転換時間は推定方法がないので、関係者の証言を聞いたのであろう。
閑話休題。敵機動部隊発見の有無、兵装転換の有無にかかわらず、敵空母出現のための待機機が、飛行甲板上にいられるのは、元々1時間程度しかないことになる。
それどころか第一次攻撃隊が帰ってくると、収容のために飛行甲板を空けなければならない。すると発艦体制の40分より短くて30分で待機機を格納庫に収容できるものとしても、その間帰投した攻撃隊を空中待機させるか、帰る時間を予測して、あらかじめ待機機を格納庫に戻すかしなければならない。帰投した攻撃隊は多くが傷ついているから、空中待機させる、というのは、かなりリスクがある。つまり各艦から半数づつ攻撃隊を出す、というのはかなり運用上面倒かつ作戦上のリスクがある。
また是本氏が、機動部隊攻撃隊発艦開始直前に急降下爆撃を受けた、という定説をとっているのは間違いと考えて差し支えないであろう。米軍による日本兵への聞き込みによれば、母艦被弾中に攻撃機はまだ格納庫にあった、という。急降下爆撃機に襲われた時に、発進し始めたのは、防空戦闘機であったというのである。まだチェックを終えていないが、海軍の戦闘詳報には、敵空母攻撃隊発進開始、という記録はないと思われる。
また、艦爆の被害から幸運に免れた飛龍も、攻撃隊を発進させたのは、赤城らが被弾してから30分もたっているのも不可解である。少なくとも4艦が一斉に的空母攻撃隊の発艦を開始したと言うわけではないことははっきりしている。
また、前記のように、各艦での半数待機というのは、極めて困難である。待機させるなら4隻のうち二隻を機動部隊攻撃用にあてる方が効率が良いのである。このようなわけで、ミッドウェー攻撃隊の編成をきちんと調べないときは、山本大将の言う半数待機を実行したのなら、当然半数の空母が待機に回されていたはずだと小生は考えていたのである。
それをしなかったのには、いくつか理由が考えられる。第一に空母ごと全機待機にまわされれば、乗員や搭乗員に大きな不満が出る。真珠湾攻撃の際も攻撃隊に入れず、艦隊防空任務に回された搭乗員には不満があったと言われる。搭載機が大幅に減ったにも拘わらず、大した攻撃目標でないため、搭載機の半数で済むとしたら、各艦一斉に攻撃隊を出す方が、第一波と第二波とのタイムラグが生じなく、集中して攻撃できる、などであろう。
実際、艦上機数は真珠湾時の六割程度しかない、翔鶴型の不参加による搭載機の不足と、ミッドウェー攻略と敵空母撃滅の二股をかけたことが、作戦をいびつにしたのである。だが空母がなかったわけではない。戦闘には参加していないが小型とはいえ、鳳翔(19機)と瑞鳳(30機)が随伴していた。また、ミッドウェーの牽制として行われたダッチハーバー攻撃には隼鷹(53)と龍驤(38機)を無駄遣いしている。
ミッドウェー海戦に参戦しなかった4艦の搭載機数合計は140機にもなるが、出所はウィキペディアによるものであり、補用機も含み、ミッドウェー海戦時かの確認はしていない、目安と考えられる程度である。このように翔鶴型がいなくても、空母と艦上機は余っていたのである。
(1)日本海軍はなぜ敗れたか・是本信義
(2)ミッドウェー・森村誠一
④ミッドウェー海戦考1
「半数待機の疑問」に書いたが是本信義氏によれば、陸上攻撃のための第一次攻撃隊は各艦27機の合計108機で、同じく108機が山本長官の厳命により、半数が空母出現のための艦船攻撃兵装で待機していた、とされる、他の資料でも類似の記述がある。しかも待機した攻撃隊は、第一次攻撃隊発艦後、すみやかに艦上に上げられ、空母出現を待っていたというのである。このことの不合理は「半数待機の疑問」に書いた。以下に(1)の戦記による、三空母被爆時の証言を整理した。
〈蒼龍の魚雷調整員の証言〉
この証言によれば、これすら怪しい。蒼龍の魚雷調整員の元木茂男氏の証言である。Wikipediaによれば、蒼龍の第一次攻撃隊の編成は零戦9機と陸用爆弾搭載の艦攻18機である。元木氏によれば、ミッドウェー島攻撃の6月5日の「・・・作業の指示があった。・・・ただちに艦攻18機に、八〇番陸用爆弾を搭載する。そして、搭載終了後、今度は急ぎ魚雷搭載の準備にかかる、というもので・・・攻撃隊が帰るまでに魚雷の準備にかかる。調整場から格納庫へ一本づつあげるのである。」
つまり、第一次攻撃隊の艦攻は800kg陸用爆弾を搭載して出撃した。そして魚雷は帰ってきた第一次攻撃隊の艦攻への搭載を予定していたのであった。この記述は伝聞ではなく、調整した本人の証言だから、この点に関しては間違いないであろう。すると飛行甲板上にはWikipediaの記述のように、零戦と対艦戦用の爆弾を搭載した艦爆が待機していた、という記述とは必ずしも矛盾はしない。矛盾はしないが、第一次攻撃隊が帰ってくるまでに、これらの対空母戦の攻撃隊は一旦、格納庫に全機戻さなければならないから、作業効率が悪い上に、対空母戦の攻撃隊が出撃可能な時間は極めて短いことになり、対空母作戦効率も悪い。換言すれば、敵空母攻撃のチャンスは極めて少なくなる、ということである。
だが、元木氏は7~8波の空襲を切り抜けたため調整場の待機を交代して、飛行甲板に出た。すると昼食のにぎりめしを二、三個食べ終わった瞬間に隣の加賀に命中弾があり、蒼龍にも対空戦闘のラッパが響いた、というから、この時に三艦にとどめを刺した艦爆の攻撃が始まったのである。この時元木氏は飛行甲板後部に10機の艦攻が待機していたのを見ている。直後に艦攻群に第一弾が命中した。
蒼龍で出撃したのは艦攻で、艦爆しか残っていなかったから、艦攻の目撃が事実なら、第一次攻撃から帰投したものとしか考えられない。すると飛行甲板で待機していた、空母攻撃隊は既に格納庫に収容されて、攻撃隊の着艦をさせたのである。格納庫への収容には相当時間がかかるうえに、この間敵機の攻撃を受けて、防空の艦戦を発着艦させながら雷爆撃の退避運動をしていたのだから、攻撃隊の着艦は困難であったろう。すると、米艦爆隊攻撃時点では、対空母攻撃隊が飛行甲板に待機していた、ということはましてあり得ない。
それにしても、着艦した艦攻が格納庫に収められずに、10機も飛行甲板上にいた、ということの解釈は難しい。ひとつ考えられるのは、これが艦爆の見間違いで、第一次攻撃隊の格納庫への収容は終えて、ミッドウェー基地攻撃か空母攻撃か分からないが、発艦準備をしていたという解釈である。それにしては他の証言から考えると時間的に早すぎて、そこまでの作業が終えていた、というのも考えにくい。
もう一つの可能性だが、零戦を艦攻と見間違えたのではないか、ということである。見間違えたとすれば、固定脚の九九艦爆より引込み脚の九七艦攻の方が可能性は高い。そうだとしても、艦隊護衛に発着を繰り返していたはずの零戦が10機も飛行甲板上にいた、というのも不可解である。
話は元に戻るが、米艦爆隊の攻撃中に、飛行甲板上に艦攻がいたということを正しいとすれば、残る解釈は、その前から雷爆撃を受けていたから、第一次攻撃隊の着艦収容作業が遅れていたのである。零戦は最後に着艦するから、艦攻が着艦し、格納庫への収容作業中で、収容待ちの艦攻約10機が残っていた、ということであろう。零戦は着艦待ちか他の艦に着艦したかのいずれかであろうとするのが、証言と最も矛盾しない。
時間的にも収容された第一次攻撃隊の艦攻が格納庫に降ろされて、雷装を施されて飛行甲板に上げられた、ということは考えられない。魚雷調整員の元木氏は、7~8波の敵の攻撃を受けている間、魚雷調整場に待機していて魚雷装着作業はしていないうちに、交代して飛行甲板に上がってにぎり飯を食べ始めたときに、10機位の艦攻を目撃したと同時に米艦爆の直撃を受けたと証言しているから、やはり目撃した艦攻は着艦したばかりの空装備の、第一次攻撃隊機だとするのが、最もつじつまが合う。
〈赤城の制空隊の証言〉
赤城の戦闘機隊の木村惟雄氏の証言である。第一次攻撃隊の制空隊に参加し、午前4時に攻撃を終え帰途につき、五時頃母艦に達すると、敵雷撃機の攻撃の最中で、雷撃機を撃退して着艦した。午前六時二十分に対空戦闘が始まり、敵雷撃機を撃退すると同時に、艦爆の攻撃を受けた。これが問題の攻撃である。
赤城に初弾が命中し、全艦が火災になったが、艦が風上に向かったので、エンジンが始動されていた、自機ではない隊長用の機であったが、飛び乗って発艦すると次々に爆弾が命中した。これが、よくミッドウェー海戦記に書かれている、「敵空母攻撃隊の最初の一機が赤城から発艦すると、直後に次々と急降下爆撃に攻撃され被弾した」という問題の一機である。この機は補助翼が味方の対空砲火で壊れ防空戦闘ができず、仕方なく飛龍に着艦したが投棄された。
つまり攻撃隊の発艦どころか、敵襲であわてて迎撃のために発艦したのである。別の資料には最初に発艦したのは赤城の艦隊直掩機だったという記述があるが、全くの間違いではないものの、着艦した第一次攻撃隊の一人が、攻撃にさらされて慌てて再度発艦したのであって、直掩のために発艦したという計画的なものではなかったのである。この証言では第一次攻撃隊は、敵襲の合間をぬって収容された機もあったということである。
恐らく艦戦は最後に着艦するだろうから、攻撃隊の多くの機が着艦できていた可能性はある。いずれにしても先の元木氏の証言と同じく、第一次攻撃隊が着艦可能であったから、飛行甲板には、山本長官の命令で飛行甲板上に敵空母攻撃隊の機が待機していたとしても、その時には飛行甲板上に既にいなかったということである。このことは時間的に無理があるから、第一次攻撃隊発進後、ただちに敵空母攻撃兵装の攻撃隊を飛行甲板上に待機させていた、ということの信憑性を疑わせる。
〈加賀の飛行長の天谷孝久氏の証言〉
氏は戦闘時、発着艦指揮所にいたから、加賀が攻撃されていた状況を見ることが可能な位置にいたことになる。第一次攻撃隊発進後しばらくすると「艦上機らしい小型の二機編隊を認めた。」とあり、この攻撃により「・・・敵機動部隊が、この飛行機の行動半径内(二〇〇カイリ以内)にいることは確実であった。」というは当然の判断であった。氏は索敵機が敵空母を発見しないことにやきもきしているが、この時点で兵装を対艦戦用にしておくのは当然であろう。もし、この機が陸上から発進したアベンジャーでも、艦上機が来たのだから、敵母艦攻撃機を意識していたなら、母艦の存在を疑うのは当然である。
所在が見つからなかろうと、兵装転換には時間がかかるのだから、艦上機の攻撃を最初に受けたときに、兵装転換だけでも行って、攻撃態勢を整えておかない、というのは大間抜け、というものであろう。ところが赤城から、空母攻撃司令信号が来て爆装から雷装への転換を始めると同時に、第一次攻撃隊が帰って来て着艦させようとすると、雷撃機が来襲して着艦は中止される。しかも雷撃機を撃退して収容をしようとすると、急降下爆撃機の攻撃が始まったという。
それならば、おそらく加賀は全く攻撃隊の収容ができなかったのである。何度も言うが、敵空母攻撃隊の発艦直前に急降下爆撃機の攻撃により、赤城、加賀、蒼龍が被弾した、などという通説はでたらめである。
加賀の第一次攻撃隊は零戦と艦爆たから、次の攻撃隊に残っているのは零戦と艦攻である。第一次「・・・攻撃隊発進後『加賀』艦上は、上空直掩機の交代機発進、第二次攻撃隊の準備も終わり・・・」とある。直掩機が交代で発着艦を繰り返しているから飛行甲板には準備が整った第二次攻撃隊はおらず、格納庫内にいたことになる。
しかも前述のようにその後索敵機の報告により雷装に切り替えていた、というのだから、少なくとも加賀の第二次攻撃隊の艦攻は陸上機兵装で、格納庫にいたのである。このことから、少なくとも、加賀は第一次攻撃隊発進後雷装の艦攻隊を飛行甲板に上げ発艦体制にあったというのではない。
〈加賀艦攻隊の松山政人氏の証言〉
松山氏は第一次攻撃隊発進より前に、早朝暗いうちに朝飯も食べずに3時間位索敵して加賀に帰投した。そこで聞いたのは対一次攻撃隊が発進していくらもたたないうちに、小型の艦上機の攻撃を受けて撃退した。氏はミッドウェー島に訓練のためいた艦上機だろうかと推定している。艦上機なのだから近くに敵空母がいるはずだ、という天谷氏の判断とは異なる。事実は最新のアベンジャー雷撃機は少数がミッドウェー島から発進し、旧式のデパステーター雷撃機は母艦から攻撃している。両方あったわけである。
その後氏が飛行甲板に上がると艦上機の攻撃が始まったが、零戦に撃退された。その時索敵機から敵機動部隊発見の報が入った。「私はいそいで甲板下の格納庫にかけつけ、愛機へ魚雷を装備した。ところが、これらの装備もおわろうとするとき、今度は雷撃中止、爆撃用意という命令である。しかたなく、いま装備したばかりの魚雷を取りはずし、いそいでいるため、魚雷を魚雷庫へもどす暇もなく格納庫においたままで、今度は爆弾庫から八〇〇キロ爆弾を運んできて、爆弾装備に変更したのである。」
この証言では、加賀の艦攻は雷装に転換する前には、爆弾装備をしていたのか、空だったのかはっきりしない。しかし、兵装がない、ということは考えにくいから、陸用爆弾を装備していたのであろう。八〇〇キロ爆弾が爆弾庫にあったのは、雷装への転換時にはゆとりがあったため、外した爆弾を爆弾庫に戻していたと考えればよいのである。
ただし、森村氏の「ミッドウェイ」によれば、兵装転換には雷装から爆装で二時間半もかかるというから、爆装→雷装→爆装などしっかり終えている時間はない可能性が高い。被爆時のいずれの機の兵装は中途半端でばらばらだっただろう。
〈証言の総括〉
阿川氏などによる通説は、待機機は敵空母攻撃兵装をしており、ミッドウェー島第二次攻撃の要有、との無電により、陸上攻撃兵装に転換している時に、索敵機から敵空母発見の報があったため、空母攻撃兵装に戻し攻撃隊を飛行甲板に上げ、発艦を始めた瞬間に被爆した、というものである。
しかし証言によれば、三空母とも被爆時に、敵空母攻撃隊が発進準備中ではなく、格納庫内にあったということにしかならない。残りの飛龍も三空母の一部の第一次攻撃隊も収容しているから、第二次攻撃隊は格納庫で待機していたのである。
本項で引用した証言から三空母の状況を推理する。赤城は、米機来週の合間をみて、第一次攻撃隊の多くを収容した直後に被弾した。加賀は連続攻撃をうけていて、ほとんど第一次攻撃隊を収容できなかった。蒼龍は第一次攻撃隊の艦攻だけ収容できたのかもしれないが、防空戦闘機が発着艦している最中に、艦攻が飛行甲板にいた、というのは不可解である。
加賀の二人の証言は矛盾している。天谷氏は艦攻への雷装中に被爆し、松山氏は雷装にした後、爆装に転換しているときに被爆したというのである。ただ、天谷氏は発着艦指揮所にいて、松山氏は兵装転換のために格納庫に行った、というから格納庫の様子については松山氏の証言の信憑性が高い。いずれにしても、米軍機の四空母攻撃から、三空母の被弾までの経過は真相がつかみにくい。
だがこれらの証言で共通しているのは、通説とは異なり、被爆時に敵空母攻撃隊は飛行甲板上ではなく、全て格納庫内にいた、ということである。
(1)証言・ミッドウェー海戦・NF文庫
⑤ミッドウェー海戦考2
ミッドウェー海戦で、山本大将には真珠湾で撃ち漏らした空母を誘い出して撃滅する、という意図が強かったと言われている。その一方で海軍上層部には、米空母は南方に居り、ミッドウェーには出てこない、と楽観していたとするむきもある。敵艦隊をおびき出すために上陸作戦をする、ということの軍事上の不適切は別に論じた。
海上自衛隊の元幹部の、是本信義氏はミッドエー敗因の根本は、山本の「敵空母機動部隊を誘い出し、これを撃滅する」という真意が南雲司令長官に伝わっていない「戦略思想の統一」の欠如にある、という。そして南雲機動部隊の実力への慢心もあったという。
そもそも、前述のように敵艦隊撃滅のための上陸作戦などというものは論外であることはさて置いても、山本長官の真意が伝わったとしても、米空母が出現したとすれば、空母攻撃戦力からは日本側は完全に不利な状態にあった、と言わざるを得ない。本項ではこれについて考える。日本側はヨークタウンは珊瑚海海戦で大破し、戦力にならないと見ていたから、米空母がいるとすれば、エンタープライズとホーネットあたりと考えていた。すると日本側の推算では米空母搭載機合計は162機から180機であり、これが日本空母攻撃に全力をかけることができる。
これに対し、日本側の空母攻撃の待機機は、およそ108機である。ヨークタウンがいないとしても、既にこれだけの差があったのである。つまり、日本側の米空母の見通しが正しかったとしても、日本側は最初から不利だと想定できたのである。
実際にはヨークタウンがいたから、定数は243機から270機となる。二波に分けて攻撃しても、一波当たりの数で既に日本機を超えている。その上、米側は30分程度の間隔で、1波と2波の全機で攻撃できる。これに対して、日本側は敵空母攻撃隊の108機をまず発進させ、次にミッドウェー島攻撃隊を帰投してから収容し、燃料と兵装を補給して、再出撃するのは、第一波の敵空母攻撃隊を収容してから何時間も後になるから、米空母機に襲われた後になってしまい、現実には再出撃は出来ない。これは想定できる話である。つまり航空戦力比では日本側の負けである。この想定は、ミッドウェー島攻撃隊が発進して後に、米空母の所在が判明した場合である。
運よく、第一次攻撃隊発進前に敵空母発見の報が入り、ミッドウェー島攻撃を中止し、米空母を攻撃することに変更してもややこしい。ひとつの想定は、対地攻撃兵装のまま第一次攻撃隊を、米空母攻撃に即時出撃させる場合である。魚雷などを積んだ、第2波は、格納庫からの飛行甲板整列と発艦作業で一時間位遅れて発進するが、第一波が先制攻撃になり、米空母機が襲ってこなければ、これが唯一の勝利の可能性がある場合だと思われる。
もうひとつは、対艦兵装にこだわった場合である。最短なのは飛行甲板上の第一次攻撃隊と格納庫内の待機機を入れ替えることであるが、それでも相当時間がかかってしまう。是本氏によれば、第一次攻撃隊発進の50分後の0520には米側に日本空母が発見されている。従って第一次攻撃隊の発進予定時刻よりよほど前に日本側が米空母を発見しないと、米側の先制攻撃を受ける。これはで日本側の負けである。現実はそうなった。
そもそも、米軍は事前情報がなくても、第一次攻撃隊が発進すれば、レーダーで日本機が発見されて、日本空母がミッドウェー島付近に遊弋していることは知れるから、日本空母の捜索が始まる。つまり米軍が先に日本空母を発見する公算が高くなる。米軍がレーダー探知能力を持っていることは、珊瑚海海戦その他の、それまでの戦訓で分かっている。米国が暗号解読で事前情報を得て有利となったのは事実としても、それは警戒網や基地航空隊の陸上機を増強したことが、大きいのであって、米国勝利の絶対条件ではないことになる。
また、米側には多少はともかく、基地航空隊が存在することも日本側に分かっている。これに追加するに米空母機の最低180機がいたと考えなければ、米空母撃滅の目的は設定する必要はない。日本側の事前情報で既に、この航空戦力比では日本側は明らかに不利である。いくら海軍上層部がミッドウェー島付近に米空母はいない、となめていたとしても、ミッドウェー作戦を強行した山本長官は、米空母撃滅をも企図としていた、というのだから、米空母がいる、という可能性が大だと想定していた、と考えなければおかしいのである。
このように、当初から米空母がいた場合の日本側の不利を想定できたとすると、山本が、不利にもかかわらず半数待機を命じたのは、念のため、というのに過ぎず、本気で敵空母撃滅を考えていたかについては疑問符がつくことになる。ミッドウェー島攻撃隊が、真珠湾攻撃の第一波183機に比べればはるかに少ないのは、攻撃目標が少ないから充分だ、ということであろう。
さらに真珠湾攻撃では予定通りの第二波171機が一時間余後に発進している。ミッドウェーの場合、第二波(第二次攻撃隊)は予定外に第一波の攻撃隊の要請で発進準備がなされた。すると計画上は約350機と108機と圧倒的にミッドウェー島攻撃戦力は少ない。
真珠湾攻撃の批判者は米空母の不在による、攻撃の不徹底を主張するが、もし、米空母がいたら、ミッドウェーとはいかないまでも、米空母を撃滅できたとしても、日本空母相当の被害を受けたはずある。
是本氏によれば、米機動部隊が日本側を発見したのは0520で、ほぼミッドウェー空襲を実施中であった。史実と異なり、同時に日本側が米空母を発見し、ただちに待機していた108機の攻撃隊を発進したとすると、互いに攻撃を開始したことになる。現に米側はその後、艦上機と陸上機によって日本の機動部隊を盛んに攻撃している。
こうなれば、航空戦力が劣る日本の攻撃隊が、米空母にどの程度の被害を与えることが出来るか、米側の攻撃隊がいなくなり、第一次攻撃隊を収容した空母の被害が、現実の海戦よりどの程度被害が軽減されているか、であろう。何回も言うが、航空機の戦力比から言えば、元々日本側不利である。
まして珊瑚海海戦では、米機動部隊の対空砲火と直援戦闘機との防空能力は大きく、日本側の防空能力は、直援戦闘機なしには、脆弱であるという戦訓は得られている。沈没した祥鳳は雷爆撃の滅多打ちにあい、レキシントンは多大な被害にもかかわらず、沈没せず、ガソリンの気化ガスの引火によって偶発的に沈没した。いずれにしても、南雲機動部隊が自慢した鎧袖一触ということはあり得ない。山本長官ら連合艦隊司令部は珊瑚海などの教訓を全く無視していた。
現に、事前に大和艦上で行われた図上演習(2)では赤城と加賀は沈没している。また「魔の5分間」の出どころのひとつは阿川弘之氏であった(2)。「・・・『第二次攻撃隊準備出来次第発艦セヨ』という命令が出た。母艦は風に立ち始め、やっと雷装に切り替え終わった攻撃隊群は、すでにプロペラを廻し出し、あと五分あったら、全機アメリカの機動部隊に向かって発艦を了え得るという時に、突然、上空から、真っ黒な敵の急降下爆撃機が三機、「赤城」をめがけて突っ込んできた。」
発艦開始から五分で二〇数機が発艦を終える、というのだ。当時の空母では一機発艦するのに一分を要する。全機発進に五分は絶対にあり得ない。現にその後攻撃隊を発艦させた飛龍は20分以上かかっている。そのことは阿川氏もよくご存じのはずだ。失礼ながら間違ったのではなく、嘘をついた、としか考えられない。これが巷間言われる「魔の5分間」の正体である。
以上のように、日本側が普通に戦えば力量も戦力も上だから勝てたはずだ、という説は全くの見落としがある。ヨークタウンがいない、というばかりではない。米空母の一隻当たりの搭載機数が、日本空母よりよほど多いことである。また、半数はミッドウェー空襲部隊であり、半数待機だから、対空母戦としては即戦力で使えず有効な搭載機数が半減する。
現実には、想定外のヨークタウンが参戦していたし、ミッドウェー島には日本の機動部隊来襲を予測して、爆撃機、雷撃機、哨戒機合わせて120機以上が配備されていた(3)(P412)。その上魚雷艇11隻と潜水艦が島の周囲を哨戒している。確かに艦隊の総数は日本の方が遥かに多い。しかし大和を中心とする「主力部隊」は何百浬もの後方にいる。駆けつけるのに全速でも10数時間かかるが全速は無理である。
一般に「・・・ミッドウェーの戦いには、アメリカをはるかにしのぐ物量でもって臨んだのである。・・・どんな馬鹿な司令官が指揮をとっていたとしても、日本は楽勝できたはずである。(4)」というのが定説である。ミッドウェー攻略作戦の批判者ですら、これに近い見解である。だが日本の図上演習でも相当な苦戦となることが既に予測されていた。
実際には、その上に日本の予想の倍の上回る航空戦力が配備されていた。これで日本機動部隊が勝つとしたら、よほど運に恵まれていなければならないのが本当であろう。現に米陸上機と艦上機の雷爆撃のほとんど全てを回避している、という実力と幸運さえあった。にもかかわらず、米側の執拗な攻撃の当然の帰結として、最後には惨敗したのである。
魔の5分は論外としても、日本空母はそのかなり前から、基地航空機と艦上機に攻撃されていて、辛うじて防空戦闘機の獅子奮迅の活躍と、巧みな操艦により被害を受けずにすんでいた。米側の攻撃の激しさをみれば、致命傷となった急降下爆撃以前に、雷爆撃の被害がなかったことが奇跡的である。
今後海軍の戦闘詳報をチェックしてみようと思う。ただ、ちらと見る限り、多くの戦死者が出ているために、欠落が多いが、攻撃隊の編成や空戦の状況など、見るべきものも多いはずである。ただ、戦闘詳報は当然膨大なものなので、チェックがいつ終わるかわからないと言い訳しておこう。
(1) 日本海軍はなぜ敗れたか・是本信義
(2) 山本五十六(下)・阿川弘之
(3) ミッドウェー・森村誠一
(4) 世界最強だった日本陸軍・福井雄三
2.2 その他
①サマール沖海戦の逃亡
栗田艦隊は昭和十九年十月二十五日スプレイグ少将の率いる第77任務部隊の護衛空母六隻以下と遭遇した。空母ガンビア・ベイ他駆逐艦を撃沈したものの、北方に機動部隊がいるとして、反転撤退してしまった。これを「なぞの反転」と称しているが、経緯を考えれば謎ではない。栗田艦隊はいつまで攻撃しても執拗に駆逐艦や航空機で反撃する護衛空母群れに混乱して追撃をやめて集結した。このとき九時十六分。攻撃命令が出たのが六時五十四分だから二時間以上攻撃してもかくのごとき戦果である。
朝日ソノラマの文庫版航空戦史シリーズのレイテ沖海戦(下)によれば、三〇ノットで逃げる正規空母を追撃して深追いしても空襲で撃破されるというのがその理由である。九時四十五分には正規空母が北方にいるという電報を受け取っていたという。このときレイテ湾からも約二時間である。
正確には不明であるが集結を終えて北進の決断をしたのは、十二時十五分ごろ。このときにも空襲を受けている。正規空母の攻撃から逃げたものが、正規空母攻撃に向かうというのである。栗田艦隊は米軍機の執拗な攻撃に疲れて逃げたのである。この矛盾を指摘するものがいないのも不思議な話である。栗田は単に逃亡したのに過ぎない。
確かに栗田艦隊がレイテ湾に突入しても、米輸送艦は揚陸作業を終了していた。そしてレイテ湾にいた米戦艦軍がそれまでの戦いで弾薬を打ち尽くしていたから容易に攻撃して勝てたという説は間違いで、米戦艦に弾薬は充分あったと立証した者もいる。しかし上陸した米軍を撃つこともできた。敵の弾薬が空でなければ日本艦隊は戦わないのか。
フィリピン沖海戦以後日本艦隊は本土に閉塞していた。12隻の戦艦のうち空襲で破壊着低せずに浮揚していたのは戦艦長門一隻だけである。大和は日本海軍が戦力を残して敗北したという「不名誉」を避けるためとエキスキューズの目的で、戦果を挙げずに撃沈されるために沖縄に出撃した。そのとき大和は天候不良のため対空砲火としてすら主砲を打つことはできなかった。たとえ敗れたとしても大和はレイテ湾でならば米戦艦と対決し、マッカーサーの上陸軍にいくばくかでも、損害を与えることが出来たのである。
それどころではない。半藤一利氏によれば(*)通説では栗田中将のもとには小澤艦隊によるおとり作戦に成功したという電文が栗田に届かなかったというのだが、実はGHQに対する証言で小澤艦隊の戦況を知っていたが、もう時期遅れだと思ったと言ったという。これに対して半藤氏は「謎」と言っているがそんなことはあるまい。小澤の犠牲を知っていても栗田は卑怯にも逃げたのである。
それならば小澤がハルゼーの機動部隊のおとりになって沈むという作戦計画は何なのか。そして電報が栗田のもとには届かなかったと言う定説は多数の旧海軍幹部によってなされたものである。崩壊した海軍の名誉の何が大切か。嘘で守る名誉とはなにか。半藤はレイテ湾から反転する重巡羽黒の士官の気持ちとして「ああ、これで終わるのだと思った将兵は多かった。」と書いている。これは指揮官栗田の気持ちでもある。兵卒としてはそれでもよかろう。指揮官がそれでは戦争はできない。繰り返して言う。栗田は逃げたのだ。
もう一つの栗田艦隊の過誤は、サマール沖の護衛空母追撃で戦艦と巡洋艦に先頭をきらせて、駆逐艦を後衛にしたことである。相手が正規空母なら高速であり、これを捕捉するのに高速の駆逐艦にしくはない。しかも駆逐艦は前衛として魚雷戦で敵艦隊を撹乱暫減するために長く計画されたもので、これでは本来の任務の放擲である。
このように大東亜戦争の日本海軍の戦術は、本来の趣旨から離れた不適な使い方をしたものが多い。駆逐艦を後衛に回した理由のひとつが、全力航走による燃料の浪費を恐れたというから、退嬰の極みである。ここにも逃げるための配慮がある。駆逐艦の乗組員たちは正規空母と刺し違える気概はあったはずだから余計な配慮である。栗田艦隊の反転といい、サマール沖の追撃中止といい、見敵必殺の闘志のないものに勝利はない。ここでは数的に優れた日本海軍の指揮官の闘志のなさは、劣勢で日本戦艦群に突撃して護衛空母を守った米駆逐艦の闘志にはかなわないのは当然である。
また米海軍は煙幕を時々有効に使っている。スラバヤ沖海戦でも駆逐艦の煙幕により戦闘が一時中断しているし、サマール沖海戦でも米駆逐艦が煙幕を有効に使って護衛空母群を守っている。何よりも戦艦と重巡の大群に突撃して護衛空母を守ろうとする駆逐艦の闘志は天晴れという他はない。既に圧倒的に優勢であった米海軍にしてこの敢闘精神である。日本海軍は1隻の損失を恐れて全滅の憂き目にあった。
魚雷艇群に対決した西村艦隊は不利な体制でも何の工夫もなく、横綱相撲をとろうとして何の戦果もなく全滅した。それでも突入を回避した志摩艦隊よりはましである。第三次ソロモン海戦では挺身攻撃隊の比叡が探照灯を照射して、米重巡群に返り討ちに会うという拙劣な戦法をとった。片や煙幕で身を隠すのに対して、明かりで敵に目標を現して示してあげたのである。私はこの勝者は有効であったという発言を平成8年頃旧海軍の千早正隆氏から防衛図書館のセミナーで聞いた。自身が比叡に乗り組んでいたのである。それにしてもどこまで身びいきなのであろうか。
*レイテ沖海戦・半藤一利・PHP
②暫減作戦を実行したのは米海軍
日本海軍は航空母艦と潜水艦を重視した。それは暫減作戦と称して、日本近海に侵攻してくる米艦隊に対して、潜水艦と空母が襲い掛かって主力艦を少しでも撃沈ないし撃破して、数的劣勢にある艦隊決戦の際に我が主力を少しでも有利にしようというのであった。 しかし開戦してみるとこれを実行したのは一方的に米海軍であった。マリアナ沖海戦では開戦僻頭大鳳、翔鶴を撃沈して主力空母を減じたのは、米潜水艦であった。フィリピン沖海戦ではもっと壮大な漸減作戦が実行された。ブルネイを出港してレイテ湾に向かった栗田艦隊主力は、早速米潜の迎撃を受け早朝から愛宕、麻耶沈没、高雄戦線離脱してしまった。
次は空母が襲い掛かり、妙高戦線離脱、武蔵沈没、などの被害を受ける。別動の西村艦隊はスリガオ海峡から突入すると、まず魚雷艇の攻撃を受け、次に駆逐艦の雷撃を受けて反撃も出来ず、扶桑他駆逐艦山雲が沈没する。これだけ艦隊を効果的に漸減されると最後は待ち構えたオルデンドルフ少将の戦艦群の砲撃その他で戦艦山城他が沈没し、帰投したのは駆逐艦一隻だけである。栗田艦隊主力はサマール沖海戦で有利な体制からでも、護衛空母群に反撃され護衛空母1隻、駆逐艦2隻を沈没させただけで執拗な反撃に重巡3隻を撃沈され、前述のように戦闘意欲を失い逃げ帰った。
そのままレイテ湾に突入したらという仮説に対する答えは諸説ある。しかしはっきりしているのは、栗田艦隊主力は米海軍の効果的な阻止にあって、本番のレイテ湾突入以前に勢力を減じられていたのである。そして漸減により戦意喪失さえしてしまった。これに対して日本海軍は真珠湾以来空母を本来の漸減ではなく、攻撃の主力として使った。潜水艦はワスプ、ヨークタウンなどの主力空母を撃沈しているが、ワスプは海戦と関係なく撃沈されているし、ヨークタウンは海戦がおおむね帰趨が決着した仕上げとして、大破したときに撃沈したものであって漸減ではない。
このように日本海軍は開戦前、長い間主力艦の補助として潜水艦と空母を力を入れて整備しながら、本来の暫減作戦は実行せず、米海軍に御株を奪われてしまったのである。空母はそれなりに活躍したからいいものの、潜水艦はよく批判される通商破壊ばかりではなく、本来の艦隊決戦にも使用されなかった。
③補助兵器を軽視した昭和海軍
佐藤和正氏によれば(*)栗田艦隊がサンベルナルジノ海峡の出口は日本海軍によって機雷封鎖されていると考えて、潜水艦を配置していなかったという。すなわち占領から撤退するとき機雷封鎖などあらゆる手段を取るのが当時の海軍における常識であった。日本海軍は艦隊決戦など正面戦闘しか考えていなかったのである。すなわちあらゆる有効な手段を講ずるという、当たり前のことすら考えていなかったのである。
米海軍が魚雷艇のような補助兵器を有効に活用したのもあまりに有名な話である。日本海軍は魚雷艇の有効性を知らされて、大戦中に開発を開始したがついに実用化できなかった。しかし同じ補助兵器でも特殊潜航艇なる超小型潜水艦の開発に力を入れている。
この差異は何か。米海軍は地理を考慮した具体的な作戦を考えていたために魚雷艇を開発した。魚雷艇には大洋を航走する航洋能力は低い。フィリピン群島のような内海しか使えないのである。つまり魚雷艇はフィリピン防衛用である。地中海のイタリア海軍が魚雷艇を作ったのは当然である。
ところが日本海軍の作戦は日本近海での艦隊決戦という抽象的なものであるから、地理を考慮しない超小型潜水艇なるものに力を入れた。しかしその使い方たるや、有利な洋上ではなく、運動も制限され対潜哨戒もしやすいハワイ軍港やシドニー湾という悪条件で無理に使った。
これは艦船が終結して攻撃しやすいという他に、攻撃後の回収を思いついたからと思われる。つまり洋上攻撃を実施すれば攻撃後の母艦による回収は困難で、鉄砲玉になる。軍港攻撃なら母艦が湾外に待機していれば、回収地点は比較的限定される。開発時には回収などは深く考えていなかったにもかかわらず、作戦実施時には指揮官として回収の可能性のないことを部下に命令するのは、人情が許さなかったのであろう。必死の体当たり攻撃を行った日本軍ではあるが、この人情は同じ日本人として理解できる。
*レイテ沖海戦・佐藤和正(下巻)光人社NF文庫
④空母戦は相打ち
珊瑚海海戦に見られるように、戦力の近い空母同士の戦いは刺し違えになるのが当然である。空母は戦艦のように備砲で直接攻撃するのではなく、空母から遥か彼方に離れた航空機により攻撃するのだから、一旦攻撃部隊を発艦させたらなすすべもないのである。
彼我の戦力に大差があれば、大戦後半の米軍のように兵力を分散できるが、差がなければ、見敵必殺で最低限の防空戦力を残して全力攻撃をせざるを得ない、戦艦同士の戦いなら、陣形の違いなど戦法の優劣により差が生じ、被害の差が逐次広がるにつれ、個艦の戦力差も広がりやがて片方が一方的劣勢になって勝敗が決定する。
ミッドウェー海戦などは片方の攻撃部隊が発艦する前に攻撃されたからワンサイドゲームになったのである。その後の南太平洋海戦では、米海軍はホーネットを失ったとはいうものの、双方叩きあいになって日本側も大被害を受け、大量の航空機とパイロットを失い、一時双方とも空母戦力喪失に等しい状態となった。空母による戦いは巷間思われるほど効率的な戦いではなく、ノーガードの叩き合いの消耗戦である。少なくとも大戦後半で、正確に管制された防空戦闘機と正確な火器管制による対空火器によって鉄壁の守りとなった、米機動部隊が出現するまでは。
意外な事に、史上最大の空母決戦と言われるマリアナ沖海戦では、米機動部隊は日本艦隊に対して、大量の航空機の撃墜以外には大した戦果は挙げてはいない。主な戦果は改装空母の飛鷹の撃沈だけである。正規空母の大鳳と翔鶴を撃沈する殊勲は潜水艦したのはたった二隻の潜水艦であった。日本の空母は9隻、米空母は15隻もいたのである。
⑤珊瑚海海戦とミッドウェー海戦
海戦史上有名な両海戦批評には欠落している視点がある。それはどちらも上陸作戦であり、なぜ両軍が空母を使ったかということである。日本海軍が空母を使ったのは常識とは異なり、日本海軍が空母を主力として認識していたからではない。単に上陸支援のための陸上基地爆撃の道具に空母を使ったのに過ぎない。それは互いに空母を発見したためにいきなり海戦が始まった珊瑚海ではなく、執拗に基地爆撃が行われたミッドウェーの例を見ればわかる。艦上機は単なる爆弾代わりに使われたのである。
珊瑚海では重巡が護衛についたが砲撃用ではない。重巡も戦艦も砲弾は対艦船の徹甲弾が主で陸上砲撃用ではないからである。正確な情報はないが当時の日本戦艦は米海軍と同様に徹甲弾しか持っていなかったと推定される。だから真珠湾では戦艦を徹甲弾でしとめる余地はあるが、陸上基地攻撃には空母が最適ということになる。ミッドウェーでは日本側は戦艦が参加しているが五百キロ以上後方にいて基地攻撃にも海戦にも参加していない。真珠湾攻撃の際と同じく、随伴することに意義があり攻撃用の意図はないのである。
それでは米軍がなぜ珊瑚海で空母に対するに空母を用いたか。実は日米の兵力を見ると面白いことがわかる。日本側兵力は正規空母2、改装空母1、重巡6、軽巡3、駆逐艦15である。対する米軍は正規空母2、重巡7、軽巡1、駆逐艦13である。日本側がやや有利とはいうもののほぼ拮抗していることがわかる。各艦種の比率まで似ているのは、空母の護衛兵力の配分の考え方が似ているからであろう。ミッドウェーでは情報の漏洩が問題にされているが、これは事前に日本側の攻撃の意図をアメリカ側で知っていたことを意味する。
そしてフレッチャー少将はこの近海にいた兵力をかき集めたのである。空母に対するに空母を持ってきたのは、戦車に対するに戦車、戦闘機に対する戦闘機、戦艦に対するものは戦艦という戦闘の定石に従ったのではあるまいかと思う。戦艦を含む日本艦隊の全容を?んでいたにもかかわらず、ミッドウェーではニミッツの決断により戦艦部隊を投入しなかった。米軍の艦隊編成ではミッドウェーでは正規空母1、駆逐艦2が増えただけと言う変わらない兵力で戦っているのが特徴である。
ミッドウェー海戦では有力な日本海軍が負けたということになっているが、戦艦や重巡といった海戦にほとんど参加していない兵力は圧倒的に多いが、実際に参加した艦上機では日本側227(常用)に対して米側232で米側が多い。米空母は露天繋留するため米空母は1隻当たりの搭載数が多いのである。しかも米側には多数の陸上機が参加している。海戦に参加した航空機の数では米側が圧倒している。その上多くの戦艦などの主力部隊は後方にいて役に立っていない。
いずれにしても日米ともに空母を主戦力と考えたから空母決戦が起きたのではない。日本は空母を上陸支援に使ったのに過ぎない。上陸支援が任務であるにもかかわらず、索敵により米空母を発見した日本の現場指揮官の判断は優秀と言うことになる。米軍は空母に対するに空母と言う発想をしたのである。米側の柔軟な発想が分かる。その証拠に米海軍はその後の上陸支援に艦砲射撃と艦上機による爆撃をミックスして使っている。
目的にあった攻撃能力をうまく時により選択していると言える。これに比較すると日本海軍は、空母なら空母だけ、戦艦なら戦艦だけという硬直した単調な攻撃方法を選択している。日露戦争のような兵力のバリエーションが少ない場合はいざ知らず、複雑になった第二次大戦では通用しないのであろう。C3Iといった指揮管制システムを運用していた米海軍に対して目に見えない部分での能力の差は大きい。ミッドウェーの敗戦を情報管理、索敵だけに帰すに本の評論は一面的である。その後の米海軍は正攻法で攻めても奇襲で無用の敗戦をすることはなかった。戦闘システムの構築と言う面でも負けていたのである。
蛇足であるが、日本ではいまだに珊瑚海海戦は戦術的には日本の勝利で、戦略的には米海軍の勝ちという評価が定着している。これは米側が、正規空母レキシントンを喪失したのに対して、日本側は正規空母を失っておらず、日本はポートモレスビー攻略を諦めたからということである。しかし戦闘の勝敗にに戦略的も戦術的もない。米国は日本のポートモレスビー攻略阻止のために出撃し、目的を達成したから被害の多寡に関係なく、米海軍の勝利である。トラファルガーの海戦で、英軍指揮官のネルソン提督は戦死したが、英海軍の勝利である。それにしても珊瑚海開戦以後、ほとんどの日本の上陸作戦は海上で米艦隊に迎撃されているが、日本艦隊が米軍の上陸作戦を迎撃した事はただの一度もない。だから日本の守備隊は、哀れにも水際迎撃を行なってことごとく撃破されてしまった。水際迎撃を放棄して米軍に大損害を与えた硫黄島の戦いも、日本艦隊による米上陸部隊の阻止行動がない以上、最後は敗れる運命にあった。
⑥米軍もレーダー照準はできなかった
第三次ソロモン海戦の第二回の会戦の夜も月のない夜だった。戦艦霧島とサウスダコタは6,000mの至近距離から打ちあった。この時日本艦隊に気付かれずにサウスダコタの後方にいたワシントンが、8,000mの距離から、探照灯を照らすことなくレーダーの測的だけで射撃して次々と40cm砲弾を命中させた。この結果翌日霧島は沈没した。これが、「太平洋戦争 海戦ガイド」による記述である。
これは一種のレーダー神話である。同書には「霧島にとって不幸だったのは、リー少将がレーダー射撃の専門家だった、ということである。」とまで書いている。果たしてワシントンはレーダー照準によって射撃していたのであろうか。当時のレーダー照準については、雑誌「丸」平成25年8月号に記述がある。モリソン戦史がスリガオ海峡夜戦について日本海海戦のT字戦法の再現であると絶賛するのに対して「残念ながら、当時のレーダー及び射撃指揮装置の能力からして、戦艦及び巡洋艦の砲撃は全くと言ってよいほどに成果を上げられなかったのである。」と断定する。
また「当時の射撃用レーダーは新型のMk-8をもってしても今日のようなペンシルビームではないため、捜索用レーダーよりは精密に距離測定ができるものの、目標照準の機能・能力は有していない。したがって正確な射撃のためには光学照準が必要であり、これは夜間では顕著な明かりがあるか、照射・照明でもされていない限りほぼ不可能である。」筆者は元海将補である。大東亜戦争で米軍が多用したレーダー付きの射撃指揮装置は戦後海自にも供給されているから、筆者の知識に間違いはない。ワシントンはレーダーの補助のもと、探照灯を使用して射撃していた霧島が放つ光で照準したのである。
この時の射撃距離は日本海海戦時代並みに近い。ワシントンは多くの命中弾を得たのは間違いない。第二次大戦当時、米軍のレーダーは捜索用として大きな威力を発揮したが、照準用としては補助的にしか使えなかったのが事実である。第二次大戦の米海軍のレーダー射撃は戦後日本では過大評価されている。サウスダコタは大破したが、霧島が発射したものの多くが三式普通弾であって、徹甲弾ではないから致命傷が与えられるはずもない。飛行場攻撃用に三式弾を優先的に発射する状態であったのには違いないが、徹甲弾を優先できなかった理由は後日考えたい。
ついでに、先に紹介した雑誌「丸」には射撃指揮装置についての専門家らしい記述がある。「当時のジャイロコンパスの性能からして変針後最低1分は直進しないと射撃に利用しうるまでには安定しないことに加え、最低三分間は自艦及び目標が共に直進の状態で測的を行なわないと正確な運動解析結果が得られないのである。」という。このため、米戦艦も山城も途中で変針していた結果、平均射距離2万~2万2千mで6隻が279発撃ちわずか2発(命中率0.72%)の命中弾しかなかった。山城を撃沈したのは、駆逐艦などの魚雷であった。
⑦珊瑚海海戦は日本の敗北
一般的には、戦果が大きかったことで日本軍の戦術的勝利で、ポート・モレスビー攻略に失敗したことを以て米軍の戦略的勝利だとみなすのが、日本では一般的である。しかし、レキシントン撃沈は日本の大鳳と同様に、気化ガソリンの誘爆というラッキーパンチによるものであり、雷爆撃の被害そのものは、沈没に至るものではなかった。それに比べわが祥鳳の撃沈は過大なまでの雷爆撃によるものである。さらに艦上機と搭乗員の被害は日本側の方がはるかに大きい。
いや被害の大きさで勝敗を言うのではない。旅順の攻防戦では、日本側の方が死傷者は多い。だが、旅順占領という戦闘目的を果たしたから、日本の勝利なのである。日本はポートモレスビー攻略という作戦目的を達成できず、米軍は上陸部隊の阻止という目的を達成したから勝利したのである。戦術の戦略のという話ではないのである。
付言すれば、米艦隊は、レーダーや無線を使って日本機を効果的に迎撃しており、日本軍のそれは明かに劣っていた。その差は時期が経てばなおさら広がっていった。その萌芽は珊瑚海海戦の時に既にあったのである。日本海軍は、せめてその点だけでも教訓を得ていれば、しゃにむに艦上機で強襲するという単細胞な戦法を考え直せたであろう。空母同士の戦いでは海軍はただでさえ米軍よりずっと少ない搭乗員を損耗していくだけだったのである。
空母同士の海戦で、皮肉な事に惨敗したはずのミッドウェー海戦だけが、わが軍の搭乗員の戦死者が少ない。他の海戦では、南太平洋海戦のように、勝利したと言われていた場合でも、搭乗員の戦死者はわが軍の方が余程多い。ミッドウェー海戦の場合は、敵空母を攻撃できたのが、わずか飛龍一艦だけだったからである。もし4空母が全力で敵空母を攻撃していたら、戦果はともかく、相当数が撃墜されていたはずである。
⑧日本海軍の年功序列
「捷号作戦なぜ失敗したのか」を読んでいるのだが、以前書評で「ミッドウェー」を紹介したが、運命の五分間が全くの嘘であることを単純明快に証明していたので、期待していた。著者の左近允氏は海兵出身だが、尉官までしかいっていないので、日本海軍に対して公平な眼とプロの眼が感じられる。
比島沖海戦での栗田艦隊の「謎の反転」について、「視界内にある『機動部隊』との決戦は打ち切り、どこにいるか分からない新たな機動部隊を求めてこれと決戦するのでは理由になっていない。」(P347)と断ずる。これは小生と全くの同意見だが、日本人が書いた図書では初めて見た。また「栗田艦隊の『敵機動部隊との決戦を求めて北上』は本音であったら夢であったし、本音でなければ撤退の言い訳であろう。」(P351)と酷評するが、実態は後者に間違いない。何度でも言うが、栗田は逃げたのである。
閑話休題。捷号作戦において、弱体とはいえ戦艦二隻の西村艦隊と、重巡と駆逐艦しかいないさらに弱小の志摩艦隊をわざわざ分けて別行動をさせた上に、同時にスリガオ海峡を突破し、レイテ湾に突入させたかが、疑問であった。同時突入は成功するはずはなく、志摩艦隊はわずかな損害を受け、西村艦隊が全滅したらしいと判断すると、反転離脱してしまうのである。
本書によれば、連合艦隊が両艦隊を一つの部隊として突入させるなら、指揮系統はひとつにしなければならならず、志摩長官は西村司令官と同期だが半年先に中将になっているから、合同部隊の指揮官は志摩長官となる。「・・・突入の直前になって戦艦二隻を基幹とする部隊の指揮官を、重巡二隻を基幹とする部隊の指揮官の下に入れることは、連合艦隊司令部としてはできなかったのではないか。」(P260)というのである。
要するに先輩の方が小部隊を率いているから、後輩であれ大部隊を率いると、捻じれが生じるというのである。志摩は西村と同期なのに、わずか半年先に中将になっているから先輩扱いなのである。これは作戦の成否よりも、年功序列やメンツを重んじる発想である。日本海軍は、機動部隊をマリアナ沖海戦で喪失し、エアカバーのもとで艦隊行動して勝利する、という見通しは完全に無くなった。
残っていた艦上機すら陸上に挙げて、台湾沖航空戦で失って、空母搭載機を喪失した。そこで乾坤一擲、いままで上陸作戦に対して主力艦隊による反撃をしてこなかった方針を捨て、連合艦隊の全力で出撃した。にもかかわらず、作戦の遂行の有利さより、年功序列とメンツを重んじたのである。
だが、これに一理なくもない。日本人の勇猛果敢な精神は、このように安心して働ける年功序列とメンツに基盤を置いていると言えなくもない。まして、明治以来建軍の伝統が確立すると、軍人の、特に幹部は官僚的になったからである。海軍は特にハンモックナンバーを重視した。軍人として武人らしさを残していたのは、兵学校出身者のエリートでは、山口多聞など、わずかしかいなかった。
指揮官の配置を急に変えるのが不都合なら、後輩となる志摩長官を、西村司令官の指揮下に入れるべきではなかったか。まして戦勝のゆとりがあるどころか、連合艦隊ひいては、国家存亡の一戦である。もし、連合艦隊司令部が事情を説明せずとも、志摩長官は士官を集めて、国家存亡の危機打開のため、西村部隊の指揮下に入ることを諄々と説明すればよいのである。
だが本書は志摩艦隊と西村艦隊が合同して突入できたとしても、両部隊は大した戦果もあげず全滅したであろう事を説明している。せめて、志摩艦隊が帰還しただけよかったというのである。結局連合艦隊の作戦計画そのものに無理があったのである。しかし、批判する者は無数にいるがマリアナ沖海戦に敗北し、フィリピン上陸した米軍に、日本海軍は捷号作戦をいかに立案すべきか、という計画を提示した者はいない。小生は、日本海軍は正攻法にこだわり過ぎたのではないかと考える。日本海軍が優勢であった、開戦直後に米海軍が行った、ゲリラ的作戦しか残っていなかったと思うのだが、素人の小生には具体的な案はないのが情けない。
捷号作戦に勝機はなかったにしても、マリアナ沖海戦に勝機はあったのだろうか。航空攻撃するならば、艦上機による先制攻撃しか戦法はしなかったにしても、そもそも艦上機による敵艦隊攻撃があの時点では無理があった。南太平洋海戦でも、ろ号作戦でも米艦隊の艦隊防空は鉄壁で、ますます強化されていることは戦訓として知られているはずである。そこに正面きって強襲しても、マリアナ沖海戦の時点では、状況はますます不利になっているのは知れている。いや、末端の将兵はともかく、幹部が彼我の防空体制の隔絶した能力差に気付いた節はない。
勝機があったとすれば、空母搭載機を零戦と偵察機だけにして、水上部隊のエアカバーと索敵だけに徹し、その保護の下に戦艦群は射程内に肉薄し、攻撃は戦艦と巡洋艦による砲撃と、駆逐艦による雷撃に徹するしかない、と考えられる。海軍はハワイ・マレー沖の勝利以来、攻撃は航空攻撃しか行わなくなっていた。
⑨やる気のない栗田の水偵放棄
左近允尚敏氏の捷号作戦はなぜ失敗したのか、は著者の経歴によって類書とは隔絶した評論となっている。全般については、別途述べるとして、ここではひとつだけ考えてみたい。それは、栗田艦隊が、故意に艦載の偵察機を射出して基地に帰してしまったことである。「栗田艦隊司令部は二十三日午前と二十四日の朝、艦隊の水上偵察機四〇機以上を手放してしまった。」(P319)とあり、草鹿参謀長は、その理由をブルネイから出撃する際には警戒を厳重にしなければならないので、水偵のほとんどをミンドロ島に進出させ、艦隊の航路の対潜警戒にあたらせることになった、という。
ところが対潜哨戒は行われず、逆に米潜に自由に跳梁されているから話にはならない。栗田の参謀としてこの指揮をとった小柳少将は、戦後の著書でサマール沖海戦について「惜しいことに飛行機皆無の栗田艦隊はこれ(レイテ湾)を確かめる方法はない、と書いて著者に「手放した責任者の『惜しいことに』は驚かされる。」(P320)と無責任さに呆れている。他人事のような無責任の言動に腹が立ったのである。戦死せずレイテ湾から逃げ帰った艦隊の幹部には、このような人物が多数いる。
著者は水偵がいれば危険な任務だが、スコールと煙幕を利用すれば米護衛空母艦隊の状況はかなり把握できたろうと惜しんでいるが、その通りで、これこそが艦隊に艦載機を搭載した本来の任務だからである。艦載機は海戦中に弾着観測や敵艦隊の状況把握のために搭載されているのである。その艦載機のほとんどを出撃直後に手放したのは、栗田艦隊の司令部が初手から海戦をやる気がないことを証明している。
善意に解釈すれば、栗田艦隊は艦載機搭乗員の命を惜しんだのであろう。水偵は複座の零式観測機か、零式三座水偵だから、四〇機ならば、搭乗員は100人前後にもなろう。搭乗員としてはかなり大勢である。海戦中に敵艦隊に向かって行った艦載機は敵戦闘機の迎撃を受け、帰還できる見込みは少ない。まして、このときは、水偵をカバーする零戦は一機もいない。海戦中に帰還したところで、停止できる艦はいないから、見捨てられる。それならば、いっそ帰してしまえと考えたとしても不思議ではない。不思議ではないが、何としても敵艦隊に勝つという戦略が感じられない。
⑩米戦艦は対艦攻撃機より強かった
第二次大戦で、戦艦に対する飛行機の優位が証明された、とするのが定説である。しかし、第二次大戦中の米戦艦に関しては、話は別なように思われる。英戦艦に関しては、九六式陸攻や一式陸攻といった大型鈍重な機体さえ、独力では排除できなかった。二隻の戦艦に対して随伴するのが、巡洋艦なしで、駆逐艦だけ四隻と言う貧弱かつ変則的な編成であったのも英海軍の間抜けさであった。
それでも、戦闘機の防空体制があれば、陸攻の攻撃は極めて困難であったと考えられている。日本海軍は、大戦果にそのことを等閑視して勝利から戦訓を得ず、陸攻によって容易に戦艦は撃沈できると考えて、ラバウルでの航空戦を戦って機材とパイロットの損耗を重ねた。
ラバウル航空戦を含め、大東亜戦争の期間中、真珠湾攻撃と言う停泊中の奇襲攻撃を除けば、日本機が米戦艦を撃沈したことはない。米戦艦に撃沈に至らずとも、航空機より大きな戦果をあげたのは、潜水艦であった。多くの戦記を読めば、航空機に対して米戦艦は自艦の対空砲火で防御することができていたようと考えられる。逆に日本機は駆逐艦ですら航空攻撃にてこずっている。
米海軍では、随伴の駆逐艦はほとんどが、両用砲で対空射撃ができたから、エスコートの役割が可能であったが、他の海軍はこのような駆逐艦を持たなかった。両用砲がなければ、駆逐艦の40mm以下の機銃では、有効射程距離からして自艦の防御をするのが、せいいっぱいであったろう。
単独航行していても、米戦艦に日本機は大きな被害を与えることができなかったのであろう。このことは、複葉機すら撃退できなかったドイツ戦艦や、陸攻に撃沈された英戦艦、もちろん日本戦艦もであるが、米戦艦の個艦防空能力は隔絶したものがあるように思われる。
小生はこの相違は、以前書いたように、対空火器管制システムの優劣だと考えている。とすれば同一システムが英国に供与されていなかったことになり疑問を感じるが、マレー沖海戦の戦闘航海中の英戦艦が、二隻でたった三機の陸攻しか撃墜できなかった事実から、Mk.37などの米国製火器管制システムあるいは、類似のものが技術供与であっても提供されていなかった可能性が大である。少なくとも昭和16年の時点ではそうであったのに違いない。開戦時に二隻の英戦艦が相手にしたのは、防弾装備の優秀な米軍機ではなく鈍重かつ防弾装備がないか、なきに等しい陸攻であったからである。
戦後、ソ連が米艦隊に対して考えた対艦攻撃法は、実に理にかなったものである。米艦隊への有人の攻撃機では確実に撃墜され、人的にも機材にも被害が大きすぎる。第二次大戦後、ミサイル誘導技術が飛躍した結果、無人の対艦ミサイルが実用化された。しかし、小出しに対艦ミサイルを撃ち込んでも確実に撃墜されて戦果は得られない。そこで飽和攻撃を生み出した。いくら対空火器が優秀でも、防空戦闘機が守っていても、対応可能なミサイルの数にはシステム上の限界がある。
従って、その限界を超える数のミサイルを撃ち込めばいいのである。これが飽和攻撃である。それに対して米国が発明したのは、多数の敵機を同時に処理できるイージスシステムである。この発明によって処理可能なミサイル数が飛躍的に増え、飽和攻撃は現実には困難となった。これが現在までの艦艇と航空機の矛と盾の争いの経緯である。従って第二次大戦中はもちろん、戦後もしばらくは、米戦艦への対艦攻撃は極めて困難であった。すなわち米戦艦は航空機よりも強かったのである。
⑪陸上要塞は艦隊より強いのか
陸上要塞は艦隊より強い、というのは定説のようである。だが、その実例はどこにあったのだろうか。大口径の要塞砲は戦艦の主砲の転用が多いから、口径において同等の艦砲の軍艦で戦うことは可能である。数においても、要塞の砲数は予測できるから、それを上回る艦隊を準備することは可能である。
照準について、要塞砲は固定されているから、海上のどの位置にいてもそこに打つことができる、というような話を聞いたことがあるが、もしブイなどの固定目標を海上に置いても艦隊が破壊することは可能である。目標のなくなった海面の平面座標をどう設定できるのであろうか。要塞砲で陸上を打つなら、ひとつの固定目標の座標に命中させて、そこからの東西南北の距離が分かれば、座標が特定できるが、固定目標がない海上ではそうはいかない。
反対に軍艦は移動するから、要塞砲による初弾の修正は困難である。自艦の速力と進路は分かるから、固定された要塞砲の位置があらかじめ分かれば、軍艦による初弾の修正は容易である。素人考えであるが、このように考えると、机上の検討では陸上要塞は艦隊より強いとは思われないのだが。
余談だが、出典は忘れたが、開戦時点では日米海軍とも戦艦の主砲には、徹甲弾しか搭載していなかったそうである。零式普通弾のような榴散弾あるいは榴弾のようなものは搭載していなかったというのである。従って艦艇に対する攻撃はできても、真珠湾要塞に対する攻撃は困難である。
徹甲弾だけでは砲台を直撃しなければ、破壊は困難である。榴弾効果のあるものも混ぜなければ、有効な攻撃は困難であろう。それより随伴した空母の艦上機を使えばよい。艦戦で制空権を確保して、艦爆で砲台を攻撃する。島嶼攻撃で米海軍が常用した手法である。その間に、戦艦群は湾内の太平洋艦隊を砲撃するのである。この方が、従来、戦艦や空母が訓練や実戦で実施してきたことと乖離もない。ただし、真珠湾の太平洋艦隊を、開戦時点で攻撃すべきであったか否かは別問題である。
⑫陸上要塞は艦隊より強いのか2
過日、陸上要塞は艦隊より強いのか、という記事を載せたところ、小生の典不明と断って、開戦時日米海軍とも戦艦の主砲には徹甲弾しか載せていなかったそうである、というコメントに対して「風来坊」さんから、「平時から徹甲弾と榴弾は同時に搭載していたはずです。確か8:2ぐらいの割合で。」という指摘をいただきました。
調べてみると、小生の方の出典が判明しました。学研の歴史群像シリーズで「日本の戦艦 パーフェクトガイド」の中に、軍事史研究家の大塚好古氏の「日本戦艦が搭載した主砲と砲弾」という記事です。この記事は小生が今まで読んだものでは、日本の戦艦の主砲弾の種類の歴史について書かれたもっとも詳しいものです。関係あるところだけかいつまんで説明します。
「日露戦争当時の日本海軍の戦艦が使用した砲弾は、徹甲弾と榴弾(弾頭部に信管をもつ瞬発型のもの。当時は高爆弾もしくは鍛鋼弾と呼ばれていた)の2種類であった。(P181)」のだが徹甲弾でも当たってすぐ爆発するので装甲を貫徹できたのは、日本海海戦でたったの1弾だけが、6インチ装甲を貫徹しただけであったそうである。
明治38年の香取型「完成と同時に、被帽徹甲弾と弾底遅動信管付きの被帽通常弾が日本海軍にもたらされることになった。(P183)」とようやく弾底信管が登場するが、徹甲弾ではなく通常弾すなわち榴弾に取り付けられていることが理解不能である。
その後外国技術の研究から、大正2年に三式徹甲弾が採用され、大正後半期まで使用されたとある。そして徹甲弾は遠距離砲戦での効果が期待できなかったため、遠距離でも効果がある、通常弾か榴弾が必要と考えられたが「検討の結果3種類を随時切り替えて砲戦を行うのが理想と考えられたが、・・・徹甲弾と被帽通常弾の2種類を搭載することが最終決定されている。P183)」ということである。
その後ジュットランド沖海戦の戦訓から、砲戦途中での弾種変更は方位射撃盤の設定変更が必要で、多大な時間を要するなどの問題があり、弾種統一が模索されて「・・・通常弾、徹甲弾、半徹甲弾のいずれを搭載するかが研究され、大正9年に8インチ砲以上の砲については、徹甲弾の搭載が原則となった。これを受けて昭和5年頃には戦艦の搭載する砲弾は徹甲弾に統一され、太平洋戦争途中まで続くことになった。(P184)」
なお、前回は「日米海軍とも」と書いてしまったが、本書を見る限り米海軍に関して、そのような記述はないので、訂正させていただく。また零式普通弾と書いたが、零式通常弾の間違いのようであるので訂正させていただく。本書ではさらに「・・・零式通常弾と三式徹甲弾が戦艦用の主砲弾として制式採用されたのは昭和19年であるが、それ以前の昭和17年中期以降から、限定的ではあるが各艦への搭載が行われている。(P185)」と書かれている。弾種から言えば、零式は榴弾で三式は榴散弾の一種であろう。
採用年と実戦使用の年が合わない例はあるので、上記文中での年号が混乱しているように見えるのはさして不自然ではないと、小生には思われる。ただ、本書を読んでいただければわかるように、これだけの多くの情報を記事にしながら、出典や根拠が記載されていないのは残念である。また、大塚氏の言うように、徹甲弾しか搭載されていなかったとしても、榴弾の備蓄があったのかも知れない。日本海海戦では、装甲貫徹効果はなくても、榴弾効果だけであれだけの戦果を得ていたことに、当時の海軍で拘っていた論者が根強くいた、と大塚氏が書いているからである。また、通常弾を追加搭載した際に、方位射撃が改造されていなかったとすれば、通常弾を積んでいなかった時点でも、方位射撃盤には、通常弾の設定が可能であった、ということになる。
また風来坊さんが徹甲弾と榴弾を混載していた、という根拠を教えていただければ有難いのですが。ぜひ原典にあたって調べてみたいと考える次第である。また、旧海軍の砲術のプロとして名高い、黛治夫氏の「艦砲射撃の歴史」という本を入手したので、上記の点についてどのような記載があるか読んでみたい。ただし、小生の学力で読破できるか、はなはだ覚束ないのであるが。
⑬なぜ米軍は日本の艦船にスキップボミングを始めたか?
元々米軍は双発機以上の大型の機体による雷撃は、魚雷の投下場所まで直進しなければならず、しかも目標が大きいので対空砲火による危険が高すぎると見ていた。従って米陸軍も爆撃機に雷装はしなかった。日本陸軍のように、はなから艦船攻撃を考慮していなかったのとは異なる。B-17などによる艦船爆撃の場合も中高度以上からで命中率は悪くても、安全に攻撃していた。
艦上機ですら、米軍は急降下爆撃によって、撃沈より損害を与えて敵艦の能力減殺することを主目的としていて、撃沈の可能性が爆撃より大きいにもかかわらず雷撃機は、従の存在だったことからも、米軍は雷撃による被撃墜を考慮していたことが分かる。
ところが戦争中期頃までに、米軍と比べると、日本の艦船の対空防御能力が著しく低いと見切ってしまった。しかし、今更爆撃機に雷装する改造を施しても、コストがかかるだけなので、爆撃により雷撃に似た効果がある、スキップボミングを採用した、という訳である。
爆弾は魚雷より遥かに安く、軽量である。しかも、速度が桁違いに大きいから命中率が高い。舷側に命中するから、装甲の薄い艦船なら撃沈が可能である。。欠点のひとつは、海面を跳ねるように、爆弾を投下するのに技量を要することだが、魚雷とて、それなりの腕が必要である。欠点の最大のものは、波浪の高さによる爆撃実施不可能なことである。
雷撃同様に、爆撃コースに入った時の対空砲火対策として、B-25などは艦船や地上攻撃用として、機首に機銃や大砲を固定して、銃砲撃しながら攻撃できるような型もあったから、艦船の対空砲火を制圧しながらのスキップボミングもできた。いずれにしても、スキップボミングが多用されたのは、駆逐艦などの小艦艇や輸送船など、元々日本の艦船でも防空能力と装甲がなきに等しいものであった。
⑭フィリピン沖海戦考
雑誌「丸」平成27年11月の特集では、フィリピン沖海戦の栗田の評価がほぼ真逆な論など色々な論考が載っている。これを閲することは、大東亜戦史を考える上で興味ある問題である。
「史上最大の海戦『捷一号作戦』考」で小高正稔氏は、栗田艦隊は小沢艦隊が米機動部隊の誘因に成功したことを十分認識していなかったこと、上陸作戦を防ぐには上陸船団攻撃だけではなく、艦隊主力である機動部隊を撃破して制海権と制空権を確保することが最重要であると指摘する。
そのために、サマール沖にいた正規空母(間違いであったにしても、そう認識していた)を叩くこと、北方にいると通信情報で認識していた機動部隊を叩くことは、「リスキーなレイテ湾突入」より選択肢としては正しい、という。だから反転は「謎ではなく、常識的思考の範疇である選択であったかもしれ」ず「・・・栗田の決断を『謎』とする考えは、有力な艦隊を全滅させても作戦目的を実現すべきだという、合理性と狂気の共存を許容する発想」であって「栗田の思考は、実はだれより正気であったかも」知れない、と結論する。
これは、レイテ湾に突入しても上陸部隊を阻止することができる可能性が全くなければ、反転帰投する、という判断は氏の言うように正しいのかもしれない。しかし、一方で全滅を覚悟して北方に米機動部隊を誘導しようとした小沢艦隊からすれば、失敗しても全滅は免れなかったつもりだろうから、情報収集の努力もせずに成功しなかった可能性大、と判断されたのではたまったものではない。現に西村艦隊は、小沢からも栗田からも情報を得なくても予定通り突っ込んだのである。眼前でそれなりに有力な西村艦隊が全滅するのを見た、弱小な志摩艦隊が逃走したのは仕方あるまい。
もうひとつの桐原敏平氏の「『栗田艦隊反転のナゾ』に迫る」、という論考もある。これは小生が過去に論じたものに近い。氏はまず、下記の疑問を提示する。
1.現に目の前にいた護衛空母を正規空母と判断していたのにこれを追いかけず、なぜ不確実な電信情報による敵機動部隊に向かったのか。しかも電信情報を受けてから三時間もたって機動部隊に向かったのだ。その電信も大和艦上において受信したのを記憶する者がいないなどの疑問が多く、捏造の可能性すらある、という。
2.西村艦隊を迎撃した有力な水上部隊がレイテ湾付近にいて、作戦命令は明確にそれを攻撃することを指示していたのになぜ無視したのか。
3.湾内に輸送船団がいなくても揚陸直後の上陸部隊を攻撃するのは有効かつ作戦命令にあったのになぜ実行しなかったのか。
4.レイテ湾突入が遅れるのが明白なのに、なぜ、西村と志摩艦隊に予定時刻変更の指示を出さなかったのか。これは同時突入の効果を狙うどころか、偵察機によりレイテ湾にいることが分かった、敵水上部隊を西村・志摩艦隊に向けて、自分は脅威を避けるつもりだったと言われても仕方ない、という。
以上の疑問は、かなり栗田艦隊の意図に疑義を持たせるのに十分である。氏は栗田は愚直に命令に従うとか、勇猛果敢である、という資質に欠けている、という。指揮官としての栗田はバタビア沖海戦やミッドウェー海戦において特異な行動をとったことからも明らかである、という。
結論としては、どの時点でも栗田は何らかの情報を理由として、レイテ湾突入を放棄反転帰投したはずだ、ということである。このことは、栗田が最初から計画的に逃げ帰ることを考えていたのではなく、性格的に色々な情報から、そういう決断をするような性向があったというのである。
早川幸夫氏は「幻の勝利 もしもレイテ湾に突入していたら」というイフを論考している。これは従来のものと大きな違いはない。レイテ湾のオルデンドルフ艦隊は、全体的には必ずしも旧式な戦艦ばかりでなく、西村艦隊を撃滅した後でも、砲弾の残量は一海戦を戦う分は残っていて、栗田艦隊にしてもそれまでの海戦で、砲弾艦艇を消耗していたから、勝機はないであろう、という。
勝機があるとすれば、西村艦隊と協働して突入したときであるが、それでも、別のアイオワ以下の米艦隊が海戦後に追いつき、ハルゼーの機動部隊が参戦し、最終的には日本艦隊は壊滅する、ということになる。海戦に限ってみれば、レイテ湾に突入すれば、確かに日本艦隊はフィリピン沖で壊滅する、というのは確実であろう。ただ早川氏は、栗田の判断が正しかったかどうか、という点には言及していない。
三氏の論考を比較すると、小高氏は桐原氏が疑問視する北方の機動部隊の存在について、何も考慮していない点に無理がある。早川氏は艦隊の海戦の勝敗については正しいが、作戦の根本目的である、米軍の上陸阻止の可能性には言及していない。桐原氏はレイテ湾突入により上陸部隊を効果的に攻撃できる、と結論しているのだが、その後の陸戦の帰趨については論究していない。
堤明夫氏は「サマール沖海戦の栗田艦隊砲戦実力」として栗田艦隊の攻撃の有効性を詳細に検討している。結論から言うと、砲弾の命中率については、混乱した実戦であることを考慮すると、まずまずであるが、水上戦の戦闘陣形が全くなっておらず、各艦が勝手に敵を追い回していただけで、艦隊司令部が全く機能していなかったとする。大艦隊が、低速の護衛空母と駆逐艦を相手に苦戦したのを見れば、当然の評価であろう。日本海軍は艦隊指揮官に砲戦の戦闘陣形を考えるトレーニングをしていなかったのではないか、とすら思える。
この点は勇猛果敢にスリガオ海峡を突破した西村艦隊も、その士気は称賛に値するが、絶望的な戦いなら、少しでも戦果を挙げるための、精緻な艦隊行動が必要だったのであろう。例えば、素人考えの結果論であるが、レイテ湾にはオルデンドルフ艦隊が並んでいたのだから、まず水雷部隊を突入させ、全魚雷を一斉にレイテ湾に向けて発射することもできたのではなかろうか。
以上四氏の論考を総合すると、栗田司令部の戦闘指揮さえ適切ならば、サマール沖でも、レイテ湾でも日本艦隊は、より大きな戦果を挙げたであろうが、最終的には全滅する可能が高かったであろう。
すると大きな疑問が残る。艦隊を全滅させてでも、米軍の上陸を阻止する行動を取り、米艦隊にかなりの打撃を与えることが出来た、として、その後のフィリピン戦の帰趨はどうなったであろうか、ということである。この点については、悲観的な論者が多い。それならば、捷一号作戦を発動しないか、日本海軍には別な戦い方があった、ということでなければならない。
考慮しなければならないのは、何とか帰投した栗田艦隊であるが、大和は絶望的な出撃をし、多くの乗組員とともに沈没した。他の戦艦以下も呉に係留されて生かされることなく壊滅した。つまり、栗田が生きながらえさせた艦隊は、その後なすすべなく結局全滅したのである。
小高氏の言うように、レイテ湾突入は狂気の沙汰であろう。だが、桐原氏の言う戦士の資質としての「命令を愚直なまでに忠実に実行し、かつ勇猛果敢に戦う気質」というのは戦闘には必要な資質であるが、狂気の沙汰と紙一重である。日清日露、支那事変、大東亜戦争と、日本軍の将兵はそうして戦い、あるときは勝利したのである。日本軍が強い、と言われたのはそのためである。
⑮大和撃沈を空母に任せたのは軍事的合理性
平成28年8月の雑誌「ミリタリー・クラシックス」54号には、大和撃沈の顛末が書かれている。大和の沖縄出撃を知った、ミッチャー提督がアイオワ級4隻とサウスダコタ級2隻による攻撃を具申した。このことは、戦艦は戦艦で仕留めたいという伝統的願望によるものと評するむきが多い。しかし、太平洋艦隊司令部は、沖縄上陸戦闘が開始されたばかりで、16インチ砲の艦砲射撃が必要となる可能性大として却下し、機動部隊による攻撃を命じたというのだ。
全くその要素はない、とは言わないが、本当の原因ではあるまい。なぜなら大和攻撃に向かった艦上機も戦艦群と同様に上陸支援に必要だったのである。そもそも大和攻撃の機動部隊の護衛として新型ばかりではないにしても、6隻の戦艦をさいているのである。根本的原因は作戦の合理性にある。大和撃沈に必要な米軍の損害の多寡を計算したのである。
過去の海戦の経験から、日本の対空戦闘能力の著しい低さを米軍は知っている。駆逐艦は対空戦闘能力は無きに等しい。防空駆逐艦と呼ばれた秋月型にしても、対空火器管制システムが大抵の米駆逐艦よりずっと劣る。戦艦や巡洋艦の高角砲も同様である。
例えばシブヤン海海戦で武蔵は多数の雷爆撃に耐えて、ようやく沈んだ。しかし、攻撃機の被害は大したことはなかったである。武蔵撃沈での米軍機の搭乗員の戦死者は数十名にも及ぶまい。一方第三次ソロモン海戦で、老齢の戦艦霧島は撃沈されたものの、16インチ砲の最新戦艦2隻と打ち合い、致命傷こそ与えなかったがサウスダコタに多数の命中弾を与えて戦場を離脱させた。上構を大破させたのである。
その被害は、人命とともに多大なものがあった。戦死者は数十名どころではなかったであろう。だから、たとえ大和1隻を最新鋭戦艦6隻で襲ったとしても、大和は沈没と引き換えに、1隻の撃沈あるいは、多大な損害を与えることはできだであろう。そう考えれば空母機動部隊の攻撃の方がはるかに損害が少ないことは想像できる。まず米艦艇の損失はあり得ないのである。
事実は結果が証明している。日本軍は大和以下6隻と約3700人を失い、米軍は艦上機10機と、搭乗員12名を失うという微々たる被害であった。
○日米の制空権下での艦隊決戦思想の相違
倉山満氏は「飛行機で戦艦を守れるようにしよう。制空権を取って艦隊決戦を有利にしようとしました。艦隊決戦主義から、制空権下での艦隊決戦主義になったということです。」(1)(P175)と書いている。一方で日本も航空機の発達から制空権下での艦隊決戦主義に移行したと言われている。だがその中身には当然相違があったと思われる。
双方に共通しているのは、弾着観測に航空機を活用し、砲の命中精度を上げるために、観測機を守るための制空権確保、ということである。それでも違いはある。日本の場合は弾着観測機を艦上戦闘機で守ることを考えた。零戦の航続距離が異常に長いのは、艦上攻撃隊の援護や陸上攻撃機の援護のためではなく、艦隊上空を観測機援護のために長時間飛行するためである。そのことをはっきり指摘したのは兵頭二十八氏と記憶している。
零戦の開発が開始されたのは、支那事変が始まった当時であり、戦闘機無用論もあった位だから渡爆撃機の援護の重要性が全く認識されておらず、当初の要求仕様は航続距離ではなく、滞空時間で示されていた。
米海軍の場合は、敵攻撃機は艦上戦闘機と、両用砲の対空砲火の二種類によって守ることとしたと考えられる。敵艦の中でも、特に空母を主として攻撃し、敵空母の航空機運用能力を無くすことを主任務にしていた。だから米空母の場合、艦上戦闘機と艦上爆撃機の比率が日本に比べて高く、雷撃機の比率が低い。戦闘機は艦隊防空と攻撃隊の直掩に使うからで、爆撃機は空母の飛行甲板を破壊して航空機運用能力を無くせばよく、必ずしも撃沈する必要はないと考えた。こうして制空権を握った上で、主力艦の決戦を行う。
駆逐艦の主砲に対空兼用の、両用砲を全面的に採用することによって、他の海軍と異なり米海軍は駆逐艦にも防空能力を持たせた。大戦後半の圧倒的防空能力とはいかなくても米艦隊は効果的な対空火力を持っていた。既に緒戦の珊瑚海海戦で日本海軍の艦上機搭乗員は、そのことを身を持って知り、戦訓として上申したが海軍上層部の取り上げるところとはならなかった。
ミッドウェー海戦では、多数の米雷撃機を零戦が撃墜し、一本の魚雷も命中させられなかったことから、敗北の結果となっても、米艦隊の防空能力の高さを認識することはなかった。運が悪かったことを意味する「魔の五分間」という神話の罪は重いのである。澤地久枝氏の「滄海よ眠れ」にも書かれているように、全体の戦死者は日本側が遥かに多かったにもかかわらず、パイロットの戦死者は米側の方がずっと多い。これは、米空母を攻撃したのは飛龍だけだったことによる。要するに、敵艦隊攻撃に参加した航空機は米海軍の方が遥かに多かったために搭乗員の被害の絶対数が多くなったのである。
日本海軍の場合は軍縮条約で劣勢に立たされた主力艦比率のために、まず決戦の前に主力艦を少しでも減らすことを考えた。そのために艦攻による雷撃ばかりではなく、陸上攻撃機を太平洋の島嶼に配置して、攻めくる米艦隊を雷撃する、陸上攻撃機なる、他の海軍に例のない機種を発明した。
日本はあくまでも、艦隊決戦以前に主力艦をより多く撃沈する意図だったのである。だから、主力艦を撃沈可能と考えられた雷撃を敵艦攻撃の主力とした。後で再浮揚したことや戦略的要素を考慮しなければ、多くの戦艦を破壊した真珠湾攻撃は、この意図からは成功だった。マレー沖海戦は、陸上攻撃機が主力艦撃沈に有効であるという幻想を日本海軍に抱かせてしまった。
わずか90機程度の陸攻が戦艦を2隻も撃沈したのだから、陸攻に期待するのも無理はない。しかし、その後の陸攻は期待に外れ、恐るべき被害に比べて戦果は挙がっていなかった。マレー沖海戦の幻想が、戦果を過大評価させ、現実の戦果を見誤る結果となったのである。
では陸攻が海軍から無用になったのか、といえばそうとも言えない。陸攻の思想を結果的に受けついたのは、ソ連だった。ソ連は戦闘爆撃機や爆撃機に対艦ミサイルを搭載して、米空母を飽和攻撃によって撃沈しようとしたのである。魚雷に替わって対艦ミサイルがソ連の「陸攻」の兵装となったのである。
まともな空母を運用できなかったソ連は、陸上から発進する爆撃機によって主力艦となった米空母に対抗しようとしたのである。航続距離の長い爆撃機から、米空母の防空圏外から、長射程の対艦ミサイルを米艦隊の防空能力を超える多数を同時発射して、撃ち漏らした対艦ミサイルで米空母を撃沈しようとした。
正に陸攻の理想とした能力を備えたのだった。ある時期に米ソ海軍が衝突したら、この企図は成功していたように思われる。しかし、よく知られているように、米海軍はイージスシステムを開発して、敵機の同時対処能力を飛躍的に増やして対処した。ソ連がカタパルトを持たないとはいえ、正規空母を持とうとしたのは正解であろう。
しかし、本質的に大陸国であるロシアが、旅順艦隊とバルチック艦隊の全滅以来、本格的な外洋艦隊を持たないのは、ロシアの宿命であるかも知れない。ソ連崩壊によってロシアは世界帝国であることを止めた結果、外洋艦隊を持つ必要はないのかも知れない。かつてはロシア帝国とはいっても、ヨーロッパ外交の1プレーヤーに過ぎず、ソ連崩壊によって、ロシアは世界帝国から元の地位に戻ったのである。
(1)負けるはずがなかった!大東亜戦争・倉山満
3.海軍には戦略はなかった
①戦略なき海軍
海軍の基本戦略は日本に侵攻する米艦隊との艦隊決戦であったという。だがこれから発生するのは戦闘の計画であって、作戦計画ではない。この錯誤は日本海海戦の大勝利による倒錯的思考でしかないように思われる。日本海海戦は別の作戦目的から発生した結果であったのに、昭和の海軍は結果を目的にしてしまった。日本海軍の日露戦争時の作戦目標とは、陸軍を朝鮮半島に輸送することと、日本近海の制海権を維持することであった。ロシア海軍が日本近海の沿岸輸送を阻止して日本の食糧やエネルギー事情を悪化させることと、日本への上陸を狙っていると考えたからである。
派遣されるであろうバルチック艦隊と旅順艦隊の合同によるロシア海軍の強化を阻止するために、まず劣勢な旅順艦隊から撃滅しようとした。そのために旅順港閉塞を行ったのは拙劣と批判されるが、単に戦うばかりではなく目的のある作戦という意味では艦隊決戦思想よりはましである。旅順港攻撃により旅順艦隊を全滅させると、残りはバルチック艦隊であるが、これとて日本攻撃を迎撃するのではなく、まず艦隊の旅順への回航阻止であった。大東亜戦争で言えばサンフランシスコか、パナマ運河経由でハワイに回航する艦隊を途中で阻止したようなものである。勿論回航距離の差と迎撃が日本近海であったことを考えれば大東亜戦争の方が条件が悪い。
しかしその後の技術の進歩は考えるべきであるし、日露戦争の教訓からは回航阻止の目的に従った技術開発も行うべきであったであろう。現に日本は近海での迎撃という戦術にこだわったために艦艇の航続距離が短く、米海軍は日本侵攻を考えたために航続距離が長い。なるほど日露戦争の戦略とて事前に計画されたものではなく、危機が迫って追い込まれた結果の発想だから単に日露戦争時の軍人が優秀というわけではない。しかし昭和の海軍には日露戦争という戦訓があり、何よりも考える時間があった。それを米海軍を日露戦争同様の良い条件で、日本近海で迎撃するという考えから一歩も出なかったのはむしろ退化である。
そこには何のために迎撃するかという目的が欠落していて、米艦隊が攻めてくれば近海で迎撃して艦隊決戦がしやすいからという本末転倒した発想となっている。空母機動部隊にしても暫減戦術の道具であった。それを突如主役にすえてしまったのである。兵頭二十八氏がこれほど長年の戦略を突如変更した海軍はない、と言うのも当然であろう。突然の危機に接して空想から現実に転化したのである。つまりそれまでの日本海軍は自分の都合のよいありもしない夢を見ていたのである。そこには来るべき危機を想定するという発想はなかった。
米国は有名なオレンジプランという日本侵攻計画を何十年も練った。大東亜戦争における米軍の反攻作戦は大筋でオレンジプランに従ったものであると言われている。プランが明瞭だからこれにそった兵器開発の方針の決定は容易である。
日米戦争を想定した日本海軍なのだから、日米の対立が激化すれば米国はどう出るか、ということを考えてみればよかったのである。石油と鉄という海軍必須の軍需物資を米国に依存している日本。米国が開戦前から禁輸すると予測しなくても、開戦して後米国からこれら物資が輸入できるはずはあるまい。しかもこれらの物資は消耗品である。とすれば、開戦後にこれらの物資をどこから調達するかということを考えなければなるまい。これは後知恵ではない。現に日本海軍は米国の禁輸が始まると蘭印からの石油調達をすぐに考えたのだから。つまり海軍は起こるべき現実に目をつぶり、危機が発生するまで何らの計画も立てなかったのである。
日本海軍は自分のした作戦を相手がすると考えず、自分がやられては困る作戦を相手に強いるという発想が何故か欠如している。艦隊決戦計画では、日露戦争で日本はロシア軍の占領地に侵攻したのにもかかわらず、日米戦争では米軍が本土ではなくまず占領地に侵攻するとは考えなかった。すなわち石油が必要なら蘭印に侵攻し、蘭印に侵攻するならシーレーン確保のためにフィリピンを占領するしかない。
するとこれらは日本本土より先に逆上陸されるはずである。米海軍は日本艦隊が大挙待っている日本本土に直接侵攻するより、より近海の日本占領地を攻撃する方が容易で、戦争資源の遮断による日本の継戦能力の途絶が可能となる。このような想像力もなく日本近海での艦隊決戦を想定したのは、現実に対米戦争を行う意志はなく、単に組織維持と予算獲得という官僚的発想だったと言われても仕方あるまい。
ガダルカナルへの鼠輸送に対する補給阻止にあれだけ苦しみながら、ハワイや西太平洋の占領地に対して何らの補給阻止をも行わなかった。繰り返すが日本の補給線よりも米海軍の補給線のほうが遥かに長く、島嶼という遮蔽物も少なく不利なのである。よく日本の潜水艦はドイツ海軍のように通商破壊作戦を行わなかったと批判される。
ドイツの通商破壊とは軍需物資だけではなく、孤島であった英国に対する民需の物資の補給の意味も大きかったから通商破壊というのである。太平洋方面では米国の民需物資の輸送の比率は少ないから、武器弾薬、兵員、艦船の回航などの軍事物資の輸送であったので通商破壊というのは適切ではないのではあるまいか。
このように日本海軍が近海における迎撃作戦だけを考えたために起こる不利は、単に作戦計画上のものばかりではない。航続距離をはじめとする艦艇の性能諸元はもとより、艦種の編成にも影響を及ぼす。例えばフィリピンなどの島嶼での作戦を考えなかったため、魚雷艇の開発がほとんど行われなかった。南洋からの資源輸送や通商破壊を考慮しなかったために、船団護衛や対潜防御に有効な兵器はほとんど開発しなかった。米軍が支那事変で使用され大発からヒントを得て、LSTなどの上陸作戦用艦艇を準備したのに、オリジナルの日本が後遅れになり有効に活用できなかった。必要に迫られれば日本人にもオリジナリティーはある。
工業力の差とは言え、戦艦や巡洋艦など大型の戦闘艦艇の開発にあまりにもエネルギーを費やしすぎたと言わざるを得ない。船体ばかりではない。大和型においては46センチ砲を始めとする諸兵装などの開発には相当のエネルギーを要したであろう。この努力をバランスよく振り向けることができたらと思うのである。
②戦略なき海軍の戦略は組織維持組織
陸軍の対ソ防衛、いわゆる北進論に対して南進論を伝統とした。相澤氏は*三国同盟に海軍が当初反対して途中から急に賛成に回ったのを、首脳の入れ替わりにより説明する従来の主張に対して、実は当初の三国同盟がドイツとの提携による北進論であったのが、独ソとの提携により米英を牽制する南進論となったからと論証している。同盟締結時の海相である及川は昭和十一年に海相と軍令部総長に、北進の意見具申を行っていたのだという。つまり及川は個人的考えで同盟に賛成したのではなく、海軍としての立場から賛成したに過ぎないと相澤氏は論証しているから、海軍首脳が賛成派に変わったという従来の説は説得力を失う。
では海軍の言う南進論とは何か。第一次大戦で得たトラック諸島などの、委任統治の南洋群島の確保であった。だが考えてみれば群島は海域は広大であるにも関わらず、日本の生存にとって重要なものではない。海軍という軍事の立場から考えても、広大な海域に散在する島は攻めるに易く、守るに難いのは素人でも分かる。そんな南進論を考えたのは陸軍に対抗する大艦隊を維持するために過ぎない。すなわち予算と組織を確保拡大するという悪しき官僚主義の発想である。そんな発想をせざるを得なかったのは海軍に戦略がないからに他ならない。
すなわち海軍にとっては対米7割の艦隊を維持すること自体が目的と化していた。なぜ7割の艦隊の維持かといえば、米艦隊と艦隊決戦に勝つためには、個艦の優越や訓練による技量の向上により勝てる可能性のあるのが7割だというのである。ここで考えられたのは漫然と日本近海に接近する米艦隊に対して、日本艦隊が艦隊決戦を挑むという抽象的なことである。そこには米艦隊が何のために来るかという発想が欠落している。
ロシアのバルチック艦隊は艦隊決戦を行うために来たのではない。とりあえずウラジオストックに艦隊を回航するという目的であった。何度も言うが日本海軍の目的も1隻でもウラジオに到着する艦艇を減らそうとしたのであって、艦隊決戦なるものは結果としておきたのである。だから日本海軍はウラジオに艦隊が行くのにどのルートを通るか想定するのに腐心したのである。
ところが昭和の海軍では結果として起きた艦隊決戦が自己目的化してしまった。米国はオレンジプランなる対日戦争計画を持っていたのは有名である。しかしそれを持って日本征服計画と必ずしも断定できない。艦艇の種類や数量、性能などを検討するためにはどのように対日戦争を戦うかを想定しなければならない。米海軍は日本海軍にない魚雷艇を開発運用していた。
それは対日侵攻の際にフィリピンなどの島嶼海域で戦闘が起きれば、航洋性や航続力が劣っても、島影からゲリラ的に大型艦艇をヒットエンドラン攻撃ができる魚雷艇のコストパーフォーマンスが高いと考えたのであろう。米魚雷艇の活躍に驚いた日本海軍は、艦艇技術は高いとされていたのについに魚雷艇を実用化できなかった。
日本の艦艇は潜水艦を除いて米海軍より著しく航続力が少ないが、それは日本近海だから航続力は少なくてもよく、その分を攻撃力向上にあてたのであった。だから現実に開戦して真珠湾を攻撃する段になると、燃料補給に苦労するのであった。その点、米海軍はオレンジプランに近い形で戦争を進めたから、性能に不足することはなかった。
その点まだ陸軍の方が良いといえよう。陸軍に石原莞爾のような戦略家が出ても、海軍にいないのはそもそも、陸軍には満洲の権益を守るという国家的な責務があったからである。海軍にはそのような責務がなく、単に日本防衛という抽象的な考え方しかなかったから、勝手に南洋群島の防衛という役にも立たないことを考えたのであった。
もし考えるべきことがあるとするならば、対米戦争が始まったときにどのように相手を攻撃するかということであったはずである。対米戦争が始まるとすれば、米国に鉄鋼や石油を全面的に依存しているから、これらの資源が断たれるという、現実に起きたことは容易に想定できたはずである。ところがそれに対する作戦計画は立てられていなかった。
何故か。考えたくなかったのである。山本五十六が水から石油を作るという詐欺師に引っかかったというエピソードがある。しかしそれほど石油不足の危険を意識していながら、山本ですら対米開戦の際に石油などの確保の戦略を研究していながった。海軍は日露戦争以後米国を仮想敵国として整備してきたのだから、対米戦争の際の戦略の研究は日米交渉が始まる以前になされていなければならなかった。
だが現実には海軍は米国の石油を使った艦隊決戦を営々と想定し続けて惰眠をむさぼった。そして日米交渉が破綻して禁輸が実行されるにいたり、蘭印の石油を奪取するということを考え付いたのである。付け焼刃でこれを実行したところで既に日本海軍の艦艇の編成も員数も性能もそれ向きにはなっていない。すなわち南洋に上陸し資源を獲得し、資源を本土まで輸送するという想定がなされていない。開戦僻頭の奇襲で南方資源の確保には成功したが、その後の補給はすぐ崩壊した。そして敵艦隊を攻撃するのか、本気でミッドウェー島を占領するか判然としないミッドウェー作戦で敗北した。
前述のように日本海海戦は、バルチック艦隊の回航阻止のための作戦より生起した。それは作戦目的からして合理的なものであった。もし同様なことを考えるとすれば、昭和の海軍は米軍艦のハワイ回航を阻止することを考えるべきであった。ミッドウェー島などは軍港施設として不充分であったから、対日戦用の海軍基地としては、ハワイしかなかったのである。だから真珠湾の一撃は正しかったのである。それは旅順港閉塞作戦と似ている。
多くの人は誤解している。ハワイ攻撃が宣戦布告なしに行われた奇襲だったから、米国民は憤激して中立から戦争に突入したと。馬鹿を言うものではない。米国は英国やソ連に軍事物資をレンドリースなどと称して行っていた。これは議会を通じた立法により行われていた。国際法上武器支援は中立を放棄したものである。すなわち事実上の参戦である。それを知らぬほど米国の大衆、少なくとも知識人は愚かではない。
日本が支那事変などと称したのは国際法上の戦争でないということにより、米国などから石油などの禁輸を行われたくないためであった。米国は対独戦に既に参戦していたのである。ハルノートは宣戦布告である。いつまでに開戦するなどと具体的に海戦予告したのはイラク戦争のほかに前例はない。何らかの脅し文句を送りつけるのがそれまでの宣戦布告であった。ハルノートを米国民が知らなかったなどというのは嘘である。
米国のマスコミはそこまでドジではない。戦争が始まることを承知していたのである。ハルノートは日米交渉を事実上反故にする宣言である。インドのパル判事が明言したとおり、ハルノートを受けたらモナコですら開戦するといったのは例えではない。
米領を攻撃しなければ米国は参戦しなかったなどというのも幻想である。レンドリース法案が通過したときから米国民の心にはガソリンがまかれていた。太平洋のどこかに戦闘が始まれば、どこで開戦したにしても米国は立ったであろう。だいいち米領フィリピンに手を着けずに南方作戦はできないではないか。
だから日本はいかに効果的に戦うか考えるしかなかったのである。米軍が太平洋を占領した日本に対する反撃の基地はハワイしかない。とすれば日露戦争の発想なら、ハワイへの米海軍艦船の回航阻止と、ハワイにおいて撃沈した戦艦の再生阻止が必要であった。旅順占領が必要でなかったようにハワイ占領も必要ではない。ハワイに対して地理的に優位なのは、米海軍ではなく日本海軍であった。日本海軍がパナマ運河を意識して大型戦艦を米海軍が作らないと考えたのは、有力な造船所が太平洋岸ではなく、大西洋岸にあったからである。
ハワイに近い基地を持ちえたのは実は日本海軍であったのであり、ハワイに対して有利だったのは日本だと考えられるのはそのためである。ハワイの海軍基地としての無力化、これに的を絞るだけで米海軍は手も足もでなかったはずである。カリフォルニアから直接に、ガダルカナル攻略の艦隊は派遣できなかったのである。せいぜいミッドウェーであるが基地としては脆弱である。グァムもハワイなくしてあり得ない。
日本は本土ないしニューギニア付近を基地としてハワイ無力化作戦を有利に戦えたはずである。ハワイが無力化されている限り米海軍は対日反抗作戦はあり得ない。その作戦計画で日本海軍はあらゆる艦船の性能と編成を決定していれば、真珠湾攻撃の洋上補給に苦労することはなかった。日本戦艦の航続距離はあまりに短すぎたのである。それは日本海海戦の結果を誤解し、さらに性能をもとめて航続距離を犠牲にするために、勝手に海戦生起を日本近海に求めたのである。
*海軍の選択・相澤淳・中公叢書
④艦隊決戦を自己目的化した日本海軍
「諸君」平成18年10月号で福田和也氏が、日本海軍は第一次大戦の戦訓として、艦隊決戦は今後生起せず海上輸送阻止の持久戦となると認識していたとある。そして日米の国力格差から海軍は持久戦に耐えられないために、米海軍動員前の速戦即決の早期決戦しかないと結論したという。それなら確かに真珠湾攻撃はこの方針に則ったものであり、以後の作戦計画は消耗戦となるから、真珠湾攻撃で講和できなければ日本は勝てなかったという結論になる。
だが日本海軍が西太平洋から日本に侵攻する米艦隊を日本近海で迎撃して米艦隊を撃滅講和するという構想は、やはり日露戦争の戦訓からも得られない。日本海軍はバルチック艦隊が旅順港に入り、そこを基地として日本海側の海上輸送を阻止して、大陸での陸軍の作戦が不可能となるとともに民需物資輸送が停滞して国内が混乱することを恐れた。ごくまともな考え方である。繰り返すが日本海軍はその結果生起した艦隊決戦から、艦隊決戦主義を保持したのは、先に福田氏が述べたような認識があったであろう。しかし太平洋上の輸送という観点から見れば、国力を度外視すれば日本のほうが米国より圧倒的に有利であった。
対米戦争を想定して見れば、米国からの物資は止まる。日英同盟が廃止されているから、最大限有利に考えても対米戦争では、英国は中立に立つ。その観点からも日本の物資はなくなるから南方に展開せざるを得ない。結果として東南アジアに植民地を持つ英国やオランダとも戦いが始まる。すると戦いは東南アジアの争奪戦となる。
オランダはさておくとしても、米英の補給線を想定すべきであろう。英国本国からの輸送はスエズ運河経由の陸伝いになるから情報は比較的得やすいであろう。米国はパナマ運河ないしサンフランシスコなどの西部海岸発で必ずハワイ経由でオーストラリアないしニュジーランドを基地とするであろう。ハワイないしミッドウェーからの直接出撃もある。
いずれにしても艦隊の通るルートは上記のようにかなり限定される。すると地理的な優位性から日本が持久できる可能性がかなり高くなる。日本海軍は艦隊決戦ではなくこのような状況に対応できる艦隊編成にすべきであったことは明白である。実際日米交渉が困難になると、日本海軍は陸軍と合同で、短期間にこのような南方進出計画を立案実行した。だから平時にこのようなシミュレーションができなかったはずがない。しなかった答えはさきの福田論文にある。日本海軍は第一次大戦の戦訓から最も重大な「戦争指導」を除外した。
戦略を放棄して戦術に固執した。それは英海軍から受け継いだ、政治に口を出さず軍務に専心するという思想によるものだそうである。だが英海軍軍人も政治的見識は高く、王室や海軍出身の議員を通じて海軍の理解者がいたという。日本海軍はこうして純粋な軍事に固執した結果、単純な艦隊決戦が自己目的化したのである。だが実際に対米戦を前にすると、戦略物資獲得の南方進出を行うのだから矛盾も甚だしい。
そして長年の準備を要する艦隊編成も装備も作戦計画もその研究を怠ったのだからすぐに負ける。太平洋上の小さな島々に占領軍を派遣して兵力を分散して各個撃破された。マキン、タラワといった小島になけなしの兵力を分散して玉砕したのは戦った兵士には申し訳ないというしかない。
⑤作戦目的なきラバウル航空戦
大東亜戦史を知るものにはラバウル航空隊はつとに有名である。奥宮正武氏によれば(*)ラバウル航空戦なるものは、昭和19年2月までの2年1ヶ月戦われたという。ラバウルからトラックに撤退した時には零戦他わずか48機に消耗していたという。数千機の機材と数千人の航空要員が失われたのである。しかし彼らは何のために戦ったのであろうか。
当時の戦闘機の常識をはるかに超える千キロ以上の距離の洋上を繰り返し往復し、戦い消耗していった。その作戦目的は何であったろう。それは主としてガダルカナル島などという戦略的な意味のない島をめぐる作戦に戦力を逐次投入したためであった。
陸軍がガダルカナル反攻を実施するといって飛行場を攻撃しても陸軍は動かない。陸軍が動けば海軍は支援しないということの繰り返しである。ガ島がなぜ必要かといえば海軍の南方拠点のトラック島を守るためであるという。
トラック島がなぜ必要かといえば*、連合艦隊が全部停泊できる静かな環礁があり、訓練などもできるというのである。地図を見ればサイパンとニューギニアの中間の更に東の洋上にある孤島群である。戦略的位置というのは全く考慮されていない。そして米艦隊のたった一撃で壊滅してしまった。日本海軍は米軍来襲の報で逃げたのである。
この程度の基地のためにガ島にこだわり、優秀な母艦航空機を陸上に上げて逐次消耗して全滅した。ミッドウェーで負けた当時といえども、この時期米空母は壊滅的であった時期すらあり、母艦戦力は日本が有利だったのである。にもかかわらず役にも立たないガ島の攻防にこだわって、有利な空母で戦わず米陸軍をも相手にしなければならない陸上航空戦を戦って敗れた。
このことについて意外なことに福田和也氏は「諸君」(平成19年4月号)で山本五十六の空母戦力に対する無理解を指摘している。すなわち山本は航空本部長在任中を含め、対艦船の航空戦力としては陸上攻撃機を主力と考えていたと言うのだ。海軍における攻撃機とは艦船攻撃を主任務とするものをいう。それが発進基地により、陸上攻撃機と艦上攻撃機に分れる。
確かに戦艦など防御の優秀な艦艇攻撃には陸上機の方が威力があると考えられる。そして陸上攻撃機を主力と考えたからこそ貴重な艦上機を陸上におろして艦船攻撃に参加させた。つまり艦上戦闘機による陸上攻撃機の援護である。山本は空母による機動戦術を考えなかった。だからいつまでもラバウルから陸上攻撃機による艦艇攻撃を行った。
それは据えもの斬りと言われたハワイ攻撃に比べ、航行中のプリンス・オブ・ウェールズとレパルス撃沈の大戦果に裏打ちされていたのに違いない。だが艦艇の対空能力が優れた米軍艦艇と迎撃戦闘機の前に陸上攻撃機は犠牲多く戦果はなきに等しかった。しかし山本は戦法を変えなかった。そして貴重な艦上機戦力を消耗した。
たしかに山本は乾坤一擲のはずのハワイ攻撃では東京で見物していたし、ミッドウェー海戦でも機動部隊を指揮せず、後方五百キロの洋上で見物していた。ところがラバウルでは陣頭指揮し最前線に赴き戦死している。
奥宮氏は陸軍がラバウル航空戦にろくに参加していないと非難している。陸軍機は洋上航法ができないなどと無理な注文まで付けている。だが陸軍は当時ビルマ航空戦を戦っていたのである。ビルマ航空戦では**では大方の常識に反して、陸軍航空隊は米英陸軍機に対してはスコアではむしろ優位といえる戦いをしていた。
ビルマと馬鹿にするなかれ。ビルマからインドへの侵攻作戦は、インドの反抗独立や英国の物資遮断の意味もあり英国の息の根をとめる可能性すらあった。戦略的に意味もなく、攻勢限界を超えたガ島攻防戦にこだわるより余ほど意味がある。その陸軍航空戦力をビルマから引き抜き、結果としてインド侵攻も失敗する。海軍の戦略なき戦いは万死に値する。
*ラバウル海軍航空隊・奥宮正武・朝日ソノラマ・新装版戦記文庫
**ビルマ航空戦・梅本弘・大日本絵画
⑥山本長官の真意
真珠湾攻撃の図上演習で日本空母は全滅に近くなる、という結果が出たのに平然と無視して強行したのは、誰あろう山本長官である。これは、自分の都合がいいように解釈する日本海軍の悪癖に帰されているが、不利な対米戦に反対した合理主義者として持ち上げられている山本長官にしてこのていたらくである。しかしそれだけだろうか。そして山本長官は真珠湾で米艦隊を全滅させて早期講和に持ち込むつもりだったとされている。しかし早期講和論者であるにしても真珠湾攻撃だけで講和に持ち込めると考えるほど単純だったのだろうか。
山本長官は条約派と言われているが、実際には主力艦の制限の軍縮条約に賛成する大蔵省の官僚を怒声で恫喝するほどの艦隊決戦派であった。航空機の威力は認めても最後の決戦は戦艦同士で決すると考えていた、こう考えると謎が解けるのではないか。もし真珠湾で徹底的に太平洋艦隊を殲滅するつもりなら、空母を使うにしても最後は戦艦の主砲でとどめを刺すはずであるが、戦艦は遥か後方において海戦に参加させなかった。
つまり真珠湾攻撃は日露戦争開戦直後の旅順港攻撃と同じで、敵主力の勢力を減殺するつもりだったのではないか。旅順港攻撃には主力艦を使わず、水雷艇の魚雷攻撃を行ったのと同様に空母を使ったのである。旅順港攻撃はほとんど戦果を上げることはできなかった。真珠湾では航空機を使えば空母は全滅するにしても、旅順港よりはるかに大きな戦果を上げることができる、と考えたのではなかろうか。図上演習で空母が全滅すると出ても、主力艦たる戦艦は残るから強行したのである。
そうすれば来るべき戦艦同士の艦隊決戦で有利に戦え、本当の勝利を上げることができ講和ができると考えたのである。旅順港の体験からは、どのみち真珠湾内では徹底した戦果は得られず、洋上での艦隊決戦によって勝利は得られると考えた。だから真珠湾攻撃では空母を犠牲にして戦艦を温存しようとしたのである。山本長官は図上演習の結果を無視したのではなかった。真珠湾攻撃で日本側の艦艇の損失は零に等しく、航空機だけで大戦果を上げるという予想外の結果に、山本長官は舞い上がってしまった。ミッドウェー攻略でも山本長官は空母の全滅のシュミレーションを無視したが、これは真珠湾攻撃の成功のために、今度こそ自信過剰のために図上演習を信頼しなくなったのである。
山本長官に躁鬱の気質があったというのが正しければ舞い上がり方は激しい。そのためそれ以後航空機を重用するようになった。だが珊瑚海海戦でもミッドウェー海戦でも戦艦を活用しなかったのは、基本的にはそれが艦隊決戦だと考えなかったためではなかろうか。両海戦ともに、島嶼の攻略作戦であり艦隊決戦ではないと考えたのである。日本海海戦で勝利した日本海軍の首脳は、山本も含め艦隊決戦とは上陸作戦等の具体的な作戦が決行される際に、それを阻止しようとする敵艦隊との衝突のために起こるという、現実的な考え方はなかったのである。
日本海海戦の勝利に酔った日本海軍にとっての艦隊決戦とは、競技場のスポーツのように、互いに艦隊を並べてヨーイドンで戦闘が始まるものであった。だからガダルカナルの攻防で山本長官は艦隊決戦に主力艦を温存するために、艦上機を陸上に上げたり陸攻を使ったりして艦船攻撃をさせて敵兵力の損耗を図った。来るべき艦隊決戦のために。ところが1000kmにもなる途方もない長距離攻撃を漫然と繰り返して大量の航空機を消耗した。戦艦を使って飛行場砲撃を行うにしても、艦齢が最も古い旧式な金剛型を使用した。万一損失しても艦隊決戦への影響は少ないからだ。海戦に空母を活用するのなら、むしろ最も高速の金剛型は温存すべきで、同じく旧式でも主砲の数が金剛型の五割増しの扶桑型の方が陸上砲撃に適しているが、やはり金剛型より砲力と防御力に優れた扶桑型は艦隊決戦に残したかったのであろう。
山本長官はやはり艦隊決戦の勝利による講和に固執したというのが本項の仮説である。航空戦力さえ整えれば対米戦には自信がある、と山本長官は考えていたとされるが、それは根本的に戦艦より航空を戦力として重視したのではなく、航空機による敵主力艦の減耗によって米艦隊との主力艦による艦隊決戦に勝利する自信があると考えていたのではなかろうか。艦隊決戦に勝つことが対米戦争に勝つための唯一の戦略である、というのが日本海軍の戦略なき「戦略」だったのである。
小生の疑問を付記すれば、何故海軍がそうなったか、である。闘将として知られる山口多聞中将ですら艦隊決戦主義以上の戦略を持っていたようには思われない。こうなった原因のスタートは、日本海海戦の勝利とそれによる講和の成立である。当時の国際法上の戦争は、戦況の有利不利によって最終的に停戦して講和する。日本海海戦が圧倒的勝利に終わり、そのことが講和をもたらしたのである。
だから艦隊決戦に勝利することが講和と言う戦争の決着に直結する、と言う発想が生まれ兵学校や海大などで教育され海軍中枢に引き継がれていったのである。しかも海軍にとって都合がいいことに、艦隊決戦が講和をもたらしたのは海軍が陸戦のサポートや補給の保護と言った、陸軍の支え役であるという補助的本質が否定されたのである。だから海軍は艦隊決戦こそ国軍の最大任務であると、陸軍と張り合ったのである。このことから艦隊兵力の予算獲得だけが海軍政策の最大任務となった。海軍の戦略は艦隊充実のための予算獲得である。
石原莞爾も自覚していたように、日露戦争の陸戦は辛勝であった。建前はともかく、このことは士官学校や陸大に行って真面目に資料を研究すれば分かったはずである。だから陸軍は、日本海海戦は、グロッキー寸前の日本が最後にラッキーパンチを当ててロシアをノックアウトしたのに過ぎなかったことを知っていたのである。その上大陸に進出した陸軍は満洲鉄道とともにロシアや支那と対峙して統治の一環として軍事を位置づけざるを得なかったのである。だから陸軍には石原莞爾のような戦略家はいても、海軍に戦略家はいなかった。これが本項の仮説である。
⑦陸上攻撃機開発という愚行
大東亜戦争の海軍の最大の愚行は、世界に類を見ない陸攻なる機種を発明して対艦攻撃に多用したことである。陸上から発進した双発の雷撃機が長躯敵艦を雷撃撃沈する。大雑把にいえば陸攻とはそのような目的で開発された機種である。もちろん陸攻も爆撃は可能であるが、水平爆撃では航行する艦艇に命中させることは困難である。命中した所で致命傷を与えて撃沈することは困難である。命中率がいい艦爆による急降下爆撃でも致命傷は与え難い。実績における例外は真珠湾で九七艦攻が使った800kg徹甲弾とティルピッツを破壊したランカスターの超大型爆弾である。兵頭二十八氏が言うように、米海軍が雷撃機より艦爆を多用したのは空母により敵艦に致命傷を与えることを期待しなかったからである。これには、爆撃で相手の反撃能力を奪っておいて、とどめは雷撃機による攻撃か戦艦の主砲弾によればいいという合理性はある。
これに対して日本海軍は、主力艦の撃沈を目的として雷撃を重視した。日米とも手法は目的にかなったものである。日本海軍はさらに艦上機ばかりではなく、陸上機にも雷撃させることを考えた。それが陸上攻撃機である。それはマレー沖海戦のプリンス・オブ・ウェールズとレパルス撃沈として見事に結実した。
日本海軍が陸上攻撃機、という海軍としては当時世界にも類例をみない機種を発明したのは何故か。それはワシントン及びロンドンの両軍縮条約の結果である。最初のワシントン条約では、戦艦のみならず空母の保有量まで制限の対象となった。日本は米海軍に勝てる最低限度とした7割の保有量を確保できず、6割に抑えられた。しかし、巡洋艦については制限がない。そこで海軍は巡洋艦の建造に邁進することになった。
その結果、大型巡洋艦(重巡洋艦)は昭和五年のロンドン条約交渉時点では、日本六万六四〇〇トンに対して、米国二万トンであり、日本はさらに四万トンが完成直前にあった。主力艦の不利を巡洋艦で補完しようとしたのである。ところがロンドン条約では、巡洋艦、駆逐艦、潜水艦とほぼ全ての戦闘艦艇に制限が課せられ、潜水艦が対米同量である他は全て対米六割に抑えられた*。
昭和七年当時海軍航空本部長であった山本五十六少々自らの発案で爆弾2トン、航続距離2,000浬以上という、大型陸上攻撃機の試作指示が出された。山本と海軍の想定はあくまでも陸攻は陸上から発進して敵主力艦を攻撃し、艦隊決戦のための暫減作戦に使用するものであるから、艦隊に随伴して動く空母の艦上機に比べて航続距離が長くなければならない。山本五十六は海軍の陸攻の発案者であったのである。その前に九三式陸攻というのがあるが、双発の艦攻の試作に失敗した少数機を陸攻として採用したのに過ぎない。
実は山本が発想した九五式陸攻には雷装はない。九七式大艇は雷装がありながら、大型鈍重で被弾の危険が大きいとして魚雷の使用は試験段階で断念されている。九五式陸攻は全幅三〇mという一式陸攻より大きく四発の連山に近い大型機であったから同様に考えられたとも推定できるが真相は不明である。九五式陸攻が大型となったのは航続距離を大きくするためであったから、大航続距離の必要性と、雷装による被弾の危険性の矛盾に陥ったのかもしれない。九五式陸攻には400kg爆弾という日本海軍としては変則な爆弾の搭載が予定されていた。250kg爆弾の上は500kg爆弾であり、400kg爆弾というのは知られていない。九七艦攻の800kg爆弾は戦艦撃沈用に、長門級の40cm徹甲弾を改造した。もしかすると、400kg爆弾は旧式戦艦に多く用いられていた30cm徹甲弾の改造かもしれない。真珠湾攻撃用800kg爆弾と同じ発想で戦艦の徹甲弾改造の400kg徹甲弾を山本が九五式陸攻用に考えていても不思議ではないが、皆さんの中で御存知の方は教えて下さい。ちなみに後の深山、連山と言った四発の大型の陸攻には雷装は考えられていない。いずれにしても、九五式陸攻の後の九六式、一式陸攻と言った双発の陸攻は雷撃爆撃両用であり、艦船攻撃にも両方が使われている。比較的大型である一式陸攻は双発機としてはかなり軽快な操縦性を持っている。
かく言うように、日本海軍の陸攻という機種は軍縮条約の生んだいびつな落とし子である。それはマレー沖海戦の大戦果として結実した。しかし、誰が論じたか失念したが、マレー沖海戦の大戦果は英海軍が戦闘機の護衛を付けないと言う大チョンボをした幸運の結果だった。当時の英海軍は立派な空母を持ちながら、まともな艦上機を開発できないほどの、航空機運用に関しては大間抜けだったのである。九五式陸攻の発案以後の成果が実って、敵戦艦を洋上で、それも次々とニ隻も撃沈したのである。それを実力と誤解した山本五十六は、それ以後、い号作戦などで艦船攻撃に陸攻を多用して戦果少なく機材、ベテラン搭乗員ともに多大な犠牲を出し続けているのは悲劇としかいいようがない。山本は、ハワイ・マレー沖海戦の大戦果に舞い上がって、これで大東亜戦争は艦隊決戦で勝てるとそれまでの持論に確信を得たのであろう。
やはり海軍が大型陸上機を艦船攻撃に大量に運用する、というのは軍縮条約による制限からの焦りが生んだ邪道であるように思われる。ガダルカナル争奪戦の元となった飛行場も、陸攻の基地として海軍が設営したものである。日本海軍は機動的に動ける空母があるのに、陸上に飛行場を建設する、という無駄を行った。艦隊と共同して敵前上陸をして陸戦を専門とする米海兵隊が陸上機を持っていたのとは事情が異なる。海兵隊と日本海軍の陸戦隊とは、戦闘の練度において隔絶の差があるのは常識である。
陸攻は三座の艦上攻撃機に比べ二倍以上の搭乗員を必要とする。九七艦攻と一式陸攻を比較すれば、ジュラルミンの使用量に至っては四倍である。同機種で比較すれば飛行距離当たりの燃料消費量は2倍以上違う。にも拘わらず積める航空魚雷は同じく1本である。あらゆる資源の使用量が大きく違うのに実質的攻撃力は同じであるという効率の悪さである。
余談だが、ビスマルクはよたよたの複葉機に容易に雷撃を許し、英戦艦二隻は鈍重な陸攻の攻撃を対空砲火で撃退できなかった。日英独海軍とは同時期の米海軍の対空火器の威力と大きな違いがあるように思われる。さて陸攻なる機種は現代にないかと言えばそうではない。ロシア海軍が引き継いだのである。バックファイア爆撃機は現代の一式陸攻である。多数の対艦ミサイルを艦隊防空陣の防衛圏外から発射して行う飽和攻撃は日本海軍の理想を実現した。貧弱な艦艇しか保有しないロシア海軍には、手軽に米空母機動部隊を制圧する手段は他になかったのである。キエフ級航空巡洋艦のように、船体に所狭しとばかりに各種兵器を満載しているのも日本海軍の艦艇と似ているようにも思われる。いずれにしてもいびつな海軍は日ソともに陸攻という愚かな機種を生んだ。飽和攻撃に対処するためにイージス艦という対抗手段が生まれた。
*東郷平八郎・岡田幹彦・展転社
⑧最低の英艦上機
英海軍は空母の先駆者であるにも拘わらず、第二次大戦当時の艦上機に関しては日米海軍に比べると、お寒い状況であった。中でも時代遅れで有名なのは、複葉の雷撃機のソードフィッシュとアルバコアである。第二次大戦中にも最前線で使われていたソードフィッシュは開発年次が古いから仕方ないとしても、後継機のアルバコアなどは、なんと低翼単葉引込脚の九七艦攻が採用されたのと同じ、昭和十二年の仕様で開発が始まったのに、複葉固定脚のアナクロなのである。逆に、でかくて複葉で、最大速度が220km/hという超のろまのソードフィッシュを撃退できなかった、ビスマルクなどのドイツ艦隊の防空能力はどうなっていたのであろう。
たが英海軍の錯誤はそれに止まらない。それは艦上戦闘機である。艦戦のブラックバーン・ロックはなんと艦爆のスキュアから開発したものである。複座でしかも後部には巨大な銃筒までが設けられている。これでは、米海軍のドーントレス艦爆にさえ空中戦では負ける。フェアリー・フルマー艦戦は陸軍の軽爆撃機から開発したもので、エンジン出力に比べ、全幅は14m以上と馬鹿でかい。艦戦と艦爆の両用に使うはずのものであったが、戦闘機としてまともに使えるはずはない。その後継機のフェアリー・ファイアフライは艦戦専用ということになったが、複座である。英海軍が艦戦の複座にこだわったのは、洋上航法のための航法士を乗せるためであったが対戦闘機戦闘には不利であるし、日米の艦戦は単座で任務を果たしている。しかし対戦闘機戦闘には不利で、搭載量が大きいと言うことが取り柄で、結局艦爆や雷撃機代わりに使われることが多かった。
ブラックバーン・ファイアブランドに至っては、自重が5tを超え、2,500馬力の巨大なエンジンを積んでも最大速度は560km/hしか出ないありさまで、唯一の取り得の搭載量の大きさから、雷撃機兼用になってしまった。しかも雷撃機なのにこちらは単座である。米海軍も、雷撃と爆撃が可能な巨大な単座の長距離艦上戦闘機XF8Bを試作した。ファイアブランドより重量もエンジンも大きいが速度性能ははるかに優れ、航続距離は4倍近く、搭載量も3倍と、大きくしただけのカタログデータ上の効果はあった。まあ、まともな対戦闘機戦は望めなかったろうが。そもそもファイアブランドがこれだけ大きな機体になったのは、性能から考えると不可解としか言いようがない。要するに発注者の仕様に問題があったのである。
このように、第二次大戦に向けて英海軍が開発した艦上機にはまともなものが皆無に等しいのである。その多くの原因は戦闘機に雷撃や爆撃などの能力を持たせようとしたことや、複座の艦戦にこだわったことにある。英空母は重装甲としたために極端に搭載機数が少ないことが一因であろうが、それだけでは説明できない。しかもその結果虻蜂取らずの見本で、全ての用途に使い道が無くなっている。唯一陸上戦闘機と対等に戦えたのが、シーファイアなのだが、戦闘での損害よりも、着艦時この方がはるかに大きいと言う無様な結果となっている。それを補って余りがあったのが、援英機などとして導入された、ヘルキャットやアベンジャーなどの米海軍の制式艦上機群であった。
確かに日米海軍共に複座や双発の戦闘機といった一種の無駄な戦闘機開発も行ってはいる。しかしそれは、まともな艦上戦闘機があっての無駄だから、本来の用途について不足をきたすことはなかった。だが、英海軍はまともな艦上戦闘機も作らずに、遊びとしか思われないような複座の艦上戦闘爆撃機のような使い物にならないものばかり開発したのが問題なのである。あげくが、艦上機としての適性が最悪のスピットファイアを使うはめになった。
一般的には飛行機のエンジンは後方から見ると時計回りに回る。最近気付いたのだが、なぜか英国製のエンジンには、この反対のエンジンもかなり存在する。艦上機が発艦しようとすると、エンジントルクのため、左舷方向に行きやすい傾向があるから、ほとんどの空母の艦橋はそれを避けて右舷に置かれている。ロールスロイス・マーリンエンジンでは問題ないのだが、後継のグリフォンは回転方向が逆な上に大馬力なものだから、これを装備した後期のシーファイアは発艦作業が大変であったろう。そこで途中から二重反転プロペラをつけるようになった。シーファングも量産機は同様にする予定であったから、影響は大きかったのである。何とかまともに戦えるシーファイアでさえこんな重大な欠陥も抱えていたのである。
英海軍の艦上機開発の失態が露呈しなかったのは、独伊の海軍力が潜水艦を除いてあまりにも貧弱だったためである。結局英海軍は航空母艦の先駆者でありながら、運用や艦上機の開発には失敗した。第二次大戦の海軍で、航空母艦の運用と艦上機の開発運用に、バランスが取れた成果をあげたのは、日米海軍しかなかったのである。ファントムやトムキャットなどの米海軍の艦上戦闘機に誇らしげに旭日旗が描かれているのは、強い日本海軍航空隊に勝ったと言う誇りを示しているのである。
⑨ハワイとシンガポール攻略
ワシントン会議で軍縮の対象となったのは、主力艦の兵力ばかりではない。太平洋における軍事基地の制限も課せられていた。日英米とも島嶼防御を現状維持して、強化しないというものである。ところがハワイとシンガポールだけが例外とされた結果、両基地とも東洋での重要な軍港ならびに要塞となった。
大東亜戦争の開戦劈頭日本軍がハワイとシンガポールを攻撃したのは、このような歴史的な背景の当然の結果である、ということを「大東亜戦争への道」で中村粲氏が書いている。全く同じことを西尾幹二氏も書いている。シンガポールは占領してしまったから、その通りであろう。しかし、ハワイについて言えば、米太平洋艦隊の主力艦が停泊していたから攻撃したのであって、軍港機能に対しては何らの攻撃もしていないことは、多くの批判がなされているところであるから、必ずしも、ハワイに関しては両氏の意見は少しばかり外れている。
その後もミッドウェー攻略を計画したが、強く推進した山本五十六の主たる企画は敵空母の撃滅であって、攻略はその誘い水に過ぎないと考えられている。山本はミッドウェー攻略が成功したら、それを足がかりにハワイ占領をする、と豪語していたと言われるが、ガダルカナルへの補給もままならなかった海軍にハワイへの補給ができようはずはない。それ以前にミッドウェーを占領したところで、ハワイから容易に攻撃される。ハワイ占領などは初期作戦が順調にいったための大風呂敷である。山本は、ミッドウェー作戦の直前に、今度の作戦は簡単だ、と愛人に語ったが、薄氷を踏む思いで作戦を練っていた日露戦争の将帥に比べ何という違いであろう。戦前から国力の圧倒的な差から、対米戦の勝利は極めて困難であるからと対米戦に反対していたと、山本シンパは書くが、現実のこの軽薄さは何としたことだろう。
ハワイの軍港機能を奪うことは両氏の言うように戦略的重要性がある。しかし別項でも述べたように、現実を考えれば、軍港機能を奪うためには軍港施設を破壊し、その後の補給、修理を継続して阻止するしかないのである。何度も言うように昭和の海軍には艦隊決戦の勝利しか目的はなく、戦略はなかったのである。
⑩大型機による艦艇攻撃は割に合わない
B-17は、緒戦でさかんに日本海軍の艦艇を爆撃したが、ほとんど戦果を挙げていない。当然であろう。5千メートル以上から爆撃するから滅多に命中しない。だがB-17の使用目的のひとつも、このような艦艇攻撃にあったから、結果を出せなかったのである。
日本の陸攻は、マレー沖海戦では、わずか3機の喪失で2隻の戦艦を撃沈する、という大戦果を挙げた。これは、都合で空母の護衛ができなかったために、戦闘機の援護がなかったことと、英戦艦の対空火器が貧弱だったことによる。これは奇跡である。
しかし、この戦果に味をしめた日本海軍は、陸攻を重用したが、その後は3年間の戦果の合計は、マレー沖海戦の一度分にも及ばなかったと思われる。海軍航空が元気であったラバウル航空戦で、陸攻は常に米軍に撃退されている。
艦船攻撃を効果的にやった爆撃機は、大戦後期のB-25などによるスキップボミングすなわち反跳爆撃による船舶攻撃で、巡洋艦以上の艦艇には、ほとんど実施されていない。対空火器が極めて少ない輸送船を狙ったものがほとんどである。
それも、対空火器を制圧する為に、機首に装備した多数の機銃を打ちっぱなしにして、攻撃したのである。このように、大型機による艦船攻撃は、高高度水平爆撃では、比較的安全だが命中しない。雷撃や反跳爆撃は効果が大きいが、魚雷や爆弾を投下する前に、直進しなければならないため、特に図体の大きい爆撃機は対空火器の目標になりやすい。
結局日米共に、大型機による艦艇攻撃ということを戦前から企画しながら、結局は失敗に終わっている。米軍は陸軍ないし、空軍が爆撃機の任務のひとつとして、艦船攻撃を企画したのに比べ、特に日本海軍は、艦船攻撃を主任務とした陸攻という、従来の海軍航空にない機種を発明したから、失敗によるロスは大きい。
日本海軍が陸攻を発明したのは、主力艦の戦力不足を補うために、大型機による大航続距離を利用して、陸上基地から米艦艇を迎撃しようというのであった。その期待は大きかった。もちろん結果論であるが、陸攻よりオーソドックスに艦攻や艦爆を多数整備した方が、物的資源、人的資源の有効活用になったのである。
もっともこれは、相手が米軍でなかったら、話は違う。以前に論じたとおり、英海軍の艦上機開発は惨憺たる有様で、米海軍の支援が無かったら、まともな艦上機運用はできなかった。英海軍は戦前既に1.5流に成り下がっていたのである。
⑪山本五十六の余計な口出し
よほどセンスがいい人でない限り、事務屋が技術に口を出し過ぎると、間違いを犯す。この類が山本五十六の海軍航空の推進であった。山本は軍人の肩書はあるが、武人ではない。誰の評論であったろうか。山本は海軍次官や大臣といった行政職につくべきであって、連合艦隊司令長官、と言った軍人としての指揮官としては不適格であるといった。いわば軍政畑の資質の人であった。
確かに日露戦争で指を失うという、海上戦闘経験を有している。しかし、その経験も山本の資質を変えることはできなかったのであろう。話を戻すと、ワシントン条約やロンドン条約で対米七割の海軍力が確保できなくなると、山本は対策として航空機による主力艦の漸減作戦を考えた。もちろんこの時の航空のトップは山本ではなかったのだが。
だが積極的に推進し、航空攻撃の虜になっていき、真珠湾攻撃、マレー沖海戦という形で結実したのはまぎれもない事実である。山本なかりせば、この二つの作戦は別な形で行われており、海軍の対米作戦が航空偏重となることもなかったであろう。航空偏重はそれまで培ってきた戦備と訓練の多くを無駄にした。「負けるはずがなかった大東亜戦争」で倉山氏はサッカーの例を挙げて、守って勝つと言う練習と人材を集めたチームが、突如実戦で攻めまくる作戦に監督が切り替えたら、試合にならない、という意味の事を言っているが、正に山本はそれをしたのである。
確かに軍事上の技術革新は必要である。しかし、それまで海軍が対米有利としてきたのは、在来型の主力艦による戦闘であり、航空機の急速な発展に短期間にフォローアップできるポテンシャルもなかった。山本は在米経験から、日米の工業力の比が隔絶しており、航空機の大量生産については、米国が圧倒的に有利であったことは承知していたのである。これに比べ主力艦である戦艦は、短期間で建造できるものではなく、戦前からの準備が必要であるから、日米の差が工業力の差ほどの開きは出ない。
元々、陸上攻撃機を開発して軍艦を攻撃する、という構想は、軍縮条約で不利になった艦艇の比率を潜水艦や航空機で漸減して、対等に近い状態にするための、補助手段であった。しかし、ハワイ、マレー沖海戦で航空機単独での攻撃に成功すると、その後の作戦は航空機単独となることが圧倒的に多くなった。山本は戦前の海軍の戦争準備の方法を覆してしまったのである。つまり山本という軍政屋が軍事技術に大きく介入して指導したために、有利なフィールドで戦わず、不利なフィールドに突入する指導的役割を果たしてしまった、と言わざるを得ない。
米軍ですら航空偏重になったわけではなく、水上艦艇、潜水艦と航空機をバランスよく組み合わせて使っている。米海軍は、建造中止となったモンタナ級や一部のアイオワ級の建造中止にした以外に、対日戦開戦以後、ノースカロライナ級以下10隻の戦艦を実戦配備したのに対して、日本では大和級の2隻だけである。しかも、日本の艦船を最も多く撃沈したのは航空機ではなく、潜水艦であることは、よく知られている。
⑫開戦後の第二段作戦
日本は、フィリピン、マレー、ニューギニア占領などの第一段作戦を終えて、石油資源の確保という開戦の目的の一部を達成すると、特に海軍は、何をしていいか分からなくなったことと、順調な作戦経過から、無駄な作戦を行うようになった。英東洋艦隊撃滅と称して、インド洋に南雲部隊を派遣して、わざわざおんぼろ空母のハーミスを滅多打ちにして得意になっていた。肝心の東洋艦隊そのものは取り逃がしたのである。
第二段作戦のヒントはアジア諸国の独立である、と「真珠湾攻撃異見」に書いた。実は倉山満氏の「負けるはずがなかった大東亜戦争」に同様なことが書いてあったので、これをフォローしてみよう。ただし、倉山氏は真珠湾攻撃はすべきではなかった、というのが基本的考え方なので、前段で相違があることは一言しておく。繰り返すが小生は、日露戦争の開戦で旅順艦隊の撃滅を考えた如く、ハワイに米太平洋艦隊の根拠地となった時点で、何らかの方法で真珠湾対策は考えずにはいられなかったと思う次第である。
その点だけ一言する。確かに、日本の艦艇は、小笠原沖やフィリピン沖で米艦隊を迎撃するのが基本戦略だから、航続距離は米本土から進出する米艦艇に比べ余程短い。ハワイを併合した時に、日本は艦隊を派遣して抗議の意思を示した位だから、将来ハワイが米国のアジア進出の拠点となることは明白である。とすれば、その時点から対米戦略としては、ハワイの無力化、と言うことを考えて艦艇のスペックを考えなければならなかったはずである。無力化とは、色々な選択肢が考えられるであろう。思い付きを書けば、真珠湾を艦艇で直接攻撃する以外にも、機雷封鎖なども選択肢としてはある。
閑話休題。倉山氏は、まず石油確保のためだから、オランダを攻めればいい(P188)というのだが、そうは問屋が卸さない、と知っている。「百歩譲って、シーレーンの都合上、フィリピンを取るのは仮にいいとしましょう。それならそこで待ち構えておけばよかった。ハワイ攻撃をやったものだから、余計な戦力を削いでフィリピン全土制圧が遅れています。」(P189)というように、フィリピン攻略は避けられなかったのであろう。
確かに首都ワシントンに攻め込むことができぬ日本は「ベトナム戦争の時のように、アメリカに音を上げさせることをやらなければいけませんでした。」(P190)というのが唯一対米戦に勝つ道であったと思う。
そこに繋がる道として「とにかくイギリスを一瞬でも早く降伏させるしかありませんでした。」(P206)というのも正解であろう。そのためには、インパール作戦を早期にやっておき、プロパガンダとしての「大東亜会議」も同時にしておく必要がある(P206)という結論には同意する。希少本に属するが大田嘉弘氏の「インパール作戦」によれば、実際に発動した昭和十九年の時点でも、英軍将校自身が相当に苦しめられたことを認めている。
ビルマ制圧後早期にインパール作戦を発動していたら成功したことは間違いないであろう。そこで倉山氏の説にいくつかの疑問を出しておく。ただし小生も確信がないのだが。まずインド独立や援蒋ルートの遮断で英国が敗北し、蒋介石との講和も成立したかどうかである。軍需産業がないのにベトナムが戦えたのは、特にソ連が無制限に軍事支援したからで、戦争が延々と続いた結果、米国が逃げ出したのである。
日本には軍需産業があったし、兵士の士気も高かった。だが問題は米国を厭戦に持ち込むだけの継戦能力があったかである。それには、シーレーンの確保や本土爆撃をされないだけの占領地の確保が出来たかである。日本は北ベトナムのように外部からの軍需物資の支援は期待できず、米国が厭戦気分が蔓延するまで、自前で軍需物資を生産しなければならないのである。
以上の疑問は問題なかったのかも知れず、何とかなったのかも知れない。だが倉山氏の立論の前提の日本陸海軍が強かった、ということには最大の疑問を感じるのである。ノモンハン事変などで機甲部隊を動員したにも拘わらず、戦闘ではソ連は勝つことができず、スターリンは最後まで日本陸軍を恐れていて対日戦に踏み切れなかったという、倉山氏の指摘は事実であろう。昭和十一年の時点では、主力艦の大口径砲弾の命中率は日本が米国の三倍あったと言う黛治夫氏の指摘も読んだ。
陸軍の三八式歩兵銃は旧式なボルトアクションで、自動装填の小銃を使っていた米軍とは火力が比べ物にならない、というのも迷信で、ノルマンディー作戦の時ですら米軍も自動装填式は行きわたっていたわけではない。九七式中戦車にしても制式採用当時は装甲厚さや砲の威力にしても、世界水準はいっていた。ドイツ軍のⅠ号戦車などは20mm機関砲しかなかったのである。
というように軍隊の士気ばかりではなく、ハードウェアを含めた総合戦力で、日本軍はある時期まで強かった、と言える。しかし小生が問題にするのは、特に海軍に於いては米国が戦間期にカタログデータに見えないところで、長速の進歩をとげていたことと、同様に独ソ戦が始まる少し前からの、ロシア陸軍の装備の格段の改良である。また海兵隊も日本陸軍を手本に、相当の強化が為されていた。
特に米海軍とは直接戦っただけその差の影響は大である。何度も書いたが、日米の差はレーダーだとか、VT信管だとかいう特殊な兵器の差ばかりが強調されるが、実際には見えにくいところ技術の差が、開戦時点では広がっていったと思わざるを得ない。
別項で述べたような射撃指揮装置による防空能力の差は隔絶していた。艦艇が被害を受けたときの消火装置などのダメージコントロール、各種の無線機などなど、カタログデータに表れない、潜在的な技術の差である。例えば日本海海戦当時は軍艦自体のシステムも単純であって、電子機器もほとんどなかった。
これらについては、第一次大戦から第二次大戦の間に相当に発達し、複雑化していったので、日本の努力も相当あったのだが、目に見えにくい分だけキャッチアップが困難であったろう。また、素材である鋼材自体にも当時の日本の技術は劣っていたから、同じカタログデータの砲弾、爆弾、装甲でも性能に差があった。爆弾の日米の差については、兵頭二十八氏が「日本海軍の爆弾」で論じている。
もちろん特殊鋼に使う希少金属の不足と言うハンディもあった。また、日本は予算の不足から艦砲、装甲、魚雷と言ったカタログ上目に見えやすい兵器の研究に予算と人材が配分された。そのため、これらの主兵器をサポートするシステムの研究開発は後手に回り、兵器のシステムが複雑化すると、差は広がっていったと考えられる。
特に米国の進歩は大きかったように思われる。マレー沖海戦でも相手が米戦艦であったら、例え防空戦闘機がいないにしても、あれほどの戦果は挙げられなかったと思われる。軍事技術の専門家ではないので、実例を多く挙げられないが、カタログデータに表れない、日米海軍の技術力の差は相当なものであったと言わざるを得ないと思う。この差を考えたら長期戦になった場合には、生産力ばかりではなく、技術力の差も出たのに違いない。
こんなことをくどくど言うのは、倉山氏の前提が、士気、技量、兵器の質など総合的戦力で日本は米国より強かったことであるように思われるからである。少なくとも、第一次大戦直後の陸海軍の兵器システムが、質はそのままで、量的に拡大しただけの兵器体系を前提に、日本軍は強かった、と言っているように思われるのである。
⑬米海軍のゲリラ戦法
大東亜戦争の緒戦、日本の空母部隊が、ハワイ、インド洋で我がもの顔に行動していた時、日本側に大した実力ではないと見下されていた米海軍は、手を咥えて見ていたわけではなく、日本海軍の隙をついて、神出鬼没のゲリラ戦法で戦果を挙げていた。そのことが以前紹介した「凡将」山本五十六に書かれている。(P107)長くなるが引用しよう。
昭和17年のことである。二月一日早朝、日本防衛戦最東端のマーシャル諸島が、米空母エンタープライズとヨークタウンの艦載機に猛烈な空襲をうけた。さらに、同部隊の重巡洋艦は、艦砲射撃まで加えてきた。・・・司令部はクェゼリン島にあったが、この奇襲によって大損害を受け、司令官八代祐吉少将も戦死した。
二月二十日には、空母レキシントン、重巡四、駆逐艦十の機動部隊が南東方面最大のラバウルに空襲をしかけてきた。ラバウルからは、中攻十七機がこれらの攻撃に向かった。しかし、敵の対空兵器と戦闘機のために十五機が撃墜され・・・大損害を受けたのである。わが中攻隊には護衛戦闘機が一機もついていなかったのがその最大の原因であった。
二月二十四日には、空母エンタープライズ、重巡二、駆逐艦六の機動部隊が、昨年末に占領したウェーク島を、これ見よがしに襲撃してきた。艦載機による空襲と重巡による艦砲射撃であった。
超えて三月四日には、同じくエンタープライズの機動部隊が、傍若無人に南鳥島にも空襲をしかけてきて、日本側に相当な損害を与えた。
三月十日には、空母レキシントンとヨークタウンの機動部隊が、ニューギニア東岸のラエ、サラモア沖の日本艦船に、約六十機で空襲をしかけてきた。軽巡夕張が小破し、輸送船四隻が沈没、七隻が中小破という大損害を受けた。
千早正隆は、その著「連合艦隊始末記」・・・で、米機動部隊について、次のように書いている。
-アメリカが守勢の立場にありながら局所的に攻撃を取る積極性、その反応の早さ、その作戦周期の短さ、その行動半径の大きさ等については、何らの注目の目を向けなかった。それらについて、真剣な研究をしたあともなかった。
ただこれら一連のアメリカの空母の動きから、日本海軍の作戦当局が引き出した一つの結論は、首都東京に対する母艦からの空襲の可能性が少なくないということであった・・・
本来ならば、南雲機動部隊がこれらの宿敵をどこかの海面に誘い出して撃滅すべきであった。その最も重要な目標に向かわず、やらずもがなの南方のザコ狩り作戦に出かけて、長期間精力を使い減らしていたのである。
というようなものである。千早の言うザコ狩りとは、昭和十七年早々に南雲部隊がラバウル、インド洋などに出かけて長躯小敵を求めて航走し、大した戦果のない割に将兵を無駄に疲れさせたことである。日本海軍は緒戦の勝利に驕慢し、強敵米国と戦っていることを忘れていて開戦時の緊張感を失っていたのは、多くの識者の指摘する所である。また、千早氏の指摘もどうかと思う。結局艦隊を動かすのは、作戦目的を果たすためであって、敵艦の撃滅は作戦目的の手段である。「南雲機動部隊がこれらの宿敵をどこかの海面に誘い出して撃滅すべき」というのは艦隊撃滅自体が目的化していることを明示している。千早に限らず、常に日本海軍の首脳の考えは、日本海海戦のように敵艦を撃滅することが、作戦の目的であった。
だがマリアナ沖で日本空母と艦上機を殲滅したのは、マリアナ諸島を攻略し、B-29による本土攻撃の基地を得るためであった。B-29の基地は、本土空襲を行い日本を屈伏させるためであった。事実上連合艦隊が撃滅されたフィリピン沖海戦も、フィリピン攻略のために生起したものである。
千早氏の考えは、主力艦が戦艦から空母に切り替わっただけで、作戦目的が艦隊決戦であることに変わりはない。日本海軍は空母による東京空襲を恐れたと言うが、これは生出氏が言う山本五十六の世論恐怖症である。なぜなら、この時点で空母による散発的な空襲を受けても、ドーリットルの東京初空襲と同じで、戦術的な効果は皆無であり、心理的なものであった。日本海軍がゲリラ的な米機動部隊による攻撃から、米空母による東京空襲しか想起しなかったというのは、かくのごとく意味を為さないものだったのである。
それより、米軍がこの間に米軍が動員したのは、エンタープライズ、ヨークタウン、レキシントンというわずか三隻であり、一度に最大二隻しか動員しない、という小規模なものであった。米軍は、日本軍の兵力が圧倒的である際には、敵の防備の薄い所を衝いて、散発的にゲリラ的な攻撃を仕掛けて戦果を挙げたことに注目する。日本が敗色濃厚になった際にも、艦隊は大規模な敵の正面からの攻撃しかせずに、殲滅されていったのとは異なる。
⑭海軍のいい加減な対米戦戦略
ロシアを仮想敵国とする陸軍に対して、海軍は対米戦を想定して予算獲得をした。艦艇の動力は日露戦争時代、石炭専焼であった。しかも後日の蒸気タービンではなく、レシプロ式の蒸気機関であった。それから重油との混焼時代を経て、最終的にボイラは重油専焼罐となった。混焼の時代にあっても、石炭燃料の比率は段々減少していった。
例えば大正2~4年に竣工した金剛型戦艦は、最初は混焼罐であったが、大正12年頃の第一次改装により、一部のボイラに重油専焼を取り入れた、石炭重油混焼で重油の比率が高まった。昭和8年頃から開始された、第二次改装では全部、重油専焼となった。この改良はひとえに性能向上のためであった。
もちろん、他の日本戦艦も似たような時期に、重油使用の比率を高めていって重油専焼罐となった。石炭なら国内産も大陸産も入手がある程度可能であるから問題が少なかったが、石油が艦艇の主燃料になったときに、主として石油は米国から輸入していることを考えるべきであった。日本海軍の仮想的国は米国だからである。
山本五十六ら海軍の幹部が、水からガソリンを作れると言う男の売り込みを聞いて、実験をやらせるという事件があった。何日もかけて、男は水の入った瓶からガソリンを取り出して見せたがもちろん、トリックに過ぎなかった、という事件である。この事件を海軍教育における初歩的科学的知識の欠如や、程度の低い詐欺に引っかかるほど海軍首脳はガソリンが自給できないと心配していた、と解説する向きが多い。
炭素の含まれない水がガソリンに変わる、などという事を信じた山本らの科学、という以前の理科の程度はひどい、というのは事実である。ところが、ガソリンを自給できない、と心配していたことが、こんな詐欺に引っかかるという事自体が、軍人としては変であるし、本気で心配していたのかを疑わせる。
というのは、現実に米国からの石油が途絶したとき、彼らが躊躇なく考えたのが、蘭印からの石油確保、という事だったからである。当時オランダ本国はドイツに降伏し亡命政府を作っているような状態だったからこそ考えられる選択肢、であるというばかりではない。もし、そんな事態ではなくても、あの時点では、最も近隣の産油地帯である蘭印から石油を調達する、ということ以外に考えられないのである。対米戦なら当然オランダも敵になるからである。
日本海軍は対米戦を想定していた。戦争の兆候が出れば、米国が石油禁輸をするのは当然である。艦艇燃料の石油依存度が高くなるにつれて、対米開戦を考えたなら当然海軍は、アメリカ以外のどこかからの石油調達対策を考えなければならない。
これは絶対必要な条件のはずである。しかし、海軍がこのことを研究していたという事を、寡聞にして知らない。対米戦の兆候が出ると、突如として蘭印からの石油確保を考えたのである。もちろん蘭印から石油が取れるくらいのことは知っていたのである。にもかかわらず、なぜ海軍が石油調達対策を真面目に研究してこなかったのか。現に、精油施設を破壊される前に、即座に占領するために有名な落下傘部隊を派遣したのは陸軍であって、海軍ではなかった。
海軍は対米戦が起こるなどとは、本気で考えていなかったからとしか考えられない。海軍は予算獲得のために、対米戦を想定していたのに過ぎない。酸素魚雷にしても、艦艇の過大な兵装にしても、対米戦を考えよ、といわれて海軍技術陣も努力し、日月火水木金金、と言われるほど兵士は必至の努力を重ねていた。訓練により多くの兵士の犠牲も出していた。しかし、海軍の幹部は根柢のところで不真面目であったのである。
⑮米国が開戦を遅らせた訳
日米交渉で米国が交渉を妥結させる気はないのに、交渉を引き延ばしたことについて、戦争の準備ができるまで待った、と言われるがそれ以上に具体的な理由を聞かない。もし、対日戦がヨーロッパへの参戦のきっかけ作りだとすれば、1941年末では遅いくらいである。結局のところ、対日戦の準備のためと考えられる。対日戦ならば海軍戦力が重要となる。
米国は日本の海軍力を恐れていたのは事実である。結局は新戦艦の完成待ちだったのではなかろうか。第一次大戦以後、最後に建造されたメリーランド級は1923年頃の竣工である。日本も同様だが、それ以後第二次大戦までに完成した戦艦はない。新戦艦が竣工したのは1941年のノースカロライナ級2隻であるが、実戦配備となったのは翌年の3月である(*)。それから、サウス・ダコタ級4隻と最後の米戦艦のアイオワ級4隻が次々と竣工している。
第二次大戦以前に保有していた日米の戦艦は、各々10隻と16隻で、対米比率は6割を僅かに超えるだけであるが、対独戦参戦を考えると、いくらかは大西洋方面にも戦力を割かなければならない。いかに米国が太平洋での戦いに海軍戦力を重視したかは、大西洋方面で専ら戦ったのが、前記16隻中の最も旧式戦艦に属する、アーカンソー級とテキサス級3隻だけだったのでも分かる。もちろん新戦艦の一部も大西洋に回されてはいるのだが。
いずれにしても、新戦艦群が1942年に実戦配備となるのを米国はぎりきり期待して、最後通牒とも言うべきハル・ノートを1941年11月に渡し、年末の開戦を待ったのである。米国は第二次大戦中に新戦艦10隻を就役させたのに対して、日本は僅かに大和級の二隻だけである。
空母となった信濃や改大和級があるではないか、と言われそうだが、米国もアイオワ級2隻も船台の上で、工事途中で建造中止され、巨大戦艦のモンタナ級も設計だけだが、5隻が計画だけで中止となっているから、計画分でも、やはり量は米国の方がよほど多い。結局日本も米国も太平洋での戦闘には戦艦を重視し、米国は新戦艦の完成を待って日本を挑発したのである。
*世界の艦船1984年6月増刊「第2次大戦のアメリカ軍艦」
⑯開戦の一撃の敗北で講和した国はない
山本五十六が真珠湾攻撃を行ったのは、国力の差で、長期戦となったら勝ち目がないから、一撃で徹底的な被害を与えて、講和に持ち込む算段だった、というのが一般的に言われているのだと思う。阿川弘幸の山本五十六にも、海軍大臣に送った「戦備に関する意見書」で「勝敗を第一日に於て決するの覚悟(下巻P28)」と書いている。しかし、同書を他の個所を読んでも必ずしも、真珠湾攻撃後、継戦することがないと考えていたとも言い切れない。一撃で決戦するつもりかどうか、山本の戦略はまことに判然としないのである。
冷静に考えてみれば、世界の戦史に領土も占領されずに、開戦劈頭の一度の大敗で敗北を認めて講和した、という例はないと思う。開戦の通告が事前に行われていれば、米国は大被害のショックから、日本が講和を申し入れれば受け入れる、と考えるのは歴史的常識として、荒唐無稽という他ない。
荒唐無稽とも思われないのは、駐米大使館の無様な不手際から、開戦の通告が遅れたために、米国世論が一気に参戦に転じたという説がまかり通っていて大問題視され、もし通告が遅れなかったら、ということが痛恨事として肥大化していって、そこで思考停止してしまった。そこで、遅れなかった時の、その後の米国の対応がどうなっていたか、ということに想像力を働かすことをしないことにあるように思う。
「未完の大東亜戦争」で渡辺望氏は、米国にとって真珠湾攻撃は米本土決戦に等しく、本土空襲などは、その報復として行われ、仕上げとして日本本土決戦を予定した、というのだが、あり得る話でも考え過ぎである。ハワイはアジア進出の橋頭保として併合したもので、州に昇格したのは戦後の話である。本土の一部と言う意識が米国人にあったとは考えにくい。米大統領が戦時中ことあるごとに真珠湾攻撃を持ち出したのは、アラモ砦やメイン号と同じく戦争の大義として利用していたのに過ぎない。
もし、山本五十六が本気で真珠湾攻撃の一撃で講和できる、と考えていたとしたら愚か過ぎるから、そんなことはないであろう。このような説は、後年の伝記作家や海軍関係者が、反戦主義だった山本は早期講和を望んでいたという根拠として、流布したものだろう。
山本の意図は、日露開戦劈頭の旅順港攻撃にならったもので、旅順港攻撃が攻撃の不徹底によって失敗したための教訓を取り入れたものである、という説を読んだことがあるが、これが正しいのだと思う。旅順港のロシア太平洋艦隊を、開戦と同時に撃滅して制海権を奪う、という発想と真珠湾の太平洋艦隊を撃滅する、という発想は類似していて、海軍軍人としては自然な発想である。
この発想は、永年海軍が想定して戦備を整えていた、開戦と同時にフィリピンを攻略すると、米艦隊が一挙に攻めてきて、フィリピン沖か小笠原沖あたりの西太平洋で、日米の艦隊決戦が起り日本が勝利する、という構想と全く異なる。そのため、突然真珠湾攻撃に転じたのは、戦争のドクトリンを突如変更することで、極めて無理がある、と言う説を唱える人も多い。小生もそのこと自体は正しいと思う。
だがそれ以前に、海軍の西太平洋での艦隊決戦ドクトリンが、対米戦の構想として現実的ではない、と考えている。米艦隊がフィリピン方面に攻めてくるのは、フィリピンに逆上陸してフィリピンを奪還するためである。米艦隊は上陸支援をしにくるのである。現実に、フィリピン沖海戦は、複雑な様相を呈し、連合艦隊と米太平洋艦隊による単純な艦隊決戦とはならなかったのである。
真面目に対米戦を考えるなら、開戦劈頭に米太平洋艦隊を奇襲して、戦力を大幅に奪っておこう、と考えるのは自然である。西太平洋沖の艦隊決戦を構想したのは、海軍は対米戦を想定していたのではなく、陸軍と張り合って予算を獲得する算段をしていたのである。
だから、日米の全艦隊が西太平洋で一度限りの艦隊決戦を行う、という空想をして、勝利のためには艦隊戦力は米国の七割でなければならない、と主張したのである。だが艦隊決戦の根拠となった日本海海戦が、バルチック艦隊と連合艦隊が互いに持てる艦隊の全力をあげて戦う結果となったのは、バルチック艦隊が日本攻撃のために出撃して衝突したのではない。ひとまずウラジオストックに全艦隊を一斉に回航しようとしたのである。
ウラジオストックに無事ついたら、再度全艦隊が一斉に出撃する理由もない。バルチック艦隊の任務は、日本軍の大陸への補給を遮断し、大陸の日本軍を孤立させ、軍需物資が枯渇したところをロシア陸軍が反撃に転じて殲滅し、戦争に勝利することであろう。
確かに山本が突如ドクトリンを変更して、突如真珠湾を攻撃したことは間違いである。しかし、本当に対米戦をすることを考えると、真珠湾に太平洋艦隊がいる限り、真珠湾を攻撃して太平洋艦隊の主力艦を漸減しておかなければならない、という発想が生まれるのである。日本海軍の永年のドクトリンが真面目に対米戦を考えていなかった、という所以である。
ちなみに陸軍は、帝国国防方針に基づき、フィリピン上陸作戦を考慮し、上陸作戦用の大発動艇や強襲揚陸艦の世界的先駆と言うべき、神州丸やあきつ丸を開発した。これらの船は大発動艇などを搭載している本格的なものである。大発は米国が参考にして上陸用舟艇を開発したという先駆的なものである。これらの上陸用艦艇は、支那事変や大東亜戦争でも活用されているから、陸軍には実戦を想定した先見の明がある。
その一方で、第一次大戦でドイツ潜水艦による通商破壊の絶大な効果を知りながら、補給遮断に潜水艦を活用することもなく、船団護衛の艦隊を編成したのは戦争末期であり、効果を発揮するには遅すぎたし、対潜機材の開発も極めて遅れていた。小生は、海軍の戦備構想が、陸軍に比べ実戦を想定していない、空想的なものであると言わざるを得ない。
⑰上陸作戦の水際阻止は当然
大東亜戦争において、日本軍は、米軍の上陸作戦の水際阻止に固執して失敗を繰り返した、と批判されている。硫黄島においては、水際阻止を諦めて、上陸後の反撃に徹したために米軍に大損害を与えた、とされている。これとて、上陸作戦を阻止することに成功した訳ではない。水際阻止はうまくいかないことの証明として、硫黄島でも上陸中に反撃してしまった一部の重砲は、またたくまに米軍艦の反撃にあい、破壊されてしまった、ことが挙げられる。
日本軍が上陸の水際阻止に固執したのは作戦の基本からは間違いではない。作戦の常道だったからである。上陸部隊が橋頭保を確保する前の、不安定な時期に撃退する、というのは筋が通っている。日本軍が水際阻止に固執して失敗を繰り返した、と批判する論には、言及されていないことがあるように思われる。
水際阻止は作戦の常道である、と言った。それなのに何故日本軍は繰り返し失敗したか、である。水際阻止に失敗した日本軍が守る島嶼には、敵上陸支援艦隊よりもはるかに劣る火力しかなかったから、水際阻止のためには、上陸支援艦隊を制圧できる、日本艦隊の攻撃力が必要だったのに、日本海軍は実行しなかったのである。これでは水際阻止が成功する道理はない。
米軍は、珊瑚海やミッドウェーで、上陸開始以前に艦隊を派遣し、上陸支援艦隊を早急に排除した。水際阻止以前の時点で上陸作戦阻止に成功したのである。珊瑚海海戦では、上陸地点の空襲にすら至らなかったのである。これに対して、ガダルカナル以降の米軍の上陸作戦に対して、日本艦隊が上陸阻止を実行したことはなかった。かろうじて、第一次ソロモン海戦において、三川艦隊が、ガダルカナルに米軍が揚陸中に上陸支援艦隊に大損害を与える戦果を挙げた。
しかし、三川艦隊はこのチャンスに、輸送船団を攻撃していると、戦場離脱前に夜が明けて、航空攻撃を受ける恐れがある、として帰投してしまった。日本海軍は艦隊決戦に固執するあまり、艦隊決戦以前に艦艇を少しでも喪失することを恐れていた。そもそも、軍艦同士の海戦を行うことは、艦隊作戦の目的ではなく、補給阻止や上陸阻止ないし、これらへの支援という作戦目的の結果として生ずるものである。
ところが日本海軍は、第一次大戦の戦訓として、独潜水艦による輸送船団攻撃による英国の苦境を知りつつ無視し、史上空前のジュットランド海戦の英独戦艦の戦いだけから戦訓を得ようとした。ドイツ艦隊のしぶとい戦いぶりを称賛する論もあるが、本海戦以後ドイツ海軍は引きこもってしまったから、勝者は英海軍である。
日本海軍の艦隊決戦への固執は、大東亜戦争において、米軍の補給阻止に何の手も打てず、逆に米軍の補給阻止に散々苦しめられた遠因となった。米軍が対日戦を行うには、米本土からハワイを経由する長大な補給線が必要だ、という大きな弱みがありながら、日本海軍は米軍の補給作戦に高見の見物を決め込んでいたのである。
日本側には賛否両論があるが、米軍の三川中将のこの海戦の戦闘指揮に対する評価は高いように思われる。これは、三川艦隊が大戦果を挙げたことに対する称賛であるが、米輸送船団を見逃したという、臥竜点睛を欠いたことに対する安堵の念もあったのではなかろうか、と小生は勘ぐっている。
これは、敵軍による称賛とは、全面的な敗北をした場合には、必ずしも行われることはない、という例証のように思われる。米軍には三川艦隊の活躍を誉めていられるだけのゆとりがあったのである。結局のところ、日本艦隊が米軍に対する上陸阻止の先手を打てなかったのは、情報収集の不十分と、判断基準が日本に都合のよいものとなっていて、敵軍の立場に立って思考しなかったからのように思われる。
もっとも戦争末期はそれどころではなかったのであろうが。いずれにしても、日本軍が島嶼上陸の水際阻止に固執したことだけを批判するのは、片手落ちのように思われる。
⑱フィリピン沖艦隊決戦の怪
日本海軍の伝統的対米戦略は、概ねこう総括できるそうである。対米開戦劈頭、フィリピンを占領する。米本土やハワイからの米軍からの応援は間に合わないから、フィリピン占領は可能だというわけだ。するとフィリピン奪還に、逆上陸船団を従えて、米主力艦隊が大挙向かってくる。それを日本艦隊が迎撃し、フィリピン沖か小笠原諸島付近で、日米艦隊決戦が生起する、というものである。
そのため艦隊の練度を上げ、夜戦や潜水艦、航空機等により、漸減作戦をし、ワシントン条約等で対米戦力不足となった主力艦隊を助けるのである。現実にマリアナ沖海戦で勝利した後、米軍は大挙してフィリピン攻略を実行した。
こう書けば、開戦の真珠湾攻撃は想定外であるにしても、フィリピン攻略部隊の迎撃と言う、日本海軍の想定はあながち見当違いではなかった。ところが、実際には海軍はフィリピン攻略艦隊を迎撃はしなかった。それどころか、易々と上陸されて後、ようやく捷1号作戦を発動し、迎撃体制を整えて待っている米艦隊に、兵力を分散して攻撃し、各個撃破されて、事実上日本海軍は壊滅した。
確かに、マリアナ沖海戦で海軍の航空艦隊は壊滅した。しかし、戦艦9隻を主力とした、水上部隊は残っていたのである。米艦隊のフィリピンに向けての航行途中なら、エンガノ岬沖で囮となって沈んだ小沢艦隊の4隻の空母を楯に、砲力戦を挑むと言うことも可能であったろう。現に栗田艦隊は、米艦上機の執拗な攻撃を受けながら、レイテ湾に向かって進撃した。米軍は栗田艦隊のレイテ湾突入が可能であったことを認めている。
まことに奇妙なのは、想定した米艦隊の襲来と言うのは、情報がなければ迎撃できないことが考えられていないことである。情報がないから、フィリピンに米軍が来ると予測しながら、迎撃できずに上陸を許したのである。現に珊瑚海海戦の原因となった、ポートモレスビー攻略作戦の情報を米軍は掴んでいたから、航行途中の日本艦隊の迎撃作戦が出来たのである。
国際関係の状況が違うとはいえ、かつての日本海軍はロシア艦隊の進路と時期の情報の収集に心血をそそいでいた。大東亜戦争の海軍上層部にはその片鱗すら見られない。いくら太平洋が広くても、米本土からは、ハワイを中継しなければ、フィリピンはもちろん、西太平洋海域には来られない。上陸されてから迎撃艦隊を派遣する、というのは大間抜けである。戦闘そのものには勝利した第一次ソロモン海戦も同様で、米輸送船団と支援艦隊が上陸地点に突入後、追っかけ三川艦隊が到着している。全てが後手なのである。
重巡インディアナポリスは原爆の部品を運搬するために、東海岸を出発し、パナマ運河、サンフランシスコ、ハワイと経由してテニアン島にたどりついている。米軍の東海岸から西太平洋の航行ルートの、ターミナルはわずかしかなく、明白なのである。
例えば長大な航続力を持つイ号潜水艦が、アメリカ西海岸、パナマ運河やハワイ周辺を看視する、といったことは可能であった。潜水艦を米西海岸まで苦労して長躯航行させて、水上機から僅かな爆弾を投下するなどということはやらせたのに、米軍の輸送ルートの情報収集に失敗しているのは、奇異としかいいようがない。
4.日本軍の航空技術論
①零戦の金星換装
零戦の設計者、堀越二郎技師の名は世界に有名である。しかし彼の海軍とのやりとりを点検して見ると、設計テクニックには素晴らしいものがある反面、新技術や軍用機に対する設計思想については疑問を抱かざるを得ない。彼は単なる高度な設計職人に過ぎない。エンジニヤではない。
零戦は最後のカンフル剤として、昭和十九年末に千馬力級の栄から千五百馬力の金星に換装することになった。堀越氏が認めているように、金星への換装は二年も前に可能だったのであり、「・・・その後もさらに改良されて、零戦は依然としてその高性能を誇っていたのかも知れない。」(*)というのである。
ところが大学同期の川崎航空機の土井武夫技師は「昭和17年4月、海軍の空技廠が堀越君(零戦設計者)に、非公式ではあるが発動機を金星とした零戦の性能向上機の打診があったとき、堀越君は設計陣容不足のため断ったと聞いている。私は、あの時期にこそ、金星をつけた零戦の性能向上機を考えるべきではなかったかと思う。」(**)と批判している。土井氏の批判は全てを物語っている。土井技師はこの時点での零戦の性能向上が戦局に与える重要性を理解しているのである。
これについて堀越技師は「昭和十七年、私は永野治航空部員の私的打診に応ずることができず、・・・」(*)と実にあっさり書く。その理由の説明と見られるくだりは次のようなものである。
・・・その幾多の改造が顕著な十項を挙げ得なかったのは、使用者側指導層の技術上の問題や戦局に関する初期の見通しが甘かったせいだと思われる点が多い。なぜなら、開戦当初から日本海軍の戦闘機特に零戦の重大な役割と冷戦に要求される改善を予見できたにもかかわらず、機種に応じた重点的人員配置などが適当でなく、担当者としては人手のいることには消極的とならざるを得なかったからである。もしこの点に対する判断処置さえよかったなら、最後型となった五四型丙は二年も早く生まれ、恐らくはその後もさらに改良されて、零戦は依然としてその高め性能を誇っていたかも知れない。
さらに金星換装などはアメリカ人などの外国人には余りにも遅かったように見えただろうとして、次のように弁明する。
これには大きな理由があったのである。これを一口にいえば、日本の産業の規模が全般的には世界第一流の水準から遠い状態にあったということである。こういう規模の小さい産業に支えられる航空機工業では、経験ある技術者の過少とも重なって、着想から実験、設計、試作、実用に至るまでに非常に時間がかかった。
さらに半ページ程にわたって日本の産業構造やそれに対する適切な指導を行わない海軍の技術行政に対する批判が続く。自分が海軍の打診を断ったことに対する悔悟の表明がないばかりか、全ての責任は日本の産業構造の後進性と、海軍の技術行政の不適切によるものだと談じているのである。余りに身勝手ではないか。もっと困難な液冷エンジンから空冷エンジンへの換装をその困難なはずの状況で同窓の土井技師は実行し得たのである。だから土井技師は自信を持って堀越技師を批判できたのである。それを海軍の責任、日本の工業の浅さに帰するとは。言うべき言葉はない。
二年前、すなわち昭和十八年に誕生していたはずの金星付零戦の誕生を阻止したのは、土井氏の指摘するように堀越技師自身であった。その後の戦時の混乱を考えれば換装作業は早ければ早いほど容易だったのである。自身の非を一言も認めず海軍に、日本の工業基盤を責める堀越技師の態度は卑劣でさえある。最後まで零戦は海軍の主力であったこと、昭和二十年に登場するのと、五二型の代わりに金星零戦が登場したのでは意味が全く異なることを考えれば、二年の遅れは絶大である。零戦とF4Fの馬力差と性能差を考えれば、金星零戦はヘルキャットと対等に戦えたであろう。その意味で昭和十七年の堀越技師の断りの意味は極めて大きい。内心それを知るからこそ、断ったことをこともなげに書き、海軍などの責任をとうとうと追及するのである。
実は堀越技師は海軍の命に唯々諾々と従う従順な性格ではない。中止を命ぜられた誉装備の烈風への自社発動機への換装を海軍と会社を説得して実行した。それにもかかわらず、零戦と烈風の仕様決定の際には、翼面加重の決定や仕様の優先事項決定を迫っている。このことは堀越技師が戦闘機の性能のあり方に定見がないことを示している。堀越技師は優秀な設計「職人」と言うべく、見識のある技術者ではない。与えられたスペックをいかに実現するかは優秀であったが、スペックのありようを示す見識はなかった。そのような人物がどうして海軍の航空行政の不見識を批判できるのか不可思議である。航空行政に定見のない者が航空行政を批判できようはずがない。
民間技術者であろうと世界の技術動向を研究し、戦闘機の性能のあり方に見識があってしかるべきである。ところが堀越技師は自らの見識を披瀝するのではなく、仕様をはっきりせよと迫るだけなのである。海軍の見識に頼るしか能のない人間にどうして海軍を見識の批判するのうりょくがあろうか。土井技師は同一期間に堀越技師よりよほど多くの軍用機の設計と改造を手がけた。三菱の体制が非能率だとする説もあるが、明らかに土井技師はしかるべく工夫をして能率的に仕事をしている。自分ならできたという自信がさきの堀越批判になったのであろう。堀越技師に伝説の設計者の冠をかぶせるには罪も多すぎる。功罪は正当に評価すべきである。
②堀越技師の戦闘機設計に対する不見識
堀越技師が海軍などを批判して自らの失敗を反省することがないことはあまりに身勝手である。烈風のエンジンは堀越技師の主張で当初の誉から三菱のMK9Aに換装することになり、昭和19年7月から作業を開始して、10月に完成している。一方の零戦五四型は同年11月に指示を受け、翌4月に完成している。零戦は武装の変更があったとはいえ、同じ中島製発動機から三菱製発動機に換装する工事の難易は同程度であったのにこの差である。
この原因は戦争が後期になるに従って、空襲などにより作業が困難になったことによることは多くの資料の証明するところでうなずける。ところが堀越技師の主張は異なる。零戦が金星に換装するのに手間がかかったのは、日本の近代産業が未熟なため産業構造が脆弱であったことによるということを著書「零戦」で延々と主張している。
烈風のMK9A換装は自ら強硬に主張していることと比較すればこれは堀越技師のエゴというほかなかろう。烈風が当初からMK9Aを搭載して量産されたとしても、昭和17年に零戦が金星に換装した場合のほうが戦局に与えた効果は、はるかに大きい。こうなると堀越氏は烈風の失敗でプライドを傷つけられる方を、戦局に与える効果より重視していたというよりほかない。
一方で昭和17年に発動機換装の打診を受けて断ったことを、事もなげに書いているからである。烈風が最初から自社製エンジンを積んで量産されていたら、と書いたがこの仮定はあり得ない。実はこれは堀越技師の主張である。試作指示の時点で誉は慣性の域に達していたのに対して、MK9Aは完成の見通しすらついていなかった。堀越技師が換装を提案した時点にやっと間に合ったのに過ぎなかったのである。兵藤二十八氏が指摘(**)するように、堀越技師は戦後になって詭弁を使ったのである。
烈風の例を引くまでもなく、エンジンを別系統に換装することは珍しいことではない。寸法の異なる他メーカーへの換装どころか、空冷から液冷エンジンへ、その逆などの例は日本はもとより外国でも多数の例はある。日本では五式戦闘機を空冷エンジンに換装したこと自体を特筆されることのように評論する向きが多いが、外国ではFw190シリーズやラボアチキン戦闘機のように換装の困難さではなく、換装による性能向上や戦闘能力向上といった面に評価の重点がおかれるが、その方が評価としては健全である。
五式戦闘機など日本の場合はエンジンの生産不足という実際面で追い込まれたからであり、性能はむしろ低下しているからである。それ以上の疑問は烈風の時に判明したように中島製から三菱製発動機に換装するのはさほど困難ではなかったということである。両者に共通するのは重量の増加、出力の増加の他エンジンの直径の差とマウント構造の相違である。疑問は細い誉から太いMK9Aに容易に変更できたということである。高さ方向では確かに内蔵のオイルクーラーを外に張り出して寸法差をカバーしているのに、胴体幅に変更がないのは奇妙である。当初からMK9Aに換装することを考慮していたのではないかとさえ疑ったがそうではなかった。雷電と同じく烈風は、胴体直径をエンジンの直径からくる必要最小限の径より大きくしても、胴体形状を流線型に成形することが、空気抵抗の減少につながるという海軍の理論を採用したから、胴体幅にゆとりがあったのである。
堀越技師は零戦の試作指示の際も烈風の際も速度、運動性能、航続距離など、要求仕様に矛盾があるとして優先事項を明確にするように発言している。これは一見担当技術者としては正当に聞こえる。しかしこのことは堀越技師には、あるべき戦闘機の未来像や、相手たる米機の動向から理想とするものは何かという主体性が欠けている。
確かに堀越技師には与えられたスペックを実現するための綿密な設計能力があることは零戦の例で証明されている。しかしエンジニヤとしての見識はなきに等しく、職人的設計者に過ぎないと言わざるを得ない。海軍側が零戦以上の高速と零戦並みの運動性能を要求したときに答えるべきは、そんなことは実現できないから要求のどれかを緩和してくれ、などということではない。
零戦の運動性能は敵F4Fに対してはるかに優れ、後継機はさらに高速化して運動性能は低下する見通しだから、烈風の運動性能をF4Fより劣る程度に低下させても、その分速度性能を向上させれば、F4Fとその後継機に総合力で充分勝つことができると説くべきだったのである。現にそのような考え方を持つ海軍の用兵者はいたのである。堀越技師は自己の専門とする戦闘機の性能について、近未来ですら定見を持たなかったのである。堀越技師はもし定見があれば、主張を控えるようなおとなしい人物ではない。烈風のエンジン換装の際には、試作中止の決定がなされたのにもかかわらず、海軍と会社を説き伏せて、会社のリスクで換装作業を行うことに成功している。むしろ信念のある事項については実行力のある人物であったことがわかる。
③発動機性能の疑惑
烈風は海軍から供給された中島航空機製の誉発動機を装備したが、性能が不足したので発動機の性能不足と推定して、三菱の名古屋工場でベンチテストしたところ、果たして額面値を25%も下回っていたと堀越は書いた。全くの素人ならいざ知らず、私にはこの話はにわかには信じられない。どんなエンジンでも製造者が一台づつ試験して納入する。すると堀越が事前にこのデータを見ていたのなら、性能が額面値を割っていることを知っていたはずである。
もし中島の試験値が額面通りであったとするなら、中島は嘘の報告書を提出したのである。私にはこのようなことは技術者の常識として信じられない。中島側は海軍から試作機に搭載されるエンジンだと知らされていたはずである。それならば中島はベストのエンジンを供給したのである。また常識として大事な試作機のエンジンの性能試験には、設計主任の堀越か彼の部下が立ち会っているはずである。その時には誉発動機の性能は確認できていたのである。
堀越は三菱側が性能試験に立ち会ったことを隠しているのではなかろうか。そして性能がどの程度であったかを知っていたことを隠している。私も排水機場のポンプのディーゼルエンジンの性能試験にユーザーとして立会いしたことが何度かある。特に主エンジンは必ず現地据付前の向上試験に立ち会うのは常識である。補機類ですら、カタログ値ではなく、一台づつ試験成績書の提出を求める。たかがポンプのエンジンですらこれである。航空機のエンジンの納入に、まして大切な試作機の場合に機体設計の関係者が立ち会うのはそれ以上に当然と理解すべきである。まして、現物の試験をせずに標準カタログ値の提出で済ませる、とは考えられない。
それではこの事態をいかに解釈すべきであるのか。答えのひとつは堀越の著書にあった。烈風の性能不足について「零戦」で堀越は他の日本製航空機の性能が試作当時に比べて低下していることを発見したと書いている。その原因は巷間で流布されているような工作技術の低下ではなかった。「この性能低下の原因は燃料の質の低下、水メタノール噴射量の調整不良その他発動機側に大部分の責任があること、またその現象が誉発動機に特に顕著であることに確信を抱くことなった。」と書いた。
そして戦闘機雷電で87オクタン燃料使用の場合の性能低下について記述している。雑誌「丸」平成18年12月号P75に陸軍一式戦闘機の性能についての記事がある。「この頃の陸軍航空隊ではまだオクタン価八七の航空八七揮発油を使用しており、海軍の零戦が使用していたオクタン価九二の九二揮発油が使用されていなかった。そのために零戦二一型とほぼ同等のハ二五発動機を装備していてもその性能を十分発揮できなかったが、昭和十六年夏には陸軍機も航空九二の使用を開始したのである。」とある。
これらの記述を総合すると答えは自ずとわかる。その前に、別項でも述べたがオクタン価に知識のない人のために簡単に説明する。オクタン価は燃料のアンチノック性能、つまりノッキングを起こしにくさを表し、オクタン価が高ければノッキングを起こしにくい。オクタン価はイソオクタンとノルマルヘプタンの混合燃料と被試験燃料のノッキング性能が同等になるときの、イソオクタンのパーセンテージを言う。92オクタンとはイソオクタン92%のものと同等のアンチノック性能を持つということである。だからオクタン価は100以上はないとも言えるのだが、100以上の場合、別な試験方法で代替してこれをパーフォーマンスナンバと言うが通常オクタン価と称することも多い。
ところでオクタン価への誤解は、オクタン価が高いものを使えばエンジンの性能が良くなるということである。ガソリンの単位重量あたり発熱量はオクタン価に関わらず一定である。ノッキングとは、エンジンの燃焼室内の圧力等の関係で、異常燃焼を起こしてシリンダやピストンを破壊してしまう現象である。だからエンジンはノッキングを起こさない範囲で運転する。オクタン価の高い燃料を使えばノッキングを起こしにくいから高い吸入圧力や圧縮比を採用できる。高いブースト圧や圧縮比を採用できるから単位排気量当たりの出力の高い高性能エンジンが設計できるというわけである。逆にそのようなエンジンは、設計の前提としたオクタン価のガソリンを使わなければ性能は確実に低下する。これで理解いただけたと思う。
堀越の言う燃料の質の低下、というのは92オクタンで設計されたエンジンに87オクタンの燃料を使用していた、ということではなかろうか。もし、そうなら、性能が低下するのは当然である。水メタノール噴射も同様で吸入空気の冷却効果があるから、過給によって上昇した吸入温度を下げる効果があるからノッキング対策となる。だからオクタン価が下がり、水メタノール噴射がうまくいかなければ性能が低下するのは当然である。堀越はこのことを指摘したのに過ぎないのであろう。この推定が正しいとすれば、陸海軍ともに昭和19年当時では燃料の不足から87オクタンの低品質燃料を使わざるを得なかったのである。そして中島の納品検査の際には92オクタンの燃料を使い、三菱の飛行試験では87オクタンの燃料を使っていたとしたら辻褄があう。ただ前間氏の著書によれば、誉は100オクタンを前提に設計していたと言うからますます分からない。。
そして飛行試験で海軍側が実際に使用される予定の87オクタン燃料を使用したのもおかしな話ではない。誉の性能不足が主としてオクタン価の低下であると指摘した以上、堀越がこの経緯に気付かないはずはない。燃料の性能低下が主原因と考えたのに、92オクタン燃料を使用しなかったから性能不足が生じたと主張しなかった堀越に私は疑念を抱く。そしてなぜ三菱製のMK9Aに換えれば性能は回復すると見通したのであろうか。
案外忘れられているのが誉とMK9Aとの性能差である。10%も出力差があったのである。そしてエンジン直径が大きいにも関わらずオイルクーラーが下にはみ出しただけで胴体寸法内にMK9Aエンジンは納まっている。すると空気抵抗に大差ない。そして「零戦」に奇妙な記述がある。最大速度343ktの計算値は要求性能に釣られて空気抵抗等を過少に見積もった過大な性能であると言うのだ(P304)。そして正直には331.5kt程度であるという。堀越は海軍に虚偽の性能計算書を提出したのだ。MK9Aの方が性能低下は少ないと考えたのだから、性能低下と馬力アップを総合して悪くても331.5ktは保証されると踏んだのだ。試験値は337~339ktであり海軍への当初見積もりより低い。
MK9Aが10%も高い馬力を性能低下なしに発揮していたのなら、海軍への当初見積もり343ktを越える性能を発揮してもおかしくない。MK9Aも性能は低オクタン燃料により低下していたのだ。以上のように推定すれば性能回復は筋が通る。MK9Aによる性能回復はもともと大馬力であったことと、性能低下が少ないことを見越した堀越技師のマジックではなかったか。誉は火星や栄などのエンジンに比べてブースト圧も圧縮比も高く設定されていたからオクタン価の低下に対してシビアであったのは当然であり、誉の性能低下が著しいという堀越の主張は事実である。
92(あるいは100)オクタンで設計されたエンジンを87オクタンで使用するためには、使用制限が課せられるから性能は低下する。一体92オクタンで設計されたエンジンを87オクタンで使用した場合の性能より、最初から87オクタンで設計された場合の方が良い性能を得られる。同じく石油資源の無いドイツ空軍は87オクタンの燃料で通すと言う賢明な選択をした。いずれにしても烈風が三菱製エンジンに換装して本来の性能が得られたという「神話」には誉より10%も出力が大きいエンジンに換装されたという、有利な前提が忘れられている。
④ムスタングよりも3倍高価な零戦
零戦の堀越二郎技師は有名な、共著「零戦」を書いている。そこには有名な米空軍のP-51ムスタング戦闘機との生産工数の比較が記されている。生産工数とは、物を作る時にかかる時間を言う。例えば100人・時と言った時、一人で働けば100時間を必要とし、5人で働けば20時間を必要とする、という事になる。
同書によればほぼ同時期の零戦は、構造重量950kgに対して工数が10,000人・時、P-51は2110kgと2,700人・時である。構造重量とはエンジンなどを除いた純粋に機体本体の重量で、工数の対象である。生産工数は10,000÷2,700で零戦は3.7倍にもなる。実際には重量の差があるから、その開きはもっと多いが。単純に考えれば零戦はムスタングの3.7倍の価格と言うことになるが、そうではない。ドルのレートで換算するとP-51は零戦の2倍の価格だと言うのだ。
この事について堀越技師は淡々と述べているだけであるが、軍事上は重大な問題を抱えている。結果的に零戦が安いのは給与水準が米国より遥かに安かったからである。現在の日本が中国で安い製品を作っているのと同じである。しかし戦時の事だから、P-51も零戦も同じ自国内で生産するしかないのだから、互いの国の給与水準の相違には何の意味もなく、工数の差だけが問題になる。
限られた人的資源でどのくらい少ない人数で武器を製造できるか、という事は重大な事である。確かに零戦の設計時点では、零戦がこれほどの大量生産をしなければならないとは想定されていないから、優秀な機体を作るためには工数がいくらかかっても仕方ないとは言えるであろう。しかし「零戦」が書かれたのは戦後である。
零戦が1万機以上生産され、戦争の帰趨を制するには大量の武器を必要とし、そのためには生産工数が少ない方が良かったという反省ができる時期であった。当時の日本人は米国の物量に負けたと言っていたからである。つまり零戦より高性能のP-51が零戦のなんと3.7分の1の労力で作られていたというのは大いに反省してしかるべきである。しかも人口は日本は半分で、工場で働く工員ははるかに少なかったのである。
それなのに堀越技師は平然と、米国は機械作業が多く日本は手作業が多いから、生産数が少ない時は日本の方が安く、多くなると米国が有利になると、淡々と述べているだけである。堀越技師には反省はないのである。さらにP-51はその後価格も工数も大幅に低減していると述べている。これは単に前述の多量生産の効果によるものだけではなく、工数低減のための設計変更の努力がなされた事を意味している。
ところが零戦はその後も工数がほとんど変わらない、と書いている。つまり生産性向上の努力がなされていない、という事である。これは自社でできる努力だから、さすがの堀越技師も海軍の批判はしていない。批判しないのは工数低減の重要性に気付いていなかったからでもある。だから「日本の航空を顧みて」という項で日本の航空技術の短所について、無線機などの機能部品が劣っていた事や防弾対策の遅れを指摘しているだけであって生産性が遥かに悪かった事については言及しない。やはり堀越技師は優秀な設計職人であって技術者ではないと断ぜざるを得ない。
⑤烈風の性能に関する疑問
本稿は「零戦」(新装改訂版・堀越二郎・奥宮正武共著、朝日ソノラマ・昭和50年3月5日初版)によっている。本文には書かれていないが、P304の比較表に次のようなことが書かれている。(表の抜粋)
表A
|
機名 |
A7M1 |
A7M1現状 |
A7M1 |
|
|
装備発動機 |
誉NK9K |
同左 |
同左 |
|
|
仮定 |
発動機出力 |
使用状況制限現 |
使用制限額面通り |
正規額面通り |
|
公称馬力/高度(メートル) |
1300/6150 |
1570/6850 |
1700/6400 |
|
|
最高速(ノット) |
300/6150 |
317/6850 |
332/6400 |
|
短評 |
抵抗係数を不当なまでに大きく仮定し馬力を1300に落として漸く説明できる。動力艤装が悪いため馬力が出ないとは考えられぬ。 |
馬力さえ額面通りならば、この程度の性能は現状のままで出ないはずはない。 |
機体付加抵抗を過小にロケット効果を過大に見積もってある。「計画要求書の要求性能」に釣られた傾向あり。 |
|
次に本文には次のような事が書かれている。
①計画要求書(P296)
最高速345kt/6000m以上、上昇力6000mまで6分以下
また烈風の性能がでないことが判明した後の検討で
②・・・この会議では発動機のたとえば三〇パーセントの不足は速度を一〇パーセント低下させるに過ぎないが、上昇力を四〇パーセント以上低下させるという専門家にとっては平凡な理屈が忘れられていた。・・・この数字は海軍の保証する額面値を二五パーセントも下回っていた。(P303)
発動機を三菱のMK9Aに換装して性能が向上したときに次のようなコメントがある。
③・・・発動機の実際の性能が額面値に近いことを示していた。
次にMK9Aに換装した性能の実測値について次のような表B(P322)が示されている。この表にはA7M1の性能実測値が310kt/6190m、上昇時間が9′-54″/6000mとあるが、表Aと本文中には最大速度300kt内外上昇時間は6000mまで10′以上を要するとある記述とも矛盾するので省略した。なおこの性能は出版協同社の日本航空機総集に三菱が計測したものとして同じ最大速度と上昇時間が記載されているので、本文中と表Aの数値は海軍の計測数値であろう。社内試験結果が軍の記録を上回るのは他にも例がある。
表Bの数値は性能以外も全て、日本航空機総集の三菱と書かれたものと一致する。ただし同書には海軍の計測値が記載されているが、三菱との相違は第一速出力の高度が1000m、第二速の高度が6000mで、自重が3100kgで、最大速度の高度が6600mであることだけで大差ない。むしろ最大速度の計測高度が上がっているが、これはエンジンの第二速の高度が上がっていることと一致する。
表B
|
記号 |
A7M2 |
||
発動機 |
名称形式 |
ハ-43、11型(MK9A) |
|
|
第一速公称馬力/公称高度(m) |
2070/1100 |
||
|
重量 |
自 重(キロ) |
3266 |
|
|
最大速度(kt)/高度(m) |
339/5660 |
||
|
|
(1)A7M1の発動機換装防火壁前方変更。(2)A7M3とほぼ同じく胴体に防弾燃料タンクを増設。 |
||
|
備考 |
重量および性能は実測値 |
||
|
発動機の馬力は額面値を記入した |
|||
さて以上で「零戦」の記述の役者がそろったので検討しよう。第一に明らかなのは、三菱は計画要求書の最高速345kt/6000m以上と言う性能に合わせて故意に性能を過大推算し海軍に提出したのである。それならば本当はどの程度であると考えていたのだろうか。表AのA7M1現状馬力額面通りと仮定、と書かれたものの327kt/6850mであるが、ことはそう単純ではない。
発動機出力は額面通りと言うのにもかかわらず、使用制限がかかっていて、すでに1700馬力から1570馬力に性能低下しているのである。使用制限とは恐らく燃料のオクタン価が下げたことであろう。「歴史群像」太平洋戦史シリーズVol.50の一式戦闘機隼のP102には隼と零戦の性能差について同じ栄系エンジンを積んでいても、陸軍は87オクタンで海軍は92オクタンを使用していたからだとあるが、その通りである。ところが「零戦」のP306にはオクタン価87を使用した雷電の性能低下が書かれていて、大戦末期の海軍機の性能低下の原因は「燃料の質の低下、水メタノール噴射量の調整不良その他の発動機側に大部分に責任があること、またその現象が誉発動機装備機に特に顕著である」と断じている。
ガソリンを使う限り発熱量の違いはないから、堀越氏の言う燃料の性能低下とはオクタン価の低下のことである。つまり表Aの「性能計算書」の発動機の性能とは、計画時点で提示されたものだから92オクタン燃料を使い、水メタノール噴射装置の適切に調整されたものを使用して中島がベンチテストを行った性能表によるものであったろう。
大切な試作機に渡すエンジンの性能が、ベンチテストの性能曲線が無い単なるカタログ値であったとは考えにくいし、量産機ならともかく試作機に中島が製造不良品を渡すとは考えられない。そして三菱はその性能によって試算を行った。中島がベンチテストを行った時は、計測の便利のために補機の一部、すなわちよく調整された水メタノール噴射装置が中島のベンチテスト用に固定装備されていたことはあり得るのである。
さらに計算書提出時点では92オクタン燃料を予定していたのに、実際には戦局の悪化から海軍は実際に使用されるであろう、87オクタンの燃料を使用するよう要求した。そこで中島が三菱に発動機を引き渡す際に87オクタン燃料で行ったベンチテストの結果が表Aの「使用制限額面通り」の性能曲線であった。三菱も海軍も87オクタン燃料を使用する、と言った瞬間に表Aの「正規額面通り」の性能は出ず「使用制限額面通り」の性能しか出ないことは承知していたのである。ところが、「零戦」の本文にはその説明が無いから事実関係が分かりにくくなるのである。またの水メタノール噴射装置はベンチテストに使用したものではない、量産用のものが着けられていたのであろう。こう考えれば中島が架空の発動機性能を三菱に渡したのではないのに、誉の性能が計画時点より大幅に低下していたということが説明できる。この説明は堀越氏が「燃料の質の低下、水メタノール噴射量の調整不良」がある、と書いたこととも合致する。
また30%の馬力低下は10%の最大速度の低下しかもたらさず、実際の馬力低下は25%程度であったにしても、そもそも343ktの計算値が過大なのだから、三菱の310ktの計測値は測定時の搭載量に違いがあったとしか考えられず、海軍の300ktと言うのが妥当なところであろう。次にA7M2の339ktという性能は、③に書かれているようにMK9Aは額面値に近い性能を出したというのだから、誉より出力がずっと大きいにもかかわらず、誉装備の場合の性能計算値を下回っていて、このことからも性能計算書に水増しがあった、と言う事を裏付けている。つまり要求性能は初めから誉どころかMK9Aを使っても完全には達成できなかったのである。
それでは堀越技師が主張するように、最初からMK9Aを使っていたらどうなったのであろうか。これには重量の検討が必要となる。「零戦」には要求性能の中に翼面荷重150kg/㎡とあるが(P296)自ページには検討の結果差し当たり130kg/㎡程度のものを試作するとあり、最終的にどの程度に設定したのか分かりにくい。しかし日本航空機総集のデータにはA7M1は143kg/㎡となっている。一方零戦のP301には正規全備重量は予定より70kgしかオーバーしていない、とあるからこれから逆算すると、140.2kg/㎡となる。実際には140kg/㎡を予定していたのである。
一方誉よりMk9Aは高馬力ではあるが重いから、A7M2の翼面荷重は153kgと大きくなってしまっている。つまり最初から重いMK9Aを積んで翼面荷重140kgを目指せば主翼は大きくなり空気抵抗は増え機体重量も増える。海軍が翼面荷重を足かせにする以上、最初からMK9Aを積んでいれば、339ktという性能は得られなかった。エンジン換装による性能向上で、翼面荷重が目標値をオーバーしていたことを海軍が忘れてしまったからこの性能は得られたのである。
皆様は、エンジンの直径差があるとして零戦の金星エンジン換装さえ量産に間に合わなかった堀越技師が、なぜ易々と烈風のエンジン換装ができたのだろうかと疑問を持たないのであろうか。理由は実に簡単なことであった。A7M1の胴体最大幅に対するエンジン直径との差は170mmある。これに対して零戦は全型78mmである。この違いは零戦が胴体幅の最大値をカウリング位置にしているのに対して、烈風は雷電にならって全長の40%一に持ってきたことによる。表Cのようにカウリングとの差が170mmあったのではないにしても、エンジン最大直径一でもまだカウリングはカバカバだったのである。ちなみにA7M2でもこの差はまだ120mmあったのである。
表C
|
名 称 |
カウリング径 (mm) |
エンジン径 (mm) |
差 (mm) |
|
F6F-5 |
1473 |
1321 |
152 |
|
F8F-2 |
1422 |
1321 |
101 |
|
F4U-1 |
1350 |
1321 |
29 |
|
キ-84 |
1260 |
1180 |
80 |
|
A6M2~M5 |
1193 |
1115 |
78 |
|
A7M1 |
胴体幅1350 |
1180 |
170 |
|
A7M2 |
胴体幅1350 |
1230 |
120 |
|
キ-100 |
1280 |
1218 |
62 |
この表によれば、グラマン製の戦闘機がカバカバのカウリングを付けていたのは当然としても、空力的洗練を求めていたという日本機よりもF4Uの方がはるかに切り詰めた設計をしていたことが分かる。Ew190の数字は分からないが写真を見る限り、F4U同様にぎりぎりのカウリングであるように思う。エンジンの直径差が140mmもある疾風とF4Uであるが、カウリングの径では90mmしかない。誉エンジンが50mm大きい直径で設計されていたら余程無理のない設計であったろう。この50mmの差と言うのは偶然にも誉とMK9Aとの差と一致しているのは皮肉である。ちなみに、悲劇の発動機「誉」と言う本では、元エンジン技術者であった著者が、誉はアメリカで良い材料などを使用して生産されていれば優秀な性能を発揮していたはずだ、と言う神話を否定して、そもそも開発目標の設定に無理があったことを論証している。
*零戦、堀越二郎・奥宮正武共著・朝日ソノラマ
**世界の傑作機NO.23、文林堂
⑥隼の3本桁神話
旧陸海軍の日本機には神話と言うべき不可解なものが航空関係誌などに流布されている。そのひとつが1式戦闘機隼の3本桁である。隼は当初より胴体機銃しか装備していなかった。後年武装強化しようとしたが、主翼が3本桁構造であるため、主翼内機銃の装備をあきらめたというのだ。私にはこの説明はどうしても理解不能なのだ。桁に機銃の機関部や銃身を貫通させる穴を開けなければならない、と言うのならどの翼内機銃装備の場合でも行っていることである。それが3本桁だとどうして不可能になるのか分からないのである。雷電などは単桁構造なので21型以降では、片方の主桁に2つの機関砲が装備されていて大きな機関部が主桁を貫通している。しかも雷電の20mm機関砲に対して、12.7mm機銃とずっと小型であり、雷電は高速を狙った薄翼である。主桁の断面性能に対する影響は大きい。紫電も同様である。紫電も雷電も初期型は主翼に片側1挺づつだったのに2挺に増やしたから、主桁に更に孔を開け、補強したのである。やればできるのである。
恐らく隼の後桁には穴を開けずに済むだろうし、前桁は細い銃身が貫通するだけだろう。1本しかない桁に大きな穴を開けるのに比べれば3本に分散されるだけ各々の桁への負担は少ない。もちろん当初なかったものを装備するのだから、補強や骨組構造の一部の変更はあり、重量は増加するであろう。私には単に設計変更の手間を嫌ったのに過ぎないとしか考えられない。そもそも機銃が貫通するために桁の断面の一部を切断するから改造できないというのなら、艦上機の折りたたみ式の主翼は完全に主翼全部が切断されている。それでも翼を展張した時には翼をピンで結合すれば済んでいるのである。もちろん切断部を補強するから重量は増加する。しかしそれでもグラマンの戦闘機などは折りたたんだ状態をコンパクトにするために翼付け根で折りたたんでいる。日本機は重量の増加を嫌ってできるだけ翼端の近くで折りたたむ。それだけの事なのである。陸軍では三式、四式、五式戦と比較的順調に後継機を開発できたため、いまさら隼に手間をかけるのは最小限にしようとした、というのは妥当な判断であると思う。零戦が後継機がなかなか得られずに武装強化を繰り返し、金星エンジンへの換装も行ったのに対して、隼が金星系エンジンへの換装計画を放棄したのも同じ事情であろう。
それでなくても戦前戦中に限らず日本の兵器は大きな改造をして性能向上するよりも、新規設計することを好む傾向が強い。彗星や五式戦が空冷エンジンに換装したのは大改造ではあるが、性能向上のためではなく、エンジンが使い物にならなくなってしまったためである。余談であるが、五式戦への改造は新規製造でなく既に完成しているエンジンなしの機体に空冷エンジンを搭載する、という芸当が他にあまり例をみない困難なものである。土井武夫技師が堀越技師について、昭和十七年の時点で金星への改造打診を断ったことを批判しているのは、自分がそれより余程困難な事をやってのけた自負もあったのだと思う。
日本製の兵器はぎりぎりに設計されているので設計変更の余地が無い、と言う風説は間違いである。改造して性能向上する合理性に対する判断が無いのである。意志が無いのである。ドイツのMe109は千馬力未満の小型軽量でぎりぎりに設計された機体であるが、終戦まで二千馬力クラスのエンジンまで搭載して性能向上を続けた。スピットフアイヤも同様である。Me109もスピットフアイヤもF6Fのような贅肉の多い構造ではなく、ぎりぎりに設計された軽量の機体であるし、主翼内の構造も必要に応じて大幅な変更をしている。両機の登場は九六式艦戦や九七戦と大して変わらないのである。自衛隊の九〇式戦車はレオバルトⅡ戦車よりずっと遅く作られたのに、レオバルトⅡが未だに性能向上を続けているのに対して、もはや一〇式戦車に変わろうとしている。「日本の兵器ゆとりのない」論者の意見と異なり、九〇式戦車は大柄で改造のゆとりがあるはずなのに何故か改造を放棄して一〇式戦車を開発した。一〇式戦車は九〇式より小型軽量なのである。
九〇式戦車は大型で北海道でしか使えない、などと言う説があるようで、これに某雑誌が反論したが正しいのであろう。そもそもこのような説は素人の私にさえ不可解である。本州では九〇式より小型の戦車しか使えないのなら、日本に上陸して戦おうとする軍隊は九〇式より小型の戦車しか持ってこられないという奇妙な事になるのではないか。このように日本の兵器には、今でも合理性のない神話がまことしやかにまかり通っている。
⑦遅働信管の罪
兵頭二十八氏の「日本海軍の爆弾」によれば、米海軍の使用した艦爆の信管は遅延時間0.01秒という極めて短いものを多用していたのは、米海軍は空母による攻撃に、敵艦の撃沈を期待していなかったからだと推定している。これは爆弾が命中してすぐに爆発するので破壊効果は大きいが、逆に艦底深くまで到達することはないから、沈没させることは困難であろうと言うのである。日本海軍は、0.03秒、0.1秒、0.2秒の三種類の信管を持っていたが、最も遅い0.2秒のものを好んで使用していた。これは米海軍とは逆に艦船の撃沈を期待したからだと言う。しかも装甲貫徹を期待して炸薬量を減らして弾体を厚くしたと言う。そのため、米海軍の1,000ポンド(約450kg)爆弾の炸薬量は、日本海軍の250kg爆弾の2~4倍はある、というのだ。その反面、米軍の爆弾の弾体は強度の高い鋼材を使っていたと言うから、装甲貫徹効果もどちらが優れているかは判然としない。
そもそも、戦艦の主要装甲が急降下爆撃で貫徹するはずもない。真珠湾攻撃で戦艦の装甲を貫徹させるために日本海軍は40cm砲弾を改造したものを水平爆撃に使用した。ここまでは兵頭氏の説を紹介しただけである。私には兵頭氏の示した爆弾の遅延時間の数値で以前から想像していたことが間違っていなかったことが分かったのである。例えば以前書評で紹介した「我敵艦ニ突入ス」の記述である。零戦が体当たりしたときに、衝突する側の舷側にいた駆逐艦の乗組員の中には爆発を避けるために反対側に走っていったら、爆弾が船体を突き破ってから爆発したために、かえって被害を受けてしまった、というのである。
特攻の記録を読むと、このように爆弾が船体を貫通して船体の外で爆発したと言う記録がかなりある。このことを、徹甲爆弾を使用したために、薄い装甲の駆逐艦では、すぐに爆発しなかった、と説明したものを見たことがある。この説明はおかしいのである。装甲が薄いから信管が作動しなかった、という説明なら分かる。だが装甲が薄かろうと、爆発した以上は信管は衝突時に作動したのである。作動した以上は、爆発のタイミングは信管の遅延時間で決まる。例えば速度300km/hで爆弾が進むと、0.2秒の間には約16.7mも進む。駆逐艦の船体幅は10m程度だから、船体内で爆発しなくて当然なのである。ちなみに米軍の0.01秒の遅延時間なら、わずか80cm程度で爆発する。桜花が撃沈した、駆逐艦マナート・L・エベールの場合は、機関部などの鉄の塊の多い部分を貫通したために爆弾が減速されたのであろう。
このことから分かるのは、信管の遅延時間が長いために、せっかく体当たりに成功しても効果が少なかった例がかなりあったと思われるのである。特攻機は戦艦や巡洋艦に体当たりできた例は少なく、ほとんどがレーダーピケットの駆逐艦であった。空母にもかなりの数が体当たりに成功して戦果を上げている。レーダーピケットは特攻機を吸収する目的で配置されていたから当然であるが、空母への体当たりに成功したのは、目標としていたばかりではなく、対空火器が貧弱だったのも原因しているように思われる。
特攻隊員の心情からすれば、駆逐艦などではなく、戦艦や空母などの大きな相手と刺し違えたい、というのは当然であろう。だが結果論ではあるが、遅延時間の短い信管と炸薬量の多い爆弾を使用した方が効果があったと言わざるを得ない。米軍は艦船の沈没よりも兵士の損耗を恐れていたから、殺傷効果が大きいことが効果的であったから、なおさらであろう。
⑧弱くない一式陸攻
一式陸攻すなわち一式陸上攻撃機と言えば、一式ライターと味方からも揶揄され、脆弱で攻撃に弱い日本機の典型とされている。しかし「我敵艦ニ突入ス」というある特攻機のパイロットを特定しようとする本に、米駆逐艦長の意外な戦闘報告書の記述がある。
一式陸攻はいい飛行機で、かなりの攻撃に耐えられるように頑丈にできている。命中しても、九七艦攻のように簡単に爆発したり火災を起こさない。空母攻撃終了後ベティーが一機帰還中、友軍機から何度も機銃掃射を受けたが、まったく被害を受けた様子はなかった。友軍機は最後には諦めてしまった。(P63)
何と被弾に弱いとされた一式陸攻が、いくら攻撃を受けても落ちなかったというのだ。かの本の著者も、一式陸攻が日本海軍では燃えやすいという評価をしていると書いている。著者はその理由を乗艦のファイヤコントロールシステムに不具合があったことを大きな原因にしている。しかし艦長の目撃したのは自艦による対空射撃ばかりではなく、いくら戦闘機に打たれても撃墜されず、戦闘機が諦めてしまうほどタフな様子もあったのだから、必ずしもファイアコントロールシステムばかりが原因とは言えないのは明らかである。
実は「歴史群像」太平洋戦争シリーズの「帝国海軍一式陸攻」という本には、一式陸攻が同じ条件でのドイツ空軍の爆撃機などと比較して、必ずしも損耗率が高いとは言えないこと、九六陸攻の戦訓から、燃料タンクの防弾が要求されており、不完全ながら初期型から防弾ゴムが使用されており、最後まで改善の努力が続けられていったことを資料によって明らかにしている。傑作なのは、パソコンゲームのデザインのアドバイザーとなった海兵隊の元パイロットが、一式陸攻について、優秀な防御力を持つようにゲームをデザインさせているのだが、その理由を「一式陸攻は決して脆い機体ではないからだよ」、と述べている。彼はガダルカナルで日本機と戦ったエースだから真実味がある。
一式陸攻が防御力の弱い機体である、とされたのは何故だろう。この本にも示唆されているのだが、被害率が高いのは対艦攻撃の時である。一式陸攻は対艦攻撃に雷撃を主としたから被害が大きいのである。雷撃は1,000m以内に肉薄し、雷撃コースでは直進したから被弾しやすい。その上に大型機だから命中率は高い。さらに別項で述べたように、米海軍の火器管制システムは日本軍のものに比べて格段に優秀である。特に日本海軍は陸攻を雷撃に重用したから、被弾に弱いとパイロットが嘆いたのも当然であろう。
B-17には雷撃装備がなかったから、高高度から艦船爆撃を行ったが、輸送船はともかく軍艦にはあまり通用しなかった。日本海軍が大型機にまで雷撃装備をしたのは、正しい選択ではなかった。日本海軍が大型機に雷装をしたのは、敵艦上機の行動半径外から敵主力艦に雷撃をするためであった。航続距離をかせぐために大型機にならざるを得なかった。しかしそのために、被弾率を高めて有効な攻撃をし得なくなったのだから、日本海軍の方針は元々矛盾を抱えていたのである。
この本には高高度性能が優秀で、P-40などでは高高度から飛来する一式陸攻は迎撃困難であると書かれている。他の本でも九九双発軽爆や一式陸攻は高高度性能が優れており、特に爆弾投下後高高度で飛び去ると米軍機は迎撃できない、という記述がある。これも考えてみれば当然で、ターボ過給機がついていない機体で比較すれば、日本機は翼面荷重が低いから高高度性能が優れている。
ちなみに一式陸攻の実用上昇限度は各型で8,950~9,220mである。アブロ・ランカスターMkⅠは7,467m、B-26Bは7,163m、A-20Cは7,718mであり、いずれも一式陸攻より1,000m以上実用上昇限度が低い。甚だしいのはブレニムで、MkⅠが一式陸攻なみに9,144mであるのに、MkⅣでは6,706mにも低下している。ターボ過給機が付いたB-24はD型がさすがに9,754mであるのに、J型では8,534mに低下している。
B-17Gは、11,015mで優れている。欧米機のデータの出所は、全てsquadron/signal publicationsのin actionシリーズである。ただB-17だけが上昇限度を、Ceilingと書いているのに対して他は正確にService ceilingと書いてあるのが気になる。実用上昇限度はService ceilingと訳されるのに対して、Ceilingだけでは絶対上昇限度かもしれないのである。またEFGの全ての型の全備重量が全く同じなのは明らかな間違いであるのでデータの信頼性に疑問がもたれる。いずれにしてもB-17の実用上昇限度は11000m程度あるのであろう。少々脱線したが一式陸攻はターボ過給機なしでは、欧米の爆撃機より高高度性能が優れているのは間違いないようである。
一式陸攻がタフである、という点には私にはもうひとつの要素があると思われる。一式陸攻は大型機の割には舵の効きがいいと言われている。これは同じメンバーにより設計された陸軍の四式重爆も同様で、垣根超え飛行ができると言われる位、軽快な舵を持っていた。超低空での運動性能がいい場合には、機体強度が高くなければならない。つまり機体が頑丈である。従って被弾したり炎上しても、構造部材が破壊して墜落することは少なかったのであろう。この点もタフだと言う評価につながる。
この点で想起されるのはB-24とB-17の相違である。B-24は被弾炎上して主翼がボッキリ折れる悲惨な記録映像があるが、B-17はそんなことはなかったそうである。これは構造の強度上の差異である。これがB-17が防弾だけではなく機体がタフである、という評価につながり、搭乗員に信頼されたと言われている。一式陸攻のタフさもこれに類似しているものと思われる。大戦末期になると、援護戦闘機も少なく、米側の防空陣も圧倒的であったから、一式陸攻の攻撃に被害が大きいのは当然である。ちなみにB-25などによる、機首の機銃を乱射しながらの反跳爆撃などは防空能力が極めて低い日本の艦船には通用しても、米艦隊には返り討ちにあうだけで通用しなかったであろう。
⑨零戦はギリギリに設計されているため発展性がなかったという神話
一般に、第二次大戦当時の日本の軍用機、特に戦闘機はぎりぎりまで切り詰めて設計されて余裕がないため、改良発展の余地がなかったと言われる。例えば零戦が十二試艦戦の時の瑞星を除き、栄系統のエンジンで通し、沢山の型を生産した割にはエンジン出力も最大速度もたいして向上していないことについて、多くの本が、ギリギリに設計されているので発展性がなかったからだ、とコメントしている。それは本当のことだろうか。
飛行機の機体は、空気力学上の要素を除けば設計上は構造物である。構造物として考えたとき、ギリギリに設計されていた、と言うのはどういう意味だろうか。構造設計の考え方のうち応力について概観してみよう。構造物は、発生する応力が許容応力以下であることが必要である。応力とは、荷重により物体内部に発生する力を単位面積当たりの力(N/m2)で表わしたものである。許容応力とは、材料が設計上許容できる応力だから、だから計算上発生する応力は許容応力以下でなければならない。許容応力は材料の種類と設計対象の構造物の種類によって技術基準等によって決められている。
最も良い構造設計は、発生する応力が許容応力に等しいことであると考えられるが、構造物は複雑な構造をしていることや、他の要素もあるので、全ての部材をそのようにすることは現実的には不可能である。しかし一般的にギリギリの構造設計をする、というのは応力の観点からいえば、できるだけ多くの部材の応力を許容応力に近くする、と言うことである。構造設計上の応力の観点からは、できるだけ多くの部材の応力を許容応力に近くする、と言う努力をしない設計者、というのはありえない。与えられたエンジンと設計仕様に対して、構造設計上ギリギリの設計をするのは当然のことなのである。
零戦よりよほど設計が古く、最後まで改良され続けたドイツのMe109や英国のスピットファイアは構造上ギリギリの設計をしていなかったから、改良が続けられたのであろうか。もちろんそうではない。改良によって重量が増加すれば、それに見合った強度となるように部材の厚さを増やすなどの設計変更をしているのである。両機とも、将来の改良をみこんで、計算上の応力が許容応力を大きく下回るような「ゆとりのある」設計をするはずがない。そんな設計者は設計者失格である。
機体設計上のゆとりのもう一点はエンジン出力に対する機体のサイズ、と言うものがある。簡単に言えば、重量と寸法の小さい機体に過大な出力のエンジンを積めば、トルクにより機体が振り回されてしまう。十二試艦戦は全幅12m、全長8.79m、自重1.65t、全備重量2.34tである。Me109の試作一号機は全幅9.87m、全長8.58m、自重1.5t、全備重量1.9tである。寸法も重量も零戦の方が大きいのである。Me109はエンジントルクの影響を解消するために、垂直尾翼の断面を非対称にしている。他にもそのような例はあるが、Me109の場合は高性能をねらってエンジンサイズに比べ機体サイズを切り詰めた結果によるものであると考えられる。つまり機体の大きさから言えば、Me109は零戦よりゆとりがないギリギリの設計なのである。それにも拘わらず、原型1号機から最終型に至るまで、大幅なパワーアップをしている。
著書による限り、設計者の堀越技師自身は零戦はギリギリに設計されていたため発展性がなかったとは言ってはいない。それどころか「零戦」(朝日ソノラマ昭和五十年版)で「・・・最後型となった五四型丙は二年も早く生まれ、恐らくはその後もさらに改良されて、零戦は依然としてその高性能を誇っていたかもしれない。」(P262)と書いている。これは昭和十七年に海軍に金星エンジンへの換装の指摘打診を受けた際に応じていれば、五二型が登場したのと同じ昭和十八年に大幅に出力向上した高性能の機体が出来ていたはずだと言っているのである。
同じ著書で「・・・たとえば金星換装などは外国人、特にスピードの速いアメリカ人には余りにも遅かったように見えたようであるが、これを、日本は外国の模倣ばかりしていたから戦争のために外国の資料が入らなくなるとよい知恵が出ない、とするには当たらない。・・・これを一口にいえば、日本の産業の規模が全般的には世界一流の水準からは遠い状態にあったということである。・・・経験ある技術者の過小とも重なって、着想から実験、設計、試作、実用に至るまで非常に時間がかかった。」と言っている。機体がギリギリに設計されていたから改良できる余地がない、とは考えてはいなかったのである。
早期の私的打診応じることができなかったのは、堀越技師が過労で倒れる位忙しかったからである。それは日本航空工業一般の基盤の貧弱さによることがあるかもしれないが、三菱の設計体制の非効率によるものである、という説もある。いずれにしても種々の要因が重なったのであろう。今となっては判然としないが、昔の雑誌で、零戦に誉エンジンを積むことはできなかったのですか、という質問に、堀越技師が、できた、と答えたのを読んだ記憶がある。これが小生の記憶違いであるにしても設計上は可能だったのである。もちろん主翼の再設計まですることになったのかも知れないが、誉がまともなエンジンであれば大幅な性能向上が期待できたであろう。現実には烈風にさえ零戦五二型丙なみの低い翼面荷重を要求する海軍は受け入れなかったのに違いはないのだが。
さらに言えば、スピットファイアにしても、Me109にしても改造を続けられた大きな要因は、設計当初から構造設計の形式に変化がなかったからである。全く新規に設計し直したところで桁構造形式などは同一のものとなることから飛躍的な性能向上が期待できないことから、新設計することと、改造でいくことを考えた場合、冶具など過去の生産設備を流用できるメリットの方が大きかったのである。
⑩沈頭鋲の無駄
風立ちぬは見ていないが、堀越二郎技師の九試単戦を語るときに必ず話題になるのが、最新技術であった沈頭鋲の採用である。通常のリベットは機体外板の外に頭が飛び出すが、沈頭鋲はこれがないから表面摩擦抵抗が減る、という訳である。ところが以前、鹿屋の自衛隊基地見学に行って対潜哨戒機のP2-Jを見て驚いた。確かに機体の前半は沈頭鋲で滑らかに仕上げられている。しかし後半部はリベットの頭が飛び出してごつごつしている。インターネットでダウンロードした下の写真を見ればおよそ見当がつくと思う。実物はもっとでこぼこの印象であった。


そこで気付いたのだが、物体の表面を空気が流れるときは、境界層という空気の流れが遅くなる部分がある。境界層の厚さは条件によって異なる。機体の後半のように、内側に湾曲している場合には厚くなる傾向にある。一生懸命平滑にしても、沈頭鋲は流速が遅い境界層に埋もれるから、抵抗の減少にほとんど寄与しなくなるとこの設計者は気付いたのである。沈頭鋲は工数がかかる。つまりP2の設計者は性能を低下させることなく、コストを縮減したのである。もちろんこのような効果は、どんな条件の機体設計にも一般的にに成り立つ訳ではない。
戦中の日本の陸海軍の航空技術者は米国の航空機は設計が大雑把だと、批判するむきが多い。しかしこの例のように、米国製の航空機はデリケートな配慮がなされていることに気付かされることが多い。世界の傑作機シリーズに航空技術論を執筆している鳥養鶴雄氏はよくそのことを指摘してくれているが、戦前の日本機に関してはそのような的確な航空評論は案外少ない。
⑪艦上機の機能分化は日本海軍の先見
英海軍は複座の艦上戦闘機あるいは、艦上戦闘爆撃機なる珍機種を次々と開発した。あるいは、ファイアブランドなる巨大な艦上戦闘機を開発した。これは戦闘機としては使い物にならず、結局雷撃機や艦爆として使われたが、単座なので中途半端であった。根本的には設計思想の混乱や、他機種からの転用が原因である。しかし、屁理屈をこねられないでもない。空母に搭載できる艦上機の数は限られている。すると、制空、雷撃、急降下爆撃、偵察などの各機能をできるだけ兼用した方が良い、と言えないこともない。
ところが、戦闘機を雷撃あるいは急降下爆撃と兼用した結果は、戦闘機としては使い物にならない、ということであった。対戦闘機の空中戦で到底勝てるしろものではなかったのである。もちろん、雷撃あるいは爆撃の用途としても使いにくかった。
日本海軍はその正反対をいった。つまり、艦上機は陸上機より制約が多いから、陸上機より全般的に劣る結果となる。それを陸上機に近づけるためには、機種を用途別に細分化させる、というものであった。この結果、艦上偵察機、という例の少ない機種さえ作った。日本海軍に近い考え方の米海軍でさえ、偵察任務は艦爆に兼用させていた。日米海軍の艦上機開発の思想はシンプルで一貫して混乱が無い。
英海軍は中途半端な艦上機を開発して混乱し、米国製の艦上機を使わざるを得なくなったのである。さらに、日米海軍は開発や運用にも適材適所で柔軟であった。彗星艦爆の試作機が高速を発揮すると、二式艦偵として採用する一方で、彩雲艦偵も開発した。大戦末期には、艦攻と艦爆を兼用する流星を開発した。米海軍は、ジェット機時代では、ビジランティ艦攻が核攻撃機としても、戦術攻撃機としても中途半端なことが分かると、早々と艦偵に切り替えて活用したし、F-18は攻撃任務も兼用させてF/A-18として使っている。
⑫航空ガソリンのオクタン価
ある記事で、大東亜戦争中、日本海軍は92オクタンで陸軍は87オクタンのガソリンを使っていたと書かれていた。だから同一エンジンを使った隼が零戦より最大速度が遅かったのは、これが原因であるというのだが、オクタン価の差があるなら可能性はある。
しかし誉エンジンは100オクタンを前提に設計されていたとされる。誉を搭載した疾風にも、87オクタンの燃料を使ったのであろうか。そうならブースト圧なり回転数に大幅な制限が加えられていたはずである。するとエンジンの性能は大幅に低下するのは当然である。このことを論じた記事を見ないから小生には実態は不明である。
既にご存じだと思うが、一部の人に誤解があるかも知れないので再度言うが、87オクタン用に設計したエンジンに、100オクタンのハイオクガソリンを使っても、性能が良くなることは一般的にはあり得ない。100オクタン用に設計したエンジンでなければ100オクタンのガソリンを使っても無駄なのである。100オクタンでも87オクタンでも、ガソリンの単位重量当たりの発熱量は同じだから、低オクタンでもハイオクでも、発生エネルギー量自体は変わらないからである。逆に100オクタンで設計されたエンジンに、87オクタンのガソリンを使用すると、前述のように使用制限をしなければならず、本来の性能を発揮できない。
オクタン価とは、燃料のアンチノック性能、すなわちノッキングを起こしにくい程度をいう。ある燃料のノッキングを起こす圧縮比が同一の、ノルマル・ヘプタンとイソ・オクタンの混合比燃料の、イソ・オクタンの比率である。87オクタンと言えば、イソ・オクタンが87%の燃料と同じ、アンチノック性能を持つ燃料を言う。細かい説明は省きごく単純化して言えば、オクタン価が高ければ、例えば高圧縮比のエンジンを設計できるから、小型で高馬力を発揮できるのである。
戦後米軍が、140オクタンのガソリンで日本の軍用機をテストした、という記事が散見されるが、先のオクタン価の定義からすれば、厳密には140オクタンと言うガソリンは存在しない。正確には、パーフォーマンスナンバーと言うが、慣例的にオクタン価と言っているのである。前述のように誉が100オクタンで設計されているとすれば、100オクタンをどれほど超えた燃料を使っても、性能は基本的には、100オクタンの場合と変わらない。ちなみに、同じレシプロエンジンでも、オクタン価はガソリンエンジンにしか適用されず、ディーゼルエンジンはセタン価を使う。
冒頭に簡単に海軍92オクタン、陸軍87オクタンという記事を紹介したが、これは正確ではないのに違いない。時期による変化もあろうし、いくら、補給を単純にするといっても、戦闘機と練習機に同じオクタン価のガソリンを使うのは、コスト面でよろしくないだろう。戦闘機のうちでも誉と栄エンジンでは燃料に要求されるオクタン価が異なる。この辺り陸海軍の運用の実態を正確に示した資料を入手したいと思う次第である。
ひとつだけ見つけたのが、林譲治氏の「太平洋戦争のロジスティクス」である。P109には、海軍の昭和13年から昭和16年までの各年ごとの「航空燃料所要量」と「航空機と使用燃料」が掲載されており、これが旧日本軍の航空燃料に関して、小生が知る最も詳しいものである。燃料の種類は100オクタン、95~92オクタン、87~85オクタンに分けられている。そして各年ごとに「航空燃料所要量」には燃料の量が「航空機と使用燃料」には各オクタン価ごとに、使用機種として陸攻、艦戦、飛行艇、などと機種ごとに使用区分が示されている貴重なものである。意外だったのが100オクタン燃料があることである。
残念ながら開戦後のデータと陸軍のデータがない。所要量は年を追うごとに高オクタン燃料の比率が増えているから、これは生産量ではなく文字通り必要量なのかも知れない。また同じ機種でも、同一オクタン価だけとは限らないから、エンジンの設計に合わせているのだろう。
⑬ヘルダイバーの要求仕様の無茶
米海軍の艦爆SB2Cヘルダイバーは、12.19m×13.72mのエレベータに2機搭載できるように、主翼を折りたたんだときの全幅を5.18m以下にするという無茶な要求であった(世界の傑作機No.40による)。そこで全長が11.17mとなった。この数字は97艦攻、天山、九九艦爆、彗星などに比べて大きい数字であるが、全長不足による縦安定不良の改修に手間取った。
これは、前掲の日本機が、1トン前後も軽いことにより、問題が無かったのである。ちなみに最後の艦攻、流星は全長11.49mとヘルダイバーを超えているから納得できる。更に大型のアベンジャー雷撃機は全長12.48mもある。ところが多くの設計変更を加えた結果、量産機のヘルダイバーは折りたたみ時全幅6.94mと要求が無視されている。
無理して寸詰まりにして安定不良を起こした上に、エレベータに2機搭載すると言う要求も満たせなかったことになる。ここからは小生の推測だが、全幅が増えた原因はふたつある。アベンジャーは12.48mの全幅ながら6m以下と言う折りたたみ時の全幅を実現している。
それは、グラマン社得意の、折りたたみ部の主翼を一度90度回転させてから、後方へ折りたたむ機構だから、折りたたみ部の主翼幅が大きくても、全高は折りたたみ前の全高以下に収まるという優れものである。これに対してヘルダイバーはオーソドックスに折りたたみ部を上方に跳ね上げる方式である。一方で、主翼の試験結果から揚力係数不足が判明し、面積を4m2近く増やす羽目になってしまった。
すると、折りたたみ翼幅制限を守ろうとすると全高が高くなってしまって、格納庫内の高さ制限に収まらなくなってしまったので、折りたたみ時の翼幅制限を解除せざるを得なくなったと言うストーリーが成り立つ。安定の改修などに相当な時間をかけているので、実際にはこんなに単純に時系列を追って進んでいたわけではあるまい。しかし、原因としてはおおむね、こんなところであったと思う。
米海軍の無体な要求から、実用化が大幅に遅れることになってしまったが、結局はドーントレス艦爆の後継として量産されて活躍したのだから、結果オーライなのであろう。小生も日本陸海軍の航空行政批判は多くしているが、どこの世界にも、そのような無体はあるもので、心して批判しなければならないと思う次第である。小生はヘルダイバーのバランスの悪い寸詰まりのスタイルは実は好きなのである。もっとも、大和を始めとする日本海軍艦船を多数沈めた、にっくき奴ではある。
⑭堀越先生から習ったのは飛行機の重量だけ
平成22年11月5日の日経新聞に、三菱重工相談役(当時)の西岡喬氏が「私の履歴書」に、東大航空科時代の想い出を書いている。その中に有名な零戦設計者の、堀越次郎氏の教師としての想い出を書いている。教授メンバーは守屋冨次郎氏の他にもそうそうたる人たちが揃っているのだが、西岡氏の語る堀越氏の授業は異色である。
「習ったのは最初から最後まで重量についてだけだった。・・・週一回の講義に見えては、グラム単位で、主翼など機体の重量や重心の計算ばかりする。」というのだ。
堀越氏の言葉で「航空機は重量が命だ。小数点以下まで細かく計算をしなくてはだめだ」というのを今でも覚えているそうだ。防大で堀越氏から授業を受けた人も、全く同じように、重量計算だけやらされた、と証言していたのを読んだ記憶があるから、どこで教えても同じだったのだろう。
堀越氏の授業を受けた両氏とも、尊敬している風なのだ。しかし、いくら重量軽減が大切だから、と言って重量計算だけしかしない、というのは余りに偏頗ではなかろうか。堀越氏らの世代は、戦後の日本人航空技術者と違い、何機もの航空機の設計の主務をした貴重な経験を持つ。その経験から、若い技術者の卵に教えることのできることは、重量以外にもいくらでもあるのではないか。余りにもったいない気がするのである。
⑮体当り専用機ではなかったキ-115
48のプラモのキ-115(剣)を作った時、意外なことを知った。モデルアートのエデュアルドの製作記事である。執筆者は加藤寛之氏であった。記事には「主任設計者の青木邦弘氏によれば、剣はロケット噴射で加速して離陸し、脚は投下してしまう。身軽となった機体で沿岸に押し寄せる敵艦艇へ投弾、引き返して胴体着陸する。操縦者は生還し、エンジンは再利用する構想だったという。その証拠に、調布に残された機体には爆弾投下安全弁が付いていたことが確認されている。製作から審査の時点になると、剣は体当り攻撃機となっていた。」とある。
日本航空機総集など既存の資料には、知る限り全て体当り専用機と書かれている。機体自体が脚投下式などを含めて全体的に簡素なものだから、素直に信じていた。しかしこの記事によれば、少なくとも計画設計時点では、体当り専用機ではなかったというのである。そこで記事の青木邦弘氏の本を探すと「中島戦闘機設計者の回想」と言う本が図書館の蔵書にあった。
青木氏は明治43年生まれで、本書は1999年に刊行されているから、かなりのご高齢になられてからの執筆である。それによれば、剣の開発の着想は、キ-87のようなまともで高級なものは、あの時点では戦争に間に合わないので、簡易に作れる小型爆撃機を作ろう、ということにあった。(P181)
戦闘機ではなく、「・・・上陸用舟艇のどまん中に瞬発信管付きの大型爆弾を放り込むだけでいい。・・・命中させる必要はない。・・・転覆させたり衝突させる効果をあげて、大混乱を引き起こすことができればよい。・・・操縦者の生還率も高いだろうし、機体の回収もできて反復して使用可能となる」飛行機である。
引込脚は設計製作に時間がかかるので、投下式にして、胴体着陸すれば、最低限製造に手間のかかるエンジンだけ再使用できればよいというのである。そこで小生に疑問が起きた。オイルクーラの位置である。剣のオイルクーラは、疾風のように胴体の真下になく、右舷側それもかなり高い位置に偏って取り付けられている。胴体着陸する構想だと読んだとき、これは胴体着陸の際の地面との抵抗を減らすためではないかと思ったのである。
完成した剣の模型を見たら間違いだと分かった。疾風のように真下に付けると、爆弾の位置と干渉するのである。それでも胴体着陸の抵抗を減らす効果は幾分かあり、うまくするとオイルクーラを破損せずに回収できるのかもしれないが、青木氏の著書にはそのような記述はない。
剣はかなりの意味で中島の自主開発に近いらしく、隼のエンジン400台あまりが、倉庫に埃をかぶっていると聞き、青木氏はゴーサインをだした。(P187)試作機が完成すると軍民関係者で安全祈願式をしたが、祝詞に「・・・往きて還ざる天翔ける奇しき器」という一句があったので、軍民関係者が数百人居並ぶ中で青木氏は「・・・本機は特攻機として造ったものではありません」と訂正したが、反論もなく儀式は進んだという。
神主さんは徴用で中島の工場で働いたことがあり、戦闘機に比べ粗末なつくりのため、皆が特攻機ではないかと噂したのを聞いて、祝詞に入れたのだと判明したと言う。奇妙なことに設計主任の青木氏が試作仕様書を見た記憶がないと言う。ところが軍に提出した計画説明書を米軍のために簡略にまとめたものが、戦後かなりたってからみつかって、読み返したところ、計画書の「型式機種」は「単発単座爆撃機」で、「任務」は「船舶の爆撃に任ず」とあり、軍艦相手とは書いていない。
また「主脚は工作困難な引込式を排し、かつ性能の低下をきたさないように投下式とし、着陸は胴体着陸とし人命の全きを期す」(P195)と書いてあった。また説明書原文には「・・・速度の遅い旧式機では操縦者の生還は期し難い・・・せめてそれに代わる飛行機として本機を作る・・・」と書いた記憶があるそうである。
剣の審査官だった陸軍将校に戦後会うと、審査報告書に「本機は爆撃機としては不適当と認む」として提出したので使われたことはあり得ない、と語った。それにしても甲型だけでも105機も作られたから、使うつもりがあったと誤解されても仕方あるまい。青木氏によるとこのころは軍も中島も相当混乱していたということだから、生産だけが進んでしまった、ということはあり得る。剣の乙型のことを肝心の青木氏は全く知らず、戦後の文献で知ったという混乱ぶりである。また相当数が生産され実戦参加した、キ-100やキ-102乙が採用手続きもなされず、制式名称もなかった時期だから。
また「戦後の文献によると、キ-一一五は昭和二十年一月二十日に『特殊攻撃機』という名称で試作命令が出されていたことになって」いたから、特攻機と言われたひとつの理由であろう、としている。なるほどと納得する次第である。だがモデルアート誌の記事のように「製作から審査の時点になると、剣は体当り攻撃機となっていた。」ということは、青木氏の著書には書かれていない。
ただ、青木氏も隼なども特攻機として使われたのは「『特攻機』という言葉は用兵上の用語で、航空技術用語には」なく隼や疾風なども特攻機として使われたのは用兵上の結果であり、製造した時点で特攻を予定していたのではない、と述べている。だから設計側も軍も作るときは予定していなかったとしても、本土決戦が行われていれば、剣が特攻機として使われていた可能性は否定できない、ということになる。
なお海軍の最初のジェット機の橘花も「特殊攻撃機」として爆装も予定されていたから、特攻機に使用予定であったとする記事も散見するが、青木氏の論理から言うと、設計製造に手間がかかる高級なジェットエンジンを一回限りの特攻の計画で作ることはあるまい。これとて実際にどう使われるか、ということとは別問題ではある。また剣が体当り専用機として設計製造されていなかったと主張するのは、剣の計画の道義的是非を言うのではなく、事実関係をいうのである。
⑯雷電と彩雲の設計思想の相違
世界の傑作機No.108「彩雲」で鳥養鶴雄氏が書いているが、海軍航空技術廠では、胴体やナセルの形状は全長の40%付近に最大断面を置くことが、空気抵抗を最小にする、という研究報告がなされて、一式陸攻、雷電、烈風らの三菱機がこの理論を採用したのだという。雷電、烈風などは、この理論によりエンジンの最大直系位置よりずっと後方で、胴体の最大幅を最大としている。特に雷電では胴体幅とエンジン直径の差は顕著である。
ところが、中島の彩雲は、この理論を採用せず、胴体最大幅をエンジン部に設定してそのまま後方の胴体も同じ幅としている。一般に海軍の技術陣は民間会社に対して自信を持っていて、陸軍より持論を民間会社に強制する場合が多いとされるが、この例を見れば、民間の設計陣が独自の技術的信念を持っていれば、海軍技術陣も受け入れたのだ、ということが分かる。
雷電などの場合は、単に設計者が、データに基づく航空技術廠の研究成果を信頼したのだということが分かる。もちろん堀越技師が海軍のデータを信頼したのは当然である。一式陸攻の場合は、胴体内に魚雷を収容することを要求されたために、胴体の全長の40%付近に最大断面積を置くことに、さほど無理はない。雷電の場合には、元々採用エンジンの直径が、出力に比べて大きいので、この理論で抵抗減少を図ろうとする意図は分かるのだが、元々小直径の誉系統を採用した烈風の場合には、別な事情があったのだと小生は推測した。
堀越技師は海軍の指定した誉の性能に信頼を置いておらず、いずれ直系が大きく大出力の三菱製のMK9Aを採用することになるだろうと考えて、あえて太い胴体を採用しておいたのだろうと考えたのである。
これは邪推だった。胴体最大幅とエンジン直径の差は、誉装備のA7M1が170mmに対して、MK9Aを採用したA7M2でも120mmあり、疾風や零戦に比べ、いずれもずっと大きかったのである。ちなみに、この値はF6Fで152mm、コンパクト化したF8Fでも101mmある。F4Uはわずか29mmで、クリアランス径(エンジン外径とカウリング内側径の差であろう)に至っては、11mmと隙間のないものになっている。いかにF4Uの空力設計がシビアだったか分かる。
余談になるが、疾風でも幅の差は80mmある。誉は巷間、もう僅か何mmか直系を大きく設定すれば、設計にゆとりを持たせられ、信頼性も確保できたと言われる。しかし、疾風とF4Uの数値の差をみれば、誉の小直径化の設計努力は、機体設計によって無駄にされてしまったのではないかと思うのである。
また、エンジン直径が1218mmで、疾風の1180mmより大きいキ-100は、カウリング幅を切り詰めて、疾風の胴体最大幅1260mmに対して、1280mmと大差ないものとしている。
⑰零戦の優秀性はパイロットの技量
零戦の優秀性は、現代の日本国内では伝説化している様相がある。渡部昇一氏らの著書でも、零戦を日本刀に例えるなどして、優秀性を讃えている著述は多い。世界に残っている旧日本軍機の中でも数が多いだけあって、飛行可能な機体も複数あり、写真集も多く出版されていて人気も高い。
零戦は優秀ではなかった、とは言わないが、そこまで特筆して語る価値はなく、強いていえば、当時の日本の軍事航空技術の水準の象徴である、というのが正確ではなかろうか。堀越技師自身、米側からの事情聴取に、正直に欧米機の模倣もあると答えているそうである。当時の日本の技術水準全体からから言えば、不思議な話でも、隠すべき話でもない。
他方、零戦に対する米軍や他の連合国のパイロットの評価は、多くが陸軍の隼と混同されている。大戦初期の空冷エンジン装備の単発単座の日本戦闘機、特に隼の多くが識別の困難さから、零戦として記録されている場合がある。米軍パイロットの高い評価の中には、隼も入っている可能性が大きいのである。
旧海軍の奥宮正武氏などは、大東亜戦争では陸軍機は全く役に立たなかったごとき酷評をしているが、実態を反映していない偏見と言わざるを得ない。確かに洋上航法の訓練のなされていない、陸軍機パイロットは洋上戦闘では、足手まといの面があったにしても、大東亜戦争全般での評価としては妥当ではない。
梅本弘氏は「ビルマ航空戦」で、連合国側の記録との照合によって、陸軍機の意外な敢闘を証明している。結論から言えば、大東亜戦争初期の零戦を代表とする日本機の活躍は、多くがパイロットの練度の高さによる。日本陸海軍は大東亜戦争開戦時、既に支那事変で航空戦を経験していた。
加藤建夫、坂井三郎、岩本徹三の大東亜戦争で活躍した、陸海軍の高名な三人のパイロットは、全て支那事変で空戦を経験している。岩本は零戦を使っての、高空からの一撃離脱戦法を常用しているが、これは本人の性格によるところが大だろうが、支那事変で複葉戦闘機と戦った体験による影響もあるものと想像する。戦闘機ばかりではなく、攻撃機や爆撃機の搭乗員も同様に支那事変で経験を積んだ。
一方の連合国のうち、対日戦の主力だった米軍は、義勇軍(!?)と称して少数のパイロットが参加していただけだった。大東亜戦争初期の、米軍の魚雷に不良品と思われる故障が多かったのも、実戦経験のブランクによるものであろう。
このパイロットの実戦経験の差が、零戦に象徴される日本軍戦闘機の優秀性として現れていたのだった。ちなみに隼はかなり初期から防弾装備をしていて、他の陸軍機も同様で、防弾装備については、海軍機の方がかなり遅れていたことは、米海軍の報告書「日本の航空機」(雑誌「丸」に連載)によっても明らかである。
また、ミッドウェー海戦で、零戦は米雷撃機を次々と撃墜して、防空の任をよく果している。しかし、これは必ずしも米艦戦より、零戦が優れていた証明にはならない。大戦後半の米海軍と異なり、当時は攻撃隊における艦戦と艦爆、雷撃機などとの連携がうまくいっておらず、零戦に手もなく撃墜された雷撃機は、艦戦の援護がなく、裸同然で突っ込んでいたのは、記録を読めばすぐ分かる。むしろ、援護なしに日本艦隊に突撃していった雷撃機の敢闘精神には脱帽する。
逆に米艦戦の援護があった攻撃隊の被撃墜率は、ぐんと下がり米艦戦は援護の任務を十分に果たしている。ミッドウェーの艦隊防空戦での零戦の活躍は、パイロットの優秀さもあるが、それ以上に米軍の連携の悪さもあったのである。
大戦後半になると、米軍技術陣は防弾不足による抗堪性の劣る零戦より、隼の評価の方が高くなっていた、とさえ言われる。かつては、難しい空戦技術が必要のない米軍機に比べ、難しい技術を必要とする旋回戦闘を主とした日本軍戦闘機は、大戦後半になると性能差もあって、負けていった、と書籍に書かれていたものが多かったが、そんなものではない。
マクロにいえば、大戦後半では緒戦とは逆に、日米間のパイロットの飛行時間に大きな差が出てきた、というだけである。現に生き残った日本のベテランパイロットは、性能差が大きかったと言われる米軍機に対しても、良く闘っている。それどころか昔、旧日本軍機の設計技術者から「P-51の高性能は、何でも世界一を自慢したかった当時の、米国の国をあげての宣伝によるものだ」と直接聞いたことがある。
類似性能のエンジンを搭載した戦闘機の総合的能力は、よほど設計のまずさがない限り、格段の差が出るものではない。零戦とF4Fについてもこのことが言える。P-51は1400馬力クラスのエンジンで、700km/hを超える最大速度を出していることになっているが、これは、1400hpで出した性能ではなく、短時間の戦闘出力によるとしか考えられない。実際問題として、元々オーバーホール間隔が300時間程度しかなかった当時の軍用エンジンで、短時間の戦闘出力を使う、というのは非現実的な話ではないが。
不思議なことに、あれだけ速度性能差があるはずのP-47が、低空では隼より低速であったことは、米軍パイロットも認めている(世界の傑作機No.65)。P-51やP-47が低空で隼などに撃墜されている例について、遠距離を進出してきたために、帰投の燃料を節約して速度を落としていたので追いつかれた、と説明する向きがあるが、撃墜されてしまっては本も子もない。要するに実際に劣っていたのである。
また、戦闘機は最大速度で空戦するわけではないから、必ずしも最大速度の差が単純に優劣を決めるわけではない。現にF-14とF/A-18は最大速度に大きな差がある。にもかかわらず、F-14が早々とリタイヤして、F/A-18に置き換えられた理由は周知の通りである。いくら電子化により自動化されている現代戦闘機でも、パイロットの技量は空中戦勝利の必要最低限の条件である。もちろん第二次大戦機と現代の戦闘機に求められる資質には、相違があるが。
⑱高速水上機性能の不思議
戦前のある時期、世界速度記録を作るのに、水上機とする例が多かった。典型的なのはマッキMc72である。双フロートを抱えているのに、709km/hの世界速度記録を出している。これは、水上機にすれば、滑走路の長さ制限がないので、主翼を最小限にして抵抗を減らせると説明されている。何せ当時の陸上機の速度記録は、566km/hだというのだから、桁違いである。
つまり、当時なら陸上機より総合的に空気抵抗を減らせると称して、実証している。それならば、その後の引込脚の実用軍用機にはどうか、興味がある。日本では零戦から二式水戦が作られている。最大速度は533km/h/4550mから436km/h/4300mに減じている。82%の減である。
以下はモデルアートNo.387からの引用である。スピットファイアも水戦を試作している。MkⅤの場合は、598km/h/5978mが513km/h/5490mに減じている。85.8%減である。もう一つMkⅨでも試作している。資料によれば、649km/h~664km/h/5900mが619km/hに減じている。95.4%~93.2%という、低い低減率である。これらは武装削減の影響もあるとされている。
もしMkⅨが700km/h出していても、低減率は90%近い。いずれにしても、二式水戦に比べて、スピットファイアのフロートによる抵抗増加はかなり少ないと言わざるを得ない。
この場合、Mc72の例を考えれば、二式水戦、ひいては日本の水上機のフロートによる抵抗が大きすぎるように思われる。ちなみにMc72とスピットファイアなどの欧米系は全て双フロートであり、二式水戦も強風も高速を狙った水上戦闘機は単フロートである。これがどう影響しているのか分からないが、日本機の場合には水上の取廻しなどを考慮して、フロートが大きく、抵抗の増大に関係しているように思われるが判然としない。
いずれにしても、速度を上げるために水上機にしているケースがあったのと、フロートによる抵抗の増加に悩む日本機との差は不可解としか思われない。
⑲中島飛行機のプロペラ後流影響思想について
世界の傑作機シリーズNo.108艦上偵察機「彩雲」に尊敬する航空技術者の鳥養鶴雄氏が、中島飛行機の設計思想について次のように述べている。
中島の技術者は「・・・プロペラの後方にあるナセルや単発機の胴体は、プロペラを通過する空気流が、前面と比べると、後方では圧縮されて、流速が速くなり、流れの断面積が小さくなる収縮流の中にあるから、エンジン後方の胴体は絞った方がいいと考えていた。それを実行したのが陸軍の九七式戦闘機、「隼」、「鍾馗」だった。「彩雲」は三座機だったから絞り込むことは出来ないが、最小断面の平行部のある細い胴体を目指した。」
とまあ、こんな記述である。航空機設計のプロであった鳥養氏には申し訳ないが、この中島の設計思想には、事実関係にいくつか疑念がある。まず、九七戦の胴体形状である。確かに平面形を見ると、エンジン最大径部分からカウルフラップ後端までかなり急激にしぼられていて、後方の胴体と、折れ曲がるように接続している、流体力学の単純な常識的には不利な形状をしている。しかし、側面形はそうはなっていないのである。前方視界の関係からカウリング上面は直線的であるのは分かるが、下面は絞ることができるのに、そのようにはしてはいないのであるのが、整合がとれていない。
実は、九七戦のカウリング設計は、NACAカウリングの過渡期として説明できる。NACAカウリングが、低抵抗の空冷エンジン用カウリングとして普及するまでは、空冷エンジンの単発機は、九試単や九六式一号艦戦のように、細い胴体の先端に大直系のカウリングをつけて、冷却空気がスムーズに流れるようにするタウネンドカウリングを採用していた。その場合の胴体断面の寸法はパイロットの居住空間、燃料や搭載機材の必要寸法から、狭くされていても支障がなかったのである。ただし、冷却空気の流量を制御できないから、過冷などになる不具合もあったのである。
後年の液冷エンジンを積んだ飛燕は、液冷エンジンの幅ぎりぎりにに合わせて、840mmという最小幅としていても、胴体幅としては足りていたのである。諸外国の液冷エンジン搭載機も似たり寄ったりであった。つまり初期にNACAカウリングを採用した九七戦は、エンジン直径と関係なく、最小の胴体必要幅を採用したから、平面形が急に絞られているようになったのに過ぎない。実は、意外な類似思想の機体が米国に存在した。カーチスP-36である。この機体も平面形は頭でっかちで、胴体は細い。
つまり、P-36も同じように初期のNACAカウリング採用の過渡的な存在なのである。世界の傑作機No.23の陸軍5式戦闘機に、これに関連する記述がある(P55)。細い飛燕の胴体に、空冷エンジンを搭載しようとしたら、直径が大き過ぎて胴体寸法と合わなくて、空気抵抗の増大が懸念されたのである。高さの方は、胴体下面に膨らみを付けることで簡単に片付いたが、平面形がどうにもならない。そこで風洞実験をしたが、そのひとつに九七戦のようにしたものがあった。
すると、絞った部分に渦流が発生して、使い物にならないと判断されて、小規模ながら胴体の幅を膨らませ、不足分は胴体側面に推力式排気管を配置して対策した、と言うのである。鳥養氏のいうように九七戦がプロペラ後流の影響で胴体を絞ったと言うのなら、キ-100の場合も問題はなかったであろう。風洞実験ではプロペラ後流の影響は試験できない。それなら風洞実験の結果はどうあれ、プロペラをつけた実機では問題ないはずだ、と判断されたはずだが川崎航空機と陸軍の技術者はそう判断しなかった。結局は九七戦方式は採用されなかったのである。現に、タウネンドカウリングからNACAカウリングに変更した、九六式二号二型艦戦以降では、胴体を全面設計変更して太くし、カウリングと胴体の段差を最小となるようにしているのも、川崎航空機の判断と一致している。
そうすると逆の疑問が生じる。九七戦は問題なかったではないか、と。世界の傑作機の筆者はこのことに言及していないので、小生の推定を紹介する。キ-100に比べると九七戦の主翼はかなり、カウリングに食い込む前方にある。つまり、カウリングが絞られたあたりに、主翼があることによって、トータルとして断面積の減少を補正できる。完全にではないにしても、実用上支障ない程度に過流の発生は少なかったのだろうと推定する。
なお、遷音速域では、胴体と主翼を含めた断面積の変化を少なくすると抵抗が少なくなる、というエリアルールがある。遷音速に至らなくても飛行機の抵抗増大などの空力的不具合は、やはり機体や主翼の断面変化の影響がいくらかはあるのではなかろうか。現にホンダジェットでは主翼上面にパイロンを設置して、エンジンを取り付けているにもかかわらず、配置の検討の結果、わざわざパイロンを後方に張り出して、エンジンが主翼直上にこないように配置している。これもエンジンと主翼の干渉を避けたのであろう。
そうすると、P-36の場合はどうなのだ、と。実はある本(*)に、P-36の輸出型であるカーチスホーク75Aの初期型の平面図(P65)があるのを見つけた。これを見て驚いた。何と主翼と胴体の平面形が配置も含めて、九七戦と瓜二つなのである。もちろん、風防と尾翼は全く違うがそれ以外はそっくりなのである。わずかな違いは、主翼のアスペクト比と、主翼前縁が九七戦が全く後退角がないのに比べ、75Aはほんのわずかに後退角がついていること位である。
例によって、九七戦は、この機体を参考にしたのではないかと疑ったが、どちらの原型機も完成時期が近いので、断定はしない。この時期のNACAカウリング採用単発機は、いずれもカウリング平面形を後方でやや絞っている、という共通点があるから、やはり設計者に共通の迷いがあったものと想像する。なお、P-36の原型機と初期の75Aは、空冷単列星形の大直径エンジンを採用しているが、P-36の実用機と後期の75Aは、二重星型でより直径が小さいものに換装しているから、カウリングの絞り込みの空力的影響少ないものと考えられる。九七戦の練習機で小直径エンジンを採用したものも同じことになっている。
以上のように、鳥養氏の言う、中島飛行機のプロペラ後流の収縮流の影響、というのには、疑義を持たざるを得ない。もっとも鳥養氏は中島の設計思想を淡々と述べているだけで、正しいとは判定はしてはいない。エンジンがなくプロペラだけが空気流れの中で回転していることを仮想すると、空気流の最高速度はプロペラ断面通過位置となる。すると流体力学の原理により、空気の流れの断面積は、プロペラ断面位置で最少となるから、プロペラより後ろで空気の流れが絞られる、ということは考えられない。
実はこのことが、プロペラによる収縮流の影響と言う考え方(俗に日本の飛行機マニアの間で「縮流理論」ともいう)に疑問を持ったきっかけである。さらに鳥養氏は、彩雲は三座機であるため、「最小断面の平行部のある」長い胴体となっていると書いておられるのは、実は正確ではない。実際には世界の傑作機No.108の断面図のように、エンジン防火壁直後から、徐々に幅が絞られて、厳密には平面図で見た胴体幅の平行部分というのはない。これは揚げ足取りではない。
他の偵察機の例を見ても、当時の偵察要員や機材などを搭載する必要幅は、誉エンジンの幅よりずっと少ないのである。それでも、彩雲の胴体の幅がかなり後方まで絞られ方が少ないのは、別の意味で「三座機」だったからである。彩雲は艦上機であり、偵察機であるため、視界確保を重視した。そのため、風防幅が大きい。幅の大きい風防を操縦員から、最後席まで長い区間を「平行」にして幅を確保している。そのために後方胴体を急に絞ることが出来なかったのである。それでも、下方視界確保のために、後方に行くにしたがって断面形が円形ではなく、上半部を細くしたものとなっている。
ちなみにP-36に戻ると、液冷エンジンに容易に換装でき、P-40となったのは、元々胴体幅が狭かったから液冷エンジンにすると丁度良かったのであって、偶然に運が良かったのである。キ-100のために弁ずれば、土井技師が空冷換装に苦労したのはエンジン寸法の違いばかりではない。エンジンなしで生産されてしまった多数の機体を、最小限の改造で金星エンジンを装着しなければならなかったからである。むしろ全て新造なら九六式二号二型艦戦のように、胴体の全面設計変更した方が設計の苦労は少なかったのである。土井技師たちの苦労は想像以上だったと思う。
また、通説では、鍾馗の胴体は「縮流理論」によって、エンジン後方の胴体が、急に細く絞られている、とされている。ハセガワの1/48のキットがこの通説に従っている。しかし、平面形を上空から写したものや、真後ろから撮影されている写真をいくらみても、胴体が絞られて凹んでいるようには見えず、単にほぼ直線的に成形されているようにしか見えない。この胴体形状はFw190のAシリーズとそっくりである。それでは直線的に成形するメリットは何か。鳥養氏の説明のように、胴体表面積が最小になって、摩擦抵抗を最小にできるのである。
ハセガワの鍾馗のような胴体形状は、渦流の発生や表面積を大きくする、という二点で流体力学的にはあまり好ましくはないのである。雷電や烈風のように、最大断面積を全長の40%位置にするために、わざわざ胴体幅をエンジン最大断面積より大きくするのは、摩擦抵抗が増えて好ましくはない、と鳥養氏が言うのは流石にプロだと思う。ちなみに、Fw190D9あたりの胴体断面積がエンジン最大断面積より大きくなっているのは、空冷エンジンの胴体設計を極力流用した結果に過ぎない。前のタイプの設計の流用は、設計の手間ばかりではなく、製作治具の共用などの、生産上のメリットも大きいことを付言しておく。
*COMBAT COLOURS Number4という大東亜戦争初期の日本機と連合軍機の塗装図集
5.艦艇の技術
①日本戦艦の砲弾への疑問
「日本の戦艦パーフェクトガイド」という雑誌を読んで驚いたが、長年の疑問も解けた。それは日本の戦艦の砲弾である。ジュットランド海戦の戦訓から、方位盤射撃装置の設定変更をさけるため、昭和5年頃から弾種を徹甲弾だけに統一したというのである。零式通常弾と三式通常弾が採用されたのが昭和19年で、配備され始めたのが昭和17年だという。
地上目標に使用できるがいずれも対空射撃用に開発されたものである。日本戦艦は大東亜戦争中期まで徹甲弾しかなかったのである。その徹甲弾は水中弾効果を得るために0.4秒もの遅動信管を備えていた。水中弾は水面に激突後200口径もの距離を走るために、その間に爆発するのを防止するというのだ。だが、もし水中弾ではなかったらどうか。舷側装甲や水平装甲を貫けば船体を通り抜けて船外に出ることもありうる長い時間である。
船体を貫いて水中で爆発してしまう可能性が大きい。まして米国の旧式戦艦や巡洋艦以下の艦艇ではさらに容易に貫徹する。つまり大和など徹甲弾はよほど運のいいところに当たって船体内に止まらない限り艦内で爆発せず船体を貫徹してしまい船体外の水中で炸裂する。要するに昔の無火薬の砲弾と同じく鉄の塊に過ぎなくなる。
それまでに使われていた砲弾は英国式で0.008秒の遅動信管であったというから、日本海軍は水中弾にこだわるあまり極端なことをしたものである。その後の砲戦技術に大きな影響を与えたジュットランド沖海戦での戦訓として、装甲貫徹後の砲弾が火薬庫で炸裂したことが効果的であったことから、日本海軍はドイツの徹甲弾を真似た0.25秒の大遅動信管を研究開発したというから、日本海軍の信管の遅動化は既にその傾向にあったのである。
米海軍も水中弾の効果については知っていたが、生起確率の問題やそのために砲弾の形状や仕様を決定するにはリスクが多すぎて、水中弾仕様の徹甲弾は開発しなかったといわれている。通常の徹甲効果よりも水中弾の効果を優先して信管の性能を決めたり、弾頭形状を決めるなどというのは本末転倒である。三式普通弾にしても対空用に作られたために、軽装甲の艦艇や地上目標に対する効果に疑義がある。
このような状態でレイテ湾に栗田艦隊が進撃しても実際にはその効果は予想より少なかったと考えられる。兵頭二十八氏が言うように戦艦の榴弾は同一重量の通常爆弾に比べて、対地上目標に対する破壊効果はずっと少なかったのであろう。兵頭氏は言及していないが、その原因は大寸法の砲弾では爆弾に比べて発射の衝撃に弱いから、弾体重量に対する鋼材重量が大きくなる、つまり炸薬重量を減じなければならないからであろう。
この意味でも戦艦の砲弾を対空射撃に使うことは最も効率が悪い。大和級の戦闘記録でも主砲を対空射撃に使う場合には、機銃要員などを艦内に対比しなければならないのに、連絡がなされなかったなどの原因により、機銃要員が多数殺傷されている。その割りに対空射撃の効果は少なかった。三式普通弾などは噴飯ものである。要するに榴弾が主力となる前に使われた榴散弾そのものである。時限信管で空中で炸裂させ前方に小弾をばらまくあれである。
地上目標に使う場合には、うまい高度で炸裂しないと効果がないから使い方が難しい。金剛と榛名がヘンダーソン飛行場に打ち込んだものの多くは三式普通弾であったから、戦後言われているように使用量の割には実は効果が少なく、不発も多かったといわれる。着発式信管も併用していたはずであるが、あくまでも補助なので信頼性が低かったか、地中で炸裂して効果が少なかったのであろう。
日本海軍の信管は爆弾においても同様に多くの戦記をチェックすると日本海軍の爆弾が命中後炸裂するまでに時間がかかっていることがわかるから、遅動信管が使用されていることがわかる。これは戦艦、巡洋艦などの重装甲の船体を貫徹させて内部で炸裂させることが目的であることは明らかである。しかし多くの場合これは逆効果であった。駆逐艦に体当たりに成功した1機の桜花の爆弾は船体の両舷を貫徹して反対側の海上で炸裂したという記録が残っている。
桜花は1.2tの爆弾を搭載していたから、瞬発していたら駆逐艦は轟沈していただろう。ところが被害は軽微だったのである。ある駆逐艦は零戦に舷側に体当たりされそうになったので、衝突側の乗組員は急いで反対側に逃げたが、爆弾はやはり両舷を貫徹して直後に爆発したので、逃げた乗員の多くが死傷したというのである。もちろん駆逐艦は沈没していない。多くの特攻隊員は大型艦船に体当たりすることを想定されていたのに、実際には被害担当艦たる駆逐艦やレーダーピケットに命中したからこのようになってしまったのである。
爆弾が瞬発に近い信管を備えていたらもっと神風攻撃による被害は増加していただろうと悔やまれる。それにしても戦艦に体当たりするにしても大遅動信管は効果がなかったのではないか。水平爆撃の場合は加速されるので急降下爆撃より爆弾の装甲貫徹力が大きいことは知られている。
同様に体当たり攻撃の撃速も数百km/hで急降下爆撃と同程度である。従って戦艦の装甲された舷側に当たったら貫徹できずにはじかれて、舷外で爆発して被害は少ないと考えられる。むしろ瞬発した方が大きい被害を与えると考えられる。艦橋などの上構に命中した場合でも、致命傷を与えることはできないが破壊効果は大きいと考えられる。信管の性能設定ひとつすら大きな影響を与えることがあるものだと考えさせられる。
②世界初のステルス兵器伊361型
おそらくレーダー対策としての世界初のステルス兵器は、日本海軍の伊361型潜水艦であろう。それに続く伊373型も輸送用潜水艦であった。計13隻が建造されている。ステルスは艦橋に限定されているが、全体の形状からしてそれで充分であったであろう。しかも現在のステルス軍艦の艦橋と同じく、上方が外に傾斜しているのも共通している。まさにステルス兵器の元祖であると言えよう。
対レーダーステルス兵器といわれる最初のものが、F117をはじめとする航空機であり、軍艦のステルス化は現在でもあまり進んでいないことを考えれば日本海軍の着想は画期的である。日本海軍の潜水艦が世界初のステルス兵器であることは、海軍自慢の軍事関係者ですら言及しない。丸スペシャル・日本海軍艦艇発達史通巻132号でも伊361型の項であっさりと「艦橋も電探防止型に改められた」と簡単に記されているだけである。
軍事雑誌「丸」平成19年2月号はステルス軍艦特集である。ある記事には「最初に軍艦のステルス化に着手したのは旧ソ連海軍であった。」として1980年に管制した軍艦の例をあげ、30数年前の日本海軍の例は言及もしない。別の記事ではさすがに日本海軍の例が3つのタイプの潜水艦が艦橋の形状と表面に特殊ゴムを貼るなどのレーダー対策をしたことを説明するが、これはこの記事の内容とかけはなれたものである。
形状と表面材料の選定は、現代でも対レーダーステルスの基本である。にもかかわらずこのことを特筆もしない。時期がはるかに遅いとはいえ、米軍がステルス兵器として軍用機や軍艦について系統的に発達させたのとは姿勢が異なる。レーダーによる被害対策として必要に迫られて、せっかく新しいジャンルを切り開いたのにもかかわらず、系統的に発展させることがなかったのは世界初のステルスであることに対する冷淡さが起因しているように思われる。
すなわち日本で画期的な技術が必要から生み出されていても、国産技術だから注目せず、外国で発明されると初めて注目する。こういった悪癖が国産の発明を生かせない根本原因である。
米軍は自らの発明の重要性を認識し体系化することが一般に行われていた。他方の日本海軍は重要性を認識することがなかったのである。八木アンテナのように、日本人は多くの発明をしながら日本の発明であるがゆえに忘れられ、外国で注目されるとオリジナルが日本であったことも忘れて取り入れる。悪癖である。
③なぜ航空母艦の艦橋は右舷にある
なぜ航空母艦の艦橋は右舷にあるか。私には、上記の疑問に対する明確な回答が巷間の書籍に書かれていないことを不思議に思える。洋書はいざしらず、寡聞にして日本で正解を書いたものを見たことが無い。例えば2011年の世界の艦船の増刊号の「日本航空母艦史」にはこう書かれている。「赤城の艦橋構造物は・・・右舷には煙突があるので左舷に設けられた。・・・しかし改装後の赤城の実績では艦後方の気流が不良で、以後の艦は右舷設置に戻され、左舷艦橋はこの2隻で終わった(155頁)。」2隻とは赤城と飛龍である。他の雑誌類もおおむね艦橋後方の気流の不良を原因としている。だが空母の航行は左右対称だからこれは全く説明になっていない。
結論を言おう。理由は不明だが、僅かな例外を除いてレシプロ航空エンジンのプロペラは、後方から見て時計方向に回転させるよう設計している。2サイクルエンジンならともかく、多くの航空エンジンに使われている4サイクルエンジンでは、原理的に設計時と逆方向の回転をさせることは出来ないのである。プロペラを回転させるトルクにより、艦上機には左旋回させる力が働く。発艦時には出力を最大にするからなおさらである。だから左舷に艦橋があるとパイロットには衝突の恐怖心が発生する。
恐怖心だけではない。実際発艦時には艦橋との衝突の危険があるし、着艦に失敗してやり直すときには、飛行甲板上の低空でスロットルを吹かすことになるから、この時にも危険が生ずる。陸上機型の戦闘機でも大馬力エンジンのトルク対策として、垂直尾翼の断面を左右非対称としているものがある。その代表例がかのBf-109である。双発のロッキードP-38などはトルク対策として、左右のエンジンの回転方向を逆にする、という贅沢なことをしている。
僅かな例外、と言ったがそれは世界的に見ての話で、英国製エンジンは案外反時計方向回転のエンジンが多い。例えば空冷ではブリストル・マーキュリー、ブリストル・セントーラス、液冷ではロールスロイス・グリフォン、ネイピア・セイバーなどである。
しかも、これらのエンジンのうち、特に大馬力のものも艦上機に使われているから大変である。元々、主脚のトレッドが狭いシーファイアは発着艦の事故が多い。それがマーリンに換えてグリフォンを搭載したからますますトラブルの原因となる。シーファイアは後期型では、トルクを消すために二重反転プロペラに変更した。同じくグリフォン搭載のシーファングも量産型では同様にした。
グリフォンまたはセントーラスを搭載していた、スピットファイア、スパイトフル、テンペストはいずれも艦上機型が作られている。シーファイア、シーファング、シーフューリーである。正確にはテンペストの改良型のフューリーは空軍に採用されず、海軍型がシーフューリーとして採用されたのであるが。
これらは全て陸上機型が通常のプロペラであるのに対して、艦上機型になると二重反転プロペラに換装されている。これだけエンジンの回転トルクによる影響は深刻で、全て艦橋が右舷にあった空母では危険なのである。機構が複雑なため、日本ではついに、二重反転プロペラを実用機に採用することはできなかった。それほど高度な技術を必要とする二重反転プロペラを採用しなければならなかったのは、その必要性を証明している。
④戦艦大和とアイオワはどちらが強い?
その答えは是本信義氏が「海軍の失敗」に明確に書いている。多くの評論では、この議論に難渋しているのと対照的である。是本氏は大和より装甲も手法の口径も一回り劣る米海軍のアイオワ級戦艦に完敗すると即断している。理由は明確で射撃指揮装置が大和が圧倒的に劣るから、武器の強さや装甲などのカタログ値は大和の方がずっと優れていても、アイオワはずっと前に大和に多数の命中弾を与えるというのである。
さすがに海上自衛隊のプロだっただけある。是本氏はアイオワは大和にないレーダー射撃ができた事も強調しているが、それがなくても射撃指揮装置の性能の差だけでも充分であったのは明白である。このように日本海軍の装備や戦闘手段はカタログデータだけ高くて、実質的能力は低い。この点は日露戦争当時には外国の軍艦の装備と大差なかったのと大きく異なる。
そういう目で見ると日本海軍はずいぶんちぐはぐな戦いをしている。例えば第三次ソロモン海戦で戦艦霧島は、戦艦サウスダコタに三式弾を多数命中させて艦橋などの構造物を大破しているが沈没させることはできずに、戦艦ワシントンのレーダー射撃で沈没した。
三式弾というのは対空射撃用の砲弾なので、いくら命中させても戦艦の装甲には跳ね返されてしまって沈没させることはできない。戦艦に対しては装甲を貫く徹甲弾を使用しなければならないのである。馬鹿な戦いをした、と思っていたら、最近ある本で、霧島は三式弾を打ち尽くさなければ、徹甲弾を発射できなかったという。つまり打ちたくても打てなくて負けたのである。
サマール沖海戦では戦艦大和は、装甲のない護衛空母や駆逐艦に徹甲弾をあびせている。正規空母にしても装甲はぺらぺらで徹甲弾ではだめである。大和の世界一大きい砲弾は、敵艦に大きな穴をあけて爆発もせずに海に飛び込んだだけである。この時日本艦隊は駆逐艦二隻と護衛空母を撃沈したが、これは戦艦金剛と巡洋艦の射撃である。
つまり日本海軍は徹甲弾を使うべき時に使わず、使うべきではない時に使うという、ど素人のような戦闘をしていたのにはあきれる。戦艦大和が図体ばかり大きくて、実質的戦闘力が少ないのと同じ事である。
⑤日米対空戦の謎
多くの大東亜戦記を読んだが、ひとつ大きな疑問があった。それは対艦船への航空機による攻撃の記述である。それは、日本のパイロットが米海軍の軍艦を攻撃する際は、対空砲火が激しくて生還は奇蹟にひとしいと書かれているのに対して、軍艦の乗組員は米軍の航空攻撃が激しくて、容易に雷爆撃されていると言う事である。対空火器を大量に装備しているはずの戦艦ですら、戦闘機の機銃掃射にさらされてもほとんどなすすべもない。これに対して日本の軍用機が米艦船をゆうゆうと銃撃したなどという記録にはお目にかかれないのである。これは輪形陣など多数の艦艇が対空砲火網をひいて待ちかまえているためではない。単独航行している場合も同様だからである。
第一、艦船攻撃の場合に、接近した航空機を40mm以下の口径の火器で攻撃する場合は、射程の面でも同志討ちを避ける面でも他の艦艇の火器の支援を受けるわけにはいかないのである。また、爆弾を水面に落下させて水切り遊びの石のように、水面を跳ねさせて艦艇に命中させる、反跳爆撃を米軍が多用して戦果を上げたので、日本軍も研究したが爆弾の性能の問題の他にも、攻撃時に艦船のかなり近くまで直線飛行するので、確実に撃墜されてしまうというので止めたという経緯がある。
反跳爆撃のコースに乗った日本の爆撃機の対空砲火の最後の相手は、高角砲ではなく、20mmないし40mm機銃だけであり、攻撃される艦船は付近の艦船の支援は受けられない。つまり日米艦船と攻撃機の条件は同一なはずである。それにもかかわらず米機は爆撃機正面に装備した機銃で対空砲火を制圧して爆撃した。これも日米の対空火器の効果の差を如実に表している。それでは多くの図書は日米の差を何と説明しているか。大抵は近接信管(VTヒューズ)とレーダー射撃の存在に帰している。
例えば、失敗の本質-日本軍の組織論的研究(ダイヤモンド社)では2章の失敗の本質で、日米の技術力の差を総括して
対空兵器もレーダーの研究開発に立ち遅れたため射撃精度は必ずしも高くなかった。また対空砲弾も米軍が開発したVT信管ではなく、在来型の信管のため効果が十分にあがらないことが多かった。
数人の共著による大作が日米の対空兵器の差をレーダーとVT信管の有無だけに帰しているのだ。しかし、これは秘密兵器好みの説明で実態を充分に説明はしていない。以下にその差異を検証したい。
当時の米国の艦船の対空火器のほとんどは、5インチ両用砲、40mm機銃、20mm機銃の組み合わせであった。当然このうちでVT信管を使えたのは5インチ砲だけである。レーダーを備えていたのは5インチ砲用の射撃式装置のMk37だけで機銃用の近接対空用のMk51にはレーダーはない。つまりこれらの秘密兵器が使われたのは、5インチ砲だけであったから、日本機に接近されたらこれらの秘密兵器は使えず、条件は日本艦艇と同様になるのである。つまり世間に流布されている説は極めて局部的なものに過ぎないのである。
日米の差には3つの原因がある。対空火器の種類の選択の相違、対空火器の性能の相違、射撃指揮装置の相違である。日本の戦艦や空母などの場合には、12.5cm高角砲と25mm機銃の組み合わせであり、米国の艦船の対空火器のほとんどは、5インチ両用砲、40mm機銃、20mm機銃の組み合わせである。対空射撃は有効射程より遠ければ効果はないが、近過ぎても効果はない。日本海軍の場合には、12.5cm高角砲の砲火を突破した敵機が25mm機銃の有効射程に入るまで艦船は無防備になる。米軍の場合にはそこに40mm機銃が待ち構えている。つまり日本機はほぼ隙間なく対空砲火に晒されているわけである。これが第一である。
米国のほとんどの駆逐艦の場合には、1930年代の艦隊型になった時代から主砲を日本の高角砲より、初速、毎分の発射速度、最大射高のいずれも優れた性能を持つ両用砲を装備している。これより優れた性能を持つのは防空駆逐艦を自称した、秋月型の10cm高角砲だけである。また日本の駆逐艦で12.5cm高角砲を持つのは大戦末期の松型だけであった。大多数の駆逐艦は高角砲ではなく対水上艦艇用の12.5cm主砲であった。一部の駆逐艦の主砲は仰角を増やして対空射撃機能を持たせているが、実質的にはほとんど役には立たない、高角砲もどきであった。だから戦艦や空母を守るはずの日本の駆逐艦は、25mm機銃以外ほとんど防空援護能力がなきにひとしかったが、25mm機銃の有効射程の外にあるから、空母や戦艦の防空支援はできない。
戦艦や空母の持つ高角砲ですら上述のように、米駆逐艦の主砲にすら劣るのである。25mm機銃と20mm機銃の相違であるが、有効射程は当然25mm機銃の方が大きいが実戦ではカタログ値の半分以下でなければ命中しても撃墜できないとされているが、これは米機の防弾装備の良さによるものもあろう。口径が小さいだけ発射速度も弾倉1セット当たりの装備弾数20mm機銃の方がずっと多い。25mm機銃は映画のように連続射撃できるものではないとされているのに対して、40mm機銃ですら、4発入りのクリップを補給してやれば間断なく射撃できるとされている。以上のように25mm機銃は近接防空には大型過ぎるのであろうが高角砲との中間口径の機銃を持たない日本海軍としてはやむをえなかったのであろう。米軍が20mm砲の威力に格段の不満を持たなかったのに対して、25mm機銃に対する不満は大きかったとされるが、これは射撃式装置など他の要因も総合したものであろう。
ここで言う射撃指揮装置とはFCS(Fire Control System)のことを言い、火器管制装置などとも言われる。FCSとは「目標の情報を入手し、それを捕捉追尾し所要のデータを得て、砲・発射機に必要な諸元を算出し伝達する装置である(世界の艦船No.493による)。第二次大戦当時の米海軍の射撃指揮の主力は5インチ砲ではMk37、40mm機銃ではMK51であった。これに対応する日本海軍のFCSは九四式高射装置と九五式機銃射撃装置であった。日本海軍のFCSの評価はどちらも芳しいものではない。日本海軍にいて戦後海上自衛隊員として、米国のFCSを用いて射撃練習をしたところ、飛行するドローンに最初から命中弾を与え、操作も簡単であったと述懐したものを読んだことがある。
軍艦マニアでは、世界一の戦艦大和と、アメリカのNo.1の戦艦アイオワと戦えばどちらが勝つかと言う話が出る。答えはまちまちで大和やや有利とアイオワやや有利が数の上では拮抗しているように思われる。これらのほとんどは射撃速度や装甲貫徹威力や装甲厚などのカタログデータを用いて論じたものである。しかし雑誌『世界の艦船」に元自衛隊の射撃の専門家が、FCSも含めた射撃指揮装置の能力の差からアイオワの勝ちであるとごく明快に論じている。これほど日米の射撃指揮装置とマン・マシンシステムの能力には差があるのである。しかも日本海軍の駆逐艦で、主砲の仰角を上げたものですら、九四式高射装置すら装備していない。僅かに秋月型が装備しているだけである。これらを総合すると、防空駆逐艦の秋月は戦時に大量生産された艦隊型のフレッチャー級駆逐艦にすら防空能力は劣ると断じざるを得ない。
日米海軍の防空能力の差は断じてVT信管やレーダーなどの「秘密兵器」の有無の差ではない。最大の要因は射撃指揮装置と言う地味な兵器の能力の差と装備した火器の差によるものである。VT信管といえども、航空機の近くを砲弾が通過しなければ爆発しないと喝破した識者がいたがその通りである。五インチ砲は15m以内を通過しなければVT信管は作動しない。ミサイルのように敵機を追尾してくれるわけではないのである。当時のレーダーは米軍のものさえ、現在のように完全に照準してくれるものとは格段の差がある。
ただ日本海軍の名誉のために言うと、マレー沖海戦で、鈍重で大型、しかも防弾装置もほとんどない陸攻を2隻の戦艦と護衛艦で3機しか撃墜できなかった英海軍の防空能力は、大戦初期とはいえ冴えない。何機か撃墜したとはいえ、何と鈍足の複葉機を撃退できず被雷したビスマルクの防空能力も知れたものであろう。戦艦ティルピッツも数十機の英航空機に襲われて、撃墜したのはわずか2機だった。日英独海軍ともに駆逐艦用の両用砲を実用化できなかったからこの点では一人米海軍が優れていた。つまり日本は悪い相手と戦ったのかも知れない、という思いもする。
⑥日米の射撃指揮装置(GFCS)の決定的な能力の差・・・前項に続く
元自衛官の是本信義氏が。海軍の失敗という著書で、日米の射撃指揮装置の能力の差について説明している。日米最高の戦艦の大和とアイオワが戦ったらどちらが勝つか、という設問である。氏は明快にアイオワの完勝である。と断ずる。アイオワの場合、距離の誤差の小修正と方向の小修正を最初の弾着でおこなうので、夾叉弾を得るのに試射1回、3分45sかかる。大和は、試射3回、8分15sを要すると言うのだ。この時間が短ければ先に命中するばかりでなく、艦の進路の変更などの影響が少ないから有利である。
さらにレーダー観測とすれば、光学式測距儀のような距離による誤差がなくなる。それどころではない、射撃番(計算機)の能力には格段の差があるし、日本海軍では射撃盤による砲の自動操縦システムを持たなかったから即応力には大きな差が出る。このような指摘は護衛艦で砲術長をしていた氏ならではの視点である。
同じく、是本氏の「日本海軍は滅び、海上自衛隊はなぜ蘇ったのか」にも明瞭な指摘がある。第二次大戦中の主力の射撃指揮装置のMk37より性能が劣る米軍から供給されたGFCSを搭載した護衛艦の砲術長として、5インチ速射砲で標的の吹き流しを射撃したと言う。VT信管ではなく、時限信管を用いていたにもかかわらず、初弾から命中したと言うのだ(P54)。他の個所でも護衛艦が次々と標的に命中させて技量の高さに米海軍の教官たちが驚いたと言う逸話を書いている。VT信管を使っていない事はもちろんであるが、技量を問題にしたのはレーダーではなく、光学照準だったからであろう。要するに当時の日本海軍の九四式高射装置との性能差の隔絶は言うまでもない。
氏は同時に、日本海軍の12.5cm高角砲と米海軍5インチ両用砲の命中率の左は、0.3%対50%であったと言う驚ろくべき統計を示す。比率は約167倍という驚異的な差になる。米海軍に比べれば、日本海軍の高角砲は全く当らないのに等しい。是本氏はVT信管とて、目標に接近しなければ有効ではないから、日本海軍がVT信管を使用しても何の役にも立たなかったろうと断言しているがその通りである。VT信管は弾道を敵機の方に向けてくれるわけではないのである。米軍のレーダー照準にしても第二次大戦当時のレーダーを今の時点のレベルで比較すべくもないから、過大評価は禁物である。VT信管はマリアナ沖海戦から使用されているが使用されたのは5インチ砲だけで、それも弾数の僅か20%である。それ以前の日本が勝利したとされる珊瑚海海戦でも、南太平洋海戦でも、艦艇の喪失トン数こそ米海軍が大きいが、艦上機の被害は日本海軍の方が大きい。
Wikipediaによれば、南太平洋海戦での喪失艦上機は日本92機、米74機で、搭乗員となると、148人と39人と更に差が開く。日米の射撃指揮装置(GFCS)の決定的な能力の差は、同じく戦艦に対する攻撃にしても、日本機は対空砲火により接近する事すら困難であったと証言されているのに、米海軍は戦闘機による機銃掃射さえ平然と行って、対空火器要員をなぎ倒している。シブヤン海海戦で大和は戦闘機による機銃掃射で主砲身内に飛び込んだ機銃弾が砲弾の信管を破壊し、砲塔内で小爆発を起こした(*)という情けないエピソードすらある。
米海軍では大東亜戦争に参加したほとんどの駆逐艦が、対水上と対空の両用砲を備えている。しかも、対水上能力に不満が残る、と言われた位対空能力を重視している。日本初の防空駆逐艦である秋月型でも、高角砲のカタログデータが優れているだけで、GFCSは相変わらずの劣った九四式高射装置である。秋月型ですら戦前からの米駆逐艦よりはるかに対空能力が劣っているのだ。ましてや、その他の駆逐艦には高角砲はもちろん九四式高射装置すらないから、対空射撃能力はない。自艦さえ守れないのである。
海軍の防空体制への批判の最大のものは、米国が早期に輪形陣を取り入れて空母の周囲に濃密な護衛艦艇を配置したことであろう。これに対して日本海軍は、戦艦などを空母から離して配置していたため、脆弱な空母護衛のための有効な対空砲火陣を張れなかった、というのである。たが輪形陣を組んだところで桁違いの対空火器の命中率ではやはりどうしようもなかった。日本機は単独航行の米駆逐艦への攻撃にも苦慮していたのに、F4F戦闘機に撃沈された駆逐艦すらあったのである。
巷間の出版物に対空砲火の効果を射撃指揮装置の能力差に求めずに、レーダーやVT信管に求める傾向が強いのは、GFCSという地味なものの開発を軽視して、主砲の口径や戦艦の装甲厚さといったカタログデータに表れやすい物を重視した日本海軍の技術開発方針と類似したメンタリティーを感じる。
*Gakken Mook GARAシリーズ、戦艦「大和」の真実
⑦航空戦艦伊勢級のカタパルト
伊勢型戦艦は、空母の不足を補うために、艦上機を運用できるように改装された。しかし見る限り伊勢型のカタパルトは、米空母のカタパルトとは異なり、水上機射出用のカタパルトと変わりはない。どうやって車輪式の艦上機を射出するのか長い間疑問に思っていたが、回答を与えてくれる本を手に入れた。模型店で入手した簡易製本の「航空戦艦伊勢・増補改訂版」という本である。機種ごとに専用の台車(滑走車)に艦上機をセットして、軌条でカタパルトまで運び、射出するのである。この場合艦上機は脚を飛行甲板に着けられないので、軌条の上しか移動できないという不便なようだが飛行甲板自体が狭いから、かえって車輪で走行するよりは都合がよかろう。市販の伊勢型戦艦の記述がある書籍には、この点を記述したものを見たことがなかったから、小生には貴重な本である。滑走車自体は使い捨てではなく、射出されて機体と分離したら回収されるのだそうである。この本の彗星を載せた滑走車の図をまねて書いたものが添付の図である。粗雑で、かの本のように立派な図ではないが、イメージだけはつかめると思う。
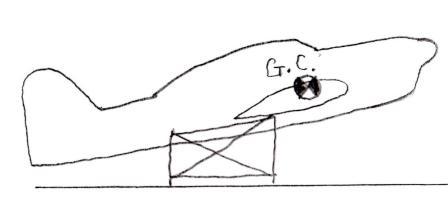
それでもまだ疑問がある。機体が3点静止姿勢に近い角度で機首が前上方を向いて滑走車に傾斜して載せられている点である。滑走車はカタパルト先端で停止し、機体だけが滑走車から離れて空中に飛び出す、と読めるように同書には記載されている。すると滑走車がカタパルト先端に到達する前に、機体が滑走車から充分浮き上がることができなければ、滑走車がカタパルト先端に到達した瞬間に機体は滑走車に押し付けられて、空中に飛び出すことはできない。
それどころではない。滑走車を射出せずにカタパルト先端で止めるためには、機体を滑走車に固定するロックをカタパルト先端で自動的に解除しなければならない。すると、図に示したように、滑走車前端の最上部より機体の重心位置(図のG.C.)は高いから、転倒モーメントが働き、機体は前転して放り出されて海中に落ちる。あるいは、水平尾翼と滑走車が干渉するのではなかろうか。いずれにしても、機体を水平にして射出しない限り、滑走車をカタパルト上に残しておく方法は小生には考えられない。いずれにしても、カタパルト前端で機体が滑走車のロックから外れても、滑走車と機体が干渉せずにスムース発艦てきるのだろうか。小生にはよく分からない。分かる方がいたら教えていただきたいと思う次第である。確かに水上機ではカタパルト上で機体は水平に保持されている。
結局は、滑走車は機体と共にカタパルトから射出されて、空中で分離して落下するしかないのではなかろうか。回収するには滑走車にワイヤロープを取りつけるなり、方法は考えられるが面倒そうである。いずれにしても滑走車に3点姿勢で取り付けられている限り、一旦は滑走車はカタパルトから射出しなければならないと考えられる。水上機の場合、フロートによってカタパルト上面とプロペラのクリアランスが確保されているから、機体を水平に保持しても、プロペラがカタパルト上面に当たることはないから、滑走車はかなり小さくて済む。艦上機の場合には機体を水平にして、カタパルト上面とプロペラのクリアランスを確保するには、滑走車全体の背が高くなり大型化する。それを防ぐため、せめて尾輪高さを下げて3点姿勢にしたのだろうか。本当のところは分からない。
なお、ドイツの空母グラーフ・ツェッペリンはカタパルトを装備する計画だったが、ある資料を見たら、カタパルトは伊勢型と同じく台車方式であった。英空母はアークロイヤルⅡ以降カタパルトを採用しているが、写真を見ても、米艦上機を運用していることから見て、米国と同じ方式であろう。
⑧なぜ米海軍は18in砲を採用しなかったのか
米海軍は、アイオワ級の後継のモンタナ級で、大和級に迫る基準排水量6万トンを超える大型戦艦を計画したにも拘わらず、主砲口径は16inにとどめた。なるほど三連装砲が3基から4基に増えて、装甲も強化しているから排水量の増加は当然である。だが、排水量を大幅に増やしたのに、なぜ大和のように18in砲にしなかったのかという疑問が、長年残った。もしかすると、その答えは意外なところにあったのかも知れないと、最近ある本を読んで考えたのである。
それは「続・海軍製鋼技術物語」(アグネ技術センター刊・堀川一男著)(以下続編という)である。続とあるように、本編があるのだが、続編ですら100ページで1,600円と高い、本編はその倍以上する。問題は高いことばかりではない。内容は金属工学にかなり精通していなければ、猫に小判、豚に真珠である。理想的には現在でもほとんど公開されていない、兵器に関する工学的知識がなければ完全には理解できない。
逆に言えば、内容が理解できれば値段は安い位だと言える密度の濃く貴重な本である。まだ続編ならば、多くが米軍が試験した日本の砲弾と装甲鈑のデータ集である。これならば、小生にも少しは読めるところがあると買った。もっとも1か月後には本編も買ってしまったのだが。
閑話休題。続編P61には「開発の当初は九一式徹甲弾の領収試験は表7.1のように非浸炭表面硬化甲鈑のVHと均質甲鈑のNVNCの両方で試験していた。ところが大口径弾はNVNCに激突すると弾体が破壊するので実施されなくなってしまい、・・・」とあり、8inだけがNVNCで試験し、戦艦に使われる14~18in砲弾では、VHで試験していた表が次に示されている。
つまり、口径が大きくなるほど、徹甲弾は均質甲鈑であるNVNCに衝突すると貫通する前に弾体が壊れてしまいやすくなるということである。適切な例ではないが、大きさの効果について説明しよう。昔年の航空機用の大型液冷エンジンは、ほとんど全てV型12気筒だった。更に大出力にするには、1気筒当たりの容積を大きくすればよさそうなものだが、そうは単純にいかない。気筒の容積は寸法の3乗で大きくなるが、表面積は2乗でしか大きくならない。容積は発熱量に比例し、冷却効果は表面積に比例するから、気筒容積を大きくすると、冷却可能な限界が生じる。そこで、W型24気筒などのように12気筒エンジンを並べるなどして気筒数を増やして、出力を増加するという無理をした。
このように同一技術水準の場合、大きさに限界が生じる場合がある。力学的な事例をあげられなかったが、海軍の試験結果から、主砲弾の口径にも限界があったのではないか。弾体が大型化すると、衝突時に弾体が貫通する以前に破壊してしまう傾向が強くなるのではないか。そこで発射速度や爆風が周囲に与える影響の大きさなどの、他の要因も考慮して、米海軍は16in砲弾が実用上の限界とみたのではないか、と考えてみたのである。もちろん何の証拠のない仮説ではある。
しかし、小生にはよく分からない記述もある。本編P159には、「大口径砲弾にはCr炭化物の硬質層は無力なばかりか熱処理時に亀裂を発生しやすくするので、金と手間のかかる浸炭を省くことにした。・・・また焼き入れで表面層を硬化する方法を考えた。これが「VH甲鈑」で「大和」の建造に貢献した。」とある。ここで本編P160によれば、NVNCとVHは成分が全く同じで、鍛造その他の工程が同じだとすれば、違いは上述のように、焼き入れして表面を硬化させているか否かであると考えられる。
NVNCが均質甲鈑であるという意味が、浸炭やVHのように焼き入れによる表面硬化もしていないものとすれば、成分が同じだから安価となるはずである。安価であり、14in以上の大口径砲弾を破壊してしまう、NVNCの方がVHよりも戦艦の装甲鈑としては適しているのではないか、とも考えられる。小生は到底両書を読み切れる知識も経験もなく、字面だけで、それも一部読んだだけで考えたのである。この仮説に自信が持てない所以である。どなたかにご教示いただけたらと思う次第である。
⑨空母の脆弱性
ミッドウェーの3空母は攻撃隊の準備中にわずか2~3発の1000ポンドないし500ポンド爆弾の命中で炎上沈没した。これは日本空母の脆弱性に起因するとみられることが多いが、根本的には一般的な空母の脆弱性によるものであろう。
米海軍にも同様の例があるからである。正規空母エセックス級のフランクリンは、沖縄戦で銀河または彗星の通常攻撃により、2発の爆弾が命中した。この爆弾は500kgの可能性もあるが、250kgだったと推定されている。爆弾は燃料と兵装を満載した艦上機のいる格納庫で炸裂して、火災を起こして沈没寸前にまで至った。
まさにミッドウエーの南雲艦隊の再現である。兵員の決死のダメコン作業で辛うじて沈没をまぬかれたが、7百人余の戦死者を出している。ミッドウェーの四空母のうち何隻かでさえ、曳航して沈没させないことも、周辺の状況によっては可能であった。しかも世界の艦船(`12年6月号)によればフランクリンは火災による船体の歪がひどく、修理には新造と同程度の経費がかかるため、修理は放棄された。沈没していないだけで全損したのである。米軍のことだから船体の損失よりも多くの人員の喪失に恐怖したことだろう。
元々ダメージコントロールに優れている米空母が戦訓によって更にタフになっていたはずなのに、わずか2発の250kg爆弾によってこれだけの被害が出るのである。空母バンカーヒルにも零戦二機が2発の250kg爆弾を命中させて、大火災となり、死者と行方不明400名近くの損害を出している。軽空母だが、彗星が投下した、わずか1発の500kgないし250kg爆弾が格納庫で爆発して、大火災を起こして沈没した。
つまり、米空母ですら、爆弾が少数でも命中すれば、かなりの損害が出ている。しかも、日本軍の散発的な攻撃によってである。多くの米空母が損害を免れていたのは、徹底した早期発見による護衛戦闘機の活躍と優秀な対空火器システムとによる、防空体制のおかげである。それでも爆弾が命中すれば前述のような大きな被害を出していたのだから、当時の空母は一般的に、被害に対して戦艦に比べはるかに脆弱であったと言える。
⑩日本の戦艦改装と航空機の性能向上の不合理
日本の戦艦は、金剛級から、長門級まで竣工から何回も改装されていることが知られている。主機の換装ということさえ行われている。特に外観上明瞭なのは、艦橋構造物が頻繁に改装されていることである。ただし欧米の戦艦の艦橋の大改装の場合、コンテ・カブール級のように、三脚檣から近代的な塔型艦橋に改装しているのに対して、基本の三脚檣、あるいは長門型のように7本柱の基本はそのままに、次々と艦橋施設を追加し続けていることである。
このため、最終形は極めて複雑な構造となり、パゴダマストと呼ばれている。この方法は、基本構造が変わらず、少しづつ改装していくことができるため、一気に塔型に変えてしまうよりは、その時々に於いては簡単である。その代わり、最適な艦橋内配置が出来ないことと、構造的に無駄が多くなる欠点がある。すなわち同じ機能を保持するためには重量の無駄が多くなる。
例えば艦橋トップに追加された測距儀を支えるために甲板から巨大なガーダーを追加したと説明されている。だが、このガーダーは、実際には、測距儀だけのためではなく、小改造の繰り返しで重くなった艦橋を支える三脚支柱の強度が不足になったためでもあろうことは想像がつく。小改装の繰り返しであのパゴダマストを作るのは、一回づつの作業は容易ではあるが、最終的には効率が悪い。
あれだけ高い艦橋でトップヘビーにならないのは、各フロアには前面と側面の一部にしか壁がない、鋼板を断片防御すらない薄っぺらのものにしている、などの無理を重ねているからであろう。一見塔型艦橋のように室内に艦橋施設が収まっているように見えるが、実際には、風除け程度のもので各フロアはおおわれているのに過ぎない。またフロア面積や配置も効率が悪いものになって、指揮には不便だろう。各フロア艦の移動も効率が悪い。
それならば、古い艦橋を撤去して新しいものを設置し直すのは、鋼材の無駄になるのだろうか。当時の日本の鋼材はアメリカから輸入したスクラップが使われている。つまり、撤去した艦橋は別な用途に使えるから、トータルとしての鋼材のロスはない。それならば、英米仏伊海軍が行ったように、小改装での対応はある時点で見切りをつけて、艦橋の改装は最適な構造となるように、全面的に改設計すべきなのである。
それなら飛行機改造の考え方はどうか。これも米英独ソ仏伊の行きかたと日本の場合は大きく異なる。日本の場合は、極力改造の幅を少なくして、エンジンの大幅パワーアップの場合などは全く新設計にしている。戦艦とは逆なのである。確かにエンジンにあった最適な設計をし直すことは、全てにとって望ましいことである。しかし、これにもデメリットはある。完全な再設計であるために、風洞実験など基礎的な設計過程を一からやり直さなければならない。生産に使う冶具の多くは全く新規に作らなければならない。
つまり新設計は実に労力と時間と資源のロスが多いし、時間もかかるのである。一品作りの戦艦と、大量生産の相違がここに現れている。冶具にしても、当初設計のものの70%が使用できれば、量産体制に混乱はない。更に一年後70%の冶具が共用できる設計変更をすれば、別な機体と同様に姿を変えて性能の向上が可能になるが、やはり生産体制の混乱は少ない。ソ連のラボアチキン戦闘機シリーズは、La-3からLa-11まで、設計変更を繰り返し、La-3とLa-11を比較すれば、機体のあらゆる部分で共通する部品はないであろう。しかし、La-3からLa-11に至るまでの途中経過を見れば、連続性はあるのである。
つまり戦時中に新規設計を行うと、大幅に性能向上はするが、施策の労力や生産体制の整備が大幅にかかり、戦争に間に合わない可能性が大きい。次善の策として既存の機体の設計変更を行えば、戦争に間に合うのである。現に日本軍で大東亜戦争で開戦後に開発を開始したものは多数あるが、実戦に間にあったものは彩雲だけである。この点は他の国で大同小異である。
Me109もスピットファイアも戦前のかなり早い時期に開発され、エンジンの大幅な性能向上を含む、設計変更を次々と続け、最後まで第一線で活躍し続けた。両機より後に開発されながら、エンジンは同一のもののわずかな性能向上型にとどめ、細々とした設計変更を続けて旧式化していった零戦とは大違いである。エンジンを栄から金星に大幅な出力増加をさせても、重量増加などで、大した性能向上が期待できない、と考えられていた、という説を述べる人もいる。
だが、自著「零戦」で「・・・最後型となった五四型丙は二年も早く生まれ、恐らくはその後もさらに改良されて、零戦は依然としてその高性能は誇っていたかも知れない」(昭和五〇年新装改訂版P262)と悔やんでいるのは、他でもない、設計者の堀越二郎技師自身なのである。陸軍は一式、二式、三式、四式、五式戦闘機と毎年新作の戦闘機を採用し続けた。紫電シリーズと五式戦が、日本の数少ない例外である。
欧米での例外は、米海軍の戦闘機である。F4F、F6F、F7F、F8Fと次々と新規設計を行っている。しかも、F6F、F8Fは基本的に同じエンジンを搭載している。どちらも中途半端な機体であったことは、両機とも戦後に大きな設計変更もされずに、放棄されて、F4Uだけが改良を繰り返して延命されている。
日本の戦車や軍用機は、戦前戦後共通して、設計変更により性能向上を行うことを嫌う傾向があるのは別項で述べたので、ここでは述べない。
⑩戦艦の砲撃術について
「戦艦十二隻」という本がある。その中で旧海軍の黛治夫元大佐と吉田俊雄元中佐が、戦艦の射撃について書いている。その中の、吉田氏の射撃砲に関する記述は意外であった。黛氏も吉田氏も砲術の専門であり、吉田氏は後述のサマール沖海戦で、大和の副砲長をしていたというのである。
戦艦が射撃をするには、発令所にある射撃盤という大型の計算機があって、入力するデータは、目標までの距離、目標の進路、速力、自艦の速力などである。これによって、射撃諸元を計算して、指揮所と各砲塔に電気信号として送信する。(P124)
ところが、敵艦の進路、速力は極めて重要な要素であるにもかかわらず、自艦上から測定する装置はまったくない、というのである(P130)というのには驚いた。その前段で、30kmの距離で敵艦が30ktで走っているとすれば、弾着までに900m動いていると、書いているのである。方向も分からないのだから、この誤差はさらに拡大する。
進路と速力を補正するのには、飛行機の観測によるか、周囲の状況から推定するしかなかったというのである。推定とは、目視により構造物の向きで進路を、艦首や艦尾の白波の立ち方で、速力を判断する、と言うことである。日本海軍が零戦の滞空時間を恐ろしく長く取って、観測機を援護しようと考えたのは至極妥当なことであった。
ところが、栗田艦隊は比島沖海戦の際に、早期に艦隊の全観測機を陸上基地に帰してしまった。吉田氏は、サマール沖海戦の際に大和は初弾から命中弾を与えて敵空母を撃沈した、と書くが(P135)、事実は、大和も長門も一発の命中弾も与えていない。スコールや敵駆逐艦の煙幕展張の妨害にあっているが、観測機があれば、支障なかったであろうし、そもそも護衛空母を正規空母と見誤ることもなかったであろう。
ここで疑問に思うのは、米海軍の射撃方法である。米海軍のMk37射撃指揮装置は対水上、対空兼用であり5in両用砲用のものである。対空射撃では日本の九四式高射装置に比べ、格段の高成績を挙げている。対空用で精度を上げるには、飛行機の進路や速度も知らなければならないから、当然Mk37はこれらのデータをレーダー以外の何かで得ていたはずである。戦艦霧島の撃沈はレーダー射撃によったと書いてある資料があるが、米軍とて当時、レーダーは補助手段であって、厳密な意味でのレーダー射撃はできなかった。
古本であるが丸スペシャル「砲熕兵器」によればMk37の計算機は、目標距離11,000mでの射撃データ計算時間は10秒であったとされている。例えば、飛行機の位置の何箇所かのデータから、飛行機の針路や速度を計算し、砲弾の到達時点での飛行機の位置を計算していたのであろう。アナログコンピュータであるにしても、10秒は長いが、これは観測データ入力から計算機の出力の間に人間が介在していることが原因ではあるまいか。
遥かに高速であり、三次元の動きをする飛行機で、このようなことが可能であれば、鈍足かつ二次元の動きしかしない、艦艇ではより容易であったろう。そう考えるのはMk37が対水上用も兼ねているからである。とすれば、5in用のMk37ばかりではなく、同時期の戦艦の主砲用の射撃指揮装置も同様に、敵艦の進路と速度も得ることができていたのに違いない。もしそうならば日米の戦艦の主砲の命中率には大きな差が出る。特に初弾においては甚だしいであろう。
戦艦十二隻の中で黛氏は、米海軍の砲術進歩の調査を命じられて、昭和九年に渡米留学し、昭和十一年七月に帰朝したとしている。この間に米退役軍人から得た「一九三四年度米海軍砲術年報」を分析すると、米海軍の大口径砲の命中率は日本の約三分の一であった。その原因は散布界の過大にあることは間違いない(P239)としている。これは、この時点での日米の射撃指揮装置自体に優劣はなく、命中率の差は主砲の散布界の大小だけによる、ということになる。軍艦の射撃訓練は、固定目標ではなく、艦艇で標的を曳航していたのである。ということは、この当時米海軍でも、計算機で敵艦の針路や速力を得てはいなかったということであろう。
ところで「砲熕兵器」によれば、Mk37は昭和十一年に開発が開始され、昭和十四年に実用化の目途がついたとされる。黛氏が米国から帰ったころ開発が開始されていたのだから、その後日米関係が悪化の一途を辿ったことを考え合わせると、それ以後の米国の砲撃術の情報は入ってこなかったのであろう。従って、Mk37と九四式高射装置の差と同様の差が、日米の戦艦の主砲の射撃指揮装置にもあったとしても不思議ではない、というのが小生の今のところの結論である。
小生は昭和五十二年刊行の黛氏の「艦砲射撃の歴史」という本を入手した。これにも昭和十一年ころまでの日米の戦艦や重巡の大口径砲の射撃についての記述がある。昭和十五年ころのデータについては、戦艦に関しては、米国のものは無いようで、読む限り海自の元海将から最近(多分昭和五〇年ころ)米海軍当局から入手した米重巡の20cm主砲のものしかないようである。(P306)つまり黛氏の米海軍の戦艦の主砲の砲術についての知識は、昭和十一以降は全く欠落しているということになる。昭和十一年以降に改良がなされていたとしても、分からないのである。
艦砲射撃の歴史は、実はほとんど読んでいないので、今後読み解けるものがあるかもしれないが、このような訳で多くは期待できないと思う。日米戦の新戦艦のノースカロライナ級、サウスダコタ級、アイオワ級と大和級の主砲の射撃指揮装置の相違について知りたいと思う所以である。
⑪米空母の抗堪性
現代の米空母は簡単には沈まない。支那軍がその点を勘違いしている可能性は、大いにある。大東亜戦争の日本軍機の猛攻によって、フランクリンやバンカーヒルといった正規空母は、甚大な被害を受けながら沈没は免れた。とは言ってもフランクリンは修理のための調査の結果、火災による高熱で、船体の鋼材に全面的に歪が発生していて、修理するのに新造と同じ費用がかかってしまう、というので修理されなかった、と雑誌「世界の艦船」に報じられていた。
戦死者も700人以上出している。戦傷者はその倍はいたろうから、乗員のほとんどが、死傷したことになったのであろう、甚大な損害であった。沈没した船でも救助によって、犠牲者がこれ以下であった例も多かっただろう。
しかし、沈没したに等しいが、沈没しなかった、ということは戦意の維持にとっては大きいのである。南太平洋海戦でホーネットが沈没して以降、日本軍機による正規空母の撃沈はない。最大のもので、軽空母プリンストンは特攻によって沈没している。プリンストンは軽巡から設計変更したもので、正規空母とは言えない。
ただし、1発の500kg爆弾の命中により、大火災を起こし、味方から雷撃処分を受けた。これは被害が大きかったのはもちろんであるが、火災により戦闘が不利になることを考慮した結果とも言われている。
それ以後原子力空母になってから、船体は大型化し、防御についても鋼材以外の特殊装甲まで使用されている。何よりも大東亜戦争で日本軍機の猛攻を受けた結果、ダメージコントロールのノウハウが蓄積されたのは大きいであろう。中国軍が米空母を攻撃するとしたら、潜水艦か航空機のASMミサイルによる攻撃であろう。
中国の潜水艦が辛うじて魚雷を命中させても、致命傷に至る前にASWの攻撃で撃沈される。また航空攻撃は、旧ソ連のようにASMによる飽和攻撃を行うまでの戦力はなかろう。結局防空陣により撃退される。現代の米空母自身の抗堪性も大きい。支那軍など問題ではなかろう。
⑫カタパルトとスキージャンプ
別項で日本海軍の航空戦艦伊勢級のカタパルトは、米英のように飛行甲板上の艦上機をそのまま射出できず、台車に載せると言う運用上の制約が多い方式であることを書いた。ドイツの未成空母のグラーフ・ツェッペリンはカタパルト装備とされていたが、図面を見る限り日本海軍と同様に台車方式のようである。異色なのは英国空母のスキージャンプ方式である。これなら、機体もいじる必要はなく、高度な技術の蓄積が要るカタパルトも不要だと飛びついたらしいのが旧ソ連である。
だが、ソ連製空母がスキージャンプ方式を通常離陸方式のCTOLの発艦に採用したのは感心できない。カタパルトを開発使用した経験がある英海軍がスキージャンプ方式を発明採用したのは、艦上機が垂直離着陸機(VTOL)のシーハリアーだったからなのである。シーハリアーは垂直離陸するためには、爆弾等の兵装が制限される。兵装の搭載量を増やしたり、航続距離増大のために燃料搭載量を増やすためには、垂直離陸を諦めて短距離離陸にしなければならない。
もちろん兵装や燃料を消費して軽量となった状態なら垂直着陸できる。搭載量を増やすと短距離離陸しなければならないのは、離陸速度の不足ばかりではない。ハリアーの主翼は離着陸にはいらないから、CTOL機に比べかなり小さい。これは空気抵抗が小さいから高速飛行には有利である。逆にいえば、ある程度の速度がないと機体重量に釣り合う揚力が発生しない。
ハリアーの垂直離陸時の揚力は全てエンジンの鉛直方向の推力である。従って離陸重量が重くなると不足するのは、この鉛直方向の推力である。そこで爆弾などの搭載量を増やすには、短距離でもいいから滑走して主翼やフラップによって揚力を補うことが必要である。
それともうひとつ、別に鉛直方向推力を補う方法があればよい。スキージャンプ台は大きな傾斜をしているから、台を通過することによって、鉛直方向のベクトルの力が機体に与えられる。それがエンジンの鉛直方向推力を補うのである。
ところがロシアや中共海軍のように通常離着陸機(CTOL)で搭載量が大きいと短距離しか滑走していないから、スキージャンプ台を過ぎても失速速度を十分に超えておらず、台で上に放り出された勢いが残っているだけだから、失速して海面上に降下してしまう。それを防ぐには、飛行場から離陸する場合より、艦上機の搭載量を制限しなければならないのである。もちろんスキージャンプで与える垂直方向速度ベクトルは離陸の補助にはなるが、カタパルトに比べて充分ではない。
このように、元々スキージャンプ台はハリアーの搭載量を大きくするために発明されたのであって、カタパルトの代用品ではないのである。現に英国のスキージャンプ台を備えた、最新鋭の大型空母クィーンエリザベスは、短距離離陸垂直着陸機(STOVL)機としてF-35Bを運用する設計である。前述のように現代の重い艦上機を短距離で離陸速度まで加速するカタパルトは、高度な技術を必要とする。
ロシアや中共は、当面カタパルトを実用化できないから、スキージャンプに飛びついたのである。従ってCTOLの戦闘機や攻撃機の運用は極めて制限が大きく、一機当たりの打撃力が小さい。その上遼寧の場合は、動力がオリジナルのものが使えなかったので、カタログデータの30ktは到底出ないと見られている。なんちゃって空母と呼ばれるゆえんである。
⑬日本海軍は米海軍に勝てない
倉山満氏の「大間違いの太平洋戦争」と「負けるはずがなかった大東亜戦争」の二著が典型であるが、倉山氏には日本軍は米英軍より強かった、という考え方がある。例えば後者には「マニラまではるばる太平洋を横断して艦隊決戦をやったところで、対米七割なら日本が勝つと日米双方の軍人が思っている。バトル・オブ・ブリテンだって結局は防者優勢なのと同じです。(P177)」
陸軍はさておき、小生は日本海軍は米海軍には、到底歯が立たなかったと考えている。倉山氏の日本海軍優勢論は、海軍の戦闘システムや技術が、第一次大戦当時のもので止まっていたというのが前提である。
第ニ次大戦時点での米海軍が日本海軍より、技術的に圧倒的に優れていたということを一部の例で説明したい。海軍と言うのは、兵士の敢闘精神や技量は当然として、ベースには技術力が必須である。海軍の戦力とは、その時の技術の粋を集めたものである。技術力の優劣が勝敗を決定する。小生は米海軍が急激に変貌して優秀となっていったのは、第一次大戦の経験以降である、と考えている。また、大東亜戦争初期の不利な時期にも米海軍軍人は、優れた敢闘精神を発揮したことが伝えられている。
まず戦艦である。よく、世界一の戦艦大和とアイオワが一対一で戦ったら、という仮想話が軍事雑誌などに書かれている。主砲の単位時間投射弾量や装甲や速度の差などの、巷間に流布されたカタログデータを比較して、大和の勝ちというのが大抵の落ちである。
ところが、元自衛官の是本信義氏は、アイオワの完勝と断じている(海軍の失敗)。アイオワは初弾データからの距離と方向の修正を同時に行うので、初弾命中が3分45秒で済む確率が高い。大和は試射3回8分15秒で初弾命中する確率が高い。この時間が短ければ、初弾が先に命中する可能性が高いばかりではなく、艦の進路などの変化の影響が少ないので、確率の差は更に広がるというのである。
さらに射撃データを計算し、砲を動かす射撃盤の性能に格段の差があるというのは、この想定外であるというのである。そこで、射撃盤の文献を調べた。当時の射撃盤自体は機械式のアナログコンピュータであるが、計算データで砲の方向と伏仰角を制御のため、日英はステップモータを使っていたのに、1920年に米海軍はセルシンを全面的に適用した新砲火制御システムを完成させた。(Vol.32、No.12・O plus E「第9光の鉛筆」による)セルシンはステップモータに比べ、精度と応答速度が格段に優れている。
セルシン自体は、射撃盤本体ではないが、射撃盤自体にも米国製には一部電子部品が組み込まれた高度なものでなかったかと小生は考えている。しかし、前述の文献には、日・独・伊の射撃式装置には、英B&S社の技術が反映されている、と書かれているが、米国を含め射撃盤の詳細は分からない、と書かれている。
大和とアイオワとの戦いには、セルシンとステップモータの差もさらに加わる。要するに日米には砲のトータルの射撃管制システムに格段の差があった。海軍の黛治夫氏が昭和10年ころ渡米して演習データを見たら、日本側の主砲の命中率は米の3倍だったと報じている。戦前の米海軍の最新型のコロラド級の竣工は1921~1923年であるが、先の文献によれば、最初に新システムを搭載したのは1923年に就役したウェスト・バージニア(コロラド級の一艦)だから、他のコロラド級を含む米戦艦には、新システムの搭載が間に合わず、黛氏が見たのは古いシステムの艦のデータだったのであろう。
だから、黛氏のいう日米の命中率の差は、射撃管制システムの差ではなく、ほとんど練度の差であったろう。だが、少なくとも1941年以後竣工したノースカロライナ級以降の10隻は間違いなく新システム搭載で、真珠湾で被害を受けて大改装された旧式戦艦数隻も、新システムに変更していた可能性は大である。
ちなみに光の鉛筆を引用した花園史学(2013年11月号)には、日本海軍が「セルシンモータ」を採用した、と書かれている。ところが引用元の光の鉛筆には、日本の多くの文献には、金剛にセルシンが採用されていると書かれているが、実はステップモータであったと否定しているのは、花園史学の筆者の読み忘れであろう。光の鉛筆の記述が間違いである、と書かれていないからである。また、この件についても後述の両用砲についても、英海軍は採用していないから、案外米英の技術協力は進んでいなかったのである。
次は米の海軍航空戦技術の差について考察する。是本氏の著書(1)には「・・・アメリカ海軍は、日本海軍の真珠湾攻撃を手本にし、急遽、戦艦主体の編成、戦法などを空母機動部隊中心に切り換えたというのが通説として定着しているが、それはまったく違う。アメリカ海軍は、空母機動部隊の打撃力の有効性を早くから(1930年代の初頭)認識し、空母に護衛の巡洋艦、駆逐艦の戦隊を配属した任務部隊として運用していた。(P51)」と書かれている。
このことは、ハードウエアの面からも例証できる。是本氏によれば(1)、日本の12.5cm高角砲と米軍の5in.両用砲の命中率は0.3%対30~50%という驚異的な差があったという。現に氏が戦後米軍の5in.砲を射撃したところ、初弾から命中して驚いた、という。当然レーダー照準ではあるまい。小生は父の影響でずいぶん戦記を読んできた。読めば読むほど不思議に思えてきたのは、日本機のパイロットは米艦を攻撃すると、駆逐艦ですら猛烈で正確な対空砲火で反撃され、接近すれば確実に撃墜されてしまうと書かれているのに対し、米機は戦艦にすら悠々と機銃掃射して、対空要員を倒したのに日本の対空砲火は手も足も出なかったと、正反対のことが書かれていたことである。
これも前述の命中率のおそろしい差をみれば納得できる。両用砲と言ったが、これは対水上艦兼用の高角砲である。駆逐艦を比較すると米艦は対空用火器管制システムを装備し、両用砲を持っているのに対して、日本では対水上用砲と対水上用火器管制システムしか持たない。つまり米駆逐艦は防空能力を持つのに、日本艦は機銃しか防空用にしか使えない。駆逐艦は戦艦や空母の対空護衛には全く使えない。元日本海軍の関係者は駆逐艦秋月級の防空能力を自慢するが、大量生産されたごく普通のフレッチャー級にすら、遥かに及ばないのはこれで理解できる。
丸スペシャルNo.19駆逐艦朝潮型秋月型には「・・・いかに高角砲のメカニズムが優れていても、レーダー付き射撃照準装置と使用砲弾にVTヒューズを欠いたことは、第二次大戦における一流の防空艦としての条件に満たなかったというべきで、おそらく大戦末期にあっては米海軍の通常型駆逐艦であるフレッチャー級にすら、その実質の防空能力は数段劣っていたものと評さざるを得なかっただろう。」とある。
これも典型的なレーダー、VT信管神話である。第二次大戦当時のレーダーは現代で言う射撃照準能力は持たず、現代の観点で言えば最良のものですら、捜索レーダーのましなものに過ぎなかった。光学式射撃管制システムにおいても日本海軍では、遥かに劣っていたのである。いくらVT信管があっても、15m程度以内に砲弾を通過させなければ有効ではないから、射撃照準能力の劣る日本のシステムでは、VT信管はほとんど威力を発揮できない。しかもマリアナ沖海戦時点でも、5in砲弾の4分の1しかVT信管は供給されていなかったし、大戦終了まで5in未満の砲弾のVT信管は開発されていなかった。だから日本はVT信管を持たなかったから不利だったと言うような記事も日本でよく見られる、秘密兵器神話である。
さらに両用砲を持つ駆逐艦が計画されたのは、ロンドン条約を契機として計画された、ファラガット級(1934年竣工)を嚆矢とする。この時期は是本氏が「アメリカ海軍は、空母機動部隊の打撃力の有効性を早くから認識」していたという時期と符合する。それ以降、ほんの一部の例外を除いて駆逐艦の主砲を両用砲としている。特に初期のものは対水上用専用に比べ重量が重く、対艦船用としては難点があったとされる。それでも、欠点をおして採用したのは、航空戦重視の現れである。
日本海軍は、ワシントン条約以降逐次制限のない駆逐艦を整備してきた。一方の米海軍は、第一次大戦参戦のため、大量の駆逐艦を保有していたため、日本海軍に比べ年々大量の駆逐艦が旧式化していった。ロンドン条約では駆逐艦などの補助艦艇にも制限を加えた。その結果米海軍は、旧式駆逐艦を軍縮の美名のもとに大量に廃棄し、両用砲と新型の火器管制システムを備えた新型駆逐艦を整備した。ロンドン条約で補助艦艇の制限がされたのは、このような米海軍の事情が大きく影響しているという説もある。
日米の差は動力にもある。ほとんどの軍艦に使用されるボイラは、蒸気の圧力と温度が高く効率の良いものを米海軍は採用しているため、馬力当たりの機関の容積や重量は軽量化されている。砲や魚雷の数などのカタログデータこそ、日本海軍の駆逐艦の方が優れているように見えたが、実質的戦闘能力は米海軍の方が優れていたのである。当然戦艦や巡洋艦でも同じことである。
これらはハードウエアの差の一部の例に過ぎない。日本海軍が、日本海海戦時とほとんど進歩がなく、司令官、艦長、参謀などの個人的連携によって戦闘を指揮していたのに対して、米海軍はソフトウエアとして現代にも通じる、C3Iといった戦闘指揮システムを開発していた。小生は知識がほとんどないので、これ以上言及しないが、要するにヤマ勘的戦闘指揮と情報を的確に分析判断する系統的組織的戦闘指揮方法の違いである。
倉山氏は、艦隊決戦では勝てないから、米海軍は通商破壊しかないと結論した(2)(P178)と書くが、世界が通商破壊の恐ろしさを認識したのは第一次大戦である。ところが日本海軍もそれを知りつつ、準備出来なかったのは、艦隊決戦に回す戦力ですら余裕がないのに、護衛艦隊などと言う後ろ向きの装備のゆとりがなかったからだろう。もちろん倉山氏の言う民族性の差もあるだろう。
以上のようにガチンコの艦隊決戦をやっても大東亜戦争時点では、日本海軍は米海軍に勝てるはずは、なかったと思う。もちろん陸軍の話はさておく。ちなみに英海軍は空母本体は立派だが、ほとんどまともな艦上機を開発できず、日本海軍の空母の敵ではなかったと思われる。しかし自前でではなく、米国製艦上機でなんとかしていた。
ドイツ海軍との戦いでも、数でねじ伏せるしかない、効率の悪い最悪の戦いをしている様子を見ても、主力艦による水上戦闘には、日本海軍には歩があるが、通商破壊対策で鍛えた、対潜能力だけは圧倒的に日本海軍の負けである。またアメリカよりも先を行っていたレーダーもあるが、英海軍が有効に活用できていたのだろうか。
(1) 日本海軍はなぜ敗れたか
(2)負けるはずがなかった大東亜戦争
6.戦争論
①なぜ北ベトナムは米軍に勝てたのか
なるほど局部的な戦闘で勝てなかったとし、被害は北が桁違いに大きかったとはいうものの、北ベトナムが米国に勝利したのは間違いない。戦争は戦争目的を達成したものが勝利者だからである。北の目的はフランスに代わった米軍をベトナムから追い出し、南を併呑することであった。米国はもっと消極的で、当初の民主的な選挙による南北の統一から、南ベトナムの維持に後退したのである。
だが産経新聞平成17年6月4日の正論、佐伯彰一氏のように「・・・北ベトナムの勇猛果敢な戦闘意欲と持久力は、おそらく世界戦史に特筆されるべき偉業に違いない。」と考える人は多数派であろう。すなわち、どういう立場であれ北ベトナムの勇敢さが対米戦の勝因とみなす。だが戦闘意欲だけで戦争に勝てればだれも苦労しないのである。
父祖のために言うが、体当たり攻撃まで実行した日本の戦闘意欲はベトナム人に勝るとも劣るものではない。それでも日本は勝てなかったということと、北ベトナムの敢闘したために勝ったという見解は明らに矛盾していることを指摘するのを寡聞にして聞かない。日本が援蒋ルートを遮断するのに苦労したように、米軍は執拗にホー・チ・ミンルートを攻撃したが失敗した。
陸路海路から北ベトナムはソ連と中国からふんだんな武器物資の援助を受けていたのである。陸路を断つことの困難はもちろん、容易なはずの海路すらソ連籍の補給艦船であるがゆえに攻撃できなかったのである。
その代償にベトナムはシベリアの奴隷労働に国民を提供し、カムラン湾を軍港として提供した。中国に対しては、その後の関係悪化もあって一切の負債を踏み倒した。ベトナムを懲罰すると称して侵攻してきた中共軍も排除した。中国は武力を持ってしてもベトナムから負債を取り立てることはできないと証明してしまったのである。
要するにベトナムは中ソのふんだんな武器物資の援助の下に多大な損害を出しながらも勝利した。日本は孤立無援の中を敢闘したのである。繰り返すが、戦闘意欲だけで勝てれば苦労しない。日本がベトナムと同一の補給を受けることができれば、大東亜戦争に勝利したことは疑いない。いくら飛行機工場を破壊されても日本軍に戦闘機は次々とふってわいたらどうだ。
いや北ベトナムには破壊すべき航空機工場すらない。それどころか北ベトナム空軍機と称して、中国やソ連軍の兵士の操縦する戦闘機が米軍機を迎撃していたことさえ稀ではない。中国から飛来するのであれば、米軍がいくら北ベトナムの飛行場を破壊しても無駄である。米軍はそういう国を相手にしていたのである。米軍は地上侵攻できず無尽蔵の武器を相手にしていた。
南では近代戦の困難なジャングルで米軍兵士の被害を増やしていった。相手は人的被害を恐れず、人的被害を恐れる米軍が逐次死傷者を増加していけば、米国に厭戦気分が広がるのは当然である。日本ですら四年の支那事変で厭戦気分が広がって言った。
米軍はその倍以上の期間をたたかったのである。もっとも不可解なのは、日本軍は補給を軽視していたと敗因に挙げる人すら、ベトナムのふんだんな補給を無視して民族主義の勝利だとか、敢闘精神だとか精神訓話を言い出し、大東亜戦争における日本に比べたベトナムの圧倒的有利さについて言及しないことに大いに疑問を抱くのである。
軍艦メカ3日本の空母、潮書房・昭和56年
②国民は敗北を知らされていなかったという嘘
大本営発表の虚偽戦果により国民は敗北を知らされていなかったと言う。嘘である。広大に広がった太平洋の占領地域。昭和18年になるとその占領地域では日本軍が次々に玉砕していく。アッツ島、サイパン島、硫黄島など数限りない。玉砕とは全滅である。全員戦死である。すなわち完全な敗北である。国民が敗北を知らされていなかったとすれば玉砕を知らされていなかったのである。
そうではない。玉砕の文字は次々と新聞に踊りラジオで絶叫されたのである。そして広大な占領地域は周辺から次々に玉砕して次第に本土に近づいてくる。占領地を取り返されているのが地図入りで知らされる。どう考えても敗北の報道である。それでも国民は敗北に気付かなかったというのか。日本国民はそんな馬鹿だったのか。人を馬鹿にするのもいい加減にするがよい。
たとえ軍艦をたくさん沈めたの飛行機をたくさん落としたのといわれても、それでも米軍はどんどん本土に迫る。そうしたら相手はそんな大被害をものともせずに、次々と攻めてくることのできる恐ろしく強大な敵だということになるではないか。台湾沖航空戦で大戦果をあげたと報道された。すると敵は台湾にまで迫ったというひどい事態になったのと考えるのが普通である。
大本営発表をうのみにして沈めた軍艦の数を累積するがよい。当時の国民はアメリカの軍艦の数については日本海軍との比較でよく知っていた。すると戦前米軍が持っていた軍艦の何倍も沈めたことになる。ところがまだ米軍は攻めてくる。アメリカにはすごい生産力があると考えるのだ。つまり大本営発表を鵜呑みにすればするほど、日本は大変なことになっていると分かるのだ。
昭和天皇は神風攻撃の報告を受けて、そこまでしなければならないのかと絶句したと伝えられる。航空機による通常攻撃ではだめだから体当たりしなければならないのだ。昭和天皇の感覚は正常である。国民は体当たり攻撃の報道を冷静に受け止めた。それは国民がむしろそれまでの報道から、この戦争は尋常な手段では勝てないということを知っていたことを意味する。国民は日本が敗北を続けていることを報道により知っていたのである。国民は敗北を知らされていなかったと言うのは、国民の常識を馬鹿にしているのだ。
③戦陣訓への誤解あるいは嘘
戦陣訓に「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪過の汚名を残すこと勿れ」と書かれていたから日本兵は捕虜にならずに自決や玉砕を選んだ、と言うのが今では定説の如くである。同時に捕虜にならないよう教えられていたから、投降する連合軍兵士を虐殺するのだと言う。結論から言えば後者は明らかな間違いである。誰も引用しないが、戦陣訓には
苟も皇軍に抗する敵あらば、烈々たる武威を振ひ断乎之を撃砕すべし。仮令峻厳の威克く敵を屈伏せしむとも、服するは撃たず従ふは慈しむの徳に欠くあらば、未だ以て全しとは言ひ難し。武は驕らず仁は飾らず、自ら溢るるを以て尊しとなす。
ともあるのである。意味は説明しても分かろう。激しい戦闘があっても、戦闘が終え降伏した敵は大切に扱え、と言っているのである。戦陣訓を忠実に守って死ぬような人間がこの条文だけ無視するなどと言う事考えられない。日本軍の残虐行為、などと言う作られた物語を信じる人間は、たとえこの条文を知っていても無視するのである。
そもそも私には、開戦の1年前にもならない昭和16年の1月に作られた戦陣訓がその後の兵士の行動を決定するほど徹底していたとは信じられないのである。日本兵であった山本七平は、戦陣訓などは聞いたこともなかった、と言っているが、これが真相であろう。極端に現実的な日本人が、一片の紙に書かれた言葉のために、恐怖を乗越えて死を選択するのが一般的であったとは考えられないのである。兵士であった父から、金持ちの子弟が軍に寄付をして将校になるのをカネ少尉と言うのだが、実力がないからカネ少尉は部下に馬鹿にされて、かえってつらい思いをしたと言う。親が軍隊で楽をさせようと思ったのが災いしたのである。また、指揮が下手で威張り散らす上官は、戦闘中に後ろから来た弾で戦死する、という噂があったそうである。忠君愛国教育が徹底していたと言われる戦前の日本人も、このように現実的なのである。それだから一片の文章のために投降しない、などというのは到底信じられないのである。
戦陣訓が作られたのは長引く支那事変で兵士に厭戦気分が蔓延して軍紀が弛緩していたのを引き締めるためである。誰が言ったのか忘れたが、その中に捕虜になるな、と言う条文が入れられたのは、支那事変の最中に支那兵に捕縛された日本人が残忍な方法で殺害されていたからだ、ということを読んだことがある。支那兵が敵を殺害する方法は長く苦しみを与える残忍な色々な方法によっている。それならばいっそ自決した方が苦しくはない、と言うのは本当の話だろう。支那兵による惨殺体は目撃されており、日本兵は支那兵が残虐行為をするのが当たり前であることを知っていたのである。
それならば大東亜戦争の場合はどうか。私たちは、捕虜を人道的に扱う連合軍、捕虜を虐待する日本軍、と言う嘘を信じ込まされている。連合軍の残虐行為は別項で説明するとして、ここでは米軍の残虐行為を記述した事で有名な「リンドバーグの戦時日記」の関連部分を引用する。1944年の項である。
談たまたま日本軍将兵の捕虜が少ないという点に及ぶ。「捕虜にしたければいくらでも捕虜にすることが出来る」と、一人の将校が答えた。「ところが、わが方の連中は捕虜をとりたがらないのだ」
「*****では二千人ぐらい捕虜にした。しかし、本部に引き立てられたのはたった百か二百だった。残りの連中にはちょっとした出来事があった。もし戦友が飛行場に連れて行かれ、機関銃の乱射を受けたと聞いたら、投降を奨励することにはならんだろう」
「あるいは両手を挙げて出て来たのに撃ち殺されたのではね」と、別の将校が調子を合わせる。・・・中略・・・
わが軍の一部兵士が日本捕虜を拷問し、日本軍に劣らぬ蛮行をやってのけていることも容認された。わが軍の将兵は日本軍の捕虜や投降者を射殺することしか念頭にない。日本人を動物以下に取り扱い、それらの行為が大方から大目に見られているのである。われわれは文明のために戦っているのだと主張されている。ところが、太平洋におけるこの戦争をこの目で見れば見るほど、われわれには文明人を主張せねばならぬ理由がいよいよ無くなるように思う。・・・中略・・・ただ祖国愛と信ずるもののために耐え、よしんば心底で望んだとしても敢えて投降しようとしない、なぜなら両手を挙げて洞窟から出ても、アメリカ兵が見つけ次第、射殺するであろうことは火を見るより明らかだから。・・・中略・・・
海兵隊は日本軍の投降をめったに受け付けなかったそうである。激戦であった。わが方も将兵の損害が甚大であった。敵を悉く殺し、捕虜にはしないというのが一般的な空気だった。捕虜をとった場合でも、一列に並べ、英語を話せる物はいないかと質問する。英語を話せる物は尋問を受けるために連行され、あとの連中は「一人も捕虜にされなかった」という。
お分かりだろう。戦争の初期には日本兵にもかなり投降者はいたのだ。そして投降をしなくなったのは拷問され、あるいは殺されることを日本兵が知ったからである。米軍に拷問されたという日本兵の証言は知る限りない。ところが拷問は行われたのである。何故か。拷問の挙句に殺されたのである。そして生き残った捕虜は優遇された。こうして人道的な米軍と言う伝説が戦後流布されることになる。米軍は「文明ための戦い」の宣伝をしたのである。
太平洋の島々では日本軍は万歳突撃をして玉砕した、と言われる。しかし兵頭二十八氏は、ほとんど全員死んだのは、米軍が戦傷者を殺したからであるという。これは納得できる。万歳突撃して射撃を受けても負傷して戦闘不能となり生存する兵士は残る。通常の戦闘では戦死者の三倍程度の負傷者が出る。万歳突撃が死亡の比率が高くても同数の負傷者が死体の間に意識を失って倒れているという可能性は充分ある。米軍は負傷して呻いている日本兵にとどめを刺したのである。これについてもリンドバーグが書いている。
わずかな生存者は茫然自失の状態で坐るか横になっているかして、アメリカ兵を目にしても身じろぎさえしなかった。第一報では一名だけ捕虜にしたとあったが、後刻、歩兵部隊の将校が私に語ったところによれば、「一名も捕虜にとらなかった」という。「うちの兵隊きたら全然、捕虜をとりたがらないのだ」
説明の必要はあるまい。米軍は生存者を全員殺したのである。そして洞窟で無傷で残った日本兵は、米軍の残虐行為を恐れて自決した。これで玉砕、という訳である。戦陣訓に書いてあったから日本兵が捕虜にならなかった、という伝説が間違いであることが理解いただけたろう。
④ロシア海軍は日本に負けて崩壊した
日露戦争でロシア海軍は消耗を続け、日本海海戦でとどめを刺されて全滅し、その後の努力にもかかわらず再建されていない。主力艦を含めた艦隊をほとんど失って、再建できていないうちに、海軍、特に日米の主力艦が空母になってしまったために、時代の変化に追いつくことができなくなってしまったからである。
第二次大戦時に保有していた戦艦、はロシア帝国時代に海軍再建を目指して建造された、ガングート級4隻と英国から貸与されたアルハンゲリスク一隻と言う、帝政ロシア時代とは比べようもない有様だった。最新鋭戦艦として名前だけ有名になった、ソビエツキー・ソユーズは独ソ戦により建造が中止されて、再開されることはなかった。
その結果、戦後は海軍が対艦ミサイルを武器とする、日本の陸攻のような機種が、米海軍に対抗する海軍の主戦力となってしまい、まともな海軍の艦艇の編成ができなくなってしまった。確かにゴルシコフ元帥らの努力によって、大型艦艇による外洋艦隊や潜水艦の充実に努めた。
ところが、建造したのは、キエフ級「空母」である。正確には航空巡洋艦と言うのだが、大型の船体にYakのVTOL機やミサイル、艦砲など、あらゆる艦載兵器を満載した中途半端なものとなった。いつ本格的な空母を建造するのかと注目されたが、結局作られたのは、キエフ級を大型化したばかりではなく、スホーイのCTOL戦闘機を搭載した一見まともなクズネツオフ級空母である。
とはいってもカタパルトが開発できず、英国流のスキージャンプ台を使った。本来スキージャンプ台は、ハリアーのような垂直離着陸機の離陸時の搭載量を増やして短距離離陸できるようにしたものであって、カタパルトほどの能力はない。ハリアーは戦闘を終えて身軽になると垂直着陸できるのである。
だから垂直離着陸能力のないスホーイの艦上戦闘機の搭載量は、飛行場を使用する場合に比べ、かなり制限される。そもそも陸上機を艦上機に流用して成功した例がほとんどないのは、英海軍の失敗を見ればわかる。予算の制約から、またまた対艦ミサイルまで積んで、航空巡洋艦と呼ばれることとなった。秋月型防空駆逐艦が、不徹底にも魚雷まで搭載させられたことに似ている。結局ソ連はまともな空母を作れずじまいだった。
中国が、クズネツオフ級一隻を用途を誤魔化して買い、結局は空母遼寧に仕立てた。とはいっても、機関の不良からカタログ値の30ktより遥かに遅い、と言われているから、実戦には使えない。練習用か脅し用くらいにしか使えまい。遼寧の経験をベースにして、本格的な空母を建造中である、と言われるが、いつ完成して、いつ就役することやら。
潜水艦にしても、タイフーン級などという第二次大戦中の戦艦に近い巨大な排水量のものを建造するなど、ポリシーが不明である。要するに大きな軍艦を数を揃えて、大海軍に見せようとしたとしか思われない。
多量の対艦ミサイルによる、米空母への飽和攻撃は、イージス艦という新艦種による阻止手段を発明され、潜水艦の充実は日本のP-3Cの大量配備によってブロックされた。結局ゴルシコフの夢だった大海軍は、金食い虫となってソ連の崩壊を早めた一因となったのであろう。ゴルシコフがソ連崩壊を見ずに亡くなったのは、せめてもの幸せだったのかも知れない。
実にソ連を大海軍国にさせなかったのは日本であって、米国を大海軍国にしたのは日本であったのかも知れない。現代の米海軍の主力艦である、空母の艦上機の尾翼に旭日旗が描かれたものを見ることができるのは、米海軍が日本海軍と正面から戦って勝利したことの、誇りの象徴なのであろう。敗れはしたものの、日本海軍はよく闘ったのである。
7.大東亜戦争宿命論
大東亜戦争は必然であったか、必然ではなかったとすれば避けるべきであったかと問う。この問いは誰にも難解である。私は避けることはできたが必然であると考える。矛盾ではない。あの時点での開戦は避けえたであろう。しかし、避けえたにしても日米の軋轢の解消は不可能であるために、いずれかの時点で日米戦争としての大東亜戦争はおきたのであろう。
①植民地解放の時期
戦争の発生の時期の良し悪しからいえば昭和十六年の開戦は遅すぎとはいえても早すぎではない。第一は植民地解放戦争としての意義である。日本人の大多数は欧米の植民地政策を解消すべきであると考えていた。従って大東亜戦争の意義として植民地の解放があったのは偶然ではない。結果的にも全世界の植民地解放に直結したのは間違いはない。
それは結果論に過ぎない、ということの何とおろかな。産業革命を見よ。彼らは自己の飽くなき欲望の実現のために機械工業の革新をしたのであって誰一人として産業革命のために働いた者はいない。しかも産業革命には植民地獲得という、他の地域からいえば悲劇の上に成り立っているのである。日本の植民地解放に伴う犠牲の何とも少ないこと。しかも悲劇の多くは日本人の血であがなっている。欧米と組んで日本を妨害した愚かな支那などは論外である。
ところが解放された植民地には欧米の爪痕がはっきり残っている。インドとパキスタンの紛争、アフリカの内戦などばかりではない。多くの国がかつての宗主国の言語を公用語として使わざるを得ない。言語が民族の重要な構成要素であることから悲劇は大きい。これらの悲劇は植民地であった期間が長かったことによる。欧米諸国はキリスト教を強制し伝統的宗教を破壊したばかりではない。インドとパキスタンのように伝来の宗教の保護を口実にイスラムとヒンズー教の対立をおこして分離支配をした。
言語においても、一部に宗主国の言語を教えて高等教育を施して、支配の手先として使い、民族的言語は統一を阻止して分断を図るという悪質な政策をとった。現在の世界の紛争のほとんどは、共産主義による侵略政策の残滓を除けばほとんどが欧米の植民地政策による。植民地時代が短ければ禍根が少ないという意味では日本の開戦は遅すぎたとさえ言える。
②戦争の技術
第二は戦争の「技術」の問題である。兵頭二十八氏が日本の兵器は欧米の模倣を現在も脱していない指摘したのは正しい。多くの技術者が独自の工夫のごとく主張する日本の兵器も実は欧米の兵器のものまねの域を脱していない。この点はロシアとよく似た実情にあるどころか機械工業の先駆であるロシアに遅れをとっている。
ロシアは捕獲したB29のコピーに成功したが、日本はB17のコピーすらできなかった。Me163ロケット戦闘機のコピーをするのに日本は、ロケット技術と関係のない無尾翼まで生真面目にコピーしたが、ロシア人は意味のない無尾翼を避けて技術的なリスクを減らすという知恵をみせた。軍事技術の格差は軍事技術の発達が進むにつれて広がる。
レーダーの開発の遅ればかりではない。いや日本ではレーダーやVT信管といった派手な技術の差ばかりが取り上げられて、通常の技術の差についてはほとんど言及されない。だから今後に活かす反省とはならないのである。ソフトウェア、例えばC3Iと呼ばれる指揮統制システムや火器管制システムなど外見に表れない差異は大東亜戦争の時点でも相当に大きい。
これが端的に表れたのは防空システムであった。艦隊防空戦闘機、レーダーピケット、個艦防空火器の組み合わせによる優れた防空体制は知られているが、対空火器にすら大きな差があったことに注目する人は少ない。戦艦大和は甲板上を銃撃されるほど敵機に自在に跳梁されるほど、対空火器は無力であった。
ところが日本の攻撃機はたとえ防空戦闘機などの防衛網を突破しても、戦艦に対しては対空火器により容易に撃墜されてほとんど被害を与えることはできなかった。戦艦ばかりではない。巡洋艦、駆逐艦の防衛網さえ容易に突破できない。
戦艦は航空機に勝てないなどと簡単に主張する人たちも、この日米の差異にはなぜか気がつかない。このような差は日露戦争の時点ではあまりなかった。すなわち戦争の技術があまり進歩していない時点であれば、相対的に日本にはがんばる余地が多く、より有利であったと言える。欧米の戦争技術へのあくなき執念は日本などアジア諸国とは隔絶している。
③日米戦争は避けられなかった
結果論といわれようと、戦争は日本にチャンスをもたらした。現在の世界は自由貿易が原則である。独立国は二百前後あり独立国は国際法上対等の建前である。有色人種に対する差別は表向きできない。日本に経済的繁栄をもたらした。現在の日本人はこれらの前提が当然であると認識している。そして過去の日本の戦争についても、そのような条件があつた上で戦争を繰り返したと無意識に考えているのに違いない。戦前の世界にそのようなことはあり得なかったと確認するのは重要なことである。
そのような国際社会をもたらしたのは、日本が明治開国以来戦った数々の戦争である。その総仕上げが大東亜戦争であった。そして欧米の植民地は崩壊し多数の独立国が成立した。それを単なる結果だと呼ぼうか。そんなはずはない。産業革命を多くの人はどう評価するであろうか。それまでの技術から格段に飛躍し、現在に至るまでの技術の長足の進歩のスタートであり、現代社会の経済的繁栄を齎したものと評価してよいであろう。
だが動機から言えば産業革命は人間のエゴに過ぎないと切り捨てることも可能である。技術を改善して産業を興して金儲けしたいというのが本当の動機であろう。そして産業革命は多くの悲劇をも齎した。産業革命により起こった産業の原料を手に入れ、製品の売り場を求めて多くの植民地が獲得された。植民地では従来の農業などの産業が破壊され、綿花など工業原料の生産のために改造された。
生産した製品の販売のために在来の手工業は淘汰された。黒人奴隷が獲得されたのも産業革命に続く生産の拡大によるものである。大航海時代と産業革命は世界を変えたのである。欧州の幸福の引き換えに、その他の地域に取り返しのつかない不幸を齎したのである。それでも人は産業革命と評価する。
その字義は善である。繰り返すが、産業革命による技術革新はエゴによる結果に過ぎない。日本の戦争による植民地解放が結果論に過ぎないと否定するものは、産業革命の意義も強く否定するがよい。日本による植民地解放は意図しないものとは言えない。
④共産主義による民族解放と日本との違い
共産主義による民族解放は方便に過ぎない。しかも性質の悪い方便である。最初はコミンテルンとして世界各国に共産党の支部が作られたのがその始まりである。ソ連に革命が起きてもこれに続くものはなかった。資本主義諸国はソ連を圧迫する。ソ連の自立は危うい。そこで資本主義の国にコミンテルン支部を作り内部からソ連を支援する。
あわよくば革命を起こしてソ連の側につかせるのである。これは多くの効果を発揮して、米国の原水爆技術などが盗まれた。東欧の共産党は戦後東欧各国をソ連の衛星国にする手段に使われた。衛星国とはていのいい属国である。あるいは準植民地であるだからチェコなど先進工業国であった東欧は搾取された。
あるいは産業構造を変えられて、ソ連経済の一部を担う国にされた。ソ連から独立した共和国でも旧ソ連の産業支配から脱却できないで未だに混乱している。さらに米国に対抗して後進国が狙われた。これが民族解放である。後進国に共産主義者を教育して送り込み、革命を起こしてソ連に従属する政府を作るのが目的である。
ソ連による一種の世界制覇である。自己矛盾しているソ連経済にとって次々と支配領域を併呑して富を吸い上げるしか存立の道はないのである。ソ連支配は拡大を続けなければならない。だからどんなに軍事的には不合理であろうと、能力的に無理であろうと冷戦を続けなければならなかったので゜ある。だからソ連崩壊までがんばるしかなかった。
これがアフリカや東南アジアなどにおいて、西欧の植民地支配に準じた混乱を未だに引きずっている。ソ連は崩壊してただの国になったソ連にとって民族解放は不要である。だが播いた種は勝手に成長して巣食った。これが民族解放の残滓である。多くのテロの原因のひとつは民族解放の名残の一面もある。日本による植民地解放はこのような矛盾はない。
⑤日本の矛盾した立場
いわゆる自虐史観の立場でなくても、日米開戦に至った経緯を外交の拙劣と批判するものは多い。岡崎冬彦氏や渡部氏などである。だが、その前提は米英との共存が可能であるということがある。ソ連ややっかいな支那に対して、共闘を組むことが可能であるということである。これは現在の世界情勢を背景として過去を見ている幻想に過ぎない。
日本が米国と対等の関係を持つには現在のような経済力と工業力がなければならない。そのためには、現在のような独立諸国と自由貿易がなければならない。経済力や工業力ばかりではない。現在のように北朝鮮や韓国、イランなどのような国が発言力を持つのは、現在のように多数の非白人の独立国があるからである。
この前提は日本が戦うことによって、たとえ最終的に敗れようと明治以来戦ってきたからである。しかももし日本が日露戦争以後戦わずにいれば、白人による世界支配は強化され、有色人種は白人と同化し独立の気概を失う。もしインドで起こったように日露戦争で刺激された独立運動が起きたらどうか。日本は米英の立場に立つ以上、米英と共に独立を阻止する立場にならなければならない。西洋人に支配されて文明化されたのは、香港など少数を除いてない。
⑥東京裁判考
テレビタックルなる番組(17.7.11)で静岡大学の某教授が、東京裁判のやり方がおかしいから裁判として認められないというのなら、どの裁判も完璧を望めないから裁判として認められないというのと等しいという主張をした。もちろんこんなものは暴論である。突然占領して乗り込んできて法律を勝手に作って裁判と称して人を殺すというのが裁判と認められるのなら、やくざのリンチも裁判の形式をとって裁判と自称すれば裁判として認められるというに等しい。
だがこの教授の言に一点だけ顧慮すべきことがある。もちろん教授の意図することとは異なるが。それは国際法、ひいては国際社会というのは道理が間違っていても、事実が通用するということである。つまり東京裁判はいんちきでも、それによって死刑は執行されたのであり、それを否定するなら米国に戦争で勝つしかない。
竹島は韓国に不法占拠されているが、事実韓国が占拠している以上、韓国が実効支配しているという事実はあり、国際社会にはこの不法を取り締まる「警察」はいないのである。いくらいんちきだと叫んだところで事実は、裁判なるもので人が殺されて文句も言えないのである。だが逆に米国を倒さなくても東京裁判を無効にする方法は現にある。それも同じく、実行するという手段である。それは戦後の日本がやったように、東京裁判の刑死者を刑死者と認めず、恩給を支払うことである。犯罪者として日本国が認めるなら、恩給は支払われない。支払う法律を通した瞬間に東京裁判を否定したのである。米国もそのことを黙認することによって、裁判の無効を認めたに等しい。靖国参拝問題も同じである。A級戦犯がいるから参拝しないといった瞬間に東京裁判を肯定したことになる。
東京裁判は行われ刑は執行された。そして再審の余地はない。しかし靖国参拝、その他により事実上裁判を否定する政治家の行動により、また米国など関係国(中共は入らない)が黙認することにより、否定することは可能である。インチキな東京裁判は終わってしまったから取り返しがつかないと認めた瞬間に東京裁判はインチキではなく、実効性を持ってしまうのだ。
⑦ハルノート公開で戦争は避けられたか
日米戦争回避の方法で最も説得力を持つのは、ハルノートを米国民に公開していたらということである。この時点で他の方法は考えられない。当時の米国民は厭戦気分が強く、ルーズベルト大統領も欧州大戦に参戦しないという公約で当選したというのがその根拠である。だが、この説にも不可解な点がある。現在ほどではないにしても、米国は情報社会である。
米国は参戦していないにしても、既に武器貸与法で英ソに武器援助をしている。法律は議会の審議を得ているのだから、多くの国民すなわち米国世論に影響を与える国民の多数は、ドイツに敵対するという合意はできている。そして石油やくず鉄の対日禁輸政策も国民の合意を得ている。すなわち不況下にあって日本に石油やくず鉄を売らないとなれば、財界には多くの打撃を与えている。そのことは秘密でもなんでもない。多くの国民は知っている。
それは対日禁輸の原因が何であるかを知っているということでもある。米政府が強硬に出た建前は中国への支援である。だが同時に日本を刺激して、暴発させて欧州大戦に参戦しようということでもある。当時の米国は宋美麗など中華民国や共産党関係のロビー活動などで、中国に対する同情論に満ちている。そればかりではない。
大陸における権益は欧州各国に独占され、米国の入る余地のあるのは満洲が主である。その満洲は日本の指導下にある。邪魔なのは日本。鉄道王ハリマンの満鉄共同経営は小村寿太郎に蹴られた。排日移民法に見られるように、日本排除の空気は米国に満ちている。その上に日本に蹂躙される可愛そうな中国、裏では米国の大陸進出を妨害する日本を排除するという実利もある。
そのための対日強硬政策は公然たるものだから、議会にしても国民世論にしても支持されていたのである。ハルノート公開により戦争を避け得るという説が見落としているのは、マスコミが発達し議会での議論が公開されている米国にあって、ハルノートに至るまでの日米交渉の経過や、対日強硬政策が米国内では周知のことであったという事実である。
もしハルノートを日本政府が公開したとしても、日米修好通商条約廃棄に至るまでの戦争寸前の米国の強攻策を知っていた米国民に対して、米政府がハルノートを送った理由を容易に説明できたであろう。却って国民はハルノートを日本政府に受け入れるよう一丸となって要求したであろう。
なるほど妥結を目指して日米了解案を提案してきた日本政府にとっては、ハルノートは唐突であったろう。しかし不況の中での貿易の全面中止という苦しい選択を受け入れ、中国を侵略するにっくき日本という意識に固まっている米国世論にとっては、それまでの政策とハルノートに大きな飛躍はなく、中国からの全面撤退という要求は中国支援の最終要求として当然のことであったはずである。
日本政府がハルノートを公開して、これを撤回しなければ日本は宣戦布告せざるを得ないと声明すれば、米国民は一気に日本撃つべしの声が広がったであろう。ハルノート公開による避戦にはそれまでの、欧州大戦への武器支援や対日強硬政策といった、戦争寸前の米国の強硬策が全く国民に秘匿され、厭戦気分の国民に忽然と公開されるということでなければならない。何も知らないというほど米国民は愚かではないのである。
その証拠にルーズベルトは真珠湾攻撃のはるか前に日本の主要都市の爆撃命令にサインしている。これは米国による奇襲開戦である。しかし欧州大戦で爆撃機が必要とされたために中止された。米国が突然日本を攻撃しても国民は支持するという判断がなければこんな命令は出されるはずがないのである。
また真珠湾攻撃の直前に大統領命令でラニカイという小型船を米海軍が運航し、日本海軍に攻撃されるという航海に出発した。これは日本に先に打たせて開戦すると言う目的である。このことは元ラニカイの艇長の証言が世界の艦船1998年6月号と昔の読売新聞の記事にある。
結局は開戦のほうが早くて失敗したが、米国はあくまでも日本と戦争をしたかったのである。このときの動機は英国を助けるために欧州大戦に参戦するためである。しかし日本爆撃は支那の依頼によるものだから根は深い。結局は日米戦争は避け得なかった
⑧米国は戦前から日本本土空襲を考えていた
「幻」の日本爆撃計画、という本によれば米国は真珠湾攻撃以前から、300機の大編隊で日本本土空襲を計画していて、その前段階として「義勇軍」航空隊なる、フライングタイガースという戦闘機部隊を大陸に派遣していたことは以前書評に書いた。この本には、B-17なら支那大陸の飛行場から日本をカバーすることができるとも書かれている。その他の中型双発爆撃機では、航続距離が不足するのである。
つまり、米国は現実に開戦してから日本本土空襲を企画したのではなく、恐らくは対日戦の想定として、かなり以前から日本本土空襲は計画の一部にあったのではないか。そして、B-29はもちろんとして、B-15、B-17、B-24といった爆撃機が四発の大型機になったのも、日本本土空襲ということをも考慮していたのではないか。
確かに大型にすれば爆弾搭載量は飛躍的に増える。しかし、無理しなくてもヨーロッパ戦線を想定すれば、B-25、B-26といった中型機でリスクなく開発ができる。高コストの高リスクの四発機の開発も厭わなかったのは、日本本土空襲と言った、対日戦をも想定していたのではないか。現に比較的航続距離が短いB-17は次第にヨーロッパ戦線に限定使用され、太平洋戦線ではB-24に置き換えられ、航続距離が長いB-29はヨーロッパでは全く使われず、日本本土空襲専用になったのである。
そしてついに、昭和16年になると、日本爆撃計画を実行に移すことになる。既に昭和14年から、ヨーロッパでは戦争が始まり、米国も中立法を改正し、大規模な軍事援英を行うことになる。中立法の改正とは名ばかりで、国際法の中立を犯して英国に軍事支援するものである。
タイミング的には米政府が欧州大戦にのめりこんでいった時期と一致するから、対日戦によって欧州大戦に全面的に参戦するのが目的であったのだろうか。日本攻撃の規模と方法からして、裏口からの参戦にしては大仰過ぎると思われる。
ブロンソン・レーの「満洲国出現の合理性」には、コミンテルンや蒋介石政権による米国での反に津活動の他、本気で日本を潰すべきだと考えている米国人の存在があった。それは満洲事変以後のことではなく、恐らくは日露戦争以前にまで遡ると小生は推定する。
昭和12年から支那事変が始まると、日本は膨大な戦費と人的損害を受けてきた。小室直樹氏によれば、その戦費で飛龍クラスの空母が何十隻も作ることができたそうである。昭和16年ともなれば、欧米諸国には日本が極めて疲弊して、さらにほかの国との戦争ができる状態ではないと見えていたはずである。日本爆撃の実行計画は、このような状態の日本の重工業にとどめを刺して、日本の軍事力を壊滅させる目的だと考える方が、合理的であると考えられる。
⑨アメリカは対日戦も対独戦もしたくてたまらなかった
マクロに見れば、第二次大戦は米国にとっては世界の覇権を握るためであった。結果から見てみよう。第二次大戦の結果はどうであったか。敗戦国から言えば、イタリアは元の木阿弥。ドイツは大ドイツの復活ならず、第三帝国は崩壊し、分割されてヨーロッパの2小国に分かれた。
戦勝国から言えば、英国を筆頭とするヨーロッパ植民地帝国は崩壊した。ソ連は半植民地たる「衛星国」東欧を手に入れ、支那と北朝鮮を勢力圏に入れた。米国は、日本各地に陸海空の基地を展開し属国としたが、支那への伸張には失敗した。結局ソ連だけが拡大し、米国と対峙することとなった。米国は日独の代わりに、中ソという共産帝国と対峙する羽目になったのである。
結局、米国は英国、日本、ドイツの追い落としに成功したものの覇権をソ連と二分することになった。ソ連をなめていたのである。伝統的にロシアと支那の強みは縦深性にある。という訳で、アメリカは英独日を追い落として覇権を握らんとしたが半分成功し、半分失敗したのである。
英国は植民地を取ってしまえば、ただの島国である。ドイツは、それ自体で実力があるから危険である。特にヒトラーのドイツは極めて危険だと感じたのである。日本には・・・非白人かつ非キリスト教国でありながら、文明国として、西欧諸国と肩を並べるに至った・・・生理的な嫌悪感を感じていたのである。
そのことと欧米人が個人として、日本人と友情を結んだものが限りなく多いこととは別の次元の話である。また戦前の米国人にも満州事変への理解を示したり、「東京裁判」で日本人のために職を賭した弁護士がいたこと、はたまた最近でも戦前の日本の立場に深い理解を示す英国人記者ヘンリー・S・ストークスがいたりする。そのこともまた欧米人の層の厚さを示すものであって、総体として欧米が日本とどう対峙したかは別の話である。
対独戦の動機は一般的には英国を救うためであるとされている。最近では前述のように、英国を世界の覇権から追い落として、入れ替わるという動機もあったという説もあるが、これにらついてはこれ以上言及しない。
問題は対独戦とは関係なく対日戦も、したかったのではないかということである。そのことはぼんやりと考え続けていたが、確信となったのは「『幻』の日本爆撃計画」という本を読んだからである。別稿でも紹介したように、時期的には対独参戦と符合するにしても、日本本土を大規模に爆撃する、ということが対独参戦の方便としては、あまりに無謀過ぎ、あまりに日本をなめているのである。
当時、日本は支那事変に四年もかかり、経済的にも軍事的にも疲弊していて、対米戦を遂行できる力は残っていないと考えたられていたのではなかろうか。日本本土を数回大規模な空襲を行えば、日本は崩壊してしまうと考えたのではなかろうか。
日本には極一部を除いて維新開国以来、対米戦を本気で考えた者は少ない。むしろアメリカ大好きが、現代と同じく一般的風潮であった。石原莞爾の世界最終戦論などは、日米の勢力が他を凌ぐから対立関係となり、最終決戦を行うという、理由の裏付けなき空想であり、あまりに観念的であり、現実味がない。石原は支那大陸の覇権構想への日米の介入が日米戦争を誘発すると考えていた。そのことは正しいのだが、世界最終戦争論における日米決戦とは、何の繋がりもないから奇妙である。
一方で米国は自身の実力がついてくると、自ずから太平洋を越えてアジア大陸に進もうとするときの障壁として、また人種的偏見から日本を主敵と看做していて、機会あればつぶそうと考えていた。明らかに対日戦をいつか行うと考えていたのである。その時期は日露戦争以前に遡るのであろう。
だから戦争の主体となる海軍の戦備は対日戦用そのものであった。日本海海戦でロシア海軍は滅び、再建されなかった。第一次大戦で敗れたドイツも同様である。ドイツは第二次大戦では艦隊を編成して運用するのではなく、必要に迫られたとはいえ、戦艦にさえ商船攻撃を主任務とする愚行をしたのである。重装甲と巨砲が商船攻撃に必要ではあるまい。英海軍が米海軍と砲火を交えることはない。やはり米海軍は対日戦備を主目的としていたのである。
対日戦備が充実凌駕しつつあった時期に、日本は支那事変により消耗しつつあった。海軍の血たる石油を握っているのはアメリカ自身である。蘭印の石油を日本が狙ったとしても、それで全て賄える訳でもなく、本土への輸送の必要もある。何よりオーストラリアの方が近いから、阻止は容易である。かく考えると、新戦艦10隻が次々と船台から降り始めた昭和16年は正にチャンスであった。米国はかねてからの強い願望を実行したのに過ぎない。
⑩戦前反戦だった米国民が日本との和平に反対したと言うのは奇妙
竹田恒泰氏の「アメリカの戦争責任」には昭和20年6月のギャラップ調査によれば、「・・・アメリカが日本を占領せずに条件を付して降伏を容認すべきか、敵を完全に打ち負かすまで戦争を続けるべきかという質問に対して、約九対一の割合で『完全な勝利』が支持されている。アメリカ政府は、国民の真珠湾攻撃への恨みを煽って戦争に邁進してきた。アメリカ国民は真珠湾攻撃を恨んでいて、大統領には日本を叩き潰すことを望んでいた。」(P102)と書かれている。
これは戦前のギャラップ調査が、欧州への戦争に参戦すべきか、と聞いた時の結果と真逆である。この両者を比較すると、実に奇妙な感に打たれる。戦前厭戦であったはずの国民が、真珠湾攻撃だけによって、ここまで正反対に国民感情が変化するものなのだろうか。実は元々米国民は好戦的なのではなかろうかと思わざるを得ない。
米西戦争のきっかけになったメイン号爆沈にしても、マスコミが騒いだだけで、犯人がスペイン政府である、という証拠が全くなかったのは、当時も米国内でよく知られていたのである。それどころか、戦前に刊行された「満洲国出現の合理性」、という米国人の著書には、米国の陰謀であるという証拠があることすら、ほのめかされている。ベトナム戦争への本格的介入となった、二度の北ベトナム魚雷艇による米駆逐艦攻撃と言う、トンキン湾事件も一度目は北の誤認によるもので、二度目は米軍によるやらせであった。
ベトナム戦争も、突然戦争が始まったわけではなく、トンキン湾事件の何年も前から米軍は介入している。米国における、ベトナム反戦運動も、一気に起きたわけではなく、共産側が仕掛け、ベトナム戦争の勝利があり得ない、と分かって徐々に米国内に広がったものである。日本への無条件降伏要求と同じく、米国民の軽薄さと好戦的なことを示しているのに過ぎない。
イラク戦争でも同じである。湾岸戦争と同じく、簡単に勝利が得られると米国民は支持し、正規戦が終わっても、いつまでたってもテロやゲリラ攻撃によって、米兵の死者が徐々に増えると、米国民の風向きは、徐々にイラクからの撤退を求めるようになった。ISとの戦いでも、オバマ大統領は、爆撃はするが、兵士の犠牲が出る可能性がある、地上軍の派遣はしない。米政府と米国民の軽薄さに気づいた結果生まれたのが、世界各地で発生するテロとISというテロ組織である。
対日戦について言えば、従前より言うように、元々米国民は日本を潰すことを求めていたのであり、戦争の勝利が確実だと分かると、好戦的な本性をむき出しにしたのに過ぎない。硫黄島の戦いでも、苦戦であったことを隠し、米国旗を立てた四人の英雄を仕立てあげてキャンペーンをすると、戦時国債はよく売れたのである。
⑪日本の歴史戦の苦境の原因
現代日本において、慰安婦や南京事件の問題で、特に中韓から非難されているのを保守系の人たちは「歴史戦」と呼称することがあるが、日本の未来の安寧にとって正に戦争に等しい、という意味では正しい。だが歴史戦は苦境である。そしてなぜ日本だけが歴史戦を戦っているのか。
かつてはドイツも、ユダヤ人の大虐殺、という歴史戦を戦っていたが、完全にそれが終えた訳ではない。元西ドイツのヴイツゼッカー大統領は「荒れ野の40年」という演説をして一応の決着をみたと考えられている。これは噴飯もので、実はドイツが行っていたとされる残虐行為には一言も謝罪していないのは、きちんと読めば分かる。例えば「ことにドイツの強制収容所で命を奪われた六百万のユダヤ人を思い浮かべます。」(岩波ブックレットP11)と書かれている。
最大の残虐行為とされる、ユダヤ人虐殺に対して「謝罪する」とは言わず「思い浮かべる」だけなのである。思い浮かべるのだけなら、被害者のユダヤ人だって「思い浮かべる」であろう。なのに多くの日本人は、ドイツは謝罪した、と騙されている。騙されているのではない、日本を批判する口実にしているだけである。
いずれにしても、ドイツは全ての批判をナチスに押しつけて、ドイツ民族の罪ではない、と逃げることに一応成功した。だが、事態が沈静化しただけで、よく考えればドイツ民族全体にも罪がある、ということを完全に否定することに成功した訳ではない。ドイツの歴史に突き刺さった棘は、完全には取り除かれてはいない。
なるほどナチスドイツは無辜の何百万人と言うユダヤ人を殺害したのであろう。しかし、共産ロシアの殺害した人々、毛沢東が殺害した人々の人数は遥かに大きい。アメリカにしても、黒人の奴隷を大量に輸入し獣扱いした。アメリカインディアンを正義の名のもとに、事実上の民族絶滅をさせた。米国が、フィリピン独立運動や第二次大戦中にフィリピンや日本で殺害した民間人は百万人どころではない。欧米諸国やロシアのユダヤ人虐待は常態化していた。ナチスドイツの迫害を知りながら、亡命しようとするユダヤ人の受け入れを拒否したのは、他ならぬ米国であるが、そのことに口を閉じている。
なのに日独だけが歴史戦で圧迫されているのは、何故であろうか。ことは簡単である。戦争に負けたからである。敗戦民族が勝者に歴史を奪われるのは、古来、東西を問わず常識であった。しかし、ヨーロッパにおけるウェストファリア条約以来の、戦時国際法の成立によって、戦争はルール化されて、勝者が賠償を取り、講和条約の成立をもって戦争は清算されることとなった。
勝者が正義を主張する必要のない時代が成立し始めたのである。国家間の紛争は戦争で決着し、正義を問わない時代が、少なくともヨーロッパでは成立した。幕末の日本は「国際公法」をそのように理解し、文明国として国際法の世界に参加する権利を得ようとし、日清日露の戦役で、目的は達成せられたかにみえた。
これを破壊したのは米国である。南北戦争とは米国内の内戦という事にされているが、実は北軍と南軍という国家間の戦争であった。それを隠蔽する為に北軍は奴隷解放と言う、虚偽の正義のスローガンを掲げ、勝利すると南軍の指導者に悪のレッテルを貼り、苛酷な処分をした。
第一次大戦では、勝者がドイツ皇帝を訴追する、という正義を主張したが亡命されて、失敗した。あまりにも戦争による被害が大きかったために、ドイツに天文学的な賠償を要求し、ウェストファリア体制は崩壊の兆しを見せたのである。さらに第二次大戦ではエスカレートし、米国は日独の無条件降伏を宣言した。
負けを悟った国が、講和を申し出て戦争が終わるという、ウェストファリア体制は無視されたのである。無条件降伏は、単に和平交渉を拒否するだけではない。勝者の絶対的正義を前提とするのである。その結果、従前の国際法になかった、政治家を含む戦争指導者を処刑するという、ニュルンベルグ裁判、東京裁判なるものを強行した。元来国際法で戦争犯罪で処断されるのは、民間人や捕虜の違法殺害という戦時国際法違反者に限られていたのである。
従って、東京裁判などでは、勝者が正義を主張するために、平和や人道に対する罪、などというかつてない罪状が主張された。そのために南京大虐殺なるものがねつ造された他、日独の残虐行為だけが誇張された上に、一方的に裁かれた。これに対してドレスデン空襲や東京大空襲、原爆投下、ベルリンなどドイツにおける米ソの膨大な残虐行為などは、歯牙にもかけられなかった。
よく知られているように、国際連合という訳は正確ではなく、枢軸国に対する連合国の意味である。従って国連の根本的性格とは、第二次大戦の連合国の正義を固定化するもので、それに反するものを許さないのである。それを象徴するものが、いわゆる国連憲章の旧敵国条項である。
第53条には、強制行動は安全保障理事会の許可を必要とするが、107条の規定又は旧敵国の侵略政策を防止する場合は、許可を必要としない、とされている。107条とは、国連憲章のいかなる規定も、旧敵国に対抗していた国が、戦争の結果としてとった行動と得たものを無効にしない、ということが書かれている。
煎じ詰めて言えば、日独などの旧敵国の行動が、連合国の一部の国に気に入らない行動をとった場合には、安保理事会の許可なく、当該国は旧敵国に対して軍事行動とる自由がある、という事である。これは解釈の幅がある恐ろしい条項である。尖閣や北方領土問題で日本が、中国やロシアの気に入らない行動をとった場合に、戦争をしかけてもよい、ということにもなりかねないのである。
もし、旧敵国条項が廃止されたとしても、日本は連合国の正義の範囲の中で行動しなければならない、ということに変わりはない。大東亜戦争は侵略ではなく、英米に追い詰められた自衛行動であった、などと政府が公然と主張することはまかりならぬ、ということである。全ての歴史戦の不利の根本原因はここにある。
多くの愚かな日本人は、歴史上初めての外国による占領とWGIPという日本人洗脳計画による、宣伝、検閲等によって、日本の戦前戦中の行動を全て悪と看做すようになった。この結果「南京大虐殺」などというものが事実として固定化された。何と慰安婦問題などは、日韓条約締結後、何十年と問題にされていなかったのに、吉田某の慰安婦強制連行の虚言や、朝日新聞のキャンペーンによって、脚光をあびてしまった。
韓国人の立場になって考えても見るが良い。慰安婦がいたのはかれらも百も承知であったが、売春と言う行為を公然と語りはしなかった。ところが当の日本人自身が、慰安婦の強制連行や、性奴隷などと言い始めたのである。それならば、韓国人は日本人を非難しないわけにはいかないのである。
韓国人がアメリカで慰安婦のキャンペーンをしているのを非難する保守系の人間は多いが、そうしなければならないように追い込んだのは、WGIPによって日本の過去は全て悪で、悪を嘘までついて弾劾することが正義だと信じ込まされた、倒錯した日本人自身である。彼等の考えが変わらぬ限り、歴史戦は負けるであろう。
その点ドイツ人は賢明である。彼等には日本に対するほど周到なWGIPはなかったし、勝利も敗北体験し慣れている。彼等は敗者としての立場をわきまえ、周到に行動し、いつか汚名を晴らすであろう。少なくとも事実に反するものを訂正し、連合国の悪事も追求し、正当なバランスをとるようになるであろう。既にワイツゼッカーの「荒野の40年」にはその萌芽がみられる。ドレスデン爆撃に対する非難等の連合国の非道もきちんと批判しているのである。その観点から言えば慰安婦問題や南京大虐殺、靖国問題の歴史戦で日本が劣勢にある根本原因は日本人自身にある。
⑫日露戦争で日本はナポレオンの教訓は考慮できなかった
ロシアがナポレオンに勝ったのは、退却戦で戦線を伸ばし、広大な領土に引き込んだ結果である。別宮暖朗氏の、「坂の上の雲」では分からない日露戦争陸戦、では奉天からのロシア軍の撤退は、日本軍の大勝利の結果である、としている。現にクロパトキンは満洲軍総司令官を降格された。
氏によれば、講和は、敗北を認めた側が、勝者に申し込むのであって、これ以上の継戦が困難だとして政府に講和工作をした児玉は間違っていた、という。講和を望むのなら戦争を続けるべきであり、それまで不足していた砲と砲弾も、奉天会戦後には、充足されていたのだという。
だが、ナポレオン戦争でも、好んで退却し、敵をロシア領深く迎え入れたのではない。負け続けていたのに過ぎない。奉天からの撤退を世界の大勢がロシアの敗北と判断したのも当然である。結局、講和が成立したのは、日本海海戦に奇跡的な勝利をおさめ、ロシア国内の不安定が拡大したため、日本のこれ以上の勢力拡大を望まない米英が、講和をロシアに斡旋したからである。米英は、ロシアの東亜での勢力拡大を、日本の軍事力で抑えられれば良いのであって、それ以上の日本の勢力拡大は無益であったどころか嫌悪する所であった。
ナポレオン戦争の時代と異なり、ロシアは国内事情によって講和を受け入れるしかなかった。たとえ海軍が全滅しようと、ロシアの国内不安がなく、陸戦を徹底して戦うことができれば、ロシアは最終的には勝てたであろう。そのような可能性まで検討した結果、日本は日露戦争を決断したのではなかった。
制海権が日本にあっても、日本の兵站が切断されないだけで、ロシアの兵站も可能である。まして、西方に進撃する日本軍の兵站は延びる一方で、ロシアは逆である。それでもナポレオンの敗北の教訓を考慮する余地は日本にはなかった。日本は戦うしか生きる道はなかったと判断したから開戦したのである。
それならば、大東亜戦争の開戦を間違っていた、と言える日本人はいない。明治の元勲なら開戦を選択しなかったとは言えないのである。ただ一部の識者が言うように、大東亜戦争にも勝てる戦略はあった可能性はある。しかし、米軍の戦争テクノロジー、特に海軍のそれは開戦時点では英独をすら遥かに凌駕していた、といえるから米国相手の「勝てる戦略」は極めて困難であろう。大東亜戦争は、海の戦いであった。
別宮氏の講和についての考え方は、意外に思われるが正しい。結局相手に徹底して勝てなければ、相手は講和しないのである。現に大東亜戦争の終戦工作は、敗北を認めた日本が行ったのである。ベトナム戦争の場合は、北ベトナム軍が敵の首都サイゴンに突入し、南ベトナム政府が崩壊して終わった。講和ではなく、無条件降伏である。支援したアメリカは、勝てない長期の戦いで厭戦に陥って撤退したのである。
日露戦争が、結局日本の勝利と言う形で講和が成立したのは、ロシアの国内事情と米英の思惑による、という極めて例外的なものである。その意味で、山本五十六が「城下の誓い」をさせることが絶対不可能と知りながら、緒戦の徹底的な勝利で、米国を厭戦気分にさせて講和に持ち込むことが唯一の勝利の道だと考えていたとしたら、大間違いである。
⑬インパール作戦なかりせば
平成29年の夏にも、インパール作戦の現地を歩く放送があった。いわゆる白骨街道だ。戦死傷者本人や遺族の苦しみを考えると、何とも言いようがないが、インパール作戦の戦死者や負傷者は当事者自身が考えているようには無駄死にではなかった。それどころか歴史的事実としては、世界史そのものを変えたのである。
インパール作戦自体、早い時期に計画されていたが、補給が困難だとして反対していたのが、後日担当とされ多くの批判をあびた牟田口参謀その人であった。作戦が発動されたのは、東條首相がチャンドラ・ボースのインド独立の熱意に動かされたからだと言う説もある。また遅れは海軍に騙されていた、という説もある。対米戦をしているのにインドに攻め込んでどうする、というのである。
発動した時勝つには遅すぎた。しかし、牟田口の作戦は英軍に評価されている。戦後インパール作戦には口を閉ざしていた牟田口は、英軍に評価されていると知った時、急に話し始めた、というのは余りに現金である。しかしインパール作戦でインド国民軍(INA)が反乱軍として捉えられた時、インドの暴動が始まって、インドの独立は実現した。
洋画の「ガンジー」にはインパールもインド国民軍も登場しない。しかし、インド独立はガンジーの無抵抗運動で成ったものではない。確かにガンジーの運動がインド国民に対して、英国への反抗心を育てたことは事実である。西洋人が「ガンジー」なる映画を作ったのは、インドが比較的平和的に独立した、という嘘のためであるとしか考えられない。
もし、インパール作戦がなかったら、インド独立は、何十年も遅れたとインド人自身は言う。これは、インド人の手だけでも独立できた、という見栄であろう。日本軍の干渉によって独立は現実に起きた。しかし何十年後に独立できる、という保証はないのである。
昔インド製作の戦争映画を見た。英語の稚拙な小生にも、上官は比較的流暢な英語を話したのが分かった。ところが階級が下がるにつれ、多分ヒンズー語系だろうが、英語以外らしい言語が混じっているのが増えていった。要するに、上流階級には英語すなわち、英国文化が浸透しているのである。数十年過ぎたら、その傾向は強くなるであろう。
独立の気運さえ失われるかも知れないのである。あるいは独立したところで、インド固有の文化は喪失しただろう。そのことは現在の南米を見るが良い。
インドの独立がなければ大英帝国の崩壊はなく、アジア、アフリカの独立はない。これら世界の植民地の独立がなければ、今の日本はない。すなわち世界と公正な貿易による日本の立国は欧米の植民地支配の終了から始まったのである。
あり得ない想定だが、外交努力で支那事変を解決し、対米戦が起きなかったとしたら、日本の平和は当面は続いたであろう。ただし、白人世界の中の唯一の有力有色人種国家と言う、閉塞した状態は続いたであろう。その間、いつの日か日本は白人国家と衝突したのは間違いない。いくら対欧米関係に神経を使ったところで、欧米は非有色人種の国家日本が、世界の大国として登場したことなどということは、心底では許し得なかったのである。
なるほど米国などの陰謀で、憲法さえ変えられてしまった。反日を生き甲斐とする異常な日本人が増殖し、テレビマスコミには戦前日本を犯罪国家のように言う人士しか登場しない雰囲気が固定化しつつある。しかし、日本はサンフランシスコ講和条約で独立したのである。主権を回復した以上は、日本の混乱は最早米国のせいにすべきではない。既にしてキャスティングボードは日本人の手にあるのである。講和条約以前の主権のない状態の憲法を今放置するのは、日本人自身の問題である。日本は解放されたのだ。
その後の全ては日本人の自己責任である。以前にも、紹介したが漱石の「猫」にこんな挿話がある。金儲けのジョークである。人に600円貸したら、すぐに返せとは言わず、月10円返すと言う話にする。すると年120円で五年で完済だが、毎月10円づつ払っているうちに、払うことが習慣になって、永遠に金を貰えると言う算段である、というジョークである。
話を聞けば馬鹿馬鹿しいが、漱石は単なるジョークとして書いてはいまい。現に日本国憲法がその類である。政府は米軍に押しつけられた憲法を仕方なく成立させたが、本音の共産党などは反対した。ところが今はどうであろう。5年の借金の完済、すなわちサンフランシスコ講和条約が成立し、旧憲法の復活の自由ができたときには、多数が強制された日本国憲法を金科玉条のごとくいいつのる。吾輩は猫であるの冗句は冗句ではなく現実におきている。国家主権がない時点で成立させられた憲法は、憲法たりえないのは当然である。
日本国憲法廃棄も含め、責任は日本人自身にある。もちろん小生は廃憲論者である。なるほど平成29年における、安倍首相の九条への自衛隊の追加は建前としてはおかしい。だが今の日本国内の、異常な改憲反対を打破する道としては、他に選択肢はないのではないか。
現に何十年も日本国憲法が使われてきたのに、今更全部廃棄するのは変だ、というのはたしか大阪の橋下市長らの法律家としての見解である。しかし、これは憲法を文章で書かれた憲法典に限定した狭量な議論である。日本国憲法を廃棄したところで、成文憲法がなくなるだけで、国体の本質と戦前戦後の慣習からなる、国体としての日本国の憲法はなくならない。
帝国憲法に内閣制度の記述がないのに、運用されていたと瑕疵をいう論者がいるが、憲法を成文典だけに見誤る瑕疵であろう。日本の憲法すなわち、国体は明治天皇の五箇条の御誓文と聖徳太子の十七条の憲法で本来は充分であり、成文典は不要とも言える。英国に成文憲法がないと、言い出すのは西洋の例があるから、という悪癖としか言えず、本質ではない。
伊藤博文たちが苦労して帝国憲法を造ったのは、欧米との不平等条約の改正の方便のひとつでもある。そのことを評価するのと、事実認識とは異なる。安倍総理がとりあえずの改憲を言うのは伊藤博文の事情と似ている。方便としの9条改憲をしなければ、対北、対中問題の対応は出来ないし、ともかくも米国製憲法を打破したと言う実績は残らないのである。
改憲によって米軍の指揮により、世界中に派兵しなければならなくなる、という論者がいるが、どこに派兵するかは日本の国策の判断であって、憲法の問題ではない。現に日本は朝鮮戦争で米軍に掃海を命令され、基地を提供して国際法上は参戦している。しかも、戦死者一人を出している。
つまりどこに派兵するかは、政策の問題であって、憲法以前の法律の問題ですらない。改憲阻止は漱石の言う、強迫観念である。現に平和憲法のおかげで、日本の平和は守られたというが日本国憲法下で、日本は朝鮮戦争とベトナム戦争に参戦したばかりではない。竹島を侵略され、数百人を下らない国民を拉致されると言う、侵略を受けて、何もできない。日本国憲法のおかげで、戦争をせずに平和に過ごした、というのはお尻を出したまま頭も土に突っ込んで逃げている、ダチョウの平和である。
現に朝鮮戦争とベトナム戦争に国際法上の参戦したばかりではなく、国民や領土を奪われて、知らぬ顔していたではないか。旧社会党の土井元委員長らは、これらの事実に極度に冷淡な、非日本人としかいいようがない。韓国の呉氏などは、朝鮮民族の性格にすら強烈な批判をした。あげくに日本に帰化した。
それはむしろ誠実な行為である。呉氏ほどの批判をするならば、韓国人からの批判に耐えかねて、というより、良心に従って国籍を替えたものと信じる。今、日本の悪逆をいいつのる者がいる。それならば、北朝鮮でもどこでも自分の理想の国に国籍を替えるが良い。それをしないのは、思想に忠実でないばかりではなく、いいたい放題の日本の社会への甘えに過ぎない。
7.日米開戦論
米国民は第二次大戦参戦を欲していた
現在の第二次大戦参戦以前の米国の状況の通説は、ルーズベルト政権は国民に隠れて英国を救うために、対独参戦を望み、米国民は大勢が第一次大戦による厭戦気分で参戦反対が、絶対多数であった、というものである。ルーズベルト(FDR)は裏口からの参戦のために、日本を挑発していたということがこれに加わる。
小生は、平成20年頃から、米国は国民と政府共に、対独参戦のみならず、対日参戦をも欲していた、と言う説を「幻の日本本土爆撃」という本を読んで以来、確信するようになった。このような説は、日本のメジャーな刊行物には皆無であるように思われる。だが一般に公表された書籍を読む限り、このような結論に至らざるを得ないのである。
まず、ルーズベルト政権が、英国を助けるために参戦を欲したと言う点については、通説の通りであると考える。最大の問題は米国民の厭戦感情である。渡辺氏の著書(*)では、真珠湾攻撃が始まるまで、世論調査では、80%を超える米国人が、戦争絶対反対であった、という。これが大多数の書籍に書かれている通説である。
ところが川田稔氏は(**)米海軍による対英援助物資運搬の米商船護送とグリーンランドの米軍の進駐などを例示して「イギリスの敗北を阻止するため、アメリカが参戦する姿勢は、これらの点からも明らかだった。なお、このころの(昭和16年4月ころの)世論調査では、「欧州参戦支持が八〇パーセントあまりにたっしていた。(P234)」と書く。アメリカが参戦云々は政府の姿勢であろう。これは通説と同じである。ところが、すぐあとに80%もの米国民が欧州参戦支持である、とことも無げに書いているのには驚いた。だから通説との矛盾は自覚していないのであろう。
これを他の書籍と比較して読み解いてみよう。数々の秘密協定も隠され続けていた。それにしても、渡辺氏が指摘する(*)、FDRが実行した多くの公表された事実から、国民や多くの政治家、政治経済軍事の専門家筋が、FDRが戦争を欲していることは明白であり、隠しようもないとしか考えられない。
まさか共産圏のような絶対秘密主義国家ならともかく、マスメディアも政治批判も発達していた米国において、大多数の米国民を完璧に騙しおおせる、というのは単純に考えて不可解過ぎる、というのが小生の根本的発想である。米軍の戦時下における、報道管制はシステマチックで厳格である、と言う点においては日本のように杜撰で恣意的でないことは知られている。
それにしても、米国が参戦前の時点でドイツがデンマークを占領したときに、米軍がグリーンランドを保障占領したと言うことが公的に知られないはずはあるまいし、米駆逐艦が独潜水艦を攻撃したということが報道されていない、ということはあり得ない。中立法の改定による交戦国への武器輸出や日本に対する経済制裁は国民の知るところである。当時の米国は、経済制裁は戦争に準ずる、という国際法解釈であったから、日本に対して戦争を強いていると国際法の専門家が指摘してもおかしくない。本書に書かれている当時公表されている事実の全てを総合すれば、FDRか三選に際して約束したとされる、参戦しないと言う公約は破られつつある、と考えなければ国民はよほど愚かか、情報から絶対的に隔離されている、としか考える他はあるまいが、そんなことはあり得ない。
チャールズ・リンドバーグの「リンドバーグ第二次大戦日記(角川文庫上巻)を見よう。リンドバーグは「翼よあれがパリの灯だ」で有名な大西洋無着陸横断の英雄であるが、欧州大戦に参戦絶対反対のキャンペーンを展開したことでも有名な人物である。彼はパイロットとして有名だったから軍関係者とも知己があるが、一民間人であり、彼の知り得た情報は一般的に国民も共有していたはずである、ということを前提にする必要がある。
リンドバーグはルーズベルトが欧州参戦に向けて画策しているということを、日記では随所に述べていることが注目される。その上、ルーズベルトは参戦しない、と公約していたにも拘わらずリンドバーグは全く信用しておらず、ルーズベルトの「三選は参戦」とすら断言している。「大多数の国民と同じく」一貫して世論に参戦反対を主張していたリンドバーグがこの調子である。リンドバーグが中立法改定その他の立法は全て参戦に向けたものだと判断しているのは、当たり前と言えば当たり前で、参戦前の米国の雰囲気が理解できるではないか。
小生が重要だと考えるのは、ルースベルトが三選された後の1941年1月6日の次の記述である。
こんにちはとりわけ、戦争前の暗い帳が頭上に重く感ぜられる。何の抵抗もなく戦争に赴こうとする人々が増えつつある。万端の用意が出来ていると主張する人たちが多い。国民の態度は前後に揺れている。最初のうち、反戦勢力が勢いを得ていたかと思うと、今ではそれと正反対の方向に振子が動いている。-国民の現実と態度と新聞の大見出しとは常に区別して見分けるように努めねばならぬ。が、全般的にいえば、アメリカの戦争介入に反対する我々の勢力は、少なくとも相対的に見た場合はじりじりと後退しつつあるように思われる。われわれにとり最大の希望は、合衆国の八十五パーセントが戦争介入に反対していると言う事実だ(最新の世論調査に拠る)。一方、約六十五パーセントが「戦争の危険を冒してまで大英帝国を助ける」ことを望んでいる。換言すれば、自ら戦争の代価を払わないでイギリスに勝ってほしいと望んでいるかのように思われるのだ。われわれはいわば希望的観測の類にのめりこんでおり、それは遅かれ早かれ、われわれを二進も三進も行かぬ状況に追い込むに違いない。
この記述は見事に当時のアメリカの世論の状況を叙述していると思われるのだ。渡辺氏も含め、日本の歴史家等は、この記述のように、世論調査の85パーセント参戦反対となっていることと、国民の大多数が参戦反対でルーズベルト自身も三選の際の公約に参戦しない、と約束したことをもって、ルーズベルトの裏口からの参戦の陰謀を主張している。ところが参戦反対の闘士であったリンドバーグの記述は、米国の状況がそのように単純なものではないことを示している。
この日記は昭和16年の1月6日の記述だから、世論調査の発表は12月末に行われたのであろう。その結果は、85%の国民が参戦反対だが、約65%戦争の危険を冒してまで英国を助けることを望んでいる、というのである。つまり戦争には反対だが、戦争の危険があっても英国を助けたい、というのであり、何が何でも戦争絶対反対と言っているのではない。その上リンドバーグによれば、国民は段々参戦に傾きつつある、というのである。
すると昭和16年4月、つまり半年後に川田氏(**)がいうように、80%が参戦支持に変化していったということはあり得る。多くの論者が米国民の大多数が参戦反対であった、というのはリンドバーグが言う「85%の国民が参戦反対」の部分だけ切り取って主張しているのだと考えれば納得できる。
ところが、リンドバーグの日記(上巻P345)には、昭和16年4月16日には「ギャラップ調査世論は奇妙な矛盾を明らかにした。八十パーセントが戦争に反対しているかの如く思われるのに、七十一パーセントはイギリスが敗北するならばという条件付で輸送船団の覇権に賛成。三日前に発表されたその調査によれば、アメリカ人の大多数はイギリスを助けるべく陸海軍あるいは空軍を一部でも派遣することには反対なのだ。回答者が混乱しているのか、世論調査の質問が回答者を混乱させたのか・・・」と書かれているのだ。参戦反対派はやや減り、イギリス支援派は1月よりやや増えている。しかも、80%の戦争反対派と71%の英国支援派は、重複しているとしか考えられない。
どうやらリンドバーグの記述は、一月も六月もギャラップ調査のようである。出所が判明している。ところが川田氏の「80%が参戦支持」は出所不明であるが、全く同じ四月に正反対の結論が出ているから、川田氏の調査の出所はギャラップ調査ではないことはほぼ間違いはあるまい。トランプとヒラリー・クリントンが争った大統領選挙でも、大メディアの世論調査は間違った結果を示しているので、一概に川田氏の記述が間違いであるとは断言はできない。
次は対日参戦計画である。これは「幻」の日本爆撃計画、に詳しい。本書に書かれているのは、日本本土爆撃計画であり、最初の大きな一発を米国が打とうとする、積極的な計画である。小生には検証能力はないが、著者のアラン・アームストロング氏はきちんと資料出所を提示しており、いい加減なものではないと考えられる。戦後アメリカ政府は、自国民の広範な民族、広範な年齢層に放射能汚染をさせる人体実験を行っている。何でもありの国なのである。
ルーズベルト大統領は戦闘機350機と爆撃機150機という大編隊により、日本の首都圏爆撃をする計画にサインしていた、というのである。もちろん中国空軍に偽装しての空襲だった、というのであるが、当時の日米国民の常識から考えても、中国がこのような戦力を持っていると考えるはずはない。
実際には、米国から爆撃機や戦闘機とそれらに付帯する整備機材を送り、パイロットと整備クルー等は義勇軍として米国から派遣する、というものであるから、人員だけでも数千人に及ぶ。注意すべきは、この計画は計画倒れになったのではない、ということである。戦闘機部隊の一部は、実際にP-40戦闘機と所要人員が派遣されている。
現在では、義勇軍として派遣されたとして有名になった「シェンノートのフライングタイガース部隊」である。計画の実行は長距離爆撃機が援英のため、調達が難しくなって実行が遅れているうちに、真珠湾攻撃が始まって、中止となった。しかし、フライングタイガース部隊は、実際に派遣されて、その後日本機と交戦している。つまり計画は実行されない机上プランではなく、実行途上にそれどころではなくなってしまったのである。
85%もの米国民が本気で参戦に絶対反対であったなら、この計画が実行されたら、囂々たる非難をあびたであろう。リンドバーグの日記は、結果的に大多数の米国民が、次第に欧州参戦やむなし、に傾いていったことを暗示している。ルーズベルトは国民の多数派の本音が参戦賛成であったことを知っていたから、どんな手段でも戦争を始めてしまえば、国民はついてくる、と踏んだとしか考えられないのである。しかし何故か渡辺氏の著書では「幻」の日本爆撃計画にも触れていない。日本に最初の一発を撃たせるためにFDRが「軍艦ライカニ」というボロ舟を太平洋に送り込んだ、比較的知られたエピソードにも触れない。
ルーズベルトの爆撃計画は、支那事変で疲弊した日本は、一撃で国力に壊滅的打撃を与えられ、日本が何年も戦うことができた、などとは考えられなかったと想定した節がある。日本を早いところ片付けて、対独戦に専念しようと考えていたのかも知れない。日本をなめていたのである。現に対日戦などは3か月で片付く、と語った米軍幹部がいるのである。
その意味では、最初の一撃が真珠湾であろうとフィリピンであろうと、どうでもよかったのであろう。「幻」の日本爆撃計画の引用にあったTHE UNITED STATES NEWSという週刊誌も調べてみた。一九四一年十月三十一日号には、BOMBER LINES TO JAPANという記事があった。図入りで、重慶、香港、シンガポール、フィリピン、グァム、ダッジハーバの6か所から本州を爆撃できる、と書いているのである。
アームストロング氏は、この記事を日本本土空襲の予告に等しいと書くが、その通りである。類似の記事は、他の有名雑誌にも掲載されていたそうだから、米国の日本本土爆撃計画を知るのに、日本はスパイさえいらない、とアームストロング氏は、言うのである。FDR政権は日本に先制攻撃をかけても、国民の賛同は得られると判断したことの、重大な傍証である。この週刊誌は軍事雑誌でもないのに、それ以前から軍用機や戦車、などのコマーシャルが満載である。この時期の米国民にも戦争に対する歓迎ムードがあったのである。
ルーズベルトや国民が対日戦を欲する大きなきっかけとなったのは、昭和12年の支那事変の開始であろうと、小生は仮設する。FDRの隔離演説はこの頃に行われているからである。さらに米国民の心理から言えば満洲事変、いやそれよりも早く、排日移民のムードが高まったころに淵源を発すると思う。この頃日米戦わば、という本がさかんに出版されているのである。
結論を言おう。FDR政権と米国民は真珠湾攻撃以前から、対独戦と同時に対日戦を欲していた。結果的に、あくまでも結果的にではあるが、真珠湾攻撃は両方の戦争に参加する重大なきっかけを作ったのである。ルーズベルトは裏口からの対独参戦を欲したのではない。真珠湾攻撃は、ガソリンの充満した部屋にマッチを放り込んだのである。真珠湾攻撃の戦果からはマッチでは失礼である。松明を放り込んだとしよう。
付記する。以上の説は、スターリンが日本と米国の双方の政府に食い込んで、米国の対独、対日参戦を画策したと言う説と矛盾するものではない。ただし、対日戦については、コミンテルンの画策の以前から米国自身にも、その淵源がなければならなかったと考える次第である。
*フーバー大統領「裏切られた自由」を読み解く・渡辺惣樹
**昭和陸軍の軌跡・川田稔
「日本の元気」のホームに戻る