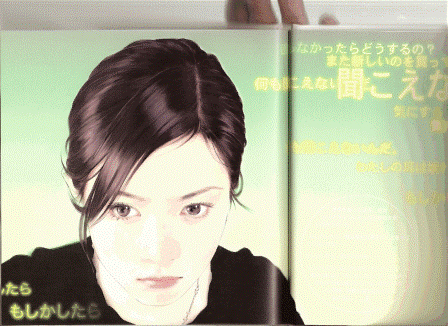�Z�]�˕����̎c��
�@�u���������̖ʉe�v(�n�Ӌ���E���ɔ�)��ǂ�ł���B���҂́A�]�ˊ��Ɋ����������{�����́A���ɓ��{��������ĂȂ��A�̕��ꓙ�̓`���|�\�̂悤�Ȃ��̂Ɏp����Ă���悤�Ɍ����邪�A����͎c��ł͂Ȃ��`�[�ɉ߂����A�c���Ă���Ƃ��������Ȃ��悤�Ȃ��̂��Ƃ����B�M�҂̓n�ӎ��͂P�X�R�O�N�����A���a�T�N�̋��s���܂�ł���B������A�炿�ł������Ƃ�������A�������ɂ͊O���ɏZ��ł����̂ł���B
�@������A���͒m��Ȃ����낤�������̓c�ɂł͂܂��A�c��Ƃ�������̂������c���Ă����ł��낤�B����͎����g�̌o���̈ꕔ�ł�����B���́A�n�ӂ���قnj�̐�㐶�܂�ł��邪�A���̖{�̋L�q�Ŏv���o�����̞O���ȑ̌��������Ă݂����B�s��̒ʂ�ɂ́A�u���ꂼ��̓X������̏��i�ɂ������邵���������Ă��邱�Ƃ��B�E�E�E�ނ�̑����͓����ɏn�B�����E�l�ł��������B���Ȃ킿�����͎�����������������̂ł���B(P214)�v�Ƃ����B
�@���ꂱ���A�M�A�n�A���ȂnjX�̏��i�����P�ƂŁA�������A�R�̂悤�ɑ���Ȃ��̂���I�ɔ����Ă����Ƃ����̂��B�Ƃ������Ƃ́A���̒��x�̂��Ƃ����Ő��v�����Ă�ꂽ�Ƃ������Ƃ��A�ƌ��_����B�����Ŏ��̐��Ƃ̘b���������B���a�R�O�N�䔼�܂ł̘b���A��ł���B
�@���Ƃ͎l���オ���������Ƒ��̐�Ɣ_�Ƃł������B�������A�_�Ƌ@�B�Ȃǂ͂Ȃ��A�n�œc�ނ��k���Ă������A����ȊO�͑S�ČL�Ȃǂ̔_�@��ɂ��l�͍�Ƃł������B�R�r�������A�R�r�̓��������̂悤�Ɉ��݁A�R�r�̔���������č��z�c�ɂ��Ă����B�R�r�̓����H�ׂ��낤���L���ɂȂ��B���X�����O�ō���Ă����B�����͎�Ƃ��đc�������Ă����悤�Ɏv���B�c���͖��������ĊO��p�ŁA�R�r�̔�̏����͕��ɂ͂ł����A�c�������Ă����B
�@�\�c��͓~�ɂȂ�ƈ���������`�����������A�T�c�}�C����V���Ɋ����Ă����َq�̂悤�Ȃ��̂�������肵�Ă����B���Y�����̒Е��ŁA�����Ђ�����̂�����A�Ê��F�����ĉ��h������̂������B��͌��C�Ȏ��͐��̒Е�������āA�����������ɑ����Ă��ꂽ�B�Ƃ��낪����N����A�������̒Е��ł��S���Ⴄ���̂ƂȂ����B�����ŒЂ����Ȃ��Ȃ�A���Ŕ����đ����Ă����̂ł���B������A������ł͂Ȃ��A�����������肵���B
�@�\�c��̎d���͏������̎d���ł������낤�B�c��͂Q�X�ŕa����������A���̎d���̈����p�����ł����A�\�c�ꂪ�N�����Ə��d���͖����Ȃ��Ă��܂����B��͑\�c�ꂩ��Ǝ���Ƃ̂�������Ȃǂ�������ꂽ�ƌ������A���Ǒ\�c�ꂪ���Ă����A�����`����Ȃǂ͈����p����Ȃ��Ȃ����B���̂悤�ɂ��Ēf��͋N���Ă������B����ɌZ�̉�����͐�Ǝ�w�ł͂Ȃ��A�Ɛg�̍�����̎d���𑱂��Ă�������A��͏��d����`���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��āA�f��͌���I�ɂȂ����B
�@���̑��e��̖�͂قƂ�ǂ��A���X�Ђ��ł������Ǝv���B�Ď�̂̔_�Ƃ����������⋼�������A���{�ŕ��ʂɎ����A�ӉZ�A���A�L���x�c�A�i�X�A�l�Q�A�卪�ȂǑ��͎��Ɨp�ł���A�s��ɏo���悤�ɂȂ����̂͌�̂��Ƃ������B�`�����͓��ވȊO�́A�T������痈��A�S�O��̂������]�Ԃɏ悹�čs�����鋛���Ă����̂ł���B
�@������́A���C�@�֎Ԃ��}���z�̂��߃X�B�b�`�o�b�N�����Ȃ���ꎞ�Ԃ����鋙�`����ʂ��ď��������Ă����̂ŁA���̃��[�g�����]�ԂɎR�قNj���ς�ʼn������Ă����̂����獡����l������ٓI�ł���B���̍��́A�S���̐�Ɣ_�Ƃł���_�Ɋ��ȊO�͂��낲�낵�Ă������A�J���~��Ɣ_��Ƃ͋x�݂ł���B���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł���B
�@�ւ̖������������̂ŁA�ւ̎����ނ���̏�ɕ��ׂĊ����Ĕ�������A���֖��p�Ƃ��Ĕ������̂ł���B�\�c��́A�c�������Ԃ͌Ò���D���Ă�����ł��G�Ђ�����Ăǂ����Ɋ�t���Ċ��ӂ���Ă����B�_�Պ����������������̂ł���B
�@����Ȃ��ƂX�Ə������̂́A�n�ӎ������̏��i�邾���Ő��v�����Ă��A���������i�͎��삾�A�Ƃ������ƂƊW������悤�Ɏv���邩��ł���B�]�c��̍���������`��Е��A�c���̎R�r��̂Ȃ߂��Ȃǂ́A��r���悤���Ȃ����N�G�̓������E�l�|�������Ǝv���B�c���Ƒ]�c��͖فX�ƍ��C�悭�A�����̍�Ƃ����Ă����̂ł���B�������A�����̔_�ƂȂǂ����ŁA�������ł����̂ł���B
�@��N���ꂪ�_�Պ��Ɍ��Ƃ�ʋl�H��ɍs������A��ؑ���𑝂₵�ϋɓI�Ɏs��ɔ���o���悤�ɂȂ����̂��A�q���̍��͕s���Ɏv�����B����܂ł͐�Ɣ_�Ƃŕ�点������A�n�ӎ��������悤�Ȑ̂̎��������̐����������̂ł���B���a�R�O��㔼����}���ɗm�����ėm�����������A�_�Ƌ@�B�������������猻�����K�v�ɂȂ����̂ł���B���̏؋��͎����w�Z�ɍs���̂Ɏ��]�Ԃ������A�����͔����Ŏc��͎��������J�[�ɖ��ς�ő���ɂ����̂ł���B�H�Ɛ��i���ɂ́A�������s�����邩�畨�X���������̂ł���B
�@�܂�A�m���A���]�ԁA�_�@������@�Ƃ��������̂��Ȃ��A����̂�������ŗV��ł�������Ȃ�A�����͔_�ƂȂǂŘd������x��������Ȃ������B���͎��O�ł����܂ōl�����B�������A�n�ӎ������m����H�Ɖ��ɂ���ē��{�������łт��A�Ƃ����Ă���̂�ǂ�œ��S�����̂ł���B���̂��Čo�������_�Ƃ͓��{��������ȑO�̎c��ŁA�̂���̋Z�p�̔_�Ƃ⏬�K�͂̎�H�ƓI�Ȃ��̂��Ƒ����o�ł���ΐ����ł����̂ł���B
�@���̑��Ɏv���o���͍̂��J�ł���B�_�n���������̂���̉Ƃ̕~�n�Ƃ��ڂ����͈͂́A�P�O�O���~�Q�O�O���ʂ������͂��ł���B��˂̘e�ɂP�����A�ՉƂ̋��E�ɂP�����A��������Ƃ̕~�n�܂łP�T�O���قǂ̎���������A��������Ƃ̕~�n�ɓ���Ƃ���ɂP����(�n���ω�)�A�~�n�̓���[�ɂP�����̍��v�S�����ɐ_�l���J���Ă����B
�@���ɓ���̂��̂́A���������薳�l�ł��邪�����̂��鏬�K�͂Ȑ_�Ђ̌`���Ƃ��Ă����B��������_�Ђ܂ł͐����[�g���ł͂��邪�A�Q�������������B�����̘e�ɂ́A���̒n���ɂ͒������傫�ȋ�ǂ̖���{�������B�n���ω��ɂ́A�N��������ċF��K�����������B�����ł͏����̉��ʼn��炩�̋F�肪����Ă������A�L�����ڂ₯�ĒP�Ȃ鏼���̖�����̓_���ł͂Ȃ����Ƃ����Ă����������A�o���Ă��Ȃ��B����͑c�����N�V���Ă���Ǝ~�߂��B�n���ω��ȊO�́A���_�A�y�_�Ƃ����ЂƂ͕��_���ΐ_�ł������낤���o���Ă��Ȃ��B�����̐_�X�ɂ́A������������ȊO�ɁA���Ă͉��炩�̍��J���s���Ă����Ǝv�����A�����̋L�����鎞��ɂ͐₦�Ă����̂��Ǝv���B���̂��Ƃ́A�n���ω��̏������Ƃ������J��K�����c���Ă������Ƃ��玄������ɐ��@�����̂ł���B
�@�����A��˂̘e���K�̐Ό˂���������S�ɊJ����ƁA�Ԃ������J���������ς̑��������āA�����Ƃ������Ƃ�����B�����͑����Ɏs���ɏ����グ��ꂽ�B�m���̉Ƃ��Â��Ȃ茚�đւ���̂ɁA�����P�O�O�����Ƃ��ڂ����̂́A�_�n�̐^�ɍ������݂̌v�悪���������炾�Ǝv�����A�����̎����A�_�X���K�͋��ꏊ�������Ȃ��Ă��܂����B
�@����͊��ɕ�������������ŁA�ꂾ���c��������ɂȂ��Ă���ł���B��͓Ɨ͂ŁA�_�X�̌�_�̂��A�V�����ꉮ�̗��ɂP�����ɂ܂Ƃ߂Ă��܂����B�{���Ȃ�A�����ł݂��ĂāA�V�������~�̕~�n�ɁA�_�X�̊e�X�̋��ꏊ���߂��J��ׂ��ł������낤���A��ɂ͂��̒m�����C�͂������������A�Ƃ��p�����Z�͍L���_�n��݂��Ȃǂ��Ď�鎖�ɋ��X�Ƃ��č��J�ɂ͊S���Ȃ������B�Ƃ�����茙���Ă������瓖�R�̌��ʂł���B��_�̂��c���������܂��ł���B�Ƃ��o�Đ��ƂɊS���Ȃ��������ɂ́A���Ƃ�肻����߂鎑�i�͂Ȃ��B
�@�u���������̖ʉe�v�ɂ��A�u�M�ƍՁv�Ƃ����͂��݂����Ă��邪�A�O�L�������Ƃ̍��J�͌×��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������A�Ƃ������ƂɑΉ����邱�Ƃ͏q�ׂ��Ă͂��Ȃ��B���m�l���������{�̋L�^����L�q����Ă���̂ŁA���̂悤�ȗނɂ͊ώ@�������悤���Ȃ������̂��낤�B�����炱�̗ނ̕����́A�c���ꂽ�K�Ƃ����`�[�����ŁA�{���̎p�͂�����L�^������������Ă������̂ɈႢ�Ȃ��B����������Ɗ��ɑ\�c��̐���̋L���ɂ���c���Ă��Ȃ������̂����m��Ȃ��B
�@�\�c��͓`����ꂽ�K������J����鎖�ɂ͔M�S����������ł���B�������A��N�̐��m���������B�ɂ́A�ς킵�����̂ł����Ȃ������B�n�ӎ��̂����Â����{�������łт��A�Ƃ����̂͌��ǁA�l�X�̐��_�̂���������m���ɂ���ĕς�������Ƃ��Ӗ�����B
�@�u���������̖ʉe�v�́u�M�ƍՁv�Ƃ����͂ɂ́A�B�ꏬ���̋L���ƈ�v����L�^���������B����́u�t�H�[�`�����͖앧�ɕ�����ꂽ�f�p�ȐM�S�̎p��`���Ă���B�w�_�ސ�h�̋ߖT�̖�ʂɂ͂����Ă��A�������K�������āA�Z���͂���ɐ����������A�ɍ��܂ꂽ�����Ȑ_�ɉ��⓺�݂Ȃǂ̂�����������B�E�E�E�x(P538)�v�Ƃ����L�q�ł���B�����ăI�[���R�b�N���`�����u���[���K�v�Ƃ����}�G(P539)�́A�܂��ɏ����̐��Ƃ̖��l�̐_�ЂƓ����p�����Ă���̂͊����I�ł������B
�@�܂��A�O�f���ł́A���{�̓c�����i���뉀�̂悤�ŁA���������R���̂܂܂ł͂Ȃ��A�l���O����Ɏ����ꂽ���������̂ł���A�Ə����B�����̎q���̂���Z���Ƃ̒�ɂ͒z�R���������B���C���͋��؍҂Ƃ�������ŁA�z�R�̒��ɂׂ͍��ʘH�������Ďq���̗V�я�ɂȂ��Ă����B�z�R�͋G�ߖ��ɍ炭���Ԃł������Ă����B�ƂƂ̋��ɂ͒��������ɂ킽���Ēւ��������B
�@���̐^�ɂ͊`�����{���A����ꂽ�X�y�[�X�����������A�`�͑��ɂ����̊p�X�ɐA�����Ă����B�Q�O���l���̒|����Ƃ����G�ؗт��������B�����̐A���͑S�Ď��R�̂��̂ł͂Ȃ��A�l�H�ɑ����������̂ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�n�ӎ��̋L�q�������i�����a�R�O�N��܂ł������̂ł���B�������A���ꂪ���m�l�����Ĕ��I�Ɋ�������̂ł��������������m�M���Ȃ��B
�@�O�f���̋L�q�Ə����̋L���ƈ�v������̂ƈ�v���Ȃ����̂��������lj�����B�c���͖ő��ɓ{��Ȃ��l���������A�y���C�����Łu�{���v�Ƃ������Ƃ��u����Ȃ��Ƃ͌�������Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Č������{�����̂�s���Ɏv�������u�n���ƒ{���Ƃ������t���A���{�l������ɗ��т������镎�J�̋Ɍ����B(P167)�v�Ƃ������Ƃƈ�v����B���ɂ͂Ȃ��ꊴ��c���͎����Ă����̂ł���B�u���̂���́w���ł������Ă���l�x�́A�����̂��Ƃ��w����x�Ƃ����̂͒������Ȃ������ƒf���Ă���B�]�˂̏����ɁA�j���t�Ə����t�̍����قƂ�ǂȂ�����(P371)�v�Ƃ����B�\�c��͊ԈႢ�Ȃ��A�u����v�ƌ����Ă������A�j���t�Ƃ̋�ʂ��Ȃ������悤�Ɏv���B��������̂��Ƃ��u�������v�ȂǂƏ����t���g�������Ƃ͍l�����Ȃ��B�����̐��Ƃ́A�������牓���Ȃ����l���t�Ɏ����a��̂���c�ɒ����������A�]�ˌ��t�̉e���͑��ɂ��݂���B
�@�_�k�n�Ƃ��āA�n�������Ă������A��n�̏K���͂Ȃ������Ƃ́A�O�f���̋L�q�ƈ�v����B���������������͏�n���i�������������̂ł���B���{�́u�L�͑l�����̂͂������肾���A�����ӂ��҂̂����ɐl�ɊÂ��邾���͒B�҂ł���(P483)�v�Ƃ����̂����A���ƂŎ����Ă����L�͑�X�A�l����邽�߂Ƃ������Ƃ��������A���ۂɑl�߂�ɖ𗧂��Ă������͉������B�������k�^�@���Ĕn�������A�Ō�̎��t�������Ă�������A�����Ɉ���[�������̂��{���ł���B
�@�S�ʓI�ɁA�����̓��{�l�͗z�C�ł悭���A�O���l�ɂ����C�Řb��������A�Ə�����Ă��邪�A���̓_�͎��̏펯�Ƃ���ʓI���{�l�ςƂ��傫���قȂ�B�����A��̎��Ƃ̐e�������͗z�C�Ől���m�肵�Ȃ������������B�����̌Z��͏]�Z�ɁA���܂��́A�O�ŗV�Ȃ��A�Ɨ�₩���ꂽ�L��������B�����B�ꎝ���Ă���Â��Ƒ��ʐ^�ł́A�c���͌L�������ď㔼�g���̑c�����ʂ��Ă��邩��A�J��������{�l�͗��ŕ��C�ł������A�Ƃ����̂����̒ʂ�ł������B�ȏ�̂悤�ɁA�O�f���ɏ����ꂽ���Ă̓��{�l�̎p�́A���̗c���L���ɂƂ��đS���ӊO�A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@�n�ӎ��́u�E�E�E�Ӑ}����̂́A�Â��悫���{�̈��ɂł��Ȃ���A����ւ̒Ǖ�ł͂Ȃ��B(P65)�v�ƒf������B����́A�P�ɈӐ}�������ł͂Ȃ��A�Ɣے肷�����ł͂Ȃ��B���������A�Â��悫���{�����ɂ��c���Ă����̂ɂ���A�Ȃ������ɂ���A���̂悤�Ȏ���̋L�����n�ӎ��ɂȂ���A���ɂ�Ǖ�͐����悤���Ȃ��̂ł���B�嗤�Ɉ�����n�ӎ��Ƃ͈قȂ�A���́A�O�q�̂悤�Ɋm���ɉߋ��̓��{�̎c�e�������̂ł���B����́u�ǂ����{�v�ł������Ƃ͎v���Ȃ��B�������A���ɂƒǕ�̔O�͔����ɂ���A�ƌ����Ă��������B
�����������̋����鑺��������
�@�����������́u�������_�v�ɂ͏����̑̌������ɂ�������炸�A�����ɗ����ł��Ă��Ȃ����������̂�������Ă����̂ŁA�����̌o���Ɨ��߂Ė{���́A���{�̋����̂Ƃ��̕���ɂ������グ��B(P169)�܂������̂̒�`�ł���B
�@�����̓��O�͓�d�K���ƂȂ��Ă���B�A�Љ���͂܂��A�����̂ɔz������A���ɋ����̂̊e�����o�[�ɍĔz�������B�B�����̂��h�i�ȏ�Ɏx�z����Ă���B
�@�Ƃ���3�����ł���B
�@�����͎q���̍��A�܂��ɁA���������̂̒��ɂ����B�������A�����̌������͕̂��O�̎p�ł������̂ɉ߂��Ȃ��̂��낤�B�@�ƇA�͐h�����Ďc���Ă������A��q�̂悤�ɇB�Ȃǂ͖����Ȃ��Ă����B�����̎��Ƃ͍���}���قŒ��ׂ�ƁA���m�̗��ȑO�Ɏd���Ă����̎傪�헐�ɕ��������߂ɁA���ďZ��ł����y�n�ɖ߂�A����ȗ��y�������B�������̒n��̂����ł��A�����Ƃ����P�O�����̓����̉ƂƂ����t�����Ă��Ȃ������B�S�Ă������ł������Ǝv���B
�@�����͔s�c�������߂Ɏ��͂��x�����������m�Ōł܂����A���̗��l�����ł������̂ɈႢ�Ȃ��B���q�����ł���������A�{�Ƃ̉䂪�Ƃ̓y�n�͍L��ł������B�R�O�N�ʑO�ɒ��̉Α��ꂪ�ł������A�����܂ōs���̂Ƀ^�N�V�[���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A��O�͂��̂�����܂ʼn䂪�Ƃ̓y�n�ł����������ł���B
�@�����Ȃǂ͊e���̉Ƃł���̂����A���҂̏o���Ƃ͉��������A�ʖ邩�瑒�V�܂ł̒i���́A�����̂̈ꑰ�őS�Ă��Ă��܂��B�H����セ�̑��̌o�������ƁA���̉Ƃ̍��z����A�f����Ȃ��Ɏ����čs���Ďg���B����قǔZ���ȊW�ł������B�c�A���Ȃǂ̑�K�͂Ȕ_��Ƃ͋����̂̒��ԑS�����W�܂��āA�e�Ƃ̓c�ނ̍�Ƃ����Ԃɂ��ĕЕt�����B�����̓c�A���̌�̖�́A�������炵���i�Ȃǂ̓����Ƃ��Ă͖ڂ����ς��̌�y�����o���Ă̑剃�����J��L�����Ă����B
�@�����ύׂ�����ƁA�������̃O���[�v�ɕ�����Ĕ��ڂ��Ă����B�s�v�c�Ȃ��Ƃɖ{�Ƃł����Ƃ������Ǘ����Ă����B��͈Ӓn�����肾����A�{�Ƃ͔n���ɂ���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɠ˂������������B����Z�������̎q���ɂ��炩����ƁA�n���ɂ����ȂƁA�{��ꂽ�B�����p���ď��������̍����̓C�W�P�Ă������̂��Ǝv���B��Ȃ��Ƃ����A�Z�����l�����}�����Ƃ��A�\�c�ꂪ�ߏ��ɌZ�����A�ɘA��čs�����A�Ƃ������Ƃ��ŋߕ������B�{���͖{�ƂɊF�����A�ɗ���ׂ��Ȃ̂ł���B
�@���������悤�ɁA�Z�Z�Z�N���o�Ƌ����̂͂قƂ�Ǖ��Ă����B�\�y�ɒZ�������B���Ă��邩�畷���ƁA�c�����品��Z���܂��Đ��`���āA�����Ɏg���Ă����A�ƌ����B�����ɂ��c���ѓ���������Ă����m���ł���A�Ƃ����ւ�͂Ȃ��B���ɕS���ɓy�����Ă����̂ł���B
�@�����珬�����������A���������̂̕���̉ߒ��͋����[���[���ł����B�u��O�A�풆�ɂ����鋤���̂́A���_�ɂ�����V�c�V�X�e���ƒ�ӂɂ����鑺�������̂ł���A���{�̐l�X�����Ɉ��Z���Ă����B�������s��ɂ���āA���_�ɂ�����V�c�V�X�e���͉��������B�E�E�E�v���I�ȋ}���A�m�~�[�����������B����ƂƂ������{�l�̐S�̍s���ꏊ�ł��������������̂��A�Q���A���Ă����A���x�����̐i�s�ƂƂ��ɁA�قƂ�ǎp���������B�v(P170)�̂ł���B
�@���{�̌o�ς̍��x�����Ƃ����ƁA���a�O�\�ܔN�����肩�炾�Ǝv���Ă��邪�A���͏��a��Z�N��̖����Ɏn�܂��Ă����̂��ƌ����B�Ƃ������Ƃ͑��������̂��A���̍�������n�܂����̂ł���B���a�R�T�N����S�T�N���P�O�N�Ԃ̎Љ�ϓ��͌������A����܂ł̂P�O�O�N�Ԉȏ�̐����l�����ω����N�����ƌ����B�����ɑ��������̂���ł����B����͏������̌������B���a�R�O�N��O���́A�q���̕��i���͘a���������B�a���ƌ����Ε��������������A�{���ȗ��߂̂悤�Ȃ��̂ɑe���ȑт���߂ėV��ł����B
�@���{�̋����̂́A���������̂ł��A�n�������̂ł��A�@�������̂ł��Ȃ��A�S�Ĉꏏ�Ɏd�������邱�Ƃɂ���Ăł���u���������́v�̂������ł���B���̎��͑O�q�̂悤�ȁA�F�Ŕ_��Ƃ��������Ă����A�Ƃ������Ƃ��珬���ɂ͎����ł���B�u�E�E�E���x�����ɂ���đ�ʂ̘J���͂��s�s�֗��o���_���ߕی쐭��ɂ���đ����ɂ����鋦���V�X�e���͉�������B����ɗ��ʌo�ς������ɂ܂ŗ����������Ƃ����̌X���ɔ��Ԃ��������B�v(P173)�Ƃ����̂����A����������ɂ͎���������B
�@�����̒m��̂̔_�Ƃƌ����͎̂��������ɋ߂���������A�����͋ɂ߂ď��Ȃ��čςށB�ߕ��͌p���͂��ŁA�Z��̂�������₨�Â��g������ő��ɔ����K�v�͂Ȃ��B�s��ɔ_�Y����Ό����͑��肽�B�����͍��Z�ɍs���̂����Â̎��]�Ԃ��Ă���������A�����͌������������A�����͕ĂƖ�������J�[�ɐς�ōs���ĕ������B���ƂŐH�ׂ�ẮA�H��ɉ^��Ő��Ă��Ă�������B�����őS�������Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ��낪����̒��x���i�݁A�_�Ƌ@�B������Ƃ����͂����Ȃ��B�������K�v�Ȃ̂ł���B���̑��苦����Ƃ͕K�v�Ȃ��Ȃ��B�����͂ǂ����邩�B�c����̂ł���B�������đ��������̂͏������B�u���������̂����A�����̓��{�l�ɂƂ��Ă͐S�̈˂菊�A�̋��ł������B�s�s�֏o�Ă��O���֍s���Ă��A�w�u���Ƃ��āA�����̓��ɂ��A��x�ꏊ�ł������B���̑��������̂��A�����Ė����Ȃ����B�T�A�����ւ�B��厖���B�E�E�E�����ŁA�@�\�W�c�������(���)�͋����̂ɐ��邱�Ƃɂ���āA����ȋ}���A�m�~�[�����������Ƃɂ����B�v(P173)���̒ʂ�ł���B
�@�������A�S���̉�Ђł͂Ȃ��A�咆��Ƃł���A������Ƃ���Ƃ͋����̂ɐ��肫���Ă��Ȃ��̂��Ƃ����B���̗��R�̐����͂Ȃ����A�z������ɁA������Ƃ���Ƃ́A����l�����Ђ��Ă��玀�ʂ܂�(���߂Ē�N�ސE�܂�)�������邱�Ƃ��������ł��낤���A�����܂ŎЈ��̖ʓ|������Ȃ������̂��낤�B�܂��A�K�͂��������Ɛl�ԊW���Z���߂��Č�����{�l�ɂ͑ς����Ȃ��̂ł��낤���B�悭�킩��Ȃ��B
�@�����͑̌����瑺�������̂����Ă��܂��A���̑���ɉ�Ђ����������̂̑���������Ă���A�Ƃ������Ƃ͂ڂ���v���Ă����B���������������́A���̂��Ƃ��ɐ������Ă��ꂽ�̂ł���B������Β����̉�Ђ́A�Ƃ����Ƌ����̂ɂ͂Ȃ�Ȃ������ł���B����͌��������́A���Ȃ킿�@�������݂��A�}���A�m�~�[���z�����邩�璆����̂ɂ͂�����Ȃ������ł���B������v���ł̑�ʋs�E�A���]�A�юv�z�̔ے肪�}���A�m�~�[�̔����������邪�A���Nj����̂��z�������̂��ƌ����B
���䐬��
�@�����Q�U�N�V���P���Ɏ��p�ŏ��Âɍs�����B��͍��͏��Îs�ƂȂ��Ă��邾�낤���A�x�O�̈���R�̘[�̐��܂�ł������B��̉ł����X�͓c�ɂŃf�p�[�g���Ȃ���������A�m���ȂǑ傫�Ȕ�����������ɂ́A�킴�킴�ꎞ�ԋD�Ԃɏ���ď��Âɔ������ɍs�����Ƃ���Ƃ��Ă����B��̉ł��悪�c�ɂŁA���ÂƂ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��Ƃ����������q���S�Ɍ����Ɋ�����ꂽ�B�D�ԂƏ������̂́A�d�Ԃł͂Ȃ��A���C�@�֎ԂŌ�Ƀf�B�[�[���̋C���ԂɂȂ�������ł���B
�@�f�p�[�g�ŐH�ׂ钋�H�͕K���ݖ����[�����������ƋL�����Ă��邪�肩�ł͂Ȃ��B��Ƀ����}�ƃ`���[�V���[���킸���ɓ�����������������Ƃ������̂����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̖����ݖ����[�����̖��̌��_�ŁA�����ɓ����������߂Ă��邪�o���Ȃ��B�������L���X�́A���������Ղ�̔����������̂̓_���Ȃ̂ł���B
�@����͎���ɂ�����䐬���ł���B���ׂ���A�����Ɠ������̂ʼn˂��ւ����Ă��Ȃ��B���Ɍ�����R�����юR�ŁA�����͎R���ɓV�����̃v���l�^���E��������A�����R�[�X�̂ЂƂ��������A�Ƃ��ɓP������č��͂Ȃ��B�}���V�����Ȃǂ͂Ȃ���������A�䐬���̌��ɍ��юR�̑S�i���������̂ł���B��Ԃ̎v���o�͎���̉ԉΌ������B���܂�ď��߂Č���{�i�I�ȉԉΑ���������A�K�͂͗y���ɏ����������̂��낤���A��\�N�ȏ��Ɍ������c��̉ԉ�������Ȉ�ۂ������B
�@���̂����ƂŌ����Ƃ����L�������Ȃ��̂ŁA�䐬�����������O�������������肩�ł͂Ȃ����A�䐬������ԉ����������O�ł���B
�����쓃

�@����͏��������Ƃ������w�Z�̍Z��ɂ���B�u���쓃�v�ł���B���̒��쓃�́A�T�Ɍ��Ă�ꂽ��������ɂ��A����̖�����哌���푈�܂łɁA���̒��Ő�v�����O�S��\�]���̕��m�̗���Ԃ߂���̂ł���B��O�̐l���́A�O���l���x���Ȃ���������A�l���䂩�炢���ΕS�l�Ɉ�l�ȏ�ł��邪�A���̊Ԃ̐����҂͂��̉��{���������낤����A�䗦�͂͂邩�ɏ��Ȃ��B
�@���̎O�S��\�]���̐�v�҂̒��̈�l�ɏf��������B���쓃�͏I�킩��Ԃ��Ȃ����Ă�ꂽ���A���̌�������͏��a�\�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B��������ɂ́u���h��F�̑嗝�z�Ɠ����퐪����������v�]�X�Ə�����Ă���B���݂̓��{�ł͂��̂悤�Ȕ�͓��ꌚ�Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���a�\�N�̓��{�l�͂܂����C�������Ă��Ȃ������̂ł���B
�@���̒��ɂ͐��Ԃ��Ȃ��ČR���i�����A���e���K���J��Ԃ��Ă����B�֒e�̒e���������邽�тɁA������ȉ䂪�Ƃ̑��K���X�̓r���r���h��āA����邩�Ǝv�����ʂł���B���e���K��ɂ͋ߏ��̎�w�����䰂��E���Ĕ���o�C�g�����Ă����B�^�J�̖�䰂͍������ꂽ�̂ł���B
�@��䰏E���͉��K�̋x�e�̍��Ԃɍs����B�Ƃ��낪���N���Ɉ�x�͕ĕ��ɎˎE����鎖���������B��˂��Ɛ�������Ă���������Ȃ͂��͂Ȃ��B�댯�Ȃ̂ŕČR�̌P���̋x�e���Ԃ͒��Ɏ��m�O�ꂳ��Ă��āA���������ԈႦ��͂����Ȃ��̂ł���B�ĕ��͗V�є����Ɍ����E���̂ł���B�I�[�X�g�����A�ɈڏZ�������l�����́A�^�X�}�j�A�̃A�{���W�j�[���n���e�B���O�V�т̑ΏۂƂ����̂Ő�ł����A�Ƃ����b����N�������Ƃ��A���͓c�ɂ̌�ˎ����͌̈ӂł������ɈႢ�Ȃ��Ɗm�M�����B
���ӂ邳�Ƃ̐_�X
�@���{�ɂ͂₨��낸�A���Ȃ킿���S���̐_������Ƃ����B�����ł��낤�B����͎��̂ӂ邳�Ƃ̗���ɂ��킵�܂��_�X
�@���̌�_�l�����킵�܂����y�n�͑S�Ĕ���ꂽ�B�ꂪ����ł͂����Ȃ��ƁA��l�ŐV�������~�Ɉڐ݂����̂��Ƃ����B�_�X�͌��X���̂悤�Ɉ�ӏ��ɒu����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�O�q�̂悤�ɍL�����~�̎l�ӏ��ɕ��U����Ă����̂ł���B�ꂪ��J���Ĉڐ݂����̂�����A��ӏ��ɂ܂Ƃ߂����_�o����鎑�i�͖l�ɂ͂Ȃ��B
�@���̐Δ�l�̂��̂ɂ͔n���ω��Ə�����Ă���B�_�ƂŔn����������ł��낤�B���Ԃ~�̒�̓�����̘e�ɂP���ʐ���オ�����ꏊ�ɒu����Ă������̂ł���B�N�Ɉ�x�����̍Փ��ɏ������Ƃ����ꏊ�ł������B�E�����Ԗڂ͉Ƃ̗��̈�˒[�ɒu����Ă����B�q���̂��낢������ŁA�K�̌˂��J�������Ƃ�����B�^���ԂȌ��������A�����ς��������Ă����B
�@���~���瓌�ɓ�S���[�g���قǗ��ꂽ�ꏊ�̑傫�ȋ�ǂ̖̉��ɒ���������ꏊ�̈�ԉ��ɁA��ԉE�̐_���J���Ă����B���l�_�Ђ̂悤�Ȃ��̂ł������낤�B�������Ԗڂ͉��~�̕~�n�̐��[�̗ƂƎs���̊p�ɒu����Ă����̂��ƋL�����Ă���B���͂��̐_�X�̂��{���𐳊m�ɂ͒m��Ȃ����A���_�A���_�A�y�_�������ƋL�����Ă���B�l�G�̉����̓����ɋ������������L��������B�������e�X�̐_�Ɉ�Ăɂ�����̂ł͂Ȃ��A�e�X�̏o�Ԃ̓�������̂ł���B���ł͐_�X���e���Ɉ����Ă������ł͂Ȃ��B
�@���S�N�߂��������~���ڂ������Ƃ�ɂ���ŁA�����~�ł��������Ƃ������Δ��c���̒킪���Ă��B���i�c�ɐ������y�̂��镗�������������Z���̑c���̒���A���Ƃ̎���[���v���Ă����̂ł���B���̐Δ�����~�Ղ��ؒn�ɂ��Ă��܂������߂ɁA�P������ĉ��ƐV�������~�Ɉڂ���Đ_�X�ׂ̗ɂ���B�]�Ɋ�ȉ��m�̗��ȑO���瑱���A�킪�Ƃɓ`���͂Ȃ��B���������������ƌn���ւ邾���ł���B�c�����A�c���̒킽���������Ƃ��̐̂ɖS���Ȃ����B������ɋS�Ђɓ������B�ӂ邳�Ƃ͖{���ɉ����ɂȂ��Ă��܂����B���ɂƂ��Ăӂ邳�Ƃ��ӂ邳�Ƃł���̂́A���܂�ɕϖe�������Ƃ̎��ӂ̌i�F�ł͂Ȃ��A���Ƃ̎O�����͂ޕς��Ȃ��R�X�̕��i�����ł���B
���Q�Q�̎�
�@���̎ʐ^�����ė~�����B�ꌩ�����̕ϓN�̂Ȃ���ł���B���݂͋�����n�ɂ���B���͖�S�O�N�Ԑ�p�̕�n�ɂ������B�킪�Ƃ͐�Ɣ_�Ƃ������B���̘e�̍���̂P�O��ʂ̕~�n�ɁA�����P���قǂ̐Ί_�𗧂āA���ɋʍ�����~���Ă������B���̒����ɂ������̂����̕�ł���B���͂ɂ͒|�őg����B��̂�����ɂ͍�̖��т�����A���Ă���B�s������s���ɂ͐Α���̊K�i��o��ƕ�n�̉��ɒ����B��������Ί_�̈�p�ɍ��ꂽ�K�i��o���Ă悤�₭�ʍ����ނ��Ƃ��o����̂ł���B�q���S�ɂ������Ȃ��肾�Ɗ��������̂ł���B�c�ɂ̓c�����i�ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��A�_�Ђ߂������͋C���������B
�@����͕��̒�܂莄�̏f���̕�ł���B�Ǔ��̈Ӗ������߂Ă��̗R������肽���B�f���͒n���̂̒��w���o��Ɖ��{��̊C�R�q��Z�p���ɋ߁A�Q�Q�ŗ��R�ɏ��W���ꂽ�B���Ƃ͍H��̈Ӗ��ł���B�C�R�̍q��@�̋Z�p�J���Ɛ��Y���s���Ă����A�C�R�q��̒��S�ɂ���Ƃ���ł���B�����̍q��Z�p�͖��Ԃ��R�A���ɊC�R���i��ł�������A���{�̍q��Z�p�̐�[���s���Ă����̂ł���B
�@�f���͊C�R�̔�s�@�̊J����Y������Ƃ���ɓ����Ă����̂ł���B�Ȃ������R�ł���s�����ɔz�����ꂽ���O���Ƃ͊W����܂��Ǝv���B��s�����Ƃ͔�s��̐݉c�A�ێ��A�h�q���s�@�̉^�p������Ƃ���ł���B
�@�f���͂Q�Q�Ő펀�����B�Q�Q�ŏ��W����A�Q�Q�Ő펀�ł���B���a�P�X�N�W���̓��ɖ��F�ɏo�����A���̌��̖��ɂ͎���ł����B���m�ɂ͐�a���ł���B��ɕ����R�����ł���Ƃ����B��q�̂悤�Ɋ挒�������f�����P�������������Ȃ������̂ł���B���{�R�̈��̌��{�̂悤�Ɍ�����V�R�P���������͑嗤�̂��������s�q����̂��߂̖h�u�����ł������ƌ����͎̂��ɂ͔[���ł���B
�@��O�ɍu���ق̏��i�ł������f���͊挒�Ȑl�ł������B�����̍u���قƂ����̂͒i���Ƃ�̂��]��������������ł���B�����w�Z�ł����߂���ƒ�̏f�������Ԃ��Č�����ƁA�c���͌���Ă����B�^�t���Ă��������債�����͂Ȃ������̂��B����ȏf�����������Ȃ����B�c���͂����ЂƂ��ڂ��Ȃ������B�����A���ꂪ�����Ă���E�E�E�ƌJ��Ԃ��Ă������A���̌�̌��t�������Ƃ��Ȃ��B��Őe�ʂɕ����ƕ�͕s���ȍs�������Ă���B�N���Ƃ��đ̂̎��R�������Ȃ��Ȃ�܂ŁA��͐É��s�̌썑�_�Ђɖ��N�Ăɒʂ��Ă����Ƃ����̂��B����������Ƒ��ɂ́A���Ƃɍs���ƉR�����Ă����B��̐e�ʉ��҂Ő펀�����̂͏f�������ł���B������ꂪ�썑�_�Ђɂ��Q�肷��Ώۂ͏f���������Ȃ��B��Əf���Ƃ͓����ʂ̔N�ł���B��̎��Ƃƕ��̉ƂƂ͐�O���牏���������ƌ�������A�f���ƕꂪ�c����ł͂Ȃ������Ƃ͂�������Ȃ��B���������ƂȂ��Ă͉i���ɕ�����Ȃ���ł���B
�@�c���̔߂��݂̑傫���͐�c�`���̕�Ƃ͕ʂɈԗ��̂悤�Ȑ�p�̕����������Ƃł��m���B���������̌�������Z�͍����ł���B���̕��������n�Ɏ����Ă����̂͂Ƃ������A�c���̐S�����߂���n���Ă��܂��A�����������n�Ɉڐ݂��Ă��܂����B�Ƃ���o�����ɂ������鎑�i�͂Ȃ��B�����c���̖��O���v�����̂����Ȃ��Ȃ������Ƃ��c�O�Ɏv���B�������݂���̂͑c���̂��������Ǝv���Ă���B�����ł��߂Ẳ��Ԃ��ɁA�����P�O�N����������_�Ђ̉Ắu�݂��܍Ղ�v�ɂ͖��N�c���̖��O�Ō������Ă���B�����͐펀�Җ{�l�̖��O�ł͂Ȃ��A�⑰�̖��O�ōs���K��������B���̌�ꂩ���������f���̏o�����O�̎ʐ^���A�����_�Ђɑ����Čf�g���Ă�����Ă��邩��A�����_�Ђɍs�����тɎ�����킹��B
�@�f���̎ʐ^�͑c��̎ʐ^�ȂǂƋ��ɁA���Ԃɏ����Ă��������疈�����Ă������̂ł���B�ʐ^���̂͂悭�B��Ă͂��邪�A���ƂȂ������̂Ȃ��ዾ����������������A�Ƃ�������������B�������A�f���̎ʐ^�͑N���Ȃ��������B�����_�ЂɌf�g����Ă���펀�҂̎ʐ^�ɂ́A�s�N�����r���������̂����Ȃ��Ȃ��B�����܂ł��Čf�g���Ă���̂́A�⑰�̑z���������ɋ������m���B���Ȃ݂ɖ����_�Ђ̗V�A�ق̈�p�ɂ́A�����_�Ђ��J��ꂽ�펀�҂̎ʐ^���⑰�̐\���o�ɂ��f�g�ł���R�[�i�[������A�펀�҂̎ʐ^�������Ƃ���B�f�g�̏��Ԃ͒P���ɐ\���o�̏��ŁA�K������тɂ͊W���Ȃ��B�������̎ʐ^�������̈ꕺ���̒��ɍ������Ă���B
�����̐킢
�@���͑吳10�N���܂�ł���B�����璥���ɍs���Ă���܂��Ȃ��푈���n�������߂ɁA���W��������嗤�ɓn�����B����͌��������Ƃ������B����͌R���p��Ƃ��Ă͐������悤�ŁA���̋L���Ⴂ�ł͂Ȃ������B���͖k�x�܂茻�����͖̉k�ɔh�����ꂽ�B���͂��@���ɂȂ�ƌR������̘b���悭�����B���������Ă����Z�ł���A��͔N������Ă���������畷����͎��������B���͑݉ƂɏZ��ł������N��̎��q���Ɗ^����l���Ƃ������������`���A���Ɍ����Ċ��ł����B�M�g������肾�����̂ł���B���ꂩ��̕���͕�����̕��������ł���B���͔h�������Ƃ����ɒʐM���ɑI�����ꂽ�B�z������ɍ��ƈႢ���Ȃ������̒��w���o�Ă������炩������Ȃ��B
�@�����������ɕ��ׂ��邢�͔x�����������@���āA�P�J���ʓ��@���ĕ��A���ČP�����I�����B�_�Ƃɐ��܂ꂽ���͊挒�Œ��������̍ۂɍb�퍇�i�A�܂茒�N�D�ǂƂ���Ă������炤�ȂÂ��Ȃ��b�ł͂���B���̌��Ȃ͌R���͐l�Ԃ�b���Ă����悢�Ƃ��낾�A���������������n�R�l�����ʂ̂Ȃ����͎���̂Ƃ���ł���A�Ƃ��������Ƃł���B���ہA�u�����сv�Ƃ����ċ����o���Έ̂��Ȃ�邪�A�������グ�̎��͂��Ȃ����߂ɂ������ĕ����ɂ����߂��邱�Ƃ�����Ƃ����B
�@���͎P������ƁA�킴�킴�����̎P�̏C�����Ɏ����čs�������B�����̎�l�͕��̐�F�ł���B��F�Ƃ��J���������̂��ƌ����邪�A����͂��̘b�ł�������B���͊�Ȑl�ŕ��i�͑��o�̔ԕt�\�́A������ϐ����Ɏ����Ȃ̂��鎚�������B���������̎����]��ɂЂǂ��̂ŁA���������̂��ƌ����āA�����Č������̂́A���ȏ��̂悤���Y��Ȏ��ł������B������R���̊�n�̊Ŕ���������Ă����̂��������B�܂��A�ΐ�ԌP���̂��߂ɁA�Z�p���Z����w�����āA�V���[�}����Ԃ̍\���}���������̂��Ǝ������Ă����B���������ƕ��͊�p�Ȑl�̂悤�ł��邪�A�������ł͕s��p�ŁA�k�^�@���^�]���Ă͐�ɗ����A���d���̒i��肪���肾�ƕꂩ����Ă����B
�@���͒ʐM���Ƃ��ĒʐM�ƈÍ���S�����Ă����B������퓬�Ől���E�������͂Ȃ��͂��ł���Bb;f
����͎����𐄒肵���̂ł����āA���a��`�I�l�����Ō����̂ł͂Ȃ��B���̘b�ł́A�u�̏�ő҂��\���Ă���ƓG���U�߂ė���̂ŁA�@�֏e��|�˂���Ǝx�߂̕������������낢�悤�ɂ����|��Ă����A�Ƃ����悤�ȃ��A���e�B�[�̂Ȃ��b����ł������̂͂��̂������낤�Ǝv���B���̘b���v���o���x�A���̔]���ɂ́A�L���ɌX�Βn�ɐl�̔����قǂ̏�̑������łȂт��Ă���Ԃ��A�吨�̐l���Ԋu�@���č��������߂ēo���Ă���i�F�������ԁB
�����؍�
�@���؍҂̓�����m��Ȃ��l�͏��Ȃ����낤�B���������ȉԂ��n���ɍ炭�ƁA�������ɂ���Ă͊Â��������������Ȃ������܂ł킩��B����������̔Z�������ł���B���Ƃ̒�ɂ͒z�R���������B�z�R�Ƃ����Ă���ԍ����Ƃ���ő�l�̐g���قǂ����Ȃ��B
�@���̏ے��̂悤�ɒ��x�����̈�ԍ����Ƃ���ɋ��؍҂���{����B�������̉Ƃ�����A���؍҂̌Ö͉Ƃ�����B���悤�ɁA���������Ɨ����Ă���B���؍҂̑����ɂ͏����Ȓr������̂����A�J�̓��ȊO�ɐ������܂��Ă������߂����Ȃ��B�~�������Ă��Ȃ��̂ł���B�������ɕ����Ă���̂ł��ł������Ă���B
�@����̎�̂Ȃ��_�Ƃ̕Ȃɒz�R�̍\���͋Â��Ă����B���ւ��炷���E�ɏo��������ɁA�z�R�̏��H�ƂȂ郁�C���X�g���[�g������B������̍��e�ɂ��S���g(���邷�ׂ�)������A�G�߂ɂ͔����s���N�̂���₩�ȉԂ��炩���B�S���g�͒��x���Ԃ̉������猩����ʒu�ɂ���B�E�e�ɂ͂�������̌Ö�����B
�@���C���X�g���[�g�͎�����邽�߂��A�Ƃ̉����ɕ��s�ɂقڒz�R�̒��S�����˂��˂��ˑ����Ĕ����邪�����͒�̃��x���ō���͂Ȃ��B�̂͂킪�Ƃɂ���̐l�������̂ł��낤�B���C���X�g���[�g�̗����ɂ͋Â����`�̐��K���ɔz�u���Ă���B���܂��������̂ŏt����H�܂Œz�R�ɂ͉����Ԃ��炭�B�Ȃ��ł��_���A�͍D�݂ł���B
�@�������Ƒ��̒N���n�ʂ�|���ȊO�ɁA�Ԃ̎��������Ă����C�z�͂Ȃ��B�������������ł͂Ȃ��̂ɁA���C���X�g���[�g���番����āA�z�R��o��悤�ɏb�����R�̓�������B�z�R�̐A���ƐA���Ȃǂ͋ߏ��̎q�������̂悢�V�я�ł������B�[���������ڂ��ł����B
�@�z�R���I���ƉƂ̊p�ɉ����ĕ��n�̒낪�����B�p�ӂ�ɂ���̂���̃��h�x�L�A�A�����͂��ł���B���Z��140cm�A���O�ł�150cm�ɖ����Ȃ��������ɂ͒j�q�̐��l���鍂���̃��h�x�L�A�͂ƂĂ��Ȃ��������ł������B���h�x�L�A���炭�Ə��āA���낻��C�����ɂ��s����A�̊��҂̉Ԃł���B���Ȃ݂Ɏ��Ƃ̃��h�x�L�A�͉��F���_���A�̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@������~���珰�̊ԂɌ������Ƃ��������s���N�̉Ԃ����锪�d��������B�������قǂ̔��d�ƉԂ̐������A�����Ƃ������Ȃ��C�i����������͉̂Ԃ̐F�̕i�̗ǂ��ƁA�w�����h�x�L�A�قǍ����Ȃ������������낤�B���ւƑΊp���̊p�̈ʒu�Ƀg�C��������̂Ŗ�������H�ڂɂȂ�B
�@�z�R���甽�Ɍ��ւ̕��ɍs���ƉƂ������߂ď��삪����Ă���B�����`�̉Ƃ̒Z�ӂɉ����ė���Ă���B�y�Ԃɉ����������ď�����Ă��邩��A����͉Ƃ̒��ɂ���̂����R�ł���B�̂͐����ȂǂȂ��������珬��Ő���������B����������@�ȂǂȂ��B�������m�̕����̗���Ŏc���ė~�����Ǝv���̂͐���@�Ɛ����֏��ł���B�e���r���①�ɂ�����Ȃ��B
�@����̌������ɂ͉Ƃɉ����ē�������B���͌�������킪�Ƃ̓c����ʂ��ĉƂ̗��̎s���ɂȂ��鉽�S���[�g�����̎����ł���B���L�n��ʂ邩�������Ȃ̂����A�y�n��蔄�肷�邽�߂ɒʍs�l�͑��l�̕��������Ȃ�ɂ�A�Ƃ��Ƃ��s���ɏ����グ���Ă��܂����B�����͎������Z��̊w��ɂȂ����̂��낤�B
�@�����Z��ł����z�R�̂���Ƃ́A���͂����Ȃ��B�����ɂ������ɏZ��ł����c���̒킪�A�����Ɣ��˂̒n�Ƃ��������h�ȐΔ�𗧂Ă����A�c���̒���Ƃ��ɂȂ��Ȃ�A�Δ���Ȃ��B�����̖ʉe�Ƃ����A�z�R�̋��؍҂Ƃ���������ړ]�����Z�̐V���Ɏc���Ă��邾���ł���B
�@���؍҂Ƃ�������͎��ƕ����A���̖X�ƂƂ��ɉ����������č����ĉ^�̂ł���B���Ƃ�����ڐ݂���ۂɈ��̔��a�̍a��x��A�����炵�Ă����Ă���ڐ݂��邱�Ƃł���B���͍��̌ꌹ�����̂Ƃ��m�����B
���ӂ邳�Ƃ̋L
�@���̐��Ƃ͒n���̐�Ɣ_�Ƃł��������A���ɉƋƂ��p���҂͂��Ȃ��B�����ȓc�ɂ̒n���o�g�҂ł��邪�A�����R���v���b�N�X�͂Ȃ��B�����ɏZ��ł���҂̑啔���͎��Ɠ������n���o�g�҂�����ł���B�����Č��X�n�����a��͏��Ȃ��B�ނ���A���k���B�ȂǁA�͂�����Ƃ��������̂��邱�Ƃ��A�܂����B���Ƃ�e�ʂƘb������Ɣ����ɕW����ƈႤ�����ƌ����̂́A�ނ���߂����B
���̑c���̒�͋��t�����Ă��Đ�O���瓌���ɏZ��ł����B�����Ďq����A��Ď��ƂɋA�邽�тɁA���Ă��̂悤�ɁA�c�ɂ̎q���́A�Ȃǂƕ��̓I�Ȃ��Ƃ��������B������Z�͎��������ăJ�b�y���܂�̕ȂɂƉA�����������B�����ݏZ�҂̂قƂ�ǂ����F�͓c�ɂ̏o�Ȃ̂ł���B
�@�������]�˃R���v���b�N�X�͂���B�]�˂ɂ͂���Ȃ�̓`�������邩��ł���B�܂��āA���ǂ�킩��Ȃ��ʁA�i�����]�˓����ɋ����ȂǂƂ����ƌn�ɂ̓R���v���b�N�X������B���Ƃ͗����Ԃꂽ�Ƃ͌����A�c���ѓ��������ꂽ�ƌn�ł���Ƃ����̂ł��邪�A����Ƃ����A���͖ؕ��̕��͕����Ė����Ȃ�A�S���̕�悾���ɂȂ��Ďc���Ă��邾���ł���B���Ɏ����ẮA�品��c���������ɐ܂��Đ��`���A�����Ɏg���Ă����A�Ƃ�����Ȃ��L�l�ł���B���m�������ȂǂƂ������̂́A�Ƃ��ɖ������Ă����̂ł���B������]�˃R���v���b�N�X�͂���B
���Ă̍����Ƃ��ēy�n�����͂����낵����R�����Ă����B�v����ɏ��̂������̂��B��������������Đ�O���ɂقƂ�ǂ̓y�n���Ă��܂��āA������g���Ă��Ȃ���������A���̔_�n����œy�n���Ƃ��邱�Ƃ��Ȃ������B����͑\�c������a�����Ď��Âɋ������������̂��A�ƕ�͌������������A�D�ɗ�����b�ł͂Ȃ��B�]�c���͂W�O�߂��܂Ő������̂ł���B��͌��������Ȃ��^����m���Ă����̂ł��낤�B
�@���ł���Ɣ_�Ƃŕ�炵�Ă����邾���̍L���y�n�������Ă����B�c�ɂ̐l�͂����l���Ǝv���܂����B���Ȃ��Ƃ��]�c����c���A���͂��l�悵�ł������B�n�������ʂł���B�̂̂��ƂƂĒ��q�����őS���Y�͒��j����������B�������j�ȉ��ɓ�����]�c���́A������Ƃ����Ŗ����œy�n�𑧎q�ɕ������B�����������͖≮�������Ȃ��B���̐��オ�i�N�e�ƏZ�y�n��Ԃ��͂����Ȃ��B���R������B�ŋߖ@�������������܂ł́A�ؒn�ł���Z�N�ȏ�Z�y�n�͉i�Z�������������B���L���̕ύX�͂Ȃ��̂ɂ�������炸�A���L�҂͎ؒn�l�ɕԂ��Ƃ͂����Ȃ��̂ł���B�����őc���͘b�������ʼn������邱�Ƃɂ����B���ǐe�ʂɂ������R�Ŏؒn�����̂ł���B����Ȃ��Ƃ����x���������B����ɂ����肸�Ԃ̑��l�̎ؒn�l�ɂ����l�̎���œy�n�����ꂽ�B
�@���l�悵�͒���Ȃ��̂ł���B����Șb��������B���S���[�g���ɓn���ēy�n��ڂ��Ă��鉓���̐e�ʂ̉Ƃ�����B���͉䂪�Ƃ̕��Ƃł���B�킪�Ƃ̕��������[�g������ɂ���X���[�v�Őڂ��Ă���B���E�̂킪�Ƃ̓��̔��ɂ͖ڈ�Ƃ��Ēւ̖���ɐA���Ă���B���������E�ɐA����ƁA�����̓y�n�ɒ���o���̂ŁA�}���łĂ��גn��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��Ƃ�����������̂ł���B
�X���[�v�̉��͗Ƃ̓c�ނł���B�Ƃ��낪�C���t���Ƌ��̖̍��̓y�n������č��������o�Ă���B�l�q�����������̂ŕ��͎���A��āA�y�n�䒠�ɍ��킹�đ��ʂ����B����Ƌ��̂킪�Ƃ̓y�n�����X�Ɛ����[�g���ÂN������āA�Ƃ̓c�ނɂȂ��Ă���B�Ƃ͖��N�ڗ����Ȃ��悤�ɁA�����ÂX���[�v�̐�������ēc��ڂ��L���Ă����̂ł���B�X���[�v�͏����Â���ĉ䂪�Ƃ̓y�n�����邩��ւ̖̍��������I�o�����̂ł���B�������10�N�ɂ킽���č��C�悭�Â��Ă����̂ł���B�Ȃ�Ƃ����A���ȍ����B���ʂ̌��ʁA�ǂ��������������͒m��Ȃ��B�������킪�Ƃ̓y�n�͎��͂̐e��(���l�ł͂Ȃ��I)���炱��ȕ��@�ł��_���Ă����̂ł���B
�@���Ƃ̋ߕӂ͎����Z��ł���18���܂ł͑S�ē����ł������B�̂̎��̏��w�Z�ł͌��P��A�������̕����̐��k���W�܂��ĉ��Z����Ƃ����K�����������B�Ƃ��낪����������������ꏏ�ɋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A�����Ɛ���͂���Ŕ��ɂ���n��̑����̎q�������Ƃ͕t���������Ȃ���Ζʎ����Ȃ��B���Ɠ����̉Ƒ��������A����n��ɂ����܂��ĔZ���ȕt�����������Ă����̂ł���B
����ɂ͗��R���������B���S�N���O�Ɏ��̑c��́A�d���Ă�����N���퍑�̑����ŕ������B�����œ����̋��Z�n��ȑO�Z��ł����̒n�̊O��ɓ����ċ��������B����}���ق̎����ɂ͂����L�ڂ���Ă���B�v����ɗ������ҕ��������҂����ō���āA�B��Z�̂ł���B�����璷���ԓ��������̋������������Ă����̂ł���B��������ِ͂̈��̐l�����Ƃ͌��ۂ��Ȃ������̂ł��낤�B
�@����ǂ��납�e�ʂ̂����ɂ́A�s���߂��܂ŗƂƂ����ʍ����Ă����Q����g�̉Ƃ����������B�ߐe�����̌��ʁA���̉Ƃɂ́A�����q���̍��܂Ń_�E���ǂ��������Ă����B�킪�Ƃ̋ߗׂ͈��̌��������Љ���`�����Ă����̂ł���B���ł͐��Ƃ̋ߏ��ɂ͔_�n�����蕥���āA�����̐l�������ڂ�Z�݁A�l���͉��\�{�ƂȂ����B���������B��Z���Ƃ͐����قȂ�̂ŋ�ʂł���B����Ȃ̂ɁA���������������o�č����̑����𑱂��Ă���B���⎞�Ԃ̌o�߂��������Đe�ʂ��ƌ������o��������āA�@�B�I�ȋ����̓I�K�������c���Ă��Ȃ��������̂Ǝv����B
�@���́u�S�v�ɂ́A���ƂȂ邱��ȃG�s�\�[�h������B��l���̒�吶�����i�����u�搶�v���l�Ԃ͂����ƂȂ�ƒN�ł����l�ƂȂ�ƌ������B�����Ŏ�l���́A����͂ǂ�Ȏ��ł����Ǝ��₷��B�搶�̓����́u�����N�B�v�ł������̂ŁA��l���͗]��ɐ����I�ȓ����ł������肷��B�����ƓN�w�I�ō����ȓ��������҂��Ă����̂��B�������ɂ͍��g�ɂ��݂Ă���B�搶�͐e�����ʂƁA�e�ł������e�ʂ���Y�ړ��Ăŏ]���ƌ��������悤�Ƃ�����ꂽ�o�������Ă����̂ł���B�q���̍����璇�ǂ������]���܂ł��A��Y�D���̉A�d�ɉ��S���Ă����B����Ȍo�����搶���}���l�ɂ������������̂ЂƂł������B
�@�搶�͐e�ʂƂ̈�Y�������A�ǂ�ȗǂ��l�Ԃ����������Ă��܂��ƌ������̂ł���B�����玄�ɂ́u�����N�v�Ƃ������t���[���ɋ����B���͉��\�N���Ђ��߂Ă����A�ЂƂ̌��ӂ����s�����B����50�㔼�Ŕ]�쌌�Ŏ��B��͓y�n�������J��Ԃ��̂�����āA���������Ƃ����Ă�Ƃ��͓y�n�ƉƂɑ������镪�������Y���邩��A����͕��̈�Y�������������悤�Ɍ������̂ŁA�U�P�҂ł��������͎����n���ď]�����B
�@�������N���O�}���V�������w������ۂɁA��ɘb���������́A�邩�ɖ����s���Ă��炤���Ƃ��v���o�����B���͍w�������ɍ����Ă����̂ł͂Ȃ�����A������Ă��炤���Ƃ����҂��Ă��������ł������B�������A�ƌ����������ŕ�͖������B���̔N�̖~�ɋA�Ȃ������A��͖ق��ĕS���~�̌�������Ŏ��ɓn�����B�A���Ă���s�R�Ɏv�������́A�������Y�����̑㏞���ƕ������B�����́A���̒ʂ肾�A�ł������B���͐�]�����B��͗������̂ł���B���͗��N�̂��~�ɋA�Ȃ��Ă��̕S���~��Ԃ����B�K�������Ӓn�ł͂Ȃ��B���͂��̎��܂ŕꂪ�A���̎��̖͈������Ƃ̂��߂ɁA�Ȃ��������Ƃɂ��Ă���A�Ǝӂ��Ă����A���̒ʂ�ɂ������ł������B�����玄�͌Z�Ƒ����ɂȂ낤�Ƃ��A�K����̈�Y�͂��炤�ƌ��ӂ����B���ɂ͗���ꂽ�����s����ƌ�����`�������������B
�@����������͉��̗��R�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�{���̗��R�͎q�������ɏ����ł����Y���c�������ƌ����~���{���̓��@������ł���B���͈�Y�����̏X����m���Ă���B��������Y�~�����̗~�]���瓦����Ȃ��B�搶�́u�����N�v�͓�����Ȃ��^���ł������Ƃ�m���Ă���B��Y�����ɂ͌���k������B�ꂪ�S���Ȃ����N�̖~�ɋA�Ȃ���ƁA�Z�͑����������Ă���A�ƌ������B���́A�؋��͂Ȃ����A�ƒf���āA��Ƃ̖���������B����ƌZ�͉������āA�O�����̓y�n�𑊑������炢���A�ƌ������̂ŁA�^�����������������B���X�c�ɂɏZ�ނ���͂Ȃ������̂ŁA�n���̕s���Y���ɁA���蕥�����˗������B
�@�Ƃ��낪�s���Y���́A��Ԕ��l�̍����y�n�̏�ɂ͏����������Ă���̂Ŕ���Ȃ�����A�P������ƌ����o�����B�Z�ɓP����v������ƁA���͎��������Ă��̂ł͂Ȃ��A�̂���e�ʂ��g���Ă���̂��A�ƌ������B�����m���Ă��Ȃ���A�Z���x�����̂ł���B�]�c�����A���q�Ɉ�����ő݂��Ă����y�n�̍Ō�̂ЂƂ������̂ł���B�ٌ�m�ɑ��k���čٔ��ƂȂ����B�n�قŕ������B�؋��W�߂̌��ʁA�ꂪ�ٔ��Ō��������������Ă������ƁA���̑����͂��̓y�n�����̃X�g���X���������ƌ����\���e�ʂ��イ�ɂȂ��ꂽ(�\���������͕s��)���ƁA��͎��ɖʂ��Y�������⏑�Ɏc���Ă����A�Ȃǂł���B�ٌ�m�͍��قł͏��Ă�A�ƌ��������A���́A���̑��������̓y�n�����̃X�g���X���������ƌ����\�������ɏ�����Ă������Ƃɋ��|���āA�㍐���~�߂��B
�����l�Ɏ����g���X�g���X�œ|��͂��܂����A�ƕ|�ꂽ�̂ł���B��c�����ٌ͕�m�ōٔ��̌��܂Ɋ���Ă���͂��Ȃ̂ɁA��}�̒Nj��ɗ܂𗬂����B�����g���g���Ɏ��͂܂�ċ������R�̌o���ɂ����̋���������Ȃ������B���ʂ��Ă���̂́A�ٌ�m�̍ٔ����E���ŋ�������邱�Ƃ��A�{���I�Ɏ��g�̖��Ɗ����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B�Ƃ��낪�A�{���I�Ɏ��g�̖��Ɗ������u�ԂɁA�l�͋��|��������B���͈ꎞ�̗{���ɁA�o�������̂��낤�Ǝ��X�ɋ��i��v�����ꂽ�B�����̌o�����܂߂āu�S�v��������Ă���̂ł��낤�B�����{�q�ɏo���ꂽ�͖̂��M�������̂ЂƂł���B���̉Ƃ͐V�h�ɒn�����c���قǂ̋��Ƃ̐��܂�ł���B���Ƃh����l���������邪�A���Ƃɐ��܂ꂽ���ɂ͐M�����Ȃ��B���Ɛ��܂�Ȃǂƌ������Ƃ́A�c��l�����̍��݂����ߍ��܂�Ă���̂ɈႢ�Ȃ��̂ł���B��������A��c�̍��݂̂��߂ɑ��������̂ł���B
��͂悻����łɗ����ɂ��S��炸�A���Ƃ̐�c�����̍��Ɏ�荞�܂ꂽ�B���̎��Ƃɂ́A��c�̗썰�̍��݂����܂��Ă����B��\�͂̂����͂���Ɋ��������B���̌��ʖS���Ȃ�����́A�c���ꂽ�Ō�̈�Y�����������āA�q���ɉЍ����c���Ȃ����߂ɁA���̐����玄�Ɍ���������悤�Ɏw�������B���͊ԈႢ�Ȃ����ꂩ��̎w�����A���̎��ŕ������B
���Ǎٔ��ɕ����͂������A�������Ƃ��̎q���������ꂵ�ނ��Ƃ����́A�f���Ƃ͂ł����B�N�����ӂ���҂͂��Ȃ����A��̈�u�ɂ�������ꂽ���Ƃ����Ŗ������鑼�͂Ȃ��B��͎����Ĉӎu���ѓO�����̂ł���B
�y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�
���n�̂��鐶��
�@���܂ǂ��n�������Ă���Ƃ���������������ǂ��ł��傤�B��n�����Ă���Ƃ����n�̔n��Ƃ��A������ɂ��Ă���������Ƃ����̂�����ł��B���̐��Ƃɂ͐̔n���ꓪ���܂����B�_�Ƃ���������ŁA�������������킯�ł͂���܂���B���̔_�Ƃ̓g���N�^�[�Ȃǂ̔_�Ƌ@�B����������܂����A�������������͔_�Ƌ@�B�ȂǂƂ������̂͂���܂���B�����Ŕn�������Ă����̂ł��B
�@���̎ʐ^�����ĉ������B���s�ɍs�������̕��i�ł��B���̌��i�Ŏ��͐��Ƃ̔n���v���o�����̂ł��B����͍k�^�@�ł��B�ו����^�ׂΓc��ڂ┨���k���@�B�ł��B�n�Ɖ��̊W��������āB�����A�n�͍k�^�@�ɂƂ��đւ��ꂽ�̂ł��B�n�������̂͏d�J���ő̗͂����邵�A������������f���P�[�g�ł��B
�@����őc���͍k�^�@�Ȃ���̂����������ƁA�ߏ��ōŏ��ɔ����܂����B����Ɣn�͗v��Ȃ��Ȃ�܂��B�����ł�����A�n�͔����邱�ƂɂȂ�܂����B����ӂ̂��Ƃł��B�n�̉a�͎��t�Ƃ����āA���Ɩ��荏���̂ɕčf�������Ղ肩���āA���ł������������̂ł��B
�@���������Ⴂ�l�͕čf�Ƃ������̂���m��Ȃ��Ǝv���܂��B�Ă𔒕Ăɐ�������Ƃ��ɂł��镲�Ƃ��������Ă����܂��傤�B�Ō�̔ӎ`�ł͂���܂��A������n�ɍŌ�̎��t���グ���̂ł��B
�@�d�����͂��ė��d�������X�Ƃ��Ă��܂��B��ɂ̓g���b�N�����t���ɂȂ��Ă��܂����B�n�̓g���b�N�ɉ^��܂��B���̂Ƃ��n�̉��炪���d���ɏƂ炳��Ă͂����茩�������B���\�N�o���܂����낤�B���ł����̌��i�͖Y��܂���B�n�̑傫�ȖځB�����Ŕn�قǂ��ꂢ�Ȋ�����Ă�����̂�m��܂���B�傫�ȏ��悤�Ȗ��B���l���Ă���l�O�ŗ܂𗬂����Ƃ͂���܂���ł������A�����������������͂��̎��������̂ɈႢ����܂���B
�@�ŋߔn���͔���Ȃ��̂ɋ��n���������邱�Ƃ�����܂����B�邩�ɔn�̊�̔��������m���߂����ƌ����C����������̂ł��B���z�ł��낤�Ǝv���܂����A�����ɂ��̎��̔n�̊�قǔ������n�ɂ͏o����Ă��܂���B�n���g���_�ƁB�F����ɂ͐M�����Ȃ��ł��傤�B���̐M�����Ȃ����������Ă������Ƃ�����������Ȃ��l�����̓�����̐l�ɂ͂��܂��B���܂�ɂ����������Ǝv������ł��傤�B�ł�����͎������̐^���ł��B�ł��������̂悤�Ȃ������������͐M�p���܂����B
�@���łɍk�^�@�̘b�����܂��B���͍k�^�@�����܂��g�����Ȃ��܂���ł����B�V���i�ɔ�т����������ŁA�G���W���̃X�^�[�g������̂ł��B�X�^�[�g�̎��s���J��Ԃ��ƃv���O���K�\�����ŔG��āA�܂��܂��X�^�[�g�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B����Ȏ����͂Ȃ����q���̎��ɐ����������܂����B���͕s��p�������̂ł��B������ו����^��ōk�^�@���^�]���Ă���ƁA�^�]�������˂Ęe�̐�ɗ����Ă��܂��܂����B���͌y���ōς̂��s�v�c�Ȃ��炢�ł��B�_�Ƃ����Ă���̂Řr�͂͋����̂ł����A���͂Ȃ����d���Ɋւ��Ă͕s��p�ŁA������ɂ���݂������Ă��܂����B�Ƃ��낪�q���Ɋy�������ɃI���W�i��������������ėV��ł����Ƃ�����p�Ȉ�ʂ��������̂ł��B�{�l�͎��ƉƂƂ������ƂƂ�������̂��܂��l�����h���Ă��܂����B�ĊO�|�p�Ƃ̋C���������̃R���v���b�N�X�ł͂Ȃ����ƍŋߎv���悤�ɂȂ�܂����B